- ホーム
- 電子書籍:おりべまこと劇場
- NEWS
- わたしの「わたしストーリー」
- 台本ライターとは?
- 実績:わたしの「しごとストーリー」
- サービスメニュー・料金プラン
- ブログ「台本屋のネタ帳」
- 仕事
- 生きる
- 食べる
- ロボット・AI
- 物語
- 歴史
- 世界
- 動物
- 音楽
- ビートルズ
- ドラマ・映画・演劇
- インターネット
- 本
- 台本
- エッセイ
- 子ども
- 2011年5月
- 家族
- エンディング
- 農業
- 旅
- 社会問題
- 昭和
- 認知症介護
- 広告
- 電子書籍
- 週末の懐メロ
- 2011年6月
- 2011年7月
- 2011年8月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年10月
- 2011年12月
- 2012年1月
- 2012年2月
- 2012年3月
- 2016年5月
- 2016年6月
- 2016年7月
- 2016年8月
- 2016年9月
- 2016年10月
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- 2017年6月
- 2017年7月
- 2017年8月
- 2017年9月
- 2017年10月
- 2017年11月
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- 2018年6月
- 2018年7月
- 2018年8月
- 2018年9月
- 2018年10月
- 2018年11月
- 2018年12月
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 新規ページ
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年4月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2020年11月
- 2020年12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- お問い合わせ
生きて祭 死して祭

「死ぬ前に一目祭りが見たい」
そう訴える老いた罪人に対し、
首切り役人が懐から狐のお面を取り出して渡す。
罪人がその面をつけると、耳には祭囃子が聞こえてくる。
彼が恍惚となり、幸福感に包まれた刹那、役人は刀を振り下ろし、
面をつけた罪人の首が宙を舞う。
「子連れ狼」と同じ小池一夫原作、小島剛夕作画コンビの劇画
「首斬り朝」は、刀剣の「試し斬り」の役目を担った
山田朝右衛門を描いた物語。
、
山田朝右衛門は打ち首の刑になった罪人の首を斬る、
いわば死刑執行人の役を兼務していたために、
江戸の町人たちから「人斬り朝右衛門」と恐れられていた。
江戸時代に実在した人物だ。
ちなみに「山田朝右衛門」というのは屋号みたいなもので、
代々同じ名を引き継ぎ、明治初期までお役目を務めていたという。
武士だが幕臣とは異なり、浪士の身分だった。
先述したストーリーは、
この「首斬り朝」の一編「祭り首」という話。
この劇画は基本的に一話読みきりで、
どちらかというと首を打たれる罪人が主役となり、
「なぜ罪を犯すことになったのか」を描く話が多い。
しかし「祭り首」は朝右衛門自身の
人生・感情にスポットが当たっている。
人々から恐れられていた「人斬り朝右衛門」は、
祭りの日は外出できなかった。
武士にとって、祭りは単なる遊びだが、
江戸の庶民にとっては、
現代のそれとは比較にならないほどの大イベント、
年に一度訪れる、命がけの祝祭である。
そんな特別めでたい日に、
不吉な死神と顔を合わせたくないというのだ。
祭というハレの日があるから、ケ(日常)が成り立つ。
解放の日にガス抜きをさせないと、庶民の間に不満が鬱積し、
世の中がうまく回らなくなる。
お上もそうした庶民の心情を無視しては
政ができないというわけである。
だから外出禁止は、なかばお上からの命令で、
それは気の毒なことに当人だけでなく家族も同様なのだ。
そのため、将来、「人斬り朝右衛門」になることを
運命づけられた少年朝右衛門は相当辛い思いをした。
10歳くらいの頃、我慢できずに
こっそり家を抜け出した少年朝衛門は、
人に見つからないよう、裏道でこっそり祭囃子を聞いていた。
すると、その裏道の入口前を、
同じ年頃の子供の集団が遊びながら走り抜け、
そのうちの一人が狐のお面を落としていった。
それを見つけた少年朝右衛門は、
こっそり拾って自分の顔にお面をつけてみる。
すると祭囃子がすぐ近くで聞こえた。
それは彼の人生で最初で最後の祭り体験になった。
漫画の中では描かれていないが、少年はその後、
急いで家に帰り、親に見つからないよう、お面を隠した。
もしかしたらその後、ずっと祭が来るたびに
家の中で一人でこっそりお面を被り、
幻聴のようなお囃子を聞いていたのかもしれない。
或いはお面を隠し持っていたおかげで、何とか大人になり、
父の後を継げたのかもしれない。
数十年後、刑執行の前日、彼は罪人が
「死ぬ前に一目祭りが見たい」と嘆願していることを知り、
箪笥の奥深くから隠し持っていた、あの狐のお面を取り出し、
しばし子供時代の回想に耽った後、
大事そうに懐に入れて家を出て、刑場へ――。
「首斬り朝」は「子連れ狼」と同じく、
父が全巻揃えて持っていた。
僕はそれを留守中に隠れて読んでいた。
「子連れ狼」より後なので、中学生だったと思う。
子連れ以上にエログロシーンが多い大人の漫画だったが、
人情噺に近い、この「祭り首」がいちばん印象に残っている。
そして、大人になって久しい今もなお、その印象は鮮明で、
罪人と朝右衛門の人生が交錯するラストシーンは、
思い出すたび、胸にじんと響く。
現代ではお祭りは、一部の人を除き、安全第一で、
神社の参道に並ぶ屋台で飲み食いするだけの
季節イベントになってしまっているが、
もともとは日本人の死生観と深くつながったものだった。
夜の神社を歩くと、ふと周囲の雑踏が消えて
生と死の境の空間に足を踏み入れたような
錯覚に落ちることがある。
死の間際に、心のどこかで祭囃子を聴くことができたら、
この世に未練を残さず別れられるのだろうか?
いい人生だったと思えるのだろうか?
祭りの季節になると、そんなことを考えるようになった。
認知症の義母の失踪

昨日の夕方、いっしょに行った近所のスーパーから
義母が忽然と姿を消した。
この店には一角にカフェコーナーがあり、
買い物客が買ったものをイートインしたり、
自販機でドリンクを飲んで休憩できるようになっている。
給水・給茶機もあり、こちらは無料だ。
この店まではそこそこ距離があるので、
来るとここに座らせてお茶を与え、休んでいてもらって、
10~15分、買い物をしている。
ところがレジを済ませて戻ってみると、姿がない。
前にも2度あったが、ひとりで店内をうろうろして
商品を見てまわっていたので、
すぐ見つかるだろうと高をくくっていたのだが、さにあらず。
2階・3階・地下を見て回ったがいない。
慌ててすっ飛んで帰り、
自転車で家とスーパーとの間の道をあちこち探し回ったが、
見つからない。
スーパーで事情を話し、防犯カメラを確認してもらったところ、
どうやら家と反対方向に歩いて行ったらしい。
頭はダメだが、体はじょうぶで健脚である。
以前も「自分の家(実家?故郷?)に帰る」と言い残して、
自分が知らない道を、ひとりでずんずん歩き続けたことがあった。
(その時は尾行していった)
日が暮れてきたので、
カミさんと相談してやむを得ず警察に届け出。
その後、家と反対方向の幹線道路を越えたあたりを
探していたら、カミさんの電話に、隣町の交番で保護された、
という連絡が入ったという。
自転車を飛ばして行ってみると、
特に疲れた様子も困った様子もなく、
交番の中にちょこんと座って涼しい顔をしている。
僕が入っていくと、わかったらしく
「この人たちはすごくいい人。それにいい男でしょ」
などと若い警官を持ち上げた。
警察の話によると、
その交番付近をウロウロしていたので声を掛けたら、
ちょっと反応がおかしいので、迷い人だなと思って保護。
さっき別の交番に届け出た本人の特徴と一致していたので、
カミさんに電話が行ったという。
最近、自分の名前が言えないこともあるが、
この時はちゃんと名乗れたらしい。
その交番はスーパーから約1キロ、
1時間近くひとり旅をしていたらしく、
さすがに疲れてどこかで休みたいと思っていたので、
交番を休憩所代わりに使ったのかもしれない。
そして、何よりも声をかけた警官が若くてちょっとイケメンで、
義母好みだったことも幸いしたのだろう。
帰る時は、彼の手を握って「また会いに来るからね」
などとのたまった。
こっちは2時間半探し回ってへとへとである。
それにしても、たまたま近所の、
わかりやすいところで保護されたからよかったが、
これは、これまで大丈夫だったからと、
目を離していた僕の大失敗。
今後、絶対に自分の都合で目を離さないと誓ったのと、
万一の時のために靴にGPSを仕込んでおこうと決めた。
電子書籍新刊「あなたはどんな大人に憧れましたか?」
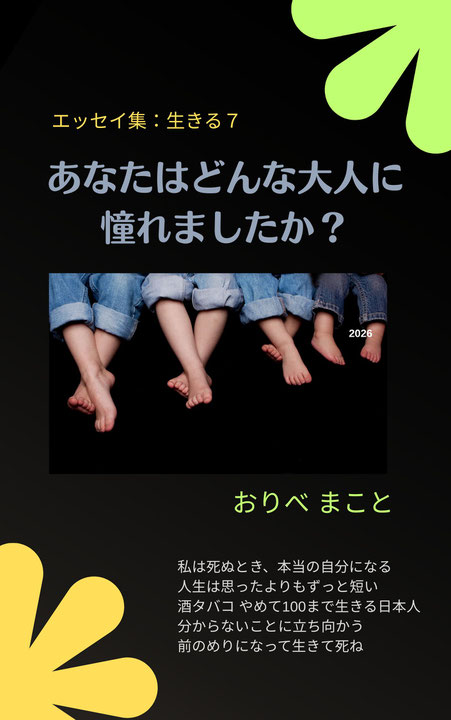
人生に迷った時、私たちは何に立ち返ればいいのだろうか。
この問いに、著者おりべまことは実体験を通して
答えを示してくれる。
デイサービスで出会った青年が語った
「やきいも屋のおっさんにあこがれていた」という言葉。
手っ取り早く稼ぐことが成功とされる現代において、
地に足をつけて人と向き合う生き方への憧れを語る彼の言葉は、
私たちが忘れてしまった大切なものを思い出させる。
本書は「生きる」をテーマにしたエッセイシリーズ第7集。
認知症を患った義母の介護体験、友人の死、
そして自分自身の老いと向き合う中で見えてきた人生の真実が、
時にユーモラスに、時に切なく描かれている。
特に印象深いのは、認知症の当事者として講演活動を続ける
クリスティーン・ブライデン氏の
「私は死ぬとき、本当の自分になる」
という言葉を紹介したエッセイ。
病気によって社会的な役割を失いながらも、
真の自己と向き合うことで見出した生きる意味は、
健常者である私たちにとっても深い示唆を与えてくれる。
また、「人生は思ったよりもずっと短い」では、
かつて才能ある批評家だった知人の変わり果てた姿を通して、
時間の有限性と行動することの大切さを説く。
若者が死について考えることを否定するのではなく、
それこそが「生きるとは何か」という
根源的な問いかけだと捉える視点も新鮮だ。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から厳選された33
編は、どれも読者の心に深く響く。
人生の後半戦を迎えた人はもちろん、
生き方に迷う若い世代にも、
きっと新たな視点を与えてくれるはずだ。
Amazon Kindleより本日発売! ¥500
もくじ
- 私は死ぬとき、本当の自分になる
- 恐竜王国 福井への遠足で「生きる」を養う
- 誕生日は誰にでも平等にある祝福の日
- 逃亡者の死の価値
- 女を舐めるべからず
- なぜ昭和の“すごい”人たちは本を出せなかったのか?
- となりのレトロより:あんたも閻魔大王様に舌抜かれるよ
- 赤いパンツの底力 ~巣鴨とげぬき地蔵デイトリップ~
- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる
- 人生は思ったよりもずっと短い
- 春休みは人生の踊り場
- 死ぬ前にもう一度ワールドツアーで歌いたい・演奏したい
- 友の旅立ちに春の花を
- 「パーフェクト・デイ」そして「またあした」
- なぜ女は「死」に関心が深いのか?
- あなたはどんな大人に憧れましたか?
- 酒タバコ やめて100まで生きる日本人
- 若者が死について考えるのは健全である
- 人生の価値観を問う「天路の旅人」
- 唐十郎さんに「君の作文は面白い」と言われたこと
- 唐十郎式創作術「分からないことに立ち向かう」
- 高齢者を高齢者扱いするべからず
- なぜ医者も歯医者も早死にするのか?
- 母の日に酒を、父の日に花を
- 息子の誕生日に考えたこと
- 経済が支配するユートピアとディストピアを見つめる 「父が娘に語る経済の話。」
- 友の49日と「友だち法要」
- 前のめりになって生きて死ね
- 父の日の秘密の花園
- タクシーの中にスマホを忘れたら
- やっぱり変わらなかった東京都知事選2024
- 「十代が!」と連呼する大人の気持ち悪さと 「母親になる可能性を持った身体」について
- 夏休みも人生も後半はあっという間
昭和歌謡・時代劇系の傑作「子連れ狼」
橋幸夫さんが亡くなった。
国民的歌手とまでいわれた、昭和歌謡の代表的な歌い手だが、
さすがに僕は、吉永小百合とのデュエットとかは、
リアルタイムでは知らない世代。
だけど子供のころ、「潮来笠」(デビュー曲)や「子連れ狼」などの
時代劇系の歌が好きだった。
自分ではよく覚えてないが、「潮来笠」は
♪いたこのいたろう ちょっとみなれば~
と、三度笠に見立てたザルを持って歌っていたらしい。
「子連れ狼」はもともと大人向けのマンガ(劇画)で
テレビドラマ化され、小学生の頃、ちょっとしたブームになった。
この曲は劇画のイメージソングとして企画され、
ドラマの主題歌になったのは後付けだったらしい。
1位にはならなかったが、
1か月くらいベスト10入りしていたと思う。
作詞は劇画の原作者である小池一雄。
イントロと途中で語りが入るのは、いかにも昭和歌謡らしい。
歌詞の1番で「しとしとぴっちゃん しとぴっちゃん」=雨、
2番で「ひょうひょうしゅるる ひょうしゅるる」=北風、
3番で「ぱきぱきぴきんこ ぱきぴんこ」=霜と、
きびしい自然を表現する、オノマトペの使い方が秀逸。
橋さんと子供合唱団の共演で3分間のドラマを生み出している。
訃報を聞いて、久しぶりに聴いてみたが、
やっぱりこれは名曲だなぁと感心した。
と同時に、小学生の時(確か5年生か6年生)の
友だちのことを思い出した。
ちなみに父がこの漫画を全巻揃えていたので、
いないときに読んでみたが、
けっこう濡れ場がふんだんに出てきて、
盗み読みするのに罪悪感を覚えた。
子供心にかなりショッキングな描写もあったが、
最近は、アニメなどでもやたらと、
刃物でズタズタ、バラバラにされる描写が出てくるので、
今思うと、かわいいものだったのかもしれない。
ゆるぎない昭和歌謡の傑作を世に送り出してくれた
橋幸夫さんのご冥福を祈ります。
心が乱れたら両手を合わせてみる

ここのところ、認知症の義母の幼児化が著しい。
欲望丸出しのガキに等しいので、大人の理屈は一切通らない。
「これやっちゃダメ」なんて言っても5分後には忘れている。
息子がチビの時代もこれほど手こずらなかった。
それに子供と違って、そのうち成長してわかるようになるだろう
という希望も抱けない。
ほとほと疲れるのだが、
それは「大人なのに」と思って接するからだ。
以前から子ども扱いはしていたが、それでもだめだ。
そこでお地蔵様あつかい・菩薩様あつかいし、
朝夕手を合わせることにした。
すると、あら不思議。
気持ちが落ち着き、イラついたり、腹が立ったり、
疲れたりすることが少なくなった。
そういえば以前、仕事で
「お仏壇のはせがわ」の社長にインタビューしたとき、
「一日三回、手を合わせると人生変わりますよ」
といわれたことがある。
一応、両親と義父の手元供養をしているので、
朝は手を合わせるようにしているが、
まだ生きている義母を菩薩視して同じようにやっていると、
なんだかメンタルヘルスにいい気がする。
はせがわのコマーシャルで女の子がやっている
「お手手のしわとしわを合わせて、しあわせ」は、
あながちでたらめではない。
僕は宗教心のカケラもない人間だが、
おそらく左右の手のひらを胸の前で合わせるという運動と姿勢が、
からだ全体の血流とか、気の流れとかに
何か影響を及ぼすのかもしれない。
そうした科学的根拠もありそうだが、
なんでも理論的に説明されてしまうと、
「なんだ、そういうことか」と納得してしまって、
生きるのがつまらなくなるような気がする。
人生にはある程度、
不思議なことや神秘的なことがあったほうが面白い。
仏壇やお墓やお寺やお宮の前でなくてもいい。
祈願も感謝も供養の心も、神仏のイメージも必要ない。
ただ何も考えず、両手を合わせるだけでよい。
もし、頭に来たり、悲しくなったり、不安になったり、
ネガティブな感情にとらわれたら、
胸の前で手と手を合わせてみよう。
できたら一日何回も「しあわせ」をやってみる。
たったそれだけで気持ちが落ち着き、気分が良くなるよ。
レット・イット・ビーTAKE28、そして、もう新しいものはもういらない
何万回聞いても飽きないビートルズの
「レット・イット・ビー」。
最近出てきたこの「テイク28」は衝撃的。
間奏のギターソロとオルガンの響き、
曲終盤のマッカートニーの
ちょっと外した歌い方が超新鮮でしびれまくる。
生涯最高のバージョンだ(今のところ)
2020年10月から2024年2月まで、
毎週末に「週末の懐メロ」という記事を180本書いて、
すごく楽しくて、いずれまた再開しようかなと思っていたが、
全然そんな気にならない。
自分にとってのベストはもう書き尽くし、
すっかり満足してしまったのだ。
音楽についてもう新しいものはいらない。
てか、街の中でもテレビやラジオでも、
懐メロしか耳に入ってこない。
お前が年寄りだからだろと言われればそれまでだけど、
若い衆も20世紀ロック・ポップスや昭和歌謡に
ご執心のように見える。
今や1960~90年代も、2020年代も変わりがない。
懐メロだけど、ネット上に初めて聴く別テイク、別バージョン、
秘蔵のライブ音源などが次から次へと上がってくる。
いまや音楽は進化ではなく、深化する時代。
古いも新しいも関係なく、
流行っているか・いないかも関係なく、
歴史的な価値があるのかどうかも関係なく、
パフォーマーが生きているのか、死んでいるのかだって
もう関係なくて、いいものはいい、好きなものは好き、
面白いものは面白いで、なんでもOKの時代になった。
みんな楽しく聴いて、
自分の魂に響くベストオブベストを掘り起こそう。
ファッションチャンネルの備蓄米

夏休みで遊びに来た20代の息子。
帰り際に「おまえ、家で備蓄米食ってるの?」と聞いたら、
「そんなまずい米食わねーよ」との返事。
「でも、おまえがうちで食っていったの、備蓄米だよ」
と言ったら、「え?」と目を丸くした。
「変わんないね」
というわけで、ぼちぼち新米の季節だが、
カミさんがショッピングチャンネルのQVCで10キロ、
備蓄米を頼んだ。
普段、おしゃれなファッションがどうだらこうだら
キャーキャー言っているチャンネルが、
なんで備蓄米を売っているのか、わけわからんが、
食費を節約してもらって、
その浮いた分を服に回してくれということなのか?
それはいいのだが、じつはこれ、
7月頭に頼んでから到着するのに1か月近くを要した。
まだ一袋目は1週間分くらい残っているので、
9月半ばあたりまで持ちそうだ。
「備蓄米ブーム」も過ぎ、ぼちぼち新米の季節だが、
これを喰い終わらないと新米には手を出さない。
てか、わざわざ倍以上のカネを出して
新米を食べようという気にならない。
うちの息子同様、古米・新米を
たんなるイメージでとらえている人が大勢いるのだろう。
ガチで何種類か食べ比べをしたら、
たしかに違うのかもしれないが、
僕は安い備蓄米で充実した食事ができれば、それで十分。
よい食卓・よい家庭は、ぜいたくなものを使わなくてもできる。
9月・10月まで、どんどん売ってほしい。
鬼滅の刃:「親孝行」という圧倒的正義

この物語の一貫したテーマは「親孝行」。
お盆休みの午後、吉祥寺という土地柄もあってか、
映画館の観客の大半は家族連れだ。
さすがに幼児はいないが、小学校低学年くらいの子が多かった。
こんなチビどもが2時間半以上もある映画をずっと見られるのか?途中で騒ぎだしたら嫌だな、と思った。
が、余計な心配だった。
これだけの大ヒットは、
過去の実績や宣伝のうまさだけでは達成できない。
文句なしのクオリティでまったく飽きさせない。
このアニメ(マンガ)の特徴は、
少年漫画と少女漫画のベストミックス。
少年マンガ得意のバトルアクションをベースに、
少女マンガ得意の内面ドラマがどんどん入ってくる。
スピード感あふれるアクションの合間に、
それぞれの登場人物の脳裏をよぎる数秒間の回想が、
10分、20分の主観的な物語として描かれるのだ。
その物語が次から次へと語られる。
双方のリズムが素晴らしく、長尺を感じさせない。
もう一つ、この映画が受け入れられるのは、
冒頭に挙げた「親孝行」というテーマの明快性。
何が正義がわからないこの時代に、
親・師匠を大事にすることの尊さを訴え、
親孝行、家族愛、兄弟愛といった圧倒的な正義を提示する。
観客にとってともわかりやすく、安心して観ていられる。
鬼殺隊は、親方様である産屋敷を父とする大家族であり、
曲者ぞろいの9人の柱は家族を支える兄弟。
主人公の炭治郎たちはその年若い弟である。
そして、彼らが闘う鬼の中でも、人間だった時代、
父親を救おうとしたり、養父であり、義父になるはずだった師匠を敬った猗窩座には同情・共感が寄せられる。
それと反対に、その美貌や天才性ゆえ、
両親を馬鹿にしていた童磨は嫌われる。
ただ、僕は彼の異常な心の闇がどのように形成されたのか、
とても興味がある。
これだけの狂気を表現できる声優さんの演技力はすごい。
近年、世間を震撼させる事件・犯罪は、
猗窩座のような、社会や他者に対する怨恨と、
童磨のような、お道化たサイコパス性が
混合したもののように思える。
「親孝行」をテーマに大成功を収めた「鬼滅の刃」。
しかし、圧倒的な正義は、巨悪に転じることもある。
宗教が、政治が、悪徳ビジネスが、
親孝行や家族愛を語りながら、巧妙に心を支配し、
金をだまし取ったり、個人の自由を侵したり、
人生を破壊するなど、人を喰う鬼に化けることがあり得る。
かつてこの国は、そこを利用して、
日本人は天皇を中心とした家族であるという夢を見せ、
富国強兵を進めて、アジア随一の軍国国家を創り上げた。
終戦の日の翌日に見たせいもあって、
どうしてもそのことが気になった。
娯楽なのだから、気にせず楽しめばいいのだが、
時として、娯楽は支配者にとって
都合の良い洗脳教育にも使われることは覚えておきたい。
終戦の日 昭和人の責任

戦争に負けた国だから、戦争の悲惨さを語れる、
原爆の悲惨さを語れる。
けれども「戦争の悲惨さなんて知ったこっちゃない」
という輩は、今、世界中で増えている。
同じ日本人の中にもそういう人は少なくないだろう。
だからこれからは悲惨さを語るだけでなく、
「なぜ、どうやって日本は戦争を始めたのか?」
そして「なぜ負けたのか?」を考え、
語り継ぐことがさらに重要になる。
あの時代、真珠湾攻撃など、緒戦の戦果に
「血沸き、肉躍った」という人が大勢いた。
「勝てば幸せになる」と信じていた人がたくさんいたのだ。
後から考えれば、そんなバカなと思えるが、
そうした愚かな熱狂があったこと、
その時の指導者層にだまされていたこと、
カルト宗教的なものが国民を洗脳していたこと。
忘れていけないと思う。
それは今の時代、近い将来にも十分起こり得るからだ。
それを防ぐためには、
ただ戦争は悲惨だと感情的に語るだけでなく、
なぜそうした愚かな考え方・愚かな行動をしてしまったのか、
冷静に考え、積極的に批判していかなくてはいけないと思う。
現代人の修行寺 檜原村・天光寺
奥多摩・檜原村の天光寺へ。
数十人が般若心情を唱える声が響いてくる。
ここは葬儀や供養と関係なく、「修行」に特化したお寺。
修行と言っても僧侶の修行でなく、対象は一般人で、
年間1万5千人が訪れるという。
「月刊終活」の取材でやってきたが、
メディア取材も多く、テレビ・新聞・雑誌はもとより、
ヒカキンをはじめ、いろいろなYouTuberも
体験レポートを発信している。
今日も本堂では、若者から中高年まで
40人近い人たちが修行に励み、写経、瞑想、お百度参り、
そして、滝行などを行っていた。
そして、10人以上の子供たち。
不登校や引きこもりの子たちもここで修行をする。
大人数が修行する場はもちろん、
食事や宿泊のための設備も整っており、
名だたる企業も修行・研修に訪れる。
お寺というより、研修センターに近い。
住職はもともと成功した実業家で、
20代の頃から飲食・不動産など、
さまざまな事業を手掛けていたが、
30代半ばで仏門を志願し、
それから10年以上かかって事業を整理したのち、
密教の修行を積んで僧籍を取得。
はなから葬式仏教に興味はなかったとのことで、
資産を投入して土地を買い、一般人の修行専門の天光寺を開いた。
ここはいわば、現代社会における「駆け込み寺」。
家庭・仕事・人生、様々な面で悩みや課題を抱える人たちや団体の
救済装置としての役割を担っているのだ。
修行した人に話を聴いたわけではないので、
本当に生き方・人間が変るのか、
ここでは悟りを開いたような気分になっても、
娑婆に戻ったらどうなるかはわからない。
でも、精神を整える施設として、
仏教の教えを活かした、こういう場所は
今の日本には必要なのだろうと思う。
秋川渓谷のある山の中だが、車でも、
電車・バスの乗り継ぎ
(五日市線・武蔵五日市駅からバス30分)でも、
都心や首都圏各地から日帰りで行ける。
座禅をやっているお寺は数あるが、
滝に打たれて修行とかって、僕は漫画でしか見たことない。
イメージの世界でしかなかったものを
リアルに体験できるお寺はそうないはず。
初心者向け修行メニューが用意されているので、
興味のある人、自分を変えたい人、
人生に変革を起こしたい人は、
ぜひ一度、体験してみるといいかも。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。
お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。




