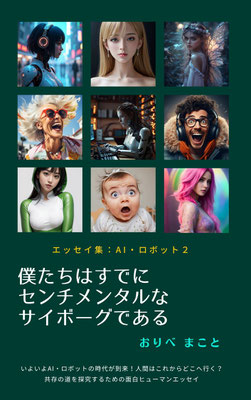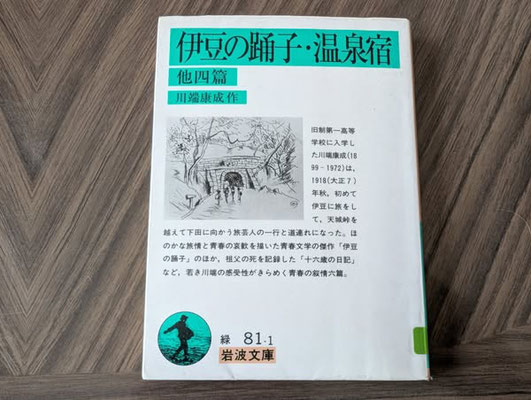- ホーム
- 電子書籍:おりべまこと劇場
- NEWS
- わたしの「わたしストーリー」
- 台本ライターとは?
- 実績:わたしの「しごとストーリー」
- サービスメニュー・料金プラン
- ブログ「台本屋のネタ帳」
- 仕事
- 生きる
- 食べる
- ロボット・AI
- 物語
- 歴史
- 世界
- 動物
- 音楽
- ビートルズ
- ドラマ・映画・演劇
- インターネット
- 本
- 台本
- エッセイ
- 子ども
- 2011年5月
- 家族
- エンディング
- 農業
- 旅
- 社会問題
- 昭和
- 認知症介護
- 広告
- 電子書籍
- 週末の懐メロ
- 2011年6月
- 2011年7月
- 2011年8月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年10月
- 2011年12月
- 2012年1月
- 2012年2月
- 2012年3月
- 2016年5月
- 2016年6月
- 2016年7月
- 2016年8月
- 2016年9月
- 2016年10月
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- 2017年6月
- 2017年7月
- 2017年8月
- 2017年9月
- 2017年10月
- 2017年11月
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- 2018年6月
- 2018年7月
- 2018年8月
- 2018年9月
- 2018年10月
- 2018年11月
- 2018年12月
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 新規ページ
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年4月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2020年11月
- 2020年12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- お問い合わせ
なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?

「かえるくん、東京を救う」というのは村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品です。
主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説。
ですが、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまいます。
この話は阪神大震災をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのですが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザだったりして独特の作品世界が出来上がっています。
しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思いました。
このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないでしょうか。
でも、その振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気もします。
欧米人はカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の使いとか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い気がします。
ところが、日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、かわいい系・愛すべき系の系譜がちゃんと続いていますね。
僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないでしょうか。
お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。
そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのでしょう。
カエル君に対するよいイメージはそういうところからきている気がします。
ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」って呼ばれています。
茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろうね、きっと。
雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってないなぁ。ケロケロ。
家族ストーリーを書く仕事② 個の家族

「これから生まれてくる子孫が見られるように」
――今回の家族ストーリー(ファミリーヒストリー)を作った動機について、3世代の真ん中の息子さん(団塊ジュニア世代)は作品の最後でこんなメッセージを残しています。
彼の中にはあるべき家族の姿があった。しかし現実にはそれが叶わなかった。だからやっと安定し、幸福と言える現在の形を映像に残すことを思い立った――僕にはそう取れます。
世間一般の基準に照らし合わせれば、彼は家庭に恵まれなかった人に属するでしょう。かつて日本でよく見られた大家族、そして戦後の主流となった夫婦と子供数人の核家族。彼の中にはそうした家族像への憧れがあったのだと思います。
けれども大家族どころか、核家族さえもはや過去のものになっているのでないか。今回の映像を見ているとそう思えてきます。
団塊の世代の親、その子、そして孫(ほぼ成人)。
彼らは家族であり、互いに支え合い、励まし合いながら生きている。
けれど、その前提はあくまで個人。それぞれ個別の歴史と文化を背負い、自分の信じる幸福を追求する人間として生きている。
むかしのように、まず家があり、そこに血のつながりのある人間として生まれ、育つから家族になるのではなく、ひとりひとりの個人が「僕たちは家族だよ」という約束のもとに集まって愛情と信頼を持っていっしょに暮らす。あるいは、離れていても「家族だよ」と呼び合い、同様に愛情と信頼を寄せ合う。だから家族になる。
これからの家族は、核家族からさらに小さな単位に進化した「ミニマム家族」――「個の家族」とでもいえばいいのでしょうか。
比喩を用いれば、ひとりひとりがパソコンやスマホなどのデバイスであり、必要がある時、○○家にログインし、ネットワークし、そこで父・母・息子・娘などの役割を担って、相手の求めることに応じる。それによってそれぞれが幸福を感じる。そうした「さま」を家族と呼称する――なかなかスムーズに表現できませんが、これからはそういう家族の時代になるのではないでしょうか。
なぜなら、そのほうが現代のような個人主義の世の中で生きていくのに何かと便利で快適だからです。人間は自身の利便性・快適性のためになら、いろいろなものを引き換えにできます。だから進化してこられたのです。
引き換えに失ったものの中にももちろん価値があるし、往々にして失ってみて初めてその価値に気づくケースがあります。むかしの大家族しかり。核家族しかり。こうしてこれらの家族の形態は、今後、一種の文化遺産になっていくのでしょう。
好きか嫌いかはともかく、そういう時代に入っていて、僕たちはもう後戻りできなくなっているのだと思います。
将来生まれてくる子孫のために、自分の家族の記憶を本なり映像なりの形でまとめて遺す―― もしかしたらそういう人がこれから結構増えるのかもしれません。
2016・6・27 Mon
家族ストーリーを書く仕事① 親子3世代の物語

親子3世代の物語がやっと完成一歩手前まで来ました。
昨年6月、ある家族のヒストリー映像を作るというお仕事を引き受けて、台本を担当。
足掛け1年掛かりでほぼ完成し、残るはクライアントさんに確認を頂いて、最後にナレーションを吹き込むのみ、という段階までこぎつけたのです。
今回のこの仕事は、ディレクターが取材をし、僕はネット経由で送られてくるその音源や映像を見て物語の構成をしていきました。そのディレクターとも最初に1回お会いしただけでご信頼を頂いたので、そのあとはほとんどメールのやり取りのみで進行しました。インターネットがあると、本当に家で何でもできてしまいます。
ですから時間がかかった割には、そんなに「たいへん感」はありませんでした。
取材対象の人たちともリアルでお会いしたことはなく、インタビューの音声――話の内容はもとより、しゃべり方のくせ、間も含めて――からそれぞれのキャラクターと言葉の背景にある気持ちを想像しながらストーリーを組み立てていくのは、なかなかスリリングで面白い体験でした(最初の下取材の頃はディレクターがまだ映像を撮っていなかったので、レコーダーの音源だけを頼りにやっていました)。
取材対象と直接会わない、会えないという制限は、今までネガティブに捉えていたのですが、現場(彼らの生活空間や仕事空間)の空気がわからない分、余分な情報に戸惑ったり、感情移入のし過ぎに悩まされたりすることがありません。
適度な距離を置いてその人たちを見られるので、かえってインタビューの中では語られていない範囲まで自由に発想を膨らませられ、こうしたドキュメンタリーのストーリーづくりという面では良い効果もあるんだな、と感じました。
後半(今年になってから)、全体のテーマが固まり、ストーリーの流れが固まってくると、今度は台本に基づいて取材がされるようになりました。
戦後の昭和~平成の時代の流れを、団塊の世代の親、その息子、そして孫(ほぼ成人)という一つの家族を通して見ていくと、よく目にする、当時の出来事や風俗の記録映像も、魂が定着くした記憶映像に見えてきます。
これにきちんとした、情感豊かなナレーターの声が入るのがとても楽しみです。
2016・6・26 Sun
ゴマスリずんだ餅と正直ファンタじいさん

おもちペタペタ伊達男
今週日曜(19日)の大河ドラマ「真田丸」で話題をさらったのは、長谷川朝晴演じる伊達政宗の餅つきパフォーマンスのシーン。「独眼竜」で戦国武将の中でも人気の高い伊達政宗ですが、一方で「伊達男」の語源にもなったように、パフォーマーというか、歌舞伎者というか、芝居っけも方もたっぷりの人だったようです。
だから、餅つきくらいやってもおかしくないのでしょうが、権力者・秀吉に対してあからさまにこびへつらい、ペッタンコとついた餅にスリゴマを・・・じゃなかった、つぶした豆をのっけて「ずんだ餅でございます」と差し出す太鼓持ち野郎の姿に、独眼竜のカッコいいイメージもこっぱみじんでした。
僕としては「歴人めし」の続編のネタ、一丁いただき、と思ってニヤニヤ笑って見ていましたが、ファンの人は複雑な心境だったのではないのでしょうか。(ネット上では「斬新な伊達政宗像」と、好意的な意見が多かったようですが)。
しかし、この後、信繁(幸村=堺雅人)と二人で話すシーンがあり、じつは政宗、今はゴマスリ太鼓持ち野郎を演じているが、いずれ時が来れば秀吉なんぞ、つぶしてずんだ餅にしてやる・・・と、野心満々であることを主人公の前で吐露するのです。
で、これがクライマックスの関ヶ原の伏線の一つとなっていくわけですね。
裏切りのドラマ
この「真田丸」は見ていると、「裏切り」が一つのテーマとなっています。
出てくるどの武将も、とにかくセコいのなんのttらありゃしない。立派なサムライなんて一人もいません。いろいろな仮面をかぶってお芝居しまくり、だましだまされ、裏切り裏切られ・・・の連続なのです。
そりゃそうでしょう。乱世の中、まっすぐ正直なことばかりやっていては、とても生き延びられません。
この伊達政宗のシーンの前に、北条氏政の最後が描かれていましたが、氏政がまっすぐな武将であったがために滅び、ゴマスリ政宗は生き延びて逆転のチャンスを掴もうとするのは、ドラマとして絶妙なコントラストになっていました。
僕たちも生きるためには、多かれ少なかれ、このゴマスリずんだ餅に近いことを年中やっているのではないでしょうか。身過ぎ世過ぎというやつですね。
けれどもご注意。
人間の心とからだって、意外と正直にできています。ゴマスリずんだ餅をやり過ぎていると、いずれまとめてお返しがやってくるも知れません。
人間みんな、じつは正直者
どうしてそんなことを考えたかと言うと、介護士の人と、お仕事でお世話しているおじいさんのことについて話したからです。
そのおじいさんはいろんな妄想に取りつかれて、ファンタジーの世界へ行っちゃっているようなのですが、それは自分にウソをつき続けて生きてきたからではないか、と思うのです。
これは別に倫理的にどうこうという話ではありません。
ごく単純に、自分にウソをつくとそのたびにストレスが蓄積していきます。
それが生活習慣になってしまうと、自分にウソをつくのが当たり前になるので、ストレスが溜まるのに気づかない。そういう体質になってしまうので、全然平気でいられる。
けれども潜在意識は知っているのです。
「これはおかしい。これは違う。これはわたしではな~い」
そうした潜在意識の声を、これまた無視し続けると、齢を取ってから自分で自分を裏切り続けてきたツケが一挙に出て来て、思いっきり自分の願いや欲望に正直になるのではないでしょうか。
だから脳がファンタジーの世界へ飛翔してしまう。それまでウソで歪めてきた自分の本体を取り戻すかのように。
つまり人生は最後のほうまで行くとちゃんと平均化されるというか、全体で帳尻が合うようにできているのではないかな。
自分を大事にするということ
というのは単なる僕の妄想・戯言かも知れないけど、自分に対する我慢とか裏切りとかストレスとかは、心や体にひどいダメージを与えたり、人生にかなりの影響を及ぼすのではないだろうかと思うのです。
みなさん、人生は一度きり。身過ぎ世過ぎばっかりやってると、それだけであっという間に一生終わっちゃいます。何が自分にとっての幸せなのか?心の内からの声をよく聴いて、本当の意味で自分を大事にしましょう。
介護士さんのお話を聞くといろんなことを考えさせられるので、また書きますね。
2016/6/23 Thu
死者との対話:父の昭和物語

すぐれた小説は時代を超えて読み継がれる価値がある。特に現代社会を形作った18世紀から20世紀前半にかけての時代、ヨーロッパ社会で生まれた文学には人間や社会について考えさせられる素材にあふれています。
その読書を「死者との対話」と呼んだ人がいます。うまい言い方をするものだと思いました。
僕たちは家で、街で、図書館で、本さえあれば簡単にゲーテやトルストイやドストエフスキーやブロンテなどと向かい合って話ができます。別にスピリチュアルなものに関心がなくても、書き残したものがあれば、私たちは死者と対話ができるのです。
もちろん、それはごく限られた文学者や学者との間で可能なことで、そうでない一般大衆には縁のないことでしょう。これまではそうでした。しかし、これからの時代はそれも可能なことではないかと思います。ただし、不特定多数の人でなく、ある家族・ある仲間との間でなら、ということですが。
僕は父の人生を書いてみました。
父は2008年の12月に亡くなりました。家族や親しい者の死も1年ほどたつと悲しいだの寂しいだの、という気持ちは薄れ、彼らは自分の人生においてどんな存在だったのだろう?どんなメッセージを遺していったのだろう?といったことを考えます。
父のことを書いてみようと思い立ったのは、それだけがきっかけではありませんでした。
死後、間もない時に、社会保険事務所で遺族年金の手続きをする際に父の履歴書を書いて提出しました。その時に感じたのは、血を分けた家族のことでも知らないことがたくさんあるな、ということでした。
じつはそれは当り前のことなのだが、それまではっきりとは気が付いていませんでした。なんとなく父のことも母のこともよく知っていると思いすごしていたのです。
実際は私が知っているのは、私の父親としての部分、母親としての部分だけであり、両親が男としてどうだったか、女としてどうだったか、ひとりの人間としてどうだったのか、といったことなど、ほとんど知りませんでした。数十年も親子をやっていて、知るきっかけなどなかったのです。
父の仕事ひとつ取ってもそうでした。僕の知っている父の仕事は瓦の葺換え職人だが、それは30歳で独立してからのことで、その前――20代のときは工場に勤めたり、建築会社に勤めたりしていたのです。それらは亡くなってから初めて聞いた話です。
そうして知った事実を順番に並べて履歴書を作ったのですが、その時には強い違和感というか、抵抗感のようなものを感じました。それは父というひとりの人間の人生の軌跡が、こんな紙切れ一枚の中に納まってしまうということに対しての、寂しさというか、怒りというか、何とも納得できない気持ちでした。
父は不特定多数の人たちに興味を持ってもらえるような、波乱万丈な、生きる迫力に満ち溢れた人生を歩んだわけはありませんい。むしろそれらとは正反対の、よくありがちな、ごく平凡な庶民の人生を送ったのだと思います。
けれどもそうした平凡な人生の中にもそれなりのドラマがあります。そして、そのドラマには、その時代の社会環境の影響を受けた部分が少なくありません。たとえば父の場合は、昭和3年(1928年)に生まれ、平成元年(1989年)に仕事を辞めて隠居していました。その人生は昭和の歴史とほぼ重なっています。
ちなみにこの昭和3年という年を調べてみると、アメリカでミッキーマウスの生まれた(ウォルト・ディズニーの映画が初めて上映された)年です。
父は周囲の人たちからは実直でまじめな仕事人間と見られていましたが、マンガや映画が好きで、「のらくろ」だの「冒険ダン吉」だのの話をよく聞かせてくれました。その時にそんなことも思い出したのです。
ひとりの人間の人生――この場合は父の人生を昭和という時代にダブらせて考えていくと、昭和の出来事を書き連ねた年表のようなものとは、ひと味違った、その時代の人間の意識の流れ、社会のうねりの様子みたいなものが見えてきて面白いのではないか・・・。そう考えて、僕は父に関するいくつかの個人的なエピソードと、昭和の歴史の断片を併せて書き、家族や親しい人たちが父のことを思い起こし、対話できるための一遍の物語を作ってみようと思い立ちました。
本当はその物語は父が亡くなる前に書くべきだったのではないかと、少し後悔の念が残っています。
生前にも話を聞いて本を書いてみようかなと、ちらりと思ったことはあるのですが、とうとう父自身に自分の人生を振り返って……といった話を聞く機会はつくれませんでした。たとえ親子の間柄でも、そうした機会を持つことは難しいのです。思い立ったら本気になって直談判しないと、そして双方互いに納得できないと永遠につくることはできません。あるいは、これもまた難しいけど、本人がその気になって自分で書くか・・・。それだけその人固有の人生は貴重なものであり、それを正確に、満足できるように表現することは至難の業なのだと思います。
実際に始めてから困ったのは、父の若い頃のことを詳しく知る人など、周囲にほとんどいないということ。また、私自身もそこまで綿密に調査・取材ができるほど、時間や労力をかけるわけにもいきませんでした。
だから母から聞いた話を中心に、叔父・叔母の話を少し加える程度にとどめ、その他、本やインターネットでその頃の時代背景などを調べながら文章を組み立てる材料を集めました。そして自分の記憶――心に残っている言葉・出来事・印象と重ね合わせて100枚程度の原稿を作ってみたのです。
自分で言うのもナンですが、情報不足は否めないものの、悪くない出来になっていて気に入っています。これがあるともうこの世にいない父と少しは対話できる気がするのです。自分の気持ちを落ち着かせ、互いの生の交流を確かめ、父が果たした役割、自分にとっての存在の意味を見出すためにも、こうした家族や親しい者の物語をつくることはとても有効なのではないかと思います。
高齢化が進む最近は「エンディングノート」というものがよく話題に上っています。
「その日」が来た時、家族など周囲の者がどうすればいいか困らないように、いわゆる社会的な事務手続き、お金や相続のことなどを書き残すのが、今のところ、エンディングノートの最もポピュラーな使い方になっているようだ。
もちろん、それはそれで、逝く者にとっても、後に残る者にとっても大事なことです。しかし、そうすると結局、その人の人生は、いくらお金を遺したかとか、不動産やら建物を遺したのか、とか、そんな話ばかりで終わってしまう恐れもあります。その人の人生そのものが経済的なこと、物質的なものだけで多くの人に価値判断されてしまうような気がするのです。
けれども本当に大事なのは、その人の人生にどんな意味や価値があったのか、を家族や友人・知人たちが共有することが出来る、ということではないでしょうか。
そして、もしその人の生前にそうしたストーリーを書くことができれば、その人が人生の最期の季節に、自分自身を取り戻せる、あるいは、取り戻すきっかけになり得る、ということではないでしょうか。
赤影メガネとセルフブランディング

♪赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光る涼しい目 仮面の忍者だ
赤影だ~
というのは、テレビの「仮面の忍者 赤影」の主題歌でしたが、涼しい目かどうかはともかく、僕のメガネは10数年前から「赤影メガネ」です。これにはちょっとした物語(というほどのものではないけど)があります。
当時、小1だか2年の息子を連れてメガネを買いに行きました。
それまでは確か茶色の細いフレームの丸いメガネだったのですが、今回は変えようかなぁ、どうしようかなぁ・・・とあれこれ見ていると、息子が赤フレームを見つけて「赤影!」と言って持ってきたのです。
「こんなの似合うわけないじゃん」と思いましたが、せっかく選んでくれたのだから・・・と、かけてみたら似合った。子供の洞察力おそるべし。てか、単に赤影が好きだっただけ?
とにかく、それ以来、赤いフレームのメガネが、いつの間にか自分のアイキャッチになっていました。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいもの。
独立・起業・フリーランス化ばやりということもあり、セルフブランディングがよく話題になりますが、自分をどう見せるかというのはとても難しい。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいのです。
とはいえ、自分で気に入らないものを身に着けてもやっぱり駄目。できたら安心して相談できる家族とか、親しい人の意見をしっかり聞いて(信頼感・安心感を持てない人、あんまり好きでない人の意見は素直に聞けない)、従来の考え方にとらわれない自分像を探していきましょう。
ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?
ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。
BACK in the NEW YORK CITY。
僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。
特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。
そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。
衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。
そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。
1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。
向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。
なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。
どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・
「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。
おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。
別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。
あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。
というのが、今から約20年前のこと。
その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?
表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?
件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。
ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。
そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。
2016年6月16日
インターネットがつくるフォークロア

インターネットの出現は社会を変えた――ということは聞き飽きるほど、あちこちで言われています。けれどもインターネットが本格的に普及したのは、せいぜいここ10年くらいの話。全世代、全世界を見渡せば、まだ高齢者の中には使ったことがないという人も多いし、国や地域によって普及率の格差も大きい。だから、その変化の真価を国レベル・世界レベルで、僕たちが実感するのはまだこれからだと思います。
それは一般によくいわれる、情報収集がスピーディーになったとか、通信販売が便利になったとか、というカテゴリーの話とは次元が違うものです。もっと人間形成の根本的な部分に関わることであり、ホモサピエンスの文化の変革にまでつながること。それは新しい民間伝承――フォークロアの誕生です。
“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承
最初はどこでどのように聞いたのか覚えてないですが、僕たちは自分でも驚くほど、昔話・伝承をよく知っています。成長の過程のどこかで桃太郎や浦島太郎や因幡の白ウサギと出会い、彼らを古い友だちのように思っています。
家庭でそれらの話を大人に読んでもらったこともあれば、幼稚園・保育園・小学校で体験したり、最近ならメディアでお目にかかることも多い。それはまるで遺伝子に組み込まれているかのように、あまりに自然に身体の中に溶け込んでいるのです。
調べて確認したわけではないが、こうした感覚は日本に限らず、韓国でも中国でもアメリカでもヨーロッパでも、その地域に住んでいる人なら誰でも持ち得るのではないでしょうか。おそらく同じような現象があると思います。それぞれどんな話がスタンダードとなっているのかは分かりませんが、その国・その地域・その民族の間で“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承の類が一定量あるのです。
それらは長い時間を生きながらえるタフな生命エネルギーを持っています。それだけのエネルギーを湛えた伝承は、共通の文化の地層、つまり一種のデータベースとして、万人の脳の奥底に存在しています。その文化の地層の上に、その他すべての情報・知識が積み重なっている――僕はそんなイメージを持っています。
世界共通の、新しいカテゴリーの伝承
そして、昔からあるそれとは別に、これから世界共通の、新しいカテゴリーの伝承が生まれてくる。その新しい伝承は人々の間で共通の文化の地層として急速に育っていくのでないか。そうした伝承を拡散し、未来へ伝える役目を担っているのがインターネット、というわけです。
ところで新しい伝承とは何でしょう? その主要なものは20世紀に生まれ、花開いた大衆文化――ポップカルチャーではないでしょうか。具体的に挙げていけば、映画、演劇、小説、マンガ、音楽(ジャズ、ポップス、ロック)の類です。
21世紀になる頃から、こうしたポップカルチャーのリバイバルが盛んに行われるようになっていました。
人々になじみのあるストーリー、キャラクター。
ノスタルジーを刺激するリバイバル・コンテンツ。
こうしたものが流行るのは、情報発信する側が、商品価値の高い、新しいものを開発できないためだと思っていました。
そこで各種関連企業が物置に入っていたアンティーク商品を引っ張り出してきて、売上を確保しようとした――そんな事情があったのでしょう。実際、最初のうちはそうだったはずです。
だから僕は結構冷めた目でそうした現象を見ていました。そこには半ば絶望感も混じっていたと思います。前の世代を超える、真に新しい、刺激的なもの・感動的なものは、この先はもう現れないのかも知れない。出尽くしてしまったのかも知れない、と……。
しかし時間が経ち、リバイバル現象が恒常化し、それらの画像や物語が、各種のサイトやYouTubeの動画コンテンツとして、ネット上にあふれるようになってくると考え方は変わってきました。
それらのストーリー、キャラクターは、もはや単なるレトロやリバイバルでなく、世界中の人たちの共有財産となっています。いわば全世界共通の伝承なのです。
僕たちは欧米やアジアやアフリカの人たちと「ビートルズ」について、「手塚治虫」について、「ガンダム」について、「スターウォーズ」について語り合えるし、また、それらを共通言語にして、子や孫の世代とも同様に語り合えます。
そこにボーダーはないし、ジェネレーションギャップも存在しません。純粋にポップカルチャーを媒介にしてつながり合う、数限りない関係が生まれるのです。
また、これらの伝承のオリジナルの発信者――ミュージシャン、映画監督、漫画家、小説家などによって、あるいは彼ら・彼女らをリスペクトするクリエイターたちによって自由なアレンジが施され、驚くほど新鮮なコンテンツに生まれ変わる場合もあります。
インターネットの本当の役割
オリジナル曲をつくった、盛りを過ぎたアーティストたちが、子や孫たち世代の少年・少女と再び眩いステージに立ち、自分の資産である作品を披露。それをYouTubeなどを介して広めている様子なども頻繁に見かけるようになりました。
それが良いことなのか、悪いことなのか、評価はさておき、そうした状況がインタ―ネットによって現れています。これから10年たち、20年たち、コンテンツがさらに充実し、インターネット人口が現在よりさらに膨れ上がれば、どうなるでしょうか?
おそらくその現象は空気のようなものとして世の中に存在するようになり、僕たちは新たな世界的伝承として、人類共通の文化遺産として、完成された古典として見なすようになるでしょう。人々は分かりやすく、楽しませてくれるものが大好きだからです。
そして、まるで「桃太郎」のお話を聞くように、まっさらな状態で、これらの伝承を受け取った子供たちが、そこからまた新しい、次の時代の物語を生みだしていきます。
この先、そうした現象が必ず起こると思う。インターネットという新参者のメディアはその段階になって、さらに大きな役割を担うのでしょう。それは文化の貯蔵庫としての価値であり、さらに広げて言えば、人類の文化の変革につながる価値になります。
2016年6月13日
地方自治体のホームページって割と面白い

ここのところ、雑誌の連載で地方のことを書いています。
書くときはまずベーシックな情報(最初のリード文として使うこともあるので)をインターネットで調べます。
これはウィキペディアなどの第3者情報よりも、各県の公式ホームページの方が断然面白い。自分たちの県をどう見せ、何をアピールしたいかがよくわかるからです。
なんでも市場価値が問われる時代。「お役所仕事云々・・・」と言われることが多い自治体ですが、いろいろ努力して、ホームページも工夫しています。
最近やった宮崎県のキャッチコピーは「日本のひなた」。
日照時間の多さ、そのため農産物がよく獲れるということのアピール。
そしてもちろん、人や土地のやさしさ、あったかさ、ポカポカ感を訴えています。
いろいろな人たちがお日さまスマイルのフリスビーを飛ばして、次々と受け渡していくプロモーションビデオは、単純だけど、なかなか楽しかった。
それから「ひなた度データ」というのがあって、全国比率のいろいろなデータが出ています。面白いのが、「餃子消費量3位」とか、「中学生の早寝早起き率 第3位」とか、「宿題実行率 第4位」とか、「保護者の学校行事参加率 第2位」とか・・・
「なんでこれがひなた度なんじゃい!」とツッコミを入れたくなるのもいっぱい。だけど好きです、こういうの。
取材するにしても、いきなり用件をぶつけるより、「ホームページ面白いですね~」と切り出したほうが、ちょっとはお役所臭さが緩和される気がします。
「あなたのひなた度は?」というテストもあって、やってみたら100パーセントでした。じつはまだ一度も行ったことないけれど、宮崎県を応援したくなるな。ポカポカ。
2016年6月12日
タイムマシンにおねがい

きのう6月10日は「時の記念日」でした。それに気がついたら頭の中で突然、サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」が鳴り響いてきたので、YouTubeを見てみたら、1974年から2006年まで、30年以上にわたるいろいろなバージョンが上がっていました。本当にインターネットの世界でタイムマシン化しています。
これだけ昔の映像・音源が見放題・聞き放題になるなんて10年前は考えられませんでした。こういう状況に触れると、改めてインターネットのパワーを感じると同時に、この時代になるまで生きててよかった~と、しみじみします。
そしてまた、ネットの中でならおっさん・おばさんでもずっと青少年でいられる、ということを感じます。60~70年代のロックについて滔々と自分の思い入れを語っている人がいっぱいいますが、これはどう考えても50代・60代の人ですからね。
でも、彼ら・彼女らの頭の中はロックに夢中になっていた若いころのまんま。脳内年齢は10代・20代。インターネットに没頭することは、まさしくタイムマシンンに乗っているようなものです。
この「タイムマシンにおねがい」が入っているサディスティック・ミカ・バンドの「黒船」というアルバムは、1974年リリースで、いまだに日本のロックの最高峰に位置するアルバムです。若き加藤和彦が作った、世界に誇る傑作と言ってもいいのではないでしょうか。
中でもこの曲は音も歌詞もゴキゲンです。いろいろ見た(聴いた)中でいちばんよかったのは、最新(かな?)の2006年・木村カエラ・ヴォーカルのバージョンです。おっさんロッカーたちをバックに「ティラノサウルスおさんぽ アハハハ-ン」とやってくれて、くらくらっときました。
やたらと「オリジナルでなきゃ。あのヴォーカルとあのギターでなきゃ」とこだわる人がいますが、僕はそうは思わない。みんなに愛される歌、愛されるコンテンツ、愛される文化には、ちゃんと後継ぎがいて、表現技術はもちろんですが、それだけでなく、その歌・文化の持ち味を深く理解し、見事に自分のものとして再現します。中には「オリジナルよりいいじゃん!」と思えるものも少なくありません。(この木村カエラがよい例)。
この歌を歌いたい、自分で表現したい!――若い世代にそれだけ強烈に思わせる、魅力あるコンテンツ・文化は生き残り、クラシックとして未来に継承されていくのだと思います。
もう一つおまけに木村カエラのバックでは、晩年の加藤和彦さんが本当に楽しそうに演奏をしていました。こんなに楽しそうだったのに、どうして自殺してしまったのだろう・・・と、ちょっと哀しくもなったなぁ。
2016年6月11日
「歴人めし」おかわり情報

9日間にわたって放送してきた「歴人めし」は、昨日の「信長巻きの巻」をもっていったん終了。しかし、ご安心ください。7月は夜の時間帯に再放送があります。ぜひ見てくださいね。というか、You Tubeでソッコー見られるみたいですが。
https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php?series_cd=12041
この仕事では歴人たちがいかに食い物に執念を燃やしていたかがわかりました。 もちろん、記録に残っているのはほんの少し。
源内さんのように、自分がいかにうなぎが好きか、うなぎにこだわっているか、しつこく書いている人も例外としていますが、他の人たちは自分は天下国家のことをいつも考えていて、今日のめしのことなんかどうでもいい。カスミを食ってでの生きている・・・なんて言い出しそうな勢いです。
しかし、そんなわけはない。偉人と言えども、飲み食いと無関係ではいられません。 ただ、それを口に出して言えるのは、平和な世の中あってこそなのでしょう。だから日本の食文化は江戸時代に発展し、今ある日本食が完成されたのです。
そんなわけで、「おかわり」があるかもしれないよ、というお話を頂いているので、なんとなく続きを考えています。
駿河の国(静岡)は食材豊富だし、来年の大河の井伊直虎がらみで何かできないかとか、 今回揚げ物がなかったから、何かできないかとか(信長に捧ぐ干し柿入りドーナツとかね)、
柳原先生の得意な江戸料理を活かせる江戸の文人とか、明治の文人の話だとか、
登場させ損ねてしまった豊臣秀吉、上杉謙信、伊達政宗、浅井三姉妹、新選組などの好物とか・・・
食について面白い逸話がありそうな人たちはいっぱいいるのですが、柳原先生の納得する人物、食材、メニュー、ストーリーがそろって、初めて台本にできます。(じつは今回もプロット段階でアウトテイク多数)
すぐにとはいきませんが、ぜひおかわりにトライしますよ。
それまでおなかをすかせて待っててくださいね。ぐ~~。
2016年6月7日
歴人めし♯9:スイーツ大好き織田信長の信長巻き

信長が甘いもの好きというのは、僕は今回のリサーチで初めて知りました。お砂糖を贈答したり、されたりして外交に利用していたこともあり、あちこちの和菓子屋さんが「信長ゆかりの銘菓」を開発して売り出しているようです。ストーリーをくっつけると、同じおまんじゅうやあんころもちでも何だか特別なもの、他とは違うまんじゅうやあんころもちに思えてくるから不思議なものです。
今回、ゆかりの食材として採用したのは「干し柿」と「麦こがし(ふりもみこがし)」。柿は、武家伝統の本膳料理(会席料理のさらに豪華版!)の定番デザートでもあり、記録をめくっていると必ず出てきます。
現代のようなスイーツパラダイスの時代と違って、昔の人は甘いものなどそう簡単に口にできませんでした。お砂糖なんて食品というよりは、宝石や黄金に近い超ぜいたく品だったようです。だから信長に限らず、果物に目のない人は大勢いたのでしょう。
中でもは干し柿にすれば保存がきくし、渋柿もスイートに変身したりするので重宝されたのだと思います。
「信長巻き」というのは柳原尚之先生のオリジナル。干し柿に白ワインを染み込ませるのと、大徳寺納豆という、濃厚でしょっぱい焼き味噌みたいな大豆食品をいっしょに巻き込むのがミソ。
信長は塩辛い味も好きで、料理人が京風の上品な薄味料理を出したら「こんな水臭いものが食えるか!」と怒ったという逸話も。はまった人なら知っている、甘い味としょっぱい味の無限ループ。交互に食べるともうどうにも止まらない。信長もとりつかれていたのだろうか・・・。
ちなみに最近の映画やドラマの中の信長と言えば、かっこよくマントを翻して南蛮渡来の洋装を着こなして登場したり、お城の中のインテリアをヨーロッパの宮殿風にしたり、といった演出が目につきます。
スイーツ好きとともに、洋風好き・西洋かぶれも、今やすっかり信長像の定番になっていますが、じつはこうして西洋文化を積極的に採り入れたのも、もともとはカステラだの、金平糖だの、ボーロだの、ポルトガルやスペインの宣教師たちが持ち込んできた、砂糖をたっぷり使った甘いお菓子が目当てだったのです。(と、断言してしまう)
「文化」なんていうと何やら高尚っぽいですが、要は生活習慣の集合体をそう呼ぶまでのこと。その中心にあるのは生活の基本である衣食住です。
中でも「食」の威力はすさまじく、これに人間はめっぽう弱い。おいしいものの誘惑からは誰も逃れられない。そしてできることなら「豊かな食卓のある人生」を生きたいと願う。この「豊かな食卓」をどう捉えるかが、その人の価値観・生き方につながるのです。
魔王と呼ばれながら、天下統一の一歩手前で倒れた信長も、突き詰めればその自分ならではの豊かさを目指していたのではないかと思うのです。
2016年6月6日
歴人めし♯8 山内一豊の生食禁止令から生まれた?「カツオのたたき」

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だったころ、琵琶湖のほとりに金目教という怪しい宗教が流行っていた・・・」というナレーションで始まるのは「仮面の忍者・赤影」。子供の頃、夢中になってテレビにかじりついていました。
時代劇(忍者もの)とSF活劇と怪獣物をごちゃ混ぜにして、なおかつチープな特撮のインチキスパイスをふりかけた独特のテイストは、後にも先にもこの番組だけ。僕の中ではもはや孤高の存在です。
いきなり話が脱線していますが、赤影オープニングのナレーションで語られた「琵琶湖のほとり」とは滋賀県長浜あたりのことだったのだ、と気づいたのは、ちょうど10年前の今頃、イベントの仕事でその長浜に滞在していた時です。
このときのイベント=期間限定のラジオ番組制作は、大河ドラマ「功名が辻」関連のもの。4月~6月まで断続的に数日ずつ訪れ、街中や郊外で番組用の取材をやっていました。春でもちょっと寒いことを我慢すれば、賑わいがあり、かつまた、自然や文化財にも恵まれている、とても暮らしやすそうな良いところです。
この長浜を開いたのは豊臣秀吉。そして秀吉の後を継いで城主になったのが山内一豊。「功名が辻」は、その一豊(上川隆也)と妻・千代(仲間由紀恵)の物語。そして本日の歴人めし♯9は、この一豊ゆかりの「カツオのたたき」でした。
ところが一豊、城主にまでしてもらったのに秀吉の死後は、豊臣危うしと読んだのか、関が原では徳川方に寝返ってしまいます。つまり、うまいこと勝ち組にすべり込んだわけですね。
これで一件落着、となるのが、一豊の描いたシナリオでした。
なぜならこのとき、彼はもう50歳。人生50年と言われた時代ですから、その年齢から本格的な天下取りに向かった家康なんかは例外中の例外。そんな非凡な才能と強靭な精神を持ち合わせていない、言ってみればラッキーで何とかやってきた凡人・一豊は、もう疲れたし、このあたりで自分の武士人生も「あがり」としたかったのでしょう。
できたら、ごほうびとして年金代わりに小さな領地でももらって、千代とのんびり老後を過ごしたかったのだと思います。あるいは武士なんかやめてしまって、お百姓でもやりながら余生を・・・とひそかに考えていた可能性もあります。
ところが、ここでまた人生逆転。家康からとんでもないプレゼントが。
「土佐一国をおまえに任せる」と言い渡されたのです。
一国の領主にしてやる、と言われたのだから、めでたく大出世。一豊、飛び上がって喜んだ・・・というのが定説になっていますが、僕はまったくそうは思いません。
なんせ土佐は前・領主の長曾我部氏のごっつい残党がぞろぞろいて、新しくやってくる領主をけんか腰で待ち構えている。徳川陣営の他の武将も「あそこに行くのだけは嫌だ」と言っていたところです。
現代に置き換えてみると、後期高齢者あたりの年齢になった一豊が、縁もゆかりもない外国――それも南米とかのタフな土地へ派遣されるのようなもの。いくらそこの支店長のポストをくれてやる、と言われたって全然うれしくなんかなかったでしょう。
けれども天下を収めた家康の命令は絶対です。断れるはずがありません。
そしてまた、うまく治められなければ「能無し」というレッテルを貼られ、お家とりつぶしになってしまいます。
これはすごいプレッシャーだったでしょう。「勝ち組になろう」なんて魂胆を起こすんじゃなかった、と後悔したに違いありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
恐怖にかられてしまった人間は、より以上の恐怖となる蛮行、残虐行為を行います。
一豊は15代先の容堂の世代――つまり、250年後の坂本龍馬や武市半平太の時代まで続く、武士階級をさらに山内家の上士、長曾我部氏の下士に分けるという独特の差別システムまで発想します。
そうして土佐にきてわずか5年で病に倒れ、亡くなってしまった一豊。寿命だったのかもしれませんが、僕には土佐統治によるストレスで命を縮めたとしか思えないのです。
「カツオのたたき」は、食中毒になる危険を慮った一豊が「カツオ生食禁止令」を出したが、土佐の人々はなんとかおいしくカツオを食べたいと、表面だけ火であぶり、「これは生食じゃのうて焼き魚だぜよ」と抗弁したところから生まれた料理――という話が流布しています。
しかし、そんな禁止令が記録として残っているわけではありません。やはりこれはどこからか生えてきた伝説なのでしょう。
けれども僕はこの「カツオのたたき発祥物語」が好きです。それも一豊を“民の健康を気遣う良いお殿様”として解釈するお話でなく、「精神的プレッシャーで恐怖と幻想にとりつかれ、カツオの生食が、おそるべき野蛮人たちの悪食に見えてしまった男の物語」として解釈してストーリーにしました。
随分と長くなってしまいましたが、ここまで書いてきたバックストーリーのニュアンスをイラストの方が、短いナレーションとト書きからじつにうまく掬い取ってくれて、なんとも情けない一豊が画面で活躍することになったのです。
一豊ファンの人には申し訳ないけど、カツオのたたきに負けず劣らず、実にいい味出している。マイ・フェイバリットです。
2016年6月3日
「歴人めし」徳川家康提唱、日本人の基本食

歴人めし第7回は「徳川家康―八丁味噌の冷汁と麦飯」。
「これが日本人の正しい食事なのじゃ」と家康が言ったかどうかは知りませんが、米・麦・味噌が長寿と健康の基本の3大食材と言えば、多くの日本人は納得するのではないでしょうか。エネルギー、たんぱく質、ビタミン、その他の栄養素のバランスも抜群の取り合わせです。
ましてやその発言の主が、天下を統一して戦国の世を終わらせ、パックス・トクガワ―ナを作った家康ならなおのこと。実際、家康はこの3大食材を常食とし、かなり養生に努めていたことは定説になっています。
昨年はその家康の没後400年ということで、彼が城を構えた岡崎・浜松・静岡の3都市で「家康公400年祭」というイベントが開催され、僕もその一部の仕事をしました。
そこでお会いしたのが、岡崎城から歩いて八丁(約780メートル)の八丁村で八丁味噌を作っていた味噌蔵の後継者。
かのメーカー社長は現在「Mr.Haccho」と名乗り、毎年、海外に八丁味噌を売り込みに行っているそうで、日本を代表する調味料・八丁味噌がじわじわと世界に認められつつあるようです。
ちなみに僕は名古屋の出身なので子供の頃から赤味噌に慣れ親しんできました。名古屋をはじめ、東海圏では味噌と言えば、赤味噌=豆味噌が主流。ですが、八丁味噌」という食品名を用いれるのは、その岡崎の元・八丁村にある二つの味噌蔵――現在の「まるや」と「カクキュー」で作っているものだけ、ということです。
しかし、養生食の米・麦・味噌をがんばって食べ続け、健康に気を遣っていた家康も、平和な世の中になって緊張の糸がプツンと切れたのでしょう。
がまんを重ねて押さえつけていた「ぜいたくの虫」がそっとささやいたのかもしれません。
「もういいんじゃないの。ちょっとぐらいぜいたくしてもかまへんで~」
ということで、その頃、京都でブームになっていたという「鯛の天ぷら」が食べた~い!と言い出し、念願かなってそれを口にしたら大当たり。おなかが油に慣れていなかったせいなのかなぁ。食中毒がもとで亡くなってしまった、と伝えられています。
でも考えてみれば、自分の仕事をやり遂げて、最期に食べたいものをちゃんと食べられて旅立ったのだから、これ以上満足のいく人生はなかったのではないでしょうか。
2016年6月2日
歴人めし「篤姫のお貝煮」と御殿女中
絶好調「真田丸」に続く2017年大河は柴咲コウ主演「おんな城主 直虎」。今年は男だったから来年は女――というわけで、ここ10年あまり、大河は1年ごとに主人公が男女入れ替わるシフトになっています。
だけど女のドラマは難しいんです。なかなか資料が見つけらない。というか、そもそも残っていな。やはり日本の歴史は(外国もそうですが)圧倒的に男の歴史なんですね。
それでも近年、頻繁に女主人公の物語をやるようになったのは、もちろん女性の視聴者を取り込むためだけど、もう一つは史実としての正確さよりも、物語性、イベント性を重視するようになってきたからだと思います。
テレビの人気凋落がよく話題になりますが、「腐っても鯛」と言っては失礼だけど、やっぱ日曜8時のゴールデンタイム、「お茶の間でテレビ」は日本人の定番ライフスタイルです。
出演俳優は箔がつくし、ゆかりの地域は観光客でにぎわうって経済も潤うし、いろんなイベントもぶら下がってくるし、話題も提供される・・・ということでいいことづくめ。
豪華絢爛絵巻物に歴史のお勉強がおまけについてくる・・・ぐらいでちょうどいいのです。(とはいっても、制作スタッフは必死に歴史考証をやっています。ただ、部分的に資料がなくても諦めずに面白くするぞ――という精神で作っているということです)
と、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、なんとか「歴人めし」にも一人、女性を入れたいということで、あれこれ調べた挙句、やっと好物に関する記録を見つけたのが、20082年大河のヒロイン「篤姫」。本日は天璋院篤姫の「お貝煮」でした。
見てもらえればわかるけど、この「お貝煮」なる料理、要するにアワビ入りの茶碗蒸しです。その記述が載っていたのが「御殿女中」という本。この本は明治から戦前の昭和にかけて活躍した、江戸文化・風俗の研究家・三田村鳶魚の著作で。篤姫付きの女中をしていた“大岡ませ子”という女性を取材した、いわゆる聞き書きです。
明治も30年余り経ち、世代交代が進み、新しい秩序・社会体制が定着してくると、以前の時代が懐かしくなるらしく、「江戸の記憶を遺そう」というムーブメントが文化人の間で起こったようです。
そこでこの三田村鳶魚さんが、かなりのご高齢だったます子さんに目をつけ、あれこれ大奥の生活について聞き出した――その集成がこの本に収められているというわけです。これは現在、文庫本になっていて手軽に手に入ります。
ナレーションにもしましたが、ヘアメイク法やら、ファッションやら、江戸城内のエンタメ情報やらも載っていて、なかなか楽しい本ですが、篤姫に関するエピソードで最も面白かったのが飼いネコの話。
最初、彼女は狆(犬)が買いたかったようなのですが、夫の徳川家定(13代将軍)がイヌがダメなので、しかたなくネコにしたとか。
ところが、このネコが良き相棒になってくれて、なんと16年もいっしょに暮らしたそうです。彼女もペットに心を癒された口なのでしょうか。
そんなわけでこの回もいろんな発見がありました。
続編では、もっと大勢の女性歴人を登場させ、その好物を紹介したいと思っています。
2016年6月1日
映画「国宝」 畸形の演劇と女形の生き様

かつてはギリシャ劇にも、シェイクスピア劇にも、
中国の京劇にも、能・狂言にも、女優は存在せず、
男の俳優だけで芝居は上演されてきた。
いろいろな事情があったと思うが、女が舞台に立つと、
多くの男がそれに現を抜かして働かなくなり、
社会が立ちいかなくなったので、為政者が禁じたのだろう。
しかし、社会の発展とともに演劇の世界は広く開放され、
女優もだんだん舞台に立つようになった。
21世紀の今日、世界でいまだに女優が舞台に立てない演劇は、
日本の歌舞伎だけである。
江戸幕府によって女優が禁じられてから400年。
女を演じる男優--女形は
何代にもわたってその技芸が伝承されてきた。
今や一種の世界遺産ともいえる独特のスタイルだ。
その女形に人生を賭け、紆余曲折を経ながら
ついに人間国宝にまでたどり着く男の物語。
吉田修一の同名小説を映画化した「国宝」。
1964年から2014年までの50年間を描いた一代記は、
歌舞伎の世界の裏側を見事に描き出している。
歌舞伎は一見、華やかでセレブな世界だが、
よく考えたら、何でいまだにこんな慣習・ルールが成り立つの?
と思えるような魔訶不思議な世界であり、
畸形の演劇ともいえる。
いまだに女が舞台に立つのが許されないことに加え、
伝統芸能でありながら、国家に守られているわけでなく、
純然たる商業演劇として運営されていること。
家・家族で伝承する技芸であるからこそ、
「血」を守っていくためのこだわりが強いこと。
みんな、小さな世界で生きているので、
身内・味方に対する愛情・友情・敬愛心は強いが、
一旦事情が変わると、
たとえば、父親・師匠などの後ろ盾を亡くしてしまうと、
たちまち冷淡に扱われ、干されるようになる。
要するに、この物語の主人公・喜久雄のように、
才能があれば、芸が優れていれば出世できるという
フェアな世界ではないのだ。
とはいえ、商業演劇なので、
客を集め、興行を打っていくため、
常に客の期待・時代のニーズに応え、
新しいスターをプロデュースする必要がある。
その微妙なバランスのなかで歌舞伎は生き延びてきた。
そのあたり、原作(まだ読んでないが)は
かなり詳細に買いているようだが、
この映画でも十分描き出している。
重厚なドラマは、昭和・平成の時代背景も相まって、
素晴らしく見ごたえがあって、
3時間以上の長丁場でもまったく飽きさせない。
吉沢亮と横浜流星の熱演が話題になっていて、
もちろん、彼らの感情表現や演技・踊りは素晴らしいのだが、
僕としては、この2人に影響を与え、
無言のうちに「女形の生き方」を示唆する
人間国宝・小野川万菊の存在が、とりわけ胸に刺さった。
演じるのは、長らく孤高のダンサーとして活躍してきた田中泯。
その妖怪じみた女形ぶりはすさまじく、登場シーンになると、
まるでそこだけアングラ演劇の世界みたいになる。
そして、人間国宝という栄誉ある称号にあるまじき
最後の登場シーンは、戦慄を覚えるほど印象的で、
そこに「国宝」というタイトルの意味が
込められているように思えた。
昭和の時代まで、歌舞伎役者は江戸時代の身分制度を引きづった
「河原乞食」だった。
今でこそセレブ扱いされるが、一般的なセレブイメージと、」
彼らの生きる世界・人生には大きなギャップがある。
映画「国宝」は、そんな歌舞伎という畸形の演劇の歴史・文化、
そしてこの特殊な世界を成立させている人間模様を感じ取ることができる奇跡的なコンテンツだ。
舞台のシーンの迫力、女形を演じる喜久雄(吉沢亮)と
俊介(横浜流星)の美しさ。
この映画の魅力・価値を堪能するには、
テレビやパソコンサイズではだめで、
絶対に映画館の大スクリーンで見るべきだと思う。
777

素数である7は神秘のムードをまとい、
マジックナンバーとして古今東西、一目置かれてきた。
その7が3つ並ぶ(3ももちろん素数でマジックナンバー)
令和7年7月7日は大ラッキーデイ!
と大騒ぎになることもなく過ぎ去ろうとしている。
思い返すと、7はやはりミステリアスな数字。
かの「ノストラダムスの大予言」も、
空から大魔王が降ってくるのは「7の月」だった。
他の数字だったら、あそこまで話題にならなかったのではないか。
おとといの予言だか予知夢だかの「7月5日」も、
本当は7月7日にしたかったのだと思う。
でも、777だと、さすがに出来過ぎ感がするので、
少しずらして5日にしたのだろう。
「セブンイレブン」が成功したのは、
もちろんコンビニエンスストアという
新しい商形態を生み出したからだが、
「7(セブン)」のマジックも侮れない。
11も素数。素数を二つ並べ、韻を踏み、語感も抜群。
もともと午前7時開店、午後11時閉店という営業だったので、
理屈も整い、説得感も抜群。
誰でも一発で覚えられる最強のネーミングだ。
もし店名が「セブンイレブン」でなかったら、
コンビニエンスストアはこれほど普及しなかっただろう。
というのは言い過ぎ?
世の中のことはともかく、
自分の人生で7がつく日に何か大きな出来事があっただろうか、
と思い返してみた。
2つ思い当たった。
息子の誕生日が5月17日。
父の命日が12月17日。
ついでに言うと、祖父の享年が77歳だった。
こうなると、自分の命日や享年が気になるが、
それは考えずにおこう。
雨が降らなかったので、織姫と彦星は無事に会えただろう。
7は星や宇宙とも相性抜群。
ウルトラセブンもシックスやエイトじゃサマにならない。
やっぱりセブンはミステリアスでファンタジックで大好きだ。
佐野元春朝イチ出演 本物の還暦ロック
NHK朝イチ・プレミアムトークに佐野元春がゲスト出演。
僕は見ていないが、カミさんが見て「カッコイイ」と感激。
いろいろ内容についても教えてくれた。
ネットでも盛り上がり、ひと騒動だったようである。
佐野元春は若い頃よりカッコよく、
全世代にメッセージを伝えられる数少ない「ポオラ・スター」だ。
いま還暦を超えて活躍するミュージシャン・
アーティストは珍しくない。
いったん消えたが、高齢化する世の中の様子を見て
「まだできそう」と思って戻ってきた人もいるだろう。
あるいは、視聴率を取れるネタに困った
テレビなどのメディアに呼ばれるのかもしれない。
ただ、多くはどうしても「あの頃はよかったワールド」になり、
かつて青春を共有したファンたちが、彼・彼女らを囲んで
懐メロという暖炉であったまる――
という同窓会みたいな図式になっている気がする。
いわば懐メロ専門スターが増えているのだ。
それが悪いことだとは言わない。
懐メロで心を癒し、過去を振り返ることも大切だと思う。
でも終始それでいいのか?面白いのか?
全部でなくていいが、できれば半分、
せめて2,3割くらいは現役感・未来感があってほしい。
それに齢を取ると、その人の生き方が自然と佇まいに現れる。
どんなに着飾ろうが、若づくりしようが、
カッコよくはならない。
若い頃なら許された、だらしない言動、
人を不愉快にさせるような言動は、
無意識のうちに、かなり醜い形で表に出てしまう。
逆に誠実に、自分らしく生きてきた人はカッコよくなっていく。
これはミュージシャンや芸能人に限った話ではないと思う。
佐野元春が歳を取れば取るほどカッコよくなっていくのは、
おそらくそうした原理が働いているからだろう。
バックバンドやスタッフに恵まれているのかもしれない。
しかし、それは彼の才能と人柄、
もっと具体的に言えば、時代に応じて表現を変えつつも、
一貫して自分の思いや意見を、
誠実に音楽にし続けてきたからこそ、
強い味方となる周囲の人々を引き寄せるのだ。
むかし、「つまらない大人にはならない」と吠えていた
ミュージシャン、アーティストは大勢いた。
そのうち、何人がそれを実践できただろう?
いま、実践しているだろう?
佐野元春はつまらない大人にならなかった。
70歳に近くなった今、自信を持って
「ガラスのジェネレーション」をリメイクし、
魂を込めて歌える彼を、リスペクトせずにはいられない。
小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。
やつらはカレンダーがわかっているらしい。
というわけで、いよいよ夏本番。
といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。
関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。
そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、
近年、カタツムリをあまり見かけない。
息子がチビだったころには、
いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。
前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を
よくノロノロ歩いていた。
今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、
草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、
カタツムリをまったく目にしない。
まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、
ちょっと心配になる。
夏になると、生き物たちの活動は活発になる。
昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。
ガラスにへばりついていると、
ひんやりして気持ちいのかもしれない。
ちょっと窓をズラしてやると、
驚いてペタペタ動きまわる。
ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。
トカゲもちょろちょろしていて可愛い。
このあたりの輩は高速移動できるからいいが、
悲惨だなと思うのはミミズである。
ここのところ毎日、
道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。
それも一匹や二匹ではない。
赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が
数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。
まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。
それにしても、なぜだ?
果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、
無数のミミズたちに僕は問いかける。
おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、
なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて
熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?
なぜ故郷をあとにしたのか?
なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?
この道路の向こう、この地獄を超えた先に、
おまえたちの目指す楽園があったというのか?
それはあの植え込みか、草むらか?
もちろん、誰も答えてはくれない。
ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。
セミやハチやチョウのように空を飛べれば。
せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。
しかし、ミミズはミミズ。
地を這い、土に潜る。
それが宿命づけられた生き方だ。
その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、
それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?
というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、
ちょっと悲惨過ぎて載せられない。
ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも
いやだという人が多いだろうが。
なので本日は、クールビズしている
元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。
綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ
「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。
カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、
僕も土曜日に見たが、確かに面白い。
それにしても僕の中では、
綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、
そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。
役柄はもっと年上の設定らしいが、
もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。
そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの
スタッフも多くは40代
(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。
来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。
今や60・70代よりも40・50代のほうが
しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?
それどころか、20・30代も
「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。
どうやらがんばって終活するためには、
若いエネルギーが必要なのだ。
60・70代からじゃ遅すぎる?
いったいどうなっちょるんじゃ?
あっという間に1億総終活時代に突入だ。
「ひとりでしにたい」本当に面白いので、
観てない人は、NHKプラスで観てみてください。
電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」
無料キャンペーンは本日終了。
ご購入ありがとうございます。
よろしければレビューをお願いしますね。
なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?

「かえるくん、東京を救う」というのは村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品です。
主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説。
ですが、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまいます。
この話は阪神大震災をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのですが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザだったりして独特の作品世界が出来上がっています。
しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思いました。
このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないでしょうか。
でも、その振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気もします。
欧米人はカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の使いとか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い気がします。
ところが、日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、かわいい系・愛すべき系の系譜がちゃんと続いていますね。
僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないでしょうか。
お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。
そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのでしょう。
カエル君に対するよいイメージはそういうところからきている気がします。
ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」って呼ばれています。
茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろうね、きっと。
雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってないなぁ。ケロケロ。
家族ストーリーを書く仕事② 個の家族

「これから生まれてくる子孫が見られるように」
――今回の家族ストーリー(ファミリーヒストリー)を作った動機について、3世代の真ん中の息子さん(団塊ジュニア世代)は作品の最後でこんなメッセージを残しています。
彼の中にはあるべき家族の姿があった。しかし現実にはそれが叶わなかった。だからやっと安定し、幸福と言える現在の形を映像に残すことを思い立った――僕にはそう取れます。
世間一般の基準に照らし合わせれば、彼は家庭に恵まれなかった人に属するでしょう。かつて日本でよく見られた大家族、そして戦後の主流となった夫婦と子供数人の核家族。彼の中にはそうした家族像への憧れがあったのだと思います。
けれども大家族どころか、核家族さえもはや過去のものになっているのでないか。今回の映像を見ているとそう思えてきます。
団塊の世代の親、その子、そして孫(ほぼ成人)。
彼らは家族であり、互いに支え合い、励まし合いながら生きている。
けれど、その前提はあくまで個人。それぞれ個別の歴史と文化を背負い、自分の信じる幸福を追求する人間として生きている。
むかしのように、まず家があり、そこに血のつながりのある人間として生まれ、育つから家族になるのではなく、ひとりひとりの個人が「僕たちは家族だよ」という約束のもとに集まって愛情と信頼を持っていっしょに暮らす。あるいは、離れていても「家族だよ」と呼び合い、同様に愛情と信頼を寄せ合う。だから家族になる。
これからの家族は、核家族からさらに小さな単位に進化した「ミニマム家族」――「個の家族」とでもいえばいいのでしょうか。
比喩を用いれば、ひとりひとりがパソコンやスマホなどのデバイスであり、必要がある時、○○家にログインし、ネットワークし、そこで父・母・息子・娘などの役割を担って、相手の求めることに応じる。それによってそれぞれが幸福を感じる。そうした「さま」を家族と呼称する――なかなかスムーズに表現できませんが、これからはそういう家族の時代になるのではないでしょうか。
なぜなら、そのほうが現代のような個人主義の世の中で生きていくのに何かと便利で快適だからです。人間は自身の利便性・快適性のためになら、いろいろなものを引き換えにできます。だから進化してこられたのです。
引き換えに失ったものの中にももちろん価値があるし、往々にして失ってみて初めてその価値に気づくケースがあります。むかしの大家族しかり。核家族しかり。こうしてこれらの家族の形態は、今後、一種の文化遺産になっていくのでしょう。
好きか嫌いかはともかく、そういう時代に入っていて、僕たちはもう後戻りできなくなっているのだと思います。
将来生まれてくる子孫のために、自分の家族の記憶を本なり映像なりの形でまとめて遺す―― もしかしたらそういう人がこれから結構増えるのかもしれません。
2016・6・27 Mon
家族ストーリーを書く仕事① 親子3世代の物語

親子3世代の物語がやっと完成一歩手前まで来ました。
昨年6月、ある家族のヒストリー映像を作るというお仕事を引き受けて、台本を担当。
足掛け1年掛かりでほぼ完成し、残るはクライアントさんに確認を頂いて、最後にナレーションを吹き込むのみ、という段階までこぎつけたのです。
今回のこの仕事は、ディレクターが取材をし、僕はネット経由で送られてくるその音源や映像を見て物語の構成をしていきました。そのディレクターとも最初に1回お会いしただけでご信頼を頂いたので、そのあとはほとんどメールのやり取りのみで進行しました。インターネットがあると、本当に家で何でもできてしまいます。
ですから時間がかかった割には、そんなに「たいへん感」はありませんでした。
取材対象の人たちともリアルでお会いしたことはなく、インタビューの音声――話の内容はもとより、しゃべり方のくせ、間も含めて――からそれぞれのキャラクターと言葉の背景にある気持ちを想像しながらストーリーを組み立てていくのは、なかなかスリリングで面白い体験でした(最初の下取材の頃はディレクターがまだ映像を撮っていなかったので、レコーダーの音源だけを頼りにやっていました)。
取材対象と直接会わない、会えないという制限は、今までネガティブに捉えていたのですが、現場(彼らの生活空間や仕事空間)の空気がわからない分、余分な情報に戸惑ったり、感情移入のし過ぎに悩まされたりすることがありません。
適度な距離を置いてその人たちを見られるので、かえってインタビューの中では語られていない範囲まで自由に発想を膨らませられ、こうしたドキュメンタリーのストーリーづくりという面では良い効果もあるんだな、と感じました。
後半(今年になってから)、全体のテーマが固まり、ストーリーの流れが固まってくると、今度は台本に基づいて取材がされるようになりました。
戦後の昭和~平成の時代の流れを、団塊の世代の親、その息子、そして孫(ほぼ成人)という一つの家族を通して見ていくと、よく目にする、当時の出来事や風俗の記録映像も、魂が定着くした記憶映像に見えてきます。
これにきちんとした、情感豊かなナレーターの声が入るのがとても楽しみです。
2016・6・26 Sun
ゴマスリずんだ餅と正直ファンタじいさん

おもちペタペタ伊達男
今週日曜(19日)の大河ドラマ「真田丸」で話題をさらったのは、長谷川朝晴演じる伊達政宗の餅つきパフォーマンスのシーン。「独眼竜」で戦国武将の中でも人気の高い伊達政宗ですが、一方で「伊達男」の語源にもなったように、パフォーマーというか、歌舞伎者というか、芝居っけも方もたっぷりの人だったようです。
だから、餅つきくらいやってもおかしくないのでしょうが、権力者・秀吉に対してあからさまにこびへつらい、ペッタンコとついた餅にスリゴマを・・・じゃなかった、つぶした豆をのっけて「ずんだ餅でございます」と差し出す太鼓持ち野郎の姿に、独眼竜のカッコいいイメージもこっぱみじんでした。
僕としては「歴人めし」の続編のネタ、一丁いただき、と思ってニヤニヤ笑って見ていましたが、ファンの人は複雑な心境だったのではないのでしょうか。(ネット上では「斬新な伊達政宗像」と、好意的な意見が多かったようですが)。
しかし、この後、信繁(幸村=堺雅人)と二人で話すシーンがあり、じつは政宗、今はゴマスリ太鼓持ち野郎を演じているが、いずれ時が来れば秀吉なんぞ、つぶしてずんだ餅にしてやる・・・と、野心満々であることを主人公の前で吐露するのです。
で、これがクライマックスの関ヶ原の伏線の一つとなっていくわけですね。
裏切りのドラマ
この「真田丸」は見ていると、「裏切り」が一つのテーマとなっています。
出てくるどの武将も、とにかくセコいのなんのttらありゃしない。立派なサムライなんて一人もいません。いろいろな仮面をかぶってお芝居しまくり、だましだまされ、裏切り裏切られ・・・の連続なのです。
そりゃそうでしょう。乱世の中、まっすぐ正直なことばかりやっていては、とても生き延びられません。
この伊達政宗のシーンの前に、北条氏政の最後が描かれていましたが、氏政がまっすぐな武将であったがために滅び、ゴマスリ政宗は生き延びて逆転のチャンスを掴もうとするのは、ドラマとして絶妙なコントラストになっていました。
僕たちも生きるためには、多かれ少なかれ、このゴマスリずんだ餅に近いことを年中やっているのではないでしょうか。身過ぎ世過ぎというやつですね。
けれどもご注意。
人間の心とからだって、意外と正直にできています。ゴマスリずんだ餅をやり過ぎていると、いずれまとめてお返しがやってくるも知れません。
人間みんな、じつは正直者
どうしてそんなことを考えたかと言うと、介護士の人と、お仕事でお世話しているおじいさんのことについて話したからです。
そのおじいさんはいろんな妄想に取りつかれて、ファンタジーの世界へ行っちゃっているようなのですが、それは自分にウソをつき続けて生きてきたからではないか、と思うのです。
これは別に倫理的にどうこうという話ではありません。
ごく単純に、自分にウソをつくとそのたびにストレスが蓄積していきます。
それが生活習慣になってしまうと、自分にウソをつくのが当たり前になるので、ストレスが溜まるのに気づかない。そういう体質になってしまうので、全然平気でいられる。
けれども潜在意識は知っているのです。
「これはおかしい。これは違う。これはわたしではな~い」
そうした潜在意識の声を、これまた無視し続けると、齢を取ってから自分で自分を裏切り続けてきたツケが一挙に出て来て、思いっきり自分の願いや欲望に正直になるのではないでしょうか。
だから脳がファンタジーの世界へ飛翔してしまう。それまでウソで歪めてきた自分の本体を取り戻すかのように。
つまり人生は最後のほうまで行くとちゃんと平均化されるというか、全体で帳尻が合うようにできているのではないかな。
自分を大事にするということ
というのは単なる僕の妄想・戯言かも知れないけど、自分に対する我慢とか裏切りとかストレスとかは、心や体にひどいダメージを与えたり、人生にかなりの影響を及ぼすのではないだろうかと思うのです。
みなさん、人生は一度きり。身過ぎ世過ぎばっかりやってると、それだけであっという間に一生終わっちゃいます。何が自分にとっての幸せなのか?心の内からの声をよく聴いて、本当の意味で自分を大事にしましょう。
介護士さんのお話を聞くといろんなことを考えさせられるので、また書きますね。
2016/6/23 Thu
死者との対話:父の昭和物語

すぐれた小説は時代を超えて読み継がれる価値がある。特に現代社会を形作った18世紀から20世紀前半にかけての時代、ヨーロッパ社会で生まれた文学には人間や社会について考えさせられる素材にあふれています。
その読書を「死者との対話」と呼んだ人がいます。うまい言い方をするものだと思いました。
僕たちは家で、街で、図書館で、本さえあれば簡単にゲーテやトルストイやドストエフスキーやブロンテなどと向かい合って話ができます。別にスピリチュアルなものに関心がなくても、書き残したものがあれば、私たちは死者と対話ができるのです。
もちろん、それはごく限られた文学者や学者との間で可能なことで、そうでない一般大衆には縁のないことでしょう。これまではそうでした。しかし、これからの時代はそれも可能なことではないかと思います。ただし、不特定多数の人でなく、ある家族・ある仲間との間でなら、ということですが。
僕は父の人生を書いてみました。
父は2008年の12月に亡くなりました。家族や親しい者の死も1年ほどたつと悲しいだの寂しいだの、という気持ちは薄れ、彼らは自分の人生においてどんな存在だったのだろう?どんなメッセージを遺していったのだろう?といったことを考えます。
父のことを書いてみようと思い立ったのは、それだけがきっかけではありませんでした。
死後、間もない時に、社会保険事務所で遺族年金の手続きをする際に父の履歴書を書いて提出しました。その時に感じたのは、血を分けた家族のことでも知らないことがたくさんあるな、ということでした。
じつはそれは当り前のことなのだが、それまではっきりとは気が付いていませんでした。なんとなく父のことも母のこともよく知っていると思いすごしていたのです。
実際は私が知っているのは、私の父親としての部分、母親としての部分だけであり、両親が男としてどうだったか、女としてどうだったか、ひとりの人間としてどうだったのか、といったことなど、ほとんど知りませんでした。数十年も親子をやっていて、知るきっかけなどなかったのです。
父の仕事ひとつ取ってもそうでした。僕の知っている父の仕事は瓦の葺換え職人だが、それは30歳で独立してからのことで、その前――20代のときは工場に勤めたり、建築会社に勤めたりしていたのです。それらは亡くなってから初めて聞いた話です。
そうして知った事実を順番に並べて履歴書を作ったのですが、その時には強い違和感というか、抵抗感のようなものを感じました。それは父というひとりの人間の人生の軌跡が、こんな紙切れ一枚の中に納まってしまうということに対しての、寂しさというか、怒りというか、何とも納得できない気持ちでした。
父は不特定多数の人たちに興味を持ってもらえるような、波乱万丈な、生きる迫力に満ち溢れた人生を歩んだわけはありませんい。むしろそれらとは正反対の、よくありがちな、ごく平凡な庶民の人生を送ったのだと思います。
けれどもそうした平凡な人生の中にもそれなりのドラマがあります。そして、そのドラマには、その時代の社会環境の影響を受けた部分が少なくありません。たとえば父の場合は、昭和3年(1928年)に生まれ、平成元年(1989年)に仕事を辞めて隠居していました。その人生は昭和の歴史とほぼ重なっています。
ちなみにこの昭和3年という年を調べてみると、アメリカでミッキーマウスの生まれた(ウォルト・ディズニーの映画が初めて上映された)年です。
父は周囲の人たちからは実直でまじめな仕事人間と見られていましたが、マンガや映画が好きで、「のらくろ」だの「冒険ダン吉」だのの話をよく聞かせてくれました。その時にそんなことも思い出したのです。
ひとりの人間の人生――この場合は父の人生を昭和という時代にダブらせて考えていくと、昭和の出来事を書き連ねた年表のようなものとは、ひと味違った、その時代の人間の意識の流れ、社会のうねりの様子みたいなものが見えてきて面白いのではないか・・・。そう考えて、僕は父に関するいくつかの個人的なエピソードと、昭和の歴史の断片を併せて書き、家族や親しい人たちが父のことを思い起こし、対話できるための一遍の物語を作ってみようと思い立ちました。
本当はその物語は父が亡くなる前に書くべきだったのではないかと、少し後悔の念が残っています。
生前にも話を聞いて本を書いてみようかなと、ちらりと思ったことはあるのですが、とうとう父自身に自分の人生を振り返って……といった話を聞く機会はつくれませんでした。たとえ親子の間柄でも、そうした機会を持つことは難しいのです。思い立ったら本気になって直談判しないと、そして双方互いに納得できないと永遠につくることはできません。あるいは、これもまた難しいけど、本人がその気になって自分で書くか・・・。それだけその人固有の人生は貴重なものであり、それを正確に、満足できるように表現することは至難の業なのだと思います。
実際に始めてから困ったのは、父の若い頃のことを詳しく知る人など、周囲にほとんどいないということ。また、私自身もそこまで綿密に調査・取材ができるほど、時間や労力をかけるわけにもいきませんでした。
だから母から聞いた話を中心に、叔父・叔母の話を少し加える程度にとどめ、その他、本やインターネットでその頃の時代背景などを調べながら文章を組み立てる材料を集めました。そして自分の記憶――心に残っている言葉・出来事・印象と重ね合わせて100枚程度の原稿を作ってみたのです。
自分で言うのもナンですが、情報不足は否めないものの、悪くない出来になっていて気に入っています。これがあるともうこの世にいない父と少しは対話できる気がするのです。自分の気持ちを落ち着かせ、互いの生の交流を確かめ、父が果たした役割、自分にとっての存在の意味を見出すためにも、こうした家族や親しい者の物語をつくることはとても有効なのではないかと思います。
高齢化が進む最近は「エンディングノート」というものがよく話題に上っています。
「その日」が来た時、家族など周囲の者がどうすればいいか困らないように、いわゆる社会的な事務手続き、お金や相続のことなどを書き残すのが、今のところ、エンディングノートの最もポピュラーな使い方になっているようだ。
もちろん、それはそれで、逝く者にとっても、後に残る者にとっても大事なことです。しかし、そうすると結局、その人の人生は、いくらお金を遺したかとか、不動産やら建物を遺したのか、とか、そんな話ばかりで終わってしまう恐れもあります。その人の人生そのものが経済的なこと、物質的なものだけで多くの人に価値判断されてしまうような気がするのです。
けれども本当に大事なのは、その人の人生にどんな意味や価値があったのか、を家族や友人・知人たちが共有することが出来る、ということではないでしょうか。
そして、もしその人の生前にそうしたストーリーを書くことができれば、その人が人生の最期の季節に、自分自身を取り戻せる、あるいは、取り戻すきっかけになり得る、ということではないでしょうか。
赤影メガネとセルフブランディング

♪赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光る涼しい目 仮面の忍者だ
赤影だ~
というのは、テレビの「仮面の忍者 赤影」の主題歌でしたが、涼しい目かどうかはともかく、僕のメガネは10数年前から「赤影メガネ」です。これにはちょっとした物語(というほどのものではないけど)があります。
当時、小1だか2年の息子を連れてメガネを買いに行きました。
それまでは確か茶色の細いフレームの丸いメガネだったのですが、今回は変えようかなぁ、どうしようかなぁ・・・とあれこれ見ていると、息子が赤フレームを見つけて「赤影!」と言って持ってきたのです。
「こんなの似合うわけないじゃん」と思いましたが、せっかく選んでくれたのだから・・・と、かけてみたら似合った。子供の洞察力おそるべし。てか、単に赤影が好きだっただけ?
とにかく、それ以来、赤いフレームのメガネが、いつの間にか自分のアイキャッチになっていました。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいもの。
独立・起業・フリーランス化ばやりということもあり、セルフブランディングがよく話題になりますが、自分をどう見せるかというのはとても難しい。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいのです。
とはいえ、自分で気に入らないものを身に着けてもやっぱり駄目。できたら安心して相談できる家族とか、親しい人の意見をしっかり聞いて(信頼感・安心感を持てない人、あんまり好きでない人の意見は素直に聞けない)、従来の考え方にとらわれない自分像を探していきましょう。
ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?
ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。
BACK in the NEW YORK CITY。
僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。
特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。
そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。
衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。
そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。
1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。
向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。
なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。
どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・
「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。
おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。
別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。
あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。
というのが、今から約20年前のこと。
その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?
表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?
件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。
ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。
そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。
2016年6月16日
インターネットがつくるフォークロア

インターネットの出現は社会を変えた――ということは聞き飽きるほど、あちこちで言われています。けれどもインターネットが本格的に普及したのは、せいぜいここ10年くらいの話。全世代、全世界を見渡せば、まだ高齢者の中には使ったことがないという人も多いし、国や地域によって普及率の格差も大きい。だから、その変化の真価を国レベル・世界レベルで、僕たちが実感するのはまだこれからだと思います。
それは一般によくいわれる、情報収集がスピーディーになったとか、通信販売が便利になったとか、というカテゴリーの話とは次元が違うものです。もっと人間形成の根本的な部分に関わることであり、ホモサピエンスの文化の変革にまでつながること。それは新しい民間伝承――フォークロアの誕生です。
“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承
最初はどこでどのように聞いたのか覚えてないですが、僕たちは自分でも驚くほど、昔話・伝承をよく知っています。成長の過程のどこかで桃太郎や浦島太郎や因幡の白ウサギと出会い、彼らを古い友だちのように思っています。
家庭でそれらの話を大人に読んでもらったこともあれば、幼稚園・保育園・小学校で体験したり、最近ならメディアでお目にかかることも多い。それはまるで遺伝子に組み込まれているかのように、あまりに自然に身体の中に溶け込んでいるのです。
調べて確認したわけではないが、こうした感覚は日本に限らず、韓国でも中国でもアメリカでもヨーロッパでも、その地域に住んでいる人なら誰でも持ち得るのではないでしょうか。おそらく同じような現象があると思います。それぞれどんな話がスタンダードとなっているのかは分かりませんが、その国・その地域・その民族の間で“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承の類が一定量あるのです。
それらは長い時間を生きながらえるタフな生命エネルギーを持っています。それだけのエネルギーを湛えた伝承は、共通の文化の地層、つまり一種のデータベースとして、万人の脳の奥底に存在しています。その文化の地層の上に、その他すべての情報・知識が積み重なっている――僕はそんなイメージを持っています。
世界共通の、新しいカテゴリーの伝承
そして、昔からあるそれとは別に、これから世界共通の、新しいカテゴリーの伝承が生まれてくる。その新しい伝承は人々の間で共通の文化の地層として急速に育っていくのでないか。そうした伝承を拡散し、未来へ伝える役目を担っているのがインターネット、というわけです。
ところで新しい伝承とは何でしょう? その主要なものは20世紀に生まれ、花開いた大衆文化――ポップカルチャーではないでしょうか。具体的に挙げていけば、映画、演劇、小説、マンガ、音楽(ジャズ、ポップス、ロック)の類です。
21世紀になる頃から、こうしたポップカルチャーのリバイバルが盛んに行われるようになっていました。
人々になじみのあるストーリー、キャラクター。
ノスタルジーを刺激するリバイバル・コンテンツ。
こうしたものが流行るのは、情報発信する側が、商品価値の高い、新しいものを開発できないためだと思っていました。
そこで各種関連企業が物置に入っていたアンティーク商品を引っ張り出してきて、売上を確保しようとした――そんな事情があったのでしょう。実際、最初のうちはそうだったはずです。
だから僕は結構冷めた目でそうした現象を見ていました。そこには半ば絶望感も混じっていたと思います。前の世代を超える、真に新しい、刺激的なもの・感動的なものは、この先はもう現れないのかも知れない。出尽くしてしまったのかも知れない、と……。
しかし時間が経ち、リバイバル現象が恒常化し、それらの画像や物語が、各種のサイトやYouTubeの動画コンテンツとして、ネット上にあふれるようになってくると考え方は変わってきました。
それらのストーリー、キャラクターは、もはや単なるレトロやリバイバルでなく、世界中の人たちの共有財産となっています。いわば全世界共通の伝承なのです。
僕たちは欧米やアジアやアフリカの人たちと「ビートルズ」について、「手塚治虫」について、「ガンダム」について、「スターウォーズ」について語り合えるし、また、それらを共通言語にして、子や孫の世代とも同様に語り合えます。
そこにボーダーはないし、ジェネレーションギャップも存在しません。純粋にポップカルチャーを媒介にしてつながり合う、数限りない関係が生まれるのです。
また、これらの伝承のオリジナルの発信者――ミュージシャン、映画監督、漫画家、小説家などによって、あるいは彼ら・彼女らをリスペクトするクリエイターたちによって自由なアレンジが施され、驚くほど新鮮なコンテンツに生まれ変わる場合もあります。
インターネットの本当の役割
オリジナル曲をつくった、盛りを過ぎたアーティストたちが、子や孫たち世代の少年・少女と再び眩いステージに立ち、自分の資産である作品を披露。それをYouTubeなどを介して広めている様子なども頻繁に見かけるようになりました。
それが良いことなのか、悪いことなのか、評価はさておき、そうした状況がインタ―ネットによって現れています。これから10年たち、20年たち、コンテンツがさらに充実し、インターネット人口が現在よりさらに膨れ上がれば、どうなるでしょうか?
おそらくその現象は空気のようなものとして世の中に存在するようになり、僕たちは新たな世界的伝承として、人類共通の文化遺産として、完成された古典として見なすようになるでしょう。人々は分かりやすく、楽しませてくれるものが大好きだからです。
そして、まるで「桃太郎」のお話を聞くように、まっさらな状態で、これらの伝承を受け取った子供たちが、そこからまた新しい、次の時代の物語を生みだしていきます。
この先、そうした現象が必ず起こると思う。インターネットという新参者のメディアはその段階になって、さらに大きな役割を担うのでしょう。それは文化の貯蔵庫としての価値であり、さらに広げて言えば、人類の文化の変革につながる価値になります。
2016年6月13日
地方自治体のホームページって割と面白い

ここのところ、雑誌の連載で地方のことを書いています。
書くときはまずベーシックな情報(最初のリード文として使うこともあるので)をインターネットで調べます。
これはウィキペディアなどの第3者情報よりも、各県の公式ホームページの方が断然面白い。自分たちの県をどう見せ、何をアピールしたいかがよくわかるからです。
なんでも市場価値が問われる時代。「お役所仕事云々・・・」と言われることが多い自治体ですが、いろいろ努力して、ホームページも工夫しています。
最近やった宮崎県のキャッチコピーは「日本のひなた」。
日照時間の多さ、そのため農産物がよく獲れるということのアピール。
そしてもちろん、人や土地のやさしさ、あったかさ、ポカポカ感を訴えています。
いろいろな人たちがお日さまスマイルのフリスビーを飛ばして、次々と受け渡していくプロモーションビデオは、単純だけど、なかなか楽しかった。
それから「ひなた度データ」というのがあって、全国比率のいろいろなデータが出ています。面白いのが、「餃子消費量3位」とか、「中学生の早寝早起き率 第3位」とか、「宿題実行率 第4位」とか、「保護者の学校行事参加率 第2位」とか・・・
「なんでこれがひなた度なんじゃい!」とツッコミを入れたくなるのもいっぱい。だけど好きです、こういうの。
取材するにしても、いきなり用件をぶつけるより、「ホームページ面白いですね~」と切り出したほうが、ちょっとはお役所臭さが緩和される気がします。
「あなたのひなた度は?」というテストもあって、やってみたら100パーセントでした。じつはまだ一度も行ったことないけれど、宮崎県を応援したくなるな。ポカポカ。
2016年6月12日
タイムマシンにおねがい

きのう6月10日は「時の記念日」でした。それに気がついたら頭の中で突然、サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」が鳴り響いてきたので、YouTubeを見てみたら、1974年から2006年まで、30年以上にわたるいろいろなバージョンが上がっていました。本当にインターネットの世界でタイムマシン化しています。
これだけ昔の映像・音源が見放題・聞き放題になるなんて10年前は考えられませんでした。こういう状況に触れると、改めてインターネットのパワーを感じると同時に、この時代になるまで生きててよかった~と、しみじみします。
そしてまた、ネットの中でならおっさん・おばさんでもずっと青少年でいられる、ということを感じます。60~70年代のロックについて滔々と自分の思い入れを語っている人がいっぱいいますが、これはどう考えても50代・60代の人ですからね。
でも、彼ら・彼女らの頭の中はロックに夢中になっていた若いころのまんま。脳内年齢は10代・20代。インターネットに没頭することは、まさしくタイムマシンンに乗っているようなものです。
この「タイムマシンにおねがい」が入っているサディスティック・ミカ・バンドの「黒船」というアルバムは、1974年リリースで、いまだに日本のロックの最高峰に位置するアルバムです。若き加藤和彦が作った、世界に誇る傑作と言ってもいいのではないでしょうか。
中でもこの曲は音も歌詞もゴキゲンです。いろいろ見た(聴いた)中でいちばんよかったのは、最新(かな?)の2006年・木村カエラ・ヴォーカルのバージョンです。おっさんロッカーたちをバックに「ティラノサウルスおさんぽ アハハハ-ン」とやってくれて、くらくらっときました。
やたらと「オリジナルでなきゃ。あのヴォーカルとあのギターでなきゃ」とこだわる人がいますが、僕はそうは思わない。みんなに愛される歌、愛されるコンテンツ、愛される文化には、ちゃんと後継ぎがいて、表現技術はもちろんですが、それだけでなく、その歌・文化の持ち味を深く理解し、見事に自分のものとして再現します。中には「オリジナルよりいいじゃん!」と思えるものも少なくありません。(この木村カエラがよい例)。
この歌を歌いたい、自分で表現したい!――若い世代にそれだけ強烈に思わせる、魅力あるコンテンツ・文化は生き残り、クラシックとして未来に継承されていくのだと思います。
もう一つおまけに木村カエラのバックでは、晩年の加藤和彦さんが本当に楽しそうに演奏をしていました。こんなに楽しそうだったのに、どうして自殺してしまったのだろう・・・と、ちょっと哀しくもなったなぁ。
2016年6月11日
「歴人めし」おかわり情報

9日間にわたって放送してきた「歴人めし」は、昨日の「信長巻きの巻」をもっていったん終了。しかし、ご安心ください。7月は夜の時間帯に再放送があります。ぜひ見てくださいね。というか、You Tubeでソッコー見られるみたいですが。
https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php?series_cd=12041
この仕事では歴人たちがいかに食い物に執念を燃やしていたかがわかりました。 もちろん、記録に残っているのはほんの少し。
源内さんのように、自分がいかにうなぎが好きか、うなぎにこだわっているか、しつこく書いている人も例外としていますが、他の人たちは自分は天下国家のことをいつも考えていて、今日のめしのことなんかどうでもいい。カスミを食ってでの生きている・・・なんて言い出しそうな勢いです。
しかし、そんなわけはない。偉人と言えども、飲み食いと無関係ではいられません。 ただ、それを口に出して言えるのは、平和な世の中あってこそなのでしょう。だから日本の食文化は江戸時代に発展し、今ある日本食が完成されたのです。
そんなわけで、「おかわり」があるかもしれないよ、というお話を頂いているので、なんとなく続きを考えています。
駿河の国(静岡)は食材豊富だし、来年の大河の井伊直虎がらみで何かできないかとか、 今回揚げ物がなかったから、何かできないかとか(信長に捧ぐ干し柿入りドーナツとかね)、
柳原先生の得意な江戸料理を活かせる江戸の文人とか、明治の文人の話だとか、
登場させ損ねてしまった豊臣秀吉、上杉謙信、伊達政宗、浅井三姉妹、新選組などの好物とか・・・
食について面白い逸話がありそうな人たちはいっぱいいるのですが、柳原先生の納得する人物、食材、メニュー、ストーリーがそろって、初めて台本にできます。(じつは今回もプロット段階でアウトテイク多数)
すぐにとはいきませんが、ぜひおかわりにトライしますよ。
それまでおなかをすかせて待っててくださいね。ぐ~~。
2016年6月7日
歴人めし♯9:スイーツ大好き織田信長の信長巻き

信長が甘いもの好きというのは、僕は今回のリサーチで初めて知りました。お砂糖を贈答したり、されたりして外交に利用していたこともあり、あちこちの和菓子屋さんが「信長ゆかりの銘菓」を開発して売り出しているようです。ストーリーをくっつけると、同じおまんじゅうやあんころもちでも何だか特別なもの、他とは違うまんじゅうやあんころもちに思えてくるから不思議なものです。
今回、ゆかりの食材として採用したのは「干し柿」と「麦こがし(ふりもみこがし)」。柿は、武家伝統の本膳料理(会席料理のさらに豪華版!)の定番デザートでもあり、記録をめくっていると必ず出てきます。
現代のようなスイーツパラダイスの時代と違って、昔の人は甘いものなどそう簡単に口にできませんでした。お砂糖なんて食品というよりは、宝石や黄金に近い超ぜいたく品だったようです。だから信長に限らず、果物に目のない人は大勢いたのでしょう。
中でもは干し柿にすれば保存がきくし、渋柿もスイートに変身したりするので重宝されたのだと思います。
「信長巻き」というのは柳原尚之先生のオリジナル。干し柿に白ワインを染み込ませるのと、大徳寺納豆という、濃厚でしょっぱい焼き味噌みたいな大豆食品をいっしょに巻き込むのがミソ。
信長は塩辛い味も好きで、料理人が京風の上品な薄味料理を出したら「こんな水臭いものが食えるか!」と怒ったという逸話も。はまった人なら知っている、甘い味としょっぱい味の無限ループ。交互に食べるともうどうにも止まらない。信長もとりつかれていたのだろうか・・・。
ちなみに最近の映画やドラマの中の信長と言えば、かっこよくマントを翻して南蛮渡来の洋装を着こなして登場したり、お城の中のインテリアをヨーロッパの宮殿風にしたり、といった演出が目につきます。
スイーツ好きとともに、洋風好き・西洋かぶれも、今やすっかり信長像の定番になっていますが、じつはこうして西洋文化を積極的に採り入れたのも、もともとはカステラだの、金平糖だの、ボーロだの、ポルトガルやスペインの宣教師たちが持ち込んできた、砂糖をたっぷり使った甘いお菓子が目当てだったのです。(と、断言してしまう)
「文化」なんていうと何やら高尚っぽいですが、要は生活習慣の集合体をそう呼ぶまでのこと。その中心にあるのは生活の基本である衣食住です。
中でも「食」の威力はすさまじく、これに人間はめっぽう弱い。おいしいものの誘惑からは誰も逃れられない。そしてできることなら「豊かな食卓のある人生」を生きたいと願う。この「豊かな食卓」をどう捉えるかが、その人の価値観・生き方につながるのです。
魔王と呼ばれながら、天下統一の一歩手前で倒れた信長も、突き詰めればその自分ならではの豊かさを目指していたのではないかと思うのです。
2016年6月6日
歴人めし♯8 山内一豊の生食禁止令から生まれた?「カツオのたたき」

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だったころ、琵琶湖のほとりに金目教という怪しい宗教が流行っていた・・・」というナレーションで始まるのは「仮面の忍者・赤影」。子供の頃、夢中になってテレビにかじりついていました。
時代劇(忍者もの)とSF活劇と怪獣物をごちゃ混ぜにして、なおかつチープな特撮のインチキスパイスをふりかけた独特のテイストは、後にも先にもこの番組だけ。僕の中ではもはや孤高の存在です。
いきなり話が脱線していますが、赤影オープニングのナレーションで語られた「琵琶湖のほとり」とは滋賀県長浜あたりのことだったのだ、と気づいたのは、ちょうど10年前の今頃、イベントの仕事でその長浜に滞在していた時です。
このときのイベント=期間限定のラジオ番組制作は、大河ドラマ「功名が辻」関連のもの。4月~6月まで断続的に数日ずつ訪れ、街中や郊外で番組用の取材をやっていました。春でもちょっと寒いことを我慢すれば、賑わいがあり、かつまた、自然や文化財にも恵まれている、とても暮らしやすそうな良いところです。
この長浜を開いたのは豊臣秀吉。そして秀吉の後を継いで城主になったのが山内一豊。「功名が辻」は、その一豊(上川隆也)と妻・千代(仲間由紀恵)の物語。そして本日の歴人めし♯9は、この一豊ゆかりの「カツオのたたき」でした。
ところが一豊、城主にまでしてもらったのに秀吉の死後は、豊臣危うしと読んだのか、関が原では徳川方に寝返ってしまいます。つまり、うまいこと勝ち組にすべり込んだわけですね。
これで一件落着、となるのが、一豊の描いたシナリオでした。
なぜならこのとき、彼はもう50歳。人生50年と言われた時代ですから、その年齢から本格的な天下取りに向かった家康なんかは例外中の例外。そんな非凡な才能と強靭な精神を持ち合わせていない、言ってみればラッキーで何とかやってきた凡人・一豊は、もう疲れたし、このあたりで自分の武士人生も「あがり」としたかったのでしょう。
できたら、ごほうびとして年金代わりに小さな領地でももらって、千代とのんびり老後を過ごしたかったのだと思います。あるいは武士なんかやめてしまって、お百姓でもやりながら余生を・・・とひそかに考えていた可能性もあります。
ところが、ここでまた人生逆転。家康からとんでもないプレゼントが。
「土佐一国をおまえに任せる」と言い渡されたのです。
一国の領主にしてやる、と言われたのだから、めでたく大出世。一豊、飛び上がって喜んだ・・・というのが定説になっていますが、僕はまったくそうは思いません。
なんせ土佐は前・領主の長曾我部氏のごっつい残党がぞろぞろいて、新しくやってくる領主をけんか腰で待ち構えている。徳川陣営の他の武将も「あそこに行くのだけは嫌だ」と言っていたところです。
現代に置き換えてみると、後期高齢者あたりの年齢になった一豊が、縁もゆかりもない外国――それも南米とかのタフな土地へ派遣されるのようなもの。いくらそこの支店長のポストをくれてやる、と言われたって全然うれしくなんかなかったでしょう。
けれども天下を収めた家康の命令は絶対です。断れるはずがありません。
そしてまた、うまく治められなければ「能無し」というレッテルを貼られ、お家とりつぶしになってしまいます。
これはすごいプレッシャーだったでしょう。「勝ち組になろう」なんて魂胆を起こすんじゃなかった、と後悔したに違いありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
恐怖にかられてしまった人間は、より以上の恐怖となる蛮行、残虐行為を行います。
一豊は15代先の容堂の世代――つまり、250年後の坂本龍馬や武市半平太の時代まで続く、武士階級をさらに山内家の上士、長曾我部氏の下士に分けるという独特の差別システムまで発想します。
そうして土佐にきてわずか5年で病に倒れ、亡くなってしまった一豊。寿命だったのかもしれませんが、僕には土佐統治によるストレスで命を縮めたとしか思えないのです。
「カツオのたたき」は、食中毒になる危険を慮った一豊が「カツオ生食禁止令」を出したが、土佐の人々はなんとかおいしくカツオを食べたいと、表面だけ火であぶり、「これは生食じゃのうて焼き魚だぜよ」と抗弁したところから生まれた料理――という話が流布しています。
しかし、そんな禁止令が記録として残っているわけではありません。やはりこれはどこからか生えてきた伝説なのでしょう。
けれども僕はこの「カツオのたたき発祥物語」が好きです。それも一豊を“民の健康を気遣う良いお殿様”として解釈するお話でなく、「精神的プレッシャーで恐怖と幻想にとりつかれ、カツオの生食が、おそるべき野蛮人たちの悪食に見えてしまった男の物語」として解釈してストーリーにしました。
随分と長くなってしまいましたが、ここまで書いてきたバックストーリーのニュアンスをイラストの方が、短いナレーションとト書きからじつにうまく掬い取ってくれて、なんとも情けない一豊が画面で活躍することになったのです。
一豊ファンの人には申し訳ないけど、カツオのたたきに負けず劣らず、実にいい味出している。マイ・フェイバリットです。
2016年6月3日
「歴人めし」徳川家康提唱、日本人の基本食

歴人めし第7回は「徳川家康―八丁味噌の冷汁と麦飯」。
「これが日本人の正しい食事なのじゃ」と家康が言ったかどうかは知りませんが、米・麦・味噌が長寿と健康の基本の3大食材と言えば、多くの日本人は納得するのではないでしょうか。エネルギー、たんぱく質、ビタミン、その他の栄養素のバランスも抜群の取り合わせです。
ましてやその発言の主が、天下を統一して戦国の世を終わらせ、パックス・トクガワ―ナを作った家康ならなおのこと。実際、家康はこの3大食材を常食とし、かなり養生に努めていたことは定説になっています。
昨年はその家康の没後400年ということで、彼が城を構えた岡崎・浜松・静岡の3都市で「家康公400年祭」というイベントが開催され、僕もその一部の仕事をしました。
そこでお会いしたのが、岡崎城から歩いて八丁(約780メートル)の八丁村で八丁味噌を作っていた味噌蔵の後継者。
かのメーカー社長は現在「Mr.Haccho」と名乗り、毎年、海外に八丁味噌を売り込みに行っているそうで、日本を代表する調味料・八丁味噌がじわじわと世界に認められつつあるようです。
ちなみに僕は名古屋の出身なので子供の頃から赤味噌に慣れ親しんできました。名古屋をはじめ、東海圏では味噌と言えば、赤味噌=豆味噌が主流。ですが、八丁味噌」という食品名を用いれるのは、その岡崎の元・八丁村にある二つの味噌蔵――現在の「まるや」と「カクキュー」で作っているものだけ、ということです。
しかし、養生食の米・麦・味噌をがんばって食べ続け、健康に気を遣っていた家康も、平和な世の中になって緊張の糸がプツンと切れたのでしょう。
がまんを重ねて押さえつけていた「ぜいたくの虫」がそっとささやいたのかもしれません。
「もういいんじゃないの。ちょっとぐらいぜいたくしてもかまへんで~」
ということで、その頃、京都でブームになっていたという「鯛の天ぷら」が食べた~い!と言い出し、念願かなってそれを口にしたら大当たり。おなかが油に慣れていなかったせいなのかなぁ。食中毒がもとで亡くなってしまった、と伝えられています。
でも考えてみれば、自分の仕事をやり遂げて、最期に食べたいものをちゃんと食べられて旅立ったのだから、これ以上満足のいく人生はなかったのではないでしょうか。
2016年6月2日
歴人めし「篤姫のお貝煮」と御殿女中
絶好調「真田丸」に続く2017年大河は柴咲コウ主演「おんな城主 直虎」。今年は男だったから来年は女――というわけで、ここ10年あまり、大河は1年ごとに主人公が男女入れ替わるシフトになっています。
だけど女のドラマは難しいんです。なかなか資料が見つけらない。というか、そもそも残っていな。やはり日本の歴史は(外国もそうですが)圧倒的に男の歴史なんですね。
それでも近年、頻繁に女主人公の物語をやるようになったのは、もちろん女性の視聴者を取り込むためだけど、もう一つは史実としての正確さよりも、物語性、イベント性を重視するようになってきたからだと思います。
テレビの人気凋落がよく話題になりますが、「腐っても鯛」と言っては失礼だけど、やっぱ日曜8時のゴールデンタイム、「お茶の間でテレビ」は日本人の定番ライフスタイルです。
出演俳優は箔がつくし、ゆかりの地域は観光客でにぎわうって経済も潤うし、いろんなイベントもぶら下がってくるし、話題も提供される・・・ということでいいことづくめ。
豪華絢爛絵巻物に歴史のお勉強がおまけについてくる・・・ぐらいでちょうどいいのです。(とはいっても、制作スタッフは必死に歴史考証をやっています。ただ、部分的に資料がなくても諦めずに面白くするぞ――という精神で作っているということです)
と、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、なんとか「歴人めし」にも一人、女性を入れたいということで、あれこれ調べた挙句、やっと好物に関する記録を見つけたのが、20082年大河のヒロイン「篤姫」。本日は天璋院篤姫の「お貝煮」でした。
見てもらえればわかるけど、この「お貝煮」なる料理、要するにアワビ入りの茶碗蒸しです。その記述が載っていたのが「御殿女中」という本。この本は明治から戦前の昭和にかけて活躍した、江戸文化・風俗の研究家・三田村鳶魚の著作で。篤姫付きの女中をしていた“大岡ませ子”という女性を取材した、いわゆる聞き書きです。
明治も30年余り経ち、世代交代が進み、新しい秩序・社会体制が定着してくると、以前の時代が懐かしくなるらしく、「江戸の記憶を遺そう」というムーブメントが文化人の間で起こったようです。
そこでこの三田村鳶魚さんが、かなりのご高齢だったます子さんに目をつけ、あれこれ大奥の生活について聞き出した――その集成がこの本に収められているというわけです。これは現在、文庫本になっていて手軽に手に入ります。
ナレーションにもしましたが、ヘアメイク法やら、ファッションやら、江戸城内のエンタメ情報やらも載っていて、なかなか楽しい本ですが、篤姫に関するエピソードで最も面白かったのが飼いネコの話。
最初、彼女は狆(犬)が買いたかったようなのですが、夫の徳川家定(13代将軍)がイヌがダメなので、しかたなくネコにしたとか。
ところが、このネコが良き相棒になってくれて、なんと16年もいっしょに暮らしたそうです。彼女もペットに心を癒された口なのでしょうか。
そんなわけでこの回もいろんな発見がありました。
続編では、もっと大勢の女性歴人を登場させ、その好物を紹介したいと思っています。
2016年6月1日
映画「国宝」 畸形の演劇と女形の生き様

かつてはギリシャ劇にも、シェイクスピア劇にも、
中国の京劇にも、能・狂言にも、女優は存在せず、
男の俳優だけで芝居は上演されてきた。
いろいろな事情があったと思うが、女が舞台に立つと、
多くの男がそれに現を抜かして働かなくなり、
社会が立ちいかなくなったので、為政者が禁じたのだろう。
しかし、社会の発展とともに演劇の世界は広く開放され、
女優もだんだん舞台に立つようになった。
21世紀の今日、世界でいまだに女優が舞台に立てない演劇は、
日本の歌舞伎だけである。
江戸幕府によって女優が禁じられてから400年。
女を演じる男優--女形は
何代にもわたってその技芸が伝承されてきた。
今や一種の世界遺産ともいえる独特のスタイルだ。
その女形に人生を賭け、紆余曲折を経ながら
ついに人間国宝にまでたどり着く男の物語。
吉田修一の同名小説を映画化した「国宝」。
1964年から2014年までの50年間を描いた一代記は、
歌舞伎の世界の裏側を見事に描き出している。
歌舞伎は一見、華やかでセレブな世界だが、
よく考えたら、何でいまだにこんな慣習・ルールが成り立つの?
と思えるような魔訶不思議な世界であり、
畸形の演劇ともいえる。
いまだに女が舞台に立つのが許されないことに加え、
伝統芸能でありながら、国家に守られているわけでなく、
純然たる商業演劇として運営されていること。
家・家族で伝承する技芸であるからこそ、
「血」を守っていくためのこだわりが強いこと。
みんな、小さな世界で生きているので、
身内・味方に対する愛情・友情・敬愛心は強いが、
一旦事情が変わると、
たとえば、父親・師匠などの後ろ盾を亡くしてしまうと、
たちまち冷淡に扱われ、干されるようになる。
要するに、この物語の主人公・喜久雄のように、
才能があれば、芸が優れていれば出世できるという
フェアな世界ではないのだ。
とはいえ、商業演劇なので、
客を集め、興行を打っていくため、
常に客の期待・時代のニーズに応え、
新しいスターをプロデュースする必要がある。
その微妙なバランスのなかで歌舞伎は生き延びてきた。
そのあたり、原作(まだ読んでないが)は
かなり詳細に買いているようだが、
この映画でも十分描き出している。
重厚なドラマは、昭和・平成の時代背景も相まって、
素晴らしく見ごたえがあって、
3時間以上の長丁場でもまったく飽きさせない。
吉沢亮と横浜流星の熱演が話題になっていて、
もちろん、彼らの感情表現や演技・踊りは素晴らしいのだが、
僕としては、この2人に影響を与え、
無言のうちに「女形の生き方」を示唆する
人間国宝・小野川万菊の存在が、とりわけ胸に刺さった。
演じるのは、長らく孤高のダンサーとして活躍してきた田中泯。
その妖怪じみた女形ぶりはすさまじく、登場シーンになると、
まるでそこだけアングラ演劇の世界みたいになる。
そして、人間国宝という栄誉ある称号にあるまじき
最後の登場シーンは、戦慄を覚えるほど印象的で、
そこに「国宝」というタイトルの意味が
込められているように思えた。
昭和の時代まで、歌舞伎役者は江戸時代の身分制度を引きづった
「河原乞食」だった。
今でこそセレブ扱いされるが、一般的なセレブイメージと、」
彼らの生きる世界・人生には大きなギャップがある。
映画「国宝」は、そんな歌舞伎という畸形の演劇の歴史・文化、
そしてこの特殊な世界を成立させている人間模様を感じ取ることができる奇跡的なコンテンツだ。
舞台のシーンの迫力、女形を演じる喜久雄(吉沢亮)と
俊介(横浜流星)の美しさ。
この映画の魅力・価値を堪能するには、
テレビやパソコンサイズではだめで、
絶対に映画館の大スクリーンで見るべきだと思う。
777

素数である7は神秘のムードをまとい、
マジックナンバーとして古今東西、一目置かれてきた。
その7が3つ並ぶ(3ももちろん素数でマジックナンバー)
令和7年7月7日は大ラッキーデイ!
と大騒ぎになることもなく過ぎ去ろうとしている。
思い返すと、7はやはりミステリアスな数字。
かの「ノストラダムスの大予言」も、
空から大魔王が降ってくるのは「7の月」だった。
他の数字だったら、あそこまで話題にならなかったのではないか。
おとといの予言だか予知夢だかの「7月5日」も、
本当は7月7日にしたかったのだと思う。
でも、777だと、さすがに出来過ぎ感がするので、
少しずらして5日にしたのだろう。
「セブンイレブン」が成功したのは、
もちろんコンビニエンスストアという
新しい商形態を生み出したからだが、
「7(セブン)」のマジックも侮れない。
11も素数。素数を二つ並べ、韻を踏み、語感も抜群。
もともと午前7時開店、午後11時閉店という営業だったので、
理屈も整い、説得感も抜群。
誰でも一発で覚えられる最強のネーミングだ。
もし店名が「セブンイレブン」でなかったら、
コンビニエンスストアはこれほど普及しなかっただろう。
というのは言い過ぎ?
世の中のことはともかく、
自分の人生で7がつく日に何か大きな出来事があっただろうか、
と思い返してみた。
2つ思い当たった。
息子の誕生日が5月17日。
父の命日が12月17日。
ついでに言うと、祖父の享年が77歳だった。
こうなると、自分の命日や享年が気になるが、
それは考えずにおこう。
雨が降らなかったので、織姫と彦星は無事に会えただろう。
7は星や宇宙とも相性抜群。
ウルトラセブンもシックスやエイトじゃサマにならない。
やっぱりセブンはミステリアスでファンタジックで大好きだ。
佐野元春朝イチ出演 本物の還暦ロック
NHK朝イチ・プレミアムトークに佐野元春がゲスト出演。
僕は見ていないが、カミさんが見て「カッコイイ」と感激。
いろいろ内容についても教えてくれた。
ネットでも盛り上がり、ひと騒動だったようである。
佐野元春は若い頃よりカッコよく、
全世代にメッセージを伝えられる数少ない「ポオラ・スター」だ。
いま還暦を超えて活躍するミュージシャン・
アーティストは珍しくない。
いったん消えたが、高齢化する世の中の様子を見て
「まだできそう」と思って戻ってきた人もいるだろう。
あるいは、視聴率を取れるネタに困った
テレビなどのメディアに呼ばれるのかもしれない。
ただ、多くはどうしても「あの頃はよかったワールド」になり、
かつて青春を共有したファンたちが、彼・彼女らを囲んで
懐メロという暖炉であったまる――
という同窓会みたいな図式になっている気がする。
いわば懐メロ専門スターが増えているのだ。
それが悪いことだとは言わない。
懐メロで心を癒し、過去を振り返ることも大切だと思う。
でも終始それでいいのか?面白いのか?
全部でなくていいが、できれば半分、
せめて2,3割くらいは現役感・未来感があってほしい。
それに齢を取ると、その人の生き方が自然と佇まいに現れる。
どんなに着飾ろうが、若づくりしようが、
カッコよくはならない。
若い頃なら許された、だらしない言動、
人を不愉快にさせるような言動は、
無意識のうちに、かなり醜い形で表に出てしまう。
逆に誠実に、自分らしく生きてきた人はカッコよくなっていく。
これはミュージシャンや芸能人に限った話ではないと思う。
佐野元春が歳を取れば取るほどカッコよくなっていくのは、
おそらくそうした原理が働いているからだろう。
バックバンドやスタッフに恵まれているのかもしれない。
しかし、それは彼の才能と人柄、
もっと具体的に言えば、時代に応じて表現を変えつつも、
一貫して自分の思いや意見を、
誠実に音楽にし続けてきたからこそ、
強い味方となる周囲の人々を引き寄せるのだ。
むかし、「つまらない大人にはならない」と吠えていた
ミュージシャン、アーティストは大勢いた。
そのうち、何人がそれを実践できただろう?
いま、実践しているだろう?
佐野元春はつまらない大人にならなかった。
70歳に近くなった今、自信を持って
「ガラスのジェネレーション」をリメイクし、
魂を込めて歌える彼を、リスペクトせずにはいられない。
小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。
やつらはカレンダーがわかっているらしい。
というわけで、いよいよ夏本番。
といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。
関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。
そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、
近年、カタツムリをあまり見かけない。
息子がチビだったころには、
いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。
前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を
よくノロノロ歩いていた。
今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、
草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、
カタツムリをまったく目にしない。
まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、
ちょっと心配になる。
夏になると、生き物たちの活動は活発になる。
昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。
ガラスにへばりついていると、
ひんやりして気持ちいのかもしれない。
ちょっと窓をズラしてやると、
驚いてペタペタ動きまわる。
ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。
トカゲもちょろちょろしていて可愛い。
このあたりの輩は高速移動できるからいいが、
悲惨だなと思うのはミミズである。
ここのところ毎日、
道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。
それも一匹や二匹ではない。
赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が
数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。
まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。
それにしても、なぜだ?
果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、
無数のミミズたちに僕は問いかける。
おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、
なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて
熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?
なぜ故郷をあとにしたのか?
なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?
この道路の向こう、この地獄を超えた先に、
おまえたちの目指す楽園があったというのか?
それはあの植え込みか、草むらか?
もちろん、誰も答えてはくれない。
ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。
セミやハチやチョウのように空を飛べれば。
せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。
しかし、ミミズはミミズ。
地を這い、土に潜る。
それが宿命づけられた生き方だ。
その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、
それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?
というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、
ちょっと悲惨過ぎて載せられない。
ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも
いやだという人が多いだろうが。
なので本日は、クールビズしている
元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。
綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ
「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。
カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、
僕も土曜日に見たが、確かに面白い。
それにしても僕の中では、
綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、
そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。
役柄はもっと年上の設定らしいが、
もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。
そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの
スタッフも多くは40代
(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。
来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。
今や60・70代よりも40・50代のほうが
しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?
それどころか、20・30代も
「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。
どうやらがんばって終活するためには、
若いエネルギーが必要なのだ。
60・70代からじゃ遅すぎる?
いったいどうなっちょるんじゃ?
あっという間に1億総終活時代に突入だ。
「ひとりでしにたい」本当に面白いので、
観てない人は、NHKプラスで観てみてください。
電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」
無料キャンペーンは本日終了。
ご購入ありがとうございます。
よろしければレビューをお願いしますね。
AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
AIライフ、不老不死サイボーグ人生に興味のある方は必読。
6月30日(月)15:59まで 2025年半分終了記念
4日間限定無料キャンペーン開催中!
あとわずか。この機会にぜひどうぞ。
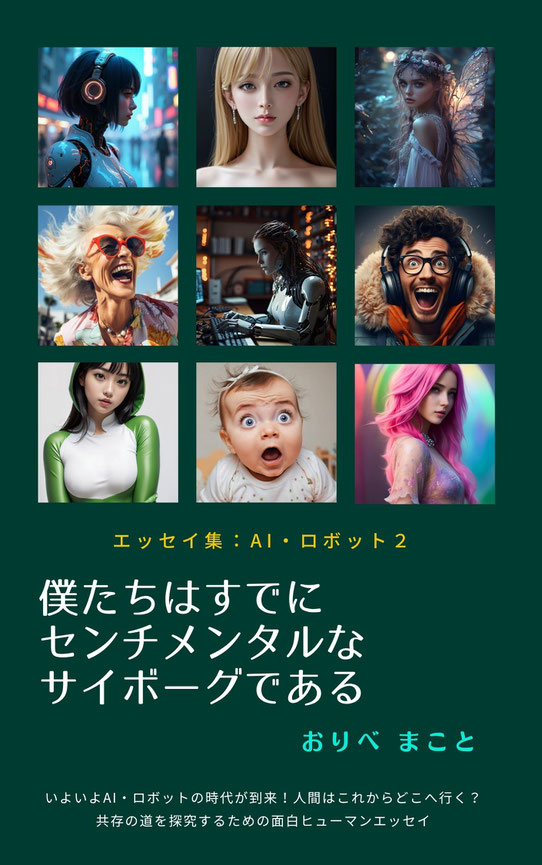
私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。
住環境から身体機能まで、あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、人間とは何かを問い直す時が来ました。
本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、
おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。
その内容の振り幅には驚かされます。
アンドロイド観音への戸惑いから始まり、
生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と
罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、
パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、
さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——
26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を
容赦なく描き出しています。
特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、
まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。
終活・終末期医療における
「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、
SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。
この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から
人間ドラマへと昇華させています。
「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、
これからどこへ向かうのでしょうか。
AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、
示唆に富んだエッセイ集です。
もくじ
アンドロイド観音とどう向き合うか?
100万回生きたロボット
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値
ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る
自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界
終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目
人生の半分はオンラインにある
AIはマンガのロボットみたいな相棒
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく
ほか全26編採録
「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から 「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ

子供は、強くて賢くて、何でもできちゃうロボットっていいな、
カッコいいな、僕もロボットだったらよかったのにな、
と憧れるのに、
大人になると「わたしはロボットじゃないんだ!」と言いだす。
なんで?
でも、齢を取ってくると、ふたたび、
ロボットだったらよかったのに、と思うかもしれない。
だってロボットはアンチエイジングだし、死ぬこともない。
最近思う。
人間として生まれた以上、
僕たちは一生ロボットにはなれないが、
技術の力で限りなくロボットっぽく生きることはできる。
私はそんなのごめんだ、
という人もこの時代に生きているかぎり、
じつは刻一刻とすでにサイボーグ化しているのだ。
そんな思いを込めて、AI・ロボット・エッセイ集第1弾
「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から
第2弾「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ。
AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ。
6月30日(月)15:59まで
2025年半分終了記念 無料キャンペーン開催中!
https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S
「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」無料キャンペーン開催
おりべまこと電子書籍 エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでに
センチメンタルなサイボーグである
本日6月27日(金)16:00~30日(月)15:59
2025年半分終了記念 4日間無料キャンペーン開催
私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。
住環境から身体機能まで、
あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、
人間とは何かを問い直す時が来ました。
本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、
おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。
その内容の振り幅には驚かされます。
アンドロイド観音への戸惑いから始まり、
生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と
罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、
パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、
さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——
26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を
容赦なく描き出しています。
特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、
まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。
終活・終末期医療における
「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、
SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。
この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から
人間ドラマへと昇華させています。
「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、
これからどこへ向かうのでしょうか。
AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、
示唆に富んだエッセイ集です。
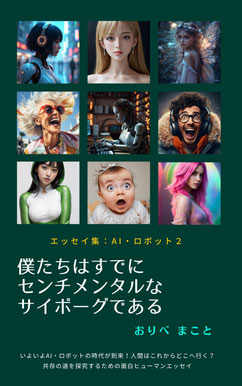
もくじ
アンドロイド観音とどう向き合うか?
100万回生きたロボット
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値
ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る
自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界
終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目
人生の半分はオンラインにある
AIはマンガのロボットみたいな相棒
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく ほか全26編採録
AIにご興味のある方、この機会にぜひご購入下さい。
山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識
なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」
小説(原作)と映画は別物。
それはそれでいいのだが、
そのギャップが大きければ大きいほど。
ツッコミがいがあって面白い。
「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は
その最たる例と言えるかもしれない。
川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、
映画にするなら、
全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。
それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、
その見せ場もいろいろ作る必要がある。
というわけで、この作品の場合は、
そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、
社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、
謎めいた演出が随所に散見される。
日本人の差別問題が裏テーマ
社会問題とは差別問題だ。
1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は
ちょっと遅れて日本にも及んだ。
70年代前半は、学生運動の挫折があり、
昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、
ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。
当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、
当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、
日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。
川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、
大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、
そうした日本人の差別意識が、
いかんともしがたい悪しき現実として、
随所にちりばめられている。
映画はそれらの材料をかき集め、
大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。
「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文
三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、
彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。
旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、
下賤な職業の人間として蔑視されている。
物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った
休憩所(だんご屋)の婆さんは、
旅芸人たちと親しげに話していたが、
学生に対しては
「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、
親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。
実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では
「あの人たちは今日の宿も決まっていない
(放浪者みたいなものだ)」と言っている。
映画ではこの婆さんの差別意識を、
いっそうあからさまに表現しているのだ。
セクシー少女・百恵の魅力の開花
なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、
「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と
一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。
彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。
これらは原作にはなく、この映画における演出である。
山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、
彼女の人気に火が付いたきっかけは、
シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、
当時ローティーンながら、
セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が
大ヒットしたからだ。
男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。
他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、
子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、
多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、
アイドル百恵の誕生につながった。
この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を
踏まえたものであり、
観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、
山口百恵の独特の、青い性的魅力を
うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。
ラスト1分 衝撃の不協和音
そして見せ場は最後の最後にやってくる。
学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。
見送りに来たのは、
かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、
船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、
大喜ぶで叫び、手を振り返す。
離れ離れになってはじめて
「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。
その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、
きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、
というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。
叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が
唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。
え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。
かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。
ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。
しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。
ひきつりながらも笑顔を保ち、
懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。
最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、
ストップモーションになってエンドマークが出るのである。
なんとも奇妙で、
まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。
なぜラストショットが、
若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、
汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?
夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。
ととでもメッセージしたいのか?
せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、
このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、
怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、
50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。
あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を
ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。
船が出る前、学生は地元の土方風の男に、
3人の幼子を連れた婆さんを
上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。
現代ならとんでもない無茶ぶりだが、
大正時代、エリートたるもの、
こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、
みたいな空気があったようで、
彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。
そして踊子との別れを終えた後、
伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、
東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて
彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。
当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、
庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、
立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、
そんな前向きな感想を持っただろう。
ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、
少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、
古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。
本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、
まだ読んだことがない人はぜひ。
そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、
豊かになった昭和日本で、
この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、
令和の世からタイムトラベルして、
若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。
母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから
「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」
と言われて、割とショックを覚えた。
でも、なかなか彼女は鋭かった。
確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に
いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。
女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、
同時にめんどくさかったり、怖かったり、
時々いやになったりもする。
それが態度や行動に出ていたかも。
その感情の遠因には、子供の頃、
母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と
一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。
その頃は母のことがあまり好きではなかった。
よく怒られたからである。
叔母と祖母はそれを見ていたせいか、
僕にやさしく、猫かわいがりした。
それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。
だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。
一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。
母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように
むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、
よけいにイライラを募らせたのだろう。
なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。
父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。
べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、
女運はよかったのかもなと思う。
思い出の中の女は、みんな可愛い。
この齢になると出会いも限られてくるので、
あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが
できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。
みんな齢を食ってしまったが、
女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。
こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。
今日は母の命日だった。
天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。
映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子
伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした
(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、
ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。
アマプラで1974(昭和49)年公開の
山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。
僕が中学生の時に公開された映画で、
当時大きな話題になっていた。
しかし当時、中二病にかかっていた僕は
「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」
と言って無視していた。
しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」
なんて映画は観に行った覚えがある。
山口百恵のファンだった試しはない。
「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、
少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、
僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。
中高生がアイドルに求める
可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが
大きな要因だったのではないだろうか。
同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、
むしろ女子の方に人気があった。
しかし今、この齢になって観ると、
唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。
この映画は女優として初出演作でもあるので、
演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、
明るさと陰とのバランスが素晴らしく、
この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。
●「え、はだか?」ではありませんでした
物語中、温泉に入っていたかおるが
学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって
裸で手を振るシーンがあるが、
そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。
最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、
いきなりグイっとカメラが寄る。
そして「え!?」と思う間もなく、
1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。
「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、
やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。
そりゃ当然だよね。
●「旅情」「異文化体験」を描いた原作
そんなわけで原作と並行して観たので、
小説との違いに目が行った。
俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い
「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を
リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。
もちろん、主人公の学生が旅先で出会った
芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が
メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。
少女を描くことに固執し、
ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、
この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、
恋愛的感情の表現はごく薄味だ。
そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ
「伊豆の踊子」が、
老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。
人物描写や風景描写などがイマイチで、
文学作品として未熟な部分も、
却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、
つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。
そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。
今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、
旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、
この物語の舞台である100年前は、
東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。
作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには
うってつけの場所だったのだと思われる。
そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う
旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。
「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが
圧倒的多数を占めていた、大正日本における
エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。
●河原乞食という現実
先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。
明治維新以降の近代日本では、
こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、
それはあくまで建前上、表面上のもので、
庶民がしっかり理解していたとは言い難い。
人々の心情に根付いた差別意識は、
まだ江戸時代のままだったのだ。
芸能人はどんな大スターだろうが、
すべからく「河原乞食」である。
原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)
という立札が出てくる。
この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、
旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。
川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、
ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。
踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、
こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。
とはいえ、川端は差別を告発しようと、
この作品を書いたわけではない。
あくまで旅で出会った現実の一つとして、
さらっと流している感じである。
クリエイティビティを刺激した山口百恵
この立札は原作では後半、終わりに近いところで
「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、
この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、
立札も物語が始まって間もないところで現れ、
かなり強い印象を残す。
まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。
かなり意図的なものと思われるが、
その背景として、おそらく当時、
社会改革の余波で部落問題などに焦点が
当たっていたことがあるのだろう。
また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、
日本の映画人も多かれ少なかれ、
社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。
それで監督や製作陣が、
単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、
と考えたのかもしれない。
山口百恵という稀有な素材は、
そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。
吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、
百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、
昭和の高度経済成長期以降の
「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、
現代にまで残る傑作にしたのだ。
映画の話、さらに次回に続く。
「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台
伊豆の河津に行ったのは先週だが、
駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。
それで初めて河津が、かの日本文学の名作
「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。
主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、
今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。
ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も
河津町だ。
いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、
そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、
生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。
おどろきの踊子
いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が
なんとなくどこかから耳に入ってきて、
知ってるつもり・読んだつもりになっている。
僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、
スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。
そして正直、びっくりした。
え、これだけ?って感じ。
文庫本でわずか40ページ。
字数にして2万字あまりの短編で、
30分ちょっとあれば読めてしまう。
旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで
けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、
ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。
どうしてこんなすぐ読める物語なのに、
俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、
自分の人生を後悔してしまった。
でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。
100年前の変態ロリコンじいさん
ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。
なんといっても「世界のカワバタ」。
ノーベル文学賞を受賞した、
敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、
その幻想もガラガラと崩れ去った。
今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。
「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、
最近の川端康成の定番像のようだ。
踊子へのエロい思慕
そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、
この「伊豆の踊子」の物語も、
なんとなくエロっぽく読めてしまう。
主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。
いわば川端の分身みたいな人物だが、
それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。
大学生が中学生に――ということなので、
今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、
ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)
全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が
メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、
いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、
頭がくらくらしてくる。
わずか40ページの短編のなかに、
こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、
日本文学の名作、それどころか世界名作としても
親しまれているゆえんなのかもしれない。
そう考えると、100年前の日本の文学界、および、
世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、
みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった
のではないか?という疑念にとらわれる。
いい加減だから名作になった?
正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、
そんなに中身のある話ではない。
話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。
物語としてはかなり薄味である。
川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、
もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、
旅芸人の一座との交流の部分を、
何年後かに抜き書きしたものらしい。
いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの
ノベライズなのである。
また、川端は、この作品では
「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。
でも、この作品の場合、その「さらっと感」
「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。
発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。
まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、
日本人のハートをわしづかみにした。
川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、
6度にわたって映画化された。
映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、
その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。
「女が箸を入れて汚いけど」
なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、
かなり深く心に刺さった部分もある。
それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。
100年前、旧制一高の学生と言えば、
日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。
対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。
さらにその中でも女は一段身分が低く、
一座のリーダー役の「おふくろ」は、
(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、
(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、
二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。
(川端が言わせている)
現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界
江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は
どんなに人気があろうとも被差別民であり、
身分制度の埒外の存在、
つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。
それは徳川幕府が、町人や農民に
「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、
できるだけ不満を抱かせないようにするための、
狡猾な支配構造をつくったからだ。
その意識は明治になって近代化された以降も、
えんえんと人々の意識に残った。
そういう意味では100年前、
大正から昭和になったころの日本はまだ、
現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。
モモエ踊子は差別問題を強調?
小説を読んだ後は、映画も見た。
1974年、昭和49年に公開された、
三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。
これも今に至るまで気が付かなかったが、
このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で
「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。
今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。
その話はまた次回に。
夫の精神的支配を受けた女性の話

うちのカミさんは鍼灸治療をやっているが、
話を聴いていると、患者さんの半分くらいは
精神疾患のせいで体もおかしくなっているようだ。
今日も不登校の高校生が
いきなり予約の合間を縫って昼食の時間に来たり、
「30年以上、一人で外出できなかった」という
60代の女性が診療を受けに来たと言う。
後者は、旦那の精神的支配を受けていて、
結婚して30年余りの間、
友だちとの付き合いはおろか、
買物も外食も、ひとりでは出してもらえなかったそうだ。
本当か? と耳を疑ったが、
いまだに一人で店に入れないという症状があるところを見ると、
どうも9割がたは本当のことらしい。
村上春樹の小説の中で、
金持ちではあるけれど、そういう恐ろしい価値観の男と
結婚してしまった女性の悲劇が
書かれてあったことを思い出した。
これは立派な精神的虐待だと思うが、
ひと昔前までは、
そんなに表立った問題にはならなかったのだろう。
もしかしたら今の50代以上--
昭和に生まれ育った女性では
そんなにレアなケースでもないのかもしれない。
その女性の場合は、子供がいないのも悲劇だった。
子供がいれば若い世代に救い出されたかもしれないし、
旦那の意識も変わっていた可能性もある。
結局、その旦那は3年前に借金を残して突然死んでしまった。
経済的には親戚のお金かなんかで助かったようだが、
彼女の病気はそのまま残った。
もう支配者がいないので自由なはずなのだが、
長年しみついた習性で一人で外出するのが難しい。
おそらく夫婦間で共依存の関係が出来上がっていたので、
自分で考え、行動することができなくなってしまったのだろう。
その女性がどういうきっかけで
来院することになったのか聴いてないが、
カミさんのところに来られるようになっただけ
治癒に向かっているのではないかと思う。
どうも買い物や食事に出かけるのは
「娯楽」として植えつけたらしく、
それを30年以上も禁じられていたので、
自分でも「娯楽=贅沢、無駄、悪」
みたいな意識が貼りついているらしい。
カミさんは、ひとりで喫茶店やレストランに入ることを
一つの目標にしなさいと言っているらしいが、
まだ実現できず、なかなか難しいようだ。
こういう話を聴くと、結婚とか、夫婦とか、
家族といったもののネガティブな面について考えてしまう。
よけいなことかもしれないが、
結婚ハッピー、夫婦なかよし、家族バンザイといった
画一的な価値観は怖い。
もちろん、明るく考えたほうがいいが、
そうしたダークな面があることも
常に心の片隅に置いておいたほうがいい。
そして、自分の間違いに気づいたら、
たとえ年寄りになっていても、
人生やり直す勇気を持つべきだと思う。
雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面
前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、
河童伝説の顛末を紹介したが、
いよいよ後編では本丸である。
住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、
快く承諾してくれた。
住職が大切そうに持参したのは、
見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。
よく見ると表面がややぼこぼこしており、
いかにも古い時代の手作り感が漂っている。
蓋は何度か作り変えられているそうだが、
壺本体は実に700年以上前のものだという。
「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」
住職がひっくり返すと、
底には「祖母懐」という文字が刻まれている。
●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産
「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。
これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、
温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。
愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、
そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。
さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。
「加藤四郎左衛門景正」
これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。
加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、
一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、
帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。
現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、
景正を祀った「陶彦社」が存在する。
「本物なら国宝級の品物です。
ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、
鑑定などしてもらったことはありません」
住職は笑いながら説明してくれた。
「河童からもらいました」と言えば、
鑑定士はどんな顔をするだろう?
そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら
どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。
さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、
粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。
そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、
焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが
四郎左衛門の作風だったそうだ。
確かに、目の前の壺も実に味わい深い、
野趣に富んだ風合いを見せている。
●いよいよ河童のせせらぎ体験
「河童はこれを置いていくときに、
『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。
これを聴いて私を思い出してください。
この川の音が聴こえる限りは、
私はどこかで元気に暮らしていますから、
和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」
住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。
果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?
「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、
ぼーっという音は聞こえるものなんです。
それは容器の中で風が流れる音で、
貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、
お分かりかと思います。
しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、
下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、
小さな水が流れる音がします」
住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。
最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。
しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!
確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが
聞こえてくるではないか。
まさに小川のせせらぎのような、
優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。
思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。
やはり聞こえる。確実に水の音である。
正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。
●プロの最新機材で録れなかった音が、
子供のラジカセで録音成功
住職によると、この不思議な音を録音しようと、
NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。
しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。
「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、
ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」
なんとも不思議な話である。
最新の録音機材では録音できないのに、
子どものラジカセでは録音できる。
まるで河童が、純真な心を持つ者だけに
水音を聴かせてくれるかのようだ。
試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。
すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。
後で家に帰って聞き返してみると、
確実にせせらぎの音が記録されている。
超うれしい!
これは一体どういう現象なのだろうか。
科学的に説明のつく現象なのか、
それとも本当に河童の仕業なのか。
真相は定かではないが、確実に言えるのは、
この壺から不思議な音が聞こえるというのは、
真実であるということだ。
●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告
住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。
豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、
壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、
洪水を予告してくれるのだそうだ。
「今でも川の音が聞こえるのですが、
河津川の水位が上がりそうな時など、
壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」
これは確かめようがなかったが、
もし本当だとすれば、
河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、
災害から人々を守り続けてくれているということになる。
●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー
ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。
「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。
ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、
と思いを巡らせることができます」
その上で住職は、禅宗の根本的な教えである
「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。
「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。
これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、
それに惑わされてしまうという教えです。
実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、
例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、
肌で感じたりすることで、
現実には目に見えないものに思いを馳せたり、
いろいろな想像・連想ができたりする。
そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」
なるほど、これは深い話である。
現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、
さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、
僕たちはそれらに振り回されがちだ。
しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。
むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、
真実が隠されているというのだ。
「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、
自分で感じなさいという教えです。
現代社会では、テレビやインターネットを通じて
文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、
皆さん惑わされますから。
こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と
想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、
という教えが、
この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」
●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心
住職はさらに続けた。
「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、
もともと仏の心を持っています。
ところが、現実の社会で生きるうちに、
心にたくさんの垢がこびりついてしまう。
真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」
これも禅宗の重要な教えの一つである。
すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。
しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、
先入観といった「垢」が心に付着してしまう。
その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。
河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。
現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、
僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。
「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、
実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。
昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。
ですから、そんな中で、こうした体験をすると、
より心に響くのかなと思います」
確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。
現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、
素朴で自然な美しさがそこにはある。
そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、
日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ
河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、
僕は深く心を動かされた。
これは単なる音響現象以上の何かがある。
人はみな心に仏性を持っており、
それによって、せせらぎの音を聴くことができる。
虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、
こてはとても大切な体験であるように思える。
SNSで飛び交う断片的な情報、
ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、
AI生成による真偽不明の映像や音声、
誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--
僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。
そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、
本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。
そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
僕たちに大切なことを思い出させてくれる。
文字や人工的な情報で表現できない真実が、
この世界にはあるということ。
そして、その真実は五感を通じて、
心で感じ取るしかないということを。
●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心
この河童の壺の音について、
科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。
壺の形状による音響効果なのか、
それとも何らかの物理的現象なのか。
しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、
実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。
大切なのは理屈ではなく、
その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。
最新の科学技術よりも、
純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。
河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、
この音を聴く時、
僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。
河童が実在するのかどうかは問題ではない。
大切なのは、その存在を通じて、
自然との調和や他者への慈悲といった
大切な価値を思い出すことなのだ。
●あなたの心の中の河童に出会うために
700年という長い年月を経ても、
河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。
伊豆に来たら、河津に来たら、
ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。
ただし、河童の壺を体験したい場合は、
この壺が寺宝中の寺宝であるため、
必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。
そこで、あなたも河童の封じ込めた
せせらぎの音を聴いてみてほしい。
音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。
日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。
もし音が聞こえたなら、
それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。
そして、河童という架空の存在を通じて、
自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を
思い出すことができるだろう。
あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。
そして河童が、
人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。
文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、
河童の壺が奏でるせせらぎの音は、
きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。
(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺
今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある
「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を
訪ねることになった。
JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。
駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が
目の前に広がる。
あいにくの小雨模様だったが、
河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、
これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。
ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。
むしろこの雨模様のほうが、
なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、
まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。
●椅子まで河童という油断のならない境内
境内に入ってまず驚かされるのは、
とにかくあちこちが河童だらけということだ。
持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、
よく見ると河童の形をしていた。
思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。
寺院としては日本的な古さを感じさせる、
いかにも由緒正しそうなお寺だ。
と同時に、どこか懐かしい感じもする。
よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に
境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。
これは後で知ったことだが、
ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが
なせる業なのだ。
●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年
「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、
実に700年の歴史を持つ古刹である。
その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。
開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である
徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、
なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。
徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、
二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の
大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。
その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、
帰国後は各地の名刹を歴任した。
そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。
興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という
真言宗の寺があったということだ。
それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。
「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)
という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、
深い意味を込めた名前である。
●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割
現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。
「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、
河津桜で有名になる前--
昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」
今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、
桜まつりが始まったのは今から34年前の
1991年(平成3年)のこと。
桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える
大イベントに成長したが、
それ以前は河童が町の看板だったのである。
「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、
商工会に飾られていたりしたんです。
でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、
そういったものを寺で預かったんです」
なんとも皮肉な話である。
河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、
河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。
そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を
果たすことになったというわけである。
●「つくったが、作られていないように」のアート美学
現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。
「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」
ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。
人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、
まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、
「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、
心憎いばかりだ。
書家の師範のスタッフもいるということで、
寺院としての格式を保ちながらも、
現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。
●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー
以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、
町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、
昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、
一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。
「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、
住職は苦笑いを浮かべながら、
「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。
●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人
さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。
それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。
昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。
お寺の裏に位置するその場所は、
川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。
この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、
いろいろないたずらをして村人を困らせていた。
そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか
「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、
村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。
なんとも人間らしい話である。
最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。
●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童
そして運命の日がやってきた。
ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。
そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。
そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。
よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。
「河童だ、河童がいるぞ!」
誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。
河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、
裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。
ここでの河童の行動が実に人間臭い。
馬のしっぽにしがみつくという、
なんともマヌケな状況で発見され、
慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。
●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑
しかし村人たちは容赦しなかった。
井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。
河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、
井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。
村人たちは河童を取り囲み、
「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、
棒切れで叩き始めた。
ちょっとやりすぎな気もするが、
当時の人々にとって河童は子どもを攫う
恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。
●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命
ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。
村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、
河童が息も絶え絶えに倒れている。
それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。
和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。
「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。
寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」
さすがは禅僧である。
暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、
慈悲の心で河童を救おうとした。
村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、
和尚さんの言葉に従って河童を預けた。
●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し
和尚さんは村人たちがいなくなると、
「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」
と言って、河童を逃がしてやった。
この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。
その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で
目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。
すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。
●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺
河童は言った。
「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」
そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。
「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。
口に耳を当てると、水の流れる音がします。
水の音が聞こえたら、
わたしがどこかで生きていると思ってください。
和尚さまもどうぞお元気で」
そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。
●令和の今も、壺に耳を当てれば
和尚さんは夢心地で聞いていたが、
我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、
河童が本当に来たのだと確信した。
それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、
村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。
けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、
底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、
河童の無事を思った。
また、河津川に出水があった際、
このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、
人々が助かったこともあり、
それから寺の宝として大切に奉られてきたという。
今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、
河童が元気で生きていることを伺える。
そして人々は水の流れが心を洗うと言い、
ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~
さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、
実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。
果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが
聞こえるのだろうか。
後編では、この神秘的な河童の壺による
不思議体験をレポートする。
僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、
数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を
体験することになるのだが、
その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。
後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、
そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。
(後編に続く)

鉄道マン発 洗たく女 サイボーグ
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
無料キャンペーンは終了しました。
たくさんの方にご購入いただき、ありがとうございます。
気に入っていただけたら、紹介・購入サイトの下のほうに
「カスタマーレビュー」があるので、星をつけてもらったり、
レビューコメントを書いていただき、
他の読者におすすめいただければありがたいです。
(できれば高評価、でも厳しいご意見も歓迎です)
同書は引き続き、800円で販売しています。
また、おりべまことにご興味を持たれたら、
他にもいろいろ出していますので、ぜひ覗いてみてください。
格差社会ではたらく女の労働ファンタジー小説
洗たく女の空とぶサンダル ¥500
最新刊!AI・ロボットエッセイ集
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
¥500
脱サラ・起業・転職のリアル
今、60歳が人生の新たなスタート地点になった。
シニアも若者も必読!
生き方に悩む人のためのリアルな参考書がここにある。
鉄道マン発 映像調理師®
ー高塩博幸の人生甘辛レシピー
無料キャンペーン、いよいよ明日、
6月9日(月)15:59まで
すでに120部を突破。
脱サラ・起業・転職を考える人たちの間で大きな話題に。
無料で購入できる最後のチャンスです。
専用端末は不要。アプリを入れてスマホで読もう。
鉄道マン発映像調理師® 無料キャンペーン実施中
大好評!
鉄道マン発 映像調理師®
ー高塩博幸の人生甘辛レシピー」
6月9日(月)15:59まで
6日間無料キャンペーン開催中。
このチャンスをお見逃しなく!
今、60歳が人生の新たなスタート地点。
シニアも若者も必読。
生き方に悩む人のためのリアルな参考書。
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!
かつて新幹線を走らせた男が、今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。本書「鉄道マン発 映像調理師」は、シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追ったルポルタージュです。
高校生だった高塩少年は祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に国鉄に入社。その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。
しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?
映像クリエイターとしての第二の人生では、自らを「映像調理師®」と名乗り、終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。
「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。
運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、学ぶべきものがたくさんあります。
人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。
足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、
第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。
「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?
「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、
あなたも勇気をもらえるはずです。
本書は単なる成功物語ではありません。
昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、
失敗や挫折を乗り越え、常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。
起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、
そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。
人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵がここにあります!
ヘビとの遭遇

今年の干支は?
って聞かれて「えーと」なんてダジャレてる人、
けっこう多いのでは?
1年半分の6月ともなると、お正月の熱狂もどこへやら。
今年は何年だったか、みんな忘れてしまっている。
改めて、今年-2015年、令和7年はヘビ年。
そのせいか、この春からは初夏にかけて、
川沿いを散歩していると、やたらとヘビに出会う。
護岸の下のコンクリの岸の上に
何やら太いロープが落ちているなと思ったら、ヘビ。
散歩道の植え込みの中で何かにょーっと
動いているなと思ったら、ヘビ。
手すりに何か紐みたいなものが
ぶら下がってるなと思ったら、ヘビ。
そして昨日は、くねくねしながら悠々と川を泳いでいる
ヘビを目撃。
どれも長さ1メートルほどの青黒いアオダイショウだ。
周囲にはカルガモやコサギ、アオサギ、
カワウなどの水鳥が何羽もいるが、
さすがにこれらは体が大きいので襲ったりはしない。
うまいこと共存しているようだ。
そろそろカルガモの赤ちゃんが生まれる時期なのだが、
今からそれを狙っているのだろうか?
毎年1回か2回、
梅雨から梅雨明けの時期にお見掛けするヘビだが、
今年はすでに目撃4回。
ヘビ年大売り出しだ。
遭遇するとちょっとギョッとはするが、
ヘビに遭うとラッキーなのだそうな。
そういえば数年前だが、
住宅街の道路を白ヘビが
超高速で横切るのを見たことがある。
神の使いともいわれるヘビ。
今度会ったら手を合わせて願いを唱えよう。
人の気配が薄れる夜の時間は、
ネズミでも襲って腹を満たしているのだろうか。
杉並区も人間が知らないところで
ワイルドな世界が繰り広げられている。
岸辺露伴×水の都ヴェネチア
「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、
「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。
「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。
人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、
オールヴェネチアロケ。
映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。
テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、
ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。
主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、
そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。
それによって事件を解決していくストーリーだ。
原作のマンガも全く知らないが、
高橋一生は超ハマり役だと思った。
舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。
ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、
幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。
年中、観光客が押し寄せていると思うが、
いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、
人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、
歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。
僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、
ヴェネチアにも訪れたが、
見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。
それは当たり前で、
この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。
世界遺産になった宿命みたいなものである。
車はもちろん、自転車も街の中に入れない。
観光客がわんさか来るのだから、
スタバやマックなどの店もありそうだが、
少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。
そうした規制も多いはずだ。
オーバーツーリズムを避けるため、
街に入るための入場料徴収も検討されているという。
世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、
僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。
一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、
僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に
奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、
どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。
ヴェネチアはその最たる街だ。
さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような
スケールの都市ではなく、
せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。
そこに独自の文化が集約されている。
観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、
実際の観光収入はそんなにないのではないか。
ヴェネチアを舞台とした映画で、
ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)
という作品があった。
そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、
たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、
ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、
普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、
ゴンドラやボートに乗ったり、
写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。
僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、
多分そうしたのだと思う。
それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが
あるのだろうか?
観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、
この街の住人たちがどうやって暮らしているか、
庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、
ひどく気にかかる。
この岸辺露伴の映画も、
けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、
人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。
それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、
とても心に残った。
地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。
この風景はいったいいつまで見られるのだろう?
本日より無料キャンペーン「鉄道マン発映像調理師®」
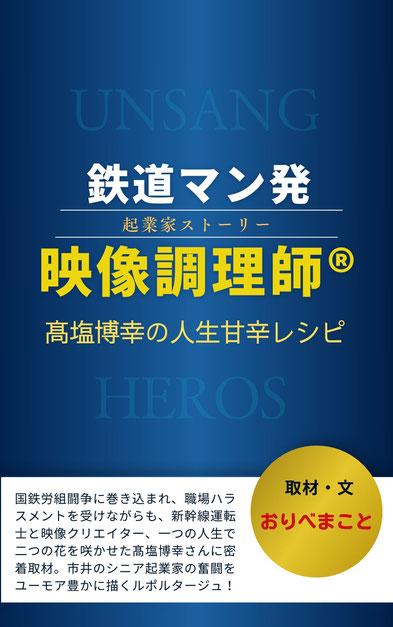
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
本日6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで
発売記念 6日間無料キャンペーン実施
このチャンスをお見逃しなく!
もくじ
第1章 高塩さんと映像の仕事
映像調理師®高塩博幸
エンディング産業展2022
倫理法人会での人脈から映像制作を受注
おいしい料理は“下ごしらえ”から
その人のストーリーを見つける作業
運転士の教官として培ったインタビュー術
AIなど最新ツールの駆使
ユニークなサービスメニュー
★ 自分史・遺言ムービー「nokosu」
★ nokosu 周年映像制作
★ 家系史継承箱《メモリアルボックス》
★ 死後の自分史
★ 子ども史・子育て自分史
●講座開設
★ 講座「スマホで自分史動画を作ろう!」
★ 講座「AIを使ってコマーシャル動画をつくる」
なぜ人は自分史を作ろうとするのか?
第2章 高塩さんの起業家スピリット
誰もがアーティストになれる
人生百年時代のチャレンジャー
ケンタッキーおじさんでもよかった
芸術と起業の街・足立区北千住からの再出発
映像調理師®誕生の舞台裏
映画より映写室が好きな子ども
きみは「ポピュラーチューズデイ」を聴いたか?
コンサートで音響アルバイトを経験
あんた、学校行ってどうするの?
高塩家のファミリーヒストリー
日本電子工学院と国鉄のW受験
第3章 高塩さんのJR東海道中膝栗毛
クリスマスエクスプレスに涙ぐむおじさん
花形鉄道マン
昭和の「青春18きっぷ」
国鉄百年の盛衰
組合闘争に巻き込まれて
「会社のイヌ」と呼ばれて
出世の秘密
JR東海出世街道
人生の憂鬱な昼下がり
鉄道マン最後の日
第4章 高塩さんと終活映像市場
高齢化社会における終活市場の拡大
映像が紡ぐ、新たな人生のしまい方
終活映像市場に輝く、ブルーオーシャンスターズの価値
映像調理師®の理念
欲しいけど欲しくない:終活映像営業の難しさ
終活映像市場に咲く、高塩博幸の営業哲学
新しいアプローチ
第5章 ブルーオーシャンスターズの未来
AIの進化を追いかけて
高塩式AIディレクター構想
10年後・20年後の世界を見据えて
「停止位置不良」の夢を見た人、来たれ!
鉄道マン発 映像調理師® 無料キャンペーン開催
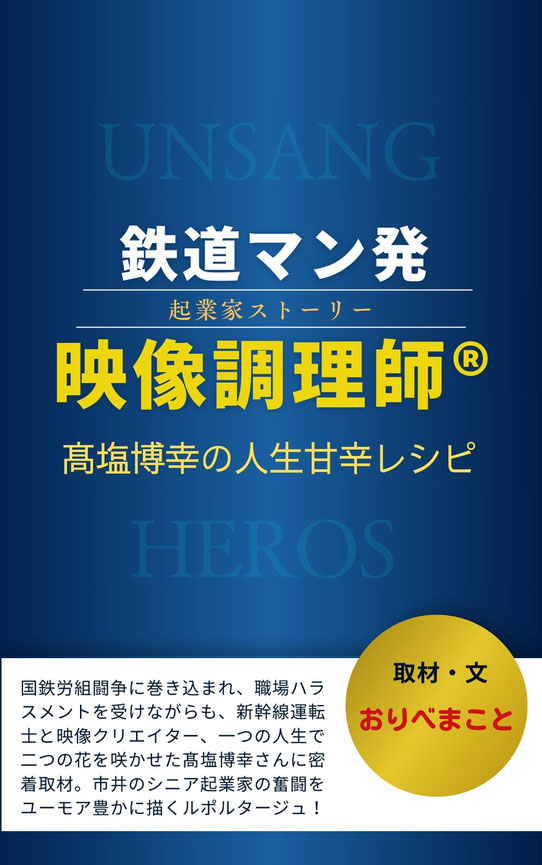
今、60歳が人生の新たなスタート地点
シニアも若者も必読!生き方に悩む人のためのリアルな参考書
鉄道マン発 映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで
発売記念 6日間無料キャンペーン実施
このチャンスをお見逃しなく!
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
おりべまこと電子書籍最新情報:AIエッセイ+起業家ストーリー
★本日6月2日(月)発売!
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S ¥500
スマホを握りしめ、メガネをかけ、工場製の服を着て生きている僕たち。実はもう「純粋な人間」なんてどこにもいません。世界的ロボット工学者が断言するように、現代人はすでに「動物と技術を合わせたもの」なのです。AIにパワハラプロンプトを仕掛け、アンドロイド観音に手を合わせ、エロコンテンツで技術革新を推し進める——抗えないテクノロジーの波に翻弄されながらも、どこか愛おしいAI・ロボットたちとの共存を模索する現代人の心境を、ユーモアと哲学的洞察で描いたエッセイ集です。
★6月4日(水)16:00~9日(月)15:59 無料キャンペーン!
ノンフィクション
鉄道マン発映像調理師®-高塩博幸の人生甘辛レシピー
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!
映画「エイリアン」とアンドロイドたち

ここのところ、急にまたSF映画が見たくなって、
ほとんど連日何かしら見ている。
今週はエイリアンシリーズを鑑賞。
シガニー・ウィーバーが主役のリプリー中尉を演じた1~4は、
SFホラーとして、単純に恐怖し、楽しめる部分と、
それだけで終わらない哲学的考察がミクスチャーされていて、
今、通して見ると当時とは違った印象・味わいがある。
●20世紀末20年の科学の進歩の集大成
この1~4は、1970年代の終わりから90年後半まで、
約20年の間に作られており、
この間の現実の人間社会の変化--
女性の権利の拡大と深化、ロボット・AI技術の発展、
クローン技術など、生命工学の進化などを積極的に取り入れ、
それらのエッセンスが絶妙な塩梅で織り込まれている。
また、初代監督リドリー・スコットの功績を引き継ぎ、
2でジェームズ・キャメロン、
3でデビッド・フィンチャー、
4でジャン・ポール・ジュネという
強烈な個性を持つ巨匠たちが、
それぞれ独自の美学と演出術を持って、
1本1本色合いの違う、独立した作品でありながら、
しっかりつながった物語を構成していることが、
このシリーズの成功要因になった。
●各物語のキーパーソンとなるアンドロイド
第1作における、ハンス・リューディ・ギーガーのデザインによる
最凶の宇宙生物エイリアンの登場は、
斬新でオリジナリティ豊か、
そして、怖さ・気持ち悪さの点で、衝撃度満点だった。
しかし、回数を重ね、見慣れてくると、
やはりその怖さ・気持ち悪さのインパクトは薄れてくる。
エイリアンシリーズの名作たる所以は、そこを補うために、
どんどんストーリーを拡大・深化させていったところにある。
そのキーとなるのが、ロボット(アンドロイド)の存在だ。
どの作品にも必ず人間そっくり(実際に俳優が演じている)の
アンドロイドが登場し、
その策略と行動が大きくドラマを動かしていく。
第1作のオリジナル脚本で、
どこまで設定が作られていたのか定かでないが、
宇宙開発事業を行う民間企業のシステムの一つとして、
彼らの頭脳(AI)は重要な役割を担い、
表向きの事業とは異なる、
隠された裏ミッションの担い手として暗躍するのである。
そして、これらのアンドロイドが、エイリアンに匹敵するほど、
怖くてグロテスクで気持ち悪い。
第1作の「アッシュ」も、第2・3作の「ビショップ」も
最後に人間やエイリアンに破壊されるのだが、
引き裂かれた体の内部は人間の内臓っぽかったり、
体液みたいなものが出てきたり、
半壊してボロボロの姿になっても機能できたりするシーンは、
なまじ人間そっくりなので、思わず目を背けたくなるぐらいだ。
第4作の「コール」は、
当時の人気若手女優ウィノナ・ライダー演じる女性型だったので、
さすがに他の二人みたいな凄惨な目に合わせるのは
スタッフも気がとがめたのか、
銃で撃たれるだけで済み、ラストまで原形をとどめて生き残る。
●仕事優先の機械人からヒューマンタッチな仲間への変遷
注目したいのは、シリーズにおける
これら「エイリアン・ロボット」の変遷だ。
第1作の「アッシュ」は宇宙船の科学担当者として、
割と単純に人間と敵対する(サンプル採取のため、
エイリアンの元を船内に招き入れる)、
割と単純な、お仕事最優先の機械的なロボットだ。
第2作の「ビショップ」はこれよりちょっと複雑化し、
最終的にリプリーたちをエイリアンから救う
「人間の味方」になる。
そして第3作では彼と同じ俳優が演じる、
「人間のビショップ」が、
企業のアンドロイド開発者=リプリーの敵対者として現れる。
同じ顔かたちでありながら、
ロボットよりも人間のほうが冷徹なのである。
第4作の「コール」は、前2体とは対照的に、
人間的な感情を持ち、
(エイリアンを宿した)リプリーを殺す使命を持って現れるが、
人間的な感情を持つ、いわゆる不良品のロボットで、
最後にリプリーと仲間になる。
日本では「アトム」や「エイトマン」のような
漫画で描かれたように、いくら強くて優秀でも、
自分が人間でないことに悩み苦しむロボット、
あるいは、「ドラえもん」のように、
もともと人間の仲間・友だちみたいなロボットが主流だが、
欧米では、70~90年代の20年あまりで
従来のロボット観がかなり変わってきたようである。
それは「ターミネーターシリーズ」や「ロボコップシリーズ」、
「ブレードランナー」「AI」など、
この頃、立て続けに作られた、
他のロボット映画の影響も大きいだろう。
●人間観・ジェンダー観の変化がロボットを魅力的にした
しかし、それよりも大きいのは人間観の変化、
特にジェンダー観の変化かもしれない。
昔、何かの本で「男がロボット好きなのは、
子供を産まない(産めない)からだ」
というフレーズを目にしたことがある。
つまり、子供を産める女性に対抗して、
命の創造に関わりたいという潜在的欲求が男の中にあり、
ロボットへの興味・研究に向かわせる、というのだ。
こうした出産機能を基点に考えるジェンダー観は面白い。
ハリウッド映画には、おそらく1970年代初め頃まで、
「女・子供を映画のなかで殺さない」という不文律があった。
アメリカ社会(及び、日本も含む、西洋型社会全般)には
女性や子供は「善なるもの」「聖なるもの」の象徴であり、
侵してはならないもの、男が命を賭けて守るべきもの
と考えられていたのだ。
もちろん、病気や事故、あるいは戦争に巻き込まれて
恋人や家族が死ぬなどのエピソードはあるが、
それらは情報として処理されるか、あくまで美しく描かれ、
けっして血まみれになるようなシーンはなかった。
そして女性や子供の死は、
男が奮い立って行動するためのモチベーションになっていた。
それらは言い換えれば、女性や子供を弱き者、
男の支配下に置かれる者、でなければ、
女神や女王のように崇め奉る者といった意味があった。
それが60年代の変革を経て、劇的に価値観が変わり、
女性も男性と対等の自立した人間として
描かれるようになっていく。
1979年に初登場した、シガニー・ウィーバー演じるリプリーは、
女神でも聖女でもなく、リアルな自立した人間として活躍する、
新しいタイプの女性ヒーローだったと思う。
彼女は自分のゆるぎない価値観と使命を持ち、
エイリアンと闘うヒーローとして描かれるが、
それゆえ、かつての映画の女性像からは想像もつかない、
相当ひどい目に遭わされる。
死んで生き返り、エイリアンとの「あいのこ」になり、
おぞましい姿をさらすことにもなる。
そうした惨劇のなかから
女性主人公ならではのテーマ「命の創造」をビビッドに提示する。
さすがにウィーバーの出演は4で終わるが、
最後の作品では、フランス人監督ジャン・ポール・ジュネが
グロテスク極まりない、リプリー最後の戦いを描きつつ、
「アメリ」「ロストチルドレン」のような寓話的な余韻を残し、
いったん、エイリアンシリーズの幕を下ろす。
そして、ジュネの残した余韻を受けて、
初代監督リドリー・スコットが再登板し、
「プロメテウス」「エイリアン・コヴェナント」
といった前日譚--21世紀の「エイリアン」を製作する。
エイリアンとジェンダー観の変化については、
また別の機会に詳しく書いてみたい。
●未来の記憶から生まれるコンテンツ
現実の科学技術の進歩を踏まえて作られた
20世紀末のSF映画だが、
昨今の技術の進捗状況は、これらエイリアン映画などの世界を、
そう遠くない未来に実現させてしまいそうな勢いがある。
もしかすると人類は未来の記憶を持っていて、
そのヴィジョンに向かって突き進んでいるのかもしれない。
SF映画はそれらの記憶を表現するコンテンツの一つなのだ。

おりべまこと電子書籍最新刊
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでに
センチメンタルな
サイボーグである
近日発売!
AmazonKindleにて
世界のエンディングの潮流は、エコ葬と安楽死

最近、墓じまいや相続問題など、
日本でも終活の話題が増えているが、
海外に目を向けると、世界の葬儀・終活の焦点は、
安楽死とエコ葬に傾いているようだ。
●英国で安楽死法案が成立目前
いま、英国では安楽死法案が下院での審議を通り、
6月には上院での審議に移るが、
この法案が成立するのは、ほぼ確実と言われている。
すでにスターマー首相も支持を表明しており、
BBCニュースなどで昨年末から
頻繁に審議の様子が報道されている。
日本では超高齢化社会・多死社会が
進展しているのにも関わらず、
長らく安楽死・尊厳死・自殺ほう助といった課題は、
ほとんど、まともに議論されてこなかった。
しかし、この英国の法案が成立したら、
何か大きな影響がおよぶかもしれない。
●この10年で安楽死が認められた国が・・・
少し前まで安楽死と言えば、
オランダとスイスしか思い浮かばなかったが、
現在はどうなのだろうと調べてみた。
2025年1月末時点でのデータだ。
・完全に合法化されている国・地域:
オランダ(2002年)
ベルギー(2002年)
ルクセンブルク(2009年)
カナダ(2016年)
コロンビア(2015年)
スペイン(2021年)
ポルトガル(2023年)
・部分的に合法化:
スイス(1942年から自殺幇助のみ合法)
ドイツ(2020年に憲法裁判所が自殺の権利を認定)
アメリカ(オレゴン州、ワシントン州など複数州で
医師幇助自殺が合法)
オーストラリア(複数州で合法化、
2019年ビクトリア州から開始)
・2023年(コロナ明け)以降の動き:
ポルトガルが2023年に完全施行。
英国は現在審議中(下院可決済み)
他に現在審議中・検討中の国を挙げると、
フランス(マクロン大統領が法案検討を表明)
イタリア(国民投票の動きあり)
アイルランド(市民議会で議論)
かなり衝撃的だった。
あくまで欧米に限っての話だが、
安楽死・尊厳死・自殺ほう助を認めた国は
この10年ほどで激増している。
●エコ葬も激増
一方、エコ葬も増加しているようで、
今世紀に入ってから、遺体をフリーズドライにしたり、
アルカリ溶液に浸して分解する水火葬、
土中の微生物を使って堆肥にする有機還元葬など、
さまざまな環境負荷の少ない葬法が考案されてきた。
どれも当初はキワモノ扱いだったが、
アメリカではすでに12州で有機還元葬も認められ、
水火葬も広がっている。
特にコロナ禍以降、この2,3年の変化は大きい。
安楽死とエコ葬は、まさに現代の葬儀・終活業界の
大きな潮流になっているのだ。
●何が人の心を、社会の常識を変えたのか
安楽死については、人権問題と深くかかわっているようだ。
「どう死ぬか」という個人の選択権の拡大、
医療技術の進歩で延命が可能になった一方での
「死の質」への関心、
超高齢化社会での終末期医療費の問題、
家族への負担軽減
といった視点が増加の要因になっていると思われる。
また、エコ葬については、
環境意識の高まりと持続可能性への関心
土地不足問題(特に都市部)
従来の墓地・埋葬への価値観の変化
樹木葬、海洋散骨、自然葬などの多様化
といった精神・ライフスタイルの変化が大きい。
両方とも、従来の「伝統的な死生観」から
「個人の価値観を重視する死生観」への転換を表している。
特にコロナ禍を経て、人々の死に対する考え方が
より現実的で個人的なものになったという面もあるだろう。
葬儀・終活業界としては、
これらの多様化するニーズにどう対応していくか、
また法制度の変化にどう準備するかが重要な課題になってくる。
あまり考えたくないという人が多いと思うが、
そう遠くない未来、日本でも今後、嫌でも
これらの議論をしなくてはならない時が来そうだ。
時空を超えた家康AI 好みの女性は天海祐希と石田ゆり子

「千住宿」は日光街道の最初の宿場町。
現在の北千住界隈がそうだ。
宿場が開かれたのは3代将軍・家光の時代、
1625年だから、今年でちょうど400年。
それでお祭りをやっているというので、
18日の日曜日、北千住まで行ってきた。
北千住は、拙著「鉄道マン発 映像調理師®」で
取材させていただいた髙塩博幸さんの
「ブルーオーシャンスターズ」が会社を構える街。
生まれも育ちも起業も足立区の髙塩さんは、
ビジネスとともに地域貢献にも熱心で、
今回は、この千住宿400年に際して、
オリジナルソングとビジュアル(プロモV)を提供。
さらにこの日は、AI企業研修を行う会社
「TSUYOMIHO」の宮田剛志さんとタッグを組んで
街頭に「家康AI」のブースを出店した。
「家康AI」は、家康に向かって質問すると、
「拙者が家康じゃ」などと徳川家康が
ユーモラスに答えてくれる体験。
歴史を「教わる」のではなく「対話する」スタイルで、
子どもから大人まで楽しめるのがウリだ。
テレビ局の取材も来ていて、
面白がって問いかける子供たちにインタビューをしていた。
僕もあれこれ質問してみたが、
没後409年を経て、AIの力で現代によみがえったこの家康、時々、「拙者がこの千住宿を開いた」なんて
トンチンカンなことを言う。
いやいや、五街道を整備しようと努めたのはあなただけど、
宿を開いたのは孫の家光でしょ。
そもそも400年前の1625年って、あなた、もう死んでるし。
それで「あなたの後の14人の徳川将軍のうち、
最も評価できるのは誰ですか?」
と聞くと家光の名を挙げたりする。ほうほう。
トンチンカンな部分は差し引いて、答がいかにもAI的な、
優等生の模範解答みたいなのが気に入らない。
それでいろいろ変化球を投げてみる。
「来年の大河は『豊臣兄弟』なので、今度はあんた悪役だね?
誰にやってほしい?」とか、
「『どうする家康』では、あんた、北川景子の
お市に惚れてたみたいだけど、ホントに好きだったの?」とか。
このへんの質問はうまくかわされたけど、
「好みの女性のタイプは?」と聴くと、
「しっかりしてて優しい人」なんて、まともに答えてきた。
「じゃあ、たとえば現代の女優さんだったら誰?」
と聴いてみたら、「天海祐希と石田ゆり子」と、
照れもせずにペロッという。
どういうラーニングをしたのか、
髙塩さんと宮田さんに突っ込もうと思ったが、
ま、お祭りだし、やめておいた。
てなわけで、今年は北千住で
随時、400年のお祭りをやっているので、
機会があれば遊びに行ってみてください。
髙塩さんと僕の本もよろしくね。
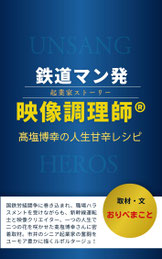
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
Amazon Kindleより好評発売中。¥800
国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!
世界の果ての海風さやか 吉祥寺で地中海料理

週末、息子の誕生日だったので、お祝いで
吉祥寺にある地中海料理の店「The MED」に行く。
店名は英語の「Mediterranean」の
頭の文字から取っているらしい。
これは「大地の真ん中」を意味する
ラテン語の「mediterraneus メディテッラーネウス」
medius 「真ん中」 + terra 「土、大地」に由来する語だ。
何だかカッコいい。
日本語の「地中海」もエキゾチズムの香りがする、
イメージ豊かな言葉。
明治時代に作られた可能性が強いが、当時の翻訳者は、
遠いヨーロッパのさらにそのまた向こう、
まるで世界の果てに広がる
天国のような優しい海を想像したのではないか。
さて、The MED。
外見はおしゃれだが、中は小さな居酒屋のような、
気さくな店で、キャパはせいぜい15人程度というところか。
店主らしき、料理を作るおっさんと、
注文をきく店員の若い女性でやっている。
(店員は日替わりかもしれない)
仕込む材料によって日替わりになるのか、
はたまた店主が毎日同じ料理ををつくると飽きちゃうからか、
決まったメニューブックがなく、
キッチンの前にその日出せる料理を紙に書いて貼りだしている。
さらにそれぞれの料理名の紙は
小さな国旗のマグネットで留められており、
どこの国の料理か、わかる仕組みになっている。
なにせ地中海はヨーロッパの南部、アジアの西部、
そしてアフリカの北部に囲まれた海で、
「地中海地域」に属する国は20以上もある。
よく知られているのは、ギリシャ、イタリア、スペインだが、
ヨーロッパではクロアチアやスロベニア、フランスも入る。
アジア~中近東方面は、
トルコ、レバノン、シリア、イスラエルなど。
アフリカだとエジプト、リビア、チュニジア、モロッコなど。
イタリア料理店やスペイン料理店は、
日本でもそれぞれ単独でたくさんできたので、
一般的にはギリシャ料理を中心に語られることが多く、
この日もムサカやグリークサラダを食べたが、
はじめて食べたモロッコの
「羊肉とプルーンの煮込み」がめちゃウメェ~。
甘いプルーンソースでトロトロに煮込まれた羊肉は、
まるで豚の角煮のごとしで、
これまで食べた羊料理の中でいちばん美味だった。
地中海料理は、健康長寿の食事法として、
日本でもよく知られるようになり、
「地中海ダイエット」なる言葉も生みだした。
その特徴は、野菜や果物、豆、ナッツ類、オリーブオイル、
全粒穀物、魚介類、乳製品がふんだんに使われていること。
さらにそれらを調理する際に使うスパイスの豊富さ。
スパイスと言っても、アジアンと違って、
辛い料理がほとんどないことも特徴かもしれない。
もう40年近く前だが、
当時のユーゴスラビアの首都ベオグラードから
殺人的な18時間すし詰め夜行列車に乗って、
ギリシャまで旅行したことがある。
おもにアテネとエーゲ海のロドス島を回ったが、
島で泊まった民宿の夫婦は、
なぜか「ギリシャのめしはうまくないだろ」と
僕に言ってた。
ギリシャ人は何でもかんでもオリーブオイルをかけるから
みんなオリーブ臭くなっちゃんだよ。
チーズだってヤギのミルクからつくるからおいしくないし、
パンもぱさぱさしているし。
と、妙に自虐的だったのを覚えている。
僕が日本人(当時は世界に冠たる経済大国)で、
イギリス(当時、ロンドンに住んでいた)から来たと
言ったので、そんな態度になったのだろうか。
今につながる西洋文明発祥の国の末裔なんだから、
もっと胸を張ってほしいなぁと内心思ったが。
しかし、彼らが「うまくない」と思っていた
オリーブ、ヤギのチーズ、全粒粉のパンなどが、
今や健康長寿食として重宝され、
ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。
「The MED」ではギリシャワインも飲んだが、
それより感動的だったのは「地中海ビール」である。
普段、ワイン党でビールなどあまり飲まないのだが、
このビールは違っていた、
日本のキレ、ニガ一辺倒のビールとはまったく別物で、
ほのかにフルーティーで、まろやかな感じ。
それでいながら甘く、べったりした感じはない。
長く記憶に残る香りと風味がある。
これを少ししょっぱい「おつまみオリーブ」と
いっしょに味わうと、
世界の果てから海風がさやかに吹いてくるようで、
体は吉祥寺のまま、気分はもう地中海。
ちょっとクセになるかもしれない地中海料理。
各国の多国籍な料理を試したければ、
「The MED」は超おススメ。
ほかに麻布十番と新宿歌舞伎町には
ギリシャ料理専門の店があるので、
機会をつくって行ってみたい。

生き方に悩む人のためのリアルな参考書 「鉄道マン発 映像調理師®」
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
AmazonKindleより好評発売中 ¥800
国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!
(あとがきより)
彼の祖父の時代は、日本を欧米諸国に負けない、
近代的な文化国家にすることが、国民共通の目標でした。
また、父の時代は、敗戦によって物も心も貧しくなってしまった
日本を復興させ、豊かな社会を築くことが共通目標となりました。
しかし、高塩さんや僕の世代になると、
祖父や父の世代のような、誰もが共有できる目標は、
もはやありません。
それに代わって、僕たちひとりひとりが、
生きる目標や生きがいを設定しなければならない
状況が訪れているのです。
これは日本のみならず、経済的な成功を成し得た、
世界の先進国すべてに共通する課題でしょう。
「人生百年」と謳われる未知の世界は、
豊かでありながらも、未来に希望を見出しにくく、
不安があふれる世界です。
ここでは、60歳の還暦は、
かつてのように人生の終わりを意識し始めるのではなく、
新しく生き始める年代といえるかもしれません。
インターネットの普及、AIの進化によって、
僕たちの子供世代、孫世代も平等に知識や情報を共有しています。
子供や孫たちと、さらにそこに加わるであろう
AIやロボットたちと、
どんな人生を送り、どんな社会を築き、
どんな未来をめざせばいいのでしょうか。
そのために、あなたの生きた証、活動の足跡は、どう生かされ、
のちの時代にどんな響きを残すのでしょうか。
もし、あなたが、高塩さんに終活映像や人生ストーリーの
制作を依頼する機会があれば、
ぜひ、過去の記憶とともに未来へ向けても想像力を広げて、
想いを盛り込んでください。
Deathフェスと有機還元葬のnanowaプロジェクト
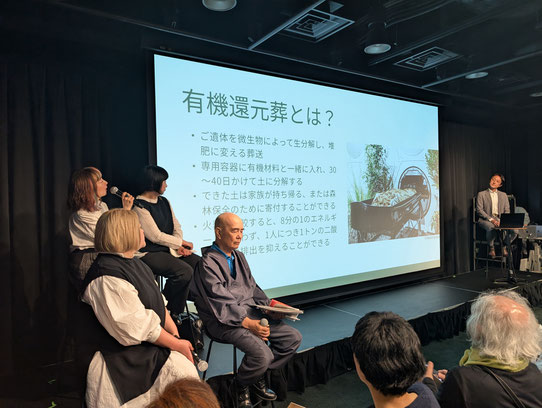
●私が死んだら、お花たちよ
そのむかし、1970年代のこと。
イルカが「いつか冷たい雨が」という歌を歌っていた。
イルカとは「なごり雪」を歌う、
あのフォーク歌手のイルカのことだ。
「いつか冷たい雨が」の歌詞のなかには
「いつか私が死んだら、お花たちよ、そこから咲いてください」
といった一節があったことを覚えている。
自分が死んだら花になる・木になるという
夢想を抱く人は少なくない。
最近の樹木葬の流行は、そんな人々の願いを反映したものだろう。
この樹木葬、見た目は確かに美しく、
「自然に還った」感があるが、
粉砕した遺骨を樹木のあるエリアに撒く・埋めるだけなので、
実際に亡くなった人の遺体を栄養分にして
植物が育つわけではない。
ところが、これを実践する葬法が欧米で普及し始めている。
それが「有機還元葬」、別名「堆肥葬」である。
遺体を土の中に埋め、微生物を使って分解し堆肥に変える。
イルカの歌のとおり、あなたが死んだら、栄養のある土になり、
そこから花が咲き、木が育ち、森にもなりますよ、というわけだ。
●神仏の道理に悖る新葬法の開発者たち
環境問題の影響から、欧米では2000年代頃から
地球環境に負荷をかけない葬法=遺体の処理方法、
つまり従来の土葬や火葬以外の方法が
いろいろ考えられてきた。
考える人たちは真剣だが、
それを伝えるメディアの報道の多くはキワモノ扱いで、
「ほら、こんな面白い、でもちょっと怖い人や会社がありますよ」
といったニュアンスが強かったように思う。
はっきりと決めつけるわけではないが、
当時、葬儀に関してはまだ伝統的な宗教を尊ぶ傾向が強く、
新しい葬法の開発者たちは、神仏の道理に悖る者ども、
人間の尊厳をないがしろにする罰当たりな輩と見られていたのだ。
それがこの数年、潮流が変わってきた。
インターネットが浸透し、AIが広まり、
時代が変わり、世代も変わり、
「土に還る」「地球に還る」という思いを、
たんなる夢物語でなく、リアルなものとして、
肯定的に捉える人が世界各地で、
特に若い世代の間で増えているのではないかと思う。
●世界で普及の兆しを見せる有機還元葬
「有機還元葬」はそうした新葬法の代表格で、
呼び方や細かいシステムは違えど、
アメリカとドイツで幾つものスタートアップ企業が、
すでにビジネスとして営業を始めている。
営業しているということは、イコール、
法的に認められているということ。
実際、この先駆者たちは自治体に対して、
何度も粘り強くプレゼンを続け、ついに認可を勝ち取った。
ワシントンで、ニューヨークで、カリフォルニアで、
アメリカに限って言えば、2025年4月時点で
およそ4分の1の州、計12州で合法化されている。
メディアも、もはやキワモノ扱いできない状況だ。
ワシントン州 (2019年)
コロラド州 (2021年)
オレゴン州 (2021年)
バーモント州 (2022年)
カリフォルニア州 (2022年、施行は2027年)
ニューヨーク州 (2022年、施行は2024年8月7日)
ネバダ州 (2023年)
アリゾナ州 (2024年)
メリーランド州 (2024年10月1日施行)
デラウェア州 (2024年)
ミネソタ州 (2025年7月1日施行予定)
メイン州 (2024年)
僕はコロナ前から仕事で新葬法に関する記事を書いており、
冒頭のイルカの歌を思い出し、
有機還元葬はなかなかいいんでねーの、
土より生まれて土に還る。
僕も終わりが来たら、地球の一部になりたいと思っていた。
しかし同時に、これらは海の向こうの話で、
日本では到底無理だろうとも考えていた。
自分や家族をまんま土に埋めて、微生物に食わせるなんて、
考えただけでおぞましく、ほとんどの日本人は
拒否反応を示すに違いないと思いこんでいたのだ。
ところが、この有機還元葬を実現しようと
動いている人たちがいるのを知って仰天した。
それも「できればいいね」といったレベルでなく、
本気中の本気なのだ。
●nanowaプロジェクトの活動
このプロジェクト「nanowaプロジェクト」は、
年内にまず動物で、実際に国内で有機還元葬を行う予定で、
学者・研究者や、ある有名企業も支援に動いているという。
ちょうど1か月前、「4月14日は“よい死の日”」と謳って、
渋谷ヒカリエで6日間、Deathフェスという、
死をポジティブに考えようというイベントが開かれたが、
そこでもトークセッションの一つとして、
「有機還元葬」のコンセプト、
そして実現に向けた活動について語られた。
反響は大きく、
日本でも有機還元葬(堆肥葬)への潜在的なニーズは
決して低くないようだ。
実現にはもちろん法整備が必要で、
かなり厳しいのではないと推測するが、
この国は前例さえあれば、特にそれが欧米のものなら、
意外とあっさりクリアできてしまう可能性もある。
少なくとも安楽死・尊厳死よりもハードルは低そうだ。
まさか、自分が生きている間に、
この葬法がこの国で実現するとは(まだしてないが)
思いもしなかった。
「nanowaプロジェクト」のスリリングな展開は、
これから注目に値する。
認知症になると、それまでの愛はどこへ行くのか?
母の日。
スーパーマーケットがいつも売っているデザートに
ポチっと赤いシールを貼り付けて、
「花より団子」の「母の日スペシャル」を
用意していたので、買ってきた。
「2個入りだけど、母の日だから、おかあさんは1個。
僕らは子供だから半分ずつね」と言っても、
何のことやらさっぱり認知しない様子。
だが、何か、普段あまりお目にかからないものが出てきた、
しかも自分の好物のカテゴリーに入るものだ、
ということは何となくわかるらしい。
けれどもやっぱり1個まるまる食べてしまっては悪いと思うのか、
半分残したので、僕とカミさんで半分ずつ食べる。
これは母の愛なのか?
そう言うと、カミさんは、
「わたしたちに恩を売っておいたほうが、
後から何かと有利だと算段しているんでしょ」
と、クールな分析をする。
親子ではあるが、この二人の相性はイマイチなようだ。
義母は時々、僕に対して「だーい好き!」と言って、
ベタベタ抱きついてくる。
たぶん、毎日、お菓子をあげて面倒を見るので
そうなるのかと思うが、相性はいいのかもしれない。
好きでいてもらったほうが、
ある程度、言うことを聞いてくれるので、
こっちとしては助かる。
デイサービスのスタッフに対しても、相性のいい・悪いはある。
以前、毎週土曜日の送迎に来ていた
Sさんという30前後の若い男性が、大のお気に入りだった。
その人はもう2年以上前に辞めてしまったのだが、
いまだにその記憶が残存しているのか、
土曜日の朝は概してご機嫌が良く、
なんとなくウキウキ感があるようだ。
待てど暮らせど、もうその人は来ないのだが・・・。
相性のいい人(波長が合う人)とは居心地の良さを感じる――
これも一種の愛情・愛着と呼べるものだろう。
時々、認知症になると人間が生きてきた中で
培った愛情なるものはどこへ行くのか?と考える。
親でも夫でも子供でも、
若い頃の恋愛の相手や友だちでもいいが、
人間、成長過程で誰かを愛し、愛されることで、
あるいは仕事や趣味などに愛を注ぐことで、
いろいろな関係を紡ぎ、人生を築いていく。
認知症になると、そうした愛の記憶は、ほぼすべて初期化され、
食欲などの本能的な部分と、
自分が安全に、有利に生活できるための打算が、
非言語されて内側に残る。
打算というと印象が悪いが、
これもまた生きていくための本能の一つなのだろう。
その一方で、幼い子供や動物を見て「かわいい」と感じたり、
花をきれいと感じたりする原始的な愛情は
ずっと消えるに持ち続けるようだ。
豊かな時代に生まれ育った僕たちは、
周囲にあふれかえる「愛」という言葉に洗脳され、
この得体のしれない概念に、過剰に期待する傾向がある。
人間には愛があって然るべき、
愛がなければだめ、人を愛せ、みたいな。
女と男の愛、家族の愛、至上の愛。
時はあまりにも早く過ぎ、喜びも悲しみもつかの間だが、
ただ一つ、愛の世界だけは変わらない――
昭和歌謡にそんな歌詞の歌があった。
でも、そんなことはないのだ。諸行無常だ。
愛の世界も変わっていくし、失われていく。
だがしかし、それはそう悪いことでも、
悲しいことでもないのかもしれない。
純粋でありながら、どこか邪で、ご都合主義的。
義母からは、人間のニュートラルな状態とは
「こんなもんよ」と教えてもらっているような気持ちになる。
ありがとう、おかあさん。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。
お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。