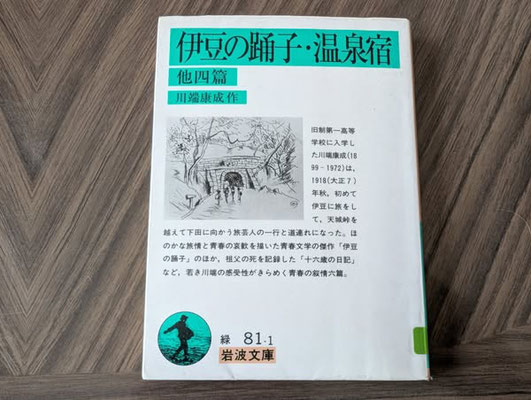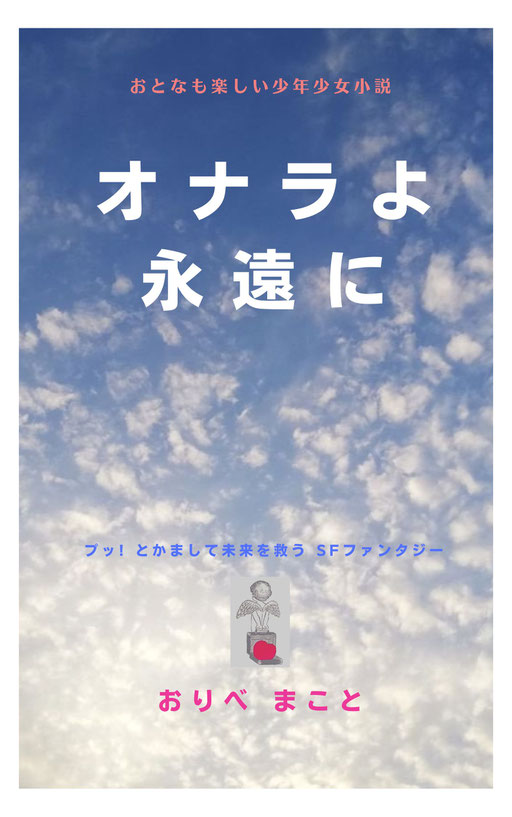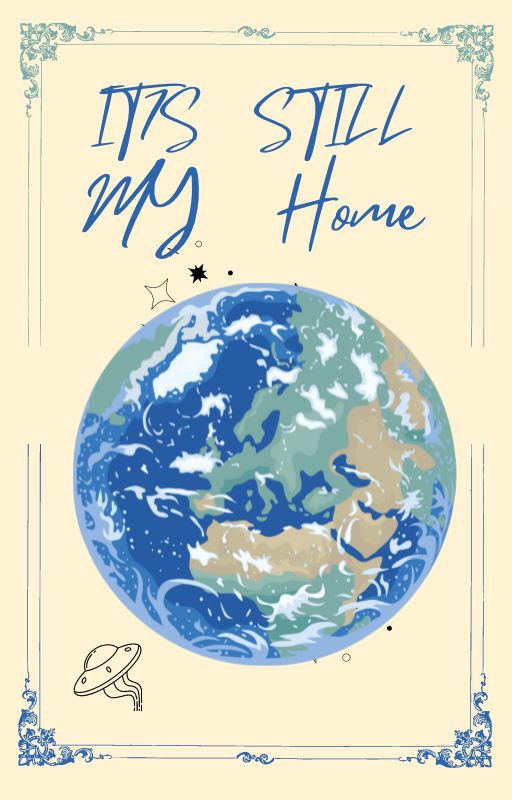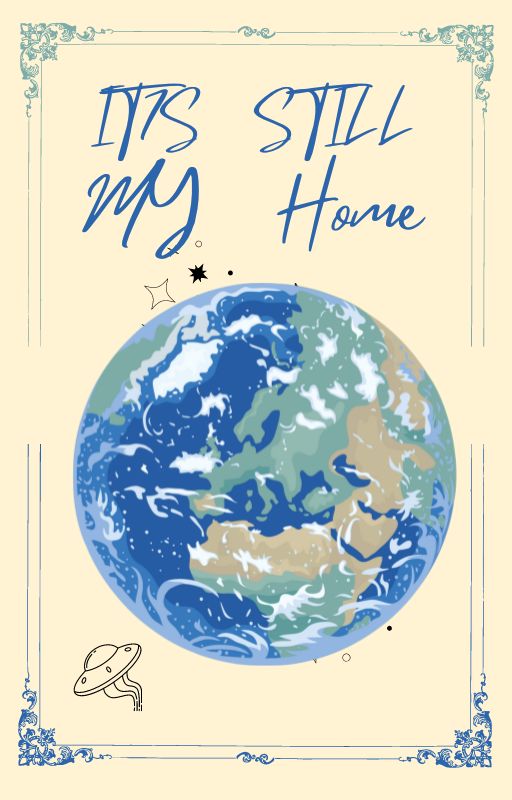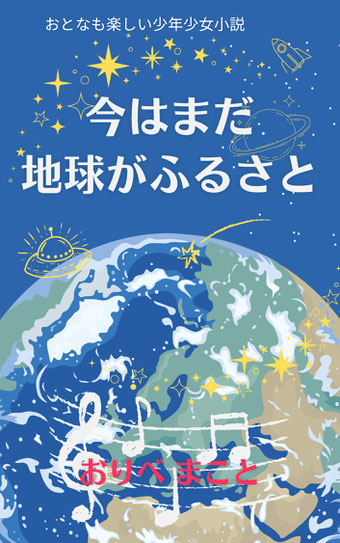- ホーム
- 電子書籍:おりべまこと劇場
- NEWS
- わたしの「わたしストーリー」
- 台本ライターとは?
- 実績:わたしの「しごとストーリー」
- サービスメニュー・料金プラン
- ブログ「台本屋のネタ帳」
- 仕事
- 生きる
- 食べる
- ロボット・AI
- 物語
- 歴史
- 世界
- 動物
- 音楽
- ビートルズ
- ドラマ・映画・演劇
- インターネット
- 本
- 台本
- エッセイ
- 子ども
- 2011年5月
- 家族
- エンディング
- 農業
- 旅
- 社会問題
- 昭和
- 認知症介護
- 広告
- 電子書籍
- 週末の懐メロ
- 2011年6月
- 2011年7月
- 2011年8月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年10月
- 2011年12月
- 2012年1月
- 2012年2月
- 2012年3月
- 2016年5月
- 2016年6月
- 2016年7月
- 2016年8月
- 2016年9月
- 2016年10月
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- 2017年6月
- 2017年7月
- 2017年8月
- 2017年9月
- 2017年10月
- 2017年11月
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- 2018年6月
- 2018年7月
- 2018年8月
- 2018年9月
- 2018年10月
- 2018年11月
- 2018年12月
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 新規ページ
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年4月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2020年11月
- 2020年12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- お問い合わせ
綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ
「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。
カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、
僕も土曜日に見たが、確かに面白い。
それにしても僕の中では、
綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、
そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。
役柄はもっと年上の設定らしいが、
もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。
そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの
スタッフも多くは40代
(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。
来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。
今や60・70代よりも40・50代のほうが
しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?
それどころか、20・30代も
「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。
どうやらがんばって終活するためには、
若いエネルギーが必要なのだ。
60・70代からじゃ遅すぎる?
いったいどうなっちょるんじゃ?
あっという間に1億総終活時代に突入だ。
「ひとりでしにたい」本当に面白いので、
観てない人は、NHKプラスで観てみてください。
電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」
無料キャンペーンは本日終了。
ご購入ありがとうございます。
よろしければレビューをお願いしますね。
山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識
なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」
小説(原作)と映画は別物。
それはそれでいいのだが、
そのギャップが大きければ大きいほど。
ツッコミがいがあって面白い。
「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は
その最たる例と言えるかもしれない。
川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、
映画にするなら、
全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。
それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、
その見せ場もいろいろ作る必要がある。
というわけで、この作品の場合は、
そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、
社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、
謎めいた演出が随所に散見される。
日本人の差別問題が裏テーマ
社会問題とは差別問題だ。
1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は
ちょっと遅れて日本にも及んだ。
70年代前半は、学生運動の挫折があり、
昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、
ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。
当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、
当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、
日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。
川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、
大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、
そうした日本人の差別意識が、
いかんともしがたい悪しき現実として、
随所にちりばめられている。
映画はそれらの材料をかき集め、
大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。
「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文
三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、
彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。
旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、
下賤な職業の人間として蔑視されている。
物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った
休憩所(だんご屋)の婆さんは、
旅芸人たちと親しげに話していたが、
学生に対しては
「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、
親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。
実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では
「あの人たちは今日の宿も決まっていない
(放浪者みたいなものだ)」と言っている。
映画ではこの婆さんの差別意識を、
いっそうあからさまに表現しているのだ。
セクシー少女・百恵の魅力の開花
なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、
「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と
一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。
彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。
これらは原作にはなく、この映画における演出である。
山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、
彼女の人気に火が付いたきっかけは、
シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、
当時ローティーンながら、
セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が
大ヒットしたからだ。
男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。
他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、
子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、
多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、
アイドル百恵の誕生につながった。
この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を
踏まえたものであり、
観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、
山口百恵の独特の、青い性的魅力を
うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。
ラスト1分 衝撃の不協和音
そして見せ場は最後の最後にやってくる。
学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。
見送りに来たのは、
かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、
船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、
大喜ぶで叫び、手を振り返す。
離れ離れになってはじめて
「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。
その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、
きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、
というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。
叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が
唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。
え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。
かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。
ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。
しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。
ひきつりながらも笑顔を保ち、
懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。
最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、
ストップモーションになってエンドマークが出るのである。
なんとも奇妙で、
まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。
なぜラストショットが、
若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、
汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?
夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。
ととでもメッセージしたいのか?
せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、
このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、
怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、
50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。
あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を
ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。
船が出る前、学生は地元の土方風の男に、
3人の幼子を連れた婆さんを
上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。
現代ならとんでもない無茶ぶりだが、
大正時代、エリートたるもの、
こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、
みたいな空気があったようで、
彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。
そして踊子との別れを終えた後、
伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、
東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて
彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。
当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、
庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、
立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、
そんな前向きな感想を持っただろう。
ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、
少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、
古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。
本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、
まだ読んだことがない人はぜひ。
そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、
豊かになった昭和日本で、
この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、
令和の世からタイムトラベルして、
若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。
映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子
伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした
(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、
ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。
アマプラで1974(昭和49)年公開の
山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。
僕が中学生の時に公開された映画で、
当時大きな話題になっていた。
しかし当時、中二病にかかっていた僕は
「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」
と言って無視していた。
しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」
なんて映画は観に行った覚えがある。
山口百恵のファンだった試しはない。
「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、
少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、
僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。
中高生がアイドルに求める
可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが
大きな要因だったのではないだろうか。
同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、
むしろ女子の方に人気があった。
しかし今、この齢になって観ると、
唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。
この映画は女優として初出演作でもあるので、
演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、
明るさと陰とのバランスが素晴らしく、
この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。
●「え、はだか?」ではありませんでした
物語中、温泉に入っていたかおるが
学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって
裸で手を振るシーンがあるが、
そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。
最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、
いきなりグイっとカメラが寄る。
そして「え!?」と思う間もなく、
1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。
「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、
やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。
そりゃ当然だよね。
●「旅情」「異文化体験」を描いた原作
そんなわけで原作と並行して観たので、
小説との違いに目が行った。
俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い
「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を
リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。
もちろん、主人公の学生が旅先で出会った
芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が
メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。
少女を描くことに固執し、
ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、
この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、
恋愛的感情の表現はごく薄味だ。
そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ
「伊豆の踊子」が、
老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。
人物描写や風景描写などがイマイチで、
文学作品として未熟な部分も、
却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、
つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。
そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。
今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、
旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、
この物語の舞台である100年前は、
東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。
作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには
うってつけの場所だったのだと思われる。
そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う
旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。
「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが
圧倒的多数を占めていた、大正日本における
エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。
●河原乞食という現実
先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。
明治維新以降の近代日本では、
こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、
それはあくまで建前上、表面上のもので、
庶民がしっかり理解していたとは言い難い。
人々の心情に根付いた差別意識は、
まだ江戸時代のままだったのだ。
芸能人はどんな大スターだろうが、
すべからく「河原乞食」である。
原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)
という立札が出てくる。
この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、
旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。
川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、
ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。
踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、
こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。
とはいえ、川端は差別を告発しようと、
この作品を書いたわけではない。
あくまで旅で出会った現実の一つとして、
さらっと流している感じである。
クリエイティビティを刺激した山口百恵
この立札は原作では後半、終わりに近いところで
「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、
この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、
立札も物語が始まって間もないところで現れ、
かなり強い印象を残す。
まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。
かなり意図的なものと思われるが、
その背景として、おそらく当時、
社会改革の余波で部落問題などに焦点が
当たっていたことがあるのだろう。
また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、
日本の映画人も多かれ少なかれ、
社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。
それで監督や製作陣が、
単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、
と考えたのかもしれない。
山口百恵という稀有な素材は、
そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。
吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、
百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、
昭和の高度経済成長期以降の
「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、
現代にまで残る傑作にしたのだ。
映画の話、さらに次回に続く。
「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台
伊豆の河津に行ったのは先週だが、
駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。
それで初めて河津が、かの日本文学の名作
「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。
主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、
今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。
ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も
河津町だ。
いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、
そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、
生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。
おどろきの踊子
いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が
なんとなくどこかから耳に入ってきて、
知ってるつもり・読んだつもりになっている。
僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、
スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。
そして正直、びっくりした。
え、これだけ?って感じ。
文庫本でわずか40ページ。
字数にして2万字あまりの短編で、
30分ちょっとあれば読めてしまう。
旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで
けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、
ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。
どうしてこんなすぐ読める物語なのに、
俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、
自分の人生を後悔してしまった。
でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。
100年前の変態ロリコンじいさん
ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。
なんといっても「世界のカワバタ」。
ノーベル文学賞を受賞した、
敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、
その幻想もガラガラと崩れ去った。
今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。
「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、
最近の川端康成の定番像のようだ。
踊子へのエロい思慕
そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、
この「伊豆の踊子」の物語も、
なんとなくエロっぽく読めてしまう。
主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。
いわば川端の分身みたいな人物だが、
それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。
大学生が中学生に――ということなので、
今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、
ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)
全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が
メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、
いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、
頭がくらくらしてくる。
わずか40ページの短編のなかに、
こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、
日本文学の名作、それどころか世界名作としても
親しまれているゆえんなのかもしれない。
そう考えると、100年前の日本の文学界、および、
世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、
みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった
のではないか?という疑念にとらわれる。
いい加減だから名作になった?
正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、
そんなに中身のある話ではない。
話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。
物語としてはかなり薄味である。
川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、
もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、
旅芸人の一座との交流の部分を、
何年後かに抜き書きしたものらしい。
いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの
ノベライズなのである。
また、川端は、この作品では
「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。
でも、この作品の場合、その「さらっと感」
「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。
発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。
まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、
日本人のハートをわしづかみにした。
川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、
6度にわたって映画化された。
映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、
その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。
「女が箸を入れて汚いけど」
なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、
かなり深く心に刺さった部分もある。
それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。
100年前、旧制一高の学生と言えば、
日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。
対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。
さらにその中でも女は一段身分が低く、
一座のリーダー役の「おふくろ」は、
(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、
(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、
二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。
(川端が言わせている)
現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界
江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は
どんなに人気があろうとも被差別民であり、
身分制度の埒外の存在、
つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。
それは徳川幕府が、町人や農民に
「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、
できるだけ不満を抱かせないようにするための、
狡猾な支配構造をつくったからだ。
その意識は明治になって近代化された以降も、
えんえんと人々の意識に残った。
そういう意味では100年前、
大正から昭和になったころの日本はまだ、
現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。
モモエ踊子は差別問題を強調?
小説を読んだ後は、映画も見た。
1974年、昭和49年に公開された、
三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。
これも今に至るまで気が付かなかったが、
このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で
「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。
今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。
その話はまた次回に。
雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面
前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、
河童伝説の顛末を紹介したが、
いよいよ後編では本丸である。
住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、
快く承諾してくれた。
住職が大切そうに持参したのは、
見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。
よく見ると表面がややぼこぼこしており、
いかにも古い時代の手作り感が漂っている。
蓋は何度か作り変えられているそうだが、
壺本体は実に700年以上前のものだという。
「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」
住職がひっくり返すと、
底には「祖母懐」という文字が刻まれている。
●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産
「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。
これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、
温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。
愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、
そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。
さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。
「加藤四郎左衛門景正」
これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。
加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、
一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、
帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。
現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、
景正を祀った「陶彦社」が存在する。
「本物なら国宝級の品物です。
ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、
鑑定などしてもらったことはありません」
住職は笑いながら説明してくれた。
「河童からもらいました」と言えば、
鑑定士はどんな顔をするだろう?
そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら
どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。
さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、
粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。
そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、
焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが
四郎左衛門の作風だったそうだ。
確かに、目の前の壺も実に味わい深い、
野趣に富んだ風合いを見せている。
●いよいよ河童のせせらぎ体験
「河童はこれを置いていくときに、
『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。
これを聴いて私を思い出してください。
この川の音が聴こえる限りは、
私はどこかで元気に暮らしていますから、
和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」
住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。
果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?
「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、
ぼーっという音は聞こえるものなんです。
それは容器の中で風が流れる音で、
貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、
お分かりかと思います。
しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、
下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、
小さな水が流れる音がします」
住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。
最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。
しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!
確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが
聞こえてくるではないか。
まさに小川のせせらぎのような、
優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。
思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。
やはり聞こえる。確実に水の音である。
正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。
●プロの最新機材で録れなかった音が、
子供のラジカセで録音成功
住職によると、この不思議な音を録音しようと、
NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。
しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。
「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、
ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」
なんとも不思議な話である。
最新の録音機材では録音できないのに、
子どものラジカセでは録音できる。
まるで河童が、純真な心を持つ者だけに
水音を聴かせてくれるかのようだ。
試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。
すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。
後で家に帰って聞き返してみると、
確実にせせらぎの音が記録されている。
超うれしい!
これは一体どういう現象なのだろうか。
科学的に説明のつく現象なのか、
それとも本当に河童の仕業なのか。
真相は定かではないが、確実に言えるのは、
この壺から不思議な音が聞こえるというのは、
真実であるということだ。
●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告
住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。
豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、
壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、
洪水を予告してくれるのだそうだ。
「今でも川の音が聞こえるのですが、
河津川の水位が上がりそうな時など、
壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」
これは確かめようがなかったが、
もし本当だとすれば、
河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、
災害から人々を守り続けてくれているということになる。
●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー
ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。
「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。
ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、
と思いを巡らせることができます」
その上で住職は、禅宗の根本的な教えである
「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。
「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。
これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、
それに惑わされてしまうという教えです。
実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、
例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、
肌で感じたりすることで、
現実には目に見えないものに思いを馳せたり、
いろいろな想像・連想ができたりする。
そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」
なるほど、これは深い話である。
現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、
さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、
僕たちはそれらに振り回されがちだ。
しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。
むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、
真実が隠されているというのだ。
「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、
自分で感じなさいという教えです。
現代社会では、テレビやインターネットを通じて
文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、
皆さん惑わされますから。
こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と
想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、
という教えが、
この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」
●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心
住職はさらに続けた。
「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、
もともと仏の心を持っています。
ところが、現実の社会で生きるうちに、
心にたくさんの垢がこびりついてしまう。
真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」
これも禅宗の重要な教えの一つである。
すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。
しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、
先入観といった「垢」が心に付着してしまう。
その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。
河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。
現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、
僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。
「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、
実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。
昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。
ですから、そんな中で、こうした体験をすると、
より心に響くのかなと思います」
確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。
現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、
素朴で自然な美しさがそこにはある。
そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、
日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ
河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、
僕は深く心を動かされた。
これは単なる音響現象以上の何かがある。
人はみな心に仏性を持っており、
それによって、せせらぎの音を聴くことができる。
虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、
こてはとても大切な体験であるように思える。
SNSで飛び交う断片的な情報、
ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、
AI生成による真偽不明の映像や音声、
誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--
僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。
そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、
本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。
そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
僕たちに大切なことを思い出させてくれる。
文字や人工的な情報で表現できない真実が、
この世界にはあるということ。
そして、その真実は五感を通じて、
心で感じ取るしかないということを。
●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心
この河童の壺の音について、
科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。
壺の形状による音響効果なのか、
それとも何らかの物理的現象なのか。
しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、
実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。
大切なのは理屈ではなく、
その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。
最新の科学技術よりも、
純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。
河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、
この音を聴く時、
僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。
河童が実在するのかどうかは問題ではない。
大切なのは、その存在を通じて、
自然との調和や他者への慈悲といった
大切な価値を思い出すことなのだ。
●あなたの心の中の河童に出会うために
700年という長い年月を経ても、
河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。
伊豆に来たら、河津に来たら、
ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。
ただし、河童の壺を体験したい場合は、
この壺が寺宝中の寺宝であるため、
必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。
そこで、あなたも河童の封じ込めた
せせらぎの音を聴いてみてほしい。
音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。
日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。
もし音が聞こえたなら、
それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。
そして、河童という架空の存在を通じて、
自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を
思い出すことができるだろう。
あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。
そして河童が、
人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。
文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、
河童の壺が奏でるせせらぎの音は、
きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。
(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺
今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある
「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を
訪ねることになった。
JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。
駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が
目の前に広がる。
あいにくの小雨模様だったが、
河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、
これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。
ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。
むしろこの雨模様のほうが、
なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、
まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。
●椅子まで河童という油断のならない境内
境内に入ってまず驚かされるのは、
とにかくあちこちが河童だらけということだ。
持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、
よく見ると河童の形をしていた。
思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。
寺院としては日本的な古さを感じさせる、
いかにも由緒正しそうなお寺だ。
と同時に、どこか懐かしい感じもする。
よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に
境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。
これは後で知ったことだが、
ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが
なせる業なのだ。
●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年
「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、
実に700年の歴史を持つ古刹である。
その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。
開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である
徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、
なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。
徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、
二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の
大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。
その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、
帰国後は各地の名刹を歴任した。
そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。
興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という
真言宗の寺があったということだ。
それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。
「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)
という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、
深い意味を込めた名前である。
●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割
現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。
「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、
河津桜で有名になる前--
昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」
今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、
桜まつりが始まったのは今から34年前の
1991年(平成3年)のこと。
桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える
大イベントに成長したが、
それ以前は河童が町の看板だったのである。
「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、
商工会に飾られていたりしたんです。
でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、
そういったものを寺で預かったんです」
なんとも皮肉な話である。
河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、
河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。
そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を
果たすことになったというわけである。
●「つくったが、作られていないように」のアート美学
現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。
「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」
ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。
人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、
まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、
「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、
心憎いばかりだ。
書家の師範のスタッフもいるということで、
寺院としての格式を保ちながらも、
現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。
●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー
以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、
町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、
昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、
一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。
「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、
住職は苦笑いを浮かべながら、
「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。
●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人
さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。
それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。
昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。
お寺の裏に位置するその場所は、
川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。
この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、
いろいろないたずらをして村人を困らせていた。
そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか
「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、
村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。
なんとも人間らしい話である。
最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。
●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童
そして運命の日がやってきた。
ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。
そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。
そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。
よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。
「河童だ、河童がいるぞ!」
誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。
河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、
裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。
ここでの河童の行動が実に人間臭い。
馬のしっぽにしがみつくという、
なんともマヌケな状況で発見され、
慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。
●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑
しかし村人たちは容赦しなかった。
井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。
河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、
井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。
村人たちは河童を取り囲み、
「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、
棒切れで叩き始めた。
ちょっとやりすぎな気もするが、
当時の人々にとって河童は子どもを攫う
恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。
●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命
ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。
村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、
河童が息も絶え絶えに倒れている。
それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。
和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。
「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。
寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」
さすがは禅僧である。
暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、
慈悲の心で河童を救おうとした。
村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、
和尚さんの言葉に従って河童を預けた。
●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し
和尚さんは村人たちがいなくなると、
「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」
と言って、河童を逃がしてやった。
この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。
その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で
目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。
すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。
●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺
河童は言った。
「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」
そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。
「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。
口に耳を当てると、水の流れる音がします。
水の音が聞こえたら、
わたしがどこかで生きていると思ってください。
和尚さまもどうぞお元気で」
そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。
●令和の今も、壺に耳を当てれば
和尚さんは夢心地で聞いていたが、
我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、
河童が本当に来たのだと確信した。
それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、
村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。
けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、
底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、
河童の無事を思った。
また、河津川に出水があった際、
このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、
人々が助かったこともあり、
それから寺の宝として大切に奉られてきたという。
今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、
河童が元気で生きていることを伺える。
そして人々は水の流れが心を洗うと言い、
ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~
さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、
実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。
果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが
聞こえるのだろうか。
後編では、この神秘的な河童の壺による
不思議体験をレポートする。
僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、
数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を
体験することになるのだが、
その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。
後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、
そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。
(後編に続く)

岸辺露伴×水の都ヴェネチア
「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、
「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。
「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。
人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、
オールヴェネチアロケ。
映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。
テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、
ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。
主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、
そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。
それによって事件を解決していくストーリーだ。
原作のマンガも全く知らないが、
高橋一生は超ハマり役だと思った。
舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。
ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、
幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。
年中、観光客が押し寄せていると思うが、
いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、
人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、
歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。
僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、
ヴェネチアにも訪れたが、
見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。
それは当たり前で、
この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。
世界遺産になった宿命みたいなものである。
車はもちろん、自転車も街の中に入れない。
観光客がわんさか来るのだから、
スタバやマックなどの店もありそうだが、
少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。
そうした規制も多いはずだ。
オーバーツーリズムを避けるため、
街に入るための入場料徴収も検討されているという。
世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、
僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。
一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、
僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に
奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、
どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。
ヴェネチアはその最たる街だ。
さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような
スケールの都市ではなく、
せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。
そこに独自の文化が集約されている。
観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、
実際の観光収入はそんなにないのではないか。
ヴェネチアを舞台とした映画で、
ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)
という作品があった。
そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、
たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、
ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、
普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、
ゴンドラやボートに乗ったり、
写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。
僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、
多分そうしたのだと思う。
それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが
あるのだろうか?
観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、
この街の住人たちがどうやって暮らしているか、
庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、
ひどく気にかかる。
この岸辺露伴の映画も、
けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、
人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。
それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、
とても心に残った。
地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。
この風景はいったいいつまで見られるのだろう?
スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」
一昨年、としまえんの跡地にオープンした
「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。
正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京
‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。
約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る
ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。
●見どころ満載6時間ツアー
映画ハリー・ポッターシリーズや、
ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の
舞台裏を体験できる。
映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、
実際に撮影で使われた小道具などが展示され、
視覚効果を使った体験型展示もある。
初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、
音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。
かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも
満足のいくツアー。
6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。
施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。
映画ハリー・ポッターシリーズは、
ほぼ2000年代に制作されており、
CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。
その分、アナログ的というか、
昔ながらの手作りの部分も残っていて、
セットや小道具などの作りこみがすごい。
魔法学校の教科書など、映らないページまで
しっかり書き込まれており、
映画スタッフの間で受け継がれてきた
「魂は細部に宿る」の精神が生きており、
職人的な意気込みが伝わってくる。
でも、こういう部分は果たして、
今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?
コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?
「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。
映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。
そんな言い方もできるのかもしれない。
●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも
というわけで、このツアー後、
アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで
全8作を一気見した。
(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)
主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、
映画各話のトーンが変わっていく。
第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、
ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる
中盤から後半にかけて、
ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。
そして、やっぱり最終作における謎解き――
ハリーの運命をめぐる、
ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。
何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、
演者の子供たちが青年に成長していく過程は、
さすがに機械では実現できない。
それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、
やはり空前絶後の作品だろう。
こんな作品は二度と作れない――
と思っていたら、
何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。
キャストはもちろん全とっかえ。
(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)
映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、
出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。
製作はすでにけっこう進行していて、
今年の夏には撮影開始予定とのこと。
製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。
1作につき1シーズンで、最低7シーズン。
後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。
いずれにしても10年スパンで、
映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。
この時代にすごい構想だ。
「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。
このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。
どうしても映画版と比較してしまうだろうが、
かなり楽しみにしている。
小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。
今また、唐十郎 襲来!
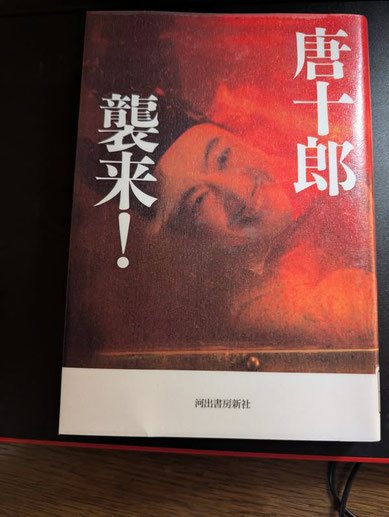
かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。
昨年11月に出された追悼本
「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。
現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している
評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。
同氏を含め、30人以上の人が、
それぞれの「唐十郎体験」を、
証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、
様々な形の文章で語っている。
中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。
もちろん、過去の原稿を転載したものだが。
あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、
あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。
蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、
二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。
唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。
●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏
特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として
長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、
まだインターネットがなかったので、
この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、
良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、
事実を大いに誇張した伝説として語られていた。
1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、
寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、
そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――
しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった
アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、
当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、
途方もないスケールとエネルギーを持った、
天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。
不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、
ほほえましい思いになった。
特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――
という話には笑ってしまった。
昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、
一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。
李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、
唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、
ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。
そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、
今の自分を支える柱の一つになっている。
●久保井研のインタビュー:
後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル
現在、座長代行・演出として唐組をまとめる
久保井研のインタビューもよかった。
彼と編集者・樋口との対話で、
状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を
創作活動の根源にしていた唐十郎が、
唐組として再出発するにあたり、
「新しいメディアによる新しい現実を描き、
豊かさの中で右往左往する人間を描く」という
手法に切り替えたという話は、とても興味深い。
過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、
テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、
唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。
どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、
パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。
唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、
半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。
●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点
そして、もう一つ感動的だったのが
「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、
明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。
1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、
彼らの明治大学実験劇場は、
都市の中での演劇に距離を置こうと、
茨城県の農村に地方公演に出かける。
都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、
どのように芝居をやり、何を得たのか?
タイトル通り、「唐十郎の原点」が、
まるで昨日のことのように鮮やかに、
朴訥な文章でつづられている。
最後のほうは読みながら涙してしまった。
本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、
生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、
後進に受け継がれた。
1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。
あれから1年。
永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍
認知症のおかあさんといっしょ2
5月6日(火)15:59まで
無料キャンペーン開催中。
もくじ:
・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族
・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉
・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?
(ほか 全36編採録)
21世紀の「傷だらけの天使」(小説版)をどう読むか?

「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」は、
作家・矢作俊彦が2008年に出した小説(講談社文庫)である。
題名で察しがつくように、これは「傷だらけの天使」の小説。
30年後の後日談だ。
今年になってからAmazpn Primeで
「傷だらけの天使」全26話を見た僕は、
頭の中で、かつての傷天熱が再燃。
いろいろネットで情報をあさり、書籍として出版されている
解説本「永遠なる『傷だらけの天使』
(山本俊輔・佐藤洋笑/集英社新書)」を、
そして、この小説を読んでみた。
●1か月近く書けなかった感想
あの衝撃の最終回でラスト、
いずこともなく去った小暮修(萩原健一)は、
30年後、どうなったのか?
それを描いた物語となれば、
傷天ファン、ショーケンファンなら、
興味を持たずにはいられないし、ぜひ読むべき作品である。
……と言いたいところだが、
同時に「読まないほうがいいよ」とも言いたくなる内容である。
思い出は思い出のまま、大事に取っておいたほうがいい。
昔の恋人にはもう一度会おうなんて思わず、
かつての美しい面影だけを抱きしめていたほうがいい。
正直、そんな心境になってしまった。
これを読み終えたのは3月末だったが、
どんな感想を書けばいいのか、うまく整理がつかず、
かれこれ1か月近く経ってしまったのは、そのせいだ。
●トリビュート小説の傑作だが
誤解がないように言っておくと、
「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」が、
読むに堪えない駄作というわけではない。
むしろその逆で、これは傑作だと思う。
探偵小説、ハードボイルド小説、エンタメ小説、
どの呼び方が一番いいのかわからないが、
とにかく、こうしたジャンルにおいて、
構成、文体、表現、リズムなど、
相当質の高い作品であることは確かだ。
作者自身が傷天ファンであり、
読者も完全に傷天ファンを対象としているので、
原作ドラマに対するリスペクトも十分すぎるくらい十分。
たとえば冒頭部分は、僕たちがこぞってマネをした、
あの伝説的なオープニング朝食シーンの
完全なオマージュになっている。
同時に、30年後、55歳になったオサムの現状を
ビビッドな表現で読者に伝える始まり方になっており、見事だ。
この冒頭部分が象徴するように、
トリビュート小説として非常によくできており、
いちいち納得できる。
しかし、だからこそ、この物語が、
多くの傷天ファンに与えるダメージ(?)も
大きいのでないかと思う。
少なくとも僕にとってはそうだった。
●萩原健一と市川森一の置き土産
1974年秋から1975年春にかけて日本テレビ系で放送された
「傷だらけの天使」は、
当時、その圧倒的存在感で人気を誇った俳優・
萩原健一を主役にした、
コミカルさとハードボイルドテイストと
人情味を併せ持つ探偵ドラマで、
斬新な内容・演出と、日本映画界を代表する監督らが参加した
「テレビ映画」として話題になった作品だ。
視聴率は振るわなかったが、
その「カッコ悪いカッコよさ」「ろくでなしの生き様」は、
当時の若者たちの心にずっぽり突き刺さり、
大量のファンを生み出し、半世紀を超えて続く伝説となった。
そうしたファンの一人である作者の矢作俊彦は1950年生まれ。
まさしくショーケンと同級生である。
彼はこの作品の執筆に際して、
主演の萩原健一と、脚本家の市川森一から承諾を得ている。
市川は登場人物やドラマの世界観の設定をつくり、
26話中、8つのエピソードの脚本を書いた、
脚本陣のメインライター。
いずれも「傷天」を代表する傑作で、
第1話(制作側の都合で放送時は第7話になった)と最終話も
彼のペンによるものだ。
市川は2011年、萩原は2019年に他界しているので、
「魔都に天使のハンマーを」は、傷天の核ともいえる二人が、
矢作に託して残した、置き土産ともいえるかもしれない。
市川は1983年に同名の脚本集を大和書房から出しているが、
その後、何度も傷天復活の話があったらしい。
しかし、幸いなことに(?)、それらは実現しなかった。
制作上の都合もあったかと思うが、
ファンも齢を取った萩原がオサムを演じる姿は
見たくなかっただろう。
そして、萩原以外の俳優がオサムを演じることも
許せなかっただろう。
●小説の世界だから許される30年後の傷天
しかし、小説の世界――僕たちの想像力の範囲でなら、
それは許される。
キャラクターの描写は的確で、
修が話すセリフの文字からショーケンの声が聴こえてくる。
僕たちは、この物語の中で「55歳の小暮修」と出会えるのだ。
それは他のキャラも同じ。
ここには、オサムがヤバい仕事を請け負っていた、
探偵事務所のボス・綾部貴子も、
その右腕として活躍していた辰巳五郎も出てくる。
最終回で横浜港から外国へ逃亡した貴子は、
もはや探偵事務所の経営者などではなく、
六本木ヒルズを根城とする組織のトップとして、
2000年代半ばの日本の政治・経済・産業界を牛耳る
フィクサーとなっている。
同じく横浜港で逮捕された辰巳は、
あの時、貴子に裏切られたのにも関わらず、
相変わらず手下として、舞台裏を跳梁跋扈している。
どちらも年齢設定は還暦をとっくに超えて
70代ということになるが、
超高齢化社会で、
いまだに昭和のジジババが幅を利かす日本においては、
何ら違和感がない。
それぞれの役を演じた岸田今日子・岸田森も、
すでにこの世を去っているが、
ここも想像力を駆使して、加齢し、より妖怪化した
二人の声を被せて読むといいだろう。
●アキラへの想い
そして、物語の中で絶大な存在感を感じさせるのが、
オサムの弟分の乾亨である。
しかし、アキラはドラマの最終回、つまり30年前に死んでいる。
もちろん生き返って登場するわけではないが、
彼はオサムの中でずっと生き続けており、
ことあるごとに心の底からよみがえってくるのだ。
文字通り、天使になったアキラへの追憶。
若かりし時代の、宝のような思い出と、
あの時、彼を見捨て、死なせてしまったという罪悪感。
それがこの物語の軸の一つになっており、
随所に現れる、ドラマから引用したアキラのセリフを読むと、
若き水谷豊のあの声と独特の言い回しが響いてくる。
(断じて、現在の、杉下右京の水谷ではない)
● 在りし日のエンジェルビルも
それぞれのキャラクターとともに、
世界観もきちんと踏襲しており、
オサムが住処としていたペントハウスも、
舞台の一つとして出てくる。
やはり傷天にはペントハウスが欠かせない。
このペントハウスのロケ地として使われた、
代々木駅近くの代々木会館ビルは、
傷天ファンの間で「エンジェルビル」と呼ばれ、
この小説が出版された当時は「不滅の廃虚」として、
まだ健在だった。
オサムだった萩原が亡くなったのが、
令和が始まった2019年3月。
このエンジェルビルが解体されたのが、同じ年の8月。
単なる偶然だろうが、ファンとしては
何らかのつながりを感じたくなる。
●1970年代と21世紀ビギニングとの融合
そんなわけで原作の世界観に忠実に……と言いたいところだが、
あくまでこちらの時代設定は、ゼロ年代半ば。21世紀の物語だ。
30年が過ぎ、もう世界は変わっているのに、
1970年代と同じ世界観で描くのは、逆にウソになる。
作者はそのあたりも心得ていて、
バーチャルワールドや生殖医療などの要素も入れ込んでいる。
1970年代には、ほとんどSF小説・SF映画に出てくるものが、
ここでは現実として違和感なく描かれており、
かつての傷天を、21世紀の物語としてシフトさせているところは
心憎い。
しかも、ゼロ年代半ばといえば、
まだデジタル社会への移行の途上で、
インターネットが今ほど社会に普及しているとは言い難く、
スマホも世のなかに登場していない。
そうしたなかで、こうした要素を駆使して描いたのは、
かなり先進的だ。
●残酷な結末
僕が最初に「読まないほうがいいよ」と言ったのは、
この「21世紀の傷天」の物語世界を形作る
キーマンが存在するからである。
それは貴子でもなければ、辰巳でもない。
他の新たな登場人物でもない。
それは原作ドラマを知る者なら、誰でも知っている人物だ。
物語の終盤、その人物とオサムとの、
二人きりの対決のシーンが描かれる。
まるで目の前で、
あの傷天のアクションが展開されているような見事な筆致。
しかし、そのシーンで、それまでのすべての謎が解け、
物語の文脈が明らかになると、
そのあまりの運命の残酷さに慄然とする。
原作のメインライター市川森一が、ドラマ作りの信条としていた、
とびきり賑やかで楽しい夢と、
奈落の底に落ちるような現実とのコントラスト。
矢作俊彦は、この後日談でも、それをしっかり踏襲した。
55歳になったオサムが、
最後に何と向き合わなくてはならなかったのか。
誰と闘わなくてはならなかったのか。
当たり前のことだが、30年もの月日が経てば、子供は大人になる。
これだけ言えば、原作を知る人は、もうピンと来るだろう。
粗野で風来坊のように生きてきたオサムだが、
彼は家族を大事にする男でもあった。
しかし、彼はそのかけがえのない家族に裏切られてしまう。
「魔都に天使のハンマーを」は、家族の物語でもあるのだ。
読み終えた後、僕は原作の様々なシーンを思い出して、
思わずため息をついてしまった。
そして、やるせない気分に覆われた。
すべて辻褄が合い、すべてが納得できる内容である。
この後日談を、一級のエンタメ小説として構築するためには、
こうするのが最高の手立てだったのだろうと思う。
でもなぁ、こうなるなら、
もう少しダメダメな話でもよかったよなぁと思ってしまった。
最後の最後に、ほんのちょっとした救いはあるんだけど。
●ショーケン死すとも傷天死なず
というわけで、長々と書いてしまった末にもう一つ気付いたのは、
傷天の30年後を描いたこの作品は、
もう20年も前に書かれたものだということ。
この20年の間にまた時代は変わった。
萩原や市川をはじめ、傷天関係者は相次いでこの世を去った。
エンジェルビルも代々木から姿を消した。
でも、その代わりに、U-NEXTやAmazon Primeなどの動画配信で、
多くの世代が、半世紀前の、
若かりしオサムとアキラの活躍を見られるようになった。
物語のなかで55歳になっていたオサムは、
もう後期高齢者の仲間入りをしている。
貴子や辰巳は90代になるだろう。
それでも超高齢化社会では、
この物語はまだ続くのではないかと思わせる。
傷天伝説の一部となった「魔都に天使のハンマーを」。
最初に「読まないほうがいいよ」と言っておきながら、
今さらだが、勇気を出して読んでみることをおすすめする。
青春の思い出の湯に浸るのは気持ちいいが、
やっぱりそれだけだと、今を生きることにはつながらない。
今を生きて、傷天を未来に伝えていきたい。
ショーケンが死んでも、「傷だらけの天使」は死なない、きっと。
魔都・横浜から遠く離れて
1975年のドラマ「傷だらけの天使」の最終回では、
修(萩原健一)が、姿をくらましたボス・
綾部貴子(岸田今日子)を探しに
横浜・中華街を訪れるシーンがある。
映像に映し出された、当時の中華街は、
いかにもヤバそうな街で、あちこちに密航の手続きを請け負う、
中国人のアンダーグランドビジネスの巣窟がありそうな、
魔都のにおいがプンプンしていた。
50年後の今、中華街はきれいに整備された観光地となり、
子供も大人も、日本人も外国人もみんな、
豚まんやら、月餅やら、チキンを平たく伸ばした台湾から上げやら、
イチゴとマスカットのミックス飴やらを食べ歩きして、
わいわい楽しさと賑わいにあふれている。
50年前のドラマの世界と現実とのギャップは大きい。
洗練された街、そして、
それを作り守っている地元の人たちに
ケチをつけようなんて気はさらさらない。
けれども、やっぱり、こうした見かけの繁栄と、
幸福感が希薄な日本人の内なる現実との
ギャップを考えると、もやもやした疑念が胸に湧き上がってくる。
「50年前よりほんとにこの国はよくなったのか?」と。
人も街も、化粧することが上手になった。
汚いものを包み隠すのがうまくなった。
それがいいこと何か悪いことなのか、わからないが、
食べ歩きをしている人の中にも、
いろいろ問題を抱えている人、
それだけでなく、精神にダメージを負い、
本当に「傷だらけの天使」になっている人がたくさんいるはずだ。
この国では20人に一人が心を病んでいると伝えられている。
観光地を行く外国人旅行者のほとんどは、
そんな話は信じられないだろう。
外からやってきた彼らから見れば、
日本は、平和で安全で、食い物も、おもちゃも、
いろいろな楽しみも豊富な、21世紀の世界における、
一種の理想郷に見えるのではないだろうか。
僕たちが到達したユートピアでは、
「私たちは見かけほど、豊かでも幸福でもないんだよ」
という顔をして街を歩いてはいけない。
楽しさ・賑やかさの裏から、
そんな無言の圧がかけられているような気もしてくる。
「傷だらけの天使」完食

最終回「祭りの後にさすらいの日々を」で、やっぱり号泣。
AmazonPrimeで「傷だらけの天使」を全26話見た。
大好きなドラマだったが、実はちゃんと見たのは3分の1くらい。
3分の1は断片的に覚えているシーンもあるが、
3分の1は全く見てなかった。
だから今回、50年の年月を経て、初めて完食。
長生きしてよかった!と思ってしまった。
この時代まで生き延びて幸福だ。
その「傷天」、この間も書いたけど、
今の基準で見ると、かなりひどい出来。
最近の映画やドラマの悪口を言う人は多いが、
30年前にラジオドラマの脚本賞を
取らせていただいた人間の目から見ると、
今の脚本・演出・演技、
すべて30年前よりはるかに高いレベルにあると思う。
少なくともテクニック的には。
だから50年前のこの作品が、
稚拙で雑なつくりに見えるのは当然かもしれない。
でもね。
面白いかどうかとなると話は別。
うまけりゃいいってものじゃない。
ちゃんと伏線があって、きれいにストーリーがつながって、
オチがついてりゃいいってもんじゃない。
本当にめちゃくちゃだけど、
このノリはどうだ。この勢いはどうだ。
ショーケンと水谷豊はもちろんいいのだが、
両岸田をはじめとする脇役のすばらしさ。
脚本家、監督をはじめ、製作スタッフの息遣いが伝わってくる。
喫煙シーン、暴力シーン、セックスシーン満載で、
コンプラなんてくそくらえ。
何よりも、あの70年代の東京の空気が
あまりにも鮮やかに封じ込められている。
戦後まだ29年、30年の世界。
ここで描かれているのは、29歳・30歳の若い日本。
新宿も渋谷も横浜も、かなりヤバい街に見える。
今の日本は、いいにつけ悪いにつけ、
おとなになって老成した80歳なのだと痛感する。
キャストもスタッフも大部分がこの世を去り、
もはやリメイクは不可能だが、
なんと作家の矢作俊彦が、
ショーケンとメインライターだった市川森一に許可を取って、
2008年にリメイク小説を書いていたと知って、びっくり。
きょうはとても冷静に書けないが、
これからまた、この昭和の名作「傷だらけの天使」について
いろいろ書いていきたいと思います。
おとなも楽しい少年小説
「おとなも楽しい少年小説」はライフワーク。
書くべき物語がたくさん自分のなかに眠っているのは、
幸福なことだと思います。
あなたも僕も、どこまで人生が続くか、わからないけど、
一度、探偵になって自分の内側を掘り起こしてみましょう。
金の林檎みたいな、思わぬ宝物が出てくるかも。
おとなも楽しい少年少女小説 2タイトル
無料キャンペーン: 2月26日(水)16:59まで実施中。
レビューもお寄せくださいね。
茶トラのネコマタと金の林檎
https://amazon.com/dp/B084HJW6PG
私立探偵の健太は、山荘に住む富豪のネコマタマダムの依頼で、黄金の林檎の探索に。
そこで見つけたものは?人生で大切なものは何か、
探しているあなたに贈る
コミカルでファンタジックな探偵小説。
叔母Q
https://amazon.co.jp/dp/B0CKWZKZJF
叔母の温子はロサンゼルスの下町のアパートで
孤独のうちに死んだ。
リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で
彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、
可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を
葬儀屋に語る。
おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン「叔母Q」
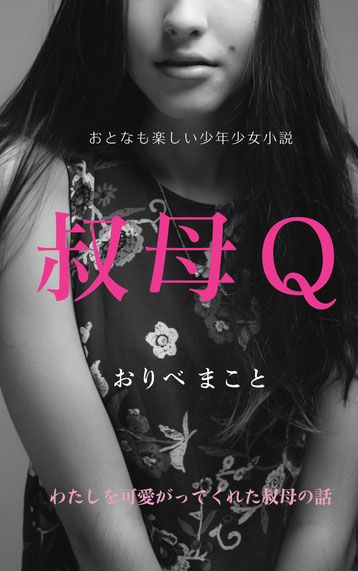
おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン
2月26日(水)16:59まで実施中。
僕の叔母は生きていれば90歳を出たところ。いま、社会で活躍している30代・40代の女性の祖母にあたる年代です。
多感な少女期に終戦を迎え、日本が戦後、
アメリカの擁護を受けながら、
新たな国家として復興するのと同じ歩みで大人になりました。
その時代、さしたる家柄にも才能にも美貌にも
恵まれていない女性の生き方は、かなり制限されていました。
20代半ばまでに結婚できた人は幸福とされましたが、
その後、自分を殺し、家族に尽くす長い人生が待っています。
一方、かわいいお嫁さんになれなかった人は、
世間から冷遇されるか、憐みや蔑みの目で見られるなかで
生きる道を選ばなくてはなりませんでした。
もちろん、例外はたくさんあって、
注目すべきイケてる女性の活躍は、
マスメディアで紹介されたり、
小説・映画・ドラマなどのモデルにもなったりしています。
しかし、叔母はそんな華やかな舞台に立つこともなく、
ありのまま自由に生きることもなく、
それでも喜びに満ちた人生への憧れ・欲求は人一倍あって、
それを抱えたまま、一生を過ごしたのではないかと思います。
本人の本当の気持ちはわかりませんが、
傍目には残念無念な女の一生。
けれども彼女のような、無数の昭和庶民の女性の、
満たされることのなかった憧れや欲求が、
現代の孫世代の女性らに受け継がれ、
活動力のエネルギーになっているような気がします。
亡くなって早や20年近く経ちますが、
なぜだか彼女は僕の心のどこかに棲み続け、
両親とは違った形で僕の人生を支え続けています。
生きている間に話を聴けなかったので、この作品における事実(と自分で思っている箇所)はせいぜい2~3割。
だから小説として、大部分は想像して書いたのですが、
フィクションの中にも、確かにこの世で生きた、
叔母の記憶を刻み込めたことに満足感を覚えています。
昭和の名もなき女性がどう生きたかの物語をお楽しみください。
探偵小説「茶トラのネコマタと金の林檎」のご紹介

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン
2月26日(水)16:59まで実施中。
都会の片隅でかろうじて生きている、しがない探偵は、
いつも仕事に、カネに飢えている。
けれどもカネのためだけで働くには、
やつも、やつの相棒もお人好し過ぎた。
夢見る女のために奮闘する心やさしき男たちの物語。
あなたの連休のおともに。

若き私立探偵の健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索だ。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れて現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、
魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。
健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、
黒い服の4人組の男たちがこの山にやってきて、
どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、
山中の雑木林に入ってスコップを振るい、
肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、
コミカルでファンタジックな探偵小説。
「傷だらけの天使」は昭和の天使の物語

「傷だらけの天使」は、
おそらく現在の60代から70代前半の男性の多くが、
ディープにハマったドラマだろう。
1974年10月から75年3月まで半年間、
毎週土曜日、日本テレビで放送された。
主役の小暮修(オサム)は、
表の社会と裏社会とを行き来しつつ、
やばい仕事で荒稼ぎをする「綾部調査事務所」の調査員。
と言えば聞こえはいいが、
実態はチンピラ探偵といったような風体の若い男。
これをショーケンこと萩原健一が演じる。
そしてその弟分であり、仕事の相棒・乾享(アキラ)の役が、
人気ドラマ「相棒」の杉下右京=水谷豊だ。
この半世紀前のドラマが、
AmazonPrimeで配信されているので見ている。
作品紹介は以下の通り。
ビル屋上のペントハウスに住み、
探偵事務所の下働きをする修(萩原健一)と、
彼を「アニキィ!」と慕う亨(水谷豊)。
修の貧乏生活を知る探偵事務所のボス、
貴子(岸田今日子)とその手下、辰巳(岸田森)は、
金をエサに彼らに毎回無茶苦茶な仕事を押しつける。
割に合わないと思いつつも、
がむしゃらな修は命懸けで危険な仕事に飛び込んでいくのだが、
根っからの善人で単細胞なゆえに、
仕事も思わぬ方向へ暴走してしまう。
笑いあり、涙あり、お色気ありで展開するストーリーには、
息をもつかせぬスピード感がみなぎっている。
どうやらコロナの時期から配信していたらしいが、
気が付かなかった。
またハマったらどうしようと思って恐る恐る見たが、
やっぱりハマってしまった。
脚本も演出も撮影も演技もメチャクチャで、
聞き取れないセリフもいっぱいいある。
だけど、やっぱり面白いし、イカしている。
泣いてしまうし、考えさせられる。
そして、「ああ、おれはやっぱり死ぬまで
傷天の世界から抜け出せない」と再認識した。
決してノスタルジーを感じたわけではない。
むしろ逆で、50年たった令和の今見るからこそ、
違った傷天の魅力が見えるのだ。
これについては、とても1回や2回では書けないので、
これからしばらく折に触れて書いていこうと思う。
今日、一つだけ書いておく。
今までこのドラマのタイトルを意識したことがなかったが、
今回、昭和から遠く離れた地点から見ると、
オサムとアキラは、
まんま「傷だらけの天使」なんだなということがわかる。
二人は人間世界に降りてきたエンジェルであり、
あのバカかげんは、
人間世界における天使のふるまいなのだ。
そういう視点で見ていくと、
ハードボイルドともコメディとも昭和残酷物語ともとれる、
この探偵ドラマが、一種のヒューマンファンタジーとして、
新鮮な輝きを帯び始める。
そして、なんで俺はこんな世界で生きているのだろうと、
大いなる疑問にとらわれるのだ。
「なんのこっちゃ?」と思うでしょうが、
また、おいおい書いていきます。
認知症の問題解決にアルバム認知症の問題対応にアルバム効果 心療回想士がつくった「人生まるごと回想アルバム」

東京ビッグサイトで12日から14日まで開催されている
「ギフトショー」に行ってきました。
太田区のブースの一角で「人生まるごと回想アルバム」を
紹介しているのは、株式会社テコデコドリーム研究所です。
アルバム本来の役割を見直す
アルバムに並んだ写真を見て、
過ぎ去りし日々を楽しむというのは、ごくありふれた行為で、
どこの誰でも実践していることのように思えます。
けれども、実はちゃんと写真を整理整頓し、
他者が見ても分かるよう管理できている高齢者はごく少数。
また、それが子供世代との間でコミュニケーションツールとして
活用されている例はさらに少ないようです。
「人生まるごと回想アルバム」は
そうしたアルバムが本来持つ役割を見直し、
可能性を伸ばすことによって生まれた商品です。
医療・介護の分野で注目の「回想法」
このアルバムは回想法で利用するシーンを
想定して作られています。
回想法とは1960年代初期に
アメリカの精神科医が開発したもので、
回想し過去の記憶をよみがえらせることで脳を活性化。
さらにその記憶を他者と共有し、
分かち合うことでより元気を出せるという精神療法です。
ご存じのようにこの10年ほどの間、
超高齢社会の進展に伴って認知症患者が激増。
それによってすでに相続などの分野で
様々な問題も起こっています。
そんな状況のなかで回想法は、認知症に対する予防効果、
あるいは症状の緩和・改善が期待できる非薬物療法として、
医療現場や介護施設、自治体の介護事業、
地域コミュニティーなどにも注目されています。
心療回想士のスタッフが開発
テコデコドリーム研究所ではスタッフ全員が
この回想法の基礎を学び、
心療回想士の資格を取得。
素材として写真を用い、
その写真を編集して作るアルバムに焦点を合わせました。
どうすれば親世代(高齢者)にとって、
より楽しく記憶をよみがえらせるものにできるか、
子供世代・孫世代とのコミュニケーションに
役立つツールにできるかを考えた上で設計し、
他にはないユニークな特徴と機能を持たました。
親子で楽しめるアルバムづくり
最も大きな特徴は、マグネット式アルバムを採用したこと。
家族みんなで閲覧しようという時、
アナログの分厚く重いアルバムを手に取るのは億劫で、
一人一人気軽に回して見るのに適していません。
また、スマホやタブレットのようなデジタル端末の画面上で
写真のデータを見るというスタイルだと、
みんなで見ている、家族で親の人生を共有している、
という感覚が持てません。
1ページずつ取り外しができるマグネット式アルバムは
そうした課題をクリアし、
家族で集まれば、自由に広げてみんなで見ることができ、
ページ追加も簡単にできるといいます。
また、記憶を呼び起こすためには“可視化”が重要。
家の中で目につく場所に写真があると、
ふとしたきっかけで大事なことを思い出したり、
家族への感情が深まることがあります。
通常、アルバムはしまっておくと中身が見えませんが、
ここでもマグネット式の利点を生かし、
お気に入りの写真があるページを
スチール製の壁や冷蔵庫に貼りつけて見ることができます。
また、アルバムそのものを360度開いて
そのままフォトスタンドとして使うこともできるといいます。
子供が親のためのアルバム編集者に
こうした特徴・機能を活かして同社では
「子供世代が高齢の親にためにアルバム編集者なること」
を推奨しています。
フィルムカメラの時代は、撮影後、
現像してプリントしなければ、写真を見られませんでした。
そのため、親世代が保存している写真の量・アルバムの量は
膨大であるケースが多く、
本人が亡くなった後は、(悲しいことではありますが)
そのほとんどを破棄しなくてはならないのが現実です。
それを踏まえて、テコデコのスタッフは、
子供世代が自分で見て貴重だと思える写真、
親のことを知らない子供や縁者の人たちが見ても
楽しめるような写真などを選び出し、
この「人生まるごと回想アルバム」を使って、
世代を超えて共有できるアルバム、
親孝行のツールとなるアルバムを作ってほしいと話していました。
施設のスタッフが心のケアにも手を伸ばせる
また、このアルバムは親が
介護施設で暮らすことになった場合にも
効果を発揮します。
介護施設のスタッフは、
親を「入居者=高齢の人」としか認知できないので、
毎日の食事や排泄の世話など、身体機能面でのケアはしますが、
感情面でのケアは天気のこと・庭の花のことなど
についてしか話せません。
生まれながらの高齢者など一人もおらず、
誰しも何十年という人生の道程、
無数の喜怒哀楽を経験してそこにたどり着くのですが、
スタッフはその一つとして想像するすべがないのです。
そんな時、このアルバムで子供時代や青春時代など、
親の人生のわずかな断片でも知ることができれば
「かわいいですね」「楽しそうですね」など、自然と会話が弾み、
心の介護・感情面のケアにも手を伸ばせるのではないか。
テコデコ研究所ではそうした期待も抱いています。
ちなみに、「回想法」の効果的な会話のポイントとして
「ほめ言葉は過去形にしないで現在形で話す」そうです。
還暦スタッフの第2のスタートアップ
テコデコドリーム研究所は、
もともとキャラクターと音楽コンテンツを
メイン事業とする会社で、
かつては各種アミューズメント施設やイベントなどで
若者や家族連れの人気を集めていましたが、
いずれも家庭の主婦を兼任していた3人のスタッフが
家族の介護に専念するために一時企業活動を休止していました。
その間、代表の池尾里香さんが施設に入居した
独身の叔母の家の整理をした際に、
それまで見たことのなかった若い叔母の
いきいきした姿の写真を大量に発見。
その中から自分の目で選んで一冊にまとめたアルバムを
本人に見せたところ、認知症気味だった叔母が大いに喜び、
互いに思い出を共有できたといいます。
同社の3人は、中小企業振興公社主催の
「事業家チャレンジ道場」で約2年間、
ものづくり・最新のマーケティング技術を勉強する中、
介護経験と回想法を活かした今回の事業を考案しました。
誕生日、母の日、父の日、施設の訪問時、
米寿や喜寿のお祝い事などに、
子から親への真心こもったプレゼントに使ってほしいというのが
彼女らの提案です。
永続的な親孝行の実現をサポート
「人生まるごと回想アルバム」は、
葬儀の遺影や式場の思い出コーナーの写真などに
使えることはもちろん、
その後の法事の場でも集まった人たちに
親の人生を偲んでもらうこと、
また、孫やその後の世代に伝えていく
「ファミリーヒストリー」としても
役立てることができるといいます。
池尾さんと、実の姉である綿井さんは、
両親の法事の席で親戚一堂にこのアルバムを見てもらったところ、
たいへん盛り上がり、皆、新鮮な感動を受けたといいます。
それがまた両親に対する供養に繋がるのでしょう。
これは単にアルバムを販売するビジネスでなく、
アルバムづくりを通して、
永続的な親孝行の実現をサポートする事業
といえるかもしれません。
もしギフトショーに行かれる方は、
ビッグサイト南館にある大田区のブースで、
ぜひ実物を手に取ってみてください。
また、このアルバムのサイトはこちらです。
https://tekodekorecollection.com/
虚と実が融合する映画「八犬伝」

「南総里見八犬伝」は
江戸時代の作家・滝沢馬琴が書いた長編小説。
1814年に始まって、
1842年の完結まで28年かかって世に出された、
世界に誇れる傑作エンタメファンタジーです。
運命に導かれて集まった仲間が
力を合わせて敵と戦うという勧善懲悪パターンは、
神秘的かつ痛快で、この活劇をモチーフにした
コンテンツが200年の間に続々と作られました。
今日の日本のマンガ・アニメ文化の基盤を築く
一要素になったことは、疑いようがありません。
僕の八犬伝との出会いは、
小学生の時に見たNHKの人形劇でしたが、
それ以後も「八犬伝」から
いくつもの映画やマンガが生まれるのを見てきました。
いちばん最近のものは、
昨年秋に劇場公開された映画「八犬伝」でしょう。
僕は見逃していたので、先日、アマプラの配信で視聴。
公開の時は評判はイマイチだったようですが、
とても楽しめました。
虚と実、二つの世界がパラレルで進む構成で、
虚はご存じ、八犬伝の活劇世界です。
原作に忠実なのはいいのですが、
ストーリーの上っ面をサーっと撫でているという感じで、
今一つ物足りないのですが、
それでもやっぱり面白いのは、さすが八犬伝。
名刀・村雨を持つ犬塚信乃、女装の犬坂毛野、
少年剣士の犬江親兵衛などはとてもイケメンで、
画面も派手で美しい。
それに対する実の世界では、
作者・滝沢馬琴と絵師・葛飾北斎、
二人のむさいジジイの対話で進みます。
これに「東海道四谷怪談」の戯作者・鶴屋南北が絡んだりして、
彼らの創作に対する考え方・思いが伝わってきて味わい深く、
このむさいじいさん・おっさんたちから
ああした華麗な物語や絵画が生まれたのが面白い。
まるで現代人のような、滝沢馬琴の家庭の事情
(一人息子がニート状態)も描かれていて、
これも考えさせられます。
いよいよ最終章、物語がクライマックスに差し掛かったところで
馬琴は失明。目が見えなくなり、執筆できなくなります。
「八犬伝」は未完の大作に終わるかと思われたときに、
代筆者として名乗りを上げたのが息子の嫁でした。
この嫁は無学で字もろくに書けない女性なのですが、
義父である馬琴が字を教えながら、二人三脚でがんばり、
わずか8か月で残りを仕上げ、物語を完成させます。
すごく感動的なエピソードですが、
この嫁がどうして馬琴に尽くし、代筆をやろうと思ったのか?
夫を先になくして寂しかったから?
義父のことを好きだったから?
「八犬伝」が好きだったから?
そのあたりがドラマとして描かれていないので、
どうも腑に落ちないのですが、それでも物語は最期を迎え、
馬琴の仕事は成就しました。
そして、まるで最近の
ファンタジー系アニメやマンガのお約束事のように、
戦いで命を落とした犬士たちも生き返るのです。
僕も小説などを書いているので、虚実が融合し、
馬琴と八犬士が遭遇するラストシーンには、
涙を抑えきれませんでした。
不平・不満はありますが、やっぱり八犬伝は面白いし、
創作の舞台裏も描かれたこの映画には、
単なるエンタメを超えた奥深さがあると思います。
きらめく都会や死の国を旅する「星の王子さま」

小さな劇場の何もない舞台は、想像力が刺激される、
自由で可能性に満ちた空間です。
今日はここで「星の王子さま」の舞台を見ました。
原作はもちろん、サン・テグジュペリの童話。
壁面全体にしわをつけたベージュの模造紙を張り付け、
あの物語の舞台になる砂漠のイメージを表現しています。
内容は原作をなぞるものではなく、
生演奏やダンスが随所に交じる、
音楽劇風・イメージコラージュ風の構成。
前半は、王様、実業家、のんべえ、点灯夫など、
へんな大人がいる星をめぐる旅など、
原作に出てくるエピソードを仮面劇で見せたり、
後半は王子様とキツネがともに
パリと東京を合わせたような、
きらびやかな都会の街を探索したり、
地下にある死の国をめぐり歩く
オリジナルのエピソードを取り入れたりと、
自由自在な展開で、不思議な世界に引き込まれました。
王子様役の女性はクラシックバレエの心得があるようで、
随所で王子の心情をダンスで表現します。
彼女のビジュアルは、絵本のイラストそっくりでありながら、
不思議なエロシティズムと、
物語全体を包む切なさ・寂しさが感じられて魅力的でした。
上演したのは、
カミさんの仕事仲間である鍼灸師の奥さんが主宰する
「クリスタルレイク」というグループ。
この奥さんというのは、もともと新劇俳優で、
劇団新人会のメンバーだった人だそうです。
大ベテランですが、キツネ役として登場した
彼女の動きはキレがよく、
せりふ回しもクリアで「生涯現役」を感じさせました。
僕たちはこうした小劇場演劇に感化された世代ですが、
昨今の舞台演劇は、
やる側も見る側もシニア世代のものになりつつあるようです。
これも時代の趨勢なのでしょうが、
若い人たちにも、こうした変幻自在の小さな空間で描かれる
リアルでアナログな演劇の空気を、
若い人たちにも、ぜひ体験してほしいと思います。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン
2月3日(月)16:59まで
昨夜よりもっといい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
映画「怪物」と脚本家の来歴、フジテレビのドラマについて

是枝裕和監督の映画「怪物」を見た。
息子を愛するシングルマザー、
生徒思いのまじめな小学校教師、
そして無邪気な子どもたちが送る平穏な日常。
それがある小さな事件がきっかけでガラガラと崩れる。
その背後にいるのは、正体不明の怪物。
ひとことで言えば、
タイトルの「怪物」とは誰か?何か?を追究する物語だ。
それは親なのか? 教師なのか?
学校という組織なのか?
それとも子供たちなのか?
いったい何なのか?
前半は学校と家、地域を舞台とした、
リアルでドキドキするサスペンス。
そして後半からクライマックスは、
それが一種のファンタジーにまで昇華する。
還暦を超えても全く衰えを感じさせない
是枝監督のクリエイティビティに舌を巻く。
音楽は最晩年の坂本龍一。
坂本龍一と言われなければ、
わからないくらい主張は少ないが、
随所でとてもいい味を出している。
そして脚本は坂元裕二。
いまや日本を代表する脚本家だが、
彼は1987年に初めて行われた
「フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者。
つまり、フジテレビが発掘した才能だ。
1991年の、あのフジ・トレンディドラマの代表作
「東京ラブストーリー」の脚本を手掛けた人でもある。
坂元氏はその後、テレビ業界が嫌になり、
一時的にテレビドラマの脚本を書かなかったこともあり、
最近はもうプロフィールにも
「東京ラブストーリー」については触れられていない。
そんな大昔のことなど持ち出す必要もなく、
クオリティの高い作品をコンスタントに手がけ、
充実した活動を展開しているからだろう。
この作品は、第76回カンヌ国際映画祭の
コンペティション部門で脚本賞も受賞している。
そんな坂元氏を輩出した1990年代のフジテレビは、
恋愛を中心としたトレンディから
先鋭的なサイコサスペンスまで、
ドラマの制作能力がとても高く、
TBSと競い合うように傑作・問題作を次々と放送していた。
それはもうすっかり過去の話だが、
そうしたコンテンツ制作の資産は残っているはずだ。
サザエさんや、ちびまる子ちゃんや、
ガチャピン&ムックもいる。
このままダメになるのは、あまりに惜しい。
けれども再出発のためには今いる、
過去の栄光に浴した経営陣営陣ではダメなことは明らか。
なんとか改革して、また優れたコンテンツ、
動画配信をしてほしいと願う。
フジテレビの話に傾いてしまったが、
是枝映画「怪物」はほんとに傑作。
カンヌで認められた、なんて話はどうでもいいので、
ぜひ、このドラマの奥に潜む怪物を
自分の目で発見してほしい。
「パーフェクトデイズ」 どうせ死ぬのに、なぜ一生懸命生きるのか? を考える映画

青く晴れわたった空を見ていると、
なぜか胸が切なくなり、涙が出てくる。
歌だったか、小説だったか、忘れてしまったが、
誰かがそんなことを書いていた。
ヴィム・ヴェンダーズ監督、役所広司主演の映画
「パーフェクトデイズ」の感想を一口で言うなら、
そんな映画だ。
たんにエンタメとして楽しませてくれるよりも、
いろいろなことを考えさせてくれるのがいい映画、
あるいは、きょうはそういう気分になっている
人にとっては、これほどいい映画はない。
役所広司演じる主人公は、トイレの清掃員・平山。
朝、夜明け前に起き出し、支度して仕事に出かけ、
終わると安い飲み屋で一杯ひっかけ、
夜はふとんで本を読んで寝る。
その単調な生活、同じような毎日の繰り返しを淡々と描く。
周囲の人たちとの、小さなエピソードはいくつかある。
そして、彼が毎朝、若木に水をやったり、
公園の木々の写真をフィルムカメラで撮ったりする描写も、
そうした命を愛する人だということを伝える。
しかし、それだけだ。
平山の生き方を変えてしまうような劇的な展開、
物語らしい物語はいっさいない。
テーマらしいテーマもないように見える。
でも、僕はこの映画の秘密めいたテーマを見つけた。
まだ序盤のあたり、同じ清掃員仲間の若い男が
平山の丁寧な仕事ぶりをちょっとくさすように、
「どうせ汚れるんですから」という。
トイレだから当然だ。
どうせ汚れるのに、汚されてしまうのに、
どうしてそんなに一生懸命になって掃除するんだ。
僕もそう思う。
きっと誰もが、若い男のセリフを借りれば、
「10人のうち9人は」、いや、もしかしたら10人が
そう思うと思う。
誰もが豊かで便利で平和に生活できる、この社会では。
「どうせ汚れるのに、どうして一生懸命掃除するのか」
これは言い換えれば、
「どうせ死ぬのに、どうして一生懸命生きるのか」
につながる。
平山はきっとそうしたことを考えながら、
毎日のトイレ清掃に励んでいる。
それがどんな仕事でも、
ていねいに仕事をすることは、
ていねいに生きることにながる。
ていねいに生きれば、一日一日がきれいに輝く。
そんなメッセージが流れている。
平山は現代社会に取り残されてしまったような人だ。
孤独だし、もう若くないし、カネも持っていなさそうだ。
スマホもパソコンも使わなければ、
ボロアパートの部屋にはテレビさえ置いていない。
車は持っているので、ラジオは聴くかもしれないが、
彼がラジオを聴くシーンは出てこない。
車内で聴くのはもっぱら古いカセットテープ。
1960年代から70年代の音楽だ。
彼の年齢は60歳前後と察せられる。
要は、学生だった40年ほど前の時代と
ほとんど変わらない生活を送っているのだ。
そんな取り残され、落ちこぼれた、
高齢者に近い孤独な男だが、
なぜか周囲の人たちを励まし、
元気づける存在になっている。
先述の若い男もそうだし、
その男が好きになった女も平山にキスをする。
極めつけは、中盤で彼のアパートにやってくる姪だ。
高校生らしき彼女は、伯父である平山を慕って、
仕事についてきたり、いっしょに銭湯に行ったりする。
この姪との会話のなかで、平山は、
「みんな一緒の世界に住んでいるようで、
じつは別々の世界に住んでいるんだ」
といった意味のことをいう。
彼のバックストーリーは一切語られないが、
この姪を連れ戻しに来た母親=彼の妹との短い会話は、
平山の人生を想像させる。
妹は高級そうな車に乗っており、
彼とは段違いの裕福風な暮らしを送っていることが
見て取れる。
また、彼の父親は高齢で認知症らしく、
施設に入っているようだ。
実家はかなりの資産家で、
長男である平山は、父の生き方に反発し、
家を出たまま、齢を重ねてしまったのかもしれない。
妹とは同じ家庭で育ちながら、
互いにまったく違う価値観を持った人間になってしまった。
けれども、きょうだい仲は悪くない。
姪の家出もそんなに深刻なものではなく、
母親に素直に従って帰っていく。
けれども彼女にとって、伯父の持っている世界は、
一種の憧れに満ちた世界として映っている。
この姪や、仕事仲間の男、そのガールフレンドらは、
みんな若く、軽やかに、
面白おかしく生きているように見える。
けれどもその裏側に漂う切なさは何だろう?
彼女らは、平山の存在に何を感じていたのだろう?
それはきっとこういう予見だ。
わたしも、おれも、いずれ齢を取り、死ぬ。
それまでどう生きればいいのか?
そうした思いにあまり齢は関係ないのかもしれない。
映画の終盤、彼が最後に励ますのは、
行きつけの飲み屋のママのもとを訪れた男である。
平山と同年代らしいこの男は、ママの元夫で、
ガンでもう寿命があまりない。
それで別れた妻に最後に会いに来たという経緯だ。
「結局、何もわからないまま終わっていく」
という男のセリフは胸に刺さる。
そんな男をやさしく励ます平山のふるまいは、
ひどく感動的だ。
平山の人生はこの先、劇的に展開する気配はなく、
きっと彼はこのアパートの一室の片隅で、
野良猫のように一生を閉じるのだろう。
社会に置き去りにされた、底辺のエッセンシャルワーカー。
高齢者に近い孤独で無口な男。
そんな彼の存在にも価値がある。
1本1万円で売れる、
聴きつぶした中古のカセットテープのように。
彼の人生は輝いている。
一日一日がパーフェクト・デイ=完璧な日だ。
このタイトルは、ルー・リードが、
1972年に発表した同名曲から取ったものだろう。
晴れわたった青空を想起させるような、
美しいが、ひどく物悲しい旋律に乗せて、
意味深な歌詞が繰り返される。
Just a perfect day
ただただ完璧な一日
You just keep me hanging on
君は僕をかろうじて生かしてくれている
You're going to reap just what you sow
自分の蒔いた種は、すべて刈り取らなくてはいけない
2023年のカンヌ映画祭など、
世界的に評価された作品であることは
あまり意識せず、
素直にありのままの気持ちで見た方がいい。
そうでないと、この映画の真価は見えてこない。
ヴェンダースの作品はむかし何本か見たが、
若い頃の自分にとっては退屈だった。
たぶんヴェンダース映画を見るのがイケてる、
カッコいいといった意識が入っていたからだろう。
これはシニアの自分には面白く見られたが、
若い人には退屈かもしれない。
でも、自分の目で見てほしいと思う。
「ベルリン天使の詩」「パリ、テキサス」など、
かつてはつまらないと思ったヴェンダース作品も
齢を取った目でもう一度、見てみたいと思う。
新しい何かを発見できるかもしれない。
自分へのクリスマスプレゼント

おりべまことの電子書籍
現代を生きる大人に贈る童話
花屋のネコの大いなる任務
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
無料キャンペーン間もなく終了。
12月23日(月)16:59まで。
さあ、急がニャいと。
自分へのクリスマスプレゼントにどうぞ。
旅のお供はネコですか?

夢をかなえたあとも、
成功を果たしたあとも、
欲しい物をすべて手に入れたあとも、
まだまだ人生は続く。
夢に届かない人も、
失敗して転んだ人も、
何も手に入れられない人も、
まだまだ人生は続く。
あなたがどっちか知らないけど、
いっしょに旅をするおともがいれば、
まだまだ人生続けられる。
現代を生きる大人のための童話
花屋のネコの大いなる任務
12月23日(月)16:59まで
無料キャンペーン開催中。
あなたの“ねこ”は、どこにいますか?
夢をかなえても、
成功を果たしても、
欲しい物をすべて手に入れても、
むなしかったり、涙が出たりする。
そんなあなたの心を満たす“ねこ”は、
どこにいますか?
現代を生きる大人のための童話
花屋のネコの大いなる任務
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPCN144Z
12月23日(月)16:59まで
無料キャンペーン開催中。
「花屋のネコの大いなる任務」無料キャンペーン

おりべまこと電子書籍最新刊
おとなも楽しい少年少女小説
「花屋のネコの大いなる任務」
本日より6日間無料キャンペーン開催中。
12月23日(月)16:59まで。
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
クリスマスの賢者の贈り物として、
あなたの胸の本棚に1部いかがかニャ?
●あらすじ
彼女は「お花屋さんになりたい」という
少女時代の夢をかなえた。
今はとある町の小さな花屋の女主人として、
ひとりで店を切り盛りしている。
花に関する豊富な知識、アレンジメントのセンスと技術。
加えて人柄もよく、お店の評判は上々で、
商売はうまいこといっている。
彼女自身も毎日、大好きな花に囲まれて
仕事ができて幸せだ。
ところが、明日は母の日という土曜日の朝、
店の外に出て、びっくりした。
そこに置いてあったカーネーションの花が
ネズミに食い荒らされていたのだ。
ショックを受けた彼女は、
今後、二度と店にネズミを寄せつけないよう、
ネコを飼う決心をする。
保護猫サイトを探すと、
かわいらしい子猫たちにまじって大人のネコがいた。
人間に保護されるまで1年間、
野良猫として生き延びてきた頼もしそうな奴だ。
しかも彼は、オスの三毛猫というレアものである。
女主人は彼を引き取り、
「ダビ」と名付け、自分に言い聞かせた。
「寂しいからじゃない。癒されたいからじゃない。
ネズミよけのためにこのネコを飼うんだ」と。
そして、自分とネコとの関係を明確にするために、
雇用契約を結ぶ。
彼女は仕事の依頼主。
その報酬として彼に食事と寝床を与える。
こうして、花屋の女主人と
三毛猫ダビの暮らしが始まった。
「花屋のネコの大いなる任務」無料キャンペーン

お待ちかね。6日間無料キャンペーン開催します。
12月18日(水)17:00~23日(月)16:59まで。
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
花好き、ネコ好きに贈るクリスマスプレゼント。ぜひ。
●あらまし
彼女は「お花屋さんになりたい」という
少女時代の夢をかなえた。
今はとある町の小さな花屋の女主人として、
ひとりで店を切り盛りしている。
花に関する豊富な知識、
アレンジメントのセンスと技術。
加えて人柄もよく、お店の評判は上々で
、商売はうまいこといっている。
彼女自身も毎日、
大好きな花に囲まれて仕事ができて幸せだ。
ところが、明日は母の日という土曜日の朝、
店の外に出て、びっくりした。
そこに置いてあったカーネーションの花が
ネズミに食い荒らされていたのだ。
ショックを受けた彼女は、
今後、二度と店にネズミを寄せつけないよう、
ネコを飼う決心をする。
保護猫サイトを探すと、
かわいらしい子猫たちにまじって大人のネコがいた。
人間に保護されるまで1年間、
野良猫として生き延びてきた頼もしそうな奴だ。
しかもオスの三毛猫というレアものである。
女主人は彼を引き取り、
「ダビ」と名付け、自分に言い聞かせた。
「寂しいからじゃない。癒されたいからじゃない。
ネズミよけのためにこのネコを飼うんだ」と。
そして、自分とネコとの関係を明確にするために、
雇用契約を結ぶ。
彼女は仕事の依頼主。
その報酬として彼に食事と寝床を与える。
こうして、
花屋の女主人と三毛猫ダビの暮らしが始まった。
「海の沈黙」:心の主食になる映画
久しぶりに映画館で、
倉本聰・作の映画「海の沈黙」を観る。
すごくよかった。
久しぶりにずしっと腹に応える映画を味わったなぁという感じ。
派手でわかりやすくておいしいけど、
あまり栄養になりそうにもない、
おやつみたいな映画が多い中、
これこそ主食となる、心の栄養になる映画。
「生き残り」と言ったら失礼かもしれないけど、
倉本聰さんは日本のテレビドラマ黄金期、
そして衰退傾向だったとはいえ、
まだまだ映画が娯楽の王座にいた時代を支えた
作り手の「生き残り」だ。
(こんな言い方は失礼だと思うけど)
今年で齢89歳。うちの義母と同い年。
改めて履歴を見ると、
なんと、僕が生まれる前、1958年から
ドラマ作りのキャリアをスタートさせている。
この20年ほどの間に
同じ脚本家の山田太一・市川森一をはじめ、
同時代に活躍した作家や監督や俳優が
次々とこの世を去っていったが、
倉本聰さんは依然健在で、
「どうしても書いておきたかった」と、
60年温めてきた構想を実現した。
キャリアが長けりゃいい作品が書けるわけじゃない。
ものを書くには気力も体力もなくてはできない。
体内のエネルギー量がどれだけあるかの問題なのだ。
こんな気力溢れる作品を書く力が残っているなんで、
驚きと尊敬の何物でもない。
セリフの一つ一つ、シーンの一つ一つが重く、深く、
濃厚な内容は、昭和の香りがプンプン。
サスペンスの要素もあり、画面には2時間の間、
緊張感がみなぎって面白いので、
若い人にも見てほしいが、やっぱりこういうのは
ウケないんだろうなとも思う。
かくいう僕も、20代・30代の頃に
こういう映画を見て傑作と思えたかどうかは怪しい。
やっぱり齢を取らないとわからないこと、
味わえないものがあるのだ。
出演陣も素晴らしい。
なかでも中井貴一は飛び抜けてシブい。
それに比べて、主演の本木雅弘は
いま一つ軽いかなぁという感じ。
これまで小泉今日子をいいと思ったことは一度もなく、
倉本作品に合うのかなと思ったが、最高だった。
もと「なってたってアイドル」なので、
この類の人は、何かにつけて「経年劣化」を揶揄される。
けれども最近、不自然な修正画像やアニメ顔、
整形美女の不気味な顔を見過ぎているせいだろうか、
たびたびアップになる、しわの寄った顔が、
リアルでナチュラルで美しい。
そう思ったのは、やっぱり自分も齢を取ったからだろう。
カミさんと朝イチ(といっても11時半)の回に行ったが、
僕たちを含めて、観客はシニア割の人たちばかり。
やっぱり昭和の作り手、昭和の観客の世界だ。
間もなくこうした世界はむかし話になるだろう。
でも僕は、リアルで深遠な昔ばなしを
大事にしていきたい。
恐怖の巨匠・楳図かずお先生逝去

わが「恐怖」の原点。
かつて子どものマンガに確実に
「恐怖」というジャンルがあった。
その創始者であり、第一人者であり続けたのが、
楳図かずおだった。
小学校の低学年の頃、
わりとお金持ちの、仲の良い女友だちがいて、
その家によく遊びに行っていたのだが、
そこに楳図マンガが連載されていた
「少女フレンド」(だと思った)が揃っていて、
その置き場所には怖くて寄りつけなかった。
「リング」の貞子が
テレビの中から抜け出してきたように、
雑誌の中から「へび女」とか「ミイラ先生」が
這い出してくるのを想像していたのだろうと思う。
その後、少年漫画誌で「猫目小僧」とか、
「半魚人」とか「恐竜少年」とか、
いろいろな楳図製恐怖マンガを読んだが、
なぜか少女系のほうが圧倒的に怖かった。
「女は怖い」という、僕の感情のOSは、
楳図かずおによって生成されたのかもしれない。
うちの母親がもっと美人で優しかったら、
「この人、へび女にならないだろうな」
と思ったかも‥だが、幸か不幸か、
あんまりそういう雰囲気の人ではなかったので
助かった(?)
いっしょに住んでいた若い叔母は
ちょっとその方面の雰囲気を持っていたような気がする。
それにしてもあんな怖いマンガを
毎日、描きまくっていた、
当時の楳図かずおの頭の中は
いったいどうなっていたのだろう?
ご本人は「ぜんぜん怖くなんかないですよ」と
言っていたが、自分なら気が狂いそうだ。
その後、ギャグやSFの分野でも
とんがった才気を見せつけ、傑作を量産。
しかもそうした恐怖、怪奇、ギャグ,SF、
ファンタジーなど、それぞれの要素が
重層的にクロスオーバーし、
誰にもまねできない「楳図ワールド」を構築した。
そして、その核には「人間」がいて、
人間が奥底に持つカオスのようなものについて
考えさせられる。
楳図かずおは人間の深いところを、
その不可解で不可思議な在り方を、
とことん掘りまくることによって、
最も原始的な感情である「恐怖」をベースとした
独自の世界をつくり上げたのだ。
そういう意味で
「まことちゃん」は「猫目小僧」の弟であり、
「おろち」は「へび女」の娘であり、
「漂流教室」と「14歳」「わたしは真吾」などは、
同列に展開するパラレルワールドになっている。
個人的に最も胸に刺さったのは、
連作オムニバス「おろち」の「秀才」だ。
「おろち」は、不滅の存在である少女
(萩尾望都「ポーの一族」のバンパイアに似ている)が
時空を旅して、人間界のさまざまな時代・場所で、
人間同士の感情が絡み合って起こるドラマに
関わっていくという話。
「秀才」はそのかなの一遍で、
教育ママとその息子の物語だが、
それまで持っていた「オバケマンガ」の概念を破る
深い人間ドラマに驚愕した。
読んだのが小学校高学年で、
大人のドラマに興味を持ち始めた時期だったので、
よけい感動したのかもしれない。
「秀才」は今でも十分通じるドラマで、
現代社会における母親という存在の
愛の深さゆえの罪深さを描き出した傑作だ。
まちがいなく歴史に名を留める漫画家・芸術家。
日本のマンガ文化の重要なパーツとなる孤高の作家。
そして最後まで自分のぶっ飛んだ個性を貫き通した
楳図かずお先生。
人間の怖さ・驚くべき世界を見せてくれてありがとう。
ご冥福を祈ります。
小説は感情の記憶 誰にでも書ける

11月の花はリンドウ。
行きつけの花屋さんをモデルにした小説を書いてる。
1万字~1万5千字程度の短編にしようと
夏の暑くなり始めた頃から書き出したのだが、
いろいろ話が展開し、
途中で止まったりして、かれこれ4カ月。
2万5千字を超えたところで
やっと完成のめどが立ってきた。
年内には何とか出版できそうだ。
今年は春先に長編を1本書き上げたので、
あとは短編を2~3本書こうと思っていたが、
かなり苦戦した。
ちょっとと体力が落ちて疲れやすくなり、
感情の流れの混乱がうまく収拾できないことが増えた。
小説は普段書いている文章と違って、
事実を綴ったり、理屈をこねたりするだけでなく、
それらと合わせて
自分の感情を掘り起こす作業だと思っている。
ぜひ表現してみたい感情があって、
それを登場人物のセリフにするために、
ストーリーや場面設定を作る場合もある。
逆に思いついたストーリーに引きずられて、
すっかり忘れていた感情がよみがえったり、
まったく思いもかけなかった感情が
登場人物のセリフに乘って現れたりする。
どっちも面白いが、根気よく書き続けないと出てこない。
アスリートと同じで、
つねに体のコンディションを整えていないと、
自分の感情と格闘できないのだ。
最近は最初のプロットを作る段階で、
AIと会話してヒントを得たりする。
感情を引き出せるストーリー作りのためなら
AIに手助けしてもらうのもよし。
そうして作ったものを何本か塩漬けしてある。
僕たちは日々、
自分の感情をあまり表に出さないように
コントロールしながら生活している。
読む相手がいる限り,SNSでも
感情全開でぶちまける、というわけにはいかない。
感情を抑えつつうまくやっていくためには
いろいろな方法があるが、
小説というフィクションの形にして
表現するという仕事は、
ひとりでできるし、場所も問わないし、金もかからない。
小説はただ感情をぶちまけるのでなく、
ストーリーやキャラクターとともに
一つの作品として形にするので、
よりクリアな記録して、貴重な人生の記憶として
遺すことができる。
今、小説は誰にでも書ける。
文才なんていらない。
僕がそのいい例である。
自分で面白いと思えるアイデアがあれば、
AIの助けを借りて、
オリジナルストーリーを作ってみればいい。
それが人にウケるかどうか、
読んでもらえるかどうかは、また別の話だけど。
終活映画「パリタクシー」と20世紀フランスの女性差別

毎月、ウェブサイトのコラム記事で
世界の終活映画の紹介をしているが、
フランスの近年の代表的な終活映画が
「パリタクシー」だ。
あらすじはシンプルで、これから施設に入居するという
92歳のおばあちゃんが、自分が住んでいた家から施設まで
タクシーに乗り、回り道をして、自分が暮らしてきた
パリの街を周遊するという物語だ。
タクシードライバーは当然、ひと癖ある中年男。
(変な奴が絡まないと、映画として面白くない)
いいおっさんだが、年齢は彼女の半分の46。
いわば息子と孫の中間みたいな、微妙な年齢設定である。
フランスも高齢化社会が進んでいるので、
こうした設定も面白く見える。
そしてまた、彼は当然のように、人生に問題を抱え、
経済的トラブルに苛まれている。
それでも救いは、彼がなんとか家族を守りたいと
考えているところだ。
しかし、タクシードライバーのギャラでは、
とても短期間にこのトラブルを解消しようにない。
つまり、追い詰められているのである。
しかし、ご安心を。
彼はけっして闇バイトに手を染めたり、
乗客であるおばあちゃんを脅したり殺したりして
カネを奪ったりしない。
これはそうした類のブラックなドラマでなく、
コメディ要素の強いヒューマンドラマである。
だから、こうした映画のお決まりで、
最初、ぎくしゃくしていた二人の仲は
しだいに打ち解け、おばあちゃんは
自分の思い出を彼に物語るようになる。
じつはその内容が、かなりブラックである。
僕が驚いたのは、彼女が若い時代、
1950年代のフランスでは、
まだひどい女性差別がまかり通っていたことだ。
何となくではあるが、20世紀にあって、
芸術・文化が発達したフランスは、
世界で指折りの先進的な国で、
女性が大事にされていたーーというイメージがあった。
この映画で語られていることは、
たぶん史実に基づいていることだと思うので、
かなり意外だった。
ほとんど昭和日本と変わらない。
もっとひどいぐらいである。
そして、彼女がより悲惨なのは、
暴力をふるった夫だけでなく、
可愛がった息子にも裏切られてしまうこと。
息子の裏切りは、当時のフランス社会の
現実を象徴しているのだろう。
普通のおばあちゃんのように見えたのだが、
ヘヴィなドラマを抱え、社会の差別と闘って
92歳まで生き延びたのだ。
厳しい人生だったが、
それでも私は良い時代を生きたと、彼女は語る。
そんな彼女の心情を表すかのように、
全編にわたって古いジャズが心地よく流れていく。
最後はとても心あったまる終わりが待っている。
てか、こんなおとぎ話みたいなオチって、
いくらヒューマンタッチの終活映画とは言え、
今どきアリ?みたいな感じ。
でも、人生がこんなおとぎ話で終わるならいい。
観た人の多くが、きっとそう言うと思う。
小学校の演劇発表会の話

演劇をやっていたので、むかしは演劇をよく見た。
しかし最近は、
・義母の介護・面倒で、
仕事以外ではめったに家をあけられない。
・観劇料が高い。
・その割に面白くない。
あるいは面白い芝居が少ないように思える。
3つの理由で、劇場に足を運ぶことは
年に1,2度しかない。
とは言え、演劇には人一倍興味がある。
受け持つ生徒の顔と名前を一発で覚えるという
離れ業をやったのにもかかわらず、
5年生女子から「キモ先生」と言われて
意気消沈してしまった小学校の臨時教師Kくんは、
この秋、演劇発表会の演出をやっている。
彼は大学時代、サークルで演劇をやった経験があるので、
それにもとづき、5年生相手に腹式呼吸やら、
舞台に立った時の目線のことなど、
ビシバシ指導をしているというのだ。
上演する芝居の内容はよく聞いていないが、
小学校なので、もちろん全員参加。
ただ、役者をやりたくない子は、
裏方でもOKなので、
照明や小道具係などを希望するらしい。
登場人物は村人1、2.3・・・みたいな役が多く、
あまり目立ちたくない子は、やはりこれらを希望。
でも、こういう機会に超積極的な、
自己主張の強い子は必ずいる。
このテの子ども、スポーツ分野は男子が多いが、
演劇などの文化・芸能系は、圧倒的に女子だ。
話を聞くと、どうやら主役は女の子で、
魔法を使えるお姫様うんぬんと言っていたので、
「アナ雪」みたいな話なのだろうか?
やる気満々、「あたしはスターよ」
みたいな女の子が3人、
クラス内オーディションで選ばれた。
面白かったのが、女の子の役なのに、
主役の立候補者の中に、男の子がいたという。
僕たちの時代には考えらえなかった。
なかなか勇気のある子だ。
彼はセリフも演技もけっこううまかったようだが、
プロの世界ならいざ知らず、
学校教育の一環である演劇発表会で
ヒロイン役に男の子を配役するわけにはいかない。
残念ながら、彼は落っことされて、
村人1、2.3・・・にされてしまったようだが、
どんな子なのか、なんだかとても気になった。
小学5年生の演劇発表会。
どんな役を希望するのか、
どんな役・どんな係に就くのか、
何かその子のこれからの人生を
暗示しているようにも見える。
もちろん、この時点ですごく引っ込み思案で、
村人1をやっていた子が
数年先に突如覚醒し、大スターになったり、
照明係をやっていた子が
そのままメカ系の道でイノベートして
有力ベンチャーになったりとか、いろいろあり得る。
勉強やスポーツの場とは違う、
可能性の舞台が、演劇の場には広がっている。
ベッソン映画「DOGMAN」は「GODMAN」
犬を自由に操る女装のダークヒーロー。
壮絶なアクション。
監督は「ニキータ」「レオン」のリュック・ベッソン。
ということで、ベッソン特有の
妙に重量感のあるアクションシーン、
そして、目を覆いたくなるような暴力・殺人シーンが
先行して頭に浮かんで、
しばらくためらっていたが、やっと見た。
良い意味で裏切られた。
「ドッグマン」(2023年)は、人間の美しさ、
そして、犬の美しさを描いた、すごくいい映画だ。
これはAmazonPrimeでなく、
映画館で観るべきだったかもしれない。
何と言っても、主役ダグラスを演じる
ケイレブ・ランドリー・ジョーンズが魅力的。
少年時代、彼は父と兄に虐待されて
犬小屋に放り込まれて生活することになり、
障害を負いながらやっと脱出する。
その後、養護施設で、のちにシェイクスピア女優になる
養護員の女性に芝居を通して生きる喜びを学び、
彼女に恋をして成長する。
しかし、そんな彼に世間は決してやさしくない。
やがてドラッグクイーンとなって歌って
アイデンティを保つ一方で、
犬たちと生活するために犯罪に手を染める。
そうした変化の在り様・人間形成の在り様を
じつにビビッドに演じ描く。
また、紹介文や予告編などから、
犬たちは恐ろしく凶暴で、獰猛で
野獣的な犬を想起させるのだが、
意外にもけっこう可愛いのが多い。
随所に人を襲うシーンがあり、
クライマックスのギャングとのバトルでは
それこそ壮絶な闘いを繰り広げるが、
けっしてリアルには描かれず、
ここで出てくる犬たちは、
ファンタジーの領域にいる生き物のように見える。
動物愛護団体の視線もあるので
襲撃・戦闘シーンは、
あまりリアルには描けないという
事情もあるのかもしれない。
ベッソンの映画はアクションやバイオレンスばかりが
取りざたされる感があるが、
彼のドラマづくりは、
いつも人間の美しさ・崇高さを追求している。
そういう意味では、
アクションで売り出す前の出世作「グランブルー」で
前面に出ていたファンタジー性こそ、
ベッソン映画の真髄・醍醐味なのだと思う。
この映画では最後にそれが表出される。
ラスト5分は本当に美しく、
ダグラスは人間を卒業して神になるかのようだ。
そして犬たちがダグラスを導く
天使のように見えて涙が出た。
「DOGMAN」は「GODMAN」。
アナグラムになっているのだ。
一つ気になるのは、全体の雰囲気が
「ジョーカー」(2019年)によく似ていること。
こちらも主役ジョーカー(アーサー)を演じた
ホアキン・フェニックスの怪演が見ものだが、
「児童虐待」「障がい者差別」「貧困との戦い」
これらを物語の根底のテーマに
置いているところも同じだ。
別にパクリだとは思わない。
こうした個人的問題と社会的問題が
ダイレクトにつながって感じられる点が現代的で、
映像系であれ、文学系であれ、
エンタメコンテンツに求められている
現代的役割の一つなのだろうと思った。
ちなみに「ジョーカー」の続編、
『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が
来月、10月11日(金)劇場公開。
なんとレディー・ガガが共演する。
父の日の秘密の花園

前にも書いたことがあるが、
行きつけの花屋の女主人は、
昔の少女マンガに出てくる、
お花屋さんになりたかった女の子が
そのまま夢を叶えて花屋になったような人である。
齢はたぶん僕と大して変わらないと思うので、
客観的に見ればりっぱなおばさんだが、
”お花大好きなの。でも、商売でやっているから
ビジネスライクなところもあるわよ。”
といった絶妙なブレンド感が漂い、
なかなかかわいい上に味がある。
40年前に逢っていたら恋に落ちていたかもしれない。
ふらっと店に入ると、いつもの黒いエプロンをつけ、
長い髪をひっつめにして、いつものように淡々と、
けれどもお花大好き感を醸し出しながら作業している。
狭い店内は季節柄、青い紫陽花が幅を利かせており、
他の花はそれに押しのけられるように
小さくなっている。
何となくとっちらかった印象だが、
花が呼吸し、人間には聞こえない言葉で
いろいろお喋りしてるような雰囲気がある。
今日は父の日なので
「父の日に花を贈る人はいないんですか?」
と聞いてみたら、
「いないですね、ほとんど」と、つれない返事。
「最近は子育てするお父さんも増えたので、
むかしより認知度上がっているはずなんですけどねー。
やっぱ父の日はお花よりお酒ですよね」
そこで前々から気になっていたことを聞いてみた。
「『お父さんだってお花が欲しい』とか、
そんな宣伝出したら売れないですかね?」
と水を向けると、
「うーん、どうでしょう?
あんまり忙しくなっても困っちゃうんで、
うちはやらないですね。
母の日もぜんぜん宣伝しないんですよ。
商売っ気がなくてすみません」
と、なぜか謝られてしまった。
へたに宣伝してカーネーションなどが
山ほど売れ残っても困る。
けっこうしっかり者で、コスト意識が高そうだ。
そして、確かに商売っ気はあまりない。
じつは僕もそこが気に入っている。
この花屋は僕が知る限り、
近辺の花屋のなかでいちばん値段が安い。
他の花屋は、ぜいたく感・贈り物感を
演出するところが多いが、ここは庶民派というか、
「さりげない日常という庭に咲く花」を
大事にしている感がある。
家に花を飾るのはぜいたくではない。
花は心の栄養剤になるのだ。
極端な話、おかずを一品減らしてでも、
部屋のどこかに生きた花を飾ったほうが
生活のクオリティが上がるのではないだろうか。
そんなことを考えていたら彼女は、
「わたし自身は、母の日も、父の日も、
お花はもちろん、
なーんもあげたことなんてないんですよ」
と言って笑ってのけた。
おとなになった少女マンガの花屋の娘は
なかなかミステリアスで奥が深い。
秘密の花園のなかで悠々と生きている感じがする。
宇野 亞喜良の世界とアングラ演劇

「90のじいさんになっても少女を描いているって
変態だよね」
先日テレビで、美術家の横尾忠則と
イラストレーターの宇野 亞喜良が
話していたのをチラ見した。
前述のセリフは横尾氏が宇野氏に言ったもの。
16日の日曜まで東京オペラシティのアートギャラリーで
宇野 亞喜良展をやっているので、
それに関連した番組だったようだ。
「変態」なんて言われて、
さすがにムッとした表情を見せていたが友達同士だし、「(常識的なことにとらわれない)天才」の、
横尾流の表現なので、
特にケンカになることもなく対談は続き、
最後はいっしょにメシを食うところで終わっていた。
宇野 亞喜良の絵の世界の主役は女性だが、
別に少女専門というわけでなく、
大人の女も描いている。
寺山修司の本や演劇の美術もよくやっていたので、
寺山流に言えば「青女(せいじょ)」が多い。
青女とは、「少年」に対して「少女」があるように、
「青年」に対して「青女」という言葉があっていい。
そう言って寺山修司が1970年代に出した
「青女論」というエッセイに出てきた言葉だ。
宇野 亞喜良の描く女の絵の特徴は、
笑わない顔と奇妙にアンバランスな体型。
笑わない顔は「大人や男に媚びない表情」と
よく言われる。
重心が下りていない、アンバランスな体型は、
女になりきっていない少女・青女特有のもの。
どこの画家か漫画家か忘れたが、
「少女の体型がアンバランスに見えるのは、
この世界に存在することにまだ慣れていないからだ」
といった類のことを言っていて、
ちょっと感心したことがある。
クリエイターが好んで描いて見せる、
10代後半の女の子特有の透明感とか、
ちょっとミステリアスな雰囲気は、
そういうところと繋がって
醸し出されるのかもしれない。
僕も熱心なファンというわけではないが、
寺山修司が好きだったこともあり、
宇野 亞喜良の絵は昔からよく目にしてきた。
イラスト・美術の世界ですでに60年以上、
第一線で活躍してきた人だが、
その魅力はまったく色あせない。
横尾忠則もそうだが、このレジェンド美術家たちは、
本当に最後の最後まで
現役の「変態じいさん」を貫きそうだ。
そんな宇野 亞喜良氏の最新作か。
先日、唐組の紅テントの芝居を見た時、
彼のイラストが載ったチラシをもらった。
今週末から花園神社で始まる新宿梁山泊の
「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」。
唐組の紅テントに対して、こちらは紫テント。
寺山修司でなく、唐十郎の状況劇場時代の芝居で、
豪華キャストが出演する。
たぶん連日満員大入りだろう。
宇野 亞喜良の、アンバランスで媚びない女たちの世界
(そしてたぶん横尾忠則の世界も)を培ったのは、
やはり1960~70年代のアングラ演劇カルチャーという
肥沃な土壌だったのだろうと思う。
ネコのタマはタマなし?

たまたまタマなしネコの話を調べることになり、
タマなしのオスの生きる道について考えてみた。
今回ここでいう「タマなし」とは
動物の去勢のことで、ジェンダー問題とは関係ない。
今どき都会で飼われるイヌやネコは、
ほぼほぼ愛玩用で、自然の状態から切り離し、
人間社会に組み入れるわけだから、
その辺に出て行ってヤリまくって
子供がうじゃうじゃできると困る。
そういうわけで避妊・去勢もやむなし、と考えられている。
ちょっと古いが、2017年の調査によると、
避妊・去勢手術をしたイヌは全体の約5割、
ネコは8割だという。
これは多分、飼い方の違いだろう。
イヌは外出の際、必ず飼い主といっしょだが、
ネコは勝手に出歩くことが多い。
それで雄雌がくっついてやっちゃうからだ。
「去勢」という言葉には心がざわつく。
男子なら誰でもそうだろう。
実際、雄イヌ・雄ネコの男性飼い主は
「そんな可哀そうなことできるか」と
反対する人が多いらしい。
それに対してメスの避妊にはあまり反対しない。
可愛い娘がその辺の男とやっちゃってできちゃったら
大変だという、父性愛(?)の由縁だろうか?
人間同様、イヌもネコもお年頃になると、
脳内にホルモンがドバドバ出て、
やりたくてたまらなくなる。
オスの立場に立つと、
強烈なフェロモンを発散しているメスに遇ったのに
ガマンを強いられると、頭狂いそうになるかもしれない。
これは人間も同じで、男の人生の半分は、
そうした己の性欲との戦いとも言えるのだ。
実際、イヌ・ネコも未去勢だとストレスが溜まって
暴力的になったり、
夜鳴きやマーキングなどの問題行動が増えるらしい。
だから男の子のイヌやネコと
なかよく平和に暮らしたければ、
できるだけ性欲に悩まされないよう、
去勢しておっとりした子にしたほうがいい――
という意見が優勢に見える。
でも、タマなしネコだと
ネズミを捕らなくなっちゃうのでは?
と思ったら、そんなことはなく、
狩猟本能そのものには大きな影響を与えないようだ。
今どき、ネコをネズミ駆除用に飼う家は少ないと思うが、
せっかくいるのなら役立ってくれれば、
それに越したことはない。
これ見よがしに血まみれの獲物を持て来られると
嫌かもしれないけど。
動物病院のネコの去勢手術の動画を見たら、
麻酔をかけて結構簡単に済ませていた。
ただ手術後、そのネコが股の間を舐めていて
「あれ、タマないぞ」と気付くシーンには、
やっぱちょっと胸が切なくなったな。
ちなみに家畜のブタやウシのオスも
少し成長すると、オス独特の体臭がついて
肉の味を落としてしまうため、去勢する。
しかし、こちらの場合、
日本ではまだ麻酔をかけずにやっているので、
アニマルフェアウェルの観点から問題視されている。
肉の味をよくするために男の子のブタ・ウシが
タマを切られて痛い思いをしているのを想像すると、
けっこう複雑な気持ちになる。
業者の人たちは、一生懸命おいしい肉を作ろうと
努力してやっているのだが……。
前のめりになって生きて死ね

本日の名言
「事実がたとえわかっていなくとも、
とにかく前進することだ。
前進し、行動している間に、事実はわかってくるものだ」
この名言の主ヘンリー・フォードは、
20世紀アメリカの自動車王。
要するにわからないと考えこむのではなく、
まず行動しろということ。
たぶん自己啓発リーダーの人たちも好んで使うフレーズだ。
そうだ、その通りだと思いつつ、
僕がこの名言を目にして連想したのは、
子供の頃に見た野球マンガ「巨人の星」の1シーンである。
それは主人公・星飛雄馬(ピッチャーです)の父・一徹が、
かの坂本龍馬の死について語るシーン。
一徹は投手生命に関わる
飛雄馬の欠点(球質が軽い)に気付き、
問い詰める息子に対して坂本龍馬の逸話を持ち出し、
「たとえドブの中で死んでも、なお前向きで死ぬ、
それが男だ」と語る。
その一徹のセリフに合わせて画面では
路上で暗殺者に襲われ血まみれになった龍馬が、
ドブの中で倒れながらも、這いつくばって前進しようとし、
ついに息絶えるという壮絶なシーンが描かれた。
当時はスポーツ根性マンガ全盛時代だったので、
一徹のセリフと、前のめりになって倒れる龍馬の表情は、
強烈に子ども心に染みた。
というわけで小学生当時、「巨人の星」を見ていた僕は、
長らくの間、これが坂本龍馬の最期だと思っていたのだ。
ところが事実はご存知のとおり、
料理屋の2階でしゃも鍋をつついていたところを
襲われたので、ドブの中で倒れようがない。
いや、もしかしたら瀕死の状態で店から這い出し、
路上にあったドブに落ちたのか?
とも考えたが、やっぱりこの話は
原作者・梶原一騎の創作だったようである。
厳密にいうと、梶原一騎はどうやら
司馬遼太郎の名作「竜馬がゆく」を読んで、
その一文にある
『男なら、たとえ溝の中でも前のめりで死ね』
をアレンジして使ったようだ。
もともと司馬遼太郎は歴史学者とか研究家ではなく、
あくまで歴史作家なので、エンタメになるよう、
史実にかなり自分のアレンジを加えている。
昭和以降の龍馬像をつくり上げ、
国民的ヒーローに押し上げたのも司馬遼太郎の功績。
梶原一騎はその功績をスポ根ドラマに
うまく取り入れたということだろう。
ちなみにこの「龍馬 前のめりで死ぬ」説は、
僕と前後する世代の人たちに
かなり大きな影響を与えたらしく、
小説家の有川ひろ(1972年生まれ・高知県出身・女性)が
「倒れるときは前のめり」という
題名のエッセイ集を出している。
寄り道が長くなったのでもとに戻す。
仕事にしても、生活にしても、
一歩一歩コツコツが大事なのはわかる。
ただ、視野を広げて人生全般を見た場合、
僕は若い頃、いずれ齢を取れば、
いろいろわからないことが
だんだんわかってくるのだろうと思っていた。
ところが現実は真逆で、
どんどんわからないことだらけになっていく。
死ぬまでに世の中の事実・真実がわかるのか?
と問われたら、ほとんど絶望的。
しかし絶望してても始まらないので、
何はともあれ、生きて一日一日大切に、
死ぬまで一歩一歩あゆむのみ。
一歩進むと二歩下がっちゃうんだけどね。
★エッセイ集:生きる 第5集
「死ぬな!きみの地球を守るために(仮題)」
Amazon Kindleより近日発売予定。
唐組公演「泥人魚」観劇記
先月亡くなった劇作家・唐十郎さんの供養もかねて、
新宿・花園神社に唐組の公演「泥人魚」を、
観に行ってきた。カミさん・息子が同伴。
この時代になると、テント芝居は貴重なアナログ体験だ。
●すべて人力のアングラテント演劇
切符の販売とか、精算方法(現金のみ)とか、
入場整理(劇団員が大声を上げて整列させる)とか、
デジタルでもっと効率的にやる方法があるのでは・・・
と思うが、たぶんないのだろう。
それにこういうやり方を続けてほしい、
という客の願いもある。
テントという、日常と異なる異空間に侵入するためには、
それなりの段取りが必要で、
すんなり簡単に事が運んでしまっては面白くない。
言い換えれば、忙しくて時間が取れない、
もっとタイパを良くしろという人には味わえない、
アナログ・人力ならではのぜいたく感が味わえる。
ござに座って見る昔ながらのアングラ式桟敷席に
(おそらく)500人くらいが詰め込まれたテント内は
現代の高齢化社会の縮図のような風景で、
半数近くが僕の同年代(60代)以上。
残りの半数がそれ以下で、男女比は半々か、
男性がちょっと多めかなという印象だ。
息子(20代後半)やそれ以下の若者もけっこういて、
中には高校生らしき子の姿もチラホラ
(学校帰りなのか、制服を着ていた)。
「入場料:子供2000円」とあったが、
さすがに子どもはいなかった。
でも、子供がこうした観劇体験をしてもいいと思う。
●状況劇場の幻影
僕は李麗仙・根津甚八・小林薫などが活躍していた
70年代後半~80年代初めの状況劇場に洗礼を受けている。
そのため、唐さんの芝居作品にはどうしてもあの頃の、
卑俗なものを聖なるものに転換させる、
リリカルでスケールの大きい幻想ロマンを求めてしまい、
唐組以降の作品にはイマイチ魅力を感じてこなかった。
けれどもこの「泥人魚」という作品には、
状況劇場時代の作品とは全く異なる魅力があった。
●諫早湾「ギロチン堤防」から生まれた物語
モチーフになっているのは、
「ギロチン堤防」という呼称が衝撃的だった
1997年の長崎県諫早湾干拓事業問題。
湾と干拓地を遮断する293枚の鉄の板(潮受け堤防)が
すごいスピードで次々と海に落とされていく
ギロチンシーンはかなりのインパクトがあり、
人々の関心も高かった。
(テレビのニュースなどで放送された)。
これはもともと戦後間もない頃に農地を増やすため、
国が計画した干拓事業、いわば国家プロジェクトだ。
これによって、かつて「豊饒の海」と言われた
諫早湾の環境は一変して、漁獲量は激減。
漁業者と農業者との対立をはじめ、
損得を巡って地域住民の深刻な分裂が起こり、
20年あまりにおよぶ長い裁判になった。
●ドキュメンタリーを重視した劇作
唐さんはその裁判が始まった2002年9月に
諫早湾まで取材に行き、自分の目で現地の海を見て、
この戯曲を書いた。
その経緯は、新潮社から出版されている戯曲のあとがきに、
また今回の観劇プログラム掲載の、
演出・久保井研氏のコラムに書かれている。
ちなみにこの久保井氏のコラムは、
唐組における劇作活動の様子が垣間見えて興味深い。
唐さんは、状況劇場の時代は自分が生まれ育った、
終戦直後の東京の下町の風俗や人々の暮らしと、
思春期から学生時代の文学・芸術体験をベースに、
60年代・70年代の世情を取り入れて
独自の劇世界を構築していた。
しかし、1988年に始まった唐組時代の作品では、
その時代ごとにクローズアップされる
現実の社会問題に材を取り、
いわばドキュメンタリー的な要素に重きを置いて
みずからの劇世界を継続・進化させていったようだ。
とはいっても、舞台に上る成果物は、
やはり常人には真似できない
妄想ワールドであり、イメージコラージュである。
「ギロチン堤防」という現実の材料から、
人魚姫、天草四郎、ハリーポッター
(2002年当時大ブームだった)など、
次々と出てくる連想がキャラになり、セリフになり、
アクションになり、劇世界をかたち作る。
あとは観客がどこまで想像力を駆使して
それについていけるかだ。
●もののけ姫と泥人魚
これはもちろん、紅テントで上演することを前提に
書かれた作品だが、普通の劇場でやっても、
あるいは映画や映像+詩みたいな作品にしても
面白いのではないかと思った。
もちろん、その場合はアレンジが必要だと思うが、
人々がネットの世界など、より現実と乖離した人工環境に
(精神的に)移り住み始めたこの時代、
海・地と人の日々の暮らしとが
緊密に繋がっていた時代の記憶を綴るこの物語は、
ある種の普遍性を孕んでいるのだ。
ちなみにいっしょに見た息子の感想は
「要するに『もののけ姫』だよね」。
うん、その通りとは言わないけど、そう遠くはない。
若い世代の感想としては面白いと思う。
みんな気にしているテーマなのだ。
終幕、ブリキの鱗を作り続ける男の口から
最後にこぼれ落ちるセリフ、
そしてお決まり通り、テントの背景が開いて
劇世界と現実の風景と溶け合うラストシーンは、
やはり状況時代と変わることなく、
卑俗なるものを聖なるものに変え得る、
唐作品独自の力と美しさに溢れている。
劇団ホシ灯りの朗読劇「マクベス」
めっちゃ美女なのに、めっちゃ邪悪。
どうせいつか死ぬのなら、
そういう女に溺れて死にたい。
――というのは男子なら一生に一度は見る夢。
(そんなことない?おれだけ?)
そんな妄想を広げていたら
頭のどこかから
「きれいはきたない、きたないはきれい」
というセリフが響いてきた。
ご存知、シェイクスピア劇「マクベス」の
オープニングに登場する魔女のセリフ。
久しぶりに「マクベス」を読みたくなったが、
手元にないので、YouTubeを覗いてみたら、
朗読劇がアップされていた。
「劇団ホシ灯り」という所はまったく知らなかったが、
聴いてみるとなかなか気持ちよく聴ける。
手だけ動かしていれば進められる
単純な仕事ならBGMとしても利用できる。
改めてシェイクスピアの劇は素晴らしいと思うとともに、
余計なビジュアルがない分、
ストレートにセリフが伝わってくるのもいい。
もちろん、マクベスのストーリーを知っているからだが、
脚色も朗読劇用にかなり圧縮して
上手く作っていると思う。
シェイクスピア劇の面白さを
従来とは違う角度から味わえる気がする。
気になって「劇団ホシ灯り」を調べてみたら、
どうもこの脚色・監督の女性がひとりで
やっているらしい。
劇団ひとり?
役者はそのプロジェクトごとに集めてくるのだろうか?
いずれにしてもなかなか面白いので、
他のも聴いてみようと思う。
犬と息子(娘)との上下関係について

先日、川沿いの公園で体長1メートル強、
体重は20キロ弱ありそうな秋田犬を散歩させている
高校生か大学生と思しき男の子に遇った。
ところがその犬、疲れたのか、
その場所が気に入ったのか、
あるいはご機嫌を損ねたのか、
途中で道の真ん中に座り込んで動かなくなった。
「おい、どうした?行くぞ、行こうよ」と、
彼が何度もなだめすかそうとも、
ハーネスのリードを引っ張ろうとも、
泰然自若としていて、
とうとうその場で寝そべり始めた。
「某は動きたくないでござる」という感じ。
歩き方や全体の雰囲気からして、
シニアっぽい犬だったので、
ゆうに10歳は超えていると推察する。
ということは彼が子犬だったころ、
今連れて歩いている若僧はまだ小学校の低学年。
親からはもちろん子ども扱いだ。
犬は上下関係に厳しい。
家のなかで息子は最低の地位。
彼がまだチビの間に犬はおとなになり、
自分はこいつより地位が上だと思っている。
息子が大きくなって、だんだん両親と対等になっても、
犬の意識は「おれは上、あいつは下」のままだろう。
だから坐りこんで
「なんで某が下っぱの貴君の言うことを
聞かねばならぬのか」となる。
困った彼はしたかたなくその犬を抱きかかえて
歩き出した。
とはいえ、20キロ近くあろう大型犬なので
そのまま家に帰るのは大変だっただろう。
それにしても、もし何らかの事情で、
それまでの主人である父や母が家からいなくなり、
息子(あるいは娘)と犬だけの暮らしになったら、
二者の関係はどうなるのだろうか?
犬の意識は「これからはおれは下、あいつが上」
に変わったりするのだろうか?
あるいは若殿(姫君)と
年長の家来みたいになったりするのだろうか?
飼い主さんで、もし知っている人がいたら
教えてください。
糸姫/状況劇場
YouTubeで状況劇場の音源が上がっていたので、
思わず聴いてしまった。
1975年秋の公演「糸姫」の千秋楽の舞台。
じつはこの「糸姫」は僕らが演劇学校で上演した
唐作品の一つ(1979年7月)である。
紡績工場の女工と、
労働の価値を考える
しがないサンドイッチマンの男を中心に、
怪しい整形外科病院、
アドルフ・ヒトラーを狂信する院長、
紡績会社の跡取りのバカ息子、
そして、整形手術に失敗した女たちが
リボンの騎士となって登場。
地獄の天使ヘルスエンジェルスの
バイクまでが舞台を走りまわる
恐るべき妄想コラージュ。
とは言え、ちゃんと筋の通った物語になっていて、
2時間観客をくぎ付けにするのが、
唐十郎作品のすごいところ。
脚本(戯曲)はもちろん読んでいるが、
こんなライブ音源を聴くのは初めて。
かなりぶった切られていて、
たぶん半分強の尺になっているが、
見せどころ(聴かせどころ)はちゃんと抑えている。
それに相当良い席で録音したらしく、
50年近く前の録音と思えないほど音質が良い。
主役の絵馬(エマ)は李麗仙。
相手役の価(アタイ)は根津甚八。
二人ともめっちゃカッコよくて
改めてしびれて聞き惚れてしまった。
あまりに生き生きしているので、
どちらもこの世を去って久しいなんて信じられない。
唐さんが作る独特のリズムのセリフの群れは
美しい音楽のようだ。
また、最後に挨拶する唐さんの声が若々しく、
いたって“まともな人”のように聞こえるのが
なんだか面白い。
そして当時の観客の熱狂的な雰囲気も
きちんと記録されている。
ポスターは“ゲージツ家”篠原勝之。
唐十郎ワールドはインスピレーションを
いたく刺激するらしく、
横尾忠則以降、多くの美術家がポスター、チラシの
デザインを担当し、
その魅力的な絵も状況劇場の人気の一要素だった。
どうやら最近、これらのポスターは美術品扱いで、
ネット上でかなり高値で取引されているらしい。
また、クマさんこと篠原勝之氏は、
この戯曲を原作として同名の漫画本を出している。
「糸姫」とまた出会えて、とても嬉しい。
いま、だれが地球と人類を救うのか?
小惑星が地球に落ちてくる。
激突すれば人類滅亡は必至。
それを回避するには小惑星の真ん中に
核爆弾をぶちこみ、破壊するしかない。
そのミッションを担ったのは、
石油採掘会社の、ろくでなしだが愛すべき男たち。
地球を、人類を、愛する人たちを救うために
男たちは悲壮な覚悟を持って宇宙空間に旅立った・・・
1998年公開のアメリカ映画「アルマゲドン」は
20世紀カルチャーてんこ盛りの、
ハリウッド映画のお手本のような作品だ。
エアロスミスが歌うドラマチックな主題歌
「ミス・ユー・シンク」も泣かせる。
このPVを見れば5分で
2時間の映画を見た気分になれる。
この手の20世紀映画で人類の危機を救うのは
みんなアメリカ人だ。
アメリカで作っているのだから当たり前だが、
やはり日本人や他国の人たちでは、
なかなかこうした地球大・宇宙大のスケールで
愛と正義と救済の物語は描けないのではないかと思う。
なぜかといえば20世紀、
現実の世界でアメリカが
「世界の警察」の役割を担っていたからだ。
それはアメリカがイギリスと共に
19世紀・20世紀の世界を形づくった責任から――
と言えなくもないのではないかと思う。
その役割がおかしくなり、やがて放棄するに至ったのは、
2001年の9・11同時多発テロがきっかけだった。
あのあたりからだんだんアメリカの関心は内へ向かい、
自分たちさえよければ他はどうでもいいや、
というふうに変わってきたのではないか。
日本人をはじめ、どの国の人たちもみんなそうだが。
「世界の警察」という意識には独善的な面が多々あり、
困った問題もたくさん引き起こしたが、
それでもやはり広く見れば、
アメリカのが言う“正義”によって
世界はバランスを保ってこられた。
今起こっているロシアとウクライナとの戦争、
イスラエルとハマスとの戦争は、
やはりアメリカが警察の役目を放棄したことが
大きな要因の一つになっているような気がしてならない。
21世紀になって、地球を救う者・人類を救う者は
いなくなってしまった。
「アルマゲドン」が旧態然としたハリウッドの
おめでたい予定調和映画と批判するのは簡単だが、
もう一度、未来のために
誰がどうやって地球を・人類を救えるのか考えてみたい。
唐十郎式創作術「分からないことに立ち向かう」

長年書き続けた理由を尋ねると
「分からないことに立ち向かうためです」と言い切った。
一昨日、亡くなった唐十郎さんが
記者に向かって言ったセリフ。
カッコいい。
わかっているから書く、のではなく、
わからないことを自分に問い、文字にする。
わからないから書き続ける、創作し続ける。
すると脳の奥深くにある泉から物語が湧き出てくる。
また、別の記事では、
「僕は書きながら考えていくんです。
テーマ、モチーフを決めないで、
1点だけ入り口を見つけて、あとはペンが走るまま」。
天才だからそうやってできたのだ、
と言えばそれまでだが、
作品のレベルは違えど、
僕にもそういうふうに書けることがある。
誰でも自分の中に表現するための水脈を持っている。
要は掘り進める勇気と技術があるかだ。
どこをどう掘れば水脈に当たるか。
唐さんは熟知していたのだろう。
その脳の奥にある泉は広く、深く、
自分を掘りまくって膨大な作品を残した。
芥川賞をはじめ、数々の文学賞を獲りまくったが、
小説もエッセイも映画もテレビも
唐さんにとってはオマケみたいなもの。
メインの仕事、主戦場は、
あくまで自分が主宰する紅テントの芝居—ー
状況劇場・唐組で上演する戯曲であり、
演出であり、出演で、
最後までいっさいブレることはなかった。
大学教授などもやったが、それも人生の付録みたなもの。
自分では教授役を演じている、
といった意識だったのではないだろうか。
華やかな場所や国際的な名声にも興味がなかったようで、
とにかく死ぬまで芝居をやり続けられられれば満足、
幸せだったのだと思う。
唐さんの訃報を聴いた後、
どうも落ち着かず、仕事も進まない。
きょうは少し昼寝をしたら、
状況劇場の芝居を観に行ったときの夢を見てしまった。
年内に唐作品のオマージュのようなものを書きたい。
山田詠美 入門編 「タイニー・ストーリーズ」
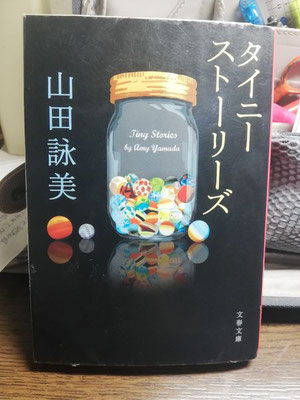
山田詠美はよくも悪しくも
デビュー作「ベッドタイム・アイズ」や
直木賞受賞作「ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー」が鮮烈過ぎた。
そのせいで黒人との恋愛・セックスを描く
女性作家という、偏見に満ちた、
スキャンダラスなイメージがついてしまったようだ。
白人にぶら下がる女はいいが、
黒人に寄っていく女はふしだら――
彼女が若い世代の作家として活躍した
1980年代から90年代はまだまだ
そうした“名誉白人”的な偏見・差別が
日本人の心の奥でとぐろを巻いていた時代だ。
僕はその後に出された「風葬の教室」
「晩年の子ども」など、
子どもを主人公にした物語が好きで、
山田詠美に対してはその側面の評価もけっこう髙いはず。
けれども、世間的にはやはり
「ベッドタイム・アイズ」のイメージが
べったり貼りついたまま、
ここまで来てしまったのではないかと思う。
それでも山田詠美は偏見的なレッテルなど
自らはがせる優れた作家で、
とてもバラエティ豊かな物語を描ける人だ。
コミカルなものからメルヘン、家庭劇、恋愛劇、
ちょっとセクシーなもの、SFチックなものまで、
21の短編からなるこの本は
そんな彼女の魅力を詰めこんだ、
詠美ワールドの入門編としておすすめ。
その中の一編「GIと遊んだ話(2)」を読んだら、
デルフォニックスの
「ラ・ラ・ミーンズ・アイ・ラブ・ユー」が
聴きたくなった。
いろんなミュージシャンがカバーしているが、
これがオリジナル。
クールで短い物語の中から
音楽が流れ出してくる筆致の素晴らしさ。
ぜひ味わってみて下さい。
あなたもわたしも呪い人? 「呪いを解く者」

フランシス・ハーディングという
イギリスのファンタジー作家の作品。
テーマはズバリ「呪い」。
舞台は架空の国で、イメージとしては中世ヨーロッパ。
主人公は呪いの「ほどき屋」の少年と、
呪いをかけられた少女。
この世界には呪いをかける「呪い人」がいて、
それを束ね、利用しようとする悪のボスが登場する。
呪いをかけられた人は動物などに変身したり、
この世界に生息する奇妙なクリーチャーが
いろいろ出てきたりして、
全体の印象は、そこはかとなく
「ハリーポッター」を想起させる。
僕が面白いなと思ったのは、
そうしたファンタジックなストーリー展開や
冒険劇、敵とのバトルよりも、
「呪い」というテーマそのもの。
中世風ファンタジーの衣をまとったこの物語で
扱われる「呪い」は古典的な感じではなく、
ひどく現代的で、僕たちが身に覚えのあるものだ。
家族間や仲間同士の支配・被支配、
夫婦間のDV、子どもへの虐待、親への憎しみ、
そして幸福な(と映る)人に対する妬み・嫉み。
もちろん古今東西、呪いというものは、
人間の性のようなものだが、
読みながらこれはほとんど
今の日本の状況ではないかと思えた。
もし、この物語の「呪い人」のような
力を持ってしまったら、
それを行使する人はきっと後を絶たないだろう。
そして、この呪いの力はある種、最強のサイコ兵器で、
悪意を持って利用しようとする輩が
大勢出てくるに違いない。
呪われる側はもちろん、呪わずにいられない人、
そしてこんな力を持ってしまった人たちの
悲しさが胸に残る。
文中に「呪いの卵」という表現があるが、
情報化・格差・競争・・・そんな社会で日々を送るうちに、
僕らは知らぬ間に自分の中に
「呪いの卵」を孕んでしまっている。
現代は誰もが表向き善良な市民である同時に、
怖ろしい「呪い人」の予備軍でもあるのだ。
陰惨で悲劇的な部分も多いが、
ファンタジー物語としてはけっこう華があるので、
映画化すると面白いのではないかと思う。

再読・嵐が丘
おりべまこと
エミリー・ブロンテ「嵐が丘」や
スティーブン・キング「スタンド・バイ・ミー」など、かつて読んだ名作を再読してみたら新たな発見が!
還暦ならではの物語エッセイ集。
AmazonKindleより発売中。¥300
春休みは勝手にアート

東京では今年は桜が咲く中で
入社式・入学式を迎えられそうだ。
春は桜だけじゃなく、いろんな花が咲く。
春休みの子どもたちが勝手に作るアートも楽しめる。
●おりべまこと電子書籍 おとなも楽しい少年少女小説
春休み無料キャンペーン いよいよ最終日へ。
3月31日(日)15:59まで!
この機会にぜひ読んでみてね。
★オナラよ永遠に
好きな女の子に恥をかかせたくない!
そう思ってオナラの罪をかぶり、
ヘーコキ野郎の汚名を着せられた救太郎が
未来から参上したヘーコキサイボーグとともに
人類を救うために活躍する愛と笑いのSF冒険劇
★ピノキオボーイのダンス
見た目は12歳だが、
淋しさとむなしさを抱えた人間たちの虐待を受けて限界に。
故障し廃棄されたレンタルロボットの少年を
拾ったのは年老いたダンサーだった。
二人の師弟愛を中心に、AI・ロボットが発達した
近未来の人間とマシンに宿った魂の行方を描くSFドラマ。
AI・ロボットは人類の子ども
今月は2021年に携わったAI関連の仕事を手伝っている。
3年前はまだ異物感のあったAIだが、
ChatGPTの登場以来、急速に社会に馴染んできた感じ。
だからもう後戻りはできないと思う。
AI、そしてこの後に進化して
普及してくるであろうロボットは、
これまでの人類のさまざまな
ストーリーの情報を吸い込んだ、
いわば「人類の子ども」である。
優れた能力、そしてまた怖ろしい能力を持つ
子どもたちに対して
僕たちはいつまでもありがたがったり、
ビビッたりしてばかりはいられない。
これまでの対立的な態度を変えて
ともに生きることを考えていかなくてはいけないだろう。
AI・ロボットといっしょに
この先、僕たちは何をするのか、したいのか?
たぶん、まだ誰もわかっていない。
おりべまこと電子書籍
おとなも楽しい少年少女小説
続・春休み無料キャンペーン7Days パート2:
3月28日(木)16:00~31日(日)15:59
★ピノキオボーイのダンス
廃棄されたレンタルロボットの少年と
年老いたダンサーとの師弟愛を中心に
近未来の人間とロボットの魂の行方を描くSFドラマ
★オナラよ永遠に
好きな女の子のオナラの罪をかばった救太郎が
未来から参上したヘーコキサイボーグとともに
人類を救うために活躍する愛と笑いのSF冒険劇
おりべまこと電子書籍 続・春休み無料キャンペーン7Days
子どもを主人公にした おとなも楽しい少年少女小説
長編4作を本日3月25日(月)16:00から7日間にわたって
0円でご購入できます。
パート1:3月25日(月)16:00~28日(木)15:59
★いたちのいのち
カナコは10歳。小学4年生。
一人娘の子育てに悩まされながら、
生活を支えるのに忙しい母親マヨと二人暮らしをしている。しかしもう一人というか一匹、一緒に暮らす同居者がいる。その名は「イタチ」。ペットのフェレットだ。
学校でも家でも口をきかないカナコにとって、
イタチは唯一、心を開いて話ができる親友であり家族だ。
子どもからちょっとおとなに変わっていくカナコと、
天使の目を持ったまま生きるフェレットのイタチ。
それぞれの視点から代わる代わる、
日常生活とその中で起こる事件の数々、
そして、ふたりの別れまでのストーリーを描く。
表紙イラストは「ほっと・ペットクリニック」
「あしたはハッピードッグ」など、
動物もの作品を多数発表している漫画家・麻乃真純が制作。
★ちち、ちぢむ
ケントの11歳の誕生日、
プレゼントを持ってきてくれるはずだったお父さんは、
身長9センチの「ちっちゃいおじさん」になって現れた。
どうしてお父さんは小さくちぢんでしまったのか?
いや、じつはお父さんだけではない。
今、社会の役に立たなくなった男たちが、ある日突然、
カエルサイズにちぢんでしまう怪現象が多発している。
将来、生物学者をめざすケントは、
「ちぢむ男=ちっちゃいおじさん」は、
やりたい放題のホモサピエンスを
これ以上のさばらせないという地球の意志によって
生まれているのではないかと推理する。
アベコベ親子の奮闘を描く奇々怪々でユーモラスな物語。
パート2:3月28日(木)16:00~31日(日)15:59
★オナラよ永遠に
好きな女の子のオナラの罪をかぶった救太郎が
未来から参上したヘーコキサイボーグとともに
人類を救うために活躍する愛と笑いのSF冒険劇
★ピノキオボーイのダンス
棄てられたレンタルロボットの少年と
年老いたダンサーとの師弟愛を中心に
近未来の人間とロボットの魂の行方を描くSFドラマ。
もうすぐサクラの季節。春休みは遊び+読書でGO!
おりべまこと春休み無料キャンペーン続行!4作品を7日間連続で
「今はまだ地球がふるさと」
無料キャンペーン終了しました。
ご購入ありがとうございます。
よろしければレビュー欄へ感想をお寄せください。
さて、好評につき、おりべまこと作品
春休み無料キャンペーン続行します。
子どもを主人公にした長編4作を
明日から7日間にわたってご購入できます。
パート1:3月25日(月)16:00~28日(木)15:59
★いたちのいのち
https://amazon.co.jp/dp/B08P8WSRVB
小4の少女カナコとペットの「イタチ」との
魂の交流を描く友情ファンタジー。
★ちち、ちぢむ
https://amazon.com/dp/B09WNC76JP
「ちっちゃいおじさん」になってしまったお父さんと
息子ケントとの親子愛を描く小人冒険劇
パート2:3月28日(木)16:00~31日(日)15:59
★オナラよ永遠に
https://www.amazon.co.jp/dp/B085BZF8VZ
好きな女の子のオナラの罪をかばった救太郎が
未来から参上したオナラ男とともに活躍するSF冒険劇
★ピノキオボーイのダンス
https://www.amazon.co.jp/dp/B08F1ZFLQ6
ロボットの少年と老ダンサーとの
師弟愛を中心に展開するSFストーリー。
もうすぐサクラの季節。
春休みは遊び+読書でGO!
ジジババとUFOについて語り合おう

齢を取ってよかったなと思うのは、
子どもから年寄りまで全世代にわたって
特に抵抗なく登場人物を書けるようになったことだ。
この話に出てくる年寄りコンビは、
書いていくうちにどんどん生き生きしてきて、
われながら面白くて愛すべきジジババになった。
二人はお茶を飲んでせんべいをかじりながら、
なぜ現代人はUFOを見たがり、心惹かれ、
時には乗り込みたくなるのかについて
真剣に討論したりする。
そしてそれぞれ驚くべき顛末を迎える。
これなら齢を取るのも怖くない。
今はまだ地球がふるさと
おりべまこと
電子書籍 Amazon Kindle 長編小説
https://amazon.co.jp/dp/B0CW1FWZ59
14歳の女の子の
夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く
青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
春休み無料キャンペーン
いよいよ明日3月24日(日)15:59まで。
この機会をぜひお見逃しなく。
泣かない ハグしない 走らない
この話の主人公のリコは、やたら何度も泣き、
母親や友だちを抱きしめ、むやみに走ったりする。
ちょっと多過ぎるなぁと思って、
推敲しながら何度か、どこか削ろうとしたがだめだった。
彼女の自然な感情を潰すわけにはいかない。
きっとこの3つが僕が齢を取るうちに失ったものだ。
ま、女の子じゃないので、
もともと泣いたりハグしたりはできないが。
「走る」については、
ほぼ毎日、ちょこちょこ川沿いを走ってはいるが、
あくまで健康保持という
理性的な目的をもってやっていること。
内から湧きあがる何かに突き上げられてとか、
感情がさく裂するのに任せてとか、
ただ単に楽しくて走り出すなんてことは
とっくの昔に忘れてしまった。
べつに哀しくも寂しくもないが、
そういう幼さ・若さはちょっと羨ましく思うことはある。
「今はまだ地球がふるさと」/おりべまこと
電子書籍 Amazon Kindle
https://amazon.co.jp/dp/B0CW1FWZ59
14歳の女の子の夢と想像と現実が入り混じった
日常生活を描く
青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
春休み無料キャンペーン
3月24日(日)15:59までやってます!
この機会にぜひ読んでみて下さい。
人はいつだって14歳にもどれる
人はいつだって14歳にもどれる。
64歳の僕のなかにも、
何歳だかわからないあなたのなかにも、
14歳の自分が暮らしている。
14歳の女の子の
夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く
青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
「今はまだ地球がふるさと」/おりべまこと
電子書籍 Amazon Kindle
https://amazon.co.jp/dp/B0CW1FWZ59
今なら無料!
春休みスペシャルキャンペーン
3月24日(日)15:59までやってます!
この機会にぜひ読んでみて下さい。
今はまだ地球がふるさと 春休みスペシャル6日間無料キャンペーン

おりべまこと 電子書籍
おとなも楽しい少年少女小説
今はまだ地球がふるさと
https://amazon.co.jp/dp/B0CW1FWZ59
本日より春休み無料キャンペーン スタート!
3月19日(火)16:00~24日(日)15:59まで。
春休み満喫の小中高大生さん、
おとなのあなたもぜひ読んでね。
がっちり長編9万1千字。
自分は“宇宙人とのあいのこ”だというリコは、小学校時代からの親友サーヤとともにあちこちの葬式を巡り「故郷の星へ帰っていく人たち」を見て回っては聖女のごとく祈りを捧げている。
そんなとき、偶然、終活サポートの仕事をしている中年男・中塚と出会い、彼を介して、ひとり暮らしでハーモニカ吹きの老人・小田部と知り合った。孤独死予備軍の小田部に興味を引かれたリコは彼に「星のおじいさま」というあだ名をつけ、食事や掃除の世話をするために家に出入りするようになり、次第に親しさを深めていく。
そんなリコに恋したシンゴが彼女の気を引くために「きみのためにUFOを呼ぼう」と言ってアプローチすると、リコが生きる世界にさまざまな不思議な現象が起こり始める。
子ども時代を卒業し、人生の旅に出る支度を始めた少女の、夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
もくじ
1 地球人の母になる
2 星のおじいさま
3 UFOに出逢ったお母さん
4 ラブリーな親友
5 恋文と宇宙の夢
6 令和終活コーポレーション
7 記念碑ツアー
8 レトロ喫茶と未来の記憶
9 取り調べ
10 里山の合宿でUFOと出逢う
11 UFO同窓会のレポート
12 奇妙な家族だんらん
13 競馬場でのドラマ
14 絶交
15 星のおじいさまの息子
16 いつか見た虹のこと
17 UFOからのメッセージ
18 天国への扉
19 魔法のアイドル誕生
20 ありがとう友だち
21 いつか家族に
今はまだ地球がふるさと」 春休み無料キャンペーン予告
春休み、夏休み、冬休み。
子どもは長い休みに成長する。
宿題のない春休みは勉強なんか忘れて、
いっぱい遊んだり本を読んだりしよう。
というわけで、
おりべまこと電子書籍最新刊
長編小説「今はまだ地球がふるさと」
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CW1FWZ59
6日間の春休み無料キャンペーンやります。
3月19日(火)16:00~24日(日)15:59
小学生、中学生、高校生のあなたに。
その頃の記憶と感性を持っているおとなのあなたにも。
新しい成長の旅に出かける支度を始めた少女の、
夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く
青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
どうぞお楽しみに!
アカデミーゴジラへの称賛と違和感

平成後半、何度もオワコンだと言われ、
アメリカに売り飛ばされていたゴジラがまさかの再生。
そして驚愕のアカデミー賞受賞。
その「ゴジラ-1.0」と、
作品賞をはじめ、各賞を総ナメにした
「オッペンハイマー」が同じ年に受賞したことには
何か因縁を感じるが、
あまりそんなことを考えている人はいないのかな?
以前も書いたが、昭和20年代を舞台にした
「ゴジラ-1.0」が
原爆投下や敗戦の傷跡をあまり感じさせなかったことに
けっこう違和感を覚えた。
もしやアメリカ市場に忖度してる?とも考えた。
今回の受賞で、ゴジラが水爆実験から生まれた怪物だという
オリジナル設定は忘却されてしまうのではないか?
そんな懸念もある。
もう一つ、今回称賛され、
たぶん受賞の一要因になったのは、
アメリカ・ハリウッドでは考えられない
低予算・少人数による制作体制。
どちらもケタ違いに安くて少ない。
これはもう日本映画のお家芸みたいなもので、
映画が量産されていた1950年代・60年代、
黒澤明や小津安二郎が活躍していた時代は、
コスパ、タイパに徹底的にこだわり、
1週間で1本とか、1か月で3本とかをあげるのは
ザラだったという。
巨大な予算と膨大な人数で映画作りを行い、
働く人たちの権利意識が強く、組合も強力で、
頻繁にデモやストライキなどをやる
ハリウッドでは到底考えられない作り方・働き方なのだ。
これもまた、資本・経営者に対する
日本の労働者の立場の弱さを表している。
と言ったら言い過ぎ?
もちろん、条件が悪い中で工夫して知恵を絞ることに
イノベーションが生まれるので、
いいことでもあるんだけど。
ただ、この働き方改革の時代に、
スタッフの健康やプライベートは大丈夫かとか、
それなりの額のギャラが
ちゃんと払われているだろうかとか、
会社の言いなりになっていないかとか、
ついついよけいなことを考えてしまう。
映画をはじめ、クリエイティブの現場は
労働基準法なんてあってなきもの、
みんな好きで、愛を込めて仕事やっているんだから、
夜中までかかろうが、休みがゼロだろうが文句なんかない。
といった世界だったはず。
気持ちがノッて、クリエイティブ魂が全開になって、
現場のテンションがグワーって盛り上がってきたところで、
「はい、6時になったんで今日はここでおしまい」
なんて言われたらドッチラケ。
昔の監督だったら「ふざけんな!」と怒鳴りまくるだろう。
と、僕は認識しているが、最近はそうした環境も
変わってきているのだろうか?
なんだかせっかくの受賞に
ケチをつけるようなことを書いたけど、
やっぱりこれは画期的な出来事。
ハリウッドの映画製作にも何か影響を与えるのだろうか?
ちょっと楽しみではある。
ありがとうロボットリヤマ

最近はどうだか知らないが、
僕が子どもの頃、よく読んだマンガでは
作者自身がしばしば作品のなかに出てきた。
おそらく手塚治虫先生がその草分けだろう。
「バンパイヤ」では完全に登場人物のひとりとなって、
物語のなかで大活躍していた。
その他、石ノ森章太郎、永井豪などの
セルフキャラも印象的で、
土田よしこなどは、ほとんど自分を主人公にした
「よしこ先生」なんてマンガを描いていた。
鳥山明先生の自画像「ロボットリヤマ」も大好きだった。
僕は「ドラゴンボール」のことはあまり知らなくて、
好きだったのは「ドクタースランプ」の方だった。
ちなみに「ロボットリヤマ」とは
当時、僕とごく一部の友人がそう呼んでいただけで、
公式なキャラ名などではない。
デビュー当時、「ドクタースランプ」の絵は衝撃的で、
お洒落なのにめっちゃギャグ漫画しているところ、
そしてアラレちゃんをはじめとするキャラが
可愛くて弾けているところは、
それまでのマンガにない、新鮮な世界だった。
鳥山先生は名古屋出身、僕も名古屋なので、
ニコちゃん大王をはじめ、
ブロークンな名古屋弁をしゃべるキャラが
いろいろ出てくるのも面白くて親しみを覚えた。
ペンギン村には作者自身もやってきて、
しばしば登場していた。
最初の頃は人間の姿で出ていたが、
すぐに自己改造して「ロボットリヤマ」になり、
ペンギン村に移住した。
鉄を食べちゃうガッちゃんによく食われて、
半壊状態になっちゃうのには、いつも笑わせてもらった。
人気が爆発し、仕事が忙しくなり、
自分がマンガ生成マシーンのように思えて
ロボット化したのだろうか。
でも、みんなに喜んでもらうマンガを描き続ける
ロボットの自分をとても楽しみ、愛していたのだと思う。
どうかごゆっくりお休みください。
64歳と14歳の「今はまだ地球がふるさと」
「僕が64歳になっても、きみは僕を愛してくれるかい?
と歌うのは、ビートルズの
「ホウェン・アイム・シックスティー・フォー」。
この歌が出された1967年頃は
64歳がイギリス人の平均寿命だったらしい。
同じころの日本人の寿命はもっと短かったと思う。
自分もその齢になって、ちょっとドキドキしている。
齢を取っていいことは、経験したどの年齢にも
自由自在に往復できること。
なので還暦を超えると時おり中二病が再発する。
中二の時は「中二病」なんて言葉はなかったけど。
おとなみたいに適当にやり過ごすことができなくて、
「生きる」ことに対して一生懸命に考えている中学生
――にたまには戻ってみてもいい。
そうしてこの先のことを考えてみる。
わたしは、あなたはどう生きたいのか?
そんな思いがあって出来上がった話。
おりべまこと電子書籍最新刊
今はまだ地球がふるさと
Amazon Kindleより¥600
自分は“宇宙人とのあいのこ”だというリコは、
小学校時代からの親友サーヤとともに
あちこちの葬式を巡り
「故郷の星へ帰っていく人たち」を見て回っては
聖女のごとく祈りを捧げている。
そんなとき、偶然、終活サポートの仕事をしている
中年男・中塚と出会い、彼を介して、
ひとり暮らしでハーモニカ吹きの老人・
小田部と知り合った。
孤独死予備軍の小田部に興味を引かれたリコは
彼に「星のおじいさま」というあだ名をつけ、
食事や掃除の世話をするために家に出入りするようになり、次第に親しさを深めていく。
そんなリコに恋したシンゴが彼女の気を引くために
「きみのためにUFOを呼ぼう」
と言ってアプローチすると、
リコが生きる世界にさまざまな
不思議な現象が起こり始める。
子ども時代を卒業し、
人生の旅に出る支度を始めた少女の、
夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く
青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
今はまだ地球がふるさと 本日発売!

おりべまこと電子書籍 最新刊 本日発売!
「今はまだ地球がふるさと」
レビューにいつもより時間がかかったので、
もしや中学生の女の子に
セクシーなセリフを言わせたのでNG?
と一瞬心配しましたが、無事出せました。
91,000字の長編小説。
Amazon Kindleより¥600で発売中!
あらすじ
自分は“宇宙人とのあいのこ”だというリコは、
小学校時代からの親友サーヤとともに
あちこちの葬式を巡り
「故郷の星へ帰っていく人たち」を見て回っては
聖女のごとく祈りを捧げている。
そんなとき、偶然、終活サポートの仕事をしている
中年男・中塚と出会い、彼を介して、
ひとり暮らしでハーモニカ吹きの老人・
小田部と知り合った。
孤独死予備軍の小田部に興味を引かれたリコは
彼に「星のおじいさま」というあだ名をつけ、
食事や掃除の世話をするために
家に出入りするようになり、
次第に親しさを深めていく。
そんなリコに恋したシンゴが
彼女の気を引くために
「きみのためにUFOを呼ぼう」
と言ってアプローチすると、
リコが生きる世界に
さまざまな不思議な現象が起こり始める。
子ども時代を卒業し、
人生の旅に出る支度を始めた少女の、
夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く
青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。
もくじ
1 地球人の母になる
2 星のおじいさま
3 UFOに出逢ったお母さん
4 ラブリーな親友
5 恋文と宇宙の夢
6 令和終活コーポレーション
7 記念碑ツアー
8 レトロ喫茶と未来の記憶
9 取り調べ
10 里山の合宿でUFOと出逢う
11 UFO同窓会のレポート
12 奇妙な家族だんらん
13 競馬場でのドラマ
14 絶交
15 星のおじいさまの息子
16 いつか見た虹のこと
17 UFOからのメッセージ
18 天国への扉
19 魔法のアイドル誕生
20 ありがとう友だち
21 いつか家族に
残酷でカオスな傑作「進撃の巨人」

約1カ月半かけてAmazonPrimeで
アニメ「進撃の巨人」全94話を見た。
先月末の途中経過でも書いたが、人間が食われる話なので、
残酷描写がかなりのもので、見続けるのが精神的にきつい。
それに慣れてきた中盤で
かつて仲間と信じていた者同士が「共食い」になるので、
これまたきつくなる。
それでも3分の2くらいのところまでは、
自分たちがなぜ壁に閉じ込められているのか、
その謎を解こう。
そして、この壁の向こうにあるはずの
海を見に行こう、という少年の夢がある。
つまり、そこまではどんなに残酷であっても
希望に満ちた冒険物語になっていて、
夢を達成した少年たちが新たな世界に旅立つ――
といった美しい結末を予感させていた。
ところが話はそんな単純ではない。
問題はそのゴールに達したあとのこと。
人生と同じで当たり前だけど、
僕たちはいつまでも少年少女のままではいられない。
この作品は安易なハッピーエンドで
お茶を濁すようなことはしなかった。
カメラが180度切り替わり、新たな世界に視界が開けると、
そこにはさらに救いのない
残酷で恐ろしい世界が広がっていて、
そこでまた戦わなければいけなくなる。
後半の話はどんどん深く複雑になり、
それまでのいろいろな謎が解けていくのだが、
ますます見るのが辛くなっていった。
そして、そもそもいったい誰が主人公だったんだっけ?
と思わせるようなカオス的な展開になっていく。
それでも向き合わずにはいられない気持ちにさせるのが、
この作品のすごいところ。
壁とは何か?
巨人とは何か?
近代日本、戦後日本社会のメタファーであり、
風刺であるという説がよく聞かれるが、
帝国主義や数々の戦争、難民問題などから形づくられた
現代の人類の世界全体の暗喩であるとも受け取れる。
ラストも決してスカッと終わらず、あれでいいのかという、
気持ちの悪い違和感が腹の中に残った。
まるで「後味の良い感動を残す物語」なんてあざ笑い、
ぶった切るかのようだ。
最後の最後のあのシーン、あのセリフは、
希望や救いと言えるのだろうか?
「進撃の巨人」の世界には
随所にさまざまな意味が込められており、
それをどう読み解き、何を考えるかは
読者・視聴者の向き合い方次第と言えるだろう。
それだけの豊かなものがこの作品には詰まっている。
少し落ち着いたら、
今度は原作のマンガを通読してみようと思っている。
いずれにしてもこの時代に、マンガ・アニメという手法で
こんなすごいドラマを創り上げた作者を
リスペクトせずにはいられない。
おりべまこと Kindle新刊:長編小説
今はまだ地球がふるさと

本日2月25日発売予定でしたが、
残念ながら提出が遅れたため、
まだレビュー中。
楽しみにされていた方、
どうもごめんなさい。
明日までお待ちくださいね。
郷竜小説「6万6千万年前の夢を見て死ね」 パート3.ジャパニーズネッシー捜索隊 その③

一方、みずからジャパニーズネッシー捜索隊の総指揮官に就任した国会議員は、隊を北と南、二班に分けて、北海道の屈斜路湖、鹿児島県の池田湖から捜索をスタート。政府公認の研究施設や大学の生物学研究所などから選ばれたスタッフがそれぞれ8名ずつ派遣され、現地調査を行った。マスコミも大挙して押し寄せて大騒ぎをしていたが、こちらもナッシー捜索の子どもたち同様、待てど暮らせどクッシーもイッシ―も現れないので、数日するうちに飽きてきた。
それからしばらく後、とある大臣のスキャンダルが発覚し、政府がマスコミの糾弾を受け、野党が色めき立つと、ジャパニーズネッシー捜索隊もそのとばっちりを受けて国会でやり玉に挙げられた。
いったいあの予算はどこから出ているのか?
国会議員がろくに仕事もしないで、あんなろくでもないことに現を向かしていいのか?
そもそもあの活動が社会的・経済的にどんな意味・どんなメリットがあるのか? など云々。
当の作家議員は抗弁するのに窮してトーンダウンし、何も見つからないまま捜索は打ち切られることになった。結局、ジャパニーズネッシー捜索隊は奈々湖には来ずじまいだったのだ。
村長はマスコミの取材に応じてコメントを残した。
「まことに残念です。ちゃんと捜索すれば、必ずや世紀の大発見になったのに。ナッシーは間違いなかったのですから」
そのコメントはちゃんとそのまま新聞や雑誌に載ったが、それだけだった。そこから何か新しい活動が展開されることはまったくなかった。そして、そんな騒ぎがあったことも遠い昔ばなしになった。いまやこの湖にナッシーの伝説があったことを知っている人さえ少なくなっている。
しかし、世の中には6600万年前に死に絶えた巨大な生き物が、今まだ、この地球上のどこかに生き続けているはずだと信じている人が驚くほど大勢いる。それはもはや願いのようなものだ。
おれたちにはその願いをかなえるミッションがある。
一彦はまじめな顔をして大善に訴えた。
大善はうんうんと頷いたものの、いったい東京で何があったのだろう?と訝った。たしかにいっしょに古文書の捜索などもやったが、彼の記憶の中の一彦は頭の良い秀才タイプで、むしろ周囲の子どもたちよりも一般常識をわきまえている男だった。
中学生になる頃には奈那湖の怪物のことなどすっかり忘れて、勉強と部活のバスケットボールに打ち込んでいた。時々、テレビや雑誌で見たオカルト話で盛り上がることはあったが、それはちょっとしたお楽しみの範疇だった。もうその頃にはみんな、おとなになって社会の常識の中で生きていかなくてはいけないことがわかっていたのだから。
いったい何が一彦を、いわば逆行させてしまったのか、大善にはわからなかったが、人が大勢来て村が賑わうことはいいことだ。そして正直、大善も時おり湖畔を散歩しては、ああ、本当に怪物が出てきて、また大騒ぎが起こればいいのにと考え、朝夕のお務めで仏に向かって祈念していたのである。
そしてもう一人、このナッシープロジェクトに参加したいという人物が現れた。その名も菜々子という。
郷竜小説「6万6千万年前の夢を見て死ね」 パート3.ジャパニーズネッシー捜索隊 その②

子どもたちが探しまわった古文書は仏像や古地図が所蔵してある部屋にしまわれていた。住職――大善の父は村長からの連絡を受けてそれを取り出しておいた。
翌日、村長以下、村のお偉方はがん首揃えて麟風寺を訪れ、住職――大善の父に古文書を見せてくれるよう願い入れた。
住職は彼らを客間に通し、とっておきの黄金に輝く法服を着て出迎えた。そして訴えを聞くとまるで時代劇のように大仰な間を取り、両手を合わせて目をつむった。そして読経を始めた。村長らも慌てて手を合わせ、首を垂れる。
一分ほどのち、住職は目を開き、傍に法具の上に用意してあった古文書をしずしずと村長らの前に取りだし、一枚ずつ広げて見せた。ミミズがのたくったような黒々とした文字が黄ばんだ和紙にえんえんと書き綴られている。村長らは食い入るような目つきでその文字の列を追っていたが、何が書いてあるのやら、さっぱり読めない。住職はいつにない厳かな口調でそこに書いてあることを解説した。
そして絵を見せる。どれも子どもの落書きみたいな絵だが、たしかに怪物らしきものが描かれている。
全員が深いため息をつき、客間はしばし沈黙に包まれた。
「これは間違いありませんな」
最初にそう声を発したのは、観光課長の田中だった。
「他の湖にはこれほどの資料はありますまい。動かぬ証拠です。ナッシーは間違いなく、日本のネッシーの一番手です」
「けどなぁ」
そう異議を唱えたのは副村長の山田だった。
「他のところには写真があるんだよ、写真が。ナッシーにはあるのか?」
「たしかありますよ、何枚か」
「なんかコブが水から突き出していたりとか、ぼんやりしてて何だかわからない黒い影が映ってるのしかないだろ。おお、これは恐竜だっていう決定的なやつはないの?」
「そんなの他のところにだってないですよ。みんな似たり寄ったりだ」
そこでけんけんがくがくの議論になり、結局、決め手は写真で、古文書はその付属品に過ぎない、という話になった。住職は憤まんやるかたない思いを抱いたが、とにかく村をあげての大事業だから協力すると約束してその場は収まった。
子どもたちは隣の部屋でふすま越しに耳を澄ませ、この会合の一部始終を聞いていた。胸が湧きたつのを感じた。そして、なんとか自分たちでナッシーの写真を撮ろうと画策し、プロジェクトチームを結成した。
カメラを持っているのは、タカシとユキヒロだ。他には女子の中にもいるかもしれない。そんなわけでタカシがリーダーとなって学校で募集をかけると、全部で十二人が参加した。
プロジェクトはずんずん進んだ。カメラマンと見張り役二人、三人で一チームとし、学校が終わって夕暮れまでの間、交替で奈々湖を見張ることにした。
彼らの空想は限りなく広がった。それまでのほほんとした長閑な佇まいだった奈々湖は、急にミステリアスでオカルト感に満ちた、底なしの不気味な湖に見え始めた。
子どもたちは会議も開いた。たいてい「緊急会議」とか「重要会議」とか「特別会議」とか、ものものしい名前がついていた。そこでは一日二時間くらいでは時間が足りない、という意見が出たが、夏休みになったら一日中見張りをしよう、ということで解決策が決まった。
しかし、そんな盛り上がりは長くは続かなかった。何日見張っても、奈々湖には何も現れない。ときどき水音がするので何かと思って見ると、水鳥が羽根をバタバタさせているだけだったりした。
当初、メンバーは皆、「おれたち、すごいことやってる感」がしていたので、そんなちょっとした異変にも色めき立って面白かったがすぐに飽きた。何回か経つうちに退屈になってきて、だんだんサボるチームも出てきた。
つづく
おりべまこと電子書籍
おとなも楽しい少年少女小説
Amazon Kindleより発売中
郷竜小説「6万6千万年前の夢を見て死ね」 パート3.ジャパニーズネッシー捜索隊 その①

ところがそれからしばらく後。村じゅうがひっくり返るような出来事が起こった。
とある国会議員が「日本のネッシーを捜索する」と言い出し、日本各地のネッシー伝説がある湖に捜索隊を送り込んだからだ。
その国会議員はもともとSF作家で、数々のベストセラー作品を発表して世間を賑わせていた。それと同時に「日本は世界で最も地球の歴史を知っている国」とか、「国土には太古の記憶が幾重にも刻まれている」いう自説を展開し、テレビの討論会などにもちょくちょく出演していた。
そして、その人気・知名度を使って参議院選挙に立候補したら、しっかり当選してしまったのだ。政治経験はもちろんゼロ。しかし、歯に衣を着せない物言いは庶民にとって痛快に映り、彼は喝采を浴びて政界に迎えられた。
参議院で何らかの実績を上げたという話は聞かないが、その男がなぜだか恐竜探しをやるというのである。しかし、彼の中では決して荒唐無稽なパフォーマンスではなく、ちゃんと論理だった、国民感情を高揚させるためのストーリーがあった。
「イギリスのごとき老大国の一地方であるスコットランドの田舎がネッシーだけで盛り上がり、年間で世界中から相当数の観光客が訪れるという。わが国にも列島各地の湖に恐竜が生息している可能性があるのだから発掘し、エコノミックアニマルではない、夢とロマンにあふれた日本国を世界にアピールすべきである」
折も折、日本は高度経済成長によって世界有数の豊かな国になりつつあった。円は高騰し、他国の通貨を圧倒する勢いは当分衰えそうにない。カネのことしか考えない成金国家の台頭に、二〇世紀の世界をリードしてきた欧米諸国は苦々しい思いを抱いている。これらの国の各地では日本製品排斥のデモが起こるなど、貿易摩擦も深刻化しており、政府もほったらかしておくわけにはいかなくなった。
そんな時に出された彼のアイデアは、そうした摩擦・軋轢を緩和する潤滑油のようなはたらきができるのではないかと期待されたらしい。それにもちろん観光客が増え、観光収入のアップも目論まれていたのだろう。
あくまでも噂だが、裏では当時の首相も絡んでいたようで、排斥運動を受けた複数の企業がスポンサーとなってこのプロジェクトを動かすことになったという。
その作家議員が公開したリストには、北海道・屈斜路湖のクッシー、山梨県・本栖湖のモッシー、鹿児島県・池田湖のイッシ―などの有名どころに連なって、最後に奈々湖のナッシーの名も挙がっていた。
今まで日本中の誰も聞いたことがなかった村の名前は、この時から突然、全国区になった。このニュースに村人たちが沸き返ったのは言うまでもない。
おりべまこと電子書籍
おとなも楽しい少年少女小説
Amazon Kindleより発売中
「進撃の巨人」の「食べる」

今さらだけど「進撃の巨人」のアニメを
アマプラで見ている。
評判は聞いていたが、巨人が人間を食うシーンが怖くて
気持ち悪くて、これまで見ていなかった。
しかし今年になって、意を決して(?)見出したら
めっちゃ面白くてドハマリ。
正月からこの1カ月ほどで、
ほぼ一気見ペースで見まくっている。
それにしても想像以上に残酷シーンが多い。
巨人が人間を食う、巨人が巨人を食う。
人食いシーンのてんこ盛りである。
感想的なものは全部見終わってから書こうと思うが、
一つだけ先に言うと、
この作品において「食べる」という行為は、
三つの意味を持っているように見受けられる。
一つは殺戮・戦争のオマージュ。
巨人は強大な力を持って襲ってくる。
心を持たない兵器・軍隊のように見える。
一つは本能だけで食欲の塊である赤ん坊や子供の暗喩。
知性を持たない、ただ人を食うだけの巨人は
「無垢の巨人」と呼ばれ、
姿形も動きも本能のまま、
無邪気に食物に向かう子供のように描かれる。
そしてもう一つは、
相手の能力を取り込む行為としての「食べる」。
最近は人種差別につながるからか、あまり聞かないが、
僕が子どもの頃には少年雑誌・マンガ誌などに
よく人食い人種の話が載っていた。
今でもそういう習慣を残している種族がいると思うが、
彼らが人を食うのは、
自分にはない敵の能力を取り入れるという意味があり、
一種の宗教的・呪術的な行為であったようだ。
この作品では能力にプラス相手の持つ記憶も
取り込めることになっており、
それがストーリーの大きな鍵になっている。
僕たちもしばしば
「食べたものが自分になる」ということを言う。
ふだんあまり意識しないが考えてみえば、
かなり恐ろしい思想・イメージだ。
太古の人類は地球上のどこでも、
それぞれの種族同士で殺し合い・食い合いをやっていた。
そして殺した敵の(時には仲間の)
人間を食うということは、他のどの動植物よりも優れた
最高の栄養を取り入れることだった。
と、科学的にどうかはともかく、そう信じられていた。
なので、少なくとも精神的には強力な栄養になった。
そうした栄養によって進化してきたのがホモサピエンスだ。
おそらく僕たちの脳のどこかには
そうした太古のホモサピの記憶が残っているのだと思う。
この先、より科学が発達し、社会が発展し、
ライフスタイルが洗練されても、
こうした原初の感覚は残り続けるのではないかと思う。
というわけで「進撃の巨人」は
すさまじいイメージが渦巻く物語であり、
とても優れた人間ドラマであり、
テーマもストーリー展開も素晴らしい作品である。
残酷シーンが大丈夫な人には、ぜひ見て欲しいと思う。
というわけでまだ最後まで辿り着いていないので、
この話はまたこんどするが、
日本のアニメのクオリティはやっぱりすごい。世界一。
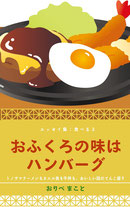
おりべまこと電子書籍新刊
エッセイ集:食べる3
おふくろの味はハンバーグ
AmazonKindleより好評発売中
郷竜小説「6600万年前の夢を見て死ね」 ★パート2「麟風寺の遺産」②

パート2.麟風寺の遺産②
奈々湖に何か得体のしれない化け物が住んでいる——
少なくとも昭和のどこかまでは、
そんな伝説が村には流布していた。
その伝説の源は麟風寺だった。
660年の歴史がある寺だ。
所蔵されている古文書には、
室町時代から江戸時代にかけて、
どのようにこの村が出来上がったのかという記録とともに、
何年かに一度、奈々湖に現れるとされる怪物の目撃談が
いくつも残されていた。
その中にはその怪物の絵が添えられたものまであった。
巨大なワニとか、オドロドロしい魚とか、
エビの化け物のようなものまで、
いろいろバラエティに富んでいる。
とにかく何か得体の知れない生き物がいることは間違いない。
村の年寄りたちは一彦や大善の両親の世代に
そんな話をよく語り聴かせたようだ。
昭和の半ばあたりまで、
こんな山間の村にはろくに娯楽がなかった。
それは一種の夜伽話として代々、
村の子どもたちを楽しませていたのかもしれない。
「バカバカしい」
一彦はすでに亡くなった父の言葉を思い浮かべた。
「非科学的にもほどがある。
あの湖にそんな大きな生き物なんかいるわけねえ。
ちょっと考えればわかることだ。
ホントに田舎者はこれだから困る」
父はいつもそう言っていた。
近郊の少しばかり大きな街の、
世間に少しは名の知れた会社に勤める
サラリーマンだった父は、
自分はこの村のやつらとは違う、
という自負があったのだろう。
一彦らの世代になると、そんな話を信じるなんてバカだ、
という方が優勢だった。
けれどもその一方で、本当だったらいいけどな、
という気持ちもちょっぴりあった。
大善はビミョーな立場に立たされていた。
なんと言っても噂のもとであるお寺の跡取りである。
「あんなデタラメを広げやがって」と、
湖の怪物のせいでいじめられることも少なくなかった。
けれどもこちらもその一方で、
怪物の絵が描かれている古文書を見たい、
見せろと言ってくるやつらも多かった。
彼と仲の良かった一彦も、
もちろんその好奇心を強く抱えた一人だ。
しかし大善自身、父がどこに
その古文書をしまっているのか知らない。
一度、一彦を含め、四人の仲間で
〈捜索隊〉を作り、
大善の父――当時の住職が留守の時に
家のあちこちを探しまわったことがある。
ある日、それがバレて大善は父にこっぴどく叱られ、
それ以降、捜索活動は打ち切りになった。
みんな、ちょっとがっかりしたが
一日でそんなことは忘れてしまった。
しょせん子どもの遊びである。
いつまでも過去のことなどにこだわっちゃいられない。
奈々湖は相変わらず子どもたちの遊び場であり続けた。
ところがそれからしばらく後。
村じゅうがひっくり返るような出来事が起こった。
●郷竜小説「6600万年前の夢を見て死ね」 パート2.麟風寺の遺産①

パート2.麟風寺の遺産①
「ガチか?イッピコ、おまえヤバイんでねぇの?」
川西大善の口からはおよそ僧侶とは思えない
俗っぽいセリフが飛び出す。
「なんで事前に相談しなかったのさ?」
「一度連絡しただろ。けどプーちゃん、忙しそうだったし」
大善は、はたと自らを振り返る。
「そういやそうだった。けっこうテンパってたかもね」
麟風寺の住職になって半年。
大善は先代住職の父から引継ぎで、
なんやかんやとバタバタしていたことを思い起こした。
愛称は「ダイちゃん」でなく「プーちゃん」。
麟風寺のプーから来ているのだが、
そこに彼の持ち味であるのんきな性格も加味されている。
大学を出た後はそれこそプータローとして、
2年ほど外国を放浪していた。
「坊主にはならねえ」が子どもの頃からの口癖だったが、
結局、頭を丸めて修行に出たあと、
実家に戻り、坊主稼業を継ぐことに決めた。
麟風寺は故郷にあるお寺で、
その若い住職は一彦の幼なじみであり親友だった。
「いや、そりゃ帰ってきてくれたのはうれしいけどさ、
せっかく東京でちゃんとした会社に就職したのに・・・」
「もったいないってこと?」
「そう思うでしょ、誰だって」
「おまえが人生相談で言ってることと違うな」
大善はインターネットの「お坊さんに相談しよう」
というサイトで人生相談に応じている。
「プー坊主」というのは彼の売りだ。
「悩んだら自分に正直になりましょう。
心の声を聞きなさい。
好きなことを優先しましょう、とか」
「まあ、そうだけど」
「先のことを考えすぎです。今を生きましょう、
とかなんとか」
「いや、それとこれとはべつで」
「そんなの無責任だろ」
「だってさ、おれはおまえが羨ましかったわけ」
そう言って大善は子ども時代と変わらないまなざしで
一彦を見た。
麟風寺の宗派では頭を剃る戒律はない。
修行を終えて戻ってきてからは普通に髪を伸ばし、
袈裟も着ていないので、大善はまったく僧侶には見えない。
二人は本堂に隣にある住居の一室で話をしている。
ここも二人が子どもだった頃のまま、
ほとんど変わっていない。
「おれは跡取りだからさ、
ここから離れられなかったんだ。
660年の歴史がこう、ずしっとのしかかってな」
大善は重い荷物を背負うようなお道化たしぐさを見せた。
「こう言っちゃなんだけど、
親父はいい時に仏様の世界へ行ったよ。
やれやれ、これからどうすりゃいいのやら」
「ひどい住職がいたもんだな。
そのセリフをお檀家さんたちに聞かせてあげたいよ」
「どうぞお好きに。お檀家さんもめっきり減っちゃってね、
もうお布施も集まらなくて」
二人の故郷はすごい勢いで過疎化が進んでいる。
自然の恵みに溢れた美しい村なのだが、
ここで生まれ育った多くの子どもたちにとっては
そうではない。
それぞれの家はきれいで新しい住宅に建て替えられ、
電化製品が行きわたり、豊かで便利な生活を送っている。
にも関わらず、いまだに昔ながらの差別意識と
おかしな因習が残る閉塞的な暗いムラなのである。
だからみんな成長し、
中学や高校を卒業するとさっさと都会へ出て行ってしまう。
大学に入れば、そのまま大都市圏の会社に就職だ。
そうでなければフリーターをやりながら
自分の好きなことをやったり起業をめざす。
一彦はそれなりの規模の旅行会社に就職したものの、
2年と経たないうちにもう退職と起業を考え出した。
起業して自分の会社を持つという漠然とした夢が
日に日に膨らみ、週末ごとに起業サークルに通い始めた。
最初はいろんな仲間がいて面白かった。
けれども何回か通ううち、じつはみんな、
大して本気じゃないことに気付いた。
口当たりのいい自己啓発書を読み漁ってヴィジョン、
言い換えれば自分に都合の良い“妄想”を膨らませ、
「起業家」「経営者」という名の職業に就こうとしている。
だから何か手っ取り早く稼げる仕事はないか。
あわよくばその稼ぎを投資に回して
資産を作って早期リタイアできないか――
そんなことばかり考えて、
いわゆるビジネスチャンスを探しまわっている。
何よりも彼らには、仕事に対する愛情が
決定的に欠落していた。
市場のニーズと言えば聞こえがいいが、
今、儲かりそうならどんな仕事でいい。
効率よくやって効率よく金を稼ぐ。
それで成功している人を見ると、
自分にもたやすくできそうな気がしてくる。
しかし、そうなるためにはやはり特別な才能がいるのだ
ということにも気がついた。
仕事に対する愛情の欠落――
つまり好きなこと、やりたいことがないことは
自分もまったく同じだった。
一彦は割と器用で、
何をやってもだいたいのことはうまくできた。
人間関係もどう立ち居ふるまえばいいか
頭が素早く回転した。
女にだってそこそこモテる。
傍目にはわりかし優秀な人間・スマートな男と
映っているはずだ。
しかしそれだけだ。
その分、がんばってやり抜きたいと思うことは何もない。
この女のためなら何でもすると思うこともない。
すべてそこそこで、ほどほどで、
このままいけば平均的な日本人はこうあるべき、
みたいな人生を歩めるだろう。
人は彼を見て、これこそ幸福と思い、
中には羨む人もいるかもしれない。
だけど、それが何なんだ?
うすっぺらいペラペラな人生。
彼の胸にはぽっかりと大きな穴が開いていた。
起業サークルに通って学べば学ぶほど、
その穴はどんどん大きくなっていった。
それは怖ろしいことだった。
この先、何十年も続く人生を
いったいどうやって生きていけばいいのか
見当がつかなかった。
マイケルのサイトに出会ったのはちょうどそんな時だった。
特に恐竜が大好きというわけでもなかったが、
彼のサイトを目にするうち、
からからに乾いた心が潤い、
みるみる小さなオアシスが育っていく。
しだいに心の中に夢が芽生えた。
自分の故郷で、現代の恐竜伝説を創る。
それによって旅行客を呼び寄せ、新たな観光名所にする。
おれみたいな人間が、どうしてそんな荒唐無稽な話、
幼稚な妄想をマジになって考えているんだ?
最初のうち、自分が自分を信じられなかった。
しかし、これはただの夢物語ではない。
なぜなら根拠がゼロではないからだ。
つづく
郷竜小説「6600万年前の夢を見て死ね」パート1-2

辰年ということで郷竜(きょうりゅう)小説スタート。
随時連載。
★パート1.マイケル・オーネストの遺言 その2
自称・スコットランド観光大使の還暦バックパッカー
マイケル・オーネストは、
スコッチウィスキーではなく、
日本のグレープフルーツサワーを飲みながら
椎名一彦相手に新宿の居酒屋でくだをまく。
「とにかくネス湖を世界遺産にしたいんだ」
彼は故郷に帰ったら、その運動に携わるという。
インヴァネスという
ネス湖観光の拠点として知られる街が彼の故郷だ。
街の中にはネス川という川が流れている。
彼はその流れを眺めて育ち、
夕日に照らし出された
川の景色の美しさを何度も語って聞かせた。
ついでにベッド・アンド・ブレックファーストを
経営していた家の娘との初恋のことも。
「アマンダは可愛かった。
白いエプロンがよく似合ってね。
ベーコンと目玉焼きを作るのが得意だったんだ。
そんなの、誰にだってできると思うだろ。
だけど、目玉焼きをきれいに
程よい加減で焼くのは思ったより難しい。
お皿に移す時に
黄身を崩さないようにするのにコツがいるんだ。
かといって黄身を固くしてしまったらおいしくない」
そんな話をしているときに、
つまみに頼んだベーコンポテトが出てきた。
マイケルは「オー!」と声を上げて
好物に飛びつき、初恋の話は
それであっけなくフェードアウトした。
一彦はインヴァネスの
ベッド・アンド・ブレックファーストで
白いエプロンを着た金髪の娘に給仕され、
ベーコンエッグの朝食を食べている自分の姿を想像した。
窓越しに鳥の声、そして川のせせらぎが聞こえてくる。
その川、ネス川はネス湖に流れ込んでいる。
それはまた、マイケルのイメージの中では
スコットランド独立というヴィジョンにも
繋がる流れでもあった。
「必ず実現してみせるよ」
彼の人生には二つの目標があるという。
ネス湖の世界遺産登録。
スコットランドの独立。
その二つがどこでどうつながるのか、よくわからない。
ところが彼はその疑問に対する答えも
ちゃんと用意しているのだ。
「ネス湖は有名ではあるが、どこの国にあるのか、
ちゃんと知らない人が世界には圧倒的に多い。
スコットランドは今、君たち日本人が言うイギリス、
すなわち、グレートブリテン、
またの名をユナイテッド・キングダム、
の一地域ということになっている。
けれどもネス湖はイギリスにある湖、
とは誰も言わないだろ?」
そう言われてみればそうかなと一彦は思った。
たしかにビッグベンやウェストミンスター寺院、
あるいはストーンヘンジやシェイクスピアの村、
ピーターラビットの村と同じように
ネス湖を「イギリスの名所」
だと思っている人は少ない気がする。
多くの日本人にとってスコットランドのイメージは
何といってもネス湖。
あとは古都エジンバラ(こちらの街並みは世界遺産)とか、
タータンチェックにバグパイプといったところか。
「だから僕はこの二つをできるだけ
同時期に実現することに意義があると思っている」
マイケル・オーネストは自分のサイト
「マイケルのローストネッシーがうまいケル」で
ネッシーの話題を提供している。
一彦はそれを見つけて彼と友だちになったのだ。
日本語版は奥さんが翻訳をやっていたが、
どうやらその表現のしかたを巡って
ケンカになったことが離婚の原因だったようだ。
男の夢は離婚も辞さない。
それくらいマイケルは
ネス湖とネッシーについて本気だった。
その熱意に一彦は心動かされた。
東京でサラリーマンをやっていた
彼の脳裏に故郷の奈々湖の景色、
そして幼い頃に一度だけ見た
あの怪物の姿がよみがえった。
ほんの一瞬だけ、目の当たりにした
天に向かって伸びる長い首。
あれはたしかに太古の恐竜だった。
6600万年前に絶滅した、
かつてこの地球を支配していた巨大生物。
妄想にかられた彼の耳にはその咆哮さえも轟いた。
何度かマイケルと会って話を聞くうち、
一彦の心はしだいに固まっていった。
いま務めている会社を辞め、
故郷に戻って観光事業をやる。
その夜――彼はその決意を
マイケルに打ち明けた。
彼は一瞬、大きく目を見開き、
「オー!」と声を上げて両手を広げ、
やたらと芝居掛かったリアクションをした。
そして一彦の肩をがっちりとつかみ、
「マイフレンド」と感嘆のセリフを漏らした。
目には涙さえあふれ、ツーと頬を伝った。
シェイクスピアの芝居でこういう人物がいたかもしれない。
「それならば君も言うべきだ。ナナコを見て死ね、と」
人生は短い。
僕たちはこの世界のほんのわずかな部分しか、
見ることも触れることもできない。
だから人々に問うべきなのだ。
あなたにとって大切なものは何か?
自分に正直になってそれを確かめなさい。
そして明日死ぬ前に
それをしっかり見ておきなさい、と。
そう言い残して、
マイケル・オーネストはイギリスに、
いや、スコットランドに旅立って行った。
郷竜小説「6600万年前の夢を見て死ね」1-1

辰年ということで郷竜(きょうりゅう)小説スタート。
随時連載します。
★パート1.マイケル・オーネストの遺言
「ネス湖を見て死ね」
マイケル・オーネストはそう言った。
まだ見たことはないが、
椎名一彦は霧に包まれたネス湖を頭に思い浮かべた。
同時に頭の半分には明るい太陽の光に照らされた
奈々湖の風景が浮かび上がった。
神秘性、何か出そうな雰囲気という点では
まったく比較にならない。
奈々湖はあまりにも長閑で緊張感に欠けている。
けれども確信しなくてはならない。
ネス湖にネッシーがいるように、
おれの故郷の奈々湖にだって〈ナッシー〉がいるのだ、と。
マイケル・オーネストは
スコットランドの観光大使を自称している。
あくまで“自称”だ。
実際はただのバックパッカーに過ぎない。
若い頃からバックパックを背負って
世界をほっつき歩いてきたが、
60歳になった今、祖国に帰ると言う。
日本が気に入って住みつき、12年暮らした。
結婚もしていたが奥さんとは昨年離婚したという。
彼が言うには奥さんはかなりエキセントリックな性格で、
とてもいっしょに暮らしていけなかったと言っている。
そういう本人も相当エキセントリックだが。
いずれにしてもそんなわけで本人曰く、
「日本はの長い世界漫遊の最後の地になる“かもしれない”」
「“かもしれない”って、
また帰ってくるかもしれないってこと?」
そう一彦が聞くと、
「未来のことは誰にも分らないからね」
マイケルは答える。
「だけど自分自身のことでしょう」
二人が飲んでいる新宿三丁目の居酒屋〈下町伯爵〉には
1960年代から70年代のポップスや映画音楽が流れている。
「自分のことだってわからない。
今の自分と未来の自分は違うから」
そう言ってマイケルは自分の頭を指さした。
「この脳は三日後には違う脳になってるよ」
笑って大好物のグレープフルーツサワーを
グイッとあおった。
スコットランドの観光大使を名乗っている割に、
スコッチウィスキーを飲んでいるところは見たことがない。
つづく
イマイチ昭和世界の「ゴジラ-1.0」

「シン・ゴジラを超えた」と評価の高い
「ゴジラ-1.0」を見た。
時代設定が太平洋戦争末期から戦後間もない、
80年近く前の日本。
ここまで時間を戻してしまうということは、
ゴジラ映画のリセットを意図しているのか?
前作 庵野監督の「シン・ゴジラ」もそうだったが、
それとは真逆のベクトルのリセットだ。
以下、ネタバレありで。
戦争直後の東京の再現ということで
昭和レトロ世界構築の実績を持つ
「ALWAYS 三丁目の夕日」の山崎監督が出陣。
街の風景・環境の作り込みなどはよくできているが、
ストーリーが「ALWAYS」と違って、
シリアスでスケールが大きいせいもあり、
この時代の雰囲気づくりにはイマイチ感が漂う。
僕が時おり、
古い日本映画を見ているせいもあるのだろうけど、
そもそも俳優さんの顔つき・体つきが、
あの時代を生きていた人と現代を生きる人とでは、
同じ日本人でもずいぶん違うと感じる。
これはもうどうしようもない。
食い物もライフスタイルも80年前とはまったく違うのだから。
そこに難癖をつけるつもりはない。
しかし、補完する工夫はもっと必要ではないかと思う。
東京のど真ん中にゴジラが上陸して、
死傷者3万人という大惨事が起こったのに、
日本政府も、当時統治していたGHQも
まったく対策に関与しないのは、
どう考えても解せない。
元軍人たちの民間組織に丸投げするっていう設定は
無理があり過ぎだ。
「シン・ゴジラ」では政府の対ゴジラを描いたので、
今回はそれを避けたというのはわかるし、
台詞の中でもなぜ日本政府も米軍も出てこないかの説明は
一応ある。
けれども少しは政府高官なり、GHQの将校なりとの
やりとりのシーンが出てこないと
リアリティ不足は否めない。
もう一つ、ストーリーで不服だったのが、
主人公・敷島(神木隆之介)の描き方。
彼はもともと特攻隊員だが、冒頭シーン、
その任務から逃げて修理班のいる島に不時着し、
そこでまだ水爆実験の影響を受ける前のゴジラに遭遇する。
飛行機の機銃でゴジラを撃とうとするができず、
結果、修理班の人たちを見殺しにしてしまう。
なぜ敷島は特攻隊の任務から逃げたのか?
なぜ危機的状況でも機銃を撃てなかったのか?
何か重要なトラウマがあるのだろうと思ってみていたが、
どれだけ話が進んでもその説明は一切ない。
なので戦後、典子(浜辺美波)と出逢って
いっしょに暮らし始めてからも
イマイチ彼に感情移入できず、ドラマに深みが出ないのだ。
典子は戦災のせいで
自分の子ではない子供を育てることになったという設定。
それ自体は戦後の混乱を表現する要素で良いと思うが、
それだけで深掘りしていないので、
イマイチ設定が生きていない。
現代の日本人への
大事なメッセージを含んでいる気もするだけに
非常にもったいないなと感じる。
映像技術だけでなく、人間ドラマの部分も
高く評価されていると聞いていたので
期待していただけに、
こうした人物造形の粗さ・ドラマ作りの甘さが
よけい気になってしまった。
もっと丁寧に描いていたら
すごくクオリティアップしたのになー
と思うと、残念でならない。
ただ、僕にとっては欠陥に思えるそうした部分が
この映画をシンプルでわかりやすいものにしているので
アメリカでも受けているのかな、とも思う。
確かにこの脚本は、主人公が
「自分にとっての戦争」を終わらせるという
ゴールに向かって
様々な困難を克服していくという、
ハリウッドの黄金律に忠実なヒーロー物語になっている。
それに水爆実験の影響でゴジラが強大化したとか、
放射能を武器とした怪獣である点も
申し訳程度に説明しているだけで、ひどく印象が薄い。
もしやこういうところもアメリカに贖罪意識を抱かせず、
売り込むための忖度?
熱線発射の際に背中のヒレが青光りして
順番に立っていくところは、
「シン・エヴァンゲリオン」の
エヴァ2号機ビーストモードだし、
ラストの海中の覚醒シーンは、
1990年の「ゴジラVSキングギドラ」のまんま焼き直し。
そうしたイメージが連なってきて、
どうも原点回帰とか昭和レトロ世界観が伝わってこない。
と、ずいぶん難癖をつけてしまったが、
新世代向け、世界向けにリセットしたと考えると、
そのへんのことも
みんな成功要因になっているようにも思える。
思えば東宝は10年おきくらいに
ゴジラ映画の製作を諦めたり、
再開させたりを繰り返しているが、
やっぱりやれば客が入り、
一定の興行収入が見込めることを考えると
ゴジラ様を完全に引退させるわけにはいかないらしい。
これまでも何度かゴジラ映画限界説がささやかれたが、
そのたびに復活し、
「もう限界だと感じた時点がスタートだ!」を
実践してきた。
次はどんな切り口でゴジラを再生させるのか、
楽しみではある。
「どうする家康」最終回:北川茶々の鮮烈な女性ヒーロー像

世間的な評判はあまり芳しくなったようだが、
僕は面白く見れた。
何より歴史の常識に固執せず、
家康を偉人でなく普通の一個人として
描いたところが良かった。
天下人に上り詰められたのは、
いわゆる能力・実力以上に人が良かった、
たまたま運がよかった、といったことを
強調したことも面白い。
実力的にははるかに上回っていた
信長・秀吉・信玄などに取って代わることができたのも、
そうした要素が作用している。
だから人間は面白い。
松潤家康の老け演技も感心したが、
ドラマ終盤は何と言っても北川景子演じる茶々の独壇場。
前回で娘時代の心情と母親としての感情の間を
揺れ動いたので、
最期はてっきりそうした面を
強調して終わるのかと思ってたら、見事に裏切られた。
火の海となった大坂城内で、息子・秀頼をはじめ、
家臣の男たちが全員自害するのを冷静に見届けた後、
最後に言い放ったのは、
もはや女であること・母であることから脱した、
乱世の鬼神のごときセリフ。
まるで伯父の信長、夫の秀吉、父の浅井長政、
さらには武田親子、真田親子などが
すべて乗り移ったようだ。
そして、それはまた400年後の現代の日本人へ向けた
痛烈な批判でもあり、呪いの言葉でもあった。
けれどもそれでいながら最後の最後、
一人の少女に還ってつぶやく今際の一言には泣かされた。
脚本もよくできているが、前回と今回、
姫の顔、母の顔、武将の顔、鬼神の顔、
一人の女性の中で次々と変化する感情を演じた
北川景子の演技力・表現力は圧巻。
かつてなかった戦国の女ヒーロー像を見事に造形した。
大坂城落城後のエピローグ。
平和になった世の中を続かせるため、
小栗旬の天海と寺島しのぶの春日局が
家康を神格化しようと努めるシーンは面白かったが、
その後の長い回想シーン、
家康の夢みるシーンはひどく冗漫に感じた。
政権の周囲にいる人々からは神とあがめられ、
他方、豊臣を支持する民衆には、
天下をかすめ取った妖怪狸とさげすまれ、
深い孤独の中で臨終を迎えた家康は、
まだ最初の妻と息子と家臣たちが生きていた
若き日の夢を見る。
やさしい家族、あたたかい笑い、明日へ向かう活力に満ちた
平和な日は家康が望んだ幸福の在り方だ。
けれども風もなく波も立たず、
安心安全でピーカンの日々がえんえんと続いたら、
人はそのありがたみを感じなくなってくる。
当たり前のことだが、幸福の在り方は一概に論じられない。
その考えると、冗漫と感じたエピローグは、
茶々の鮮烈な死のシーンと
素晴らしいコントラストをなしており、
このドラマの終わり方としては良いのではないかと思った。
一個人としての家康の人生はどうだったのか?
男たちが戦いに明け暮れる中で女性はどう生きたのか?
世の中で成功するためには何が必要なのか?
自分の本当の心を知るすべはあるのか?
平和な環境のなかでより良く生きるためには
どうすればいのか?
エンターテインメントであることはもちろんだが、
いろいろな問いかけをしてくれたドラマだったので
1年間本当に楽しめた。
ドラマなので史実がどうこうとか難癖をつけるのでなく、
今を生きる視聴者の心にどれだけ響くかを最優先して
これからも作っていってほしいと思う。
みかんせんべいに秘められた物語

認知症の人の頭のなかには
どんなファンタジーの世界が広がっているのか
興味が尽きない。
何度か、義母が夜中や早朝に起き出して、
食べ物などをガメていく話を書いたが、
きょうは部屋の中から「みかんせんべい」が発見された。
夜中にガメたみかんを布団の下に隠し、
そのまま寝たのでぺっちゃんこ。
当然、布団の下はみかんの汁でぐちゃぐちゃ。
発見者のカミさんはカンカンである。
俗にいう認知症の人の「問題行動」だが、
まぁこれくらいのことなら明日ふとんを干せば
いいだけの話だし、怒っても本人は憶えていない。
それよりもどうしてガメたものを食べずに、
こんなふうに隠したり、しまいこんだりしてしまうのか?
秋口はお腹が減るせいか、たいてい食べていたが、
最近、寒くなってからは備蓄しようとする傾向がある。
冬眠する動物みたいに食糧を蓄えておこうという
本能が働くのも理由の一つだと思うが、
どうもそうした即物的な理由だけではないような気がする。
幻の家族やお友だちと会話していることを考え合わせると、
どうやら義母の4畳半の部屋には異次元ドアがあり、
その向こうには彼女にしかわからないストーリーが流れ、
そのストーリーを生きているのではないか。
そして、そう生きることが彼女の存在の芯にある
アイデンティティ、生きる意味と
つながっているのではないかと思える。
というわけで、汁が抜けてぺったんこに
みかんせんべいを見ているうちに
義母のストーリーを解き明かしてみたいという
妄想にかられた。
その前に、明日晴れたら洗濯と布団干しをやろう。
みかんせんべいは食べてみたが、
パサパサしててさすがにおいしくない。

短編小説
ざしきわらしに勇気の歌を
https://www.amazon.com/dp/B08K9BRPY6
Kindleより発売中。¥300 認知症の寅平じいさんの頭のなかに広がるファンタジーの物語。認知症の人のアイデンティティはどうなるのか、追究したいテーマだ。
気になったら、ぜひ読んでみてください。
京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族
京都の百万遍にある知恩寺というお寺で
毎月15日に「てづくり市」という市が立つ。
その名の通り、結構広い境内いっぱい
関西・近畿一円から集まった業者が
露店を開き、衣料・アクセサリー・工芸品・アート・
玩具・生活雑貨など、手作り品を売っている。
関西弁があふれ、とても楽しくてにぎやかだ。
そのなかで布で作った人形を売っている店があり、
かわいいお地蔵さんが目に留まった。
10数個あったが、一つ一つ顔と着物が微妙に異なる。
売り子のおねえさんによると、
95歳のおばちゃんが作っているのだそうだ。
そんな話を聞いて、義母のお土産にと一つ買ってきた。
(旅行中はショートステイに預けていた)
鏡台の前にずらりと並んだお友だちの間に
さりげに置いておいたら、
新入りに気付かないのか、自然に受け入れているのか、
とくにリアクションもなく、この1週間過ごしている。
彼女にとってはお地蔵さんも、タコやネコやワンちゃんと
同列扱いのようだ。
それでもって昼となく夜となく
これらマスコット相手におしゃべりをしている。
それだけでなく最近は幻視なのか、
やたらとどこかの子どもや、もうこの世にいない
親やきょうだい、見知らぬ先生とかお兄さん・お姉さんまで
遊びにくるようで、いろいろ訊かれるのだが、
「こっちにはいないよ」とか
「さあ、どこに行ったんだろう?」とか、
「会えてよかったね。きっとまた来るよ」とか言ってかわすと、
納得したのかしないのかわからないが、一応ひっこむ。
それでまたちょっと経つと部屋で誰かと話している。
知らない人が見たらびっくりするかもしれないが、
すっかり慣れて日常の風景になってしまった。
一時期、「お母さんのところに帰る」と言って、
止めるのも聞かずに家を出ていくことが会って往生した。
数日前に見たNHKのクローズアップ現代で
「認知症行方不明者1万8千人の衝撃」
という特集をやっていたが、
これは本当に大問題である。
家族や子供が家の中にいて話ができるなら
いきなり「かえるかえるケロケロ」と騒ぎ出さずに済んで
こちは助かるというものだ。
考えてみれば、どこか違う世界の子供と会ったり、
もうこの世を去ってしまった家族がいたりするなんて
幸福なくらしである。
そういうふうに考えていかないと、
これからの「高齢者の5人にひとりが認知症」なんて時代を
到底乗り越えていけないのではないか。
お地蔵さん、義母がずっと幸福でありますように。
地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論

むかし書いたラジオドラマの脚本で
廃園になった遊園地に
宇宙から飛来した円盤が降り立つのを
高校生の女の子と男の子が見に行くという
シーンを書いたことがある。
特撮にしようか、CGにしようか、VFXにしようか
そんなこと考えもせず、予算なんかまったく気にかけず、
リスナーの想像力に丸投げできるのが
ラジオドラマのいいところ。
てなわけで書けてしまったわけだが、
「未知との遭遇」や「E.T.」みたいな
映画に影響されているので、
いつもそういうシーンが頭にある。
てか最近、ほんとに異星人が来てくれないかと考える。
ロシア×ウクライナ
イスラエル×パレスチナ
中国の動きも怪しいし、
北朝鮮は相も変わらずミサイル打ちまくって、
軍事パレードもやりまくっている。
ウクライナ、パレスチナでの
「やったもの勝ち」の現実を見て、
台湾や韓国は、中国や北朝鮮のことが
気が気じゃないだろう。
これら、いがみ合っている国はみな、
もとをただせばみんな近親者同士。
憎み合いって、実は赤の他人より
近しい家族同士のほうがヤバイ。
「人類一家みなきょうだい」という
キャッチフレーズがあったが、
親が亡くなって相続が“争族”になるように
その家族・きょうだいがヤバいんです。
今は過去200年の人類近代化の遺産を
未来へどう継承するか、相続の時代に突入している。
相続は争族になり、
もうほとんど第3次世界大戦が起こっても
おかしくない状態になっているのではないか。
この状況を変えられるのは
地球外生物=宇宙人しかないのではないかと思ってしまう。
いま、マジで世界各地の大都市にUFOが飛来すれば、
どの国もくだらない戦争をやめるのではないか。
宇宙人が「地球を征服しに来た」と宣言すれば、
世界は一致団結するだろう。
それで本当に宇宙人の攻撃が始まったらどうするのか?
そこまで考えてないけど、
今の状況を変えるには宇宙へ向かって
「彼ら」を呼ぶしかないのでは。
もうすでにウクライナで、パレスチナで、
恐ろしいことが起こりまくっているのだから。
地球の家族が仲良くできるチャンスはないのか?
名作小説の"こんな読み方もできるんじゃね?"的読書ガイド

おりべまこと電子書籍 エッセイ集:物語
再読・嵐が丘
ブロンテ、カフカ、イシグロ、キングなど、
名作小説の読書ガイド。
スティーブン・キングは
ハリウッド映画の原作率ナンバーワンの作家だけど、
どれも長いし、ホラーは苦手、という人には
「スタンド・バイ・ミー」
「刑務所のリタ・ヘイワーズ」
「ゴールデンボーイ」など、
比較的短くて、読みごたえたっぷりの中編がおすすめ。
ホラーの根底にある人間心理のドラマが楽しめます。
そんな読み方の参考書としても。
10月31日(火)16:59 まで
新発売記念4日間無料キャンペーン実施中
もくじ
●再読「嵐が丘」:呪われた家族・愛情関係から解き放たれる少女の物語
●続・再読「嵐が丘」: 呪われた家族・愛情関係から解き放たれる少女の物語
●嵐が丘の旅の追憶
●カフカの寓話「ロビンソン・クルーソー」
●カフカの寓話②「小さな寓話」
●チェコのカッパ
●成長に希少価値がある時代の「三銃士」
●「忘れられた巨人」は、僕たちの未来を描いた物語なのかもしれない
●香水(パフューム):人間存在の深淵につながる「におい」の世界
●スタンド・バイ・ミー 死の淵を覗きに行く少年たちの冒険譚
●女目フィルターの少年像と少女版スタンドバイミーについて
●「刑務所のリタ・ヘイワーズ」:凡人の希望と絶望をめぐる物語
●「ゴールデンボーイ」:誰もが怪物になり得る恐怖の神話
●ゴーストの正体と人間のストーリーテリング
●どうして人は地球滅亡・人類滅亡の物語を創り続けるのか?
読書の秋は、世界名作を読みなおして人生を書きかえよう。
「再読・嵐が丘」本日より4日間無料キャンペーン

おりべまこと電子書籍・新刊
再読・嵐が丘
本日10月28日(土)17:00~31日(火)16:59
新発売記念4日間無料キャンペーン!
読書の秋は、世界名作を読みなおして人生を書きかえよう。
エミリー・ブロンテ「嵐が丘」は
世間で言われてきた恋愛小説などではなく、
毒親の虐待に打ち克ち、
新たな人生を切り拓くつ子どもたちの勇気の物語。
ブロンテ、カフカ、カズオ・イシグロ、
スティーブン・キングなど、世界名作、ベストセラー小説の
"こんな読み方もできるんじゃね?"的読書ガイド。
もくじ
●再読「嵐が丘」:呪われた家族・愛情関係から解き放たれる少女の物語
●続・再読「嵐が丘」: 呪われた家族・愛情関係から解き放たれる少女の物語
●嵐が丘の旅の追憶
●カフカの寓話「ロビンソン・クルーソー」
●カフカの寓話②「小さな寓話」
●チェコのカッパ
●成長に希少価値がある時代の「三銃士」
●「忘れられた巨人」は、僕たちの未来を描いた物語なのかもしれない
●香水(パフューム):人間存在の深淵につながる「におい」の世界
●スタンド・バイ・ミー 死の淵を覗きに行く少年たちの冒険譚
●女目フィルターの少年像と少女版スタンドバイミーについて
●「刑務所のリタ・ヘイワーズ」:凡人の希望と絶望をめぐる物語
●「ゴールデンボーイ」:誰もが怪物になり得る恐怖の神話
●ゴーストの正体と人間のストーリーテリング
●どうして人は地球滅亡・人類滅亡の物語を創り続けるのか?
全15編
新刊「再読・嵐が丘」本日発売

おりべまこと電子書籍新刊 エッセイ集:物語
再読・嵐が丘 本日発売!
世界名作を読みなおして、人生を書きかえよう。
エミリー・ブロンテ「嵐が丘」は恋愛小説ではなく、
毒親の虐待に打ち克ち、新たな人生を切り拓くつ子どもたちの勇気の物語。
ブロンテ、カフカ、カズオ・イシグロ、スティーブン・キングなど、世界名作、ベストセラー小説の
"こんな読み方もできるんじゃね?"的読書ガイド。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から
15編のエッセイを編集・リライト。
もくじ
●再読「嵐が丘」:呪われた家族・愛情関係から解き放たれる少女の物語
●続・再読「嵐が丘」: 呪われた家族・愛情関係から解き放たれる少女の物語
●嵐が丘の旅の追憶
●カフカの寓話「ロビンソン・クルーソー」
●カフカの寓話②「小さな寓話」
●チェコのカッパ
●成長に希少価値がある時代の「三銃士」
●「忘れられた巨人」は、僕たちの未来を描いた物語なのかもしれない
●香水(パフューム):人間存在の深淵につながる「におい」の世界
●スタンド・バイ・ミー 死の淵を覗きに行く少年たちの冒険譚
●女目フィルターの少年像と少女版スタンドバイミーについて
●「刑務所のリタ・ヘイワーズ」:凡人の希望と絶望をめぐる物語
●「ゴールデンボーイ」:誰もが怪物になり得る恐怖の神話
●ゴーストの正体と人間のストーリーテリング
●どうして人は地球滅亡・人類滅亡の物語を創り続けるのか?
読書の秋は世界名作を読みなおして、人生を書きかえよう。
「嵐が丘」への旅はいかが?

おりべまこと電子書籍 新刊予告
「再読・嵐が丘」 10月26日(木)発行予定
秋の読書シリーズ第1集。
エミリー・ブロンテ「嵐が丘」は恋愛小説ではなく、
毒親に打ち克つ子供たちの勇気の物語。
コロナが終わったからって
わざわざ人ごみの観光地に出かけなくても
本の中で素晴らしい旅が体験できます。
ブロンテ、カフカ、キングなどの
"こんな読み方もできるんじゃね?"的名作読書ガイド。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から
15編のエッセイを編集・リライト。
第2集「再読・坊ちゃん」
第3集「再読・村上春樹」も準備中。
どうぞお楽しみに。
「叔母Q」 発売記念4日間無料キャンペーン

新刊「叔母Q」発売記念4日間無料キャンペーン
本日10月14日(土)17:00~10月17日(火)16:59
AmasonPrimeキャンペーンのついでにぜひどうぞ。
叔母の温子(ながこ)は
ロサンゼルスの下町のアパートで孤独のうちに死んだ。
リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で
彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、
可愛がってくれた叔母と
昭和の家族についての話を葬儀屋に語る。
子供だった「わたし」と、
戦後の時代を生きた叔母との記憶の断片を
つなぎ合わせた物語。
短編。2万3千字。
叔母Q

おりべまこと電子書籍新刊「叔母Q」 本日発売
叔母の温子(ながこ)は
ロサンゼルスの下町のアパートで孤独のうちに死んだ。
リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で
彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、
可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を
葬儀屋に語る。
「わたしも叔母のことが好きでした」
そう口にするとあの口もとのホクロを思い出した。
家族だった彼女は恋人でもあった。
生まれて初めて意識した大人の女だった。
子供だった「わたし」と、
戦後の時代を生きた叔母との記憶の断片を
つなぎ合わせた物語。短編小説。2万3千字。¥500
もくじ
1 パンパン 1960年
2 リトルトーキョー 2023年
3 結婚式 1988年
4 昭和家族 1960年代
5 チューベー 1968年
6 ナンシー 2023年
7 母と叔母 1968年
8 GHQ 1945年
9 ロサンゼルス 2023年
10 姪と叔母 2023年
おりべまこと電子書籍新刊 おとなも楽しい少年少女小説「叔母Q」
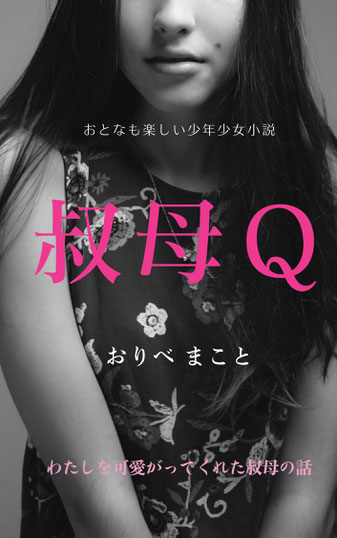
叔母の温子はロサンゼルスの下町のアパートで孤独死した。
リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で
彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、
可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を
葬儀屋に語る。
「わたしも叔母のことが好きでした」
そう口にすると彼女の口もとのホクロを思い出し、
閉じられていた記憶の扉が次々と開いていった。
短編(2万字) 10月12日(木)発売予定。
豊臣秀吉とジャニーズ 英雄の凋落と昭和システムの崩壊

大河ドラマ「どうする家康」では
ムロツヨシ演じる豊臣秀吉の最期が近づいている。
次回予告を見る限り、
秀吉は側室である茶々(淀の方)に復讐され、
(心理的に)殺されるという展開らしい。
北川景子が市と茶々(淀の方)の母娘二役なので、
予想はしていたが、やはりショッキングだ。
太閤・秀吉の死因は病死だが、
天下人としてはあまりに寂しいものだったことは
長年の謎とされている。
それをここまであからさまに
愛人の憎しみによってとどめを刺される
というストーリーは前代未聞であり、
衝撃を受ける人は多いのではないだろうか。
茶々は家康が思いを寄せた市の娘であり、
乱世のなかで非業の死を遂げた
信長と市というカリスマ兄妹が
転生した存在とも言える。
父(浅井長政)と母(市)を殺し、
自分を凌辱した男に対する凄まじい復讐。
彼女が一種のモンスターとなって
最後に家康の前に立ちはだかるというのは
ドラマとしてすごいダイナミズム。
市と淀を見事に演じ分ける北川景子の演技は
(あざとさも含めて)ヤバすぎる。
秀吉は昭和の成長時代、
庶民にとって英雄以外の何者でもなかった。
戦国武将の中でも人気抜群であり、
百姓の子せがれから天下人に成りあがった
サクセスストーリーは、誰もが見習うべきものであり、
みんなが尊敬すべき人物だった。
それが平成時代を通して、
徐々にそのヒーローの皮がはがされていき、
負の部分も含めて人間くさい側面に
光が当てられるようになっていった。
そして令和の今、このドラマでは
かつての英雄像の「凋落」ともいえる扱い。
その伏線は昨日の放送回における
高畑淳子演じる大政所(秀吉の母・仲)の
臨終のセリフに現われている。
「あの息子は自分が本当は何を欲しかったのか、
自分でわからなくなってしまった」
このドラマは家康が主役なので、
秀吉がなぜあれほど民衆に慕われ、
人を惹きつけたのかといった
ポジティブな面はほとんど描かれない。
逆にその俗物的な部分や、
自分の欲望を満たすためには手段を選ばない
あくどさばかりが強調されていることに
秀吉ファンは怒りさえ覚えるだろう。
僕はべつに秀吉ファンではないが、
地元の名古屋で育ったので、
やはり秀吉は尊敬すべき英雄であり、
いわば正義の基準だった。
ちなみに名古屋駅には太閤口という玄関があり、
太閤通りという道路が走っている。
名古屋の人たちは、まさかわれらが太閤様が
テレビドラマでこんなふうに描かれる時代が来るとは
夢にも思っていなかっただろう。
ドラマは時代の変化・価値観の変化を
如実に表すメタファーである。
こうした秀吉像の変化は、
リアル世界では芸能界の英雄として亡くなった
ジャニー喜多川氏と重なる。
製作者側はもちろん、そんなことは意図していない。
これは僕の個人的な見解だが、
まんざら見当違いでもないと思う。
今年のはじめ頃、ジャニー氏がここまで国内で糾弾され、
彼の犯罪を隠蔽し、王国を守ってきた
ジャニーズ事務所がこんな惨状になろうとは、
少なくとも一般人は誰も予想していなかった。
長らく日本を支え、生き延びてきた昭和システムが
音を立てて崩壊したのだ。
この事実は芸能やマスコミの世界のみならず、
いろいろな所に波及していくだろう。
日本の社会を覆っていた昭和の幻影が拭い去られた———
まだ1年を振り返るのには早すぎるが、
この先、令和5年、2023年は
そういう年として記憶されるかもしれない。
母校 池袋の舞台芸術学院を訪ねる
昨日ふたたび池袋へ行く。
10日あまり前とは別の仕事の取材だが、
たまたま同じ池袋。
先月は雨天であまり街の写真が撮れなかったので、
少し早めに行ってスマホでウロウロ撮影作業。
劇場の話に合わせる写真がいるので、
西口にあるわが母校 舞台芸術学院にも足を運んでみた。
卒業したのはもう43年も前のことだ。
当然、校舎は改築されているが、
場所も道路を通し、区画整理した関係で
僕たちの通っていた頃より20mほど移動している。
創立されたのは1948(昭和23)年。
終戦からまだ3年目のことで、
このあたり一帯は焼け野原だったらしい。
ホームページを見て見たら、
こんな創立の物語があった。
https://www.bugei.ac.jp/about/school/
演劇を志したひとりの青年、野尻徹。
彼は幸運にも復員し、池袋で演劇活動の拠点、
「スタジオ・デ・ザール」を開設しました。
しかしその志半ば、彼は27歳でこの世を去ります。
彼の演劇への「思い」はここで潰えたようにみえました。
しかし、彼のあまりにも早い死を悲しんだ父、
与顕は息子の遺志継承を願います。
「地に落ちた一粒の麦、徹死して幾百幾千の
舞台人となって実るであろう事を」
1948年9月13日、与顕は焼け跡の残る
東京・池袋に演劇を渇望した息子、
徹の遺志を継ぐべく、私財を投じ、
若者が演劇に打ち込むための場
「舞台芸術学院」を創立しました。
(※以上、ホームページより抜粋)
初代学長である秋田雨雀、副学長である土方与志は、
日本の近代演劇史・文化史に名を遺す人なので
いちおう知っていたのだが、
真の創設者である野尻さん親子のことは
恥ずかしながらまったく知らなかった。
これは75年前、西口公園に闇市が群れをなし、
池袋全体がダークでカオスな街だった時代の話である。
(池袋のヤバさ加減は、小説・ドラマになった
「池袋ウェストゲートパーク」あたりまで引き継がれてた)
75年の歴史のなかで有名・無名かかわらず、
多くの演劇人、そして、そこに連なるハンパ者たちを
輩出している舞台芸術学院。
60年代の舞芸の学生が、南池袋の仙行寺と関わったことから
小劇場「シアターグリーン」が生まれ、
その活動が波及し、西口公園の
「東京芸術劇場」につながり、
その他、東口の「サンシャイン劇場」「あうるすぽっと」、
野外劇場「グローバルリングシアター」、
最近ではシネマコンプレックス、商業施設と一体化した
文化施設「HAREZA(ハレザ)」の一角を占める
「東京建物ブリリアホール」という劇場もできた。
百貨店・家電量販店・アニメショップなどの
印象が強い池袋だが、
いまや新宿・渋谷をしのぐ劇場が花咲く街である。
その最初の一粒がわが母校だったことに
改めて驚きと感動を覚えた。
在籍時を含めて45年間、創立の話を知らなかったのは、
ハンパ者卒業生の一人として、ほんとに恥ずかしい限り。
長い時間を要しないと、僕のようなボンクラには
世界が見えない、意味が分からない。
しかし、とりあえずこの母校と池袋の劇場の件については
死ぬ前に気付いてよかった。
自分の新しい歴史がまた新しく始まった気がする。
映画「ロスト・キング」ーーリチャードⅢ世遺骨発掘の物語

何かを達成するのはクレイジーなエネルギーである。
フリッパ(離婚したシングルマザーの中年女性)は、
たまたま子どもの付きそいで
シェイクスピア作の「リチャードⅢ世」の舞台を見る。
それが彼女の人生を変えた。
リチャードⅢ世の霊が彼女にとりついた。
あの世からやってきたリチャードとの対話から
彼の遺骨が墓にも納められず埋もれ、
名誉を棄損されていることを知る。
そして8割方インスピレーションによって、
その遺骨の眠る場所を探り当てる。
こう書くと、荒唐無稽なオカルト映画、
あるいはインディー・ジョーンズのような
考古学者の冒険譚なのかと思うかもしれないが、
これは事実をもとに作られた映画である。
英国レスターにおいて
リチャードⅢ世の遺骨発掘が行われたのは、
わずか5年前。2,018年のこと。
国営放送BBCは、そのドキュメンタリーを作ったが、
それを劇映画化したもの。
脚色・演出はされているが、
ストーリー自体は事実そのもである。
主人公のフリッパは、
もともと考古学に縁もゆかりもないもない。
「リチャードⅢ世」は、知る人ぞ知る、
シェイクスピア劇の中でも屈指の人気を誇る作品だ。
リチャードがこの世を去って1世紀後、
シェイクスピアがその伝説をもとに造形したのが
せむしで醜く、心も歪み荒んだ極悪の王。
その残虐非道さ故、
英国歴代の正当な王とは認められていなかった。
しかし、リチャードの人柄と行為は、
彼のあとに政権を握った王朝が、
自らの正義を民衆に示すために捏造したものだった。
ちょうど明治政府が徳川幕府の政治を貶めたように。
江戸幕府の開幕時、
徳川家が豊臣家の影を消し去ったように。
フリッパはリチャード(の幻影)との対話と、
あくなき調査によってそのことを確信し、
遺棄された彼の遺骨のありかも突き止め、
孝行学者と大学を動かして発掘調査を行う。
あくまでドキュメンタリー風の作品なので、
ドキドキハラハラみたいなエンタメ感は乏しいが、
面白く、妙に感動的な映画だ。
フリッパの行動の動機は、
世紀の発見をして歴史を覆してやろうといった
崇高な目的や野心のためでもなく、
もちろん一発当ててやろうという金儲けや
損得勘定のためでもない。
本当に霊に取りつかれてしまったか、
リチャードに恋をしてしまったか、
要ははた目から見たらめっちゃクレイジーな熱意なのだ。
それでも元夫や子供たちは彼女を応援し支える。
あくまでドキュメンタリー風の作品なので、
ドキドキハラハラみたいなエンタメ感は乏しいが、
そうした家族愛もあり、面白く、妙に感動的な映画だ。
そしてもう一つ。
彼女が自分の発想で、単独で始めたことを、
世紀の大発見という成果が得られると、
ちゃっかりその手柄を横取りし、
自分たちの栄誉にしてしまおうとする
大学や学者の在り方も、
リチャードを貶めた次期王朝権力と重なって面白い。
歴史は常にその時々の勝者・成功者・権力者が
つくってきたものである。
僕たちが英雄と信じている人が、
とんでもない悪人や詐欺師だったり、
悪漢や愚者だと思っていた人が、
実は英雄だったりすることもある。
インターネットが発達した世の中では
そうした驚くべきどんでん返しも起こり得る。
世界はまだまだ神秘にあふれ、
変化していく可能性を孕んでいる。
歴史が深く、多彩な物語が眠る英国だから作り得た
と思われるこの映画は、
そんなことまで考えさせてくれる。
アメリカンドリーマーだった叔母の話

仕事が一段落し、しばし猛暑から解放されたので、
義母を連れて阿佐ヶ谷をぶらぶらしに行く。
アンティーク雑貨店のショーウィンドウに
全身アメリカンファッションのマネキンを見て、
義母と同い年(昭和10年=1935年生まれ)の
叔母のことを思い出した。
小学校の低学年の頃まで数年間、一緒に住んでいて、
甥である僕をずいぶん可愛がってくれた。
アメリカ大好きな人で、
結構ハイカラな考え方・ライフスタイルを持っている
叔母だった。
彼女がティーンエージャーだった時代、
日本はGHQ=ほぼアメリカの占領下だった。
ただし彼女が若い頃は、まともな日本人の女は、
もちろんこんな格好はできなかった。
GHQが去り、高度経済成長が始まって、
彼女は新しく生まれた自由な戦後世代を
羨望の目を持って見ていたイメージがある。
ガキだった僕を相手に
「わたしももう10年遅く生まれていれば・・・」と
呟いていたことをいまだに憶えている。
小学校の高学年になる頃には、
もう離れて住むようになっていたし、
両親もあまり彼女のことを話さなかったので、
その後の叔母の人生はよく知らない。
僕は漠然と、
いずれ彼女はアメリカに移住するのだろうと思っていたが、
まだ一般庶民がそう簡単に海外に行ける時代ではなかった。
その代り、というわけではないが、
中年になってちょっとお金持ちのおっさんの後妻になった。
その叔母は兄である父より先、15年ほど前に亡くなった。
亡くなった時は独身だった。
結婚はあまりうまくいかなかったのか?
その辺の事情は結局わかかずじまいだ。
わかっているのは彼女にとって、
憧れていたアメリカは最期まで遠い地だった、
ということだけだ。
自分も大人になってわかったが、
まだチビの甥や姪というのは、自分の息子・娘と違って、
割と無責任に甘やかし、可愛がれる、
オモチャやペットのような存在だ。
たぶん僕の中にはあの叔母に甘やかされたことが、
のちの女性観にも影響しているのではないかな、
と思うことがある。
思いがけず面影がよみがえったこの叔母の供養のために、
何か彼女をモデルにした話を書こうと思っている。
坊ちゃんとマドンナと清さん

夏目漱石の「坊ちゃん」を初めて読んだのは
小4か小5のときだった。
以来、何度か読んで、
最後はいつだったのか思い出せないが、
多分、高校生の時以来だろう。
ご存じ、江戸っ子口調の名調子。
これほど痛快で印象的な一人称の語り口は、
この作品とサリンジャーの
「ライ麦畑でつかまえて」ぐらいだ。
図書館のヤングアダルト文庫の棚で
ふと目にすると、あのべらんめえ文体が脳裏によみがえり、
手に取って読みたくなったのだ。
★なぜマドンナが表紙を飾るのか?
表紙にはマンガっぽいイラストで
主人公の坊ちゃんとマドンナが描かれている。
近年、なぜか「坊ちゃん」というと
表紙にマドンナが登場するパターンが多い。
内容を知らない人、
あるいは昔読んだがよく憶えていないという人は、
赴任先の松山で、名家のお嬢さんであるマドンナと
坊ちゃんが出会い、憧れ、恋をする、
というストーリーを思い描くかと思う。
ところがこれはまったくの誤解で、
主人公はマドンナに何の感情も持たない。
むしろ「うらなりから赤シャツに寝返った女」として
あまり良い感情を抱かないと言ってもいいぐらいだ。
出版社は「明治の青春小説」と銘打っているし、
明治ファッションの女性は飾りになるので、
ほとんど活躍の場がないマドンナを
表紙に載せたがるのだろう。
誤解するのは読者の勝手というわけだ。
昭和以降、特に戦後の青春小説・青春マンガには
この「マドンナ」という、男の女性幻想をかたちにした
偶像が頻繁に登場するようになった。
果ては歌謡曲のタイトルになったり、
アメリカの歌手が自分でそう名乗ったりしたので、
一般的にすっかり定着したが、
明治の頃は西洋画に精通した人以外、
マドンナなんて初めて聴く言葉で、
意味など知らないという人が大半だったと思われる。
だから日本人にマドンナの
「聖母・聖女=清く、美しく、愛し尊敬すべき女性」という
イメージを植え付けたのは、
漱石作品の中でも最も人気が高い
この小説だと言っても過言ではないだろう。
★マドンナは清さん
しかし、この定義からすれば、
坊ちゃんから見るマドンナは、
子供の頃から可愛がってくれ、
惜しみない愛情で支えてくれた清さんの方である。
そう言えば、僕が小学生の時に初めて読んだ本の表紙には、
坊ちゃんが見上げる空の向こうには、
ちょっとだけ微笑む和服姿の清さんが描かれていた。
しかし、清さんは若くてきれいなお嬢様ではなく、
坊ちゃんの家の下女、住み込みのお手伝いさんで、
しかもけっこう年寄りである。
この小説の登場人物は、主人公をはじめ、
一人も年齢が特定されていないが、
物語の舞台が発表時の
明治39年(1906年)あたりだとすると、
ほとんどは明治生まれ・明治育ちの人たちである。
ただ一人、清さんは明治維新を体験した人だ。
武士の名家の出身らしいが、
「瓦解(明治維新)の時に零落して、
ついに奉公までするようになった」というから、
おそらく50代後半~60代前半である。
いまと違ってもう立派なお婆さんだ。
しかも人生の辛酸をなめた元・お嬢さまの。
子ども頃から可愛がってもらっているのだから、
母や祖母のように慕うのはわかるが、
坊ちゃんの清さんへの感情は、
そうした家族に対するものとはまたちょっと違う。
さりとて恋愛でもない。
もっと齢が近ければ、そうなり得たかもしれないが、
あまり生々しさを伴わない、尊敬の念を交えた、
女性という偶像に対する愛情が混じっている。
子供の頃は母以上に彼を可愛がった清さんは
坊ちゃんの将来に夢を託し、
おとなになったら面倒を見てもらおうと思っている。
そういう意味では彼女の愛もけっして純粋なものではなく、
ギブアンドテイクの関係と言えなくもない。
ただし、成長した坊ちゃんは、
自分に期待を託す彼女の言うことは、かなりおかしく、
贔屓の引き倒しで、現実離れしていることに気付く。
「こんな婆さんに逢ってはかなわない。
自分の好きな者は必ずえらい人物になって、
嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じていた」
「婆さんは何も知らないから、年さえとれば
兄の家がもらえると信じている」
「(学校を)卒業すれば金が自然とポケットの中に
湧いてくると思っている」
などと冷静に分析し、
“もとは身分のある者でも、
教育のない婆さんだから仕方がない”清さんの
無知ぶり・夢みる少女ぶりにあきれ果てている。
それでも坊ちゃんは清さんを嗤ったりは絶対しない。
彼にとって、知識量・情報量は、
人間的な価値とは決して比例しないのだ。
子供の頃、読んだときは気が付かなったが、
この二人のやりとりは本当に面白く、笑えて哀しく、
清さんはめっちゃ可愛い。
松山で教職に就き、不快な目に会うたびに坊ちゃんは、
そんな清さんの人間的な気品・尊さに思いを巡らせるが、
痛快なストーリーの裏側で、
こうした女性への愛とリスペクトの念があるからこそ、
この小説を単なる面白ばなしでなく、
奥行きと味わいの深いものにしている。
★時代に取り残される坊ちゃん
「坊ちゃん」の読み方の一つとして、
「時代に適応できる者とできない者の物語」
という視点がある。
前者は、話の中で悪人とされる赤シャツや野だいこであり、
後者はとっちめる側の正義の坊ちゃんや山嵐だ。
マドンナも、坊ちゃんからは
うらなりから赤シャツに寝返った、
およそマドンナらしくない女と見做されるが、
彼女は若かりし頃の清さんと同じ立場にある。
この時代の女性の社会低地位は低く、
生き方は今と比較にならないほど制限されていた。
没落寸前の名家の娘として、
いくら身分があるとはいえ、
世渡り下手・自己主張ベタ・まじめなだけで面白くない
許嫁のうらなりよりも、
既に教頭職を得て、将来有望、しかも話術に長けていて
楽しませてくれそうな赤シャツのほうになびくのも
しかたがないところだろう。
下手をすれば清さんと同じく、
零落の道に転がり落ちることになるので必死なのだ。
マドンナとあだ名をつけられて、
男性の夢を壊さないよう、ホホホとおとなしく
笑っているわけにはいかない。
マドンナファンには申し訳ないが、
もしかしたら、彼女の方が赤シャツに目を付け、
誘ったのではにかとさえ思える。
楽しくて痛快な「坊ちゃん」だが、
この明治後期、時代は変わり、
価値観も急速に変わっていた。
よく読むと、それを表現するかのように、
この物語は別れの連続だ。
母が死に、父が死に、生れ育った家は人手にわたり、
兄とも別れ、いわば天涯孤独の身の上になる。
松山ではうらなり(坊ちゃんは彼を人間的に
上等と評価している)を見送り、
赤シャツ・野だいこを叩きのめして訣別するが、
相棒で親友になった山嵐とは新橋で別れる。
ちなみに幕府軍として
明治政府と最後まで戦った会津出身の山嵐は、
江戸時代のサムライ精神の象徴とも取れる。
そして帰って来た彼を涙ながらに出迎えてくれた
マドンナ清さんも、
それからいくらも経たないうちに肺炎で死んでしまう、
坊ちゃんは本当にひとりぼっちになってしまうのだ。
★坊ちゃんは何歳なのか?
今回、読み返してみて、最大の疑問として残ったのは、
この物語を語っている時の坊ちゃんは、
いったい幾つなのだろうということ。
東京に帰って来た彼は街鉄(電車)の技手になり、
清さんと一緒に暮らし始めたもののが、
最後に清さんは「今年の2月に死んでしまった」とある。
ニュアンス的に、仕事に慣れ、生活も落ち着いてきた矢先に
亡くなってしまったと読めるから、
新しい仕事に就いてから1,2年後くらいだろうか。
そしてそれから半年ほど経ってから、
自分の人生を振り返った時、
松山での経験と、清さんという存在の大きさを
語ってみたくなったということだろう。
だとしても、坊ちゃんはまだ20代の溌剌とした若者だ。
その後、彼がどうしたのか、
兄や山嵐と再会する機会はあったのか、
結婚して家庭を持ったのか、興味津々である。
でもきっと、どれだけ年をとっても
この物語のような名調子は消えなかっただろう。
坊ちゃんという人物は、時代に適応できない者の代表格で、
自分の価値観に固執するあまり、教職を失ったが、
それでも新しい職を得て、一人でも生きる道を見出した。
★死ぬまで続く名調子
この頃と同じく、
最近も時代に合わせる
必要性・適応する柔軟性が強調されるが、
人間だれしも、
生まれながらの「自分のリズム」を持っている。
それをないがしろにして、周囲に合わせようとすると、
やっぱりろくなことにならないのではないか。
たとえ得になる生き方だとしても、
損をしない人生だとしても、
それが自分のリズム・語り口・文体と相いれないものなら
気持ち悪くて、長続きなどしない。
世間に通用してもしなくても、
坊ちゃんのように自分のべらんめえを並べ立てて
生き抜いた方がうんと気持ちいいのではないだろうか。
気分が凹んだときの活力剤として、
「坊ちゃん」は、はるか1世紀を超えた過去から
今でも僕たちにいろんなことを教えてくれていると思う。
週末の懐メロ148:ウェルカム上海/吉田日出子
1979年、オンシアター自由劇場が上演した音楽劇
「上海バンスキング」のテーマ曲。
昭和10年代(1930年代後半から40年代前半)の
上海租界を舞台に、
享楽的に生きるジャズマンをめぐる物語で、
劇中演奏されるのはジャズのオールドナンバーだが、
オープニングとクロージングを飾るこの曲はオリジナル。
主人公のまどか役で歌手の吉田日出子は
小劇場界では名の知れた魅力的な女優だったが、
この芝居まで歌手としての経験はほとんどなかった。
また、ジャズマンたちも串田和美(シロー)や
笹野高史(バクマツ)をはじめ、楽器は素人同然。
にもかかわらず、演奏はノリにノってて素晴らしかった。
それはもちろん、この物語がとてつもなく面白く、
感動的だったからである。
僕は「上海バンスキング」の初演を見た。
当時、オンシアター自由劇場の拠点劇場は、
外苑東通りと六本木通り(首都高3号)とが交わる
六本木交差点からすぐ近くの雑居ビルの地下にあった。
キャパ100人の小さな劇場(というよりも芝居小屋)には
観客が溢れかえり、
広さ8畳程度の狭い舞台には、
主演級の他、楽器を携えた楽団員役を含め
20人を超えるキャストが出入りして熱演した。
あんな狭いところでいったいどうやっていたのか、
思い出すと不思議で仕方がない。
舞台となるのは、まどかとシロー夫妻の家の広間だが、
舞台セットなどは椅子とテーブルがあるだけ。
そこが突如ジャズクラブに変貌したりするシーン構成、
いろいろな登場人物が錯綜するストーリー展開、
そして時代が日中戦争、さらに太平洋戦争へ続いていく
ドラマの流れは、リアリズムをベースに、
時にファンタジーが入り混じり、
さらに歴史の残酷さを描き出す叙事詩にもなるという、
舞台劇の醍醐味に満ちていた。
ジャズと笑い・ユーモアに彩られながらも、
「上海バンスキング」はけっしてハッピーな物語ではない。
後半は戦争の暗雲が登場人物たちの人生を狂わせていき、
終盤、自由を、仲間を、そして音楽を失ったシローは、
アヘンに溺れ、やがて廃人になってしまう。
変わり果てた夫を抱きしめて、まどかは最後に
「この街には人を不幸にする夢が多過ぎた」と呟く。
ひどく苦い結末を迎える悲劇なのだが、
追憶の中、二人の心によみがえる「ウェルカム上海」は、
思わず踊りだしたくなるほど陽気で軽やか。
その楽しいスウィングは、
同時に哀しく美しい抒情に包まれる。
劇作家・斎藤憐はこの作品で
演劇界の芥川賞とされる岸田國士戯曲賞を受賞。
オンシアター自由劇場は
1979年の紀伊国屋演劇賞団体賞を受賞。
再演するごとに人気は高まり、
キャパ100人の劇場は連日満員で客が入りきらなくなり、
やがて大きな劇場で何度も再演されることになる。
それまで演劇など見たことのなかった人たちでさえも
虜にし、1984年には、深作欣二監督、
松坂慶子・風間杜夫の主演で映画化。
20世紀の終わりまで上演され続ける
日本の演劇史に残る名作になった。
オールドファンとしては、
吉田日出子をはじめとするオリジナルキャストの
歌・演奏・演技はあまりにも印象的で忘れ難いが、
新しい若いキャストで今の時代に再演しても
ヒットするだろうと思う。
不幸のリスクを背負っても夢を求めるのか、
夢など見ずに幸福(というより不幸ではない状態)を
求めるのか、
いつの時代も、いくつになっても、
人生の悩みと迷いは変わらないのだ。
もう一度、舞台で「ウェルカム上海」を聴いてみたい。

夏休み無料キャンペーン第5弾
「ポップミュージックをこよなく愛した僕らの時代の妄想力」
8月20日(日)16時59分まで
ポップミュージックが世界を覆った時代、ホームビデオもインターネットもなくたって、僕らはひたすら妄想力を駆使して音楽と向き合っていた。
心の財産となったあの時代の夢と歌を考察する音楽エッセイ集。
映画「ザリガニの鳴くところ」 陸と海との境界の物語

事件の真相は、初恋の中に沈んでいる――。
宣伝コピーがカッコいい「ザリガニの鳴くところ」は、
全世界で累計1500万部を売り上げた
ディーリア・オーエンズの同名小説の映画化。
1969年、ノースカロライナ州の湿地帯で、
将来有望な金持ちの青年が変死体で見つかる。
殺人事件の容疑者として逮捕されたのは、
「湿地の少女」と呼ばれる孤児の女の子。
彼女を裁く陪審員裁判で事件の真相が明かされていく。
しかし、本当の真実が明かされるのは
それから半世紀のちの現代(映画のエピローグ)。
人生の結論はすぐには現れず、
目に見えないところに深く沈み、
思いがけない時に浮かび上がってくる。
原作小説は一昨年、読んでいた。
作者のオーエンズは動物学者で、
その知見をふんだんに活かし、
湿地の生態系について詳しく描写しており、
それと人間ドラマとがブレンドされて、
詩的でスケールの大きな物語になっている。
湿地という土地自体がミステリアスで、
様々な暗喩に満ちており、
人間の心のなかの世界を表現しているかのようだ。
ただ、ミステリー映画という頭で見ると、
正直、論理的に甘い部分が気になるかもしれない。
冒頭の宣伝コピーも
実際の内容とはちょっとズレてる感じが否めない。
映画化に際してストーリーは単純化され、
殺人事件の真相解明に焦点が絞られているが、
アメリカ社会に深く根を張った
児童虐待・家庭崩壊の問題も
もっと突っ込んで描いてよかった気がする。
アマプラで見た(今でも見られる)が、
陸と海との境界となっている雄大な湿地帯の風景と、
そこで暮らす人々のライフスタイルは、
映画館のスクリーンサイズで見たかった、という印象。
その映像をバックにしたプロローグとエピローグの
ナレーションもしびれるほど詩的でイマジネーティブ。
「ザリガニの鳴くところ」というタイトルの意味も分かる。
そして、ラブシーンがいい。
ドラマの文脈、映像の美しさ。
若い俳優さんがあまり美男美女過ぎないのもいい。
こんなきれいなラブシーンは久しぶりに見た気がして、
年甲斐もなく、ムズムズソワソワしてしまった。

夏休み無料キャンペーン 第4弾
ちち、ちぢむ
8月18日(金)15時59分まで
ろくでなしだけど大好きなお父さんが
「ちっちゃいおじさん」に!
人新世(アンドロポセン)の時代を生きるアベコベ親子の奇々怪々でユーモラスな冒険と再起の物語
手鎖心中/江戸の夕立

井上ひさしの「手鎖心中」は
歌舞伎にもなった直木賞受賞作。
この作品も面白いのだが、
併載されている「江戸の夕立」が
表題作に輪をかけてめっちゃ面白い。
長めの中編というか、短めの長編というか、
そこそこボリュームもあるので、
読みごたえもたっぷり。
主人公は大商店の放蕩息子の若旦那と
そのご祝儀目当てでベタベタお世辞を連発しながら
くっついて歩く太鼓持ち。
平和な江戸の街で、ぬくぬくした環境で生まれて育って、
軽薄短小な人生を謳歌する二人組の軽妙なやりとりで、
ハリウッド映画ばりの波乱万丈の物語が綴られていく。
はでに買い物したり、花魁遊びが出来たのも序盤まで。
その後は江戸を離れ、東北地方を放浪するはめに。
しかもそれは暴力、漂流、バクチ、友情、裏切り、
奴隷労働、疫病、借金、旅芸、女狂い、家庭崩壊など、
現代の、僕らの人生でも起こり得る、
あらゆる災厄のてんこ盛り。
笑いとユーモアの味付けで救われているが、
まさに地獄めぐりの旅である。
そんなひどい目に遭いながらも
人間的に成長するわけでなく、
放蕩していた頃のろくでなしのまま、
9年をかけてやっと江戸の街に帰ってきた二人。
ところがその故郷はなんと・・・という展開で、
けっしてハッピーエンドとはいえない、
かなり苦み走ったラストを迎える。
ただ、このラストが僕は好きである。
すべてを失った代わりに、
彼らは生きるための何かを得た、
その思わせてくれる、心に響く結末だ。
井上ひさしはお芝居もたくさん書いていて、
ユーモア・人情を描く作家だと思われている。
しかしその実、彼が人生・人間社会を見る目は
かなりシニカルで、だからこそユーモア・人情が映え、
胸に深く沁み込んでくる。
地獄の奴隷労働の仲間が死の間際、
「女の裸が見てえ」という願いをかなえるために
キリシタンの娘が一肌脱ぐシーンなどは
涙が止まらんかった。
いくら齢を取ったって人間、
大して成長するわけではない。
バカはバカのまま、ろくでなしはろくでなしのまま。
だから笑えて泣ける。だからいいのだ。
最近やたらと多い感動の美談、
人間ってすばらしい!と讃えるストーリーに
食傷気味の方におすすめです。
幸福を追求して人間を改造する「シン・仮面ライダー」

アマプラで「シン・仮面ライダー」を見た。
すごいなと思ったのは、敵であるショッカーの設定。
悪の組織であるはずのショッカーは、
なんとこの作品では「人間の幸福を追求する組織」である。
フルネームだと「Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling」。
「計画的知識を埋め込んで改造した持続可能な幸福の組織」
とでも訳せばいいのか。
それぞれの頭文字をつなげて「SHOCKER」。
もちろん、これは庵野監督の創作である。
怪人(改造人間)のモチーフが昆虫であるところを
考え合わせると、地球環境との調和も追求しているようだ。
当然、この幸福の追求は、
一般社会で生活する人間にとっては
歪んだおぞましいものだが、
主人公の仮面ライダー・本郷猛も、
ラスボスであるショッカーの首領も、
不条理な無差別殺人事件によって父や母を奪われた遺族である。
彼らの立場になって考えていくと、
つまり見方を変えると、ショッカーが目指すものこそ
正義と捉えてみてもおかしくない。
もちろん、本当のご遺族の方が
こうした考えを持つようになるということではないが、
原典の「仮面ライダー」が持つテーマ性を深堀りして、
現代に新たな世界観を築き上げた
庵野秀明監督の想像力・創造力はやはり尊敬に値する。
ゴジラやウルトラマンと違って、
仮面ライダーは等身大のヒーローであり、
この話は、僕たちの人生とごく身近な、
家族・友人・その周りの社会をめぐる物語とも言える。
1号・本郷猛と2号・一文字隼人との
人間関係・信頼関係の成り立ちも良い。
登場人物の中ではヒロインのルリ子がとてもよかった。
演じているのは、今やっている朝ドラのヒロイン役
(牧野博士の妻)の浜辺美波。
狂言回しのような役柄で、
彼女のセリフと行動によって
この話の世界観・構造が語られていくのだが、
彼女と彼女に対する本郷の愛あっての
「シン・仮面ライダー」という感じがする。
僕はテレビの「仮面ライダー」が始まった頃、
すでに小学校の高学年だったので、
やや冷めた目で見ていて、
初期シリーズ(1号・本郷猛のシリーズ)を
半分ほど見ただけだ。
ウルトラシリーズと違ってほとんど思い入れがないので、
今回も期待せず、事前情報もほとんど仕入れていなかった。
結局、劇場に行かず、アマプラで見てしまったのだが、
すばらしかった。
「幸福のために人間を改造する」というテーマのもとで
これだけの物語を作り得るのはすごいことだ。
「仮面ライダー」なんて知らない・興味ないという人も
ぜひ観て見るといいのでは、と思う。
カッパの正体を解明(?)した本

頭にお皿、背中に甲羅、口はくちばし状、手足に水かき、
からだは人間の子ども(幼児~小学校低学年)
くらいの大きさで、
皮膚がヌメヌメしていて体色は緑系。
いたずら好きで、キュウリが大好物。
過去100年くらいで、
日本人の間にそんなカッパのイメージが定着した。
地域によってまちまちだった呼び名も、
かの芥川龍之介が、死の間際、
そのものズバリ「河童」という小説を書いてから
統一された感じがする。
そのカッパは実在するのか否か?
その他、柳田国男の「遠野物語」をとっかかりに
東北の民話の世界を探検し、
登場する怪異・妖怪の類の秘密を解き明かそう
というのがこの本「荒俣宏妖怪探偵団 ニッポン見聞録」
の趣旨である。
おなじみ、この手の妖怪学・博物学の大家・
荒俣宏先生を中心に、
小説家・理学博士がチームを組んで、
東北各地の大学教授・学者、博物館などの研究員、
郷土研究家、お寺の住職などを訪ねて回る。
面白いのは、たとえばカッパに話を絞れば、
みんな、カッパの実在を肯定していること。
ただ、そのカッパとされる妖怪は、
“現代人の視点で見ると”、
どれも別の様々な生き物であるという点だ。
あるところではそれはウミガメだったり、
あるところではイモリ、あるところではカワウソ、
あるところではネコだったりする。
それら爬虫類・両棲類・鳥類・哺乳類にまでまたがる
多種多様な生き物が、
「カッパ」という妖怪・生き物に
ひとくくりにカテゴライズされていたのだ。
どういうことかというと、
人間は自分(あるいは自分を取り巻く社会)が持っている
知識・情報の埒外にあるものと遭遇したとき、
「わけのわからないもの」としておくことができず、
それを分類するために
特定のファイルみたいなものを必要とする。
その一つに「カッパ(地域によって呼び名は異なる)」と
題されたファイルがあり、
「これは何だ?わからん」と思ったものをみんな、
とりあえずそのカッパファイルの中に突っ込んでいたのだ。
だからそれぞれの動物の特徴・生態・イメージが、
そのファイルのなかで混ざり合い、繋がり合い、
時には化学変化を起こして、
カッパという妖怪の形になって
多くの人々の頭のなかに生息するようになり、
民間伝承として伝えられるようになった。
そしてまたその伝承・民話をもとにして
時代ごとに絵師などがカッパの姿を絵として描き上げた、
ということらしい。
僕たち現代社会で生きる人間は、
科学的に解明された知識・情報を
すでに頭のなかに仕入れてあるので、
これは犬とか、カエルとか、ウサギであると知っている。
だから、なんでカメやイモリやカワウソやネコを
カッパだなんて思ったんだろう、と不思議がるが、
それは逆で、カッパというファイルの中から
Aタイプが実はカメで、Bタイプがカワウソで、
Cタイプがネコだった・・と、
後で(だいたい明治以降~昭和初期の間に)
分類・整理されたのである。
言い換えれば、江戸時代以前の日本人にとって、
奇妙な野生動物は皆、UMA(未確認動物)であり、
ほんの150年ほど前まで日本の海も山も里もUMAで
溢れかえっていたのである。
この本ではカッパ以外にも
いろいろな妖怪・民俗学的伝承が紹介されているが、
そうした昔と今の人間の心の地図の違いについて
気付かせてくれることに重要な価値があると思う。
荒俣宏妖怪探偵団 ニッポン見聞録 東北編
著者:荒俣宏/荻野慎諧・峰守ひろかず
発行:学研プラス 2017年
空を見る洗たく女

「洗たく女の空とぶサンダル」では
主人公のアカネに教わったことがある。
それはいつでも、どんな時でも空を見ること。
僕たちは空を飛べないけど、見続けることはできる。
この星で暮らす限り、みんな、この空の下で生きている。
空には未来があり、ビジョンがある。
そしてまた空は僕たちの心の中を映し出している。
うまく行かないときは空を見るといい。
雲がどう動いていくのか見るといい。
朝と昼間と夕方は違った顔をしているし、
星が広がる夜空はまた別の世界だ。
潜在意識がどうとか、瞑想術がこうとか、
そんものを学ばなくても、ただ空を見上げるだけで、
これまで見えていなかったものが見えてくる。
できたら毎日。
今日もひどく暑そうだが、
ちょっとの間なら外に出てもいいだろう。
あれば木陰に入って晴れた空を眺める。
空は世界であり、自分自身でもある。

洗たく女の空とぶサンダル
無料キャンペーンは昨日終了しました。
ご購入いただいた方、ありがとうございました。もしよければレビューをよろしくお願いします。
引き続きAmazonKindleで販売しています。他の本も読み放題サブスクもあります。今後も洗たく女を応援してください。
男をいやす はたらく女

先日、若い女の子がゴミ回収の仕事を
やっているところに出くわし、びっくりした。
女子がそうした仕事に就くことに何の異論もないが、
彼女はびしっとメイクしていて、
帽子からはみ出た髪はきれいにサラサラしていて、
ほとんどアイドルみたい。
朝、この仕事でバイトして、作業着から普段着に着替えて
芸能事務所なりロケ現場に行くのだろうか・・・
と勝手に想像した。
本当のところはもちろん知らないが、
その労働する姿とルックスとのギャップに
いたく心癒された。
ご本人はそんなつもりはカケラもないと思うが。
3K的な肉体労働の現場でも、
昔と違って女性がバリバリ働いている。
経済が成長していく時代は、
女はどんな職業・職場でも、
女は日々働く男たちを慰労する役割が中心で、
実際の労働の価値はその副産物でしかなかった。
時は流れ、経済が落ち込み、
男だけじゃダメだということで社会進出が当たり前になり、
今では経済・産業の世界において
女性が主役を務めることも少なくない。
しかし誤解を恐れず言えば、
それでも職場で女は男を癒し、
多かれ少なかれ夢を施している。
これは人間社会が女と男で成り立っている以上、
仕方ないことだと思うし、
それで職場のテンションが上がればいいことだと思う。
ただ、その現実と夢のバランスが崩れると、
世の中ではいろいろ事件が起きる。
「洗たく女と空とぶサンダル」は当初、
足の大きい女性を主人公にして話にしようと
思っていたのが、
いつの間にか、この資本主義社会において
そうした労働に勤しむ女についての幻想が入り込み、
奇妙なファンタジー物に化けた。
はたらく女性と
はたらく女性を愛する男性に読んでもらいたい一冊です。
洗たく女の七夕キャンペーン実施中
7月10日(月)15:59まで6日間無料です。
この機会をぜひお見逃しなく!
おりべまこと おとなも楽しい少年少女小説 最新刊
洗たく女の 空とぶサンダル
amazon Kindleにて発売中(キャンペーン期間中無料)
洗たく女の七夕無料キャンペーン本日スタート!

洗たく女の七夕キャンペーン
本日7月5日(水)16時スタート!
7月10日(月)15:59まで6日間無料です。
この機会をぜひお見逃しなく!
おりべまことKindle電子書籍
おとなも楽しい少年少女小説 最新刊
洗たく女の 空とぶサンダル
まるで足だけガリバー旅行記。
人並外れて足が大きいアカネは、その大足のせいでかわいい靴が履けないし、
人生何をやってもうまくいかないと思いこんでいた。
けれども、そんなコンプレックスのタネだった
大足のおかげで彼女は救われる。
DV夫の顔面にガリバーキックをかましてKO。
離婚して自由になると、足で洗たくをする、
富裕層御用達の洗たく屋に就職し、
ずんずん人生を切り開く。
洗たく女として日々働くようになったアカネは、
ある日、街中で足の向くまま歩いていくと
名誉に迷い込み、靴アートの芸術家に遭遇。
その芸術家が、自分の作品に興味を抱いてくれたお礼に、と贈ってくれた一足のサンダルは、魔法の空飛ぶサンダルで、そこから人々の命の“洗たく”をする
アカネの新しい仕事が始まる。
はたらく女の夢と希望、そして歪んだ現実との格闘・逃走を描く労働ファンタジー。3万2千字。中編小説。
洗たく女の七夕キャンペーン情報

予告!七夕キャンペーンやります。
おりべまことKindle電子書籍 おとなも楽しい少年少女小説
洗たく女の空とぶサンダル
明日7月5日(水)16時から10日(月)15時59分まで
6日間無料キャンペーン
はらたく女の夢と希望、
そして歪んだ現実との格闘・逃走を描く労働ファンタジー。
3万2千字中編小説。この機会にぜひ読んでみてくださいね。
魔法のサンダルを履いた はたらく女のものがたり

おりべまことKindle新刊
おとなも楽しい少年少女小説
「洗たく女の空とぶサンダル」
~魔法のサンダルを履いた はたらく女のものがたり~
1日延びて明後日7月1日(土)発売予定になりました。
当初、1万5千~2万字程度の短編にするつもりだったけど、
やっているうちに3万字超えの中編に育ってしまった。
小説はまとまった時間が必要で大変だけど、
書いているうちに生き物のように踊り出して楽しい。
主人公のアカネちゃん、どうもありがとう。
「街とその不確かな壁」:そこは現代人の魂の拠り所
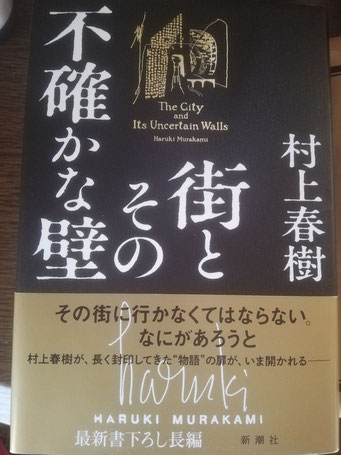
読み終わってまず思ったのが、
40年前の
「世界の終わりとハードボールドワンダーランド」は、
本当に本当に、すごい作品だったな、
また読み直さねば、ということ。
いちばん好きな作品なので、完全に主観、
贔屓の引き倒しだけど。
著者本人があとがきで割とそっけなく
あの作品を書いた時のことを回想しているが、
本当に2本立てなんて手法をよくぞ思いついたものだ。
「ハードボールドワンダーランド」は、
レイモンド・チャンドラーもどきの
スリリングでミステリアスな探偵もので、
あの時代に脳科学を探究した、
めっちゃSFでプログレなエンタメ小説だった。
それが「世界の終わり(=今回の作品のセカンドバージョン)」と共鳴し合うことで、プログレ感二乗。
インスピレーションの大渦巻きが起こった。
結局、村上春樹の小説って
「風の歌」「ピンボール」を序章として、
「羊をめぐる冒険」
「世界の終わりとハードボールドワンダーランド」
「ノルウェイの森」という、
彼の表現スタイルを確立した初期3作で
オールドファンの心は支配されている。
10代・20代であの3作に出逢ってしまった人たちは、
もうそこから離れられないのだ。
本人も言っているように、クオリティ・完成度は
後年の作品の方が高いし、
文章の濃密度は相当増していると思う。
けど、それが作品の魅力と比例するかというと、
どうもそうではない。
何というか、村上さんはさっぱり成長しない
僕のような読者を置き去りにし、
どんどんキャリアを積み上げ、進化したんだろうなと思う。
僕は40年前からカタツムリ程度にしか進んでいないのだ。
そんなわけでこの作品の第1部における
少年と少女のシーンには、
懐かしさとみずみずしさがないまぜになって
思わず涙が出た。
少女はどこか「ノルウェイの森」の直子を想起させた。
けれども「ノルウェイ」のような恋愛ものや、
「羊」や「ハードボイルド」のようなエンタメ感を
この作品に求めるのは間違っている。
そして第1部を読み終えた時に、
前々から思っていた疑問が氷解した。
なぜこんなに村上春樹の小説が売れるのか?
自分も含めてなぜみんな、恋愛でもエンタメでもない、
こんなわけのわからない話を毎度読みたがるのか?
それも日本だけでなく、全世界的傾向だ。
その疑問が第1部を読み終えた時に、
するっとわかった。
村上春樹が書く物語の中には、魂の拠り所があるのだ。
自然から離反し、伝統的な民俗からも離反した、
この200年あまりで形成された、欧米由来の現代文明。
そのなかで人生を送る人間は、
現実的な社会生活を送る心身と、
より深いところで息づく魂とが明らかに分離している。
魂は行き場を失っていつもどこかをウロウロしているのだ。
しかし、村上春樹の物語の中には、
その行き場、魂が落ち着く環境が整っている。
著者自身はそんなこと意識していないと思うが、
僕たちの世代の大勢の読者が、そのことを発見したのだ。
なので、村上小説を読むことは
どこか宗教の信仰に近いものがあるのかもしれない。
それから40年あまり。
日々、とほうもない量のコンテンツが
出されるようになったが、
現代人の魂の拠り所になり得るものは依然として少ない。
需要と供給のバランスは大きく崩れたままだ。
数年に一度刊行される村上春樹の長編は、
その需要に応えられる、
数少ないブランドものコンテンツなのだ。
という視点で読み進めていくと、
第2部は、まさしく魂の拠り所を失った
現代人の放浪の物語になっている。
魂の拠り所を求めて中年になった人と老年になった人、
そしてその下の若い世代の人のことが描かれ、
第3部では中年は再び魂の故郷へ帰っていく。
ただしそこは「故郷」という言葉からイメージされるような
やさしい場所でも、暖かい場所でもない。
「不確かな壁がある街」は、
安全で便利な環境のなかで生活する
現代人の心の中にある街なのだ。
村上春樹はこの20年余りのインタビューやエッセイで、
「世界の終わりとハードボールドワンダーランド」を
書き直したいと、つねづね言っていた。
「街とその不確かな壁」のファーストバージョンは、
それ以前に雑誌に発表したものなので、
今回の執筆は彼にとって、
まさに「3度目の正直」と言えるのだろう。
正直、面白かったとか、感動したとかという感想はない。
ただ、近年の作品にはない、独特の色合いを持った
「純・村上春樹作品」といった印象を受けた。
「海辺のカフカ」も「1Q84」も「騎士団長殺し」も
最初読んだときは違和感だらけだったが、
時間が経ち、何度か読み返すうちに面白くなった。
この作品を通して、村上春樹は、なぜ自分は物語を
紡いできたのかを探究・確認したかったのだと思う。
次に行くために踏まなくてはならないステップ、
超えなくてはならない
「40年間の壁」だったのだろうと思う。
それを果たした今、これから先は
集大成に匹敵する作品に取り組むのだろうか。
というわけでこの本がいいのかどうかの結論は先送り。
正直、面白かったとか、感動したとかという感想はない。
不満を言えば、読んでいて笑える、
ユーモラスな部分がないのが、ちとさびしい。
それから周囲から女の描き方について言われたせいか、
珍しく濡れ場がない。
それとは逆に、近年の作品にはない、独特の色合いを持った
「純・村上春樹作品」といった印象がある。
「海辺のカフカ」も「1Q84」も「騎士団長殺し」も
最初読んだときは違和感だらけだったが、
時間が経ち、何度か読み返すうちに面白くなった。
「街とその不確かな壁」も読み手の変化に応じて
これから先、全然違う作品になり得るだろう。
そして、いつものことだが、村上小説は
「まだおまえの人生には秘められた可能性があるよ」
と感じさせてくれる不思議な力がある。
それこそが単なるエンタメを超えた文学の力だと思う。
週末の懐メロ140:クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ
今年、ロック殿堂入りを果たしたケイト・ブッシュ。
彼女のようなタイプの音楽は、
あまりこうした権威にウケが悪いし、
ファンも殿堂入りがどうこうなんて気にしていない。
しかし昨年(2022年)、
1985年に発表した「神秘の丘」が、
ドラマ「ストレンジャーシングス」の挿入歌に使われ、
世界中で前代未聞のリバイバル大ヒット。
ロック殿堂側もこれ以上、
彼女を無視していられなくなったというのが
正直なところなのだろう。
「クラウドバスティング」は「神秘の丘」と同じく
5枚目のアルバム「愛のかたち(Hounds of Love)」の
挿入歌。
楽曲としては言うまでもなく、
80年代のミュージックビデオとして、
さらにその後、40年弱のポップミュージック史を見ても、
最高レベルの作品である。
「クラウドバスティング」 は本屋で見かけた
ピーター・ライヒという人が書いた本
「ブック・オブ・ドリームス」に
インスパイアされて作りました。
とても変わった美しい本で、
子供のころの父親を見る視線で、
親子の特別な関係について書かれていました。
お父さんは本当にかけがえのない人だったのです。
ケイト・ブッシュがそう語るピーター・ライヒとは、
オーストリア出身で、
精神分析学の権威フロイトの弟子だった
ヴィルヘルム・ライヒの息子である。
この楽曲が描くのは、父ヴィルヘルムと息子ピーターが、
オカルティックな生命エネルギーを駆使して
「クラウドバスター」というマシンを動かす物語。
ミュージックビデオは、
レトロっぽいSF短編映画のようなつくりになっている。
ヴィルヘルムを演じるのは、ハリウッドの名優
ドナルド・サザーランド。
そして息子ピーターはケイト・ブッシュ自身。
この頃、彼女は他の楽曲では成熟した女性の魅力を放ち、
かなり色っぽかったのだが、ここでは髪を切って
一転、男の子に。
父の意志を成し遂げようとする少年に扮し、
美しい丘を駆け上がっていくシーンには
完全にしびれてしまった。
「嵐が丘」「神秘の丘」――
彼女の音楽の世界で、丘は魔法の舞台である。
ヴィルヘルム・ライヒは精神分析家・精神科医というより、
人間の心のありかの研究者・思想家として
20世紀前半に活躍した人。
社会運動にも関わり、
『ファシズムの大衆心理』(1933年)などの著作で
後世にも影響を与えている。
第2次世界大戦が勃発する前にアメリカに移住したが、
その頃からかなりオカルトめいた思想を抱くようになり、
「生命体(organism)」と「オーガズム(orgasm)」を
組み合わせた「オルゴンエネルギー」という
生命エネルギーの概念を打ち出した。
そして1940年、
そのオルゴンを集めるというオルゴン集積器を作り、
ガン患者に効果があると主張し。
これが原因でアメリカ食品医薬品局から
弾圧を受けることになる。
秘密組織の黒服の男たちに拘束される下りは、
そのあたりのドキュメントをドラマ化したものだ。
ここで登場する「クラウドバスター」という
サイケでスチームパンクっぽい怪物マシンは、
オルゴンエネルギーによって雲を創り出し、
大地に雨を降らせるという代物。
連れ去られた父に代わって、
息子がその目的を実現するというストーリーになっている。
雲を作り出すのにクラウドバスター(雲を蹴散らす)
という名は矛盾しているのだが、
これはオルゴンエネルギー(生命エネルギー)が
心の暗雲を払って生命体に潤いをもたらすといった思想の
暗喩になっているのかもしれない。
いずれにしてもこんな虚実ないまぜのSFじみた話から
途方もなくパワフルで美しい楽曲を編み出した
ケイト・ブッシュの才能はすごいの一言。
そしてこのビデオのラストシーンーー
丘の頂上で怪物マシンを稼働させた少年のシルエットは、
ケイト・ブッシュの音楽を表すアイコンとしても
長らく愛されてきた。
2015年にピーター・ライヒの
「ブック・オブ・ドリームス」が
再発売されたが、その表紙にはなんと
このビデオのラストシーンがデザインとして使われている。
さらに2010年からはケイト・ブッシュの
トリビュートバンドが活動。
そのバンド名が「クラウドバスティング」だ。
どうやら本人公認らしく、演奏もパフォーマンスも
単なるカバーをはるかに超えて、
「こんにちは地球」など、
彼女がライブでやったことのない楽曲も見事に再現。
21世紀にケイト・ブッシュの
新しい音楽世界を創り出している。
●こんにちは地球/クラウドバスティング
仮面の女と母の愛

ちょっと前に息子から新しいガンダムが
面白いと薦められたので、
「機動戦士ガンダム 水星の魔女」を見てみた。
去年の秋に1クールやっていて、
今年の春から2クール目をやっている。
現在は2クール目の途中だが、
かなりハマってこの3日ほどで21話をイッキ見。
ガンダム伝統のSF戦争ものに、
少女マンガ(学校・恋愛・仲間・LGBT)と
ビジネスドラマ(企業の宇宙経済圏・M&A・ベンチャー起業)を掛け合わせたつくりになっていて、
ちょっと「エヴァンゲリオン」を匂わせる要素も
入っており、とても見ごたえがある。
ガンダムは息子がチビの頃、「ガンダムSEED」など、
3作ほどいっしょに見ていただけで、
その歴史についてはよく知らないが、
今回のは新機軸らしく、主人公が女の子だ。
この主人公のスレッダというのが、
昔ながらの少女マンガのヒロインを彷彿とさせる、
純情で、ちょっとドジでヘタレな田舎娘というキャラで、
かわいい。
最初の方はガンダムで学園少女マンガをやるのか?
魔女だの魔法使いだのって、ハリーポッターの路線なのか?
というノリで始まったが、
さすがに世界観とキャラクター紹介を済ませた
1クール目の終盤から
ハードでシリアスなガンダムらしい展開になってきて、
オールドファンはほっとしただろう。
スレッダちゃんも話が進むにつれ、
単なる純情娘でなく、
過酷な運命を背負っていることがわかってきて、
ガンダムの主人公らしくなっていく。
「水星の魔女」というメインタイトルが示す通り、
ほかの登場人物も、圧倒的に女が多く、
キャラクターも女のほうが魅力的だ。
特にすごいのが、レディ・プロスペラという
スレッダちゃんの母親で、
新興のモビルスーツ企業の経営者。
しかもこの女性は、
ガンダムシリーズの名物の仮面キャラである。
彼女の復讐劇が、この物語の重要な軸になっているようだ。
シャア・アズラブル由来の仮面キャラは、
仮面をつけているというだけで、
相当ガンダムファンが期待し、
作る側のプレッシャーも大きいと思うが、
脚本のセリフも声優さんの演技も素晴らしく、
見事にそれに応えている。
序盤のビジネスシーンで、
「水星の地場に顔と腕を持っていかれた」と言って、
仮面(実際には目元まで隠すヘッドギア)と
義手を付けている理由を説明するが、
娘と会話する時は普通に外して素顔を晒している。
べつに顔面が崩れて醜くなっているとか、
外見上の異常は見られない。
なので、どうもこの仮面(ヘッドギア)を
装着すること自体になにか秘密があって、
ふつうに「働いているお母さん」
というわけではなさそうだ。
そのあたりは後半でどんでん返しをやるのだろう。
最後はやはり母と娘の対決になるのか?
女同士で戦うのを見るのはちょっと怖いので、
あまり凄惨なシーンにはしてほしくないけど。
この物語ではまた、社会格差や世代格差、
毒親など、親子間の問題なども
巧みに取り入れていているが、
究極のテーマは、
おそらく「母の愛」ということになるのだと思う。
それもかなり怖くて、狂気を秘めた愛。
従来のこうしたロボットもの・戦闘ものでは、
女性は、かわいかったり、お姫様だったり、
女神様だったり、色っぽい悪魔だったり、
やさしいお母さんだったり、
いわゆる「男が求める女性」として、
あまく描かれることが多かったが、
エヴァンゲリオン以来、だいぶ変わってきたようだ。
それにしても今さらながら、
最近のアニメは作劇術も画像表現も質が高い。
いろんな意味で楽しめ、
今の世の中の在り方・若い世代の思考タイプも学べる。
週末の懐メロ137:ハリケーン/ボブ・ディラン
現代アメリカ社会の欺瞞・腐敗・不条理をえぐる
吟遊詩人ボブ・ディランが1976年発表した
アルバム「欲望」のトップナンバー。
ギターに合わせてフィドル(バイオリン)がうねり、
ベースとドラムがロックなリズムを刻む中、
無実の罪を着せられた60年代の黒人ボクサー
ルービン“ハリケーン”カーターの物語を歌い綴る。
紛れもない、ディランの最高傑作だ。
惨劇を告げるオープニングから見事に構成された長編詩は、
8分以上にわたって聴く者の胸にひたすら
熱情溢れた言葉の直球を投げ続け、
“ハリケーン”の世界に引きずり込む。
殺人罪で投獄されたカーターは
獄中で自伝「第16ラウンド」を書いて出版し、
冤罪を世に訴えた。
その本を読んだディランは自らルービンに取材して、
この曲を書き上げたという。
その冤罪がいかにひどいものであったかは
曲を聴いての通りで、
人種差別がまだ正々堂々とまかり通っていた時代とはいえ、
こんなでっち上げがまかり通っていたことに驚くばかり。
けれども半世紀以上たった今も
実情は大して変わっていないのかもしれない。
そしてまた、昔々のアメリカの人種差別、
黒人差別の話だから僕たちには関係ないとは
言っていられないのかもしれない。
冤罪はどこの国でも起こり得る。
もちろん日本でも。
かの「袴田事件」が今年3月、
ようやく無罪決着になったのは、
事件から57年もたってからのこと。
失われた時間は二度と戻らない。
僕の子ども時代、日本の警察は
「刑事事件の検挙率世界一」
「世界で最も優秀な警察組織」と喧伝されていたが、
その検挙率を高く維持するために
相当数のでっち上げがあったのではないかと推察する。
権力者やその親族などが、
裏工作で罪を免れられるというのは、
昭和の時代では、広く認識されていたのでないか思う。
当然、その犠牲となった人も少なくないだろう。
人間の世界では表通りを見ているだけでは計り知れない
さまざまな事情・感情・思惑が絡み合って冤罪が生まれる。
人の一生を台無しにするほどの年月を費やした
「袴田事件」はそれでも無実が明らかにされた分、
まだマシと言えるのか?
泣き寝入りするしかなかった人たち、
最悪、闇に葬られた人たちは
いったいどれくらいいるのだろう?
どの国でも無実の罪を着せられるのは、
社会的に弱い立場にある人たちであることに変わりない。
「忖度」が大切にされるこの国では、令和の世になっても、
権力者やその親族などが罪を犯した場合、
たとえ裏からの命令や強制力が働かなくても、
周囲の「空気」によって冤罪を被ることもあり得そうだ。
ディランは痛烈に歌う。
「こんな国に暮らしていて恥ずかしい」と。
カーターは黒人であることに加え、
よくある話として、11歳の時に窃盗で捕まり、
少年院に入っていた履歴などが偏見として働き、
冤罪を生んだ。
ただ、幸運?(皮肉な言い方)なことに
社会の流れを変えた公民権運動と結びついて、
また、彼が名を知られたボクサーだったこともあって、
社会から注目されたのだ。
その後、支援者たちの尽力で、
彼に有利な証拠が隠蔽されていたこと、
彼に不利な証言をした証人が
偽証していたことなどがわかり、
1988年、20年間の獄中生活を経て、
ついにカーターの無実は認められ自由の身になった。
世界チャンピオンにもなれた男の夢は
とうの昔に潰えていたけれども、
1993年、世界ボクシング評議会(WBC)は、
彼に世界ミドル級名誉チャンピオンの称号と
チャンピオンベルトを授与した。
1999年、彼の半生とこの事件のドキュメントは
デンゼル・ワシントンが主演する
映画『ザ・ハリケーン』となった。
主題歌にこの曲が選ばれたことは言うまでもない。
その後、冤罪救済活動団体の責任者となった
“ハリケーン”は、最期まで冤罪と闘い続けた。
2014年、カナダ・トロントで死去。享年77歳。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。
お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。