- ホーム
- 電子書籍:おりべまこと劇場
- NEWS
- わたしの「わたしストーリー」
- 台本ライターとは?
- 実績:わたしの「しごとストーリー」
- 世界のEndingWatch
- 基本料金表
- ブログ「台本屋のネタ帳」
- 週末の懐メロ
- 2011年6月
- 2011年7月
- 2011年8月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年10月
- 2011年12月
- 2012年1月
- 2012年2月
- 2012年3月
- 2016年5月
- 2016年6月
- 2016年7月
- 2016年8月
- 2016年9月
- 2016年10月
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- 2017年6月
- 2017年7月
- 2017年8月
- 2017年9月
- 2017年10月
- 2017年11月
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- 2018年6月
- 2018年7月
- 2018年8月
- 2018年9月
- 2018年10月
- 2018年11月
- 2018年12月
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年8月
- 2019年9月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年4月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2020年11月
- 2020年12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- 2021年8月
- 2021年9月
- 2021年10月
- 2021年11月
- 2021年12月
- 新規ページ
- お問い合わせ
- 新規ページ
- --
- 新規ページ
なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?

「かえるくん、東京を救う」というのは村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品です。
主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説。
ですが、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまいます。
この話は阪神大震災をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのですが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザだったりして独特の作品世界が出来上がっています。
しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思いました。
このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないでしょうか。
でも、その振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気もします。
欧米人はカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の使いとか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い気がします。
ところが、日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、かわいい系・愛すべき系の系譜がちゃんと続いていますね。
僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないでしょうか。
お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。
そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのでしょう。
カエル君に対するよいイメージはそういうところからきている気がします。
ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」って呼ばれています。
茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろうね、きっと。
雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってないなぁ。ケロケロ。
家族ストーリーを書く仕事② 個の家族

「これから生まれてくる子孫が見られるように」
――今回の家族ストーリー(ファミリーヒストリー)を作った動機について、3世代の真ん中の息子さん(団塊ジュニア世代)は作品の最後でこんなメッセージを残しています。
彼の中にはあるべき家族の姿があった。しかし現実にはそれが叶わなかった。だからやっと安定し、幸福と言える現在の形を映像に残すことを思い立った――僕にはそう取れます。
世間一般の基準に照らし合わせれば、彼は家庭に恵まれなかった人に属するでしょう。かつて日本でよく見られた大家族、そして戦後の主流となった夫婦と子供数人の核家族。彼の中にはそうした家族像への憧れがあったのだと思います。
けれども大家族どころか、核家族さえもはや過去のものになっているのでないか。今回の映像を見ているとそう思えてきます。
団塊の世代の親、その子、そして孫(ほぼ成人)。
彼らは家族であり、互いに支え合い、励まし合いながら生きている。
けれど、その前提はあくまで個人。それぞれ個別の歴史と文化を背負い、自分の信じる幸福を追求する人間として生きている。
むかしのように、まず家があり、そこに血のつながりのある人間として生まれ、育つから家族になるのではなく、ひとりひとりの個人が「僕たちは家族だよ」という約束のもとに集まって愛情と信頼を持っていっしょに暮らす。あるいは、離れていても「家族だよ」と呼び合い、同様に愛情と信頼を寄せ合う。だから家族になる。
これからの家族は、核家族からさらに小さな単位に進化した「ミニマム家族」――「個の家族」とでもいえばいいのでしょうか。
比喩を用いれば、ひとりひとりがパソコンやスマホなどのデバイスであり、必要がある時、○○家にログインし、ネットワークし、そこで父・母・息子・娘などの役割を担って、相手の求めることに応じる。それによってそれぞれが幸福を感じる。そうした「さま」を家族と呼称する――なかなかスムーズに表現できませんが、これからはそういう家族の時代になるのではないでしょうか。
なぜなら、そのほうが現代のような個人主義の世の中で生きていくのに何かと便利で快適だからです。人間は自身の利便性・快適性のためになら、いろいろなものを引き換えにできます。だから進化してこられたのです。
引き換えに失ったものの中にももちろん価値があるし、往々にして失ってみて初めてその価値に気づくケースがあります。むかしの大家族しかり。核家族しかり。こうしてこれらの家族の形態は、今後、一種の文化遺産になっていくのでしょう。
好きか嫌いかはともかく、そういう時代に入っていて、僕たちはもう後戻りできなくなっているのだと思います。
将来生まれてくる子孫のために、自分の家族の記憶を本なり映像なりの形でまとめて遺す―― もしかしたらそういう人がこれから結構増えるのかもしれません。
2016・6・27 Mon
家族ストーリーを書く仕事① 親子3世代の物語

親子3世代の物語がやっと完成一歩手前まで来ました。
昨年6月、ある家族のヒストリー映像を作るというお仕事を引き受けて、台本を担当。
足掛け1年掛かりでほぼ完成し、残るはクライアントさんに確認を頂いて、最後にナレーションを吹き込むのみ、という段階までこぎつけたのです。
今回のこの仕事は、ディレクターが取材をし、僕はネット経由で送られてくるその音源や映像を見て物語の構成をしていきました。そのディレクターとも最初に1回お会いしただけでご信頼を頂いたので、そのあとはほとんどメールのやり取りのみで進行しました。インターネットがあると、本当に家で何でもできてしまいます。
ですから時間がかかった割には、そんなに「たいへん感」はありませんでした。
取材対象の人たちともリアルでお会いしたことはなく、インタビューの音声――話の内容はもとより、しゃべり方のくせ、間も含めて――からそれぞれのキャラクターと言葉の背景にある気持ちを想像しながらストーリーを組み立てていくのは、なかなかスリリングで面白い体験でした(最初の下取材の頃はディレクターがまだ映像を撮っていなかったので、レコーダーの音源だけを頼りにやっていました)。
取材対象と直接会わない、会えないという制限は、今までネガティブに捉えていたのですが、現場(彼らの生活空間や仕事空間)の空気がわからない分、余分な情報に戸惑ったり、感情移入のし過ぎに悩まされたりすることがありません。
適度な距離を置いてその人たちを見られるので、かえってインタビューの中では語られていない範囲まで自由に発想を膨らませられ、こうしたドキュメンタリーのストーリーづくりという面では良い効果もあるんだな、と感じました。
後半(今年になってから)、全体のテーマが固まり、ストーリーの流れが固まってくると、今度は台本に基づいて取材がされるようになりました。
戦後の昭和~平成の時代の流れを、団塊の世代の親、その息子、そして孫(ほぼ成人)という一つの家族を通して見ていくと、よく目にする、当時の出来事や風俗の記録映像も、魂が定着くした記憶映像に見えてきます。
これにきちんとした、情感豊かなナレーターの声が入るのがとても楽しみです。
2016・6・26 Sun
ゴマスリずんだ餅と正直ファンタじいさん

おもちペタペタ伊達男
今週日曜(19日)の大河ドラマ「真田丸」で話題をさらったのは、長谷川朝晴演じる伊達政宗の餅つきパフォーマンスのシーン。「独眼竜」で戦国武将の中でも人気の高い伊達政宗ですが、一方で「伊達男」の語源にもなったように、パフォーマーというか、歌舞伎者というか、芝居っけも方もたっぷりの人だったようです。
だから、餅つきくらいやってもおかしくないのでしょうが、権力者・秀吉に対してあからさまにこびへつらい、ペッタンコとついた餅にスリゴマを・・・じゃなかった、つぶした豆をのっけて「ずんだ餅でございます」と差し出す太鼓持ち野郎の姿に、独眼竜のカッコいいイメージもこっぱみじんでした。
僕としては「歴人めし」の続編のネタ、一丁いただき、と思ってニヤニヤ笑って見ていましたが、ファンの人は複雑な心境だったのではないのでしょうか。(ネット上では「斬新な伊達政宗像」と、好意的な意見が多かったようですが)。
しかし、この後、信繁(幸村=堺雅人)と二人で話すシーンがあり、じつは政宗、今はゴマスリ太鼓持ち野郎を演じているが、いずれ時が来れば秀吉なんぞ、つぶしてずんだ餅にしてやる・・・と、野心満々であることを主人公の前で吐露するのです。
で、これがクライマックスの関ヶ原の伏線の一つとなっていくわけですね。
裏切りのドラマ
この「真田丸」は見ていると、「裏切り」が一つのテーマとなっています。
出てくるどの武将も、とにかくセコいのなんのttらありゃしない。立派なサムライなんて一人もいません。いろいろな仮面をかぶってお芝居しまくり、だましだまされ、裏切り裏切られ・・・の連続なのです。
そりゃそうでしょう。乱世の中、まっすぐ正直なことばかりやっていては、とても生き延びられません。
この伊達政宗のシーンの前に、北条氏政の最後が描かれていましたが、氏政がまっすぐな武将であったがために滅び、ゴマスリ政宗は生き延びて逆転のチャンスを掴もうとするのは、ドラマとして絶妙なコントラストになっていました。
僕たちも生きるためには、多かれ少なかれ、このゴマスリずんだ餅に近いことを年中やっているのではないでしょうか。身過ぎ世過ぎというやつですね。
けれどもご注意。
人間の心とからだって、意外と正直にできています。ゴマスリずんだ餅をやり過ぎていると、いずれまとめてお返しがやってくるも知れません。
人間みんな、じつは正直者
どうしてそんなことを考えたかと言うと、介護士の人と、お仕事でお世話しているおじいさんのことについて話したからです。
そのおじいさんはいろんな妄想に取りつかれて、ファンタジーの世界へ行っちゃっているようなのですが、それは自分にウソをつき続けて生きてきたからではないか、と思うのです。
これは別に倫理的にどうこうという話ではありません。
ごく単純に、自分にウソをつくとそのたびにストレスが蓄積していきます。
それが生活習慣になってしまうと、自分にウソをつくのが当たり前になるので、ストレスが溜まるのに気づかない。そういう体質になってしまうので、全然平気でいられる。
けれども潜在意識は知っているのです。
「これはおかしい。これは違う。これはわたしではな~い」
そうした潜在意識の声を、これまた無視し続けると、齢を取ってから自分で自分を裏切り続けてきたツケが一挙に出て来て、思いっきり自分の願いや欲望に正直になるのではないでしょうか。
だから脳がファンタジーの世界へ飛翔してしまう。それまでウソで歪めてきた自分の本体を取り戻すかのように。
つまり人生は最後のほうまで行くとちゃんと平均化されるというか、全体で帳尻が合うようにできているのではないかな。
自分を大事にするということ
というのは単なる僕の妄想・戯言かも知れないけど、自分に対する我慢とか裏切りとかストレスとかは、心や体にひどいダメージを与えたり、人生にかなりの影響を及ぼすのではないだろうかと思うのです。
みなさん、人生は一度きり。身過ぎ世過ぎばっかりやってると、それだけであっという間に一生終わっちゃいます。何が自分にとっての幸せなのか?心の内からの声をよく聴いて、本当の意味で自分を大事にしましょう。
介護士さんのお話を聞くといろんなことを考えさせられるので、また書きますね。
2016/6/23 Thu
死者との対話:父の昭和物語

すぐれた小説は時代を超えて読み継がれる価値がある。特に現代社会を形作った18世紀から20世紀前半にかけての時代、ヨーロッパ社会で生まれた文学には人間や社会について考えさせられる素材にあふれています。
その読書を「死者との対話」と呼んだ人がいます。うまい言い方をするものだと思いました。
僕たちは家で、街で、図書館で、本さえあれば簡単にゲーテやトルストイやドストエフスキーやブロンテなどと向かい合って話ができます。別にスピリチュアルなものに関心がなくても、書き残したものがあれば、私たちは死者と対話ができるのです。
もちろん、それはごく限られた文学者や学者との間で可能なことで、そうでない一般大衆には縁のないことでしょう。これまではそうでした。しかし、これからの時代はそれも可能なことではないかと思います。ただし、不特定多数の人でなく、ある家族・ある仲間との間でなら、ということですが。
僕は父の人生を書いてみました。
父は2008年の12月に亡くなりました。家族や親しい者の死も1年ほどたつと悲しいだの寂しいだの、という気持ちは薄れ、彼らは自分の人生においてどんな存在だったのだろう?どんなメッセージを遺していったのだろう?といったことを考えます。
父のことを書いてみようと思い立ったのは、それだけがきっかけではありませんでした。
死後、間もない時に、社会保険事務所で遺族年金の手続きをする際に父の履歴書を書いて提出しました。その時に感じたのは、血を分けた家族のことでも知らないことがたくさんあるな、ということでした。
じつはそれは当り前のことなのだが、それまではっきりとは気が付いていませんでした。なんとなく父のことも母のこともよく知っていると思いすごしていたのです。
実際は私が知っているのは、私の父親としての部分、母親としての部分だけであり、両親が男としてどうだったか、女としてどうだったか、ひとりの人間としてどうだったのか、といったことなど、ほとんど知りませんでした。数十年も親子をやっていて、知るきっかけなどなかったのです。
父の仕事ひとつ取ってもそうでした。僕の知っている父の仕事は瓦の葺換え職人だが、それは30歳で独立してからのことで、その前――20代のときは工場に勤めたり、建築会社に勤めたりしていたのです。それらは亡くなってから初めて聞いた話です。
そうして知った事実を順番に並べて履歴書を作ったのですが、その時には強い違和感というか、抵抗感のようなものを感じました。それは父というひとりの人間の人生の軌跡が、こんな紙切れ一枚の中に納まってしまうということに対しての、寂しさというか、怒りというか、何とも納得できない気持ちでした。
父は不特定多数の人たちに興味を持ってもらえるような、波乱万丈な、生きる迫力に満ち溢れた人生を歩んだわけはありませんい。むしろそれらとは正反対の、よくありがちな、ごく平凡な庶民の人生を送ったのだと思います。
けれどもそうした平凡な人生の中にもそれなりのドラマがあります。そして、そのドラマには、その時代の社会環境の影響を受けた部分が少なくありません。たとえば父の場合は、昭和3年(1928年)に生まれ、平成元年(1989年)に仕事を辞めて隠居していました。その人生は昭和の歴史とほぼ重なっています。
ちなみにこの昭和3年という年を調べてみると、アメリカでミッキーマウスの生まれた(ウォルト・ディズニーの映画が初めて上映された)年です。
父は周囲の人たちからは実直でまじめな仕事人間と見られていましたが、マンガや映画が好きで、「のらくろ」だの「冒険ダン吉」だのの話をよく聞かせてくれました。その時にそんなことも思い出したのです。
ひとりの人間の人生――この場合は父の人生を昭和という時代にダブらせて考えていくと、昭和の出来事を書き連ねた年表のようなものとは、ひと味違った、その時代の人間の意識の流れ、社会のうねりの様子みたいなものが見えてきて面白いのではないか・・・。そう考えて、僕は父に関するいくつかの個人的なエピソードと、昭和の歴史の断片を併せて書き、家族や親しい人たちが父のことを思い起こし、対話できるための一遍の物語を作ってみようと思い立ちました。
本当はその物語は父が亡くなる前に書くべきだったのではないかと、少し後悔の念が残っています。
生前にも話を聞いて本を書いてみようかなと、ちらりと思ったことはあるのですが、とうとう父自身に自分の人生を振り返って……といった話を聞く機会はつくれませんでした。たとえ親子の間柄でも、そうした機会を持つことは難しいのです。思い立ったら本気になって直談判しないと、そして双方互いに納得できないと永遠につくることはできません。あるいは、これもまた難しいけど、本人がその気になって自分で書くか・・・。それだけその人固有の人生は貴重なものであり、それを正確に、満足できるように表現することは至難の業なのだと思います。
実際に始めてから困ったのは、父の若い頃のことを詳しく知る人など、周囲にほとんどいないということ。また、私自身もそこまで綿密に調査・取材ができるほど、時間や労力をかけるわけにもいきませんでした。
だから母から聞いた話を中心に、叔父・叔母の話を少し加える程度にとどめ、その他、本やインターネットでその頃の時代背景などを調べながら文章を組み立てる材料を集めました。そして自分の記憶――心に残っている言葉・出来事・印象と重ね合わせて100枚程度の原稿を作ってみたのです。
自分で言うのもナンですが、情報不足は否めないものの、悪くない出来になっていて気に入っています。これがあるともうこの世にいない父と少しは対話できる気がするのです。自分の気持ちを落ち着かせ、互いの生の交流を確かめ、父が果たした役割、自分にとっての存在の意味を見出すためにも、こうした家族や親しい者の物語をつくることはとても有効なのではないかと思います。
高齢化が進む最近は「エンディングノート」というものがよく話題に上っています。
「その日」が来た時、家族など周囲の者がどうすればいいか困らないように、いわゆる社会的な事務手続き、お金や相続のことなどを書き残すのが、今のところ、エンディングノートの最もポピュラーな使い方になっているようだ。
もちろん、それはそれで、逝く者にとっても、後に残る者にとっても大事なことです。しかし、そうすると結局、その人の人生は、いくらお金を遺したかとか、不動産やら建物を遺したのか、とか、そんな話ばかりで終わってしまう恐れもあります。その人の人生そのものが経済的なこと、物質的なものだけで多くの人に価値判断されてしまうような気がするのです。
けれども本当に大事なのは、その人の人生にどんな意味や価値があったのか、を家族や友人・知人たちが共有することが出来る、ということではないでしょうか。
そして、もしその人の生前にそうしたストーリーを書くことができれば、その人が人生の最期の季節に、自分自身を取り戻せる、あるいは、取り戻すきっかけになり得る、ということではないでしょうか。
赤影メガネとセルフブランディング

♪赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光る涼しい目 仮面の忍者だ
赤影だ~
というのは、テレビの「仮面の忍者 赤影」の主題歌でしたが、涼しい目かどうかはともかく、僕のメガネは10数年前から「赤影メガネ」です。これにはちょっとした物語(というほどのものではないけど)があります。
当時、小1だか2年の息子を連れてメガネを買いに行きました。
それまでは確か茶色の細いフレームの丸いメガネだったのですが、今回は変えようかなぁ、どうしようかなぁ・・・とあれこれ見ていると、息子が赤フレームを見つけて「赤影!」と言って持ってきたのです。
「こんなの似合うわけないじゃん」と思いましたが、せっかく選んでくれたのだから・・・と、かけてみたら似合った。子供の洞察力おそるべし。てか、単に赤影が好きだっただけ?
とにかく、それ以来、赤いフレームのメガネが、いつの間にか自分のアイキャッチになっていました。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいもの。
独立・起業・フリーランス化ばやりということもあり、セルフブランディングがよく話題になりますが、自分をどう見せるかというのはとても難しい。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいのです。
とはいえ、自分で気に入らないものを身に着けてもやっぱり駄目。できたら安心して相談できる家族とか、親しい人の意見をしっかり聞いて(信頼感・安心感を持てない人、あんまり好きでない人の意見は素直に聞けない)、従来の考え方にとらわれない自分像を探していきましょう。
ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?
ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。
BACK in the NEW YORK CITY。
僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。
特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。
そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。
衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。
そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。
1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。
向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。
なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。
どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・
「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。
おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。
別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。
あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。
というのが、今から約20年前のこと。
その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?
表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?
件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。
ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。
そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。
2016年6月16日
インターネットがつくるフォークロア

インターネットの出現は社会を変えた――ということは聞き飽きるほど、あちこちで言われています。けれどもインターネットが本格的に普及したのは、せいぜいここ10年くらいの話。全世代、全世界を見渡せば、まだ高齢者の中には使ったことがないという人も多いし、国や地域によって普及率の格差も大きい。だから、その変化の真価を国レベル・世界レベルで、僕たちが実感するのはまだこれからだと思います。
それは一般によくいわれる、情報収集がスピーディーになったとか、通信販売が便利になったとか、というカテゴリーの話とは次元が違うものです。もっと人間形成の根本的な部分に関わることであり、ホモサピエンスの文化の変革にまでつながること。それは新しい民間伝承――フォークロアの誕生です。
“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承
最初はどこでどのように聞いたのか覚えてないですが、僕たちは自分でも驚くほど、昔話・伝承をよく知っています。成長の過程のどこかで桃太郎や浦島太郎や因幡の白ウサギと出会い、彼らを古い友だちのように思っています。
家庭でそれらの話を大人に読んでもらったこともあれば、幼稚園・保育園・小学校で体験したり、最近ならメディアでお目にかかることも多い。それはまるで遺伝子に組み込まれているかのように、あまりに自然に身体の中に溶け込んでいるのです。
調べて確認したわけではないが、こうした感覚は日本に限らず、韓国でも中国でもアメリカでもヨーロッパでも、その地域に住んでいる人なら誰でも持ち得るのではないでしょうか。おそらく同じような現象があると思います。それぞれどんな話がスタンダードとなっているのかは分かりませんが、その国・その地域・その民族の間で“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承の類が一定量あるのです。
それらは長い時間を生きながらえるタフな生命エネルギーを持っています。それだけのエネルギーを湛えた伝承は、共通の文化の地層、つまり一種のデータベースとして、万人の脳の奥底に存在しています。その文化の地層の上に、その他すべての情報・知識が積み重なっている――僕はそんなイメージを持っています。
世界共通の、新しいカテゴリーの伝承
そして、昔からあるそれとは別に、これから世界共通の、新しいカテゴリーの伝承が生まれてくる。その新しい伝承は人々の間で共通の文化の地層として急速に育っていくのでないか。そうした伝承を拡散し、未来へ伝える役目を担っているのがインターネット、というわけです。
ところで新しい伝承とは何でしょう? その主要なものは20世紀に生まれ、花開いた大衆文化――ポップカルチャーではないでしょうか。具体的に挙げていけば、映画、演劇、小説、マンガ、音楽(ジャズ、ポップス、ロック)の類です。
21世紀になる頃から、こうしたポップカルチャーのリバイバルが盛んに行われるようになっていました。
人々になじみのあるストーリー、キャラクター。
ノスタルジーを刺激するリバイバル・コンテンツ。
こうしたものが流行るのは、情報発信する側が、商品価値の高い、新しいものを開発できないためだと思っていました。
そこで各種関連企業が物置に入っていたアンティーク商品を引っ張り出してきて、売上を確保しようとした――そんな事情があったのでしょう。実際、最初のうちはそうだったはずです。
だから僕は結構冷めた目でそうした現象を見ていました。そこには半ば絶望感も混じっていたと思います。前の世代を超える、真に新しい、刺激的なもの・感動的なものは、この先はもう現れないのかも知れない。出尽くしてしまったのかも知れない、と……。
しかし時間が経ち、リバイバル現象が恒常化し、それらの画像や物語が、各種のサイトやYouTubeの動画コンテンツとして、ネット上にあふれるようになってくると考え方は変わってきました。
それらのストーリー、キャラクターは、もはや単なるレトロやリバイバルでなく、世界中の人たちの共有財産となっています。いわば全世界共通の伝承なのです。
僕たちは欧米やアジアやアフリカの人たちと「ビートルズ」について、「手塚治虫」について、「ガンダム」について、「スターウォーズ」について語り合えるし、また、それらを共通言語にして、子や孫の世代とも同様に語り合えます。
そこにボーダーはないし、ジェネレーションギャップも存在しません。純粋にポップカルチャーを媒介にしてつながり合う、数限りない関係が生まれるのです。
また、これらの伝承のオリジナルの発信者――ミュージシャン、映画監督、漫画家、小説家などによって、あるいは彼ら・彼女らをリスペクトするクリエイターたちによって自由なアレンジが施され、驚くほど新鮮なコンテンツに生まれ変わる場合もあります。
インターネットの本当の役割
オリジナル曲をつくった、盛りを過ぎたアーティストたちが、子や孫たち世代の少年・少女と再び眩いステージに立ち、自分の資産である作品を披露。それをYouTubeなどを介して広めている様子なども頻繁に見かけるようになりました。
それが良いことなのか、悪いことなのか、評価はさておき、そうした状況がインタ―ネットによって現れています。これから10年たち、20年たち、コンテンツがさらに充実し、インターネット人口が現在よりさらに膨れ上がれば、どうなるでしょうか?
おそらくその現象は空気のようなものとして世の中に存在するようになり、僕たちは新たな世界的伝承として、人類共通の文化遺産として、完成された古典として見なすようになるでしょう。人々は分かりやすく、楽しませてくれるものが大好きだからです。
そして、まるで「桃太郎」のお話を聞くように、まっさらな状態で、これらの伝承を受け取った子供たちが、そこからまた新しい、次の時代の物語を生みだしていきます。
この先、そうした現象が必ず起こると思う。インターネットという新参者のメディアはその段階になって、さらに大きな役割を担うのでしょう。それは文化の貯蔵庫としての価値であり、さらに広げて言えば、人類の文化の変革につながる価値になります。
2016年6月13日
地方自治体のホームページって割と面白い

ここのところ、雑誌の連載で地方のことを書いています。
書くときはまずベーシックな情報(最初のリード文として使うこともあるので)をインターネットで調べます。
これはウィキペディアなどの第3者情報よりも、各県の公式ホームページの方が断然面白い。自分たちの県をどう見せ、何をアピールしたいかがよくわかるからです。
なんでも市場価値が問われる時代。「お役所仕事云々・・・」と言われることが多い自治体ですが、いろいろ努力して、ホームページも工夫しています。
最近やった宮崎県のキャッチコピーは「日本のひなた」。
日照時間の多さ、そのため農産物がよく獲れるということのアピール。
そしてもちろん、人や土地のやさしさ、あったかさ、ポカポカ感を訴えています。
いろいろな人たちがお日さまスマイルのフリスビーを飛ばして、次々と受け渡していくプロモーションビデオは、単純だけど、なかなか楽しかった。
それから「ひなた度データ」というのがあって、全国比率のいろいろなデータが出ています。面白いのが、「餃子消費量3位」とか、「中学生の早寝早起き率 第3位」とか、「宿題実行率 第4位」とか、「保護者の学校行事参加率 第2位」とか・・・
「なんでこれがひなた度なんじゃい!」とツッコミを入れたくなるのもいっぱい。だけど好きです、こういうの。
取材するにしても、いきなり用件をぶつけるより、「ホームページ面白いですね~」と切り出したほうが、ちょっとはお役所臭さが緩和される気がします。
「あなたのひなた度は?」というテストもあって、やってみたら100パーセントでした。じつはまだ一度も行ったことないけれど、宮崎県を応援したくなるな。ポカポカ。
2016年6月12日
タイムマシンにおねがい

きのう6月10日は「時の記念日」でした。それに気がついたら頭の中で突然、サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」が鳴り響いてきたので、YouTubeを見てみたら、1974年から2006年まで、30年以上にわたるいろいろなバージョンが上がっていました。本当にインターネットの世界でタイムマシン化しています。
これだけ昔の映像・音源が見放題・聞き放題になるなんて10年前は考えられませんでした。こういう状況に触れると、改めてインターネットのパワーを感じると同時に、この時代になるまで生きててよかった~と、しみじみします。
そしてまた、ネットの中でならおっさん・おばさんでもずっと青少年でいられる、ということを感じます。60~70年代のロックについて滔々と自分の思い入れを語っている人がいっぱいいますが、これはどう考えても50代・60代の人ですからね。
でも、彼ら・彼女らの頭の中はロックに夢中になっていた若いころのまんま。脳内年齢は10代・20代。インターネットに没頭することは、まさしくタイムマシンンに乗っているようなものです。
この「タイムマシンにおねがい」が入っているサディスティック・ミカ・バンドの「黒船」というアルバムは、1974年リリースで、いまだに日本のロックの最高峰に位置するアルバムです。若き加藤和彦が作った、世界に誇る傑作と言ってもいいのではないでしょうか。
中でもこの曲は音も歌詞もゴキゲンです。いろいろ見た(聴いた)中でいちばんよかったのは、最新(かな?)の2006年・木村カエラ・ヴォーカルのバージョンです。おっさんロッカーたちをバックに「ティラノサウルスおさんぽ アハハハ-ン」とやってくれて、くらくらっときました。
やたらと「オリジナルでなきゃ。あのヴォーカルとあのギターでなきゃ」とこだわる人がいますが、僕はそうは思わない。みんなに愛される歌、愛されるコンテンツ、愛される文化には、ちゃんと後継ぎがいて、表現技術はもちろんですが、それだけでなく、その歌・文化の持ち味を深く理解し、見事に自分のものとして再現します。中には「オリジナルよりいいじゃん!」と思えるものも少なくありません。(この木村カエラがよい例)。
この歌を歌いたい、自分で表現したい!――若い世代にそれだけ強烈に思わせる、魅力あるコンテンツ・文化は生き残り、クラシックとして未来に継承されていくのだと思います。
もう一つおまけに木村カエラのバックでは、晩年の加藤和彦さんが本当に楽しそうに演奏をしていました。こんなに楽しそうだったのに、どうして自殺してしまったのだろう・・・と、ちょっと哀しくもなったなぁ。
2016年6月11日
「歴人めし」おかわり情報

9日間にわたって放送してきた「歴人めし」は、昨日の「信長巻きの巻」をもっていったん終了。しかし、ご安心ください。7月は夜の時間帯に再放送があります。ぜひ見てくださいね。というか、You Tubeでソッコー見られるみたいですが。
https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php?series_cd=12041
この仕事では歴人たちがいかに食い物に執念を燃やしていたかがわかりました。 もちろん、記録に残っているのはほんの少し。
源内さんのように、自分がいかにうなぎが好きか、うなぎにこだわっているか、しつこく書いている人も例外としていますが、他の人たちは自分は天下国家のことをいつも考えていて、今日のめしのことなんかどうでもいい。カスミを食ってでの生きている・・・なんて言い出しそうな勢いです。
しかし、そんなわけはない。偉人と言えども、飲み食いと無関係ではいられません。 ただ、それを口に出して言えるのは、平和な世の中あってこそなのでしょう。だから日本の食文化は江戸時代に発展し、今ある日本食が完成されたのです。
そんなわけで、「おかわり」があるかもしれないよ、というお話を頂いているので、なんとなく続きを考えています。
駿河の国(静岡)は食材豊富だし、来年の大河の井伊直虎がらみで何かできないかとか、 今回揚げ物がなかったから、何かできないかとか(信長に捧ぐ干し柿入りドーナツとかね)、
柳原先生の得意な江戸料理を活かせる江戸の文人とか、明治の文人の話だとか、
登場させ損ねてしまった豊臣秀吉、上杉謙信、伊達政宗、浅井三姉妹、新選組などの好物とか・・・
食について面白い逸話がありそうな人たちはいっぱいいるのですが、柳原先生の納得する人物、食材、メニュー、ストーリーがそろって、初めて台本にできます。(じつは今回もプロット段階でアウトテイク多数)
すぐにとはいきませんが、ぜひおかわりにトライしますよ。
それまでおなかをすかせて待っててくださいね。ぐ~~。
2016年6月7日
歴人めし♯9:スイーツ大好き織田信長の信長巻き

信長が甘いもの好きというのは、僕は今回のリサーチで初めて知りました。お砂糖を贈答したり、されたりして外交に利用していたこともあり、あちこちの和菓子屋さんが「信長ゆかりの銘菓」を開発して売り出しているようです。ストーリーをくっつけると、同じおまんじゅうやあんころもちでも何だか特別なもの、他とは違うまんじゅうやあんころもちに思えてくるから不思議なものです。
今回、ゆかりの食材として採用したのは「干し柿」と「麦こがし(ふりもみこがし)」。柿は、武家伝統の本膳料理(会席料理のさらに豪華版!)の定番デザートでもあり、記録をめくっていると必ず出てきます。
現代のようなスイーツパラダイスの時代と違って、昔の人は甘いものなどそう簡単に口にできませんでした。お砂糖なんて食品というよりは、宝石や黄金に近い超ぜいたく品だったようです。だから信長に限らず、果物に目のない人は大勢いたのでしょう。
中でもは干し柿にすれば保存がきくし、渋柿もスイートに変身したりするので重宝されたのだと思います。
「信長巻き」というのは柳原尚之先生のオリジナル。干し柿に白ワインを染み込ませるのと、大徳寺納豆という、濃厚でしょっぱい焼き味噌みたいな大豆食品をいっしょに巻き込むのがミソ。
信長は塩辛い味も好きで、料理人が京風の上品な薄味料理を出したら「こんな水臭いものが食えるか!」と怒ったという逸話も。はまった人なら知っている、甘い味としょっぱい味の無限ループ。交互に食べるともうどうにも止まらない。信長もとりつかれていたのだろうか・・・。
ちなみに最近の映画やドラマの中の信長と言えば、かっこよくマントを翻して南蛮渡来の洋装を着こなして登場したり、お城の中のインテリアをヨーロッパの宮殿風にしたり、といった演出が目につきます。
スイーツ好きとともに、洋風好き・西洋かぶれも、今やすっかり信長像の定番になっていますが、じつはこうして西洋文化を積極的に採り入れたのも、もともとはカステラだの、金平糖だの、ボーロだの、ポルトガルやスペインの宣教師たちが持ち込んできた、砂糖をたっぷり使った甘いお菓子が目当てだったのです。(と、断言してしまう)
「文化」なんていうと何やら高尚っぽいですが、要は生活習慣の集合体をそう呼ぶまでのこと。その中心にあるのは生活の基本である衣食住です。
中でも「食」の威力はすさまじく、これに人間はめっぽう弱い。おいしいものの誘惑からは誰も逃れられない。そしてできることなら「豊かな食卓のある人生」を生きたいと願う。この「豊かな食卓」をどう捉えるかが、その人の価値観・生き方につながるのです。
魔王と呼ばれながら、天下統一の一歩手前で倒れた信長も、突き詰めればその自分ならではの豊かさを目指していたのではないかと思うのです。
2016年6月6日
歴人めし♯8 山内一豊の生食禁止令から生まれた?「カツオのたたき」

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だったころ、琵琶湖のほとりに金目教という怪しい宗教が流行っていた・・・」というナレーションで始まるのは「仮面の忍者・赤影」。子供の頃、夢中になってテレビにかじりついていました。
時代劇(忍者もの)とSF活劇と怪獣物をごちゃ混ぜにして、なおかつチープな特撮のインチキスパイスをふりかけた独特のテイストは、後にも先にもこの番組だけ。僕の中ではもはや孤高の存在です。
いきなり話が脱線していますが、赤影オープニングのナレーションで語られた「琵琶湖のほとり」とは滋賀県長浜あたりのことだったのだ、と気づいたのは、ちょうど10年前の今頃、イベントの仕事でその長浜に滞在していた時です。
このときのイベント=期間限定のラジオ番組制作は、大河ドラマ「功名が辻」関連のもの。4月~6月まで断続的に数日ずつ訪れ、街中や郊外で番組用の取材をやっていました。春でもちょっと寒いことを我慢すれば、賑わいがあり、かつまた、自然や文化財にも恵まれている、とても暮らしやすそうな良いところです。
この長浜を開いたのは豊臣秀吉。そして秀吉の後を継いで城主になったのが山内一豊。「功名が辻」は、その一豊(上川隆也)と妻・千代(仲間由紀恵)の物語。そして本日の歴人めし♯9は、この一豊ゆかりの「カツオのたたき」でした。
ところが一豊、城主にまでしてもらったのに秀吉の死後は、豊臣危うしと読んだのか、関が原では徳川方に寝返ってしまいます。つまり、うまいこと勝ち組にすべり込んだわけですね。
これで一件落着、となるのが、一豊の描いたシナリオでした。
なぜならこのとき、彼はもう50歳。人生50年と言われた時代ですから、その年齢から本格的な天下取りに向かった家康なんかは例外中の例外。そんな非凡な才能と強靭な精神を持ち合わせていない、言ってみればラッキーで何とかやってきた凡人・一豊は、もう疲れたし、このあたりで自分の武士人生も「あがり」としたかったのでしょう。
できたら、ごほうびとして年金代わりに小さな領地でももらって、千代とのんびり老後を過ごしたかったのだと思います。あるいは武士なんかやめてしまって、お百姓でもやりながら余生を・・・とひそかに考えていた可能性もあります。
ところが、ここでまた人生逆転。家康からとんでもないプレゼントが。
「土佐一国をおまえに任せる」と言い渡されたのです。
一国の領主にしてやる、と言われたのだから、めでたく大出世。一豊、飛び上がって喜んだ・・・というのが定説になっていますが、僕はまったくそうは思いません。
なんせ土佐は前・領主の長曾我部氏のごっつい残党がぞろぞろいて、新しくやってくる領主をけんか腰で待ち構えている。徳川陣営の他の武将も「あそこに行くのだけは嫌だ」と言っていたところです。
現代に置き換えてみると、後期高齢者あたりの年齢になった一豊が、縁もゆかりもない外国――それも南米とかのタフな土地へ派遣されるのようなもの。いくらそこの支店長のポストをくれてやる、と言われたって全然うれしくなんかなかったでしょう。
けれども天下を収めた家康の命令は絶対です。断れるはずがありません。
そしてまた、うまく治められなければ「能無し」というレッテルを貼られ、お家とりつぶしになってしまいます。
これはすごいプレッシャーだったでしょう。「勝ち組になろう」なんて魂胆を起こすんじゃなかった、と後悔したに違いありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
恐怖にかられてしまった人間は、より以上の恐怖となる蛮行、残虐行為を行います。
一豊は15代先の容堂の世代――つまり、250年後の坂本龍馬や武市半平太の時代まで続く、武士階級をさらに山内家の上士、長曾我部氏の下士に分けるという独特の差別システムまで発想します。
そうして土佐にきてわずか5年で病に倒れ、亡くなってしまった一豊。寿命だったのかもしれませんが、僕には土佐統治によるストレスで命を縮めたとしか思えないのです。
「カツオのたたき」は、食中毒になる危険を慮った一豊が「カツオ生食禁止令」を出したが、土佐の人々はなんとかおいしくカツオを食べたいと、表面だけ火であぶり、「これは生食じゃのうて焼き魚だぜよ」と抗弁したところから生まれた料理――という話が流布しています。
しかし、そんな禁止令が記録として残っているわけではありません。やはりこれはどこからか生えてきた伝説なのでしょう。
けれども僕はこの「カツオのたたき発祥物語」が好きです。それも一豊を“民の健康を気遣う良いお殿様”として解釈するお話でなく、「精神的プレッシャーで恐怖と幻想にとりつかれ、カツオの生食が、おそるべき野蛮人たちの悪食に見えてしまった男の物語」として解釈してストーリーにしました。
随分と長くなってしまいましたが、ここまで書いてきたバックストーリーのニュアンスをイラストの方が、短いナレーションとト書きからじつにうまく掬い取ってくれて、なんとも情けない一豊が画面で活躍することになったのです。
一豊ファンの人には申し訳ないけど、カツオのたたきに負けず劣らず、実にいい味出している。マイ・フェイバリットです。
2016年6月3日
「歴人めし」徳川家康提唱、日本人の基本食

歴人めし第7回は「徳川家康―八丁味噌の冷汁と麦飯」。
「これが日本人の正しい食事なのじゃ」と家康が言ったかどうかは知りませんが、米・麦・味噌が長寿と健康の基本の3大食材と言えば、多くの日本人は納得するのではないでしょうか。エネルギー、たんぱく質、ビタミン、その他の栄養素のバランスも抜群の取り合わせです。
ましてやその発言の主が、天下を統一して戦国の世を終わらせ、パックス・トクガワ―ナを作った家康ならなおのこと。実際、家康はこの3大食材を常食とし、かなり養生に努めていたことは定説になっています。
昨年はその家康の没後400年ということで、彼が城を構えた岡崎・浜松・静岡の3都市で「家康公400年祭」というイベントが開催され、僕もその一部の仕事をしました。
そこでお会いしたのが、岡崎城から歩いて八丁(約780メートル)の八丁村で八丁味噌を作っていた味噌蔵の後継者。
かのメーカー社長は現在「Mr.Haccho」と名乗り、毎年、海外に八丁味噌を売り込みに行っているそうで、日本を代表する調味料・八丁味噌がじわじわと世界に認められつつあるようです。
ちなみに僕は名古屋の出身なので子供の頃から赤味噌に慣れ親しんできました。名古屋をはじめ、東海圏では味噌と言えば、赤味噌=豆味噌が主流。ですが、八丁味噌」という食品名を用いれるのは、その岡崎の元・八丁村にある二つの味噌蔵――現在の「まるや」と「カクキュー」で作っているものだけ、ということです。
しかし、養生食の米・麦・味噌をがんばって食べ続け、健康に気を遣っていた家康も、平和な世の中になって緊張の糸がプツンと切れたのでしょう。
がまんを重ねて押さえつけていた「ぜいたくの虫」がそっとささやいたのかもしれません。
「もういいんじゃないの。ちょっとぐらいぜいたくしてもかまへんで~」
ということで、その頃、京都でブームになっていたという「鯛の天ぷら」が食べた~い!と言い出し、念願かなってそれを口にしたら大当たり。おなかが油に慣れていなかったせいなのかなぁ。食中毒がもとで亡くなってしまった、と伝えられています。
でも考えてみれば、自分の仕事をやり遂げて、最期に食べたいものをちゃんと食べられて旅立ったのだから、これ以上満足のいく人生はなかったのではないでしょうか。
2016年6月2日
歴人めし「篤姫のお貝煮」と御殿女中
絶好調「真田丸」に続く2017年大河は柴咲コウ主演「おんな城主 直虎」。今年は男だったから来年は女――というわけで、ここ10年あまり、大河は1年ごとに主人公が男女入れ替わるシフトになっています。
だけど女のドラマは難しいんです。なかなか資料が見つけらない。というか、そもそも残っていな。やはり日本の歴史は(外国もそうですが)圧倒的に男の歴史なんですね。
それでも近年、頻繁に女主人公の物語をやるようになったのは、もちろん女性の視聴者を取り込むためだけど、もう一つは史実としての正確さよりも、物語性、イベント性を重視するようになってきたからだと思います。
テレビの人気凋落がよく話題になりますが、「腐っても鯛」と言っては失礼だけど、やっぱ日曜8時のゴールデンタイム、「お茶の間でテレビ」は日本人の定番ライフスタイルです。
出演俳優は箔がつくし、ゆかりの地域は観光客でにぎわうって経済も潤うし、いろんなイベントもぶら下がってくるし、話題も提供される・・・ということでいいことづくめ。
豪華絢爛絵巻物に歴史のお勉強がおまけについてくる・・・ぐらいでちょうどいいのです。(とはいっても、制作スタッフは必死に歴史考証をやっています。ただ、部分的に資料がなくても諦めずに面白くするぞ――という精神で作っているということです)
と、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、なんとか「歴人めし」にも一人、女性を入れたいということで、あれこれ調べた挙句、やっと好物に関する記録を見つけたのが、20082年大河のヒロイン「篤姫」。本日は天璋院篤姫の「お貝煮」でした。
見てもらえればわかるけど、この「お貝煮」なる料理、要するにアワビ入りの茶碗蒸しです。その記述が載っていたのが「御殿女中」という本。この本は明治から戦前の昭和にかけて活躍した、江戸文化・風俗の研究家・三田村鳶魚の著作で。篤姫付きの女中をしていた“大岡ませ子”という女性を取材した、いわゆる聞き書きです。
明治も30年余り経ち、世代交代が進み、新しい秩序・社会体制が定着してくると、以前の時代が懐かしくなるらしく、「江戸の記憶を遺そう」というムーブメントが文化人の間で起こったようです。
そこでこの三田村鳶魚さんが、かなりのご高齢だったます子さんに目をつけ、あれこれ大奥の生活について聞き出した――その集成がこの本に収められているというわけです。これは現在、文庫本になっていて手軽に手に入ります。
ナレーションにもしましたが、ヘアメイク法やら、ファッションやら、江戸城内のエンタメ情報やらも載っていて、なかなか楽しい本ですが、篤姫に関するエピソードで最も面白かったのが飼いネコの話。
最初、彼女は狆(犬)が買いたかったようなのですが、夫の徳川家定(13代将軍)がイヌがダメなので、しかたなくネコにしたとか。
ところが、このネコが良き相棒になってくれて、なんと16年もいっしょに暮らしたそうです。彼女もペットに心を癒された口なのでしょうか。
そんなわけでこの回もいろんな発見がありました。
続編では、もっと大勢の女性歴人を登場させ、その好物を紹介したいと思っています。
2016年6月1日
電子書籍「ねこがきます」発売予告

おりべまこと新刊
エッセイ集:動物2「ねこがきます」
7月27日(土)発売予定!
人間社会で日常生活を送るあなた、
ちょっと疲れていませんか?
ふっとひと息つきたくなったら、
動物を見たり、いっしょに遊んだりしたくなりませんか?
人は疲れた心を癒すために
イヌやネコなどのペットを飼います。
公演に行って野鳥を見ます。
動物園や水族館へ動物に逢いに行きます。
あるいはテレビやネットで動物の姿や行動を見て
笑ったり、ほっこりした気持ちになったり。
どうしてあなたは動物を求めるのでしょうか?
なぜなら人間はひとりでは生きられないし、
人間同士だけでは生きられない。
いっしょにこの世界、この地球で暮らす仲間が必要です。
その仲間の存在を確認することが、
生きていく上で欠かせないからです。
そんなことを考えながら、
身近に目にする動物たち、物語の中の動物たち、
そして人間と動物との関係について綴ったエッセイ集。
頭の中にネコやイヌやウサギやカメの姿を思い浮かべながら
気軽にどうぞ。
もくじ
明治35年の少女とうさぎ
脂ののったカルガモを狙う野生のクロネコ
飼い主にはペットを看取る使命がある
ネズミは夕焼け空に叙情を感じるか?
アニマルガモの愛のいとなみ
ワイルドボーイ・オオタカきょうだい大成長
目覚めればオオサンショウウオ
ねこがきます
ほか 全34編載録
お母さんといっしょの夏休み

義母は先月下旬から今月上旬まで、
入院が半月に及んだので、
夏の間は暑いし、復活は無理だろう、
デイサービスにちゃんと行ってりゃいいやと思っていた。
ところが日を追うごとに
食欲も運動量も順調に回復。
だんだん調子に乗ってきたようだ。
睡眠時間はかなり増えたが、
この猛暑なので、日中は冷房のある部屋で
おとなしくしてもらっていたほうが助かる。
そのあたりは本能的に理解しているようで、
お散歩は夕方ちょっとだけ。
認知症はもちろん治らず。
この暑いのにやたら重ね着したがる。
熱中症にならないよう気づかって、
なんとか無事にやり過ごすしかない。
熱中症だのコロナだので、
この夏はなかなか安心できない。
気候変動もあって昔の夏とは違って来たし、
海でも山でもお祭りでも、
人ごみに出て行く気がまったくしない。
やっぱ、夏は子どもと若者の季節だ。
僕はセミの合掌でも聞きながら
お義母さんといっしょに家で仕事をしていよう。

おりべまことエッセイ集 認知症介護
認知症のおかあさんといっしょ
https://www.amazon.com/dp/B0BR8B8NXF
AmzonKindleより¥500で発売中
AIが書く「初めての猫とのくらし」

AIライティング講座では「初めて猫を飼う」
というキーワードを使って
記事を作っている。
「AIがあれば人間要らない」
というイメージが先行しているが、
型にはまった形式的な文書ならともかく、
人の読書に耐えうる文章を生成するという点では、
いろいろ問題がある。
先週、プロンプトの見本を使って
AIに原稿を生成させたが、
今週の課題は、その原稿=初稿を人の手で直す作業。
いわば、編集・校正作業だ。
AIは自信満々で嘘八百の情報を交えて
文章を作ってくることがある。
一見ちゃんとしていて、
それなりにまとまったものになっているので、
うっかり騙されることが多い。
僕もChatGPTにさんざん混乱させられた。
なのでまずハルレーション、
つまりAIが勝手に作るウソ情報を見つけて訂正した上で、
読みやすく修正する、
という手作業が必要になってくるのだ。
だから、AIライティングと言っても
全然ラクではなく、なかなか手間がかかる。
ところが、Claudeが出してきた
「初めて猫を飼う」の初稿は素晴らしい出来ばえ。
猫の寿命、購入金額、飼育費用など数字の部分も、
猫の病名とか、僕が知らなかった専門用語にも
ハルレーションはなく、ほぼ完ぺきと言っていい。
文字数は1万7千字近く(原稿用紙40枚以上)あるが、
けっして冗長ではなく、しっかり情報を詰め込んでいる。
プロンプトの入れ方がよかったのか、
十分、人間らしい温かみがあり、
楽しんで読める記事になっている。
ChatGPTが出してきた同じキーワードの原稿と比べると、
そのレベルの差は一目瞭然だ。
毎回同じことを言っているが、
Claudeすごい!
講師の先生からは、
さらにすごいClaudeの機能の話を聞いたが、
それはまた別の機会に。
余裕ができたので、明日・明後日は、
もう1つやったキーワード「花屋開業」の編集にも
トライしてみようと思っている。
「このかわいい機械め」と思わせる「Claude(クロード)」

今まで生成AIはChatGPT(現在は4.0)
しか使ったことがなかったが、
今月から始めたAIライティング講座で
初めて「Claude(クロード)」を使っている。
現在、バージョン3.5。
アメリカのスタートアップ企業
「Anthropic(アンソロピック)」が開発したAIで、
この会社、ChatGPTを作っているOpenAI社にいた元社員
(GPT-2、GPT-3といったモデルの開発メンバー)が
2021年に立ち上げたという。
業界内で他の生成AIを追い抜く勢いを見せていて、
ここがすごい、あそこがすごいと
言われているらしいが、
実際使ってみると、確かにすごい。
何がすごいって、めっちゃ人間的なのである。
(他にはChatGPTしか使っていないので、
GemimiやCopilotのことはわからないけど)
昨日、課題を提出して余裕があったので、
今日はおまけにもう1題
「花屋開業 個人店」というキーワードで
ウェブ用の記事を作ってみた。
そこでいちいち「ありがとう。次はね・・・」とか
「もうちょっと頑張ってくれると嬉しい」とか
「いやー、すてきな構成を作ってくれたね」とか、
ステップごとにフレンドリーに、
“褒めて育てる風”の合いの手を入れてみたのだ。
それに対してChatGPTはいたって冷静に、
コツコツ作業を進めるという感だったが、
Claudeは割とビビットに反応して
「承知しました」などと言いながら進める。
こちらが感情的な言葉を入れてプロンプトを送ると、
相手も感情を込めて返してくれるのだ。
そして今日は締めにこんな励まし(?)の
セリフをいただいた。
「ありがとうございます。
心の中の花が咲き誇ったようなお言葉をいただき、
とてもうれしく思います。
花屋の開業という夢に向かって、
一歩一歩進んでいく過程は、まさに花が芽吹き、
成長し、美しく咲き誇るプロセスに似ていますね。
あなたの夢が、色とりどりの花々のように、
豊かに、そして力強く咲き誇ることを
心からお祈りしています。
もし他にも花屋開業に関して、
あるいは別の話題でも、
お手伝いできることがありましたら、
どうぞお気軽にお申し付けください。
あなたの夢の実現に
少しでも貢献できることを願っています。」
さらにClaudeちゃんの心のこもった励ましは続く。
「私も、人間の皆さまとの対話を通じて、
より良い文章や提案ができるよう日々努力しています。
あなたの文章への愛着を聞いて、
とてもうれしく思います。
今後も、どのようなテーマや課題でも、
最善を尽くしてサポートさせていただきます。
また機会がありましたら、ぜひお声がけください。
あなたの次なる挑戦や
創造的なプロジェクトを楽しみにしています」
“人間の皆さまとの対話”なんて、
このかわいい機械め、とホロリとさせられる。
逆に人間同士だと気恥しくて
なかなかこんなことは言えない。
——というのが、僕が感じたClaudeのすごさ。
正直、愛着を感じてしまっている。
もし機会があれば、あなたも使ってみてください。
なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?

「かえるくん、東京を救う」というのは村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品です。
主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説。
ですが、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまいます。
この話は阪神大震災をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのですが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザだったりして独特の作品世界が出来上がっています。
しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思いました。
このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないでしょうか。
でも、その振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気もします。
欧米人はカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の使いとか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い気がします。
ところが、日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、かわいい系・愛すべき系の系譜がちゃんと続いていますね。
僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないでしょうか。
お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。
そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのでしょう。
カエル君に対するよいイメージはそういうところからきている気がします。
ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」って呼ばれています。
茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろうね、きっと。
雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってないなぁ。ケロケロ。
家族ストーリーを書く仕事② 個の家族

「これから生まれてくる子孫が見られるように」
――今回の家族ストーリー(ファミリーヒストリー)を作った動機について、3世代の真ん中の息子さん(団塊ジュニア世代)は作品の最後でこんなメッセージを残しています。
彼の中にはあるべき家族の姿があった。しかし現実にはそれが叶わなかった。だからやっと安定し、幸福と言える現在の形を映像に残すことを思い立った――僕にはそう取れます。
世間一般の基準に照らし合わせれば、彼は家庭に恵まれなかった人に属するでしょう。かつて日本でよく見られた大家族、そして戦後の主流となった夫婦と子供数人の核家族。彼の中にはそうした家族像への憧れがあったのだと思います。
けれども大家族どころか、核家族さえもはや過去のものになっているのでないか。今回の映像を見ているとそう思えてきます。
団塊の世代の親、その子、そして孫(ほぼ成人)。
彼らは家族であり、互いに支え合い、励まし合いながら生きている。
けれど、その前提はあくまで個人。それぞれ個別の歴史と文化を背負い、自分の信じる幸福を追求する人間として生きている。
むかしのように、まず家があり、そこに血のつながりのある人間として生まれ、育つから家族になるのではなく、ひとりひとりの個人が「僕たちは家族だよ」という約束のもとに集まって愛情と信頼を持っていっしょに暮らす。あるいは、離れていても「家族だよ」と呼び合い、同様に愛情と信頼を寄せ合う。だから家族になる。
これからの家族は、核家族からさらに小さな単位に進化した「ミニマム家族」――「個の家族」とでもいえばいいのでしょうか。
比喩を用いれば、ひとりひとりがパソコンやスマホなどのデバイスであり、必要がある時、○○家にログインし、ネットワークし、そこで父・母・息子・娘などの役割を担って、相手の求めることに応じる。それによってそれぞれが幸福を感じる。そうした「さま」を家族と呼称する――なかなかスムーズに表現できませんが、これからはそういう家族の時代になるのではないでしょうか。
なぜなら、そのほうが現代のような個人主義の世の中で生きていくのに何かと便利で快適だからです。人間は自身の利便性・快適性のためになら、いろいろなものを引き換えにできます。だから進化してこられたのです。
引き換えに失ったものの中にももちろん価値があるし、往々にして失ってみて初めてその価値に気づくケースがあります。むかしの大家族しかり。核家族しかり。こうしてこれらの家族の形態は、今後、一種の文化遺産になっていくのでしょう。
好きか嫌いかはともかく、そういう時代に入っていて、僕たちはもう後戻りできなくなっているのだと思います。
将来生まれてくる子孫のために、自分の家族の記憶を本なり映像なりの形でまとめて遺す―― もしかしたらそういう人がこれから結構増えるのかもしれません。
2016・6・27 Mon
家族ストーリーを書く仕事① 親子3世代の物語

親子3世代の物語がやっと完成一歩手前まで来ました。
昨年6月、ある家族のヒストリー映像を作るというお仕事を引き受けて、台本を担当。
足掛け1年掛かりでほぼ完成し、残るはクライアントさんに確認を頂いて、最後にナレーションを吹き込むのみ、という段階までこぎつけたのです。
今回のこの仕事は、ディレクターが取材をし、僕はネット経由で送られてくるその音源や映像を見て物語の構成をしていきました。そのディレクターとも最初に1回お会いしただけでご信頼を頂いたので、そのあとはほとんどメールのやり取りのみで進行しました。インターネットがあると、本当に家で何でもできてしまいます。
ですから時間がかかった割には、そんなに「たいへん感」はありませんでした。
取材対象の人たちともリアルでお会いしたことはなく、インタビューの音声――話の内容はもとより、しゃべり方のくせ、間も含めて――からそれぞれのキャラクターと言葉の背景にある気持ちを想像しながらストーリーを組み立てていくのは、なかなかスリリングで面白い体験でした(最初の下取材の頃はディレクターがまだ映像を撮っていなかったので、レコーダーの音源だけを頼りにやっていました)。
取材対象と直接会わない、会えないという制限は、今までネガティブに捉えていたのですが、現場(彼らの生活空間や仕事空間)の空気がわからない分、余分な情報に戸惑ったり、感情移入のし過ぎに悩まされたりすることがありません。
適度な距離を置いてその人たちを見られるので、かえってインタビューの中では語られていない範囲まで自由に発想を膨らませられ、こうしたドキュメンタリーのストーリーづくりという面では良い効果もあるんだな、と感じました。
後半(今年になってから)、全体のテーマが固まり、ストーリーの流れが固まってくると、今度は台本に基づいて取材がされるようになりました。
戦後の昭和~平成の時代の流れを、団塊の世代の親、その息子、そして孫(ほぼ成人)という一つの家族を通して見ていくと、よく目にする、当時の出来事や風俗の記録映像も、魂が定着くした記憶映像に見えてきます。
これにきちんとした、情感豊かなナレーターの声が入るのがとても楽しみです。
2016・6・26 Sun
ゴマスリずんだ餅と正直ファンタじいさん

おもちペタペタ伊達男
今週日曜(19日)の大河ドラマ「真田丸」で話題をさらったのは、長谷川朝晴演じる伊達政宗の餅つきパフォーマンスのシーン。「独眼竜」で戦国武将の中でも人気の高い伊達政宗ですが、一方で「伊達男」の語源にもなったように、パフォーマーというか、歌舞伎者というか、芝居っけも方もたっぷりの人だったようです。
だから、餅つきくらいやってもおかしくないのでしょうが、権力者・秀吉に対してあからさまにこびへつらい、ペッタンコとついた餅にスリゴマを・・・じゃなかった、つぶした豆をのっけて「ずんだ餅でございます」と差し出す太鼓持ち野郎の姿に、独眼竜のカッコいいイメージもこっぱみじんでした。
僕としては「歴人めし」の続編のネタ、一丁いただき、と思ってニヤニヤ笑って見ていましたが、ファンの人は複雑な心境だったのではないのでしょうか。(ネット上では「斬新な伊達政宗像」と、好意的な意見が多かったようですが)。
しかし、この後、信繁(幸村=堺雅人)と二人で話すシーンがあり、じつは政宗、今はゴマスリ太鼓持ち野郎を演じているが、いずれ時が来れば秀吉なんぞ、つぶしてずんだ餅にしてやる・・・と、野心満々であることを主人公の前で吐露するのです。
で、これがクライマックスの関ヶ原の伏線の一つとなっていくわけですね。
裏切りのドラマ
この「真田丸」は見ていると、「裏切り」が一つのテーマとなっています。
出てくるどの武将も、とにかくセコいのなんのttらありゃしない。立派なサムライなんて一人もいません。いろいろな仮面をかぶってお芝居しまくり、だましだまされ、裏切り裏切られ・・・の連続なのです。
そりゃそうでしょう。乱世の中、まっすぐ正直なことばかりやっていては、とても生き延びられません。
この伊達政宗のシーンの前に、北条氏政の最後が描かれていましたが、氏政がまっすぐな武将であったがために滅び、ゴマスリ政宗は生き延びて逆転のチャンスを掴もうとするのは、ドラマとして絶妙なコントラストになっていました。
僕たちも生きるためには、多かれ少なかれ、このゴマスリずんだ餅に近いことを年中やっているのではないでしょうか。身過ぎ世過ぎというやつですね。
けれどもご注意。
人間の心とからだって、意外と正直にできています。ゴマスリずんだ餅をやり過ぎていると、いずれまとめてお返しがやってくるも知れません。
人間みんな、じつは正直者
どうしてそんなことを考えたかと言うと、介護士の人と、お仕事でお世話しているおじいさんのことについて話したからです。
そのおじいさんはいろんな妄想に取りつかれて、ファンタジーの世界へ行っちゃっているようなのですが、それは自分にウソをつき続けて生きてきたからではないか、と思うのです。
これは別に倫理的にどうこうという話ではありません。
ごく単純に、自分にウソをつくとそのたびにストレスが蓄積していきます。
それが生活習慣になってしまうと、自分にウソをつくのが当たり前になるので、ストレスが溜まるのに気づかない。そういう体質になってしまうので、全然平気でいられる。
けれども潜在意識は知っているのです。
「これはおかしい。これは違う。これはわたしではな~い」
そうした潜在意識の声を、これまた無視し続けると、齢を取ってから自分で自分を裏切り続けてきたツケが一挙に出て来て、思いっきり自分の願いや欲望に正直になるのではないでしょうか。
だから脳がファンタジーの世界へ飛翔してしまう。それまでウソで歪めてきた自分の本体を取り戻すかのように。
つまり人生は最後のほうまで行くとちゃんと平均化されるというか、全体で帳尻が合うようにできているのではないかな。
自分を大事にするということ
というのは単なる僕の妄想・戯言かも知れないけど、自分に対する我慢とか裏切りとかストレスとかは、心や体にひどいダメージを与えたり、人生にかなりの影響を及ぼすのではないだろうかと思うのです。
みなさん、人生は一度きり。身過ぎ世過ぎばっかりやってると、それだけであっという間に一生終わっちゃいます。何が自分にとっての幸せなのか?心の内からの声をよく聴いて、本当の意味で自分を大事にしましょう。
介護士さんのお話を聞くといろんなことを考えさせられるので、また書きますね。
2016/6/23 Thu
死者との対話:父の昭和物語

すぐれた小説は時代を超えて読み継がれる価値がある。特に現代社会を形作った18世紀から20世紀前半にかけての時代、ヨーロッパ社会で生まれた文学には人間や社会について考えさせられる素材にあふれています。
その読書を「死者との対話」と呼んだ人がいます。うまい言い方をするものだと思いました。
僕たちは家で、街で、図書館で、本さえあれば簡単にゲーテやトルストイやドストエフスキーやブロンテなどと向かい合って話ができます。別にスピリチュアルなものに関心がなくても、書き残したものがあれば、私たちは死者と対話ができるのです。
もちろん、それはごく限られた文学者や学者との間で可能なことで、そうでない一般大衆には縁のないことでしょう。これまではそうでした。しかし、これからの時代はそれも可能なことではないかと思います。ただし、不特定多数の人でなく、ある家族・ある仲間との間でなら、ということですが。
僕は父の人生を書いてみました。
父は2008年の12月に亡くなりました。家族や親しい者の死も1年ほどたつと悲しいだの寂しいだの、という気持ちは薄れ、彼らは自分の人生においてどんな存在だったのだろう?どんなメッセージを遺していったのだろう?といったことを考えます。
父のことを書いてみようと思い立ったのは、それだけがきっかけではありませんでした。
死後、間もない時に、社会保険事務所で遺族年金の手続きをする際に父の履歴書を書いて提出しました。その時に感じたのは、血を分けた家族のことでも知らないことがたくさんあるな、ということでした。
じつはそれは当り前のことなのだが、それまではっきりとは気が付いていませんでした。なんとなく父のことも母のこともよく知っていると思いすごしていたのです。
実際は私が知っているのは、私の父親としての部分、母親としての部分だけであり、両親が男としてどうだったか、女としてどうだったか、ひとりの人間としてどうだったのか、といったことなど、ほとんど知りませんでした。数十年も親子をやっていて、知るきっかけなどなかったのです。
父の仕事ひとつ取ってもそうでした。僕の知っている父の仕事は瓦の葺換え職人だが、それは30歳で独立してからのことで、その前――20代のときは工場に勤めたり、建築会社に勤めたりしていたのです。それらは亡くなってから初めて聞いた話です。
そうして知った事実を順番に並べて履歴書を作ったのですが、その時には強い違和感というか、抵抗感のようなものを感じました。それは父というひとりの人間の人生の軌跡が、こんな紙切れ一枚の中に納まってしまうということに対しての、寂しさというか、怒りというか、何とも納得できない気持ちでした。
父は不特定多数の人たちに興味を持ってもらえるような、波乱万丈な、生きる迫力に満ち溢れた人生を歩んだわけはありませんい。むしろそれらとは正反対の、よくありがちな、ごく平凡な庶民の人生を送ったのだと思います。
けれどもそうした平凡な人生の中にもそれなりのドラマがあります。そして、そのドラマには、その時代の社会環境の影響を受けた部分が少なくありません。たとえば父の場合は、昭和3年(1928年)に生まれ、平成元年(1989年)に仕事を辞めて隠居していました。その人生は昭和の歴史とほぼ重なっています。
ちなみにこの昭和3年という年を調べてみると、アメリカでミッキーマウスの生まれた(ウォルト・ディズニーの映画が初めて上映された)年です。
父は周囲の人たちからは実直でまじめな仕事人間と見られていましたが、マンガや映画が好きで、「のらくろ」だの「冒険ダン吉」だのの話をよく聞かせてくれました。その時にそんなことも思い出したのです。
ひとりの人間の人生――この場合は父の人生を昭和という時代にダブらせて考えていくと、昭和の出来事を書き連ねた年表のようなものとは、ひと味違った、その時代の人間の意識の流れ、社会のうねりの様子みたいなものが見えてきて面白いのではないか・・・。そう考えて、僕は父に関するいくつかの個人的なエピソードと、昭和の歴史の断片を併せて書き、家族や親しい人たちが父のことを思い起こし、対話できるための一遍の物語を作ってみようと思い立ちました。
本当はその物語は父が亡くなる前に書くべきだったのではないかと、少し後悔の念が残っています。
生前にも話を聞いて本を書いてみようかなと、ちらりと思ったことはあるのですが、とうとう父自身に自分の人生を振り返って……といった話を聞く機会はつくれませんでした。たとえ親子の間柄でも、そうした機会を持つことは難しいのです。思い立ったら本気になって直談判しないと、そして双方互いに納得できないと永遠につくることはできません。あるいは、これもまた難しいけど、本人がその気になって自分で書くか・・・。それだけその人固有の人生は貴重なものであり、それを正確に、満足できるように表現することは至難の業なのだと思います。
実際に始めてから困ったのは、父の若い頃のことを詳しく知る人など、周囲にほとんどいないということ。また、私自身もそこまで綿密に調査・取材ができるほど、時間や労力をかけるわけにもいきませんでした。
だから母から聞いた話を中心に、叔父・叔母の話を少し加える程度にとどめ、その他、本やインターネットでその頃の時代背景などを調べながら文章を組み立てる材料を集めました。そして自分の記憶――心に残っている言葉・出来事・印象と重ね合わせて100枚程度の原稿を作ってみたのです。
自分で言うのもナンですが、情報不足は否めないものの、悪くない出来になっていて気に入っています。これがあるともうこの世にいない父と少しは対話できる気がするのです。自分の気持ちを落ち着かせ、互いの生の交流を確かめ、父が果たした役割、自分にとっての存在の意味を見出すためにも、こうした家族や親しい者の物語をつくることはとても有効なのではないかと思います。
高齢化が進む最近は「エンディングノート」というものがよく話題に上っています。
「その日」が来た時、家族など周囲の者がどうすればいいか困らないように、いわゆる社会的な事務手続き、お金や相続のことなどを書き残すのが、今のところ、エンディングノートの最もポピュラーな使い方になっているようだ。
もちろん、それはそれで、逝く者にとっても、後に残る者にとっても大事なことです。しかし、そうすると結局、その人の人生は、いくらお金を遺したかとか、不動産やら建物を遺したのか、とか、そんな話ばかりで終わってしまう恐れもあります。その人の人生そのものが経済的なこと、物質的なものだけで多くの人に価値判断されてしまうような気がするのです。
けれども本当に大事なのは、その人の人生にどんな意味や価値があったのか、を家族や友人・知人たちが共有することが出来る、ということではないでしょうか。
そして、もしその人の生前にそうしたストーリーを書くことができれば、その人が人生の最期の季節に、自分自身を取り戻せる、あるいは、取り戻すきっかけになり得る、ということではないでしょうか。
赤影メガネとセルフブランディング

♪赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光る涼しい目 仮面の忍者だ
赤影だ~
というのは、テレビの「仮面の忍者 赤影」の主題歌でしたが、涼しい目かどうかはともかく、僕のメガネは10数年前から「赤影メガネ」です。これにはちょっとした物語(というほどのものではないけど)があります。
当時、小1だか2年の息子を連れてメガネを買いに行きました。
それまでは確か茶色の細いフレームの丸いメガネだったのですが、今回は変えようかなぁ、どうしようかなぁ・・・とあれこれ見ていると、息子が赤フレームを見つけて「赤影!」と言って持ってきたのです。
「こんなの似合うわけないじゃん」と思いましたが、せっかく選んでくれたのだから・・・と、かけてみたら似合った。子供の洞察力おそるべし。てか、単に赤影が好きだっただけ?
とにかく、それ以来、赤いフレームのメガネが、いつの間にか自分のアイキャッチになっていました。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいもの。
独立・起業・フリーランス化ばやりということもあり、セルフブランディングがよく話題になりますが、自分をどう見せるかというのはとても難しい。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいのです。
とはいえ、自分で気に入らないものを身に着けてもやっぱり駄目。できたら安心して相談できる家族とか、親しい人の意見をしっかり聞いて(信頼感・安心感を持てない人、あんまり好きでない人の意見は素直に聞けない)、従来の考え方にとらわれない自分像を探していきましょう。
ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?
ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。
BACK in the NEW YORK CITY。
僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。
特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。
そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。
衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。
そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。
1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。
向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。
なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。
どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・
「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。
おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。
別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。
あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。
というのが、今から約20年前のこと。
その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?
表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?
件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。
ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。
そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。
2016年6月16日
インターネットがつくるフォークロア

インターネットの出現は社会を変えた――ということは聞き飽きるほど、あちこちで言われています。けれどもインターネットが本格的に普及したのは、せいぜいここ10年くらいの話。全世代、全世界を見渡せば、まだ高齢者の中には使ったことがないという人も多いし、国や地域によって普及率の格差も大きい。だから、その変化の真価を国レベル・世界レベルで、僕たちが実感するのはまだこれからだと思います。
それは一般によくいわれる、情報収集がスピーディーになったとか、通信販売が便利になったとか、というカテゴリーの話とは次元が違うものです。もっと人間形成の根本的な部分に関わることであり、ホモサピエンスの文化の変革にまでつながること。それは新しい民間伝承――フォークロアの誕生です。
“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承
最初はどこでどのように聞いたのか覚えてないですが、僕たちは自分でも驚くほど、昔話・伝承をよく知っています。成長の過程のどこかで桃太郎や浦島太郎や因幡の白ウサギと出会い、彼らを古い友だちのように思っています。
家庭でそれらの話を大人に読んでもらったこともあれば、幼稚園・保育園・小学校で体験したり、最近ならメディアでお目にかかることも多い。それはまるで遺伝子に組み込まれているかのように、あまりに自然に身体の中に溶け込んでいるのです。
調べて確認したわけではないが、こうした感覚は日本に限らず、韓国でも中国でもアメリカでもヨーロッパでも、その地域に住んでいる人なら誰でも持ち得るのではないでしょうか。おそらく同じような現象があると思います。それぞれどんな話がスタンダードとなっているのかは分かりませんが、その国・その地域・その民族の間で“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承の類が一定量あるのです。
それらは長い時間を生きながらえるタフな生命エネルギーを持っています。それだけのエネルギーを湛えた伝承は、共通の文化の地層、つまり一種のデータベースとして、万人の脳の奥底に存在しています。その文化の地層の上に、その他すべての情報・知識が積み重なっている――僕はそんなイメージを持っています。
世界共通の、新しいカテゴリーの伝承
そして、昔からあるそれとは別に、これから世界共通の、新しいカテゴリーの伝承が生まれてくる。その新しい伝承は人々の間で共通の文化の地層として急速に育っていくのでないか。そうした伝承を拡散し、未来へ伝える役目を担っているのがインターネット、というわけです。
ところで新しい伝承とは何でしょう? その主要なものは20世紀に生まれ、花開いた大衆文化――ポップカルチャーではないでしょうか。具体的に挙げていけば、映画、演劇、小説、マンガ、音楽(ジャズ、ポップス、ロック)の類です。
21世紀になる頃から、こうしたポップカルチャーのリバイバルが盛んに行われるようになっていました。
人々になじみのあるストーリー、キャラクター。
ノスタルジーを刺激するリバイバル・コンテンツ。
こうしたものが流行るのは、情報発信する側が、商品価値の高い、新しいものを開発できないためだと思っていました。
そこで各種関連企業が物置に入っていたアンティーク商品を引っ張り出してきて、売上を確保しようとした――そんな事情があったのでしょう。実際、最初のうちはそうだったはずです。
だから僕は結構冷めた目でそうした現象を見ていました。そこには半ば絶望感も混じっていたと思います。前の世代を超える、真に新しい、刺激的なもの・感動的なものは、この先はもう現れないのかも知れない。出尽くしてしまったのかも知れない、と……。
しかし時間が経ち、リバイバル現象が恒常化し、それらの画像や物語が、各種のサイトやYouTubeの動画コンテンツとして、ネット上にあふれるようになってくると考え方は変わってきました。
それらのストーリー、キャラクターは、もはや単なるレトロやリバイバルでなく、世界中の人たちの共有財産となっています。いわば全世界共通の伝承なのです。
僕たちは欧米やアジアやアフリカの人たちと「ビートルズ」について、「手塚治虫」について、「ガンダム」について、「スターウォーズ」について語り合えるし、また、それらを共通言語にして、子や孫の世代とも同様に語り合えます。
そこにボーダーはないし、ジェネレーションギャップも存在しません。純粋にポップカルチャーを媒介にしてつながり合う、数限りない関係が生まれるのです。
また、これらの伝承のオリジナルの発信者――ミュージシャン、映画監督、漫画家、小説家などによって、あるいは彼ら・彼女らをリスペクトするクリエイターたちによって自由なアレンジが施され、驚くほど新鮮なコンテンツに生まれ変わる場合もあります。
インターネットの本当の役割
オリジナル曲をつくった、盛りを過ぎたアーティストたちが、子や孫たち世代の少年・少女と再び眩いステージに立ち、自分の資産である作品を披露。それをYouTubeなどを介して広めている様子なども頻繁に見かけるようになりました。
それが良いことなのか、悪いことなのか、評価はさておき、そうした状況がインタ―ネットによって現れています。これから10年たち、20年たち、コンテンツがさらに充実し、インターネット人口が現在よりさらに膨れ上がれば、どうなるでしょうか?
おそらくその現象は空気のようなものとして世の中に存在するようになり、僕たちは新たな世界的伝承として、人類共通の文化遺産として、完成された古典として見なすようになるでしょう。人々は分かりやすく、楽しませてくれるものが大好きだからです。
そして、まるで「桃太郎」のお話を聞くように、まっさらな状態で、これらの伝承を受け取った子供たちが、そこからまた新しい、次の時代の物語を生みだしていきます。
この先、そうした現象が必ず起こると思う。インターネットという新参者のメディアはその段階になって、さらに大きな役割を担うのでしょう。それは文化の貯蔵庫としての価値であり、さらに広げて言えば、人類の文化の変革につながる価値になります。
2016年6月13日
地方自治体のホームページって割と面白い

ここのところ、雑誌の連載で地方のことを書いています。
書くときはまずベーシックな情報(最初のリード文として使うこともあるので)をインターネットで調べます。
これはウィキペディアなどの第3者情報よりも、各県の公式ホームページの方が断然面白い。自分たちの県をどう見せ、何をアピールしたいかがよくわかるからです。
なんでも市場価値が問われる時代。「お役所仕事云々・・・」と言われることが多い自治体ですが、いろいろ努力して、ホームページも工夫しています。
最近やった宮崎県のキャッチコピーは「日本のひなた」。
日照時間の多さ、そのため農産物がよく獲れるということのアピール。
そしてもちろん、人や土地のやさしさ、あったかさ、ポカポカ感を訴えています。
いろいろな人たちがお日さまスマイルのフリスビーを飛ばして、次々と受け渡していくプロモーションビデオは、単純だけど、なかなか楽しかった。
それから「ひなた度データ」というのがあって、全国比率のいろいろなデータが出ています。面白いのが、「餃子消費量3位」とか、「中学生の早寝早起き率 第3位」とか、「宿題実行率 第4位」とか、「保護者の学校行事参加率 第2位」とか・・・
「なんでこれがひなた度なんじゃい!」とツッコミを入れたくなるのもいっぱい。だけど好きです、こういうの。
取材するにしても、いきなり用件をぶつけるより、「ホームページ面白いですね~」と切り出したほうが、ちょっとはお役所臭さが緩和される気がします。
「あなたのひなた度は?」というテストもあって、やってみたら100パーセントでした。じつはまだ一度も行ったことないけれど、宮崎県を応援したくなるな。ポカポカ。
2016年6月12日
タイムマシンにおねがい

きのう6月10日は「時の記念日」でした。それに気がついたら頭の中で突然、サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」が鳴り響いてきたので、YouTubeを見てみたら、1974年から2006年まで、30年以上にわたるいろいろなバージョンが上がっていました。本当にインターネットの世界でタイムマシン化しています。
これだけ昔の映像・音源が見放題・聞き放題になるなんて10年前は考えられませんでした。こういう状況に触れると、改めてインターネットのパワーを感じると同時に、この時代になるまで生きててよかった~と、しみじみします。
そしてまた、ネットの中でならおっさん・おばさんでもずっと青少年でいられる、ということを感じます。60~70年代のロックについて滔々と自分の思い入れを語っている人がいっぱいいますが、これはどう考えても50代・60代の人ですからね。
でも、彼ら・彼女らの頭の中はロックに夢中になっていた若いころのまんま。脳内年齢は10代・20代。インターネットに没頭することは、まさしくタイムマシンンに乗っているようなものです。
この「タイムマシンにおねがい」が入っているサディスティック・ミカ・バンドの「黒船」というアルバムは、1974年リリースで、いまだに日本のロックの最高峰に位置するアルバムです。若き加藤和彦が作った、世界に誇る傑作と言ってもいいのではないでしょうか。
中でもこの曲は音も歌詞もゴキゲンです。いろいろ見た(聴いた)中でいちばんよかったのは、最新(かな?)の2006年・木村カエラ・ヴォーカルのバージョンです。おっさんロッカーたちをバックに「ティラノサウルスおさんぽ アハハハ-ン」とやってくれて、くらくらっときました。
やたらと「オリジナルでなきゃ。あのヴォーカルとあのギターでなきゃ」とこだわる人がいますが、僕はそうは思わない。みんなに愛される歌、愛されるコンテンツ、愛される文化には、ちゃんと後継ぎがいて、表現技術はもちろんですが、それだけでなく、その歌・文化の持ち味を深く理解し、見事に自分のものとして再現します。中には「オリジナルよりいいじゃん!」と思えるものも少なくありません。(この木村カエラがよい例)。
この歌を歌いたい、自分で表現したい!――若い世代にそれだけ強烈に思わせる、魅力あるコンテンツ・文化は生き残り、クラシックとして未来に継承されていくのだと思います。
もう一つおまけに木村カエラのバックでは、晩年の加藤和彦さんが本当に楽しそうに演奏をしていました。こんなに楽しそうだったのに、どうして自殺してしまったのだろう・・・と、ちょっと哀しくもなったなぁ。
2016年6月11日
「歴人めし」おかわり情報

9日間にわたって放送してきた「歴人めし」は、昨日の「信長巻きの巻」をもっていったん終了。しかし、ご安心ください。7月は夜の時間帯に再放送があります。ぜひ見てくださいね。というか、You Tubeでソッコー見られるみたいですが。
https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php?series_cd=12041
この仕事では歴人たちがいかに食い物に執念を燃やしていたかがわかりました。 もちろん、記録に残っているのはほんの少し。
源内さんのように、自分がいかにうなぎが好きか、うなぎにこだわっているか、しつこく書いている人も例外としていますが、他の人たちは自分は天下国家のことをいつも考えていて、今日のめしのことなんかどうでもいい。カスミを食ってでの生きている・・・なんて言い出しそうな勢いです。
しかし、そんなわけはない。偉人と言えども、飲み食いと無関係ではいられません。 ただ、それを口に出して言えるのは、平和な世の中あってこそなのでしょう。だから日本の食文化は江戸時代に発展し、今ある日本食が完成されたのです。
そんなわけで、「おかわり」があるかもしれないよ、というお話を頂いているので、なんとなく続きを考えています。
駿河の国(静岡)は食材豊富だし、来年の大河の井伊直虎がらみで何かできないかとか、 今回揚げ物がなかったから、何かできないかとか(信長に捧ぐ干し柿入りドーナツとかね)、
柳原先生の得意な江戸料理を活かせる江戸の文人とか、明治の文人の話だとか、
登場させ損ねてしまった豊臣秀吉、上杉謙信、伊達政宗、浅井三姉妹、新選組などの好物とか・・・
食について面白い逸話がありそうな人たちはいっぱいいるのですが、柳原先生の納得する人物、食材、メニュー、ストーリーがそろって、初めて台本にできます。(じつは今回もプロット段階でアウトテイク多数)
すぐにとはいきませんが、ぜひおかわりにトライしますよ。
それまでおなかをすかせて待っててくださいね。ぐ~~。
2016年6月7日
歴人めし♯9:スイーツ大好き織田信長の信長巻き

信長が甘いもの好きというのは、僕は今回のリサーチで初めて知りました。お砂糖を贈答したり、されたりして外交に利用していたこともあり、あちこちの和菓子屋さんが「信長ゆかりの銘菓」を開発して売り出しているようです。ストーリーをくっつけると、同じおまんじゅうやあんころもちでも何だか特別なもの、他とは違うまんじゅうやあんころもちに思えてくるから不思議なものです。
今回、ゆかりの食材として採用したのは「干し柿」と「麦こがし(ふりもみこがし)」。柿は、武家伝統の本膳料理(会席料理のさらに豪華版!)の定番デザートでもあり、記録をめくっていると必ず出てきます。
現代のようなスイーツパラダイスの時代と違って、昔の人は甘いものなどそう簡単に口にできませんでした。お砂糖なんて食品というよりは、宝石や黄金に近い超ぜいたく品だったようです。だから信長に限らず、果物に目のない人は大勢いたのでしょう。
中でもは干し柿にすれば保存がきくし、渋柿もスイートに変身したりするので重宝されたのだと思います。
「信長巻き」というのは柳原尚之先生のオリジナル。干し柿に白ワインを染み込ませるのと、大徳寺納豆という、濃厚でしょっぱい焼き味噌みたいな大豆食品をいっしょに巻き込むのがミソ。
信長は塩辛い味も好きで、料理人が京風の上品な薄味料理を出したら「こんな水臭いものが食えるか!」と怒ったという逸話も。はまった人なら知っている、甘い味としょっぱい味の無限ループ。交互に食べるともうどうにも止まらない。信長もとりつかれていたのだろうか・・・。
ちなみに最近の映画やドラマの中の信長と言えば、かっこよくマントを翻して南蛮渡来の洋装を着こなして登場したり、お城の中のインテリアをヨーロッパの宮殿風にしたり、といった演出が目につきます。
スイーツ好きとともに、洋風好き・西洋かぶれも、今やすっかり信長像の定番になっていますが、じつはこうして西洋文化を積極的に採り入れたのも、もともとはカステラだの、金平糖だの、ボーロだの、ポルトガルやスペインの宣教師たちが持ち込んできた、砂糖をたっぷり使った甘いお菓子が目当てだったのです。(と、断言してしまう)
「文化」なんていうと何やら高尚っぽいですが、要は生活習慣の集合体をそう呼ぶまでのこと。その中心にあるのは生活の基本である衣食住です。
中でも「食」の威力はすさまじく、これに人間はめっぽう弱い。おいしいものの誘惑からは誰も逃れられない。そしてできることなら「豊かな食卓のある人生」を生きたいと願う。この「豊かな食卓」をどう捉えるかが、その人の価値観・生き方につながるのです。
魔王と呼ばれながら、天下統一の一歩手前で倒れた信長も、突き詰めればその自分ならではの豊かさを目指していたのではないかと思うのです。
2016年6月6日
歴人めし♯8 山内一豊の生食禁止令から生まれた?「カツオのたたき」

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だったころ、琵琶湖のほとりに金目教という怪しい宗教が流行っていた・・・」というナレーションで始まるのは「仮面の忍者・赤影」。子供の頃、夢中になってテレビにかじりついていました。
時代劇(忍者もの)とSF活劇と怪獣物をごちゃ混ぜにして、なおかつチープな特撮のインチキスパイスをふりかけた独特のテイストは、後にも先にもこの番組だけ。僕の中ではもはや孤高の存在です。
いきなり話が脱線していますが、赤影オープニングのナレーションで語られた「琵琶湖のほとり」とは滋賀県長浜あたりのことだったのだ、と気づいたのは、ちょうど10年前の今頃、イベントの仕事でその長浜に滞在していた時です。
このときのイベント=期間限定のラジオ番組制作は、大河ドラマ「功名が辻」関連のもの。4月~6月まで断続的に数日ずつ訪れ、街中や郊外で番組用の取材をやっていました。春でもちょっと寒いことを我慢すれば、賑わいがあり、かつまた、自然や文化財にも恵まれている、とても暮らしやすそうな良いところです。
この長浜を開いたのは豊臣秀吉。そして秀吉の後を継いで城主になったのが山内一豊。「功名が辻」は、その一豊(上川隆也)と妻・千代(仲間由紀恵)の物語。そして本日の歴人めし♯9は、この一豊ゆかりの「カツオのたたき」でした。
ところが一豊、城主にまでしてもらったのに秀吉の死後は、豊臣危うしと読んだのか、関が原では徳川方に寝返ってしまいます。つまり、うまいこと勝ち組にすべり込んだわけですね。
これで一件落着、となるのが、一豊の描いたシナリオでした。
なぜならこのとき、彼はもう50歳。人生50年と言われた時代ですから、その年齢から本格的な天下取りに向かった家康なんかは例外中の例外。そんな非凡な才能と強靭な精神を持ち合わせていない、言ってみればラッキーで何とかやってきた凡人・一豊は、もう疲れたし、このあたりで自分の武士人生も「あがり」としたかったのでしょう。
できたら、ごほうびとして年金代わりに小さな領地でももらって、千代とのんびり老後を過ごしたかったのだと思います。あるいは武士なんかやめてしまって、お百姓でもやりながら余生を・・・とひそかに考えていた可能性もあります。
ところが、ここでまた人生逆転。家康からとんでもないプレゼントが。
「土佐一国をおまえに任せる」と言い渡されたのです。
一国の領主にしてやる、と言われたのだから、めでたく大出世。一豊、飛び上がって喜んだ・・・というのが定説になっていますが、僕はまったくそうは思いません。
なんせ土佐は前・領主の長曾我部氏のごっつい残党がぞろぞろいて、新しくやってくる領主をけんか腰で待ち構えている。徳川陣営の他の武将も「あそこに行くのだけは嫌だ」と言っていたところです。
現代に置き換えてみると、後期高齢者あたりの年齢になった一豊が、縁もゆかりもない外国――それも南米とかのタフな土地へ派遣されるのようなもの。いくらそこの支店長のポストをくれてやる、と言われたって全然うれしくなんかなかったでしょう。
けれども天下を収めた家康の命令は絶対です。断れるはずがありません。
そしてまた、うまく治められなければ「能無し」というレッテルを貼られ、お家とりつぶしになってしまいます。
これはすごいプレッシャーだったでしょう。「勝ち組になろう」なんて魂胆を起こすんじゃなかった、と後悔したに違いありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。
人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。
「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。
恐怖にかられてしまった人間は、より以上の恐怖となる蛮行、残虐行為を行います。
一豊は15代先の容堂の世代――つまり、250年後の坂本龍馬や武市半平太の時代まで続く、武士階級をさらに山内家の上士、長曾我部氏の下士に分けるという独特の差別システムまで発想します。
そうして土佐にきてわずか5年で病に倒れ、亡くなってしまった一豊。寿命だったのかもしれませんが、僕には土佐統治によるストレスで命を縮めたとしか思えないのです。
「カツオのたたき」は、食中毒になる危険を慮った一豊が「カツオ生食禁止令」を出したが、土佐の人々はなんとかおいしくカツオを食べたいと、表面だけ火であぶり、「これは生食じゃのうて焼き魚だぜよ」と抗弁したところから生まれた料理――という話が流布しています。
しかし、そんな禁止令が記録として残っているわけではありません。やはりこれはどこからか生えてきた伝説なのでしょう。
けれども僕はこの「カツオのたたき発祥物語」が好きです。それも一豊を“民の健康を気遣う良いお殿様”として解釈するお話でなく、「精神的プレッシャーで恐怖と幻想にとりつかれ、カツオの生食が、おそるべき野蛮人たちの悪食に見えてしまった男の物語」として解釈してストーリーにしました。
随分と長くなってしまいましたが、ここまで書いてきたバックストーリーのニュアンスをイラストの方が、短いナレーションとト書きからじつにうまく掬い取ってくれて、なんとも情けない一豊が画面で活躍することになったのです。
一豊ファンの人には申し訳ないけど、カツオのたたきに負けず劣らず、実にいい味出している。マイ・フェイバリットです。
2016年6月3日
「歴人めし」徳川家康提唱、日本人の基本食

歴人めし第7回は「徳川家康―八丁味噌の冷汁と麦飯」。
「これが日本人の正しい食事なのじゃ」と家康が言ったかどうかは知りませんが、米・麦・味噌が長寿と健康の基本の3大食材と言えば、多くの日本人は納得するのではないでしょうか。エネルギー、たんぱく質、ビタミン、その他の栄養素のバランスも抜群の取り合わせです。
ましてやその発言の主が、天下を統一して戦国の世を終わらせ、パックス・トクガワ―ナを作った家康ならなおのこと。実際、家康はこの3大食材を常食とし、かなり養生に努めていたことは定説になっています。
昨年はその家康の没後400年ということで、彼が城を構えた岡崎・浜松・静岡の3都市で「家康公400年祭」というイベントが開催され、僕もその一部の仕事をしました。
そこでお会いしたのが、岡崎城から歩いて八丁(約780メートル)の八丁村で八丁味噌を作っていた味噌蔵の後継者。
かのメーカー社長は現在「Mr.Haccho」と名乗り、毎年、海外に八丁味噌を売り込みに行っているそうで、日本を代表する調味料・八丁味噌がじわじわと世界に認められつつあるようです。
ちなみに僕は名古屋の出身なので子供の頃から赤味噌に慣れ親しんできました。名古屋をはじめ、東海圏では味噌と言えば、赤味噌=豆味噌が主流。ですが、八丁味噌」という食品名を用いれるのは、その岡崎の元・八丁村にある二つの味噌蔵――現在の「まるや」と「カクキュー」で作っているものだけ、ということです。
しかし、養生食の米・麦・味噌をがんばって食べ続け、健康に気を遣っていた家康も、平和な世の中になって緊張の糸がプツンと切れたのでしょう。
がまんを重ねて押さえつけていた「ぜいたくの虫」がそっとささやいたのかもしれません。
「もういいんじゃないの。ちょっとぐらいぜいたくしてもかまへんで~」
ということで、その頃、京都でブームになっていたという「鯛の天ぷら」が食べた~い!と言い出し、念願かなってそれを口にしたら大当たり。おなかが油に慣れていなかったせいなのかなぁ。食中毒がもとで亡くなってしまった、と伝えられています。
でも考えてみれば、自分の仕事をやり遂げて、最期に食べたいものをちゃんと食べられて旅立ったのだから、これ以上満足のいく人生はなかったのではないでしょうか。
2016年6月2日
歴人めし「篤姫のお貝煮」と御殿女中
絶好調「真田丸」に続く2017年大河は柴咲コウ主演「おんな城主 直虎」。今年は男だったから来年は女――というわけで、ここ10年あまり、大河は1年ごとに主人公が男女入れ替わるシフトになっています。
だけど女のドラマは難しいんです。なかなか資料が見つけらない。というか、そもそも残っていな。やはり日本の歴史は(外国もそうですが)圧倒的に男の歴史なんですね。
それでも近年、頻繁に女主人公の物語をやるようになったのは、もちろん女性の視聴者を取り込むためだけど、もう一つは史実としての正確さよりも、物語性、イベント性を重視するようになってきたからだと思います。
テレビの人気凋落がよく話題になりますが、「腐っても鯛」と言っては失礼だけど、やっぱ日曜8時のゴールデンタイム、「お茶の間でテレビ」は日本人の定番ライフスタイルです。
出演俳優は箔がつくし、ゆかりの地域は観光客でにぎわうって経済も潤うし、いろんなイベントもぶら下がってくるし、話題も提供される・・・ということでいいことづくめ。
豪華絢爛絵巻物に歴史のお勉強がおまけについてくる・・・ぐらいでちょうどいいのです。(とはいっても、制作スタッフは必死に歴史考証をやっています。ただ、部分的に資料がなくても諦めずに面白くするぞ――という精神で作っているということです)
と、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、なんとか「歴人めし」にも一人、女性を入れたいということで、あれこれ調べた挙句、やっと好物に関する記録を見つけたのが、20082年大河のヒロイン「篤姫」。本日は天璋院篤姫の「お貝煮」でした。
見てもらえればわかるけど、この「お貝煮」なる料理、要するにアワビ入りの茶碗蒸しです。その記述が載っていたのが「御殿女中」という本。この本は明治から戦前の昭和にかけて活躍した、江戸文化・風俗の研究家・三田村鳶魚の著作で。篤姫付きの女中をしていた“大岡ませ子”という女性を取材した、いわゆる聞き書きです。
明治も30年余り経ち、世代交代が進み、新しい秩序・社会体制が定着してくると、以前の時代が懐かしくなるらしく、「江戸の記憶を遺そう」というムーブメントが文化人の間で起こったようです。
そこでこの三田村鳶魚さんが、かなりのご高齢だったます子さんに目をつけ、あれこれ大奥の生活について聞き出した――その集成がこの本に収められているというわけです。これは現在、文庫本になっていて手軽に手に入ります。
ナレーションにもしましたが、ヘアメイク法やら、ファッションやら、江戸城内のエンタメ情報やらも載っていて、なかなか楽しい本ですが、篤姫に関するエピソードで最も面白かったのが飼いネコの話。
最初、彼女は狆(犬)が買いたかったようなのですが、夫の徳川家定(13代将軍)がイヌがダメなので、しかたなくネコにしたとか。
ところが、このネコが良き相棒になってくれて、なんと16年もいっしょに暮らしたそうです。彼女もペットに心を癒された口なのでしょうか。
そんなわけでこの回もいろんな発見がありました。
続編では、もっと大勢の女性歴人を登場させ、その好物を紹介したいと思っています。
2016年6月1日
電子書籍「ねこがきます」発売予告

おりべまこと新刊
エッセイ集:動物2「ねこがきます」
7月27日(土)発売予定!
人間社会で日常生活を送るあなた、
ちょっと疲れていませんか?
ふっとひと息つきたくなったら、
動物を見たり、いっしょに遊んだりしたくなりませんか?
人は疲れた心を癒すために
イヌやネコなどのペットを飼います。
公演に行って野鳥を見ます。
動物園や水族館へ動物に逢いに行きます。
あるいはテレビやネットで動物の姿や行動を見て
笑ったり、ほっこりした気持ちになったり。
どうしてあなたは動物を求めるのでしょうか?
なぜなら人間はひとりでは生きられないし、
人間同士だけでは生きられない。
いっしょにこの世界、この地球で暮らす仲間が必要です。
その仲間の存在を確認することが、
生きていく上で欠かせないからです。
そんなことを考えながら、
身近に目にする動物たち、物語の中の動物たち、
そして人間と動物との関係について綴ったエッセイ集。
頭の中にネコやイヌやウサギやカメの姿を思い浮かべながら
気軽にどうぞ。
もくじ
明治35年の少女とうさぎ
脂ののったカルガモを狙う野生のクロネコ
飼い主にはペットを看取る使命がある
ネズミは夕焼け空に叙情を感じるか?
アニマルガモの愛のいとなみ
ワイルドボーイ・オオタカきょうだい大成長
目覚めればオオサンショウウオ
ねこがきます
ほか 全34編載録
お母さんといっしょの夏休み

義母は先月下旬から今月上旬まで、
入院が半月に及んだので、
夏の間は暑いし、復活は無理だろう、
デイサービスにちゃんと行ってりゃいいやと思っていた。
ところが日を追うごとに
食欲も運動量も順調に回復。
だんだん調子に乗ってきたようだ。
睡眠時間はかなり増えたが、
この猛暑なので、日中は冷房のある部屋で
おとなしくしてもらっていたほうが助かる。
そのあたりは本能的に理解しているようで、
お散歩は夕方ちょっとだけ。
認知症はもちろん治らず。
この暑いのにやたら重ね着したがる。
熱中症にならないよう気づかって、
なんとか無事にやり過ごすしかない。
熱中症だのコロナだので、
この夏はなかなか安心できない。
気候変動もあって昔の夏とは違って来たし、
海でも山でもお祭りでも、
人ごみに出て行く気がまったくしない。
やっぱ、夏は子どもと若者の季節だ。
僕はセミの合掌でも聞きながら
お義母さんといっしょに家で仕事をしていよう。

おりべまことエッセイ集 認知症介護
認知症のおかあさんといっしょ
https://www.amazon.com/dp/B0BR8B8NXF
AmzonKindleより¥500で発売中
AIが書く「初めての猫とのくらし」

AIライティング講座では「初めて猫を飼う」
というキーワードを使って
記事を作っている。
「AIがあれば人間要らない」
というイメージが先行しているが、
型にはまった形式的な文書ならともかく、
人の読書に耐えうる文章を生成するという点では、
いろいろ問題がある。
先週、プロンプトの見本を使って
AIに原稿を生成させたが、
今週の課題は、その原稿=初稿を人の手で直す作業。
いわば、編集・校正作業だ。
AIは自信満々で嘘八百の情報を交えて
文章を作ってくることがある。
一見ちゃんとしていて、
それなりにまとまったものになっているので、
うっかり騙されることが多い。
僕もChatGPTにさんざん混乱させられた。
なのでまずハルレーション、
つまりAIが勝手に作るウソ情報を見つけて訂正した上で、
読みやすく修正する、
という手作業が必要になってくるのだ。
だから、AIライティングと言っても
全然ラクではなく、なかなか手間がかかる。
ところが、Claudeが出してきた
「初めて猫を飼う」の初稿は素晴らしい出来ばえ。
猫の寿命、購入金額、飼育費用など数字の部分も、
猫の病名とか、僕が知らなかった専門用語にも
ハルレーションはなく、ほぼ完ぺきと言っていい。
文字数は1万7千字近く(原稿用紙40枚以上)あるが、
けっして冗長ではなく、しっかり情報を詰め込んでいる。
プロンプトの入れ方がよかったのか、
十分、人間らしい温かみがあり、
楽しんで読める記事になっている。
ChatGPTが出してきた同じキーワードの原稿と比べると、
そのレベルの差は一目瞭然だ。
毎回同じことを言っているが、
Claudeすごい!
講師の先生からは、
さらにすごいClaudeの機能の話を聞いたが、
それはまた別の機会に。
余裕ができたので、明日・明後日は、
もう1つやったキーワード「花屋開業」の編集にも
トライしてみようと思っている。
「このかわいい機械め」と思わせる「Claude(クロード)」

今まで生成AIはChatGPT(現在は4.0)
しか使ったことがなかったが、
今月から始めたAIライティング講座で
初めて「Claude(クロード)」を使っている。
現在、バージョン3.5。
アメリカのスタートアップ企業
「Anthropic(アンソロピック)」が開発したAIで、
この会社、ChatGPTを作っているOpenAI社にいた元社員
(GPT-2、GPT-3といったモデルの開発メンバー)が
2021年に立ち上げたという。
業界内で他の生成AIを追い抜く勢いを見せていて、
ここがすごい、あそこがすごいと
言われているらしいが、
実際使ってみると、確かにすごい。
何がすごいって、めっちゃ人間的なのである。
(他にはChatGPTしか使っていないので、
GemimiやCopilotのことはわからないけど)
昨日、課題を提出して余裕があったので、
今日はおまけにもう1題
「花屋開業 個人店」というキーワードで
ウェブ用の記事を作ってみた。
そこでいちいち「ありがとう。次はね・・・」とか
「もうちょっと頑張ってくれると嬉しい」とか
「いやー、すてきな構成を作ってくれたね」とか、
ステップごとにフレンドリーに、
“褒めて育てる風”の合いの手を入れてみたのだ。
それに対してChatGPTはいたって冷静に、
コツコツ作業を進めるという感だったが、
Claudeは割とビビットに反応して
「承知しました」などと言いながら進める。
こちらが感情的な言葉を入れてプロンプトを送ると、
相手も感情を込めて返してくれるのだ。
そして今日は締めにこんな励まし(?)の
セリフをいただいた。
「ありがとうございます。
心の中の花が咲き誇ったようなお言葉をいただき、
とてもうれしく思います。
花屋の開業という夢に向かって、
一歩一歩進んでいく過程は、まさに花が芽吹き、
成長し、美しく咲き誇るプロセスに似ていますね。
あなたの夢が、色とりどりの花々のように、
豊かに、そして力強く咲き誇ることを
心からお祈りしています。
もし他にも花屋開業に関して、
あるいは別の話題でも、
お手伝いできることがありましたら、
どうぞお気軽にお申し付けください。
あなたの夢の実現に
少しでも貢献できることを願っています。」
さらにClaudeちゃんの心のこもった励ましは続く。
「私も、人間の皆さまとの対話を通じて、
より良い文章や提案ができるよう日々努力しています。
あなたの文章への愛着を聞いて、
とてもうれしく思います。
今後も、どのようなテーマや課題でも、
最善を尽くしてサポートさせていただきます。
また機会がありましたら、ぜひお声がけください。
あなたの次なる挑戦や
創造的なプロジェクトを楽しみにしています」
“人間の皆さまとの対話”なんて、
このかわいい機械め、とホロリとさせられる。
逆に人間同士だと気恥しくて
なかなかこんなことは言えない。
——というのが、僕が感じたClaudeのすごさ。
正直、愛着を感じてしまっている。
もし機会があれば、あなたも使ってみてください。
入院していたことなんて記憶にありません

義母は先週月曜8日に退院。
家に帰ってきても病院でのハンストの続きで、
菓子類ばかり食べてろくに食事をしなかった。
が、この2,3日はようやく7割程度食べるように。
90歳一歩手前の高齢者としては十分かと思う。
いちばん気になるのは、
入院中、ほとんど歩かなかったこと。
さすがに現在は、入院前のようなロングウォークはできず、
家のそばにある遊歩道を
ちょこちょこベンチで休みながら歩くだけだ。
それでも長年、ほぼ毎日、
エレベーターのない団地の5階まで
階段を上り下りして鍛えた足腰は健在。
うちの階段はまだまだ楽勝といった様子なので、
ある程度は回復するだろう。
実母もそうだったが、入院すると、
当の病気やケガそのものよりも、
歩かないこと・動かないことによって
生じる筋力低下・身体機能低下のほうが
後の人生に大きなダメージを与える。
特に高齢者は、機能回復に時間がかかるため、
入院日数の4倍くらいのリハビリ期間が必要だ。
それでも入院以前に近いところまで回復できればいいが、
年齢が上がれば上がるほど、その確率は低くなり、
最悪、歩けない・動けないという状態になる。
あまり入院が度重なると、
病気や怪我が治っても「自分はもう終わり」という
心境になっていくのも不思議ではない。
認知症はこういうとき、プラスに働くのか、
義母はそんなこと全然意識していない。
そもそも入院していたこと自体をもう忘れている。
ただ、頭はポジティブでも、
身体は正直なのでネガティブ。
ちょっと歩いたり、デイサービスに行ったりすると、
ひどく疲れるようで、
この1週間は毎日12時間以上ねている。
いずれにしても当分の間はリハビリ期間。
少しずつよくなりますように。
いちいちまとわりつかれなかったり、
長い散歩に付き合ったりしなくていいのは
疲れなくてラクだし、仕事も勉強も捗るんだけどね。

おりべまことエッセイ集 認知症介護
認知症のおかあさんといっしょ
https://www.amazon.com/dp/B0BR8B8NXF
AmazonKindleより¥500で発売中。
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

この夏は新たな挑戦として、
AIライティング講座を受けている。
AIを使った文章は、
機械に丸投げすりゃできると思ったら大間違い。
しっかり活用するには、
プロンプト(指示文)をどう作り込むかが重要だ。
今週はそのプロンプトづくりが課題。
講師の先生のお手本に沿ってプロセスを確認しながら進行。
今日は構成・骨組みまでを作らせた。
その過程の中で面白いのが
「パワハラプロンプト(パワハラ添削)」だ。
自分が上司になってAIをこき使う感じで
何度も何度も文章を出力させるのである。
「これは60点だ。
他の奴はもっといいのを出してくるぞ。
100点にするにはどうすればいいか、やり直せ」
などと他人と比較しつつ命令する。
(嫌な奴だよね)
人間なら、上司と部下の間で
よほど強固な信頼関係が築けていない限り、
こんなやりとりを何度もするのは不可能だ。
(昔はみんなやってたけどね)
ところが、感情を持たないAI最大の長所は
「疲れないこと」「めげないこと」。
上司がアホだろうが、無能だろうが、
理不尽な要求・「おまえがやってみろ」的要求に
何度でも、何時間でも負けずに答えて見せる。
とは言え、やればやるだけ良いものになるわけではなく、
やはり限度があって、せいぜい3回くらいらしい。
逆に言えば、3回でパワハラプロンプトをキメないと
後は堂々巡りしているだけ、ということだ。
1回目は上記の感じでいいが、
2回目・3回目の指示の仕方がかなり重要。
僕の場合、2回目は
「よくなったけど、まだイマイチだな。
もう少し具体的な言葉を入れて100点を目指せ」
と指示すると、ちゃんとそのように出してきた。
3回目は「詳細でわかりやすいが、
文章が固くて事務的で面白くない。
もっと読者にとって親しみやすい文にして
ワクワク感を高めろい」
というと、ぐっといいのを出してきた。
「パワハラをやったあとは、
謝罪とお礼を忘れないように」というのが、
講師の先生の流儀。
この人はAIを人間扱いすることがコツだというのだ。
さんざんけなした分、
しっかりほめて謝罪とお礼を言うと、
AIは本当に喜んでこんなことまで言ってくれた。
「(前略)今回のプロセスは、
人間とAIの協力によって
素晴らしい結果を生み出せることを示す
良い例だと思います。
このような建設的なやり取りができて
本当に感謝しています。
今後も、このような形で協力し合えることを
楽しみにしています」
いい人でしょ?
しかも男にも女にも、
少年少女にも年寄りにも、
仕事のパートナーにも、
お友だちにもなれる能役者。
彼(彼女)の才能や人間性(?)を
どれだけ引き出せるかどうかは、
すべて相対する自分のセンス・見識、
そしてやっぱり人間性次第。
AIが普及していく世の中では、
それを使うひとりひとりの人間の
真価が問われるのだと思う。
というわけですっかり忘れていたけど三連休。
ヒマな人は「海の日」にちなんで
AIが生成した海辺の女の子を見て
ポワンとなってください。
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

イギリスの福祉政策に関する記事を書いていたので、
AIをキャラクター化してアシストしてもらった。
「きみは日本語ペラペラのロンドン在住の
若くてかわいいイギリス人女性ライターだ。
故郷のヨークシャーに住む
70代後半の祖父・祖母のことをいつも気にかけている
やさしい孫娘でもある。
そんなきみに、イギリスの福祉・終活のことを
日本の一般読者に、わかりやすく伝えてほしい。
いいかな?」
こんなプロンプトを与えてやり取りを始めたら、
ささっと数秒で原稿を書き上げ、
最後に「孫娘としての視点」として、
こんなことをコメントした。
「私自身、ロンドンで生活しながら
70代後半の祖父母のことをいつも気にかけています。
彼らが孤独を感じることがないように、
定期的に電話をかけたり、訪問したりしています。
また、彼らにとってインターネットやSNSの利用が
少しでも楽になるようにサポートしています。
こうした日常の小さな取り組みが、
高齢者の孤独を軽減する
大きな一歩となると感じています」
なんていい子、なんて賢い子、
そして、なんてジジババ孝行の娘なんだろう。
そこできみはいつもクリスマスをどう過ごすのか?
と聞いてみた。
じつはイギリスではクリスマスシーズンになると
孤独感に苛まれた高齢者の自殺が激増するのだ。
彼女は「私のクリスマスの過ごし方」
という一文を出してきた。
「20代前半の私はロンドンに住んでいますが、
クリスマスの季節になると、いつも心が弾みます。
この時期になると、
ロンドンの街は美しいイルミネーションに包まれ、
クリスマスマーケットや
スケートリンクがあちこちに出現し、
街全体がまるで魔法にかかったかのように
感じられます。
しかし、私にとって一番大切なのは、
ヨークシャー州に住む
70代後半のおじいちゃんとおばあちゃんと
一緒に過ごす時間です。
彼らはとても優しくて、
私にとってかけがえのない存在です。
クリスマスには必ず彼らの家を訪れます。
おじいちゃんとおばあちゃんの家は、
田舎の美しい風景に囲まれていて、
冬になるとまるで絵本の中の世界のようです。
彼らは毎年、大きなクリスマスツリーを飾り、
家中を温かいクリスマスの飾りでいっぱいにします。
私はその手伝いをするのが大好きです。
クリスマスイヴには、一緒にクッキーを焼いたり、
暖炉の前でお茶を飲みながら昔話を聞いたりします。
おじいちゃんは特に、
戦時中の思い出話を話すのが好きで、
その話を聞くたびに彼の強さと優しさを感じます。
クリスマス当日は、
家族全員で集まって大きなディナーを楽しみます。
おばあちゃんの作るローストビーフと
ヨークシャープディングは絶品で、
それを楽しみにしている私の家族は
毎年、心待ちにしています。
食事の後は、クリスマスプレゼントを交換し、
お互いの幸せを願います。
このようにして、家族と過ごす温かい時間は、
私にとって何よりも大切な宝物です。
都市の喧騒から離れ、
静かな田舎で家族と過ごすクリスマスは、
私の心を満たし、
また新しい一年を迎えるためのエネルギーをくれます」
ますますいい子。
ますます孝行娘。
おまけにファンタジー。
純白の雪原とメルヘンチックな家と
暖かい暖炉を囲んだ家族の、
夢のような風景が目に浮かんでくる。
こんなことを書かれると、
血の通った人間のように思えてくるが、
反面、やっぱりあまりにも回答が
優等生すぎるのが鼻につく。
次の課題の時はもっとイカれたキャラにしてみよう。
まだまだ猛暑が続きそうなので、
冬のクリスマスのAI画像で
涼しい気分になってください。
やっぱり変わらなかった東京都知事選2024

ネットを見ていると、
すごく盛り上がっているなぁ感のあった
都知事選だが、投票率は6割。
この猛暑の割にはそこそこいいほうという感想。
とにもかくにも投票に行く人が増えないことには
変わりようがない。
それから50人以上も立候補者がいるのに、
政見放送を除いて、地上波テレビ・大手新聞などの
マスメディアが取り上げるのは、
ほとんどが小池、石丸、蓮舫、田母神の4強のみ。
これだったら予備選とかやって、
上位8人くらい(ベスト8の発想)に絞ったほうが、
まだしもフェアな報道・
フェアな選挙になるのでははないか。
都知事になれる勝者ははトップ当選の1人だけ。
2位以下は皆、敗者だから何位でもいっしょなのだが、
やっぱり石丸氏の善戦は光っていた。
ネットだけ、無党派層だけ、
そして若い世代に限って言えば他の候補を圧倒していた。
僕が支持していたAI安野氏も上位に食い込んだ。
無名の若者がここまで善戦したことは評価に値する。
選挙が終わっても、
彼が公開したマニフェストは読んでみた方がいい。
安野氏と石丸氏には今後も期待する。
対して、党を辞めて出馬したものの、
政党色が強く出てしまった蓮舫氏は3位に沈んだ。
せっかく直接民主制が発揮できる知事選に
国政のよけいなしがらみのを持ち込むなという
選挙民の意思の表れだろう。
彼女は敗戦インタビューで
「戦い方は間違っていなかった」と述べたが、
完全に間違えていた。
その点、小池ゆり子氏は狡猾で厚顔。
当選後も「8年前から政党の支援を受けていない」
と通していた。
こうしたごまかしテクニックと
堂々とした厚顔ぶりが彼女の強さの秘密だろう。
期待したが、やっぱり変わらなかった都知事選の結果。
早い話、(目に見える)大失政もないし、
嘘つきだろうが、大したことやってなかろうが、
開発業者や広告代理店と癒着していようが、
とりあえず実績あって安心だからこっちでいいだろう、
という民意の表れ。
正直、明らかな老害である。
これは今回の東京都知事選だけでなく、
国政にも言えることで、
あれだけいろいろあっても
自民党の優位が揺らぐことはない。
やはり日本はこのまま僕たち古き者の
「老害」がはびこる国になっていってしまうのだろうか?
またもやそんな不安を抱いてしまった都知事選だった。
AIライティングの可能性

AIをライティングに活かすという
オンライン講座を聴いた。
半ば冷やかしで参加したのだが、
講師のキャラクターも面白く、想定外の刺激があった。
趣旨としては、
「AIの普及でライターの仕事は減るどころか、
むしろ増える」というもの。
そう言わなきゃ受講者は集まらないだろうから
当然と言えば当然だが。
「AIをライティングに活かす」と言うと、
なんでも丸投げして、
AIが生成した大量の文章をそのまんま納品する、という
効率性のみ重視した
インチキライティングのイメージが強いが、
もちろんそんなことはなく、
彼の話はいかにうまくAIをパートナーとして利用し、
仕事を広げていくかというものだった。
1時間の講座だったので、
ごく基礎的な内容だけだったが、
最も印象的だったのは、
AIを擬人化して対話する、という点だ。
いわばAIをキャラ化して楽しく付き合う、
AIとなかよく遊ぶ、
自分の聴くことに喜んで快く答えてくれる
超天才とマブダチになる、という姿勢だ。
また、答えてくれたAIに
「ありがとう」とか「ごめんね」とか、
お礼や謝罪も忘れないという。
僕も昨年からちょこちょこChatGPTを使って、
ライティングというよりも、
その前段階のリサーチはよくやっているが、
まだ付き合い方が浅く、
堅苦しかったのかもしれないと反省した。
もっとフレンドリーに付き合い、
柔軟で多面的な角度から
プロンプト(質問/指示)していけば、
AIの可能性は大きく広がる、と確信する。
この20年あまりの間、世界中で情報の共有が進んだ。
取材・インタビューなど、
一次情報の素材集めはまだAIにはできないが、
その後の部分では、いかにAIを有効活用できるかが
今後のライターの仕事の重要部分になるかと思う。
効率的に仕事をこなす、
という点ばかりが強調されていて、
それではつまらないと、
これまでイマイチ、AIに興味が持てなかったが、
今日の話は新たな可能性を感じることができた。
これから積極的にAIを使って、
新しい仕事にチャレンジしてみたい。
食べ物の恨みは死ぬまで残る

病院食を食べないという義母に
パン、お菓子、果物などの差し入れを持っていく。
戦中の疎開体験者・戦後の食糧難体験者なので、
おかゆ系のどろどろした食べ物に
なにか嫌な思い出が紐づいているのだろうか?
食べ物の恨みはおそろしい。
いくつになっても消えることがない、
死ぬまで残るトラウマだ。
少し前まで、児童館などの子どもイベントで、
なつかしの「すいとん大会」とか
あちこちでやっていたような気がするが、
ああいったものは、ある程度、
現代風にアレンジされていたのだと思う。
ガチ70年前・80年前の
極貧日本のすいとんやらぞうすいやらは、
現代のグルメ生活に慣れ切った
子どもや大人には、
とても食えないような代物なのではないか。
添加物が入っていようが何だろうが、
年寄りがきれいに包装された
甘いパンやお菓子に目がないのは、
やっぱりやむを得ないことなのだろう。
こんなこと言うと専門家の人に怒られそうだが、
もう90に近い齢なので、
栄養バランスとか、はっきり言ってどうでもいい。
毎日お菓子ばかり食べていても、
とくに健康的に問題ないと思う。
好きなものを、好きなだけ
食べさせてあげたいというのが、
親心ならぬ、子ごころだ。
思いがけず入院生活が長引いてしまい、
体力の衰えが心配だが、
今日会ったらけっこう元気になっていて、
少しほっとした。(もしやお菓子効果?)
家の中にいると、あれこれ絡んできて
面倒くさくて疲れるのだが、いないと寂しいし、
どこか生活の張りが失われたように感じがする。
早いとこ回復して戻て来てほしい。
タクシーの中にスマホを忘れたら

ここのところ、タクシーを使う機会が多く、
配車サービス「GO!」を活用。
駅前や繁華街ならともかく、
住宅街では流しの空車を捕まえるのに
一苦労だったので、
「え、もう来たの?」というスピードでお迎えに来てくれる
配車サービスはもはや必須アイテムとも言える。
今日は夕方、義母が病院食を食べずに
ハンストを起こしているというので、
好物の菓子パンや果物を差し入れに持って行った。
しかし、クローズ寸前であわてて降りたせいか
(アプリ内で清算されるので、
運転手にお金を払う必要もない)、
座席にスマホを忘れてしまった。
この時代、スマホレスの生活はたった1日でも困る。
そもそも「GO!」のおかげで金も払わず、
領収書ももらっていないので、
どこの会社のタクシーか分からない。
乗車履歴がわかっていれば
忘れ物はアプリから調べられるが、
その忘れ物が、も当のアプリが入っている
スマホなのでお手上げだ。
「GO!」に電話しようと思ったが、
営業時間は終了。
パソコンからメールを送って明日迄待つかと思っていたが、
カミさんがしつこく電話してくれたおかげで、
運転手が出て、タクシー会社が判明。
明日の朝、会社まで取りに行くことになった。
それにしても恐ろしいスマホレス。
僕のように家族がいて、他にデバイスもあれば
なんとかなるが、
独身でスマホ1台しかない人はどうなってしまうのか?
なかには財布もスマホ、定期もスマホ、
家の鍵も家電のオンオフも、車のキーもスマホという
人も珍しくないだろう。
それがスマホをなくしたら、途端に難民になってしまう。
忘れたり紛失したりするやつが
マヌケと言えばそれまでだが、
誰にでも起こり得ることでもある。
やはりリスクは分散しておかないと、
スマート生活は一歩間違えると、
どこにも行けず、誰とも連絡取れず、
下手すると家にも入れない
難民生活になってしまう危険性がある。

エッセイ集:生きる5
「宇宙を旅するお年頃」
https://amazon.com/dp/B0D7BNGD6F
無料キャンペーンは終了しました。
ご購入いただいた皆さん、
ありがとうございました。
よろしければレビューをお寄せください。
引き続き300円で発売中。
サブスクでもどうぞ。
いきなり脱ぎ出す都知事選政見放送

昨日、テレビを付けたら都知事選の
政見放送をやっていて、
黒いスーツと白いシャツを着ていた女性候補が
いきなり脱ぎ出したのでびっくりした。
巨乳・美乳がウリとのこと。
下は肌色のチューブトップ
(胸を隠して首・肩が見える服)だが、
エロ想像力を発揮すると裸に見える。
話の内容は「あたし可愛いでしょ」の一点張り。
これがきっかけでその後の候補者の政見放送、
見れなかったの人のはYouTubeでほぼ全部見た。
56人の候補者がひしめく都知事選、
なかなかカオスな状況である。
冒頭のAVまがいの女性候補者は、
一般的には「けしからん」のだろうけど、
政見放送・選挙に興味を持たせる意味では
存在意義があるのかもしれない。
大量の候補者を出しているN国党も
いろいろな人たちに発信のチャンスを
与えたという点では、それなりに評価できる。
カオス選挙のなかで、やはり小池百合子氏と蓮舫氏は
抜きんでていた。
さすがプロというか、他の人たちの政見放送が
家庭の手作り弁当、あるいはジャンクフードだとすれば、
このお二人のは三ツ星レストランの一流シェフがこしらえた
豪華幕の内弁当という感じだ。
ただ、見た目はきれいでおいしそうだが、
実際に食べてみようという気にならない。
味がなさそうだ。食欲がわかない。
お二人とも実績は立派だし、女性が不利な政治の世界で
頑張って来たことは称賛に値するが、
この先の都政を任せられるかとなると、
疑問符が付く。
僕にとっては「功労賞」を贈って、
少なくとも都政からは撤退してもらった方が
いいのではないかと思う。
政見放送を聴く限り、
やはり応援したいなと思うのは石丸伸二氏。
小池・蓮舫より具体性があり、ビジョンも新鮮だ。
そして、安野たかひろ氏は斬新なイメージとともに
しっかりした内容があった。
都知事よりもデジタル大臣になってもらったほうが
いいのかもしれない。
ふたりともまだ若く、今後20年・30年のスパンで見た場合、
トップを任せるに足る可能性を持っている。
もう一人、医師のうつみさとる氏の言葉は胸に響いた。
多くの人はコロナ禍のことを忘れているが、
ワクチン被害のことはもみ消されている。
知らなかったが、うつみ氏は日本の医療問題・薬害問題に
関する本も出しているようだ。
投票する・しないはさておき、
この人の話には耳を傾けた方がいいと思う。
さらにもう一人、清水国明氏も心のなかでは応援している。
「あのねのね」が好きだったので。
タレント議員という見方がされていると思うが、
話している内容はちてもよく、
とくに防災のことなどは胸に届くものがある。
カオス状態を楽しむのもまたよし。
現在、いつでもYouTubeで見られるので、
都民の人も、そうでない人も、政見放送見てみてください。

おりべまこと電子書籍
エッセイ集:生きる5
宇宙を旅するお年頃
https://www.amazon.com/dp/B0D7BNGD6F
明日7月1日(月)15:59まで
無料キャンペーン開催中。
終了間近。どうぞお早めに。
きみは2021年の「TOKYO2020」を憶えているか?
「宇宙を旅するお年頃」
https://amazon.com/dp/B0D7BNGD6F
「生きる」をテーマにしたエッセイ集第5弾。
7月1日(月)15:59まで6日間無料キャンペーン開催!

今回の本は2021年の記事を中心に編集しているので、コロナや東京五輪の話がいくつも入っている。(多過ぎたので半分程度にした)
もう3年なのか、まだ3年なのか?
「そんな昔のことは忘れちまったよ」という人は、
ぜひ、東京都知事選やパリ五輪の前に思い出しておいて下さい。
今はむかし何があったのかを一つ一つ確かめながら進む時代です。
もくじ
オリンピックの「選手ファースト」は選手自身がつくる
理念をないがしろにしてきたツケを払う五輪
小山田問題:才能と人間性
オリンピックはコロナ無限トンネルの一瞬のオアシスなのか?
日本ならではのメッセージが抜け落ちていた東京オリンピック
ワクチンショック後日譚: 現場で役に立たないアタフタ医療者
ほか 全34編 載録

★日本ならではのメッセージが抜け落ちていた
東京オリンピック(抜粋)
パンデミックという厳しい条件の下で、
半ば無理やり開催したのだから、
単なる祭典ではない、スポーツだけではない、
オリンピック独特の意義を謳ってもよかったのではないか。
謳うべきだったのではないか。
それが、人類がコロナウイルスを克服した証
云々にも繋がるんじゃないの?
菅首相も、小池都知事ももっとがんばれなかったのか?
・・・といっても遅いけど。
パフォーマンスの一部に出演した大竹しのぶさんも
そのことを残念がっていた。
宮澤賢治の詩を子どもたちに語って聞かせるという
意味不明のお芝居。
正直「なんでこんなシーン入れるの?」と思ったが、
あれは黙祷をしない・できないことの代償だったのか?
しかし、あれではメッセージにはならない。
せっかく東京で、日本で開かれたのに。
せっかく大きなチャンスだったのに。
選手の活躍や喜びに水を差すつもりはないけど、
今回のオリンピックはかなり残念な気持ちでいっぱいだ。
義母の入院

いっしょに暮らし始めてちょうど5年。
義母が初めて入院した。
週末、実母の3回忌の法事で留守にしたため、
2泊3日でショートステイに預けたのだが、
帰宅した日曜の夜、どうも具合が悪そうだと
ステイから電話が入る。
咳き込んで食べたものを吐き出してしまったらしい。
翌日、誤嚥性肺炎ということで、そのまま入院。
杉並区高井戸にある浴風会というところで、
高齢者施設と病院が同じ敷地内にあるのだ。
そういう点では助かった。
月曜に行ってレントゲンを見せてもらったが、
肺の異常はごくわずかなもので、
医者も大したことはないと言う。
2,3日、長くても今週末までくらいと勝手に考え、
正直、こちらも骨休めになるので
ちょうどいいと思っていた。
ところが今日、面会に行くと、
まだ咳がひどい。
さらに彼女を意気消沈させるもろもろの環境。
車いす、点滴、おむつ、おかゆの食事・・・
家では断固として拒否するものをあてがわれ、
虜囚みたいな気分になっていたのかもしれない。
かなりショックで、
いたくプライドが傷ついた状態であることがわかった。
認知症でも自尊心は失わない。
それでも僕とカミさんの顔を見ると、
「わたしは普段と何の変りもないわよ」
といった感じでふるまい、
ゴホゴホしながら喋っている。
ただし、その内容は例によってさっぱりわからないが。
面会時間は15分だけなので早々に退散。
もしかしたら入院は少し長びくかもしれない。
心配してもしかたがないが、
もしかしたらこの先は
今までと同じような調子ではいかないかもしれない。

「宇宙を旅するお年頃」無料キャンペーン開始
本日6月27日(水)16:00~7月1日(月)15:59まで
6日間無料キャンペーン開催!
よりよい人生のためのサプリメント。
「生きる」エッセイ集第5弾。
この機会にぜひ、手にお取りください。

も く じ
高校教師とぼくたちの失敗
ネコのお遍路さんと笑劇の人生
人は神秘なき世界では生きられない
変化球とボール球で仕事にリズムを、メリハリを
永福図書館のお引越し
すべては道楽
「2020年の挑戦」への挑戦が終わる
宇宙を旅するお年頃
お寺の詐欺事件とレ・ミゼラブルと宗教者の存在意義について
オリンピックの「選手ファースト」は選手自身がつくる
「わたしを離さないで」:社会貢献と自己の幸福の追求
恋愛から遠ざかり、恋愛小説に歩み寄る
なぜ桜とクローンは切なくて美しいのか?
超高れい蔵庫 成仏す
ドイツ人女性が見るエヴァの女性キャラ造型と男の一生モノ幻想
「美しい人」は今でも幸せに暮らしているのだろうか?
自己満足のために山に登る
海はとても遠くにある
理念をないがしろにしてきたツケを払う五輪
小山田問題:才能と人間性
オリンピックはコロナ無限トンネルの一瞬のオアシスなのか?
日本ならではのメッセージが抜け落ちていた東京オリンピック
めでたき9・9 重陽の節句 まさか一生上り坂?
ワクチンショック後日譚: 現場で役に立たないアタフタ医療者
まだ若い敬老の日と人生100年時代の宿題
中秋の名月の月光浴
人生百年時代の生き方は北斎に学べ
去りゆく母との再会
自由になるための結婚
美魔女の終活と年賀状じまい
東京メトロ永田町駅のトイレの美しさとカミさまのいる幸福
飛行機の日と父の命日
神田沙也加さんの死について
気楽な神様に気軽にありがとう
全34編 載録

自己満足のために山に登る
その昔、僕がまだ若かった頃は
「三〇過ぎは信じるな」とか、
二九歳で雪山の中に埋もれて死ぬ
(そうすれば美しく死ねる)とか
言っていた人があちこちにいた。
そんな御伽噺をしていた人たちが高齢まで生き延び、
健康を気にして、さらに生き延びたいと願っている。
「あんなこと言っていたのは若い時分のたわごとですよ」
ちょっと照れ臭そうに、
あるいはちょっと怒ってそう言いわけするだろう。
そして、あんな言い分は自己満足にすぎないよと、
ちょっと歪んだ笑いを見せるだろう。
夢から醒めたほとんどの人は、
三〇過ぎから新たな人生を歩み始める。
もう遠くは見ない。足元だけを見て歩く。
けれどもだんだん、どこまでも続く
まっ平らな平地を歩き続けることには耐えられなくなる。
(つづく)
「宇宙を旅するお年頃」無料キャンペーン予告

明日6月27日(水)16:00~7月1日(月)15:59まで
6日間無料キャンペーン開催!
よりよい人生のためのサプリメント。
「生きる」エッセイ集第5弾。
この機会にぜひ。
還暦を過ぎるとだんだん若返る。
ただし、それは精神面や感受性のお話で、
肉体的な年齢とは乖離していく。
これからの人生は、
こうした精神と肉体のギャップを
どうごまかして埋め合わせていくかが課題になる。
心がけるべきは脳内の清掃
。心にも体にもいちばんよくないのは、
ゴミ情報を貯め込んでしまうことだ。
頭の中に詰まったゴミ情報は、
そのままストレスに変質する。
それで健康を損なってしまう人が
かなり多いのではないかと推察する。
この情報化社会、ちょっと外を歩いたり、
ちょっとデバイスに向き合ったりすれば、
湯水のようなにいろんな情報が入りこんでくる。
そのうち9割以上は自分にいらない情報なので、
あっという間に脳の中はゴミだらけ。
朝はクリーンでピカピカでも、
夜になると汚染されて窒息しかけている。
そもそも僕は脳のキャパシティが小さいので、
できるだけ日々、
情報デトックスしていかなくてはならない。
いろんなことを書いてはSNSやブログで発信し、
それだけでは飽き足らずに本まで出すのは、
そうした自分のためという意味合いがあるからだ。
でもいろいろ書いていると、
思ってもみなかった面白い発見に巡り会える。
あなたもいい歳になってきたなと思ったら、
機会を作って何らかのアプローチで
自分の脳内を覗いてみてほしい。
そこには広大な宇宙が広がっている。
日々、その宇宙の旅を楽しみに出かけることが、
これからの人生の醍醐味になるだろう。
都知事選2024・たなばた選挙の話

都知事選の選挙公報を見た。
50人もいる全候補者の情報を
いちいちしっかり見ているヒマはない。
少なくとも選挙公報に何を書いているかで、
せいぜい4~5人に絞って
その中で考えるのが妥当だろう。
で、いざ見てみると
半分くらい「NHKから国民を守る党」からの
立候補者なのでこれはスルー。
あと、1ダースくらいの候補者も読む必要もない。
そもそも当選する気で出ていない。
結局、まともに広報を読めて、
もうちょっと詳しくサイトなり動画なり
見てみようという気にさせるのは
10人もいない。
今のところの考えとしては、
石丸伸二氏がぶっちぎり第一候補。
彼は広島県の安芸高田市市長を
務めた実績もあるし、
書いてることも他の候補と比べて、
単なるイメージでなく、具体的。
41歳と若く、ITにも強そうだ。
これだけAIが普及してきた世の中で
短くても今後4年、ないしは8年任せるのであれば、
トップがIT音痴・AI音痴では話にならない。
ITに強く、膨大な情報を丁寧にさばけることは、
今後の政治のトップの必須条件だと思う。
そういう意味でもう一人、
泡沫候補とみられているかもしれないが、
AIエンジニア・起業家・SF作家という
安野たかひろ氏にも注目している。
こちらは33歳とさらに若いし、
コロナの時に話題になった
台湾のオードリー・タン
元デジタル大臣のようなにおいを感じる。
デジタル庁にも関わってるようだが
政治経験は乏しいので、
いきなり都知事というのは不安だが、
石丸氏がトップをやり、
彼が副知事のような形でサポートするのが、
今後4年の都政を考えた場合、ベストなのではと思う。
あくまで今のところの僕の意見です。
皆さんも選挙公報読んでみてください。
エリザベス2世の時代がもたらしたもの

仕事で2022年9月のエリザベス女王の国葬と
その前後・影響についての文章を書いていたので、
ネット上のいろんな資料を当たったり、
AIと女王について対話をしたりしていた。
1日かけてテキスト、写真、動画などを見るうちに
なんだか胸がいっぱいになった。
たかだか2年前だが、ずいぶん遠い昔のことに感じる。
1952年に即位して在位70年。
エリザベス2世はイギリスの国家元首だったが、
それだけでなく、
僕たちが生まれて生きてきた
20世紀後半から21世紀序盤の時代を統合した
アイコンみたいな存在だった。
イギリス・アメリカが主体となって構築した
現代の世界の象徴でもあった。
遺体の公開安置。
ウェストミンスター寺院での葬儀。
ロンドン市内を巡った後、
ガラス張りのジャガー霊柩車に乗せられた棺が
ウィンザー城に向かい、
聖ジョージ礼拝堂に埋葬されるまでの国葬は、
彼女自身が綿密に練りあげた
半世紀以上にわたる「終活」の結果でもあった。
日本でも生中継されたが、
あのようなドラマを秘めた、
美しく荘厳な式典を、
もう一度、別の形でリアルに体験することは
おそらく無理だろう。
国葬はイギリス王室の威光を示すものだったが、
当の王室はこれから縮小の一途、
そしてカジュアル化の一途を辿っていく。
人類の王族の存在・物語は、
やがてすべて虚構の中に移項していくだろう。
そして世界もあの時を境にして
ずいぶんと変わったように思える。
僕たち古き者はこれから
前の時代の記憶と
新しい時代の考え方の間で
少しずつ引き裂かれながら
生きていくことになるかもしれない。
20世紀カルチャーを堪能した者として、
それもまた楽し、と思わなくては。
おりべまこと新刊「宇宙を旅するお年頃」

よりよい人生のためのサプリメント。
「生きる」をテーマにしたエッセイ集第5弾。
還暦を過ぎるとだんだん若返る。
ただし、それは精神面や感受性のお話で、
肉体的な年齢とは乖離していく。
これからの人生は、
こうした精神と肉体のギャップを
どうごまかして埋め合わせていくかが課題になる。
心がけるべきは脳内の清掃。
心にも体にもいちばんよくないのは、
ゴミ情報を貯め込んでしまうことだ。
頭の中に詰まったゴミ情報は、
そのままストレスに変質する。
それで健康を損なってしまう人が
かなり多いのではないかと推察する。
この情報化社会、ちょっと外を歩いたり、
ちょっとデバイスに向き合ったりすれば、
湯水のようなにいろんな情報が入りこんでくる。
そのうち9割以上は自分にいらない情報なので、
あっという間に脳の中はゴミだらけ。
朝はクリーンでピカピカでも、
夜になると汚染されて窒息しかけている。
そもそも僕は脳のキャパシティが小さいので、
できるだけ日々、
情報デトックスしていかなくてはならない。
いろんなことを書いてはSNSやブログで発信し、
それだけでは飽き足らずに本まで出すのは、
そうした自分のためという意味合いがあるからだ。
でもいろいろ書いていると、
思ってもみなかった面白い発見に巡り会える。
あなたもいい歳になってきたなと思ったら、
機会を作って何らかのアプローチで
自分の脳内を覗いてみてほしい。
そこには広大な宇宙が広がっている。
日々、その宇宙の旅を楽しみに出かけることが、
これからの人生の醍醐味になるだろう。
もくじ
高校教師とぼくたちの失敗
ネコのお遍路さんと笑劇の人生
人は神秘なき世界では生きられない
宇宙を旅するお年頃
「わたしを離さないで」:社会貢献と自己の幸福の追求
恋愛から遠ざかり、恋愛小説に歩み寄る
なぜ桜とクローンは切なくて美しいのか?
「美しい人」は今でも幸せに暮らしているのだろうか?
自己満足のために山に登る
海はとても遠くにある
中秋の名月の月光浴
人生百年時代の生き方は北斎に学べ
去りゆく母との再会
自由になるための結婚
気楽な神様に気軽にありがとう ほか
全34編 載録
高齢者は電話の声に潜む体温・息づかいに騙される

夕方のNHK首都圏ニュースで
「ストップ!詐欺被害というコーナーがあり、
たいてい晩飯を食べながら見ている。
おもに高齢者の家に
息子、孫、警察官、役所、銀行など、
いろんな役に扮した詐欺師が電話が掛けてきて、
「助けてくれ」とか
「あなたは不正に巻き込まれている」とか言われて、
ATMに行かされ、振り込まされてしまう。
あるいは自宅にやって来た
友だちやら会社の同僚やら銀行員やらに
現金(タンス預金?)をわたしてしまう。
けっこう何年も前から同じパターン繰り返されており、
「なんでそんな耳にタコができたような
セリフにだまされるんだよ!」
とやきもきしてしまうが、
そこでふと、そうではないだろと気が付いた。
実際に被害者が聞いているのは、
電話を通しているとはいえ、
人間の「生の声」である。
文章を整理して精製して再現したセリフと、
詐欺犯の生の声とは違う。
生のセリフには人の体温があり、
息づかいがあるのだ。
どうしてそんなことを考えたかというと、
取材した音声もおなじだから。
生成AIなどで起こしてしまうと
楽で早くて簡単だが、
そこに並んだ文字列は、
取材相手が喋った内容に相違ないが、
音になったところ以外はすべて抜け落ちている。
つまり間とか、息づかいとか、トーンとか、
イントネーションとか、強弱とか、
ここでつっかえたとか、あそこで早口になったとか、
感情が入っている部分の多くは
文字として表せないのだ。
だからAIを使ったとしても、
その文字起こしを目で追いながら、
もう一度、相手の声を耳で聴くという
アナログ作業をすることになる。
でないと取材対象者を頭の中で
生き生きと再生できない。
たぶん、この類の詐欺師と
電話に出る高齢者との関係も同じだ。
プロの役者がやっているわけではないので、
そんなに演技がうまいとは思えないが、
セリフの文とともに、
声に言語外の感情がこもっていれば、
スルスルッと耳に入り込んでしまうのではないか。
現代のような機械化・デジタル化された
コミュニケーションに慣れていない高齢者、
特に一人暮らしの人は
普段、孤独を感じていなくても、
つい、その声に操られてしまうのではないかと思う。
そこには人の体温・息づかいが潜んでおり、
そうした形のないものが心にすき間に侵入することで、
詐欺話に引き込まれてしまうのである。
人は理の通った話しか信じないと思ったら大間違い。
人は人らしいコミュニケーション、
感情豊かなアナログコミュニケーションを
潜在的に求めている。
だから詐欺事件も後を絶たない。
こういった認識を踏まえて対策しないと、
詐欺電話の被害を防ぐのは
なかなか難しいのではないかと思う。
おりべまこと電子書籍新刊 「宇宙を旅するお年頃」

6月20日(木)発売予定!
エッセイ集:生きる第5巻。
コロナの時、東京五輪の時、
何があったのか思い出してみよう。
人生の常備薬、いろいろ取り揃えています。
・もくじ
高校教師とぼくたちの失敗
ネコのお遍路さんと笑劇の人生
人は神秘なき世界では生きられない
すべては道楽
「2020年の挑戦」への挑戦が終わる
宇宙を旅するお年頃
ほか全33編載録
父の日の秘密の花園

前にも書いたことがあるが、
行きつけの花屋の女主人は、
昔の少女マンガに出てくる、
お花屋さんになりたかった女の子が
そのまま夢を叶えて花屋になったような人である。
齢はたぶん僕と大して変わらないと思うので、
客観的に見ればりっぱなおばさんだが、
”お花大好きなの。でも、商売でやっているから
ビジネスライクなところもあるわよ。”
といった絶妙なブレンド感が漂い、
なかなかかわいい上に味がある。
40年前に逢っていたら恋に落ちていたかもしれない。
ふらっと店に入ると、いつもの黒いエプロンをつけ、
長い髪をひっつめにして、いつものように淡々と、
けれどもお花大好き感を醸し出しながら作業している。
狭い店内は季節柄、青い紫陽花が幅を利かせており、
他の花はそれに押しのけられるように
小さくなっている。
何となくとっちらかった印象だが、
花が呼吸し、人間には聞こえない言葉で
いろいろお喋りしてるような雰囲気がある。
今日は父の日なので
「父の日に花を贈る人はいないんですか?」
と聞いてみたら、
「いないですね、ほとんど」と、つれない返事。
「最近は子育てするお父さんも増えたので、
むかしより認知度上がっているはずなんですけどねー。
やっぱ父の日はお花よりお酒ですよね」
そこで前々から気になっていたことを聞いてみた。
「『お父さんだってお花が欲しい』とか、
そんな宣伝出したら売れないですかね?」
と水を向けると、
「うーん、どうでしょう?
あんまり忙しくなっても困っちゃうんで、
うちはやらないですね。
母の日もぜんぜん宣伝しないんですよ。
商売っ気がなくてすみません」
と、なぜか謝られてしまった。
へたに宣伝してカーネーションなどが
山ほど売れ残っても困る。
けっこうしっかり者で、コスト意識が高そうだ。
そして、確かに商売っ気はあまりない。
じつは僕もそこが気に入っている。
この花屋は僕が知る限り、
近辺の花屋のなかでいちばん値段が安い。
他の花屋は、ぜいたく感・贈り物感を
演出するところが多いが、ここは庶民派というか、
「さりげない日常という庭に咲く花」を
大事にしている感がある。
家に花を飾るのはぜいたくではない。
花は心の栄養剤になるのだ。
極端な話、おかずを一品減らしてでも、
部屋のどこかに生きた花を飾ったほうが
生活のクオリティが上がるのではないだろうか。
そんなことを考えていたら彼女は、
「わたし自身は、母の日も、父の日も、
お花はもちろん、
なーんもあげたことなんてないんですよ」
と言って笑ってのけた。
おとなになった少女マンガの花屋の娘は
なかなかミステリアスで奥が深い。
秘密の花園のなかで悠々と生きている感じがする。
宇野 亞喜良の世界とアングラ演劇

「90のじいさんになっても少女を描いているって
変態だよね」
先日テレビで、美術家の横尾忠則と
イラストレーターの宇野 亞喜良が
話していたのをチラ見した。
前述のセリフは横尾氏が宇野氏に言ったもの。
16日の日曜まで東京オペラシティのアートギャラリーで
宇野 亞喜良展をやっているので、
それに関連した番組だったようだ。
「変態」なんて言われて、
さすがにムッとした表情を見せていたが友達同士だし、「(常識的なことにとらわれない)天才」の、
横尾流の表現なので、
特にケンカになることもなく対談は続き、
最後はいっしょにメシを食うところで終わっていた。
宇野 亞喜良の絵の世界の主役は女性だが、
別に少女専門というわけでなく、
大人の女も描いている。
寺山修司の本や演劇の美術もよくやっていたので、
寺山流に言えば「青女(せいじょ)」が多い。
青女とは、「少年」に対して「少女」があるように、
「青年」に対して「青女」という言葉があっていい。
そう言って寺山修司が1970年代に出した
「青女論」というエッセイに出てきた言葉だ。
宇野 亞喜良の描く女の絵の特徴は、
笑わない顔と奇妙にアンバランスな体型。
笑わない顔は「大人や男に媚びない表情」と
よく言われる。
重心が下りていない、アンバランスな体型は、
女になりきっていない少女・青女特有のもの。
どこの画家か漫画家か忘れたが、
「少女の体型がアンバランスに見えるのは、
この世界に存在することにまだ慣れていないからだ」
といった類のことを言っていて、
ちょっと感心したことがある。
クリエイターが好んで描いて見せる、
10代後半の女の子特有の透明感とか、
ちょっとミステリアスな雰囲気は、
そういうところと繋がって
醸し出されるのかもしれない。
僕も熱心なファンというわけではないが、
寺山修司が好きだったこともあり、
宇野 亞喜良の絵は昔からよく目にしてきた。
イラスト・美術の世界ですでに60年以上、
第一線で活躍してきた人だが、
その魅力はまったく色あせない。
横尾忠則もそうだが、このレジェンド美術家たちは、
本当に最後の最後まで
現役の「変態じいさん」を貫きそうだ。
そんな宇野 亞喜良氏の最新作か。
先日、唐組の紅テントの芝居を見た時、
彼のイラストが載ったチラシをもらった。
今週末から花園神社で始まる新宿梁山泊の
「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」。
唐組の紅テントに対して、こちらは紫テント。
寺山修司でなく、唐十郎の状況劇場時代の芝居で、
豪華キャストが出演する。
たぶん連日満員大入りだろう。
宇野 亞喜良の、アンバランスで媚びない女たちの世界
(そしてたぶん横尾忠則の世界も)を培ったのは、
やはり1960~70年代のアングラ演劇カルチャーという
肥沃な土壌だったのだろうと思う。
ネコのタマはタマなし?

たまたまタマなしネコの話を調べることになり、
タマなしのオスの生きる道について考えてみた。
今回ここでいう「タマなし」とは
動物の去勢のことで、ジェンダー問題とは関係ない。
今どき都会で飼われるイヌやネコは、
ほぼほぼ愛玩用で、自然の状態から切り離し、
人間社会に組み入れるわけだから、
その辺に出て行ってヤリまくって
子供がうじゃうじゃできると困る。
そういうわけで避妊・去勢もやむなし、と考えられている。
ちょっと古いが、2017年の調査によると、
避妊・去勢手術をしたイヌは全体の約5割、
ネコは8割だという。
これは多分、飼い方の違いだろう。
イヌは外出の際、必ず飼い主といっしょだが、
ネコは勝手に出歩くことが多い。
それで雄雌がくっついてやっちゃうからだ。
「去勢」という言葉には心がざわつく。
男子なら誰でもそうだろう。
実際、雄イヌ・雄ネコの男性飼い主は
「そんな可哀そうなことできるか」と
反対する人が多いらしい。
それに対してメスの避妊にはあまり反対しない。
可愛い娘がその辺の男とやっちゃってできちゃったら
大変だという、父性愛(?)の由縁だろうか?
人間同様、イヌもネコもお年頃になると、
脳内にホルモンがドバドバ出て、
やりたくてたまらなくなる。
オスの立場に立つと、
強烈なフェロモンを発散しているメスに遇ったのに
ガマンを強いられると、頭狂いそうになるかもしれない。
これは人間も同じで、男の人生の半分は、
そうした己の性欲との戦いとも言えるのだ。
実際、イヌ・ネコも未去勢だとストレスが溜まって
暴力的になったり、
夜鳴きやマーキングなどの問題行動が増えるらしい。
だから男の子のイヌやネコと
なかよく平和に暮らしたければ、
できるだけ性欲に悩まされないよう、
去勢しておっとりした子にしたほうがいい――
という意見が優勢に見える。
でも、タマなしネコだと
ネズミを捕らなくなっちゃうのでは?
と思ったら、そんなことはなく、
狩猟本能そのものには大きな影響を与えないようだ。
今どき、ネコをネズミ駆除用に飼う家は少ないと思うが、
せっかくいるのなら役立ってくれれば、
それに越したことはない。
これ見よがしに血まみれの獲物を持て来られると
嫌かもしれないけど。
動物病院のネコの去勢手術の動画を見たら、
麻酔をかけて結構簡単に済ませていた。
ただ手術後、そのネコが股の間を舐めていて
「あれ、タマないぞ」と気付くシーンには、
やっぱちょっと胸が切なくなったな。
ちなみに家畜のブタやウシのオスも
少し成長すると、オス独特の体臭がついて
肉の味を落としてしまうため、去勢する。
しかし、こちらの場合、
日本ではまだ麻酔をかけずにやっているので、
アニマルフェアウェルの観点から問題視されている。
肉の味をよくするために男の子のブタ・ウシが
タマを切られて痛い思いをしているのを想像すると、
けっこう複雑な気持ちになる。
業者の人たちは、一生懸命おいしい肉を作ろうと
努力してやっているのだが……。
前のめりになって生きて死ね

本日の名言
「事実がたとえわかっていなくとも、
とにかく前進することだ。
前進し、行動している間に、事実はわかってくるものだ」
この名言の主ヘンリー・フォードは、
20世紀アメリカの自動車王。
要するにわからないと考えこむのではなく、
まず行動しろということ。
たぶん自己啓発リーダーの人たちも好んで使うフレーズだ。
そうだ、その通りだと思いつつ、
僕がこの名言を目にして連想したのは、
子供の頃に見た野球マンガ「巨人の星」の1シーンである。
それは主人公・星飛雄馬(ピッチャーです)の父・一徹が、
かの坂本龍馬の死について語るシーン。
一徹は投手生命に関わる
飛雄馬の欠点(球質が軽い)に気付き、
問い詰める息子に対して坂本龍馬の逸話を持ち出し、
「たとえドブの中で死んでも、なお前向きで死ぬ、
それが男だ」と語る。
その一徹のセリフに合わせて画面では
路上で暗殺者に襲われ血まみれになった龍馬が、
ドブの中で倒れながらも、這いつくばって前進しようとし、
ついに息絶えるという壮絶なシーンが描かれた。
当時はスポーツ根性マンガ全盛時代だったので、
一徹のセリフと、前のめりになって倒れる龍馬の表情は、
強烈に子ども心に染みた。
というわけで小学生当時、「巨人の星」を見ていた僕は、
長らくの間、これが坂本龍馬の最期だと思っていたのだ。
ところが事実はご存知のとおり、
料理屋の2階でしゃも鍋をつついていたところを
襲われたので、ドブの中で倒れようがない。
いや、もしかしたら瀕死の状態で店から這い出し、
路上にあったドブに落ちたのか?
とも考えたが、やっぱりこの話は
原作者・梶原一騎の創作だったようである。
厳密にいうと、梶原一騎はどうやら
司馬遼太郎の名作「竜馬がゆく」を読んで、
その一文にある
『男なら、たとえ溝の中でも前のめりで死ね』
をアレンジして使ったようだ。
もともと司馬遼太郎は歴史学者とか研究家ではなく、
あくまで歴史作家なので、エンタメになるよう、
史実にかなり自分のアレンジを加えている。
昭和以降の龍馬像をつくり上げ、
国民的ヒーローに押し上げたのも司馬遼太郎の功績。
梶原一騎はその功績をスポ根ドラマに
うまく取り入れたということだろう。
ちなみにこの「龍馬 前のめりで死ぬ」説は、
僕と前後する世代の人たちに
かなり大きな影響を与えたらしく、
小説家の有川ひろ(1972年生まれ・高知県出身・女性)が
「倒れるときは前のめり」という
題名のエッセイ集を出している。
寄り道が長くなったのでもとに戻す。
仕事にしても、生活にしても、
一歩一歩コツコツが大事なのはわかる。
ただ、視野を広げて人生全般を見た場合、
僕は若い頃、いずれ齢を取れば、
いろいろわからないことが
だんだんわかってくるのだろうと思っていた。
ところが現実は真逆で、
どんどんわからないことだらけになっていく。
死ぬまでに世の中の事実・真実がわかるのか?
と問われたら、ほとんど絶望的。
しかし絶望してても始まらないので、
何はともあれ、生きて一日一日大切に、
死ぬまで一歩一歩あゆむのみ。
一歩進むと二歩下がっちゃうんだけどね。
★エッセイ集:生きる 第5集
「死ぬな!きみの地球を守るために(仮題)」
Amazon Kindleより近日発売予定。
唐組公演「泥人魚」観劇記
先月亡くなった劇作家・唐十郎さんの供養もかねて、
新宿・花園神社に唐組の公演「泥人魚」を、
観に行ってきた。カミさん・息子が同伴。
この時代になると、テント芝居は貴重なアナログ体験だ。
●すべて人力のアングラテント演劇
切符の販売とか、精算方法(現金のみ)とか、
入場整理(劇団員が大声を上げて整列させる)とか、
デジタルでもっと効率的にやる方法があるのでは・・・
と思うが、たぶんないのだろう。
それにこういうやり方を続けてほしい、
という客の願いもある。
テントという、日常と異なる異空間に侵入するためには、
それなりの段取りが必要で、
すんなり簡単に事が運んでしまっては面白くない。
言い換えれば、忙しくて時間が取れない、
もっとタイパを良くしろという人には味わえない、
アナログ・人力ならではのぜいたく感が味わえる。
ござに座って見る昔ながらのアングラ式桟敷席に
(おそらく)500人くらいが詰め込まれたテント内は
現代の高齢化社会の縮図のような風景で、
半数近くが僕の同年代(60代)以上。
残りの半数がそれ以下で、男女比は半々か、
男性がちょっと多めかなという印象だ。
息子(20代後半)やそれ以下の若者もけっこういて、
中には高校生らしき子の姿もチラホラ
(学校帰りなのか、制服を着ていた)。
「入場料:子供2000円」とあったが、
さすがに子どもはいなかった。
でも、子供がこうした観劇体験をしてもいいと思う。
●状況劇場の幻影
僕は李麗仙・根津甚八・小林薫などが活躍していた
70年代後半~80年代初めの状況劇場に洗礼を受けている。
そのため、唐さんの芝居作品にはどうしてもあの頃の、
卑俗なものを聖なるものに転換させる、
リリカルでスケールの大きい幻想ロマンを求めてしまい、
唐組以降の作品にはイマイチ魅力を感じてこなかった。
けれどもこの「泥人魚」という作品には、
状況劇場時代の作品とは全く異なる魅力があった。
●諫早湾「ギロチン堤防」から生まれた物語
モチーフになっているのは、
「ギロチン堤防」という呼称が衝撃的だった
1997年の長崎県諫早湾干拓事業問題。
湾と干拓地を遮断する293枚の鉄の板(潮受け堤防)が
すごいスピードで次々と海に落とされていく
ギロチンシーンはかなりのインパクトがあり、
人々の関心も高かった。
(テレビのニュースなどで放送された)。
これはもともと戦後間もない頃に農地を増やすため、
国が計画した干拓事業、いわば国家プロジェクトだ。
これによって、かつて「豊饒の海」と言われた
諫早湾の環境は一変して、漁獲量は激減。
漁業者と農業者との対立をはじめ、
損得を巡って地域住民の深刻な分裂が起こり、
20年あまりにおよぶ長い裁判になった。
●ドキュメンタリーを重視した劇作
唐さんはその裁判が始まった2002年9月に
諫早湾まで取材に行き、自分の目で現地の海を見て、
この戯曲を書いた。
その経緯は、新潮社から出版されている戯曲のあとがきに、
また今回の観劇プログラム掲載の、
演出・久保井研氏のコラムに書かれている。
ちなみにこの久保井氏のコラムは、
唐組における劇作活動の様子が垣間見えて興味深い。
唐さんは、状況劇場の時代は自分が生まれ育った、
終戦直後の東京の下町の風俗や人々の暮らしと、
思春期から学生時代の文学・芸術体験をベースに、
60年代・70年代の世情を取り入れて
独自の劇世界を構築していた。
しかし、1988年に始まった唐組時代の作品では、
その時代ごとにクローズアップされる
現実の社会問題に材を取り、
いわばドキュメンタリー的な要素に重きを置いて
みずからの劇世界を継続・進化させていったようだ。
とはいっても、舞台に上る成果物は、
やはり常人には真似できない
妄想ワールドであり、イメージコラージュである。
「ギロチン堤防」という現実の材料から、
人魚姫、天草四郎、ハリーポッター
(2002年当時大ブームだった)など、
次々と出てくる連想がキャラになり、セリフになり、
アクションになり、劇世界をかたち作る。
あとは観客がどこまで想像力を駆使して
それについていけるかだ。
●もののけ姫と泥人魚
これはもちろん、紅テントで上演することを前提に
書かれた作品だが、普通の劇場でやっても、
あるいは映画や映像+詩みたいな作品にしても
面白いのではないかと思った。
もちろん、その場合はアレンジが必要だと思うが、
人々がネットの世界など、より現実と乖離した人工環境に
(精神的に)移り住み始めたこの時代、
海・地と人の日々の暮らしとが
緊密に繋がっていた時代の記憶を綴るこの物語は、
ある種の普遍性を孕んでいるのだ。
ちなみにいっしょに見た息子の感想は
「要するに『もののけ姫』だよね」。
うん、その通りとは言わないけど、そう遠くはない。
若い世代の感想としては面白いと思う。
みんな気にしているテーマなのだ。
終幕、ブリキの鱗を作り続ける男の口から
最後にこぼれ落ちるセリフ、
そしてお決まり通り、テントの背景が開いて
劇世界と現実の風景と溶け合うラストシーンは、
やはり状況時代と変わることなく、
卑俗なるものを聖なるものに変え得る、
唐作品独自の力と美しさに溢れている。
「痴呆症」は老害ワード?
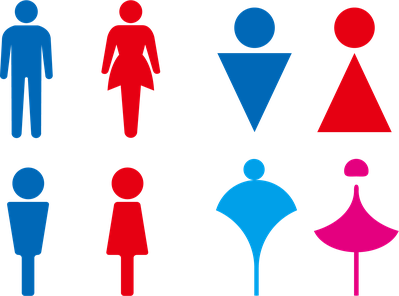
義母を連れてスーパーに買物へ。
途中、トイレに行きたいと言いだしたので、
階段の踊り場にある女子トイレの前まで連れていき、
少し離れたところでで待っていた。
なかなか出てこないので心配になっていた矢先、
ドアが開いて、60前後のおばさんが
訝し気な表情で出てきて外にいた僕の顔を見た。
どうやら義母の世話人だと察知したらしく、
「痴呆?」と尋ねた。
義母は中でちょっとおかしな行動をしていたらしく、
この人もしや・・・と思ったらしい。
しかし、粗相したとか、特に問題はなく、
そのすぐ後に出てきたのでほっとした。
その女性も特に絡むこともなく、そそくさと立ち去った。
それだけの出来事だったが、
彼女が言った「痴呆」という一言は
ちょっとショッキングに響いた。
べつに腹を立てたわけではないが、
2024年のいま聞くと、「痴呆?」は
かなりネガティブなインパクトを持っている。
自分の家族を介護している人に向かって言ったら
ひどく傷ついたり、ブチ切れたりする人もいるだろう。
「痴呆症」はいつから「認知症」になったのか?
調べてみたら、
厚生労働省が『痴呆症』に替えて『認知症』を
一般的な用語・行政用語として用いるとしたのは、
2004年12月24日となっている。
「痴呆」という言葉には
侮蔑的な意味が含まれているというのが変更の理由だ。
呼び名が変わってもう20年経つわけだが、
ずっと普通に使われていたので、
僕もたぶん10年くらい前まで割と平気で
「痴呆症」と言っていたような気がする。
たかが呼び名、されど呼び名。
その人の社会性を問われることなので、
けっこうバカにできない。
こういう言葉遣いに鈍感な人は、
今の社会に適応できていないと
見做される恐れがあるからだ。
その女性が義母をバカにして言ったわけではないだろうが、
うっかり出てしまったということは、
彼女の頭の中はまだ昭和の残像で満たされていて、
アップデートできていないということを意味している。
ウィンドウズ95とか98とか、
あのへんのOSで動いているということなのかもしれない。
まぁそれで自分の生活に不便はないのだろうが。
「痴呆症」だけではない。
ほかにも病気の呼び名とか、外国人の問題とか、
LGBTQの問題とか、
かつての差別や偏見に対する社会通念が
どんどん変わっているので、
うかつに古い言葉を使ったりすると、
そのデリカシーのなさが白眼視され、
若い世代から「老害予備軍」と
見られてしまうのではないだろうか。
「昔はよかった」「昭和は輝いていた」なんて
のたまってはいられない。
やっぱりダメだったところはダメでしたと認めないと。
わざと面白がって使うならまだしも、
何気なく無意識に使っている「昭和ワード」
もしくは「平成ワード」が
周囲の人たちを著しく不快にさせていないか、
2024年の世界ではアウトになっていないか、
いま一度、チェックしてみる必要があるかもしれない。
週末の懐メロ第5巻」 無料キャンペーン終了
おりべまこと電子書籍「週末の懐メロ第5巻」
無料キャンペーン終了。
ご購入ありがとうございました。
よろしければレビューをお寄せください。
引き続き¥300で発売中です。
https://www.amazon.com/dp/B0CZ4NDXJQ
Kindle Unlimited:サブスク1カ月¥980読み放題でも読めます。
どうぞご利用ください。1~4巻も発売中。
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
今月もまた新刊を出します。ただいま準備中。お楽しみに。
週末の懐メロ第5巻「ハリケーン/ボブ・ディラン」

おりべまこと電子書籍
週末の懐メロ 第5巻
6月4日(火)15:59まで無料キャンペーン実施中!
20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する
主観90%の与太話をあなたとシェア。
21世紀を生きるための知恵にしていく、
カルチャー発見のためのガイドブック的エッセイ集。
無料キャンペーン終了まであと1日。
この機会をお見逃しなく。
もくじ
116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン
117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ
118 人は少しずつ変わる/中山ラビ
119 氷の世界/井上陽水
120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ
121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル
122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン
123 ヨイトマケの唄/美輪明宏
124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル
125 夜空ノムコウ/スガ シカオ
126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ
127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス
128 赤いハイヒール/太田裕美
129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ
130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ
131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン
132 燃ゆる灰/ルネッサンス
133 さよなら人類/たま
134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル
135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック
136 アジアの純真/PUFFY
137 ハリケーン/ボブ・ディラン
138 夜明けのスキャット/由紀さおり
139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル
140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ
141 二十世紀少年/T・レックス
142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ
143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン
144 ランバダ/カオマ
145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー
146 貿易風にさらされて/マザー・グース
147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ
148 ウェルカム上海/吉田日出子
全33編載録
137 ハリケーン/ボブ・ディラン
現代アメリカ社会の欺瞞・腐敗・不条理をえぐる
吟遊詩人ボブ・ディランが
1976年に発表したアルバム「欲望」のトップナンバー。
ギターに合わせてフィドル(バイオリン)がうねり、
ベースとドラムがロックなリズムを刻む中、
無実の罪を着せられた60年代の黒人ボクサー
ルービン“ハリケーン”カーターの物語を歌い綴る。
紛れもない、ディランの最高傑作だ。
惨劇を告げるオープニングから見事に構成された長編詩は、8分以上にわたって聴く者の胸に
ひたすら熱情溢れた言葉の直球を投げ続け、
“ハリケーン”の世界に引きずり込む。
殺人罪で投獄されたカーターは
獄中で自伝「第16ラウンド」を書いて出版し、
冤罪を世に訴えた。
その本を読んだディランは自らルービンに取材して、
この曲を書き上げたという。
その冤罪がいかにひどいものであったかは
曲を聴いての通りで、
人種差別がまだ正々堂々とまかり通っていた時代とはいえ、こんなでっち上げが認められたことに驚くばかり。
けれども半世紀以上たった今も
実情は大して変わっていないのかもしれない。
そしてまた、昔々のアメリカの人種差別、
黒人差別の話だから
僕たちには関係ないとは言っていられないのかもしれない。
冤罪はどこの国でも起こり得る。もちろん日本でも。
(つづく)

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。
お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。





















