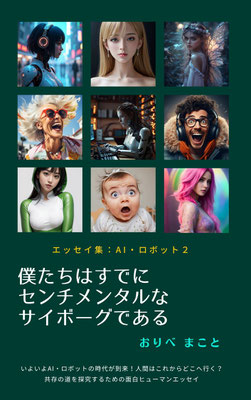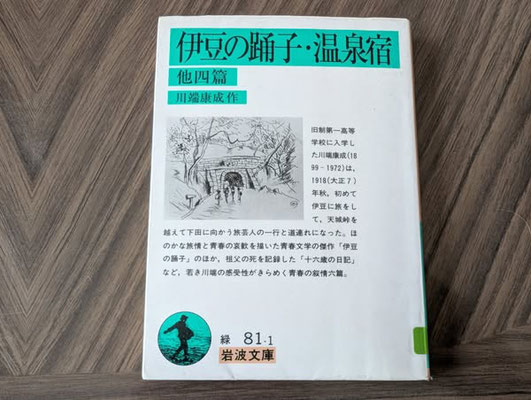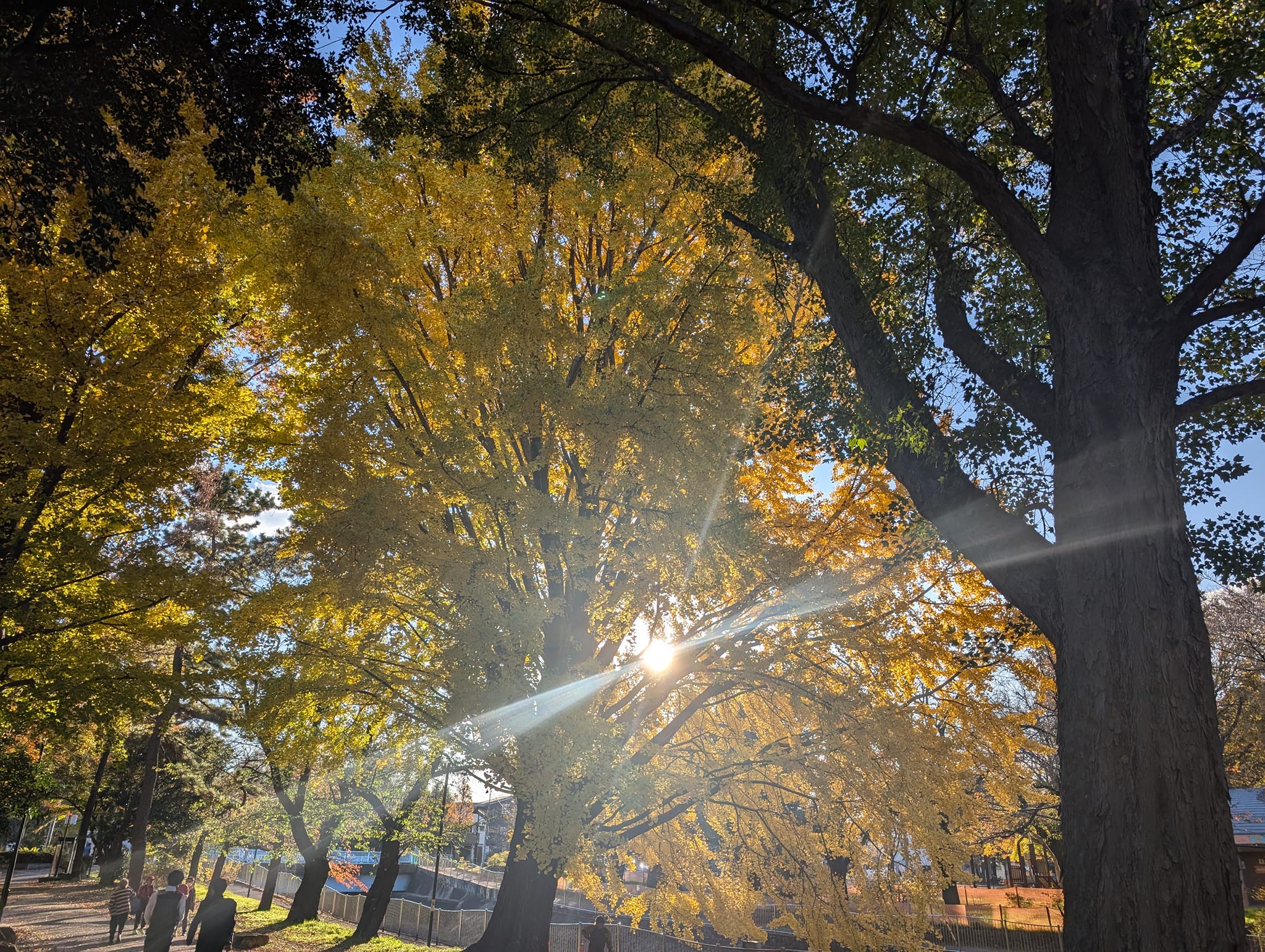- ホーム
- 電子書籍:おりべまこと劇場
- NEWS
- わたしの「わたしストーリー」
- 台本ライターとは?
- 実績:わたしの「しごとストーリー」
- サービスメニュー・料金プラン
- ブログ「台本屋のネタ帳」
- 仕事
- 生きる
- 食べる
- ロボット・AI
- 物語
- 歴史
- 世界
- 動物
- 音楽
- ビートルズ
- ドラマ・映画・演劇
- インターネット
- 本
- 台本
- エッセイ
- 子ども
- 2011年5月
- 家族
- エンディング
- 農業
- 旅
- 社会問題
- 昭和
- 認知症介護
- 広告
- 電子書籍
- 週末の懐メロ
- 2011年6月
- 2011年7月
- 2011年8月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年10月
- 2011年12月
- 2012年1月
- 2012年2月
- 2012年3月
- 2016年5月
- 2016年6月
- 2016年7月
- 2016年8月
- 2016年9月
- 2016年10月
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- 2017年6月
- 2017年7月
- 2017年8月
- 2017年9月
- 2017年10月
- 2017年11月
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- 2018年6月
- 2018年7月
- 2018年8月
- 2018年9月
- 2018年10月
- 2018年11月
- 2018年12月
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 新規ページ
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年4月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2020年11月
- 2020年12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- お問い合わせ
綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ
「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。
カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、
僕も土曜日に見たが、確かに面白い。
それにしても僕の中では、
綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、
そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。
役柄はもっと年上の設定らしいが、
もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。
そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの
スタッフも多くは40代
(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。
来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。
今や60・70代よりも40・50代のほうが
しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?
それどころか、20・30代も
「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。
どうやらがんばって終活するためには、
若いエネルギーが必要なのだ。
60・70代からじゃ遅すぎる?
いったいどうなっちょるんじゃ?
あっという間に1億総終活時代に突入だ。
「ひとりでしにたい」本当に面白いので、
観てない人は、NHKプラスで観てみてください。
電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」
無料キャンペーンは本日終了。
ご購入ありがとうございます。
よろしければレビューをお願いしますね。
AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
AIライフ、不老不死サイボーグ人生に興味のある方は必読。
6月30日(月)15:59まで 2025年半分終了記念
4日間限定無料キャンペーン開催中!
あとわずか。この機会にぜひどうぞ。
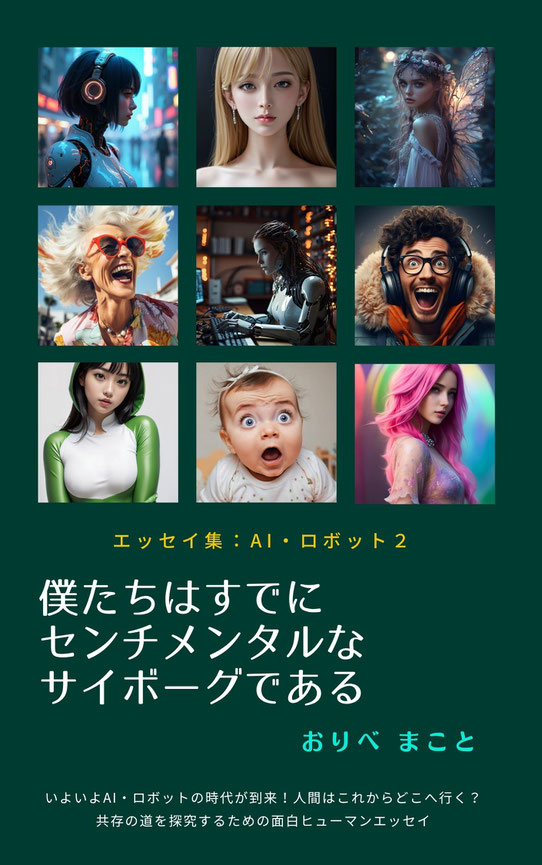
私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。
住環境から身体機能まで、あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、人間とは何かを問い直す時が来ました。
本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、
おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。
その内容の振り幅には驚かされます。
アンドロイド観音への戸惑いから始まり、
生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と
罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、
パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、
さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——
26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を
容赦なく描き出しています。
特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、
まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。
終活・終末期医療における
「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、
SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。
この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から
人間ドラマへと昇華させています。
「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、
これからどこへ向かうのでしょうか。
AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、
示唆に富んだエッセイ集です。
もくじ
アンドロイド観音とどう向き合うか?
100万回生きたロボット
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値
ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る
自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界
終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目
人生の半分はオンラインにある
AIはマンガのロボットみたいな相棒
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく
ほか全26編採録
「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から 「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ

子供は、強くて賢くて、何でもできちゃうロボットっていいな、
カッコいいな、僕もロボットだったらよかったのにな、
と憧れるのに、
大人になると「わたしはロボットじゃないんだ!」と言いだす。
なんで?
でも、齢を取ってくると、ふたたび、
ロボットだったらよかったのに、と思うかもしれない。
だってロボットはアンチエイジングだし、死ぬこともない。
最近思う。
人間として生まれた以上、
僕たちは一生ロボットにはなれないが、
技術の力で限りなくロボットっぽく生きることはできる。
私はそんなのごめんだ、
という人もこの時代に生きているかぎり、
じつは刻一刻とすでにサイボーグ化しているのだ。
そんな思いを込めて、AI・ロボット・エッセイ集第1弾
「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から
第2弾「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ。
AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ。
6月30日(月)15:59まで
2025年半分終了記念 無料キャンペーン開催中!
https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S
「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」無料キャンペーン開催
おりべまこと電子書籍 エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでに
センチメンタルなサイボーグである
本日6月27日(金)16:00~30日(月)15:59
2025年半分終了記念 4日間無料キャンペーン開催
私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。
住環境から身体機能まで、
あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、
人間とは何かを問い直す時が来ました。
本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、
おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。
その内容の振り幅には驚かされます。
アンドロイド観音への戸惑いから始まり、
生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と
罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、
パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、
さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——
26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を
容赦なく描き出しています。
特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、
まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。
終活・終末期医療における
「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、
SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。
この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から
人間ドラマへと昇華させています。
「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、
これからどこへ向かうのでしょうか。
AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、
示唆に富んだエッセイ集です。
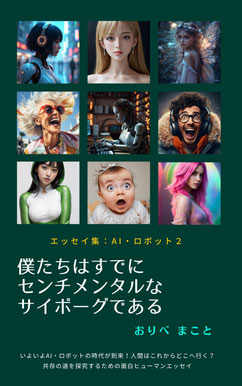
もくじ
アンドロイド観音とどう向き合うか?
100万回生きたロボット
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値
ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る
自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界
終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目
人生の半分はオンラインにある
AIはマンガのロボットみたいな相棒
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく ほか全26編採録
AIにご興味のある方、この機会にぜひご購入下さい。
山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識
なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」
小説(原作)と映画は別物。
それはそれでいいのだが、
そのギャップが大きければ大きいほど。
ツッコミがいがあって面白い。
「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は
その最たる例と言えるかもしれない。
川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、
映画にするなら、
全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。
それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、
その見せ場もいろいろ作る必要がある。
というわけで、この作品の場合は、
そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、
社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、
謎めいた演出が随所に散見される。
日本人の差別問題が裏テーマ
社会問題とは差別問題だ。
1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は
ちょっと遅れて日本にも及んだ。
70年代前半は、学生運動の挫折があり、
昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、
ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。
当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、
当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、
日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。
川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、
大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、
そうした日本人の差別意識が、
いかんともしがたい悪しき現実として、
随所にちりばめられている。
映画はそれらの材料をかき集め、
大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。
「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文
三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、
彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。
旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、
下賤な職業の人間として蔑視されている。
物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った
休憩所(だんご屋)の婆さんは、
旅芸人たちと親しげに話していたが、
学生に対しては
「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、
親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。
実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では
「あの人たちは今日の宿も決まっていない
(放浪者みたいなものだ)」と言っている。
映画ではこの婆さんの差別意識を、
いっそうあからさまに表現しているのだ。
セクシー少女・百恵の魅力の開花
なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、
「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と
一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。
彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。
これらは原作にはなく、この映画における演出である。
山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、
彼女の人気に火が付いたきっかけは、
シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、
当時ローティーンながら、
セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が
大ヒットしたからだ。
男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。
他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、
子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、
多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、
アイドル百恵の誕生につながった。
この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を
踏まえたものであり、
観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、
山口百恵の独特の、青い性的魅力を
うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。
ラスト1分 衝撃の不協和音
そして見せ場は最後の最後にやってくる。
学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。
見送りに来たのは、
かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、
船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、
大喜ぶで叫び、手を振り返す。
離れ離れになってはじめて
「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。
その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、
きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、
というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。
叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が
唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。
え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。
かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。
ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。
しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。
ひきつりながらも笑顔を保ち、
懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。
最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、
ストップモーションになってエンドマークが出るのである。
なんとも奇妙で、
まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。
なぜラストショットが、
若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、
汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?
夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。
ととでもメッセージしたいのか?
せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、
このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、
怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、
50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。
あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を
ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。
船が出る前、学生は地元の土方風の男に、
3人の幼子を連れた婆さんを
上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。
現代ならとんでもない無茶ぶりだが、
大正時代、エリートたるもの、
こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、
みたいな空気があったようで、
彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。
そして踊子との別れを終えた後、
伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、
東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて
彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。
当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、
庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、
立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、
そんな前向きな感想を持っただろう。
ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、
少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、
古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。
本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、
まだ読んだことがない人はぜひ。
そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、
豊かになった昭和日本で、
この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、
令和の世からタイムトラベルして、
若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。
母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから
「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」
と言われて、割とショックを覚えた。
でも、なかなか彼女は鋭かった。
確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に
いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。
女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、
同時にめんどくさかったり、怖かったり、
時々いやになったりもする。
それが態度や行動に出ていたかも。
その感情の遠因には、子供の頃、
母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と
一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。
その頃は母のことがあまり好きではなかった。
よく怒られたからである。
叔母と祖母はそれを見ていたせいか、
僕にやさしく、猫かわいがりした。
それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。
だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。
一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。
母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように
むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、
よけいにイライラを募らせたのだろう。
なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。
父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。
べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、
女運はよかったのかもなと思う。
思い出の中の女は、みんな可愛い。
この齢になると出会いも限られてくるので、
あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが
できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。
みんな齢を食ってしまったが、
女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。
こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。
今日は母の命日だった。
天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。
映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子
伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした
(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、
ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。
アマプラで1974(昭和49)年公開の
山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。
僕が中学生の時に公開された映画で、
当時大きな話題になっていた。
しかし当時、中二病にかかっていた僕は
「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」
と言って無視していた。
しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」
なんて映画は観に行った覚えがある。
山口百恵のファンだった試しはない。
「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、
少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、
僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。
中高生がアイドルに求める
可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが
大きな要因だったのではないだろうか。
同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、
むしろ女子の方に人気があった。
しかし今、この齢になって観ると、
唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。
この映画は女優として初出演作でもあるので、
演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、
明るさと陰とのバランスが素晴らしく、
この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。
●「え、はだか?」ではありませんでした
物語中、温泉に入っていたかおるが
学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって
裸で手を振るシーンがあるが、
そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。
最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、
いきなりグイっとカメラが寄る。
そして「え!?」と思う間もなく、
1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。
「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、
やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。
そりゃ当然だよね。
●「旅情」「異文化体験」を描いた原作
そんなわけで原作と並行して観たので、
小説との違いに目が行った。
俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い
「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を
リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。
もちろん、主人公の学生が旅先で出会った
芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が
メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。
少女を描くことに固執し、
ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、
この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、
恋愛的感情の表現はごく薄味だ。
そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ
「伊豆の踊子」が、
老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。
人物描写や風景描写などがイマイチで、
文学作品として未熟な部分も、
却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、
つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。
そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。
今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、
旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、
この物語の舞台である100年前は、
東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。
作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには
うってつけの場所だったのだと思われる。
そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う
旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。
「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが
圧倒的多数を占めていた、大正日本における
エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。
●河原乞食という現実
先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。
明治維新以降の近代日本では、
こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、
それはあくまで建前上、表面上のもので、
庶民がしっかり理解していたとは言い難い。
人々の心情に根付いた差別意識は、
まだ江戸時代のままだったのだ。
芸能人はどんな大スターだろうが、
すべからく「河原乞食」である。
原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)
という立札が出てくる。
この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、
旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。
川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、
ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。
踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、
こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。
とはいえ、川端は差別を告発しようと、
この作品を書いたわけではない。
あくまで旅で出会った現実の一つとして、
さらっと流している感じである。
クリエイティビティを刺激した山口百恵
この立札は原作では後半、終わりに近いところで
「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、
この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、
立札も物語が始まって間もないところで現れ、
かなり強い印象を残す。
まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。
かなり意図的なものと思われるが、
その背景として、おそらく当時、
社会改革の余波で部落問題などに焦点が
当たっていたことがあるのだろう。
また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、
日本の映画人も多かれ少なかれ、
社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。
それで監督や製作陣が、
単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、
と考えたのかもしれない。
山口百恵という稀有な素材は、
そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。
吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、
百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、
昭和の高度経済成長期以降の
「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、
現代にまで残る傑作にしたのだ。
映画の話、さらに次回に続く。
「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台
伊豆の河津に行ったのは先週だが、
駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。
それで初めて河津が、かの日本文学の名作
「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。
主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、
今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。
ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も
河津町だ。
いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、
そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、
生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。
おどろきの踊子
いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が
なんとなくどこかから耳に入ってきて、
知ってるつもり・読んだつもりになっている。
僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、
スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。
そして正直、びっくりした。
え、これだけ?って感じ。
文庫本でわずか40ページ。
字数にして2万字あまりの短編で、
30分ちょっとあれば読めてしまう。
旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで
けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、
ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。
どうしてこんなすぐ読める物語なのに、
俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、
自分の人生を後悔してしまった。
でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。
100年前の変態ロリコンじいさん
ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。
なんといっても「世界のカワバタ」。
ノーベル文学賞を受賞した、
敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、
その幻想もガラガラと崩れ去った。
今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。
「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、
最近の川端康成の定番像のようだ。
踊子へのエロい思慕
そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、
この「伊豆の踊子」の物語も、
なんとなくエロっぽく読めてしまう。
主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。
いわば川端の分身みたいな人物だが、
それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。
大学生が中学生に――ということなので、
今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、
ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)
全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が
メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、
いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、
頭がくらくらしてくる。
わずか40ページの短編のなかに、
こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、
日本文学の名作、それどころか世界名作としても
親しまれているゆえんなのかもしれない。
そう考えると、100年前の日本の文学界、および、
世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、
みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった
のではないか?という疑念にとらわれる。
いい加減だから名作になった?
正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、
そんなに中身のある話ではない。
話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。
物語としてはかなり薄味である。
川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、
もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、
旅芸人の一座との交流の部分を、
何年後かに抜き書きしたものらしい。
いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの
ノベライズなのである。
また、川端は、この作品では
「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。
でも、この作品の場合、その「さらっと感」
「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。
発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。
まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、
日本人のハートをわしづかみにした。
川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、
6度にわたって映画化された。
映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、
その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。
「女が箸を入れて汚いけど」
なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、
かなり深く心に刺さった部分もある。
それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。
100年前、旧制一高の学生と言えば、
日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。
対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。
さらにその中でも女は一段身分が低く、
一座のリーダー役の「おふくろ」は、
(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、
(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、
二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。
(川端が言わせている)
現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界
江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は
どんなに人気があろうとも被差別民であり、
身分制度の埒外の存在、
つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。
それは徳川幕府が、町人や農民に
「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、
できるだけ不満を抱かせないようにするための、
狡猾な支配構造をつくったからだ。
その意識は明治になって近代化された以降も、
えんえんと人々の意識に残った。
そういう意味では100年前、
大正から昭和になったころの日本はまだ、
現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。
モモエ踊子は差別問題を強調?
小説を読んだ後は、映画も見た。
1974年、昭和49年に公開された、
三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。
これも今に至るまで気が付かなかったが、
このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で
「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。
今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。
その話はまた次回に。
夫の精神的支配を受けた女性の話

うちのカミさんは鍼灸治療をやっているが、
話を聴いていると、患者さんの半分くらいは
精神疾患のせいで体もおかしくなっているようだ。
今日も不登校の高校生が
いきなり予約の合間を縫って昼食の時間に来たり、
「30年以上、一人で外出できなかった」という
60代の女性が診療を受けに来たと言う。
後者は、旦那の精神的支配を受けていて、
結婚して30年余りの間、
友だちとの付き合いはおろか、
買物も外食も、ひとりでは出してもらえなかったそうだ。
本当か? と耳を疑ったが、
いまだに一人で店に入れないという症状があるところを見ると、
どうも9割がたは本当のことらしい。
村上春樹の小説の中で、
金持ちではあるけれど、そういう恐ろしい価値観の男と
結婚してしまった女性の悲劇が
書かれてあったことを思い出した。
これは立派な精神的虐待だと思うが、
ひと昔前までは、
そんなに表立った問題にはならなかったのだろう。
もしかしたら今の50代以上--
昭和に生まれ育った女性では
そんなにレアなケースでもないのかもしれない。
その女性の場合は、子供がいないのも悲劇だった。
子供がいれば若い世代に救い出されたかもしれないし、
旦那の意識も変わっていた可能性もある。
結局、その旦那は3年前に借金を残して突然死んでしまった。
経済的には親戚のお金かなんかで助かったようだが、
彼女の病気はそのまま残った。
もう支配者がいないので自由なはずなのだが、
長年しみついた習性で一人で外出するのが難しい。
おそらく夫婦間で共依存の関係が出来上がっていたので、
自分で考え、行動することができなくなってしまったのだろう。
その女性がどういうきっかけで
来院することになったのか聴いてないが、
カミさんのところに来られるようになっただけ
治癒に向かっているのではないかと思う。
どうも買い物や食事に出かけるのは
「娯楽」として植えつけたらしく、
それを30年以上も禁じられていたので、
自分でも「娯楽=贅沢、無駄、悪」
みたいな意識が貼りついているらしい。
カミさんは、ひとりで喫茶店やレストランに入ることを
一つの目標にしなさいと言っているらしいが、
まだ実現できず、なかなか難しいようだ。
こういう話を聴くと、結婚とか、夫婦とか、
家族といったもののネガティブな面について考えてしまう。
よけいなことかもしれないが、
結婚ハッピー、夫婦なかよし、家族バンザイといった
画一的な価値観は怖い。
もちろん、明るく考えたほうがいいが、
そうしたダークな面があることも
常に心の片隅に置いておいたほうがいい。
そして、自分の間違いに気づいたら、
たとえ年寄りになっていても、
人生やり直す勇気を持つべきだと思う。
雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面
前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、
河童伝説の顛末を紹介したが、
いよいよ後編では本丸である。
住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、
快く承諾してくれた。
住職が大切そうに持参したのは、
見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。
よく見ると表面がややぼこぼこしており、
いかにも古い時代の手作り感が漂っている。
蓋は何度か作り変えられているそうだが、
壺本体は実に700年以上前のものだという。
「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」
住職がひっくり返すと、
底には「祖母懐」という文字が刻まれている。
●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産
「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。
これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、
温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。
愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、
そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。
さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。
「加藤四郎左衛門景正」
これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。
加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、
一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、
帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。
現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、
景正を祀った「陶彦社」が存在する。
「本物なら国宝級の品物です。
ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、
鑑定などしてもらったことはありません」
住職は笑いながら説明してくれた。
「河童からもらいました」と言えば、
鑑定士はどんな顔をするだろう?
そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら
どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。
さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、
粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。
そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、
焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが
四郎左衛門の作風だったそうだ。
確かに、目の前の壺も実に味わい深い、
野趣に富んだ風合いを見せている。
●いよいよ河童のせせらぎ体験
「河童はこれを置いていくときに、
『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。
これを聴いて私を思い出してください。
この川の音が聴こえる限りは、
私はどこかで元気に暮らしていますから、
和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」
住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。
果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?
「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、
ぼーっという音は聞こえるものなんです。
それは容器の中で風が流れる音で、
貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、
お分かりかと思います。
しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、
下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、
小さな水が流れる音がします」
住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。
最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。
しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!
確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが
聞こえてくるではないか。
まさに小川のせせらぎのような、
優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。
思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。
やはり聞こえる。確実に水の音である。
正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。
●プロの最新機材で録れなかった音が、
子供のラジカセで録音成功
住職によると、この不思議な音を録音しようと、
NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。
しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。
「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、
ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」
なんとも不思議な話である。
最新の録音機材では録音できないのに、
子どものラジカセでは録音できる。
まるで河童が、純真な心を持つ者だけに
水音を聴かせてくれるかのようだ。
試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。
すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。
後で家に帰って聞き返してみると、
確実にせせらぎの音が記録されている。
超うれしい!
これは一体どういう現象なのだろうか。
科学的に説明のつく現象なのか、
それとも本当に河童の仕業なのか。
真相は定かではないが、確実に言えるのは、
この壺から不思議な音が聞こえるというのは、
真実であるということだ。
●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告
住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。
豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、
壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、
洪水を予告してくれるのだそうだ。
「今でも川の音が聞こえるのですが、
河津川の水位が上がりそうな時など、
壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」
これは確かめようがなかったが、
もし本当だとすれば、
河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、
災害から人々を守り続けてくれているということになる。
●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー
ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。
「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。
ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、
と思いを巡らせることができます」
その上で住職は、禅宗の根本的な教えである
「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。
「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。
これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、
それに惑わされてしまうという教えです。
実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、
例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、
肌で感じたりすることで、
現実には目に見えないものに思いを馳せたり、
いろいろな想像・連想ができたりする。
そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」
なるほど、これは深い話である。
現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、
さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、
僕たちはそれらに振り回されがちだ。
しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。
むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、
真実が隠されているというのだ。
「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、
自分で感じなさいという教えです。
現代社会では、テレビやインターネットを通じて
文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、
皆さん惑わされますから。
こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と
想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、
という教えが、
この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」
●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心
住職はさらに続けた。
「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、
もともと仏の心を持っています。
ところが、現実の社会で生きるうちに、
心にたくさんの垢がこびりついてしまう。
真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」
これも禅宗の重要な教えの一つである。
すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。
しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、
先入観といった「垢」が心に付着してしまう。
その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。
河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。
現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、
僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。
「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、
実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。
昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。
ですから、そんな中で、こうした体験をすると、
より心に響くのかなと思います」
確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。
現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、
素朴で自然な美しさがそこにはある。
そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、
日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ
河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、
僕は深く心を動かされた。
これは単なる音響現象以上の何かがある。
人はみな心に仏性を持っており、
それによって、せせらぎの音を聴くことができる。
虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、
こてはとても大切な体験であるように思える。
SNSで飛び交う断片的な情報、
ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、
AI生成による真偽不明の映像や音声、
誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--
僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。
そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、
本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。
そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
僕たちに大切なことを思い出させてくれる。
文字や人工的な情報で表現できない真実が、
この世界にはあるということ。
そして、その真実は五感を通じて、
心で感じ取るしかないということを。
●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心
この河童の壺の音について、
科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。
壺の形状による音響効果なのか、
それとも何らかの物理的現象なのか。
しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、
実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。
大切なのは理屈ではなく、
その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。
最新の科学技術よりも、
純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。
河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、
この音を聴く時、
僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。
河童が実在するのかどうかは問題ではない。
大切なのは、その存在を通じて、
自然との調和や他者への慈悲といった
大切な価値を思い出すことなのだ。
●あなたの心の中の河童に出会うために
700年という長い年月を経ても、
河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。
伊豆に来たら、河津に来たら、
ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。
ただし、河童の壺を体験したい場合は、
この壺が寺宝中の寺宝であるため、
必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。
そこで、あなたも河童の封じ込めた
せせらぎの音を聴いてみてほしい。
音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。
日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。
もし音が聞こえたなら、
それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。
そして、河童という架空の存在を通じて、
自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を
思い出すことができるだろう。
あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。
そして河童が、
人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。
文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、
河童の壺が奏でるせせらぎの音は、
きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。
(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺
今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある
「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を
訪ねることになった。
JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。
駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が
目の前に広がる。
あいにくの小雨模様だったが、
河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、
これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。
ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。
むしろこの雨模様のほうが、
なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、
まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。
●椅子まで河童という油断のならない境内
境内に入ってまず驚かされるのは、
とにかくあちこちが河童だらけということだ。
持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、
よく見ると河童の形をしていた。
思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。
寺院としては日本的な古さを感じさせる、
いかにも由緒正しそうなお寺だ。
と同時に、どこか懐かしい感じもする。
よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に
境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。
これは後で知ったことだが、
ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが
なせる業なのだ。
●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年
「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、
実に700年の歴史を持つ古刹である。
その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。
開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である
徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、
なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。
徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、
二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の
大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。
その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、
帰国後は各地の名刹を歴任した。
そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。
興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という
真言宗の寺があったということだ。
それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。
「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)
という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、
深い意味を込めた名前である。
●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割
現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。
「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、
河津桜で有名になる前--
昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」
今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、
桜まつりが始まったのは今から34年前の
1991年(平成3年)のこと。
桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える
大イベントに成長したが、
それ以前は河童が町の看板だったのである。
「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、
商工会に飾られていたりしたんです。
でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、
そういったものを寺で預かったんです」
なんとも皮肉な話である。
河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、
河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。
そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を
果たすことになったというわけである。
●「つくったが、作られていないように」のアート美学
現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。
「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」
ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。
人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、
まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、
「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、
心憎いばかりだ。
書家の師範のスタッフもいるということで、
寺院としての格式を保ちながらも、
現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。
●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー
以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、
町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、
昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、
一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。
「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、
住職は苦笑いを浮かべながら、
「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。
●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人
さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。
それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。
昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。
お寺の裏に位置するその場所は、
川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。
この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、
いろいろないたずらをして村人を困らせていた。
そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか
「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、
村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。
なんとも人間らしい話である。
最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。
●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童
そして運命の日がやってきた。
ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。
そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。
そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。
よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。
「河童だ、河童がいるぞ!」
誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。
河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、
裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。
ここでの河童の行動が実に人間臭い。
馬のしっぽにしがみつくという、
なんともマヌケな状況で発見され、
慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。
●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑
しかし村人たちは容赦しなかった。
井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。
河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、
井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。
村人たちは河童を取り囲み、
「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、
棒切れで叩き始めた。
ちょっとやりすぎな気もするが、
当時の人々にとって河童は子どもを攫う
恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。
●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命
ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。
村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、
河童が息も絶え絶えに倒れている。
それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。
和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。
「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。
寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」
さすがは禅僧である。
暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、
慈悲の心で河童を救おうとした。
村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、
和尚さんの言葉に従って河童を預けた。
●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し
和尚さんは村人たちがいなくなると、
「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」
と言って、河童を逃がしてやった。
この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。
その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で
目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。
すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。
●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺
河童は言った。
「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」
そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。
「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。
口に耳を当てると、水の流れる音がします。
水の音が聞こえたら、
わたしがどこかで生きていると思ってください。
和尚さまもどうぞお元気で」
そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。
●令和の今も、壺に耳を当てれば
和尚さんは夢心地で聞いていたが、
我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、
河童が本当に来たのだと確信した。
それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、
村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。
けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、
底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、
河童の無事を思った。
また、河津川に出水があった際、
このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、
人々が助かったこともあり、
それから寺の宝として大切に奉られてきたという。
今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、
河童が元気で生きていることを伺える。
そして人々は水の流れが心を洗うと言い、
ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~
さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、
実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。
果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが
聞こえるのだろうか。
後編では、この神秘的な河童の壺による
不思議体験をレポートする。
僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、
数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を
体験することになるのだが、
その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。
後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、
そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。
(後編に続く)

鉄道マン発 洗たく女 サイボーグ
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
無料キャンペーンは終了しました。
たくさんの方にご購入いただき、ありがとうございます。
気に入っていただけたら、紹介・購入サイトの下のほうに
「カスタマーレビュー」があるので、星をつけてもらったり、
レビューコメントを書いていただき、
他の読者におすすめいただければありがたいです。
(できれば高評価、でも厳しいご意見も歓迎です)
同書は引き続き、800円で販売しています。
また、おりべまことにご興味を持たれたら、
他にもいろいろ出していますので、ぜひ覗いてみてください。
格差社会ではたらく女の労働ファンタジー小説
洗たく女の空とぶサンダル ¥500
最新刊!AI・ロボットエッセイ集
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
¥500
脱サラ・起業・転職のリアル
今、60歳が人生の新たなスタート地点になった。
シニアも若者も必読!
生き方に悩む人のためのリアルな参考書がここにある。
鉄道マン発 映像調理師®
ー高塩博幸の人生甘辛レシピー
無料キャンペーン、いよいよ明日、
6月9日(月)15:59まで
すでに120部を突破。
脱サラ・起業・転職を考える人たちの間で大きな話題に。
無料で購入できる最後のチャンスです。
専用端末は不要。アプリを入れてスマホで読もう。
鉄道マン発映像調理師® 無料キャンペーン実施中
大好評!
鉄道マン発 映像調理師®
ー高塩博幸の人生甘辛レシピー」
6月9日(月)15:59まで
6日間無料キャンペーン開催中。
このチャンスをお見逃しなく!
今、60歳が人生の新たなスタート地点。
シニアも若者も必読。
生き方に悩む人のためのリアルな参考書。
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!
かつて新幹線を走らせた男が、今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。本書「鉄道マン発 映像調理師」は、シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追ったルポルタージュです。
高校生だった高塩少年は祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に国鉄に入社。その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。
しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?
映像クリエイターとしての第二の人生では、自らを「映像調理師®」と名乗り、終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。
「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。
運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、学ぶべきものがたくさんあります。
人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。
足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、
第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。
「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?
「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、
あなたも勇気をもらえるはずです。
本書は単なる成功物語ではありません。
昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、
失敗や挫折を乗り越え、常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。
起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、
そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。
人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵がここにあります!
ヘビとの遭遇

今年の干支は?
って聞かれて「えーと」なんてダジャレてる人、
けっこう多いのでは?
1年半分の6月ともなると、お正月の熱狂もどこへやら。
今年は何年だったか、みんな忘れてしまっている。
改めて、今年-2015年、令和7年はヘビ年。
そのせいか、この春からは初夏にかけて、
川沿いを散歩していると、やたらとヘビに出会う。
護岸の下のコンクリの岸の上に
何やら太いロープが落ちているなと思ったら、ヘビ。
散歩道の植え込みの中で何かにょーっと
動いているなと思ったら、ヘビ。
手すりに何か紐みたいなものが
ぶら下がってるなと思ったら、ヘビ。
そして昨日は、くねくねしながら悠々と川を泳いでいる
ヘビを目撃。
どれも長さ1メートルほどの青黒いアオダイショウだ。
周囲にはカルガモやコサギ、アオサギ、
カワウなどの水鳥が何羽もいるが、
さすがにこれらは体が大きいので襲ったりはしない。
うまいこと共存しているようだ。
そろそろカルガモの赤ちゃんが生まれる時期なのだが、
今からそれを狙っているのだろうか?
毎年1回か2回、
梅雨から梅雨明けの時期にお見掛けするヘビだが、
今年はすでに目撃4回。
ヘビ年大売り出しだ。
遭遇するとちょっとギョッとはするが、
ヘビに遭うとラッキーなのだそうな。
そういえば数年前だが、
住宅街の道路を白ヘビが
超高速で横切るのを見たことがある。
神の使いともいわれるヘビ。
今度会ったら手を合わせて願いを唱えよう。
人の気配が薄れる夜の時間は、
ネズミでも襲って腹を満たしているのだろうか。
杉並区も人間が知らないところで
ワイルドな世界が繰り広げられている。
岸辺露伴×水の都ヴェネチア
「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、
「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。
「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。
人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、
オールヴェネチアロケ。
映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。
テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、
ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。
主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、
そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。
それによって事件を解決していくストーリーだ。
原作のマンガも全く知らないが、
高橋一生は超ハマり役だと思った。
舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。
ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、
幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。
年中、観光客が押し寄せていると思うが、
いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、
人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、
歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。
僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、
ヴェネチアにも訪れたが、
見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。
それは当たり前で、
この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。
世界遺産になった宿命みたいなものである。
車はもちろん、自転車も街の中に入れない。
観光客がわんさか来るのだから、
スタバやマックなどの店もありそうだが、
少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。
そうした規制も多いはずだ。
オーバーツーリズムを避けるため、
街に入るための入場料徴収も検討されているという。
世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、
僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。
一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、
僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に
奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、
どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。
ヴェネチアはその最たる街だ。
さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような
スケールの都市ではなく、
せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。
そこに独自の文化が集約されている。
観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、
実際の観光収入はそんなにないのではないか。
ヴェネチアを舞台とした映画で、
ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)
という作品があった。
そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、
たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、
ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、
普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、
ゴンドラやボートに乗ったり、
写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。
僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、
多分そうしたのだと思う。
それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが
あるのだろうか?
観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、
この街の住人たちがどうやって暮らしているか、
庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、
ひどく気にかかる。
この岸辺露伴の映画も、
けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、
人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。
それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、
とても心に残った。
地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。
この風景はいったいいつまで見られるのだろう?
本日より無料キャンペーン「鉄道マン発映像調理師®」
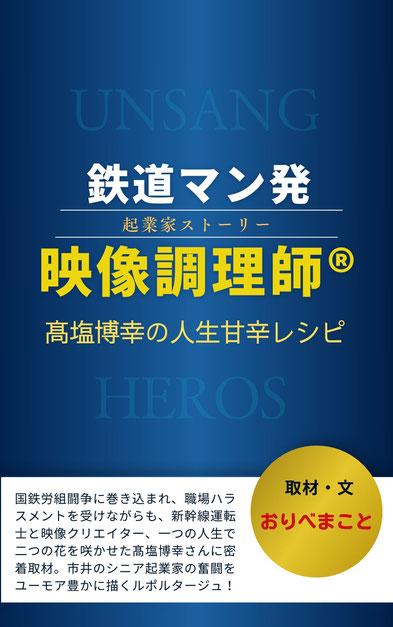
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
本日6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで
発売記念 6日間無料キャンペーン実施
このチャンスをお見逃しなく!
もくじ
第1章 高塩さんと映像の仕事
映像調理師®高塩博幸
エンディング産業展2022
倫理法人会での人脈から映像制作を受注
おいしい料理は“下ごしらえ”から
その人のストーリーを見つける作業
運転士の教官として培ったインタビュー術
AIなど最新ツールの駆使
ユニークなサービスメニュー
★ 自分史・遺言ムービー「nokosu」
★ nokosu 周年映像制作
★ 家系史継承箱《メモリアルボックス》
★ 死後の自分史
★ 子ども史・子育て自分史
●講座開設
★ 講座「スマホで自分史動画を作ろう!」
★ 講座「AIを使ってコマーシャル動画をつくる」
なぜ人は自分史を作ろうとするのか?
第2章 高塩さんの起業家スピリット
誰もがアーティストになれる
人生百年時代のチャレンジャー
ケンタッキーおじさんでもよかった
芸術と起業の街・足立区北千住からの再出発
映像調理師®誕生の舞台裏
映画より映写室が好きな子ども
きみは「ポピュラーチューズデイ」を聴いたか?
コンサートで音響アルバイトを経験
あんた、学校行ってどうするの?
高塩家のファミリーヒストリー
日本電子工学院と国鉄のW受験
第3章 高塩さんのJR東海道中膝栗毛
クリスマスエクスプレスに涙ぐむおじさん
花形鉄道マン
昭和の「青春18きっぷ」
国鉄百年の盛衰
組合闘争に巻き込まれて
「会社のイヌ」と呼ばれて
出世の秘密
JR東海出世街道
人生の憂鬱な昼下がり
鉄道マン最後の日
第4章 高塩さんと終活映像市場
高齢化社会における終活市場の拡大
映像が紡ぐ、新たな人生のしまい方
終活映像市場に輝く、ブルーオーシャンスターズの価値
映像調理師®の理念
欲しいけど欲しくない:終活映像営業の難しさ
終活映像市場に咲く、高塩博幸の営業哲学
新しいアプローチ
第5章 ブルーオーシャンスターズの未来
AIの進化を追いかけて
高塩式AIディレクター構想
10年後・20年後の世界を見据えて
「停止位置不良」の夢を見た人、来たれ!
鉄道マン発 映像調理師® 無料キャンペーン開催
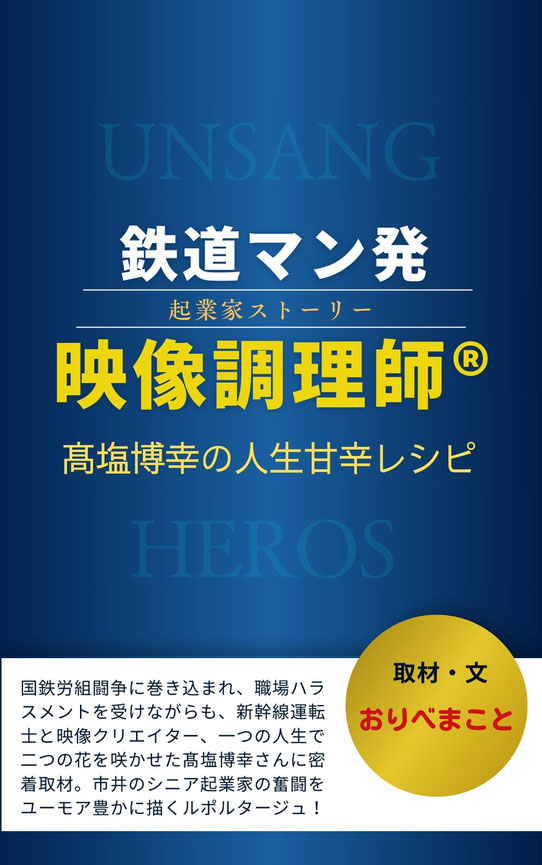
今、60歳が人生の新たなスタート地点
シニアも若者も必読!生き方に悩む人のためのリアルな参考書
鉄道マン発 映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで
発売記念 6日間無料キャンペーン実施
このチャンスをお見逃しなく!
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
おりべまこと電子書籍最新情報:AIエッセイ+起業家ストーリー
★本日6月2日(月)発売!
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S ¥500
スマホを握りしめ、メガネをかけ、工場製の服を着て生きている僕たち。実はもう「純粋な人間」なんてどこにもいません。世界的ロボット工学者が断言するように、現代人はすでに「動物と技術を合わせたもの」なのです。AIにパワハラプロンプトを仕掛け、アンドロイド観音に手を合わせ、エロコンテンツで技術革新を推し進める——抗えないテクノロジーの波に翻弄されながらも、どこか愛おしいAI・ロボットたちとの共存を模索する現代人の心境を、ユーモアと哲学的洞察で描いたエッセイ集です。
★6月4日(水)16:00~9日(月)15:59 無料キャンペーン!
ノンフィクション
鉄道マン発映像調理師®-高塩博幸の人生甘辛レシピー
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!
映画「エイリアン」とアンドロイドたち

ここのところ、急にまたSF映画が見たくなって、
ほとんど連日何かしら見ている。
今週はエイリアンシリーズを鑑賞。
シガニー・ウィーバーが主役のリプリー中尉を演じた1~4は、
SFホラーとして、単純に恐怖し、楽しめる部分と、
それだけで終わらない哲学的考察がミクスチャーされていて、
今、通して見ると当時とは違った印象・味わいがある。
●20世紀末20年の科学の進歩の集大成
この1~4は、1970年代の終わりから90年後半まで、
約20年の間に作られており、
この間の現実の人間社会の変化--
女性の権利の拡大と深化、ロボット・AI技術の発展、
クローン技術など、生命工学の進化などを積極的に取り入れ、
それらのエッセンスが絶妙な塩梅で織り込まれている。
また、初代監督リドリー・スコットの功績を引き継ぎ、
2でジェームズ・キャメロン、
3でデビッド・フィンチャー、
4でジャン・ポール・ジュネという
強烈な個性を持つ巨匠たちが、
それぞれ独自の美学と演出術を持って、
1本1本色合いの違う、独立した作品でありながら、
しっかりつながった物語を構成していることが、
このシリーズの成功要因になった。
●各物語のキーパーソンとなるアンドロイド
第1作における、ハンス・リューディ・ギーガーのデザインによる
最凶の宇宙生物エイリアンの登場は、
斬新でオリジナリティ豊か、
そして、怖さ・気持ち悪さの点で、衝撃度満点だった。
しかし、回数を重ね、見慣れてくると、
やはりその怖さ・気持ち悪さのインパクトは薄れてくる。
エイリアンシリーズの名作たる所以は、そこを補うために、
どんどんストーリーを拡大・深化させていったところにある。
そのキーとなるのが、ロボット(アンドロイド)の存在だ。
どの作品にも必ず人間そっくり(実際に俳優が演じている)の
アンドロイドが登場し、
その策略と行動が大きくドラマを動かしていく。
第1作のオリジナル脚本で、
どこまで設定が作られていたのか定かでないが、
宇宙開発事業を行う民間企業のシステムの一つとして、
彼らの頭脳(AI)は重要な役割を担い、
表向きの事業とは異なる、
隠された裏ミッションの担い手として暗躍するのである。
そして、これらのアンドロイドが、エイリアンに匹敵するほど、
怖くてグロテスクで気持ち悪い。
第1作の「アッシュ」も、第2・3作の「ビショップ」も
最後に人間やエイリアンに破壊されるのだが、
引き裂かれた体の内部は人間の内臓っぽかったり、
体液みたいなものが出てきたり、
半壊してボロボロの姿になっても機能できたりするシーンは、
なまじ人間そっくりなので、思わず目を背けたくなるぐらいだ。
第4作の「コール」は、
当時の人気若手女優ウィノナ・ライダー演じる女性型だったので、
さすがに他の二人みたいな凄惨な目に合わせるのは
スタッフも気がとがめたのか、
銃で撃たれるだけで済み、ラストまで原形をとどめて生き残る。
●仕事優先の機械人からヒューマンタッチな仲間への変遷
注目したいのは、シリーズにおける
これら「エイリアン・ロボット」の変遷だ。
第1作の「アッシュ」は宇宙船の科学担当者として、
割と単純に人間と敵対する(サンプル採取のため、
エイリアンの元を船内に招き入れる)、
割と単純な、お仕事最優先の機械的なロボットだ。
第2作の「ビショップ」はこれよりちょっと複雑化し、
最終的にリプリーたちをエイリアンから救う
「人間の味方」になる。
そして第3作では彼と同じ俳優が演じる、
「人間のビショップ」が、
企業のアンドロイド開発者=リプリーの敵対者として現れる。
同じ顔かたちでありながら、
ロボットよりも人間のほうが冷徹なのである。
第4作の「コール」は、前2体とは対照的に、
人間的な感情を持ち、
(エイリアンを宿した)リプリーを殺す使命を持って現れるが、
人間的な感情を持つ、いわゆる不良品のロボットで、
最後にリプリーと仲間になる。
日本では「アトム」や「エイトマン」のような
漫画で描かれたように、いくら強くて優秀でも、
自分が人間でないことに悩み苦しむロボット、
あるいは、「ドラえもん」のように、
もともと人間の仲間・友だちみたいなロボットが主流だが、
欧米では、70~90年代の20年あまりで
従来のロボット観がかなり変わってきたようである。
それは「ターミネーターシリーズ」や「ロボコップシリーズ」、
「ブレードランナー」「AI」など、
この頃、立て続けに作られた、
他のロボット映画の影響も大きいだろう。
●人間観・ジェンダー観の変化がロボットを魅力的にした
しかし、それよりも大きいのは人間観の変化、
特にジェンダー観の変化かもしれない。
昔、何かの本で「男がロボット好きなのは、
子供を産まない(産めない)からだ」
というフレーズを目にしたことがある。
つまり、子供を産める女性に対抗して、
命の創造に関わりたいという潜在的欲求が男の中にあり、
ロボットへの興味・研究に向かわせる、というのだ。
こうした出産機能を基点に考えるジェンダー観は面白い。
ハリウッド映画には、おそらく1970年代初め頃まで、
「女・子供を映画のなかで殺さない」という不文律があった。
アメリカ社会(及び、日本も含む、西洋型社会全般)には
女性や子供は「善なるもの」「聖なるもの」の象徴であり、
侵してはならないもの、男が命を賭けて守るべきもの
と考えられていたのだ。
もちろん、病気や事故、あるいは戦争に巻き込まれて
恋人や家族が死ぬなどのエピソードはあるが、
それらは情報として処理されるか、あくまで美しく描かれ、
けっして血まみれになるようなシーンはなかった。
そして女性や子供の死は、
男が奮い立って行動するためのモチベーションになっていた。
それらは言い換えれば、女性や子供を弱き者、
男の支配下に置かれる者、でなければ、
女神や女王のように崇め奉る者といった意味があった。
それが60年代の変革を経て、劇的に価値観が変わり、
女性も男性と対等の自立した人間として
描かれるようになっていく。
1979年に初登場した、シガニー・ウィーバー演じるリプリーは、
女神でも聖女でもなく、リアルな自立した人間として活躍する、
新しいタイプの女性ヒーローだったと思う。
彼女は自分のゆるぎない価値観と使命を持ち、
エイリアンと闘うヒーローとして描かれるが、
それゆえ、かつての映画の女性像からは想像もつかない、
相当ひどい目に遭わされる。
死んで生き返り、エイリアンとの「あいのこ」になり、
おぞましい姿をさらすことにもなる。
そうした惨劇のなかから
女性主人公ならではのテーマ「命の創造」をビビッドに提示する。
さすがにウィーバーの出演は4で終わるが、
最後の作品では、フランス人監督ジャン・ポール・ジュネが
グロテスク極まりない、リプリー最後の戦いを描きつつ、
「アメリ」「ロストチルドレン」のような寓話的な余韻を残し、
いったん、エイリアンシリーズの幕を下ろす。
そして、ジュネの残した余韻を受けて、
初代監督リドリー・スコットが再登板し、
「プロメテウス」「エイリアン・コヴェナント」
といった前日譚--21世紀の「エイリアン」を製作する。
エイリアンとジェンダー観の変化については、
また別の機会に詳しく書いてみたい。
●未来の記憶から生まれるコンテンツ
現実の科学技術の進歩を踏まえて作られた
20世紀末のSF映画だが、
昨今の技術の進捗状況は、これらエイリアン映画などの世界を、
そう遠くない未来に実現させてしまいそうな勢いがある。
もしかすると人類は未来の記憶を持っていて、
そのヴィジョンに向かって突き進んでいるのかもしれない。
SF映画はそれらの記憶を表現するコンテンツの一つなのだ。

おりべまこと電子書籍最新刊
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでに
センチメンタルな
サイボーグである
近日発売!
AmazonKindleにて
世界のエンディングの潮流は、エコ葬と安楽死

最近、墓じまいや相続問題など、
日本でも終活の話題が増えているが、
海外に目を向けると、世界の葬儀・終活の焦点は、
安楽死とエコ葬に傾いているようだ。
●英国で安楽死法案が成立目前
いま、英国では安楽死法案が下院での審議を通り、
6月には上院での審議に移るが、
この法案が成立するのは、ほぼ確実と言われている。
すでにスターマー首相も支持を表明しており、
BBCニュースなどで昨年末から
頻繁に審議の様子が報道されている。
日本では超高齢化社会・多死社会が
進展しているのにも関わらず、
長らく安楽死・尊厳死・自殺ほう助といった課題は、
ほとんど、まともに議論されてこなかった。
しかし、この英国の法案が成立したら、
何か大きな影響がおよぶかもしれない。
●この10年で安楽死が認められた国が・・・
少し前まで安楽死と言えば、
オランダとスイスしか思い浮かばなかったが、
現在はどうなのだろうと調べてみた。
2025年1月末時点でのデータだ。
・完全に合法化されている国・地域:
オランダ(2002年)
ベルギー(2002年)
ルクセンブルク(2009年)
カナダ(2016年)
コロンビア(2015年)
スペイン(2021年)
ポルトガル(2023年)
・部分的に合法化:
スイス(1942年から自殺幇助のみ合法)
ドイツ(2020年に憲法裁判所が自殺の権利を認定)
アメリカ(オレゴン州、ワシントン州など複数州で
医師幇助自殺が合法)
オーストラリア(複数州で合法化、
2019年ビクトリア州から開始)
・2023年(コロナ明け)以降の動き:
ポルトガルが2023年に完全施行。
英国は現在審議中(下院可決済み)
他に現在審議中・検討中の国を挙げると、
フランス(マクロン大統領が法案検討を表明)
イタリア(国民投票の動きあり)
アイルランド(市民議会で議論)
かなり衝撃的だった。
あくまで欧米に限っての話だが、
安楽死・尊厳死・自殺ほう助を認めた国は
この10年ほどで激増している。
●エコ葬も激増
一方、エコ葬も増加しているようで、
今世紀に入ってから、遺体をフリーズドライにしたり、
アルカリ溶液に浸して分解する水火葬、
土中の微生物を使って堆肥にする有機還元葬など、
さまざまな環境負荷の少ない葬法が考案されてきた。
どれも当初はキワモノ扱いだったが、
アメリカではすでに12州で有機還元葬も認められ、
水火葬も広がっている。
特にコロナ禍以降、この2,3年の変化は大きい。
安楽死とエコ葬は、まさに現代の葬儀・終活業界の
大きな潮流になっているのだ。
●何が人の心を、社会の常識を変えたのか
安楽死については、人権問題と深くかかわっているようだ。
「どう死ぬか」という個人の選択権の拡大、
医療技術の進歩で延命が可能になった一方での
「死の質」への関心、
超高齢化社会での終末期医療費の問題、
家族への負担軽減
といった視点が増加の要因になっていると思われる。
また、エコ葬については、
環境意識の高まりと持続可能性への関心
土地不足問題(特に都市部)
従来の墓地・埋葬への価値観の変化
樹木葬、海洋散骨、自然葬などの多様化
といった精神・ライフスタイルの変化が大きい。
両方とも、従来の「伝統的な死生観」から
「個人の価値観を重視する死生観」への転換を表している。
特にコロナ禍を経て、人々の死に対する考え方が
より現実的で個人的なものになったという面もあるだろう。
葬儀・終活業界としては、
これらの多様化するニーズにどう対応していくか、
また法制度の変化にどう準備するかが重要な課題になってくる。
あまり考えたくないという人が多いと思うが、
そう遠くない未来、日本でも今後、嫌でも
これらの議論をしなくてはならない時が来そうだ。
時空を超えた家康AI 好みの女性は天海祐希と石田ゆり子

「千住宿」は日光街道の最初の宿場町。
現在の北千住界隈がそうだ。
宿場が開かれたのは3代将軍・家光の時代、
1625年だから、今年でちょうど400年。
それでお祭りをやっているというので、
18日の日曜日、北千住まで行ってきた。
北千住は、拙著「鉄道マン発 映像調理師®」で
取材させていただいた髙塩博幸さんの
「ブルーオーシャンスターズ」が会社を構える街。
生まれも育ちも起業も足立区の髙塩さんは、
ビジネスとともに地域貢献にも熱心で、
今回は、この千住宿400年に際して、
オリジナルソングとビジュアル(プロモV)を提供。
さらにこの日は、AI企業研修を行う会社
「TSUYOMIHO」の宮田剛志さんとタッグを組んで
街頭に「家康AI」のブースを出店した。
「家康AI」は、家康に向かって質問すると、
「拙者が家康じゃ」などと徳川家康が
ユーモラスに答えてくれる体験。
歴史を「教わる」のではなく「対話する」スタイルで、
子どもから大人まで楽しめるのがウリだ。
テレビ局の取材も来ていて、
面白がって問いかける子供たちにインタビューをしていた。
僕もあれこれ質問してみたが、
没後409年を経て、AIの力で現代によみがえったこの家康、時々、「拙者がこの千住宿を開いた」なんて
トンチンカンなことを言う。
いやいや、五街道を整備しようと努めたのはあなただけど、
宿を開いたのは孫の家光でしょ。
そもそも400年前の1625年って、あなた、もう死んでるし。
それで「あなたの後の14人の徳川将軍のうち、
最も評価できるのは誰ですか?」
と聞くと家光の名を挙げたりする。ほうほう。
トンチンカンな部分は差し引いて、答がいかにもAI的な、
優等生の模範解答みたいなのが気に入らない。
それでいろいろ変化球を投げてみる。
「来年の大河は『豊臣兄弟』なので、今度はあんた悪役だね?
誰にやってほしい?」とか、
「『どうする家康』では、あんた、北川景子の
お市に惚れてたみたいだけど、ホントに好きだったの?」とか。
このへんの質問はうまくかわされたけど、
「好みの女性のタイプは?」と聴くと、
「しっかりしてて優しい人」なんて、まともに答えてきた。
「じゃあ、たとえば現代の女優さんだったら誰?」
と聴いてみたら、「天海祐希と石田ゆり子」と、
照れもせずにペロッという。
どういうラーニングをしたのか、
髙塩さんと宮田さんに突っ込もうと思ったが、
ま、お祭りだし、やめておいた。
てなわけで、今年は北千住で
随時、400年のお祭りをやっているので、
機会があれば遊びに行ってみてください。
髙塩さんと僕の本もよろしくね。
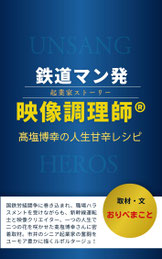
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
Amazon Kindleより好評発売中。¥800
国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!
世界の果ての海風さやか 吉祥寺で地中海料理

週末、息子の誕生日だったので、お祝いで
吉祥寺にある地中海料理の店「The MED」に行く。
店名は英語の「Mediterranean」の
頭の文字から取っているらしい。
これは「大地の真ん中」を意味する
ラテン語の「mediterraneus メディテッラーネウス」
medius 「真ん中」 + terra 「土、大地」に由来する語だ。
何だかカッコいい。
日本語の「地中海」もエキゾチズムの香りがする、
イメージ豊かな言葉。
明治時代に作られた可能性が強いが、当時の翻訳者は、
遠いヨーロッパのさらにそのまた向こう、
まるで世界の果てに広がる
天国のような優しい海を想像したのではないか。
さて、The MED。
外見はおしゃれだが、中は小さな居酒屋のような、
気さくな店で、キャパはせいぜい15人程度というところか。
店主らしき、料理を作るおっさんと、
注文をきく店員の若い女性でやっている。
(店員は日替わりかもしれない)
仕込む材料によって日替わりになるのか、
はたまた店主が毎日同じ料理ををつくると飽きちゃうからか、
決まったメニューブックがなく、
キッチンの前にその日出せる料理を紙に書いて貼りだしている。
さらにそれぞれの料理名の紙は
小さな国旗のマグネットで留められており、
どこの国の料理か、わかる仕組みになっている。
なにせ地中海はヨーロッパの南部、アジアの西部、
そしてアフリカの北部に囲まれた海で、
「地中海地域」に属する国は20以上もある。
よく知られているのは、ギリシャ、イタリア、スペインだが、
ヨーロッパではクロアチアやスロベニア、フランスも入る。
アジア~中近東方面は、
トルコ、レバノン、シリア、イスラエルなど。
アフリカだとエジプト、リビア、チュニジア、モロッコなど。
イタリア料理店やスペイン料理店は、
日本でもそれぞれ単独でたくさんできたので、
一般的にはギリシャ料理を中心に語られることが多く、
この日もムサカやグリークサラダを食べたが、
はじめて食べたモロッコの
「羊肉とプルーンの煮込み」がめちゃウメェ~。
甘いプルーンソースでトロトロに煮込まれた羊肉は、
まるで豚の角煮のごとしで、
これまで食べた羊料理の中でいちばん美味だった。
地中海料理は、健康長寿の食事法として、
日本でもよく知られるようになり、
「地中海ダイエット」なる言葉も生みだした。
その特徴は、野菜や果物、豆、ナッツ類、オリーブオイル、
全粒穀物、魚介類、乳製品がふんだんに使われていること。
さらにそれらを調理する際に使うスパイスの豊富さ。
スパイスと言っても、アジアンと違って、
辛い料理がほとんどないことも特徴かもしれない。
もう40年近く前だが、
当時のユーゴスラビアの首都ベオグラードから
殺人的な18時間すし詰め夜行列車に乗って、
ギリシャまで旅行したことがある。
おもにアテネとエーゲ海のロドス島を回ったが、
島で泊まった民宿の夫婦は、
なぜか「ギリシャのめしはうまくないだろ」と
僕に言ってた。
ギリシャ人は何でもかんでもオリーブオイルをかけるから
みんなオリーブ臭くなっちゃんだよ。
チーズだってヤギのミルクからつくるからおいしくないし、
パンもぱさぱさしているし。
と、妙に自虐的だったのを覚えている。
僕が日本人(当時は世界に冠たる経済大国)で、
イギリス(当時、ロンドンに住んでいた)から来たと
言ったので、そんな態度になったのだろうか。
今につながる西洋文明発祥の国の末裔なんだから、
もっと胸を張ってほしいなぁと内心思ったが。
しかし、彼らが「うまくない」と思っていた
オリーブ、ヤギのチーズ、全粒粉のパンなどが、
今や健康長寿食として重宝され、
ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。
「The MED」ではギリシャワインも飲んだが、
それより感動的だったのは「地中海ビール」である。
普段、ワイン党でビールなどあまり飲まないのだが、
このビールは違っていた、
日本のキレ、ニガ一辺倒のビールとはまったく別物で、
ほのかにフルーティーで、まろやかな感じ。
それでいながら甘く、べったりした感じはない。
長く記憶に残る香りと風味がある。
これを少ししょっぱい「おつまみオリーブ」と
いっしょに味わうと、
世界の果てから海風がさやかに吹いてくるようで、
体は吉祥寺のまま、気分はもう地中海。
ちょっとクセになるかもしれない地中海料理。
各国の多国籍な料理を試したければ、
「The MED」は超おススメ。
ほかに麻布十番と新宿歌舞伎町には
ギリシャ料理専門の店があるので、
機会をつくって行ってみたい。

生き方に悩む人のためのリアルな参考書 「鉄道マン発 映像調理師®」
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
AmazonKindleより好評発売中 ¥800
国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!
(あとがきより)
彼の祖父の時代は、日本を欧米諸国に負けない、
近代的な文化国家にすることが、国民共通の目標でした。
また、父の時代は、敗戦によって物も心も貧しくなってしまった
日本を復興させ、豊かな社会を築くことが共通目標となりました。
しかし、高塩さんや僕の世代になると、
祖父や父の世代のような、誰もが共有できる目標は、
もはやありません。
それに代わって、僕たちひとりひとりが、
生きる目標や生きがいを設定しなければならない
状況が訪れているのです。
これは日本のみならず、経済的な成功を成し得た、
世界の先進国すべてに共通する課題でしょう。
「人生百年」と謳われる未知の世界は、
豊かでありながらも、未来に希望を見出しにくく、
不安があふれる世界です。
ここでは、60歳の還暦は、
かつてのように人生の終わりを意識し始めるのではなく、
新しく生き始める年代といえるかもしれません。
インターネットの普及、AIの進化によって、
僕たちの子供世代、孫世代も平等に知識や情報を共有しています。
子供や孫たちと、さらにそこに加わるであろう
AIやロボットたちと、
どんな人生を送り、どんな社会を築き、
どんな未来をめざせばいいのでしょうか。
そのために、あなたの生きた証、活動の足跡は、どう生かされ、
のちの時代にどんな響きを残すのでしょうか。
もし、あなたが、高塩さんに終活映像や人生ストーリーの
制作を依頼する機会があれば、
ぜひ、過去の記憶とともに未来へ向けても想像力を広げて、
想いを盛り込んでください。
Deathフェスと有機還元葬のnanowaプロジェクト
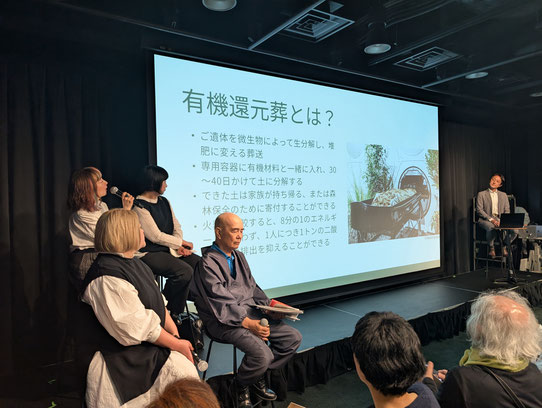
●私が死んだら、お花たちよ
そのむかし、1970年代のこと。
イルカが「いつか冷たい雨が」という歌を歌っていた。
イルカとは「なごり雪」を歌う、
あのフォーク歌手のイルカのことだ。
「いつか冷たい雨が」の歌詞のなかには
「いつか私が死んだら、お花たちよ、そこから咲いてください」
といった一節があったことを覚えている。
自分が死んだら花になる・木になるという
夢想を抱く人は少なくない。
最近の樹木葬の流行は、そんな人々の願いを反映したものだろう。
この樹木葬、見た目は確かに美しく、
「自然に還った」感があるが、
粉砕した遺骨を樹木のあるエリアに撒く・埋めるだけなので、
実際に亡くなった人の遺体を栄養分にして
植物が育つわけではない。
ところが、これを実践する葬法が欧米で普及し始めている。
それが「有機還元葬」、別名「堆肥葬」である。
遺体を土の中に埋め、微生物を使って分解し堆肥に変える。
イルカの歌のとおり、あなたが死んだら、栄養のある土になり、
そこから花が咲き、木が育ち、森にもなりますよ、というわけだ。
●神仏の道理に悖る新葬法の開発者たち
環境問題の影響から、欧米では2000年代頃から
地球環境に負荷をかけない葬法=遺体の処理方法、
つまり従来の土葬や火葬以外の方法が
いろいろ考えられてきた。
考える人たちは真剣だが、
それを伝えるメディアの報道の多くはキワモノ扱いで、
「ほら、こんな面白い、でもちょっと怖い人や会社がありますよ」
といったニュアンスが強かったように思う。
はっきりと決めつけるわけではないが、
当時、葬儀に関してはまだ伝統的な宗教を尊ぶ傾向が強く、
新しい葬法の開発者たちは、神仏の道理に悖る者ども、
人間の尊厳をないがしろにする罰当たりな輩と見られていたのだ。
それがこの数年、潮流が変わってきた。
インターネットが浸透し、AIが広まり、
時代が変わり、世代も変わり、
「土に還る」「地球に還る」という思いを、
たんなる夢物語でなく、リアルなものとして、
肯定的に捉える人が世界各地で、
特に若い世代の間で増えているのではないかと思う。
●世界で普及の兆しを見せる有機還元葬
「有機還元葬」はそうした新葬法の代表格で、
呼び方や細かいシステムは違えど、
アメリカとドイツで幾つものスタートアップ企業が、
すでにビジネスとして営業を始めている。
営業しているということは、イコール、
法的に認められているということ。
実際、この先駆者たちは自治体に対して、
何度も粘り強くプレゼンを続け、ついに認可を勝ち取った。
ワシントンで、ニューヨークで、カリフォルニアで、
アメリカに限って言えば、2025年4月時点で
およそ4分の1の州、計12州で合法化されている。
メディアも、もはやキワモノ扱いできない状況だ。
ワシントン州 (2019年)
コロラド州 (2021年)
オレゴン州 (2021年)
バーモント州 (2022年)
カリフォルニア州 (2022年、施行は2027年)
ニューヨーク州 (2022年、施行は2024年8月7日)
ネバダ州 (2023年)
アリゾナ州 (2024年)
メリーランド州 (2024年10月1日施行)
デラウェア州 (2024年)
ミネソタ州 (2025年7月1日施行予定)
メイン州 (2024年)
僕はコロナ前から仕事で新葬法に関する記事を書いており、
冒頭のイルカの歌を思い出し、
有機還元葬はなかなかいいんでねーの、
土より生まれて土に還る。
僕も終わりが来たら、地球の一部になりたいと思っていた。
しかし同時に、これらは海の向こうの話で、
日本では到底無理だろうとも考えていた。
自分や家族をまんま土に埋めて、微生物に食わせるなんて、
考えただけでおぞましく、ほとんどの日本人は
拒否反応を示すに違いないと思いこんでいたのだ。
ところが、この有機還元葬を実現しようと
動いている人たちがいるのを知って仰天した。
それも「できればいいね」といったレベルでなく、
本気中の本気なのだ。
●nanowaプロジェクトの活動
このプロジェクト「nanowaプロジェクト」は、
年内にまず動物で、実際に国内で有機還元葬を行う予定で、
学者・研究者や、ある有名企業も支援に動いているという。
ちょうど1か月前、「4月14日は“よい死の日”」と謳って、
渋谷ヒカリエで6日間、Deathフェスという、
死をポジティブに考えようというイベントが開かれたが、
そこでもトークセッションの一つとして、
「有機還元葬」のコンセプト、
そして実現に向けた活動について語られた。
反響は大きく、
日本でも有機還元葬(堆肥葬)への潜在的なニーズは
決して低くないようだ。
実現にはもちろん法整備が必要で、
かなり厳しいのではないと推測するが、
この国は前例さえあれば、特にそれが欧米のものなら、
意外とあっさりクリアできてしまう可能性もある。
少なくとも安楽死・尊厳死よりもハードルは低そうだ。
まさか、自分が生きている間に、
この葬法がこの国で実現するとは(まだしてないが)
思いもしなかった。
「nanowaプロジェクト」のスリリングな展開は、
これから注目に値する。
認知症になると、それまでの愛はどこへ行くのか?
母の日。
スーパーマーケットがいつも売っているデザートに
ポチっと赤いシールを貼り付けて、
「花より団子」の「母の日スペシャル」を
用意していたので、買ってきた。
「2個入りだけど、母の日だから、おかあさんは1個。
僕らは子供だから半分ずつね」と言っても、
何のことやらさっぱり認知しない様子。
だが、何か、普段あまりお目にかからないものが出てきた、
しかも自分の好物のカテゴリーに入るものだ、
ということは何となくわかるらしい。
けれどもやっぱり1個まるまる食べてしまっては悪いと思うのか、
半分残したので、僕とカミさんで半分ずつ食べる。
これは母の愛なのか?
そう言うと、カミさんは、
「わたしたちに恩を売っておいたほうが、
後から何かと有利だと算段しているんでしょ」
と、クールな分析をする。
親子ではあるが、この二人の相性はイマイチなようだ。
義母は時々、僕に対して「だーい好き!」と言って、
ベタベタ抱きついてくる。
たぶん、毎日、お菓子をあげて面倒を見るので
そうなるのかと思うが、相性はいいのかもしれない。
好きでいてもらったほうが、
ある程度、言うことを聞いてくれるので、
こっちとしては助かる。
デイサービスのスタッフに対しても、相性のいい・悪いはある。
以前、毎週土曜日の送迎に来ていた
Sさんという30前後の若い男性が、大のお気に入りだった。
その人はもう2年以上前に辞めてしまったのだが、
いまだにその記憶が残存しているのか、
土曜日の朝は概してご機嫌が良く、
なんとなくウキウキ感があるようだ。
待てど暮らせど、もうその人は来ないのだが・・・。
相性のいい人(波長が合う人)とは居心地の良さを感じる――
これも一種の愛情・愛着と呼べるものだろう。
時々、認知症になると人間が生きてきた中で
培った愛情なるものはどこへ行くのか?と考える。
親でも夫でも子供でも、
若い頃の恋愛の相手や友だちでもいいが、
人間、成長過程で誰かを愛し、愛されることで、
あるいは仕事や趣味などに愛を注ぐことで、
いろいろな関係を紡ぎ、人生を築いていく。
認知症になると、そうした愛の記憶は、ほぼすべて初期化され、
食欲などの本能的な部分と、
自分が安全に、有利に生活できるための打算が、
非言語されて内側に残る。
打算というと印象が悪いが、
これもまた生きていくための本能の一つなのだろう。
その一方で、幼い子供や動物を見て「かわいい」と感じたり、
花をきれいと感じたりする原始的な愛情は
ずっと消えるに持ち続けるようだ。
豊かな時代に生まれ育った僕たちは、
周囲にあふれかえる「愛」という言葉に洗脳され、
この得体のしれない概念に、過剰に期待する傾向がある。
人間には愛があって然るべき、
愛がなければだめ、人を愛せ、みたいな。
女と男の愛、家族の愛、至上の愛。
時はあまりにも早く過ぎ、喜びも悲しみもつかの間だが、
ただ一つ、愛の世界だけは変わらない――
昭和歌謡にそんな歌詞の歌があった。
でも、そんなことはないのだ。諸行無常だ。
愛の世界も変わっていくし、失われていく。
だがしかし、それはそう悪いことでも、
悲しいことでもないのかもしれない。
純粋でありながら、どこか邪で、ご都合主義的。
義母からは、人間のニュートラルな状態とは
「こんなもんよ」と教えてもらっているような気持ちになる。
ありがとう、おかあさん。
新刊「鉄道マン発 映像調理師® 高塩博幸の人生甘辛レシピ」
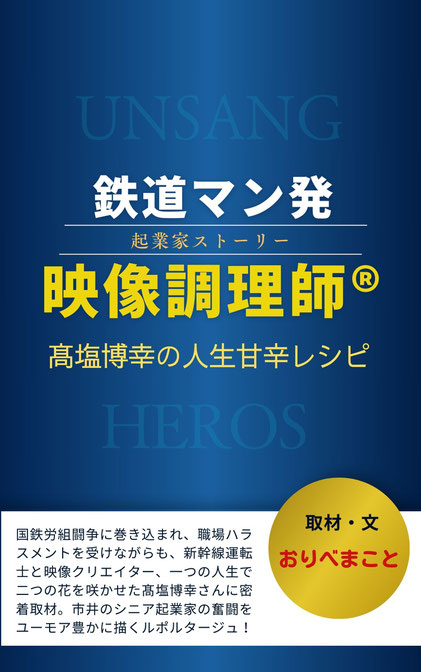
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
かつて新幹線を走らせた男が、
今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。
本書「鉄道マン発 映像調理師」は、
シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追った
ルポルタージュです。
高校生だった高塩少年は
祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に
国鉄に入社。
その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、
JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。
しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。
それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、
還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?
映像クリエイターとしての第二の人生では、
自らを「映像調理師®」と名乗り、
終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。
「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。
運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、
クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、
学ぶべきものがたくさんあります。
人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。
足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、
第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。
「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?
「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、あなたも勇気をもらえるはずです。
本書は単なる成功物語ではありません。
昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、
失敗や挫折を乗り越え、
常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、
そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。
人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵が
ここにあります!
スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」
一昨年、としまえんの跡地にオープンした
「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。
正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京
‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。
約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る
ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。
●見どころ満載6時間ツアー
映画ハリー・ポッターシリーズや、
ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の
舞台裏を体験できる。
映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、
実際に撮影で使われた小道具などが展示され、
視覚効果を使った体験型展示もある。
初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、
音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。
かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも
満足のいくツアー。
6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。
施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。
映画ハリー・ポッターシリーズは、
ほぼ2000年代に制作されており、
CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。
その分、アナログ的というか、
昔ながらの手作りの部分も残っていて、
セットや小道具などの作りこみがすごい。
魔法学校の教科書など、映らないページまで
しっかり書き込まれており、
映画スタッフの間で受け継がれてきた
「魂は細部に宿る」の精神が生きており、
職人的な意気込みが伝わってくる。
でも、こういう部分は果たして、
今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?
コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?
「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。
映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。
そんな言い方もできるのかもしれない。
●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも
というわけで、このツアー後、
アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで
全8作を一気見した。
(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)
主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、
映画各話のトーンが変わっていく。
第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、
ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる
中盤から後半にかけて、
ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。
そして、やっぱり最終作における謎解き――
ハリーの運命をめぐる、
ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。
何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、
演者の子供たちが青年に成長していく過程は、
さすがに機械では実現できない。
それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、
やはり空前絶後の作品だろう。
こんな作品は二度と作れない――
と思っていたら、
何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。
キャストはもちろん全とっかえ。
(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)
映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、
出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。
製作はすでにけっこう進行していて、
今年の夏には撮影開始予定とのこと。
製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。
1作につき1シーズンで、最低7シーズン。
後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。
いずれにしても10年スパンで、
映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。
この時代にすごい構想だ。
「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。
このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。
どうしても映画版と比較してしまうだろうが、
かなり楽しみにしている。
小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。
ジャイアント太鼓in府中
昨日、府中駅から東京競馬場に向かう途中、
出くわした、直径2メートルはあろうかという大太鼓。
バットみたいなバチで打つと、
すごい音が街中に響きわたる。
毎年4月30日〜5月6日の1週間、
大國魂神社を中心に府中市内で開催される
「くらやみ祭り」の一つ、「大太鼓送り込み」だ。
東京都の無形民俗文化財に指定しているらしい。
初めて見たが、間近で見るとすごい迫力。
偶然出会えてラッキーだ。
それにしても、この太鼓の皮は何だろう?
大きさからして牛以外に考えられないが、
どうやって作っているのか気になった。
ぜひ職人さんの仕事を取材してみたい。

おりべまこと電子書籍
認知症の
おかあさんといっしょ2(に)
https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99
無料キャンペーン終了しました。
ご購入いただいた方、ありがとうございました。
よろしければ、レビューをお寄せください。
引き続き、AmazonKindleにおいて、
¥500で販売中です。
東京競馬場ローズガーデンで漫遊
どこに行っても混雑しているゴールデンウイーク。
穴場はないかと、大穴狙って府中にある東京競馬場へ行く。
大あたり!ガラガラだ。
土日は競馬はやっていない。
お目当てはバラである。
東京競馬場にはバラ園――ローズガーデンがあって、
無料開放しているのだ。
6月1日の日本ダービーに合わせて調整しているので、
見頃としてはまだ少し早いが、十分に美しく、見ごたえがある。
全体が7つのエリアで構成されており、
300品種を超えるバラと脇役の小さな花・葉・草も充実している。
歩いているとロンドンの公園にいるようだ。
歴代のダービー馬の記念碑と、騎手の人形がかわいい
ダービーホースアベニューもいい感じだ。
そして何より有名な庭園と違って、
あまり知られていないので来園者が少なく、すいていて、
ストレスフリー。ついでに入園料もフリー。
人の映り込みなども気にせず、写真も好きなだけとれる。
テーブルやベンチもたくさんあるので飲食も自由だ。
だだし、自販機も含めて飲食関係の販売施設はないので、
府中駅周辺でドリンクとかサンドイッチとか
お弁当とか持っていくといい。
連休はもう終わりだが、5月・6月の平日はおすすめ。
正門前に電車の駅があるが、
競馬が開催される土日しか運行していないので、
アクセスは府中駅から。ぷらぷら歩いても15分程度です。

おりべまこと電子書籍
認知症の
おかあさんといっしょ2(に)
https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99
5月6日(火)15:59まで無料キャンペーン開催中。
「認知症のおかあさんといっしょ2(に)無料キャンペーン開催中」

「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。
「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。
幻の家族と会話する義母。
笑いあり、涙あり、驚きありの認知症介護エッセイ。
認知症になっても人生は続く。
むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。
この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、
ユーモアとリアリティで描き出しています。
忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。
もくじ
- 幸せの歌と認知症の女
- 春だけど自分にいいこと何かやってる?
- サスペンスフルな認知症映画「ファーザー」
- 蛭子能収さんと「with弱者」の社会の実現について
- 認知症 花のアートワーク
- 二度と洋食屋には連れていくべからず
- 認知症患者に安心とハピネスを
- 食卓のマナーと認知症
- また今日もざしきわらしがやってきた
- 赤ちゃんはおとなになって働いています
- 要介護認定更新の日
- 認知症と回想療法士
- リス系認知症患者の冬じたく
- 京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族
- 認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉
- 認知症患者のごあいさつを受け止められますか?
- みかんせんべいに秘められた物語
- 魔女っ子カーチャン
- 親の介護は5年で卒業(というマイルール)
- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる
- 認知症患者の純粋な「かわいい」の価値
- 鏡の国のお義母さん
- 「痴呆症」は老害ワード?
- 義母の入院
- 食べ物の恨みは死ぬまで残る
- 入院していたことなんて記憶にありません
- お母さんといっしょの夏休み
- 義母の回復と阿佐ヶ谷の七夕まつり
- 笑える遺影
- 秋の最後の日の散歩
- 年末の認知症ミステリー
- 義母のお正月スペシャル
- 90歳は人生卒業の齢?
- 生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること
- 認知症になっても人生は続くか?
- AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する
(全36編採録)
今また、唐十郎 襲来!
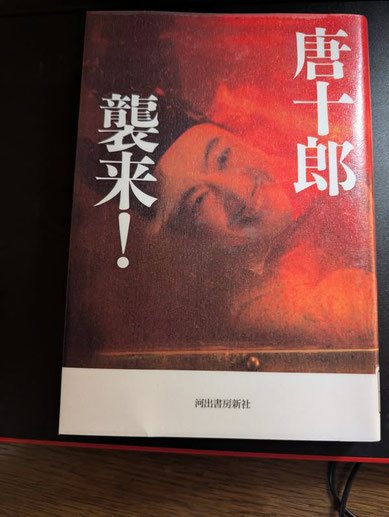
かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。
昨年11月に出された追悼本
「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。
現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している
評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。
同氏を含め、30人以上の人が、
それぞれの「唐十郎体験」を、
証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、
様々な形の文章で語っている。
中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。
もちろん、過去の原稿を転載したものだが。
あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、
あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。
蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、
二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。
唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。
●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏
特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として
長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、
まだインターネットがなかったので、
この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、
良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、
事実を大いに誇張した伝説として語られていた。
1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、
寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、
そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――
しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった
アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、
当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、
途方もないスケールとエネルギーを持った、
天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。
不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、
ほほえましい思いになった。
特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――
という話には笑ってしまった。
昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、
一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。
李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、
唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、
ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。
そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、
今の自分を支える柱の一つになっている。
●久保井研のインタビュー:
後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル
現在、座長代行・演出として唐組をまとめる
久保井研のインタビューもよかった。
彼と編集者・樋口との対話で、
状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を
創作活動の根源にしていた唐十郎が、
唐組として再出発するにあたり、
「新しいメディアによる新しい現実を描き、
豊かさの中で右往左往する人間を描く」という
手法に切り替えたという話は、とても興味深い。
過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、
テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、
唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。
どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、
パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。
唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、
半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。
●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点
そして、もう一つ感動的だったのが
「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、
明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。
1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、
彼らの明治大学実験劇場は、
都市の中での演劇に距離を置こうと、
茨城県の農村に地方公演に出かける。
都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、
どのように芝居をやり、何を得たのか?
タイトル通り、「唐十郎の原点」が、
まるで昨日のことのように鮮やかに、
朴訥な文章でつづられている。
最後のほうは読みながら涙してしまった。
本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、
生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、
後進に受け継がれた。
1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。
あれから1年。
永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍
認知症のおかあさんといっしょ2
5月6日(火)15:59まで
無料キャンペーン開催中。
もくじ:
・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族
・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉
・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?
(ほか 全36編採録)
義母の「むき出しの欲」から人生の幸福度について考える

先月、義母をショートステイに預けたら、
ちょっとしたトラブルがあった。
他の利用者が持っていたぬいぐるみを
「これは自分のものだ」と言い張り、
ガメてしまったのである。
どうやらその持ち主さんは安心のために、
いつもそのぬいぐるみを持ち歩いているらしいが、
義母に取られて、かなりパニクったようだ。
怒り心頭だったのか、泣き喚いたのか、わからないが、
とにかく大げんか。
スタッフの人は双方をなだめるのに苦労したらしい。
とはいえ、そこは認知症のありがたいところで
執着はいつまでも続かず、5分か10分、
気をそらすと忘れてしまう。
そして、それ以降は義母の目に触れさせない
という措置を取って、一件落着したらしい。
まるで保育園や幼稚園の幼児みたいで、
やれやれという感じだが、ここのところ、
こうしたトラブルが増えてきた。
家のなかでも、自分の食べ残したお菓子や食器、
家族共用のタオルや、使用済みの包み紙などに対して
「わたしのものだ」と異様な執着心を見せ、
それを取り上げようとしたカミさんとケンカになることが多い。
こうした「物に対するむき出しの欲」は
認知症患者特有のものというわけでなく、
今どきの年寄りの「あるある現象」だと思う。
人間らしいと言えば人間らしいし、
子供の場合は可愛さにもつながるが、
おとなの場合は、そうではない。
齢を取ったら聖人のように悟るべきだとは言わないが、
欲に取りつかれた老齢の人間の姿は、
やっぱり醜いなと思うし、哀れさを感じてしまう。
3年前に亡くなった実母(義母より6歳上)には、
こうした傾向はほとんどみられなかった。
いっしょに暮らしていなかったので確かなことは言えないが、
帰省で何泊かした時見ていても、
娘である妹とケンカすることはなかったし、
妹からそれで困ったという話も聞かなかった。
そして施設に入ってからは、
神様の領域に入ったような、穏やかな顔をしていた。
二人の違いは、人生全体の幸福度の違いなのかなと思う。
やはり幸福度が低く、
不満やストレスが多い生き方をしていると、
あるところまでは我慢が効いて体裁を保っていても、
高齢化して社会人としての枷が外れてしまうと、
抑えつけていた欲がむき出しになってしまう。
さらに言うと、母世代(戦前生まれ)の女性は、
やはり伴侶との結婚生活の影響が大きいのだと思う。
僕の両親は、適当に仲良く暮らしていて、
父は一切家事をしない人だったが、
あまり母にやかましいことは言わなかった。
7回忌なので悪いことは言いたくないが、
義父は亭主関白で、かなり義母の「しつけ」にうるさく、
彼女の希望を抑えつけ、
単独で外出することをめったに許さず、
家に縛りつけていたらしい。
いっしょにあちこち旅行に出かけるなど、
表面的には仲良し夫婦と見られていたようだが、
その見た目は、義母が我慢することで
成り立っていたのかもしれない。
もちろん、幸福度はそれだけで決まるものではないだろうが、
いっしょに暮らす人間との相性はかなりウェイトが高い。
今、女性の生き方は昔と比べて多様化して、
もう「すべては男次第、亭主次第」というわけではない。
結婚式のころはテンションが上がっているので、
互いに「幸福にします・なります」と、
ペロッと言えちゃうが、
数年たって、こりゃだめだなと思ったら、
迷わずさっさと離婚したほうが人生を汚さずに済む。
今の日本で「我慢が美徳」と思って生きていると、
欲望むき出しの醜い高齢者になるリスクが高まるのだ。
義母には申し訳ないが、つくづくそう思う。
彼女の名誉のために言っておくと、
欲にかられるのは、あくまで部分的であり、
四六時中そうなっているわけではない。
むしろ普段とのギャップが大きいので、
悲しい気分になり、考えさせられるのだ。
いずれにしても、愛されるジジババにならなくてもいいが、
ある程度きれいで、
子供たちから多少はリスペクトされる人間にりたい。

★おりべまこと電子書籍
Amaazon Kindle
認知症のおかあさんと
いっしょ2(に)
本日5月1日(木)16:00~
6日(火)15:59まで
無料キャンペーン開催。
笑いあり、涙あり、驚きあり。認知症になっても人生は続く。
社会が抱える高齢化問題の一面を、
ユーモアとリアリティで描き出し、新たな視点で捉え直す試み。
福祉関係者や医療従事者には現場の生の声として、
一般読者には自分や家族の将来の姿として、
多くの示唆を与えてくれるでしょう。
ユーモアを失わない文体と鋭い観察眼が、
重いテーマを読者に負担なく伝える稀有なエッセイ集です。
昭和の価値観はどこまで生き延びるのか?

昨日は、昭和100年の「昭和の日」だった。
最近は、なんでもデオドラントしないと気が済まない
ホワイト社会が進行中で、
昭和の価値観が次々とバッシングされている。
中居正広の性暴力問題から発展したフジテレビの問題しかり。
八代亜紀のヌード写真入りCDの問題しかり。
●性暴力を受けた女性がセクシー写真集を出すふしぎ
中居くんを擁護するわけではないが、性被害を受け、
PTSDになったという元フジテレビの女性アナが、
自身でカミングアウトした本や
セクシーな写真集を出しているのは、僕には理解しがたいし、
同性の間でも首をかしげている人は多いのではないか。
いろいろ理屈や事情があるのだろうけど、
いちいちそれに耳を傾ける人はそんなにいないだろう。
そしてまた、不思議なことに、彼女のこうした奇異な行動には、
僕が知る限り、あまり批判的な意見を聞かない。
被害者なのだから、
ということで優しくしなくてはいけないからか?
下着や水着の写真集を買うことで彼女を応援しようということか?それとも中居くんの擁護者・性暴力の容認者と思われるのが
嫌だから?
これもやっぱり僕には理解できない。
まだまだ昭和の価値観に染まっている人たちは、日本人の大半を占めていると思うが、みんな、このホワイト社会化についていっているのだろうか?正直、僕は息切れしている。
●昭和歌謡の女性歌手は花魁である
八代亜紀さんのCDの件は、裁判沙汰に発展する気配だが、
当のレコード会社は、そうなる前に発売してしまった。
転売目的で買った人も大勢いるようで
早くも高値を付けて売られている。
これは裁判になる前に商売完了という筋書きだ。
裁判に持ち込まれたとして、どんな裁きになるかはわからないが、倫理的にはともかく、
このレコード会社の社長が法律的に重罪になるとは思えない。
今でこそ「昭和歌謡」は、音楽通からもリスペクトされているが、昭和の時代、歌謡曲の歌手、
特に女性はクラブのホステスとほぼ同様の扱いだった。
という言い方に語弊があれば、江戸時代の遊郭の女郎、
あるいはもう少し上の花魁という扱いである。
今年のNHKの大河ドラマ「べらぼう」の主な舞台・吉原は、
江戸最大の遊郭があった街。
とびきり歌のうまい花魁は大人気で、
彼女のためなら大金を貢ぐという旦那は大勢いただろう。
ただし、社会的には身分制度の埒外で、
身請け制度があったことからも、
人間ではあるが「商品」としてのニュアンスが
強かったと思われる。
昭和はまだこうした江戸時代の芸能文化の流れを引きづっていて、歌ったり踊ったり芝居をしたりする人たちは、
一種の「商品」として見られていたと思われる。
たとえ八代さんほどの大歌手だとしてもだ。
だから「権利を買い取って所有している」という、
かの社長の主張は、
(下品だが)昭和の価値観からすれば正当なものだし、
その権利を使って商売するのが、どうして悪いのだ?となる。
亡くなって自分の意思を示せない八代さんの写真を出すことには
僕も反対だ。
だが、かといって
「八代さんが生きていたら絶対に認めないはずだ」という意見は
勝手な決めつけだろう。
僕は「多くの人に自分が若い頃の美しい姿を見てほしい」と
希望することも十分あり得ると思う。
女性の方々はどう思うだろうか?
●人間臭さ・エロ臭さにおう昭和の価値観はいずこへ
エロい方向の話に偏ってしまったが、
今後、AIが浸透し、様々な情報が整理され、
管理社会・デオドラント社会が進展してくると、
その一方で、ある意味野蛮で、汚く、
下品でいい加減な昭和の価値観は
ますます重要性を増してくるだろう。
なぜなら昭和が(もしくは20世紀が)人間による、
最後の、人間臭い時代、
最後のエロ臭い時代として認識されるようになるからだ。
その後、人間臭さ・エロ臭さを脱臭された人間はどこへ行くのか?昭和の価値観はどこまで生き延びるのか?
とても楽しみである。
それにしても、こんなことを考えている時点で、
僕はもう、時代に取り残された昭和人なのだろうと思う。
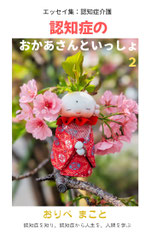
認知症のおかあさんといっしょ2(に)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99
5月1日(木)16:00~6日(火)15:59
6日間無料キャンペーン開催!
この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、ユーモアとリアリティで描き出しています。忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。
認知症患者専門店は商売繁盛?

先日、義母を美容院に連れて行った。
前にも書いたが、お抱え美容師(?)のTさんは、
腕はそこそこだが、接客の達人である。
義母は普段ニコニコしているが、
自分の体をいじくられるのが大嫌いで、
医者などでも随分と手こずる。
なので、正直、なるべく連れていきたくない。
美容院も何かされる、どこかいじくられるに違いないと、
カンがはたらくのだろう。
カミさんと二人がかりで、
できるだけご機嫌のいい状態で連れていくのだが、
店のドアの前まで来るとさっと顔色が変わり、足が止まる。
断固として入ろうとしないこともあり、
そういう時はやむを得ず、そのまま近所を
一回りして戻ってきたりする。
しかし今回はちょうどいいタイミングで、
Tさんがドアを開けてくれて、目が合うと
義母の表情がふわっと崩れた。
Tさんは、認知症患者の扱いに慣れているのか、
それとも単純に相性がいいのかわからないが、
一旦店に入ってしまえば安心してまかせられる。
すごく丁寧な接客というわけでなく、
適度にフレンドリーなところがいいのだ。
何かあったときのために、
一応、僕たちは店内の待合スペースにいるのだが、
これまでトラブルが起こったためしはない。
今回はピンクっぽい金髪にして
「ほぉら、かわいくなりましたよ」と言われ、
義母はご満悦である。
家からすぐ近くというわけでなく、
徒歩15分程度(義母を連れていると20分程度)。
あちこちいろんな店を試したが、
もうここしかないと、この2,3年は完全に御用達である。
もしこれから認知症患者が増えるとしたら、
そういうお客に対しても、柔軟に対応してくれる店は重宝され、
繁盛するだろう。
どのジャンルにも「認知症患者専門店」
なんてものができるかもしれない。

おりべまこと電子書籍
「認知症のおかあさんといっしょ2」
https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99
5月1日(木)16:00~6日(火)15:59まで
無料キャンペーン開催。お楽しみに!
「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。幻の家族と会話する義母。笑いあり、涙あり、驚きありの認知症介護エッセイ。認知症になっても人生は続く。むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、ユーモアとリアリティで描き出しています。忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。
21世紀の「傷だらけの天使」(小説版)をどう読むか?

「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」は、
作家・矢作俊彦が2008年に出した小説(講談社文庫)である。
題名で察しがつくように、これは「傷だらけの天使」の小説。
30年後の後日談だ。
今年になってからAmazpn Primeで
「傷だらけの天使」全26話を見た僕は、
頭の中で、かつての傷天熱が再燃。
いろいろネットで情報をあさり、書籍として出版されている
解説本「永遠なる『傷だらけの天使』
(山本俊輔・佐藤洋笑/集英社新書)」を、
そして、この小説を読んでみた。
●1か月近く書けなかった感想
あの衝撃の最終回でラスト、
いずこともなく去った小暮修(萩原健一)は、
30年後、どうなったのか?
それを描いた物語となれば、
傷天ファン、ショーケンファンなら、
興味を持たずにはいられないし、ぜひ読むべき作品である。
……と言いたいところだが、
同時に「読まないほうがいいよ」とも言いたくなる内容である。
思い出は思い出のまま、大事に取っておいたほうがいい。
昔の恋人にはもう一度会おうなんて思わず、
かつての美しい面影だけを抱きしめていたほうがいい。
正直、そんな心境になってしまった。
これを読み終えたのは3月末だったが、
どんな感想を書けばいいのか、うまく整理がつかず、
かれこれ1か月近く経ってしまったのは、そのせいだ。
●トリビュート小説の傑作だが
誤解がないように言っておくと、
「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」が、
読むに堪えない駄作というわけではない。
むしろその逆で、これは傑作だと思う。
探偵小説、ハードボイルド小説、エンタメ小説、
どの呼び方が一番いいのかわからないが、
とにかく、こうしたジャンルにおいて、
構成、文体、表現、リズムなど、
相当質の高い作品であることは確かだ。
作者自身が傷天ファンであり、
読者も完全に傷天ファンを対象としているので、
原作ドラマに対するリスペクトも十分すぎるくらい十分。
たとえば冒頭部分は、僕たちがこぞってマネをした、
あの伝説的なオープニング朝食シーンの
完全なオマージュになっている。
同時に、30年後、55歳になったオサムの現状を
ビビッドな表現で読者に伝える始まり方になっており、見事だ。
この冒頭部分が象徴するように、
トリビュート小説として非常によくできており、
いちいち納得できる。
しかし、だからこそ、この物語が、
多くの傷天ファンに与えるダメージ(?)も
大きいのでないかと思う。
少なくとも僕にとってはそうだった。
●萩原健一と市川森一の置き土産
1974年秋から1975年春にかけて日本テレビ系で放送された
「傷だらけの天使」は、
当時、その圧倒的存在感で人気を誇った俳優・
萩原健一を主役にした、
コミカルさとハードボイルドテイストと
人情味を併せ持つ探偵ドラマで、
斬新な内容・演出と、日本映画界を代表する監督らが参加した
「テレビ映画」として話題になった作品だ。
視聴率は振るわなかったが、
その「カッコ悪いカッコよさ」「ろくでなしの生き様」は、
当時の若者たちの心にずっぽり突き刺さり、
大量のファンを生み出し、半世紀を超えて続く伝説となった。
そうしたファンの一人である作者の矢作俊彦は1950年生まれ。
まさしくショーケンと同級生である。
彼はこの作品の執筆に際して、
主演の萩原健一と、脚本家の市川森一から承諾を得ている。
市川は登場人物やドラマの世界観の設定をつくり、
26話中、8つのエピソードの脚本を書いた、
脚本陣のメインライター。
いずれも「傷天」を代表する傑作で、
第1話(制作側の都合で放送時は第7話になった)と最終話も
彼のペンによるものだ。
市川は2011年、萩原は2019年に他界しているので、
「魔都に天使のハンマーを」は、傷天の核ともいえる二人が、
矢作に託して残した、置き土産ともいえるかもしれない。
市川は1983年に同名の脚本集を大和書房から出しているが、
その後、何度も傷天復活の話があったらしい。
しかし、幸いなことに(?)、それらは実現しなかった。
制作上の都合もあったかと思うが、
ファンも齢を取った萩原がオサムを演じる姿は
見たくなかっただろう。
そして、萩原以外の俳優がオサムを演じることも
許せなかっただろう。
●小説の世界だから許される30年後の傷天
しかし、小説の世界――僕たちの想像力の範囲でなら、
それは許される。
キャラクターの描写は的確で、
修が話すセリフの文字からショーケンの声が聴こえてくる。
僕たちは、この物語の中で「55歳の小暮修」と出会えるのだ。
それは他のキャラも同じ。
ここには、オサムがヤバい仕事を請け負っていた、
探偵事務所のボス・綾部貴子も、
その右腕として活躍していた辰巳五郎も出てくる。
最終回で横浜港から外国へ逃亡した貴子は、
もはや探偵事務所の経営者などではなく、
六本木ヒルズを根城とする組織のトップとして、
2000年代半ばの日本の政治・経済・産業界を牛耳る
フィクサーとなっている。
同じく横浜港で逮捕された辰巳は、
あの時、貴子に裏切られたのにも関わらず、
相変わらず手下として、舞台裏を跳梁跋扈している。
どちらも年齢設定は還暦をとっくに超えて
70代ということになるが、
超高齢化社会で、
いまだに昭和のジジババが幅を利かす日本においては、
何ら違和感がない。
それぞれの役を演じた岸田今日子・岸田森も、
すでにこの世を去っているが、
ここも想像力を駆使して、加齢し、より妖怪化した
二人の声を被せて読むといいだろう。
●アキラへの想い
そして、物語の中で絶大な存在感を感じさせるのが、
オサムの弟分の乾亨である。
しかし、アキラはドラマの最終回、つまり30年前に死んでいる。
もちろん生き返って登場するわけではないが、
彼はオサムの中でずっと生き続けており、
ことあるごとに心の底からよみがえってくるのだ。
文字通り、天使になったアキラへの追憶。
若かりし時代の、宝のような思い出と、
あの時、彼を見捨て、死なせてしまったという罪悪感。
それがこの物語の軸の一つになっており、
随所に現れる、ドラマから引用したアキラのセリフを読むと、
若き水谷豊のあの声と独特の言い回しが響いてくる。
(断じて、現在の、杉下右京の水谷ではない)
● 在りし日のエンジェルビルも
それぞれのキャラクターとともに、
世界観もきちんと踏襲しており、
オサムが住処としていたペントハウスも、
舞台の一つとして出てくる。
やはり傷天にはペントハウスが欠かせない。
このペントハウスのロケ地として使われた、
代々木駅近くの代々木会館ビルは、
傷天ファンの間で「エンジェルビル」と呼ばれ、
この小説が出版された当時は「不滅の廃虚」として、
まだ健在だった。
オサムだった萩原が亡くなったのが、
令和が始まった2019年3月。
このエンジェルビルが解体されたのが、同じ年の8月。
単なる偶然だろうが、ファンとしては
何らかのつながりを感じたくなる。
●1970年代と21世紀ビギニングとの融合
そんなわけで原作の世界観に忠実に……と言いたいところだが、
あくまでこちらの時代設定は、ゼロ年代半ば。21世紀の物語だ。
30年が過ぎ、もう世界は変わっているのに、
1970年代と同じ世界観で描くのは、逆にウソになる。
作者はそのあたりも心得ていて、
バーチャルワールドや生殖医療などの要素も入れ込んでいる。
1970年代には、ほとんどSF小説・SF映画に出てくるものが、
ここでは現実として違和感なく描かれており、
かつての傷天を、21世紀の物語としてシフトさせているところは
心憎い。
しかも、ゼロ年代半ばといえば、
まだデジタル社会への移行の途上で、
インターネットが今ほど社会に普及しているとは言い難く、
スマホも世のなかに登場していない。
そうしたなかで、こうした要素を駆使して描いたのは、
かなり先進的だ。
●残酷な結末
僕が最初に「読まないほうがいいよ」と言ったのは、
この「21世紀の傷天」の物語世界を形作る
キーマンが存在するからである。
それは貴子でもなければ、辰巳でもない。
他の新たな登場人物でもない。
それは原作ドラマを知る者なら、誰でも知っている人物だ。
物語の終盤、その人物とオサムとの、
二人きりの対決のシーンが描かれる。
まるで目の前で、
あの傷天のアクションが展開されているような見事な筆致。
しかし、そのシーンで、それまでのすべての謎が解け、
物語の文脈が明らかになると、
そのあまりの運命の残酷さに慄然とする。
原作のメインライター市川森一が、ドラマ作りの信条としていた、
とびきり賑やかで楽しい夢と、
奈落の底に落ちるような現実とのコントラスト。
矢作俊彦は、この後日談でも、それをしっかり踏襲した。
55歳になったオサムが、
最後に何と向き合わなくてはならなかったのか。
誰と闘わなくてはならなかったのか。
当たり前のことだが、30年もの月日が経てば、子供は大人になる。
これだけ言えば、原作を知る人は、もうピンと来るだろう。
粗野で風来坊のように生きてきたオサムだが、
彼は家族を大事にする男でもあった。
しかし、彼はそのかけがえのない家族に裏切られてしまう。
「魔都に天使のハンマーを」は、家族の物語でもあるのだ。
読み終えた後、僕は原作の様々なシーンを思い出して、
思わずため息をついてしまった。
そして、やるせない気分に覆われた。
すべて辻褄が合い、すべてが納得できる内容である。
この後日談を、一級のエンタメ小説として構築するためには、
こうするのが最高の手立てだったのだろうと思う。
でもなぁ、こうなるなら、
もう少しダメダメな話でもよかったよなぁと思ってしまった。
最後の最後に、ほんのちょっとした救いはあるんだけど。
●ショーケン死すとも傷天死なず
というわけで、長々と書いてしまった末にもう一つ気付いたのは、
傷天の30年後を描いたこの作品は、
もう20年も前に書かれたものだということ。
この20年の間にまた時代は変わった。
萩原や市川をはじめ、傷天関係者は相次いでこの世を去った。
エンジェルビルも代々木から姿を消した。
でも、その代わりに、U-NEXTやAmazon Primeなどの動画配信で、
多くの世代が、半世紀前の、
若かりしオサムとアキラの活躍を見られるようになった。
物語のなかで55歳になっていたオサムは、
もう後期高齢者の仲間入りをしている。
貴子や辰巳は90代になるだろう。
それでも超高齢化社会では、
この物語はまだ続くのではないかと思わせる。
傷天伝説の一部となった「魔都に天使のハンマーを」。
最初に「読まないほうがいいよ」と言っておきながら、
今さらだが、勇気を出して読んでみることをおすすめする。
青春の思い出の湯に浸るのは気持ちいいが、
やっぱりそれだけだと、今を生きることにはつながらない。
今を生きて、傷天を未来に伝えていきたい。
ショーケンが死んでも、「傷だらけの天使」は死なない、きっと。
80代も20代も、20世紀ロックカルチャーを共有する時代

エリック・クラプトンの来日公演に行ってきた
K君(24歳)の報告を聴く。
「レイラ」はやらなかったが、
いきなり「ホワイトルーム」や「サンシャイン・ラブ」の
クリームナンバー。
80歳で武道館ライブを行ったクラプトンは、
2年前、自ら作った同会場の最年長記録を更新したという。
クラプトンとほぼ同年代と思しき、隣の席のじいさんが彼に向って、まるで孫に語るように
「クラプトンが日本に来るのもこれが最後じゃろう」と語った。
その目は涙ぐんでいたという。
80で1時間半のライブをやっちゃうクラプトンも偉いが、
武道館まで足を運んでくるあんたも偉いよ。
そこで僕も思わずK君に語ってしまった。
いや、おまえ、クリームって、俺が中高生のころは、
すでに伝説のバンドだったんだよとか、
俺の友達が高校の文化祭でクリームのコピーやって
鼻高々だったんだよとか、
ベース、ドラムと3人のバンドで、
協調性やバンドとしてのまとまりとか、曲の完成度とか、
そんなのどうでもいいと思ってる連中で、
いつも崩壊ぎりぎりのところで演奏していたんだぜとか、
「ホワイトルーム」や「サンシャイン・ラブ」は、
1960年代後半の時代精神を描いたの歌詞だけど
、一回りして、今の時代に合ってるかもなとか、
ベースのジャック・ブルースも、
ドラムのジンジャー・ベイカーもとっくの昔に死んじゃったけど、クラプトンはヤクまみれになっても、
女でひどい目にあったり、ひどい目に合わせたりしても、
息子が死んだりしても、
この齢になるまで生きてきた。生き残ってきた。
もうカネも名声も十分すぎるほど手にしているのに、
それでもライブをやるっていうのは、
根っから音楽が好きなんだろう。この際、
死ぬまで日本に来続けてほしいよなとか、
そんなどうでもいいことをえんえん語ってしまったが、
K君は好青年なので、
しっかり相槌を打ちながら、僕の話に耳を傾けてくれた。
正直、僕はそれほどクラプトンファンではないので、
演奏を聴くのはYouTubeで十分と思っているのだが、
わざわざ来日公演に行った、
アート、カルチャー大好きのK君の話は面白かった。
それにしても、80代も20代も音楽が共有できる時代が来るなんて、まったく想像できなかった。
こうして20世紀のポップ&ロックカルチャーは
未来に引き継がれていく。
のだろうか?
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく

「全国初摘発“生成AI”で作成した裸女性の
わいせつ画像をポスターにし販売か 男女4人逮捕」のNEWS。
僕をはじめ、多くの人は、驚きでもなんでもなく、
「やっぱり出たか」
「このタイミングで出たか」といった、
冷静な(?)感想を抱いたと思う。
これはマーケティング的必然。
いくらで売ってたのか知らないが、
リアルな写真集やアダルトビデオと違って、
モデルや女優さんも、カメラマンも、
ディレクターも、ロケ費用もいらない。
コストがかからないので、
売り上げのほとんどは利益になる。
人間、エロいカネもうけ、ボロい金儲けには、
惜しみなくエネルギーを注げるようにできている。
試しに「AI エロ 画像」で検索してみたら、
出るわ、出るわ。
そのほとんどはボカシが掛かって見えないが、
水着や下着付きならOK。
いかに日々、AIエロクリエイターたちが
創造力を発揮しているか、
そのエネルギーたるや、大したものだ。
「わいせつ」と言っても、
アダルトビデオサイトよりだいぶマシなのでは?
と思うが、今回の摘発は今後、
AIを使ってエロコンテンツでビジネス考えてる人たちへの
牽制・見せしめなのだろう。
でもこの先、テクノロジーが
人間の慰安に使われるのは必至だと思う。
ロボットもある程度のレベルに達した後は、
この方面から開発技術が進むのではないか。
今のところ、AI・ロボット相手に性欲をたぎらせるのは、
気持ち悪いし、人間として異常ではないか、
という見方が強いと思うが、
いずれみんな慣れてしまって、
いつの間にか社会的にも認められていくだろう。
むしろバーチャルエロが、
現実世界の性犯罪の抑止力になるのではないか?
そして、肉体を慰めてもらった後は、
心も慰めてもらう、といった形で、
AI・ロボットは恋人や友達や家族に
進化していくのかもしれない。
こんな妄想が、妄想でなくなる日が来るのも、
そう遠い先の話ではなさそうだ。
桜と友だちの遺影と役に立たない記憶
義母を花見に連れて行ったのだが、
地面に落ちているゴミばかり気にしているので
「おかあさん、ちゃんと桜を見な。
あと何回見られるかわかんないんだよ」と言ったら、
「あ、そうか、そうだよね。わー、きれい」と、
妙に素直に納得。
「これが最後かもしれない」と思って花見をする人は、
あまりいないと思うが、
もちろん、そうなる可能性はゼロではない。
めめんと・もり。
と考えたところで、今日(正確には昨日だったか?)が、
昨年死んだ友達の一周忌だということを思い出した。
なので、桜の花に、心の中で彼女の遺影を被せて黙とうする。
用意した遺影は劇団時代の、とびきりかわいい(?)やつだ。
彼女は演劇学校の同級生で、いしょに劇団をやった仲間だった。
この先、桜の季節になると、
いつも彼女のことを思い出すのだろうか?
わからない。
演劇学校や劇団時代やロンドン時代の仲間、
小中高の同級生・友達、
このあたり、たぶん200人ぐらいは、
わりと正確に顔と名前を記憶している。
やっぱり、それぞれ何かしらの良い思い出を共有しているのだ。
もうほとんどの人と会うことはないだろうし、
相手はとっくの昔に忘れているだろうけど。
だから、死んだことを知ったら、
いちいち葬式や墓参りにはいかないが、
心の中で遺影にして弔ってやることはできると思う。
何の意味もないし、何の役にも立たない。
でも、そういうことが自分にとって大事なことだと思える。
生きてる証拠でもあるしね。
おりべまこと電子書籍新刊「認知症のおかあさんといっしょ2(に)」

おりべまこと電子書籍新刊 本日発売!
エッセイ集:認知症介護2
「認知症のおかあさんといっしょ2(に)」
AmzonKindleより500円で発売中。
(本書紹介文より)
「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。
「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。
幻の家族と会話する義母。笑いあり、涙あり、驚きありの
認知症介護エッセイ。
認知症になっても人生は続く。
むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。
この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、
ユーモアとリアリティで描き出しています。
忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。
本書は単なる介護記録ではありません。認知症という鏡を通して、
現代日本社会の価値観や人間関係を問い直す社会批評でもあるのです。「認知症になったら人生終わり」という社会通念に、
著者は半ば同意しながらも、
そこに新たな人生の可能性を見出そうとしています。
福祉関係者や医療従事者には現場の生の声として、
一般読者には自分や家族の将来の姿として、
多くの示唆を与えてくれるでしょう。
ユーモアを失わない文体と鋭い観察眼が、
重いテーマを読者に負担なく伝える稀有なエッセイ集です。
もくじ
- 幸せの歌と認知症の女
- 春だけど自分にいいこと何かやってる?
- サスペンスフルな認知症映画「ファーザー」
- 蛭子能収さんと「with弱者」の社会の実現について
- 認知症 花のアートワーク
- 二度と洋食屋には連れていくべからず
- 認知症患者に安心とハピネスを
- 食卓のマナーと認知症
- また今日もざしきわらしがやってきた
- 赤ちゃんはおとなになって働いています
- 要介護認定更新の日
- 認知症と回想療法士
- リス系認知症患者の冬じたく
- 京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族
- 認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉
- 認知症患者のごあいさつを受け止められますか?
- みかんせんべいに秘められた物語
- 魔女っ子カーチャン
- 親の介護は5年で卒業(というマイルール)
- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる
- 認知症患者の純粋な「かわいい」の価値
- 鏡の国のお義母さん
- 「痴呆症」は老害ワード?
- 義母の入院
- 食べ物の恨みは死ぬまで残る
- 入院していたことなんて記憶にありません
- お母さんといっしょの夏休み
- 義母の回復と阿佐ヶ谷の七夕まつり
- 笑える遺影
- 秋の最後の日の散歩
- 年末の認知症ミステリー
- 義母のお正月スペシャル
- 90歳は人生卒業の齢?
- 生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること
- 認知症になっても人生は続くか?
- AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する
(全36編採録)
「永遠なる『傷だらけの天使』を読む
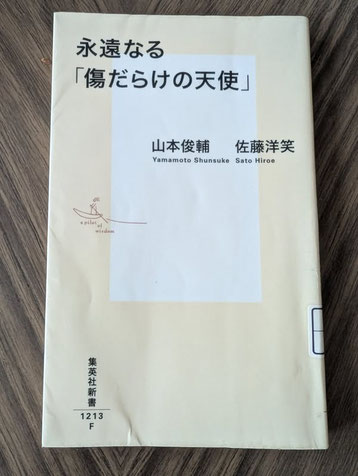
本放送から50年を経たショーケン(萩原健一)主演の
探偵ドラマ「傷だらけの天使」。
僕らのように、リアルタイムで出会った世代にとって、
このドラマは、いわばビートルズのような、
シンボルカルチャー的存在だが、
新たな世代のファンもけっこういるらしい。
その「傷だらけの天使」について解説した本が1年前、
2024年1月に出版されていた。
●貴重な資料集
制作の舞台裏、さまざまなエピソードについて書かれており、
関係者の貴重な証言が盛りだくさん――
と言いたいところだが、もう50年も前のドラマなので、
関係者の多くはもうこの世にいない。
それでも、主演の萩原健一の自伝「ショーケン」のなかで、
彼が「傷天」について語ったコメントを取り上げ、
その裏を取る形で、当時、制作現場に携わったスタッフ
(のなかでまだ健在な人たち)に取材。
どのようにこの名作ドラマが作られたのか、
丹念に探究しており、当時の現場の記憶の証言集・
貴重な資料集として読める。
●当時の名監督らが参戦
1970年代半ばは、まだテレビドラマは
映画より格下と見られていた時代だが、
「傷天」には、深作欣二や恩地日出夫など、
映画の世界で名をはせていた名監督らが参戦。
テレビドラマでありながら、
映画としてのヤバさを前面に打ち出した、
「テレビ映画」という新しいジャンルを開拓した。
そうした挑戦的で、冒険心に富んだ企画ゆえに、
テレビをばかにしていた映画通からも
リスペクトされていた作品なのである。
主演のショーケン自身も企画段階から携わっており、
ここでは、そのあたりの開発ストーリーと、
監督、脚本家、プロデューサーらが、
この企画にいかに情熱を注いでいたかなど、
スタッフにまつわるエピソードが詳しく書かれており、
とても読みごたえがある。
そうしたスタッフの意気込みをフルに反映した、
スタート時の数本には、カオスのような熱気が込められており、
コミカルでありながら、戦後の影を引きづった、
ダークで意味深な社会背景、
若者の夢を描く反面、現実の残酷さを刃物のようにつきつける、
独特のトーンがあって、すごく面白い。
また、同じく開始初期はやたらとセクシーシーンが多いのだが、
監督らがいかにゲスト女優をあおって脱がせたかなど、
今なら完全にセクハラ・パワハラで、
レッドカードとなるエピソードもいろいろ書かれている。
とはいえ、テレビに似つかしくない、
先進的すぎるつくりが災いして、
また、セクシーシーン、暴力シーンが
テレビサイズではヤバすぎて、
視聴者からひんしゅくを買ったため、
ショーケン人気に乗じた割には視聴率は伸びず、
本放送時の評判はさんざんだったようだ。
さらに深作監督らが撮った最初の7本くらいで
予算をかなり使ってしまい、
途中から路線を変更せざるを得なくなってしまった。
しかし、それが弟分アキラ(水谷豊)の存在感を
クローズアップすることにつながり、
このドラマの最大の魅力となる、
オサムとアキラのコンビネーションによる
独特のノリが生まれたのだと思う。
伝説の最終回・衝撃のラストはどう生まれたのか?
ただ、残念なのは、
あの伝説の最終回に関する記述が少ないことだ。
最終回「祭りのあとにさすらいの日々を」の脚本を書いたのは、
メインライターだった市川森一。
市川はオサムとアキラのキャラクターや、
物語の設定を作り、全26話のうち、7話を手掛けた。
(この本の中では、そのあたりの経緯もちゃんと紹介している)
僕は手元にその市川が1983年に出した
脚本集「傷だらけの天使」(大和書房刊)を持っているが、
最終回のラストシーンは、どしゃ降りの雨の中、
死んだアキラを背負って、
ペントハウスの階段を下りてきたオサムが、
「まだ墓場にゃいかねえぞ!」と叫ぶところで終わっている。
それがどこでどうやって、アキラの遺体をリヤカーに乗せて夢の島
(当時は、現在の整備された街からは想像もできない、
大都会・東京の巨大なゴミ捨て場)に棄てて、
いずこともなく去ってゆく――という、
僕らの胸に一生のトラウマを残す、あの、苦く切ない、
衝撃的な幕切れに変ったのか、
そこを丹念に掘り返してほしかった。
最終回の撮影現場を語れる萩原健一も、
工藤栄一監督も鬼籍に入ってしまったが、
まだ一人、重要人物が現役バリバリで活躍している。
アキラ役の水谷豊だ。
アキラ:水谷豊の不在
この本には水谷豊の証言がないのも、大きな穴に思える。
著者もメインキャストのなかで唯一健在の彼に対して、
当然、アプローチはしたと思うが、
取材を拒まれたのかもしれない。
聞くところによると、水谷は「傷天」については
ほとんど語りたがらないという。
アキラ役が嫌いだったとも聞く。
しかし、それは嘘だろう。
彼はクレバーな人なので、いまだに多くの人が「傷天」を、
アキラを愛していることを知っている。
いまだにアキラこそ、
水谷のベストパフォーマンスという人も少なくない。
彼としてはその後、役者として生きていくために
アキラの幻影を振り払う必要があり、
あえて「傷天」について語ることを封印したのだと思う。
けれども、あの野良犬のような惨めなアキラの死から、
その後、半世紀にわたって、ドラマ・映画で大活躍する名優・
水谷豊が誕生したのは間違いない事実。
彼があの役を愛していないわけはない。
改めて「傷天」を通して見ると、
アキラという一見とぼけた少年のようなキャラクターの奥深さ、
それを見事に表現し、独自のものにした
水谷豊の芸達者ぶりに舌を巻く。
それについてはまた、別の機会に書いていきたいと思う。
なぜ今、まだ「傷天」なのか?
もう一つだけ不満を言わせてもらうと、本の紹介文のなかで、
「なぜ『傷だらけの天使』は、
いまだわたしたちの心に残り続けるのか、
その理由と価値を問う。」
とあるのだが、これに匹敵する著者の考察は、
まとまった形で綴られておらず、
肩透かしされた思い、物足りなさを感じる。
それとも、今回はあくまで資料集・証言集の域でとどめて、
考察はまた別の機会で、ということなのだろうか?
それならそれで楽しみだが、
いい機会なので、僕も自分でも一丁考察して、
自分なりの「傷だらけの天使」の本を
書いてみようかと思っている。
かさこ交流会で感じた「人生後半の奮闘」

一昨日、横浜・鶴見で開かれた
かさこさん主催の交流会に行きました。
カメラマン・ライター・Kindle作家のかさこさんは、
ネット発信のエキスパートであり、
ネット集客などの課題に悩む
個人事業主のアドバイザーでもあります。
世の中にはたくさんのフォロワーを集める、
インフルエンサーと呼ばれる発信者がいますが、
そのなかでもかさこさんは、
最も信頼できる発信者の一人だと思っています。
交流会に集まったなかでは、自分を含め、
人生後半を奮闘する人たち、
アラカンや還暦超えてがんばる人たちがたくさんいました。
もちろん、みんな、いろいろトライして結果を出したい、
好きなことをやって稼ぎたい、食っていきたいわけだけど、
こうして自分で仕事を始めて、
ジタバタやっていること自体が、
いいね、すごいなと思うのです。
僕の両親や、認知症になってしまった義母(90)の世代は、
敗戦によってペッシャンコになってしまった日本を復興させ、
豊かな社会を築くことを共通目標としていました。
しかし、僕の世代になると、両親らのような
誰もが共有できる目標は、もはやありません。
それに代わって、僕たちひとりひとりが、
生きる目標や生きがいを
設定しなければならない状況が訪れています。
何らかの形でその設定ができないと、
人生において幸福感を得るのは難しい。
経済的に食えないと生きていけないし、
経済や仕事や情報の奴隷になって、
精神が壊れても生きられない。
「人生百年」と謳われる未知の世界は、
豊かで便利で情報がいっぱいあるにも関わらず、
どうにも未来に希望を見出しにくく、不安があふれる世界です。
ここでは還暦は、
かつてのような定年退職後の余生ではなく、
新しく生き始める年代、と同時に、
人生の終わりも考えなきゃいけない、
かなり複雑な年代といえるかもしれません。
そう簡単に「逃げ切り」はできません。
いろんな面白い人と会って、そんなことを考えました。
みんな、今までも十分がんばってきたかもしれないが、
まだまだがんばろう。
AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する

AIと認知症を結び付けて考えたことがある。
正確にはAIでなくてロボットだ。
施設で暮らす老人の気持ちを、ロボットの介護士が汲み取り、
ルールを破って、彼の脱走を幇助してしまう。
若い頃にそんなストーリーを思いつき、
ドラマのシナリオや小説に書いた。
どれだけAIやロボットが社会に普及しても、
介護の分野はあくまで人間にしかできない仕事。
そう考える人、そう願う人、
そうでなくてはいけないと考える人は多いと思うが、
昨今のAIの進化状況を見ていると、
あながちそうでないかもと思えてくる。
もしかしたらAIやロボットに任せてしまったほうが、
いろいろな面でうまくいくのではないか。
認知症の義母は、ふだんは穏やかでにこやか。
人当たりもよく、ぜんぜん知らない人でも、
道ですれ違うとあいさつを交わす。
ある意味、社交性に富んでいるのだが、
最近、僕たちやデイサービスのスタッフなど、
ケアする相手を手こずらせる問題行動が、だんだん増えてきた。
もともとへそを曲げると頑固になるところがあるのだが、
特に昨年夏に肺炎っぽくなって1週間あまり入院した後は、
子供の「いやいや」みたいなことを頻繁に起こすようになった。
歯を磨かない、爪を切らせない、お風呂に入らない、
薬を飲まない、検温させない、送迎の車から降りない・・・
そういう時にふと考えるのは、
これがケアする相手が、僕たち人間でなくロボットだったら、
こんなに強く拒否するだろうか?
諦めてもっと素直に従うのではないかと思うのだ。
その人の個人データを取り込んで、パーソナリティを把握すれば、
ロボットのほうがもっと優しく、
うまく対処できるのではないかという気がしている。
(もちろんセキュリティ上の問題、倫理上の問題はあるが)
なぜなら比較した場合、機械より人間のほうがリスクが大きい。
少なくとも機械は、人間のように、
互いに嫌悪や憎悪を抱いたり、
ケアする相手に虐待や差別をすることがあったり、
暴言を吐き、暴力をふるったりして、
肉体・精神を痛めつけるようなことはしないだろう。
患者のほうも慣れてしまえば、
むしろ機械のほうがいいと思うかもしれない。
人間のケアラーだったら拒絶する夢想・妄想にも、
機械はうまく合わせて対応してくれる可能性が高い。
また、いっしょに暮らす家族も
苦しい思い・悲しい思いをせず、ストレスを減らせる。
実際、アメリカでは終活相談を、
人間ではなくAIとしたいという人が増えているらしい。
なぜなら、AIは人種や社会的身分、
経済状態などで相手を差別することなく、
平等に扱ってくれるからだという。
「AIのほうが人間よりも人間的
」という逆転現象も起こりうるのだ。
というか、部分的にはもう起こっているといえそうだ。
ちょっと前なら「おまえはSFの見過ぎ・読み過ぎ」と
鼻で笑われていたことが、
この数年のうちに実現するのかもしれない。
AI・ロボット関連の技術にまつわる常識も、
人間の寿命やライフスタイルに関する常識も、
毎日、劇的に変わり続けている。
義母の場合、前兆として、
ちょっと高齢者うつっぽい時期があったようで、
そこから数えると、認知症歴はかれこれ20年。
世の中の標準値では、今のところ、
認知症患者の余命は発症後5~12年となっているので、
それはもうはるかに超えている。
今後、義母のように認知症を患いながら、
長く生きる人は、ますます増えてくるだろう。
認知症の人たちと一緒に生きる社会、
それなりに寄り添える社会をつくっていくためには、
AI・ロボット関連の技術はきっと必要不可欠になるだろう。
彼らのサポートを借りずに、
人間らしさも保てないし、
人間の尊厳は成り立たない。
そんな時代がもう来ているのではないか。
人間と機械が競い合ったり、対抗したりする時代は、
じつはもう終わっているのかもしれない。
3月24日(月)16:59まで無料キャンペーン実施中。
残り1日。まだ間に合います。
ぜひ、この機会にお手持ちのデバイスに入れてください。
読むのはあとからでもOKですよ。
おりべまこと電子書籍:3月の無料キャンペーン開催
本日3月19日(水)17:00~24日(月)16:59 6日間
2019年6月に義母を引き取り、いっしょに暮らすようになった。
以来、認知症が僕のライフワーク(?)になった。
彼女は少なくとも認知症15年選手。
彼女に寄り添おうとすると、
日常生活が容易に非日常の世界にすり替わる。
こうしたケアも一つの人生経験。
ということで日々の格闘の様子を時折ブログに書いている。
エッセイ集はそれをまとめたもの。
それと同時に認知症をネタにした小説も書くようになった。
こんな風に言うと怒られるかもしれないが、
認知症は面白い。
失礼があってはいけないが、
もっと面白がって、いっしょに泣いたり、笑ったり、
怒ったりしていい。
どちらも第2弾を準備中ですが、
ぜひ、あなたもこの2冊で認知症の世界を冒険してください。
認知症のおかあさんといっしょ
認知症の義母との暮らしを楽しくつづる介護エッセイ
認知症を知り、認知症から人生を考え、人間を学ぶ。
ざしきわらしに勇気の歌を
ロボット介護士に支えられて余生を送っている
認知症の寅平じいさん。
彼がある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。
その子を追って木の穴に潜り込むと、
奥には妖怪の国が広がっていた。
認知症×ロボット介護士×妖怪戦争の近未来ファンタジー小説。
おりべまこと電子書籍:3月の無料キャンペーン予告!
明日3月19日(水)17:00~24日(月)16:59 6日間
認知症のおかあさんといっしょ
認知症の義母との暮らしを楽しくつづる介護エッセイ
「いいの、手なんか握って?」
「だって手をつながないと危ないよ」
「いいの本当に? 奥さんはいらっしゃるの?」
「はい、いますけど(あなたの娘ですよ)」
「わあ、どうしよう? 奥さん、怒らないかしら?」
「だいじょうぶです。公認ですから」
「わあ、うれしい。こうしたこと一生忘れないわ」
「喜んでもらえて何よりです」
そんな対話から始まった義母の介護の日々を綴った面白エッセイ。
認知症を知り、認知症から人生を考え、人間を学ぶ。
ざしきわらしに勇気の歌を
認知症×ロボット介護士×妖怪の近未来ファンタジー小説
ロボット介護士に支えられて余生を送っている
認知症の寅平じいさん。
彼がある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。 その子を追って木の穴に潜り込むと、
奥には妖怪の国が広がっていた。
子どもの正体はざしきわらし。
ざしきわらしは最強の妖怪“むりかべ”の脅威から
人間を守るために闘うので、応援してほしいと寅平に頼む。
寅平はこれぞ自分のミッションと思い、
闘うざしきわらしのために勇気の出る歌を歌う。
AIとのコラボをenjoy

AIは無料バージョンで十分。
もちろん、AIを使って何をするかによって違いますが、
文章生成の分野に限っては、どれも無料版でいいと思います。
現在、仕事で使うためにGemini、Claude、ChatGPTと、
アシスタントを3人雇用。
これがその日によって、かなりコンディションが違っていて、
どれが一番いいとは言えません。
あえて言うと、割とまじめな事務系文章はChatGPT。
そつがないけど、いかにもAIです、という感じの文章。
ちょっとユニークで面白い文章を出してくるのはClaude。
Claudeが出してくる文章は、ちょっと人間っぱい匂いというか、
ぬくもりがあります。
もちろん、プロンプト次第ですが。
「もっとくだけて、柔らかくして」と指示すると、
かなりズッコケながらも、
ちゃんと使えるようにそれなりにまとめてくるところが偉い。
Geminiは特徴が言いづらいけど、
前者二つの中間みたいな感じ。
こちらは柔らかい文章を要求すると、
本当にグダグダのを出してきて使い物になりません。
ただ、いちばんタフなのはGeminiで、
取材のメモ・音声起こしなどを資料としてぶちこむ際、
他の2種だと多すぎて受け付けてくれないことがあるけど、
Geminiはかなりの分量でもOK。
それになんといっても付き合いの長いGoogle製なので、
使う頻度はいちばん多いかも。
適材適所で、こういう仕事はChatGPTで、
こういうのはClaudeで・・・と決めようかと思ったけど、
あえてはっきり区分けせず、その時のカンを働かせて、
これはClaude、これはChatGPT、これはGeminiと、
とっかえひっかえ使っています。
もしかしたら、どれかメインを決めて
有料版を使ったほうが捗るのかもしれないけど、
僕はそれぞれに個性があって面白いと思っているので、
あえて絞らず、3人のアシスタントとのコラボを楽しんでいます。
それともう一人、第4のアシスタントが、
GensPark(ジェンスパーク)。
これはリサーチ専用のスペシャリスト。
もうググるのは古い。
検索テーマが決まっていれば、GensParkが次から次へと
めっちゃ効率的に、目的に到達するための情報を出してくれます。
しかも、その情報がどこのサイトにあるのかも
一緒に出してくれるので、ありがたい。
しかもしかも、最近は出した情報を一つにまとめて
レポートにして提示するという芸当をはじめたので、
ただの便利な検索エンジンの枠を超えようとしています。
てなわけで楽しいAIとのコラボだけど、
あくまでみんなアシスタントさんなので、
出されたものは参考文献。
それをちょこっとリライトしてOKのこともあれば、
ほとんど無視して自分で書いてしまうこともあります。
いずれにしてもAIをどう運用していくのかは、
これから仕事を続けていく上での避けられない課題です。
給料は出せないけど、仕事をしてくれたら、
ちゃんと「ありがとう」とお礼をします。
すると皆、ちゃんと誠実に返してくれるのです。
たとえ相手が機械でも結構うれしいし、
疲れが取れる感じがします。
これ、メンタル的にけっこう重要ですよ。
AI、侮るなかれ、粗末に扱うなかれ。
卒業の時は「じゃあまたな」

3月は卒業シーズン。別れの季節。
おとなはやたらと別れを美化し、
その意義を「人間の成長」と結び付けて語りたがる。
でも、子供にとってはちんぷんかんぷんだ。
昭和のころ。
少なくとも僕は小中の卒業式ではそうだった。
ちょっとしみじみしたのは、その少し前の2月ごろ、
卒業文集を作っていた時だ。
クラスのみんなの作文を読むのは好きで、
あいつ、こんなこと書いたのかと、
面白がったり、じんとしたりしていた。
しかし、そのあとがいけなかった。
卒業式の「練習」をやたらとやらされて、
ほとほと嫌になり、早く卒業したいと思ってた。
そんなわけで、晴れのその日のお式が終わって校門を出たら、
「ヤッホー!」と叫び出したいくらい
うれしかったことを覚えている。
(実際には叫ばなかったが)
男子で泣いてる奴なんて一人もいなかった。
女子はもしかしたらいたかもしれないが、記憶にない。
あなたはどうでしたか?
卒業式が終わった後は友達の家に集まって遊んでいたと思う。
なにせ、そこからは宿題も何もない春休みだ。
公立の小中だったので、小6から中1になるといっても、
クラスの大半の連中は同じ学校だった。
私立の学校に行くやつが、クラスで数人いたと思うが、
そいつらはちょっと寂しそうな顔をしていた。
そんなわけで、春休み中、
それまでと全然変わりなくグダグダ遊んでいて、
夕方帰る時は「じゃあな」「またな」と言って別れた。
だけど、それでも、これから自分たちは変わるんだろうな、
今までとは違っちゃうんだろうな、
もう子供ではいられないんだろうな
――という漠然とした予感だけは、みんな持っていた気がする。
僕に残されている「卒業」は、もう人生からの卒業だけだ。
仕事で葬儀屋などの取材をするので、
「永遠のお別れ」とか「さようならがあったかい」とか、
やたらと美しいフレーズを耳にする。
もちろん、それにケチをつけるつもりはないが、
そこはかとなく、
小学校の卒業式の堅苦しさを思い出してげんなりする。
おおげさなのは嫌だ。
あの解放感あふれる春休みの時のように、
「じゃあな」「またな」と言ってお別れするのが希望だが、
そううまくはいかないのかもしれない。
美しい60歳(70歳)が増えると、日本は変わる

かつて化粧品のコマーシャルで
「美しい50歳が増えると、日本は変わる」
というキャッチコピーがあった。
(正確かどうか自信ないが、そういった趣旨のフレーズです)
確か、もう30年近く前だ。
そんな時代はとっくに過ぎ去り、
今やこれを60歳・70歳と言い換えても、なんら違和感がない。
「美しい60歳(70歳)が増えると、日本は変わる」
なんでそんなことを思いついたかというと、
先日、知り合いの女性と話す機会があって、
彼女が去年から年金をもらっていると聞いて驚いたからである。
えー、あの人、僕より年上だったの!?
彼女はさっぱりした性格で、はっきりものをいうが、
おばさんにありがちな、ずけずけという感じではない。
失礼ながら特に美人というわけではないのだが、
何よりもスタイルがいい。
まじまじ観察したことはないが、
ぱっと見た目、スラリと背が高く、脚も長く、適度にスリム。
そして、いつもスポーティーな服装(ときに革ジャン)で、
カッコよく中型のバイクをかっ飛ばしている。
意識しているのかどうかわからないが、
降りてヘルメットを外すときに長い髪がバサッとこぼれる。
映画でマンガで、女性ライダーのこのしぐさに
心臓ズキュンされた男は少なくないはずだ。
うわさによると、もとレディース(暴走族)。
だったかどうかは定かでないが、
ライダースタイルはあまりにもサマになっている。
そんな人が「高齢者」と呼ばれ、年金をもらう。
自分もそうなのに「こんな世界に足を踏み入れているのか」と、
動揺を隠せない。
そりゃ日本も変わるぞ。
よく変わるのか、悪く変わるのかはわからんが。
ただ、60代・70代になると周囲で亡くなったり、
体が効かなくなったりする同世代が増えるのも事実。
あくまで主観だが、元気を保ち続ける人と、
急速に衰える人とのギャップが大きくなる。
ちなみにライダーの彼女は、
エッセンシャルワーカーとして働いていて、
当分、辞めるつもりはないようだ。
何度かケガもしているはずだが、
やっぱり体を動かしているのがいいのだろうか?
何が元気の維持と衰退との分かれ目になるのかはわからない。
とりあえず、いま現在、健康で頭も体も働くことに感謝しつつ、
日々を生きる。
魔都・横浜から遠く離れて
1975年のドラマ「傷だらけの天使」の最終回では、
修(萩原健一)が、姿をくらましたボス・
綾部貴子(岸田今日子)を探しに
横浜・中華街を訪れるシーンがある。
映像に映し出された、当時の中華街は、
いかにもヤバそうな街で、あちこちに密航の手続きを請け負う、
中国人のアンダーグランドビジネスの巣窟がありそうな、
魔都のにおいがプンプンしていた。
50年後の今、中華街はきれいに整備された観光地となり、
子供も大人も、日本人も外国人もみんな、
豚まんやら、月餅やら、チキンを平たく伸ばした台湾から上げやら、
イチゴとマスカットのミックス飴やらを食べ歩きして、
わいわい楽しさと賑わいにあふれている。
50年前のドラマの世界と現実とのギャップは大きい。
洗練された街、そして、
それを作り守っている地元の人たちに
ケチをつけようなんて気はさらさらない。
けれども、やっぱり、こうした見かけの繁栄と、
幸福感が希薄な日本人の内なる現実との
ギャップを考えると、もやもやした疑念が胸に湧き上がってくる。
「50年前よりほんとにこの国はよくなったのか?」と。
人も街も、化粧することが上手になった。
汚いものを包み隠すのがうまくなった。
それがいいこと何か悪いことなのか、わからないが、
食べ歩きをしている人の中にも、
いろいろ問題を抱えている人、
それだけでなく、精神にダメージを負い、
本当に「傷だらけの天使」になっている人がたくさんいるはずだ。
この国では20人に一人が心を病んでいると伝えられている。
観光地を行く外国人旅行者のほとんどは、
そんな話は信じられないだろう。
外からやってきた彼らから見れば、
日本は、平和で安全で、食い物も、おもちゃも、
いろいろな楽しみも豊富な、21世紀の世界における、
一種の理想郷に見えるのではないだろうか。
僕たちが到達したユートピアでは、
「私たちは見かけほど、豊かでも幸福でもないんだよ」
という顔をして街を歩いてはいけない。
楽しさ・賑やかさの裏から、
そんな無言の圧がかけられているような気もしてくる。
「傷だらけの天使」完食

最終回「祭りの後にさすらいの日々を」で、やっぱり号泣。
AmazonPrimeで「傷だらけの天使」を全26話見た。
大好きなドラマだったが、実はちゃんと見たのは3分の1くらい。
3分の1は断片的に覚えているシーンもあるが、
3分の1は全く見てなかった。
だから今回、50年の年月を経て、初めて完食。
長生きしてよかった!と思ってしまった。
この時代まで生き延びて幸福だ。
その「傷天」、この間も書いたけど、
今の基準で見ると、かなりひどい出来。
最近の映画やドラマの悪口を言う人は多いが、
30年前にラジオドラマの脚本賞を
取らせていただいた人間の目から見ると、
今の脚本・演出・演技、
すべて30年前よりはるかに高いレベルにあると思う。
少なくともテクニック的には。
だから50年前のこの作品が、
稚拙で雑なつくりに見えるのは当然かもしれない。
でもね。
面白いかどうかとなると話は別。
うまけりゃいいってものじゃない。
ちゃんと伏線があって、きれいにストーリーがつながって、
オチがついてりゃいいってもんじゃない。
本当にめちゃくちゃだけど、
このノリはどうだ。この勢いはどうだ。
ショーケンと水谷豊はもちろんいいのだが、
両岸田をはじめとする脇役のすばらしさ。
脚本家、監督をはじめ、製作スタッフの息遣いが伝わってくる。
喫煙シーン、暴力シーン、セックスシーン満載で、
コンプラなんてくそくらえ。
何よりも、あの70年代の東京の空気が
あまりにも鮮やかに封じ込められている。
戦後まだ29年、30年の世界。
ここで描かれているのは、29歳・30歳の若い日本。
新宿も渋谷も横浜も、かなりヤバい街に見える。
今の日本は、いいにつけ悪いにつけ、
おとなになって老成した80歳なのだと痛感する。
キャストもスタッフも大部分がこの世を去り、
もはやリメイクは不可能だが、
なんと作家の矢作俊彦が、
ショーケンとメインライターだった市川森一に許可を取って、
2008年にリメイク小説を書いていたと知って、びっくり。
きょうはとても冷静に書けないが、
これからまた、この昭和の名作「傷だらけの天使」について
いろいろ書いていきたいと思います。
アメリカがくれた長い夢の終わり

生まれてこの方、
つねにアメリカがトップリーダーを務める世界で生きてきた。
けれども、その世界が終わってしまったことを
先日のトランプ×ゼレンスキー会談で痛感。
「今さら何ねぼけたこと言ってるの?
そんなの、とっくの昔に終わってたじゃん、ばーか!」
と言われそうだが、どんなに横暴でも、パワハラ的でも、
やっぱりアメリカは民主主義の総本山であり、
文化的価値観の中心地だという思いは変わらなかった。
おかしな言動も目立つけど、
いい映画、いい音楽をいっぱい作っているし、
コンピューター、インターネット利用でも
ずいぶんお世話になっているし、
最後には世界をまとめ、
人類を望ましい方向に持っていってくれるのだろう。
そうした尊敬すべき面を持った国のはず。
だからというわけじゃないけど、
属国扱いも我慢する必要があるんじゃないか。
CとかRとかNKとか、
ヤクザな国が暴れ出したら止めてくれそうだし・・・
と、心の中でなかば願いのようなものを抱いていた。
だけど、もうおしまいDeath。
あの大統領には、国づくりの理念も哲学もなく、
他の国と協調しようとか、世界の秩序を保とうとか、
そんな考えはまったくない。
あるのはビジネスのノウハウと
「おれたちゃ偉いんだ」というプライドのみ。
カードがどうのこうのって、
まるでゲームやギャンブルをやっているかのようだ。
自分の国がどうすりゃもうかるか、得するか、
ってことしか頭にない。
でも、これは大統領とその取り巻き連中だけの指向性ではない。
少なくともアメリカ人の過半数が同じように考えているのだ。
こっちだって生活きびしいんだから、
民主党みたいなきれいごと並べて、
ほかの国の面倒見てる余裕なんてないんだよ。
こっちが得しなきゃ、もうやめやめ。
というわけで、もはや尊敬されよう、
気高くあろうなんて気もさらさらなく、
ぶっちゃけカネかねカネ。
まぁ、日本人も五十歩百歩かもしれないが。
いずれにしても、これまでの世界地図はビリビリになった。
80年前、アメリカに負け、アメリカに救ってもらった、
われらが日本。
その思いが強すぎて、僕たちは、
世界がこのまま何世紀も続くんだろうという、
長い長い夢を見ていたのかもしれない。
じゃあいったいどうすりゃいいかなんて、わからない。
とりあえず、グルメとアニメと平和ボケを売りにして、
ニッポン良いとこ、一度はおいで~
と、独自の文化の発信に励み、
ジャパンファンを世界中に広げておく、
といったことをやっていくしかなさそうだ。
人形供養はクールジャパンの原点

3月3日。昨日までのうららかな春の到来から一転、
真冬に逆戻りになったひな祭りの日。
「この時期から5月の子どもの日を過ぎるころまでが、
一番たくさん、お人形さんがいらしゃいます」
そう話すのは、都内でも人形供養で有名なお寺のご住職です。
やはり、お節句になると、子どもが巣立った家では、
ひな人形や五月人形が押し入れで
冬眠していることを思い出すのでしょう。
思い出深い人形だけど、
もう出番がないのにいつまでもしまっておくわけにはいかない。
ぼちぼち終活で、生前整理もしなきゃいけなし・・・
と、そんな気持ちが働きますが、
そのままゴミとして捨てるのは胸が痛みます。
いや、そんな生易しいものじゃなく、
張り裂けそうになるかもしれません。
それで信頼できるお寺、魂を静めてくれる、
人形供養のお寺に駆け込むのです。
べつに極度にセンチメンタルな人の話ではありません。
それが通常の日本人ならではのマインドというものですよね。
これをお読みのあなたも納得できるのではないでしょうか。
海外目線ではStrange
同じ日本人としては、ごく自然な心の働きなのですが、
海外の人には、こうした人形供養、
ひいては針供養とか、道具の供養とか、
モノに対する供養の習慣が、ものすごく奇異に映るそうです。
きょう取材したご住職のもとにも、
海外メディアの取材がちょくちょくあるらしく、
「どうして日本人は人形供養をするのか?
他の国では、テディベアが壊れたり汚れたりしても、
教会に持ち込むことなんてしない。
バザー用に売りに出したりはするけど」
てなことを言われるそうです。
生き物でないモノに魂が宿るという感性、
その宿った魂と別れるとき、
きちんとお別れをしたいという気持ちは、
日本民族特有のものなのかもしれません。
そしてまた、宗教者がその気持ちを受けて、
きちんと儀式を行うという文化を持っているのは、
これまた、世界広しといえども、日本だけなのでしょう。
供養の心が現代の日本カルチャーを生み出す
モノをモノとしか見ない外国人から見れば、
おかしな文化・習慣でしょうが、
こうしたことが、彼らを魅了する
日本のグルメ、アニメ、キャラクターなど、
ユニークなジャパニーズカルチャーに
つながっているのではないか、と思います。
動物にしても、精魂込めて牛や豚を育てて、
おいしい肉にして、亡くなった後はちゃんと動物供養をする。
といったストーリーは、
やっぱり外国の人は素直に納得できないでしょう。
「だって食べるために育ててるんじゃん」って。
人間の世界に違和感なく入り込み、
平等な友達になるアトムやドラえもんのようなロボットも、
「人形供養・モノ供養がある国」だから生まれた
ファンタジーです。
ただ、意外だったのは、
人形供養を行うお寺は全国でも数少ないということ。
僕はけっこうあちこちのお寺で
やっているものだと思っていました。
檀家さんに頼まれて、あるいは桃の節句や端午の節句の時だけ
行うところはあるかもしれませんが、
そのお寺ではほぼ毎日、全国から受け付けており、
受け取ったら翌朝には供養しているといいます。
ただ受け取って、お経を上げて終わりでなく、
あちらへ旅立たせるためには、
かなり手間も暇も費用も掛かるようです。
ゴミの分別を思い出してもらえればわかりますが、
中には、素材ごとにばらばらにしなくてはならないものもあり、
最近は環境問題で厳しい規制があるので、
専門の産廃業者とコラボして事に当たっているそうです。
歴史・文化の土壌で花咲くクールジャパン
この話を聴いて、
かわいい人形が「産業廃棄物」になるなんて――
と、内心、行き場のない悲しみやら、憤りやら、
切なさ、やるせなさを覚えたあなたは、
とてもまっとうな日本人マインドを持った人だと思います。
そうした和のマインドは、料理、ファッション、家屋、
各種のコンテンツなど、
生活のいたるところに溶け込んでいる気がします。
やはり現代の、有形無形の「クールジャパン」の数々は、
長らく培った日本の歴史・文化の土壌があるからこそ
咲ける花々なのでしょう。
認知症になっても人生は続くか?

先日、ある介護士の方のSNS投稿で、
喫茶店で高齢者たちが
「認知症になったら人生終わりだよね」と
会話しているのを聞いて、
心穏やかではいられなくなった、というものがありました。
彼は施設で認知症患者の人たちの面倒を見ています。
他の投稿でその奮闘ぶりをレポートしていますが、
これがまた凄まじい。
読むと、うちの義母の奇行・妄想・へそまげ・おもらしなんて、
まだまだかわいいものだなと思ってしまいます。
この介護士の方は、ひどい目に遭いつつも、
患者さんたちの純真な人間性に触れることで、
教えられたり救われたりするというのです。
ちょっときれいごとっぽいけど、
僕も義母と一緒に暮らしていて、
彼と同じようなことを感じるときがあります。
それは幼い子供と接しているような感覚です。
彼ら・彼女らは社会人という枠組みから抜け落ち、
子供に還っています。
いろいろおかしな言動は、
ストレスなく日常生活を送りたい僕たちにとっては
困りものですが、
子供と同じと解釈すれば、ある程度は大目に見れます。
でも、自分が認知症になったら・・・と考えると、
「人生終わりだよね」には、半分は同意せざるを得ません。
僕も息子を育てましたが、はじめは何もできなかった赤ん坊が、
だんだん自分でなんでもできるようになっていくのを見るのは
感動的でした。
本人も、あれもできる、これもできると、
日々実感していくのは、大きな喜びだったでしょう。
しかし、老いることはその逆の道をたどることです。
だんだん自分一人では何もできなくなっていく。
これは怖い。
僕は死ぬことにも、老いることにも
そんなに恐怖心を持っていませんが、
自分一人で何もできなくなるということには
大きな恐怖を感じます。
喫茶店のおばあさんたちも、
きっと僕と近い気持ちを持っているのでしょう。
「認知症になったら人生終わり」
それは自分のプライド・アイデンティティを失う恐怖であり、
社会から見捨てられる恐怖を表す言葉とも受け取れます。
でも、件の介護士さんのように
「そうじゃない」という人の意見が共感を得て、
認知症の人は日常生活はうまくできないけど、
あの人たちがいるとうれしい、楽しいという人、
だから助けになろうという人が増えれば、
この社会はまた変わってくるかもしれません。
これから先、認知症の人も障害を持った人も
豊かに楽しく暮らせる社会になるのか、
欲とエゴと嫉妬心むき出しの、
ラットレース社会がますます進展するのか、
その端境期が来ているのかもしれません。
認知症になって過去のことなど忘れても、
毎日生まれ変わったような気持ちで人生を続けられる。
とりあえず1日3分、そういう世界を想像してみようと思います。
おとなも楽しい少年小説
「おとなも楽しい少年小説」はライフワーク。
書くべき物語がたくさん自分のなかに眠っているのは、
幸福なことだと思います。
あなたも僕も、どこまで人生が続くか、わからないけど、
一度、探偵になって自分の内側を掘り起こしてみましょう。
金の林檎みたいな、思わぬ宝物が出てくるかも。
おとなも楽しい少年少女小説 2タイトル
無料キャンペーン: 2月26日(水)16:59まで実施中。
レビューもお寄せくださいね。
茶トラのネコマタと金の林檎
https://amazon.com/dp/B084HJW6PG
私立探偵の健太は、山荘に住む富豪のネコマタマダムの依頼で、黄金の林檎の探索に。
そこで見つけたものは?人生で大切なものは何か、
探しているあなたに贈る
コミカルでファンタジックな探偵小説。
叔母Q
https://amazon.co.jp/dp/B0CKWZKZJF
叔母の温子はロサンゼルスの下町のアパートで
孤独のうちに死んだ。
リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で
彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、
可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を
葬儀屋に語る。
おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン「叔母Q」
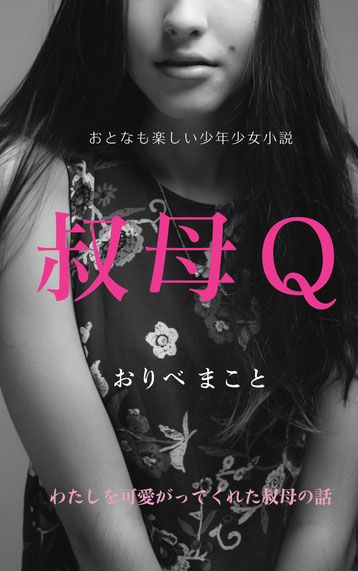
おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン
2月26日(水)16:59まで実施中。
僕の叔母は生きていれば90歳を出たところ。いま、社会で活躍している30代・40代の女性の祖母にあたる年代です。
多感な少女期に終戦を迎え、日本が戦後、
アメリカの擁護を受けながら、
新たな国家として復興するのと同じ歩みで大人になりました。
その時代、さしたる家柄にも才能にも美貌にも
恵まれていない女性の生き方は、かなり制限されていました。
20代半ばまでに結婚できた人は幸福とされましたが、
その後、自分を殺し、家族に尽くす長い人生が待っています。
一方、かわいいお嫁さんになれなかった人は、
世間から冷遇されるか、憐みや蔑みの目で見られるなかで
生きる道を選ばなくてはなりませんでした。
もちろん、例外はたくさんあって、
注目すべきイケてる女性の活躍は、
マスメディアで紹介されたり、
小説・映画・ドラマなどのモデルにもなったりしています。
しかし、叔母はそんな華やかな舞台に立つこともなく、
ありのまま自由に生きることもなく、
それでも喜びに満ちた人生への憧れ・欲求は人一倍あって、
それを抱えたまま、一生を過ごしたのではないかと思います。
本人の本当の気持ちはわかりませんが、
傍目には残念無念な女の一生。
けれども彼女のような、無数の昭和庶民の女性の、
満たされることのなかった憧れや欲求が、
現代の孫世代の女性らに受け継がれ、
活動力のエネルギーになっているような気がします。
亡くなって早や20年近く経ちますが、
なぜだか彼女は僕の心のどこかに棲み続け、
両親とは違った形で僕の人生を支え続けています。
生きている間に話を聴けなかったので、この作品における事実(と自分で思っている箇所)はせいぜい2~3割。
だから小説として、大部分は想像して書いたのですが、
フィクションの中にも、確かにこの世で生きた、
叔母の記憶を刻み込めたことに満足感を覚えています。
昭和の名もなき女性がどう生きたかの物語をお楽しみください。
探偵小説「茶トラのネコマタと金の林檎」のご紹介

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン
2月26日(水)16:59まで実施中。
都会の片隅でかろうじて生きている、しがない探偵は、
いつも仕事に、カネに飢えている。
けれどもカネのためだけで働くには、
やつも、やつの相棒もお人好し過ぎた。
夢見る女のために奮闘する心やさしき男たちの物語。
あなたの連休のおともに。

若き私立探偵の健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索だ。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れて現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、
魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。
健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、
黒い服の4人組の男たちがこの山にやってきて、
どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、
山中の雑木林に入ってスコップを振るい、
肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、
コミカルでファンタジックな探偵小説。
おりべまこと2月の電子書籍無料キャンペーン
2月21日(金)17:00~26日(水)16:59
コミカル探偵小説「茶トラのネコマタと金の林檎」
昭和家族小説「叔母Q」
短編小説2作を無料でご購読いただけます。
寒波が居座る3連休のおともにどうぞ。
茶トラのネコマタと金の林檎
20代半ばで独立起業し、6畳一間のアパートの自分の部屋で探偵事務所を開いた私立探偵・飛田健太(とびた・けんた)。
その健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れ、“なんちゃってホームズ”のいでたちで現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。 健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、黒服・黒メガネの4人組の男たちがこの山にやってきて、どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、山中の雑木林に入ってスコップを振るい、肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、コミカルでファンタジックな探偵小説。短編。2万4千字。
叔 母 Q
叔母の温子(ながこ)はロサンゼルスの下町のアパートで孤独のうちに死んだ。
リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、
可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を葬儀屋に語る。
「わたしも叔母のことが好きでした」
そう口にするとあの口もとのホクロを思い出した。
家族だった彼女は恋人でもあった。
生まれて初めて意識した大人の女だった。
子供だった「わたし」と、
戦後の時代を生きた叔母との記憶の断片をつなぎ合わせた物語。
短編。2万2千字。
「傷だらけの天使」は昭和の天使の物語

「傷だらけの天使」は、
おそらく現在の60代から70代前半の男性の多くが、
ディープにハマったドラマだろう。
1974年10月から75年3月まで半年間、
毎週土曜日、日本テレビで放送された。
主役の小暮修(オサム)は、
表の社会と裏社会とを行き来しつつ、
やばい仕事で荒稼ぎをする「綾部調査事務所」の調査員。
と言えば聞こえはいいが、
実態はチンピラ探偵といったような風体の若い男。
これをショーケンこと萩原健一が演じる。
そしてその弟分であり、仕事の相棒・乾享(アキラ)の役が、
人気ドラマ「相棒」の杉下右京=水谷豊だ。
この半世紀前のドラマが、
AmazonPrimeで配信されているので見ている。
作品紹介は以下の通り。
ビル屋上のペントハウスに住み、
探偵事務所の下働きをする修(萩原健一)と、
彼を「アニキィ!」と慕う亨(水谷豊)。
修の貧乏生活を知る探偵事務所のボス、
貴子(岸田今日子)とその手下、辰巳(岸田森)は、
金をエサに彼らに毎回無茶苦茶な仕事を押しつける。
割に合わないと思いつつも、
がむしゃらな修は命懸けで危険な仕事に飛び込んでいくのだが、
根っからの善人で単細胞なゆえに、
仕事も思わぬ方向へ暴走してしまう。
笑いあり、涙あり、お色気ありで展開するストーリーには、
息をもつかせぬスピード感がみなぎっている。
どうやらコロナの時期から配信していたらしいが、
気が付かなかった。
またハマったらどうしようと思って恐る恐る見たが、
やっぱりハマってしまった。
脚本も演出も撮影も演技もメチャクチャで、
聞き取れないセリフもいっぱいいある。
だけど、やっぱり面白いし、イカしている。
泣いてしまうし、考えさせられる。
そして、「ああ、おれはやっぱり死ぬまで
傷天の世界から抜け出せない」と再認識した。
決してノスタルジーを感じたわけではない。
むしろ逆で、50年たった令和の今見るからこそ、
違った傷天の魅力が見えるのだ。
これについては、とても1回や2回では書けないので、
これからしばらく折に触れて書いていこうと思う。
今日、一つだけ書いておく。
今までこのドラマのタイトルを意識したことがなかったが、
今回、昭和から遠く離れた地点から見ると、
オサムとアキラは、
まんま「傷だらけの天使」なんだなということがわかる。
二人は人間世界に降りてきたエンジェルであり、
あのバカかげんは、
人間世界における天使のふるまいなのだ。
そういう視点で見ていくと、
ハードボイルドともコメディとも昭和残酷物語ともとれる、
この探偵ドラマが、一種のヒューマンファンタジーとして、
新鮮な輝きを帯び始める。
そして、なんで俺はこんな世界で生きているのだろうと、
大いなる疑問にとらわれるのだ。
「なんのこっちゃ?」と思うでしょうが、
また、おいおい書いていきます。
認知症の問題解決にアルバム認知症の問題対応にアルバム効果 心療回想士がつくった「人生まるごと回想アルバム」

東京ビッグサイトで12日から14日まで開催されている
「ギフトショー」に行ってきました。
太田区のブースの一角で「人生まるごと回想アルバム」を
紹介しているのは、株式会社テコデコドリーム研究所です。
アルバム本来の役割を見直す
アルバムに並んだ写真を見て、
過ぎ去りし日々を楽しむというのは、ごくありふれた行為で、
どこの誰でも実践していることのように思えます。
けれども、実はちゃんと写真を整理整頓し、
他者が見ても分かるよう管理できている高齢者はごく少数。
また、それが子供世代との間でコミュニケーションツールとして
活用されている例はさらに少ないようです。
「人生まるごと回想アルバム」は
そうしたアルバムが本来持つ役割を見直し、
可能性を伸ばすことによって生まれた商品です。
医療・介護の分野で注目の「回想法」
このアルバムは回想法で利用するシーンを
想定して作られています。
回想法とは1960年代初期に
アメリカの精神科医が開発したもので、
回想し過去の記憶をよみがえらせることで脳を活性化。
さらにその記憶を他者と共有し、
分かち合うことでより元気を出せるという精神療法です。
ご存じのようにこの10年ほどの間、
超高齢社会の進展に伴って認知症患者が激増。
それによってすでに相続などの分野で
様々な問題も起こっています。
そんな状況のなかで回想法は、認知症に対する予防効果、
あるいは症状の緩和・改善が期待できる非薬物療法として、
医療現場や介護施設、自治体の介護事業、
地域コミュニティーなどにも注目されています。
心療回想士のスタッフが開発
テコデコドリーム研究所ではスタッフ全員が
この回想法の基礎を学び、
心療回想士の資格を取得。
素材として写真を用い、
その写真を編集して作るアルバムに焦点を合わせました。
どうすれば親世代(高齢者)にとって、
より楽しく記憶をよみがえらせるものにできるか、
子供世代・孫世代とのコミュニケーションに
役立つツールにできるかを考えた上で設計し、
他にはないユニークな特徴と機能を持たました。
親子で楽しめるアルバムづくり
最も大きな特徴は、マグネット式アルバムを採用したこと。
家族みんなで閲覧しようという時、
アナログの分厚く重いアルバムを手に取るのは億劫で、
一人一人気軽に回して見るのに適していません。
また、スマホやタブレットのようなデジタル端末の画面上で
写真のデータを見るというスタイルだと、
みんなで見ている、家族で親の人生を共有している、
という感覚が持てません。
1ページずつ取り外しができるマグネット式アルバムは
そうした課題をクリアし、
家族で集まれば、自由に広げてみんなで見ることができ、
ページ追加も簡単にできるといいます。
また、記憶を呼び起こすためには“可視化”が重要。
家の中で目につく場所に写真があると、
ふとしたきっかけで大事なことを思い出したり、
家族への感情が深まることがあります。
通常、アルバムはしまっておくと中身が見えませんが、
ここでもマグネット式の利点を生かし、
お気に入りの写真があるページを
スチール製の壁や冷蔵庫に貼りつけて見ることができます。
また、アルバムそのものを360度開いて
そのままフォトスタンドとして使うこともできるといいます。
子供が親のためのアルバム編集者に
こうした特徴・機能を活かして同社では
「子供世代が高齢の親にためにアルバム編集者なること」
を推奨しています。
フィルムカメラの時代は、撮影後、
現像してプリントしなければ、写真を見られませんでした。
そのため、親世代が保存している写真の量・アルバムの量は
膨大であるケースが多く、
本人が亡くなった後は、(悲しいことではありますが)
そのほとんどを破棄しなくてはならないのが現実です。
それを踏まえて、テコデコのスタッフは、
子供世代が自分で見て貴重だと思える写真、
親のことを知らない子供や縁者の人たちが見ても
楽しめるような写真などを選び出し、
この「人生まるごと回想アルバム」を使って、
世代を超えて共有できるアルバム、
親孝行のツールとなるアルバムを作ってほしいと話していました。
施設のスタッフが心のケアにも手を伸ばせる
また、このアルバムは親が
介護施設で暮らすことになった場合にも
効果を発揮します。
介護施設のスタッフは、
親を「入居者=高齢の人」としか認知できないので、
毎日の食事や排泄の世話など、身体機能面でのケアはしますが、
感情面でのケアは天気のこと・庭の花のことなど
についてしか話せません。
生まれながらの高齢者など一人もおらず、
誰しも何十年という人生の道程、
無数の喜怒哀楽を経験してそこにたどり着くのですが、
スタッフはその一つとして想像するすべがないのです。
そんな時、このアルバムで子供時代や青春時代など、
親の人生のわずかな断片でも知ることができれば
「かわいいですね」「楽しそうですね」など、自然と会話が弾み、
心の介護・感情面のケアにも手を伸ばせるのではないか。
テコデコ研究所ではそうした期待も抱いています。
ちなみに、「回想法」の効果的な会話のポイントとして
「ほめ言葉は過去形にしないで現在形で話す」そうです。
還暦スタッフの第2のスタートアップ
テコデコドリーム研究所は、
もともとキャラクターと音楽コンテンツを
メイン事業とする会社で、
かつては各種アミューズメント施設やイベントなどで
若者や家族連れの人気を集めていましたが、
いずれも家庭の主婦を兼任していた3人のスタッフが
家族の介護に専念するために一時企業活動を休止していました。
その間、代表の池尾里香さんが施設に入居した
独身の叔母の家の整理をした際に、
それまで見たことのなかった若い叔母の
いきいきした姿の写真を大量に発見。
その中から自分の目で選んで一冊にまとめたアルバムを
本人に見せたところ、認知症気味だった叔母が大いに喜び、
互いに思い出を共有できたといいます。
同社の3人は、中小企業振興公社主催の
「事業家チャレンジ道場」で約2年間、
ものづくり・最新のマーケティング技術を勉強する中、
介護経験と回想法を活かした今回の事業を考案しました。
誕生日、母の日、父の日、施設の訪問時、
米寿や喜寿のお祝い事などに、
子から親への真心こもったプレゼントに使ってほしいというのが
彼女らの提案です。
永続的な親孝行の実現をサポート
「人生まるごと回想アルバム」は、
葬儀の遺影や式場の思い出コーナーの写真などに
使えることはもちろん、
その後の法事の場でも集まった人たちに
親の人生を偲んでもらうこと、
また、孫やその後の世代に伝えていく
「ファミリーヒストリー」としても
役立てることができるといいます。
池尾さんと、実の姉である綿井さんは、
両親の法事の席で親戚一堂にこのアルバムを見てもらったところ、
たいへん盛り上がり、皆、新鮮な感動を受けたといいます。
それがまた両親に対する供養に繋がるのでしょう。
これは単にアルバムを販売するビジネスでなく、
アルバムづくりを通して、
永続的な親孝行の実現をサポートする事業
といえるかもしれません。
もしギフトショーに行かれる方は、
ビッグサイト南館にある大田区のブースで、
ぜひ実物を手に取ってみてください。
また、このアルバムのサイトはこちらです。
https://tekodekorecollection.com/
虚と実が融合する映画「八犬伝」

「南総里見八犬伝」は
江戸時代の作家・滝沢馬琴が書いた長編小説。
1814年に始まって、
1842年の完結まで28年かかって世に出された、
世界に誇れる傑作エンタメファンタジーです。
運命に導かれて集まった仲間が
力を合わせて敵と戦うという勧善懲悪パターンは、
神秘的かつ痛快で、この活劇をモチーフにした
コンテンツが200年の間に続々と作られました。
今日の日本のマンガ・アニメ文化の基盤を築く
一要素になったことは、疑いようがありません。
僕の八犬伝との出会いは、
小学生の時に見たNHKの人形劇でしたが、
それ以後も「八犬伝」から
いくつもの映画やマンガが生まれるのを見てきました。
いちばん最近のものは、
昨年秋に劇場公開された映画「八犬伝」でしょう。
僕は見逃していたので、先日、アマプラの配信で視聴。
公開の時は評判はイマイチだったようですが、
とても楽しめました。
虚と実、二つの世界がパラレルで進む構成で、
虚はご存じ、八犬伝の活劇世界です。
原作に忠実なのはいいのですが、
ストーリーの上っ面をサーっと撫でているという感じで、
今一つ物足りないのですが、
それでもやっぱり面白いのは、さすが八犬伝。
名刀・村雨を持つ犬塚信乃、女装の犬坂毛野、
少年剣士の犬江親兵衛などはとてもイケメンで、
画面も派手で美しい。
それに対する実の世界では、
作者・滝沢馬琴と絵師・葛飾北斎、
二人のむさいジジイの対話で進みます。
これに「東海道四谷怪談」の戯作者・鶴屋南北が絡んだりして、
彼らの創作に対する考え方・思いが伝わってきて味わい深く、
このむさいじいさん・おっさんたちから
ああした華麗な物語や絵画が生まれたのが面白い。
まるで現代人のような、滝沢馬琴の家庭の事情
(一人息子がニート状態)も描かれていて、
これも考えさせられます。
いよいよ最終章、物語がクライマックスに差し掛かったところで
馬琴は失明。目が見えなくなり、執筆できなくなります。
「八犬伝」は未完の大作に終わるかと思われたときに、
代筆者として名乗りを上げたのが息子の嫁でした。
この嫁は無学で字もろくに書けない女性なのですが、
義父である馬琴が字を教えながら、二人三脚でがんばり、
わずか8か月で残りを仕上げ、物語を完成させます。
すごく感動的なエピソードですが、
この嫁がどうして馬琴に尽くし、代筆をやろうと思ったのか?
夫を先になくして寂しかったから?
義父のことを好きだったから?
「八犬伝」が好きだったから?
そのあたりがドラマとして描かれていないので、
どうも腑に落ちないのですが、それでも物語は最期を迎え、
馬琴の仕事は成就しました。
そして、まるで最近の
ファンタジー系アニメやマンガのお約束事のように、
戦いで命を落とした犬士たちも生き返るのです。
僕も小説などを書いているので、虚実が融合し、
馬琴と八犬士が遭遇するラストシーンには、
涙を抑えきれませんでした。
不平・不満はありますが、やっぱり八犬伝は面白いし、
創作の舞台裏も描かれたこの映画には、
単なるエンタメを超えた奥深さがあると思います。
「ちょっと死について考えてみたら怖くなかった」ってホント?

思わず聞き返したくなるような、このタイトル。
いやいやいや、やっぱ死ぬのは怖いですよ。
そうなの? じゃあチョット江東区森下までいらっしゃいよ。
ママといっしょに、あなたらしい生と死について考えましょうよ。ってなことを言っちゃうのが、
この本の著者・村田ますみさんです。
森下にあるのは「めめんともり」という、
1年前にオープンした、たぶん日本初の終活スナック。
「カラオケないけどカンオケあります」をキャッチフレーズに、
夜な夜な大人が集まって、
一杯やりながら「生きるとは?」「死ぬとは?」と語り合い、
それぞれの死生観を養っているところです。
「メメント・モリ(Memento Mori)」
=ラテン語で「死を思え」。
年齢にかかわらず、君も僕も明日死んでしまうかもしれない。
その可能性を忘れずに、今を大事にして生きろ。
悔いがないよう、好きなことをやって生きろ。
そんなメッセージとともに、
最近、わりとよく耳にする言葉ではありませんか?
自分はどう生きるのか?=どう死ぬのか?
といった哲学的な思考を、世代を問わず、
みんながいっせいに始めたのかもしれません。
そうした時代の空気から
終活スナック「めめんともり」は生まれたわけですが、
なんと、今月には早くも2号店が沖縄・那覇にオープンしました。村田さんはこの2つの終活スナックのオーナーで、
夜ごとお客さんの話を聞き、
自分の考えをまとめながら、
この本を書いたようです。
内容概略(もくじ)は下記の通り。
第1章 なぜ終活スナック?めめんともり開業のルーツを辿る
第2章 あなたの理想の死は?
第3章 棺桶に入って生まれ変わる!?
第4章 自分らしい最期を大切に
第5章 多様な選択ができることで、死の捉え方がかわる
第6章 自分らしい最期を迎えるために必要なこと
とても楽しく読めるエッセイなので、
ぜひ手に取ってみてください。
2月27日発売予定です。
ちなみに村田ますみさんは、
日本における海洋散骨のパイオニアでもあります。
以前、僕がテレビの情報番組の仕事に携わっていたころ、
多くの女性が「夫の家のお墓に入りたくない」
という声を上げ始めていました。
それから30年あまりがたち、娘世代になると、
こうした従来の葬儀供養のあり方に異を唱える
女性がますます増えています。
そして、前の世代と違うのは、
彼女らは単に不平を言うだけでなく、
勇気をもって自ら行動し、
これまでの葬儀供養にまつわる
常識・社会通念を変えようとしています。
村田さんもその一人で、
彼女の言動に共感した多くのフォロワー事業者が現れ、
あれよあれよという間に、海洋散骨は、
すっかり葬送の選択肢の一つになった感があります。
時代が変われば、生き方も、死に方も、葬送も変わる。
終活スナック開業の背景から、
理想の最期について考えるヒント、
入棺体験を通じた「生まれ変わり」のプロセス、
そして、終活の実践的なアドバイスまで、
いつか死を迎えるあなたや僕に向けて語りかけてきます。
死は恐れるものではなく、生き方を見つめ直すもの。
でも、ホントに怖くないですか、村田さん?
つまらない大人にならない
自分の中で特にヒーロー視する人物はいませんが、
佐野元春さんだけには注目しています。
かつて「つまらない大人にはなりたくない」
と歌っていた佐野元春ももう70に近い齢。
口だけでなく、本当につまらない大人にならなかった。
齢をとれば取るほどカッコよくなっていることは、
コヨーテバンドを率いて演奏する
彼の姿を見れば、誰もが認めるところです。
現代を生きる人間として、ある種の理想的。
He has aged badly.
座標となる「ポーラスター」です。
その佐野元春が、昨年はコヨーテとともに
「ヤングブラッズ」を、
今年は「ガラスのジェネレーション」をリメイク。
どちらも元気の出るご機嫌なロックナンバーでしたが、
いまの彼が歌うと、少し切なさを帯びた、
とても深みのある歌に聴こえてきます。
ここでニューバージョンを作ったのは、
オールドファンへのサービスなのか?
若い世代へメッセージを送ろうとしているのか?
いや、もしかしたら同世代のシニアたちに、
もう一度、「荒ぶる胸の思いをよみがえらせろ」
「つまらない大人になるな」と
鼓舞しようとしているのかもしれません。
個人的には自身のニューヨーク体験を
サウンド化した「ヴィジターズ」(1984年)が好きなので、
あのアルバムの曲をリメイクしてほしいと思っています。
特に40年前、日本人として初めてヒップホップを導入した
「コンプリケーション・シェイクダウン」。
あのクールな傑作を、
新しい歌詞で再現してくれるとうれしい。
♪フィジカルなダンス メンタルなダンス
システムの中のディスコティック
というサビの歌詞は、40年前よりむしろ現代こそ響く言葉。
佐野元春の歌を聴くと、僕もまだまだこれからだ、
時代の流れに抗って生き続けるべきだと思うのです。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン
2月3日(月)16:59まで
昨夜よりもっといい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
きらめく都会や死の国を旅する「星の王子さま」

小さな劇場の何もない舞台は、想像力が刺激される、
自由で可能性に満ちた空間です。
今日はここで「星の王子さま」の舞台を見ました。
原作はもちろん、サン・テグジュペリの童話。
壁面全体にしわをつけたベージュの模造紙を張り付け、
あの物語の舞台になる砂漠のイメージを表現しています。
内容は原作をなぞるものではなく、
生演奏やダンスが随所に交じる、
音楽劇風・イメージコラージュ風の構成。
前半は、王様、実業家、のんべえ、点灯夫など、
へんな大人がいる星をめぐる旅など、
原作に出てくるエピソードを仮面劇で見せたり、
後半は王子様とキツネがともに
パリと東京を合わせたような、
きらびやかな都会の街を探索したり、
地下にある死の国をめぐり歩く
オリジナルのエピソードを取り入れたりと、
自由自在な展開で、不思議な世界に引き込まれました。
王子様役の女性はクラシックバレエの心得があるようで、
随所で王子の心情をダンスで表現します。
彼女のビジュアルは、絵本のイラストそっくりでありながら、
不思議なエロシティズムと、
物語全体を包む切なさ・寂しさが感じられて魅力的でした。
上演したのは、
カミさんの仕事仲間である鍼灸師の奥さんが主宰する
「クリスタルレイク」というグループ。
この奥さんというのは、もともと新劇俳優で、
劇団新人会のメンバーだった人だそうです。
大ベテランですが、キツネ役として登場した
彼女の動きはキレがよく、
せりふ回しもクリアで「生涯現役」を感じさせました。
僕たちはこうした小劇場演劇に感化された世代ですが、
昨今の舞台演劇は、
やる側も見る側もシニア世代のものになりつつあるようです。
これも時代の趨勢なのでしょうが、
若い人たちにも、こうした変幻自在の小さな空間で描かれる
リアルでアナログな演劇の空気を、
若い人たちにも、ぜひ体験してほしいと思います。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン
2月3日(月)16:59まで
昨夜よりもっといい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
愛妻の日:伴侶ネグレストにならないために

今日、1月31日は「愛妻の日」です。
「日本愛妻家協会」なる団体が
1(アイ)・31(サイ)という、
かなり苦しい語呂合わせから生み出した記念日です。
これをネタにした
「愛妻家・愛夫家は人生の成功者?」という
エッセイを2年前に書きました。
拙著「昨夜よりもっといい夢を見る方法」の
最初に採録しています。
人生の成功と言えば、大金を稼いで大金持ちとか、
仕事で大活躍とか、有名になったとか、
たくさんの人に認められたとか、
社会的に高い地位に就いたとか、
通常語られるのはそうしたことです。
若い時代には、おそらくそこに
「恋愛の成就」「結婚」というものも
含まれると思います。
しかし、これはいったん手にして齢を取ると、
かつての輝きを失って色あせてしまうことが多いようです。
そして進行すると、妻ネグレスト、夫ネグレストになります。
それでも互いの利害のためにするずる関係を続けるのは、
人生全体から見ると、
離婚より始末が悪いことになりかねません。
最近は投資ばやりですが、
このエッセイで書いたのは、
いつまでも妻を愛せる、夫を愛せることは、
人生において、最大のリターンが見込める、
最高の投資ではないか―ーということです。
器用でどんな仕事も楽々こなせる人と、
不器用で何をやっても下手な人とがいるように、
モテモテなのに、誰ともうまく関係が結べない人と、
モテないけど、苦もなくよい恋愛・結婚関係を
結べる人とがいるようです。
異性としての魅力に加え、人間性、相性、
運・タイミングなど、多様な要素が絡むので難しいのですが、
最近の若い衆は自分のライフプランにこだわりすぎたり、
周囲の情報に振り回されすぎではないかと思います。
恋愛・結婚こそ、人生最大の勘どころ。
ひとの意見やアドバイスを取り入れるのが
全部ダメとは言いませんが、
あくまで自分の直観力を信じて、
相手とともに迎える未来を想像しながら
挑むべきではないでしょうか。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン
2月3日(月)16:59まで
昨夜よりもっといい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
「昨夜よりもっといい夢を見る方法」無料キャンペーン

あなたの心にゆらぎを送り、
あなたの人生をほんのり照らす。
「生きる」をテーマにした
おりべまことエッセイ第6集。
本日より2月3日(月)16:59まで
無料キャンぺーン実施中!
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。
そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」
2022年9月から23年末のなかから抜粋。
もくじ
・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?
・「芝浜」と女落語家
・名古屋の母と母校の話
・入学祝いはやっぱり桜
・百年生きるホモサピの世界はこれから
・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶
・これからどうやって旅に出るか?
・自分の未来、世界の未来、子どもの未来
・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない
・ときにはダンゴより花
・4630万円の振り込み
・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?
・井上ひさしと笑いについて
・人生は長くて短い
・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる
・潮騒の音楽を楽しむための海
・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用
・いい夢を見る方法
・なぜ30年前のトレンディードラマには お彼岸が出てこなかったのか?
・親より先に死んではいけません
・余命7年で行こう
・女じゃなくなる恐怖
・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。
・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」
・こっそりカメ走
・人生は地中に埋もれた化石のようなもの
・アーカイブ世代のクロニクル研究
・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?
・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話
・9月15日はロージンの日?
・お祭リベンジ
・同窓会の話
・地球の重力に逆らうべからず
・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論
・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方
・美しきニューヨークのカレンダー
生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること

認知症の義母は、夫(義父)の遺影を見ると、
いつも「この人だれ?」ときいてきます。
何十年も夫婦としていっしょに暮らしてきたのに、
まったく覚えていないのです。
ある仕事で人生相談の相談文を頼まれたので、
このことをネタにして女性(娘)の悩みを書いてみました。
「あんなに仲の良い夫婦だったのに、
父のことをすっからかんに忘れてしまった母が
憎いやら、悲しいやら、やるせないやら・・・」
と、えんえん自分の心情を吐露し、
「結局、愛し合うってどういうことなのでしょう?
どうして人と人とは愛し合うのでしょうか?」
と、相談者に問いかける文章です。
20世紀・21世紀生きる僕たちは、
生まれてから、テレビ、映画、マンガ、小説、ゲームなど、
毎日いろいろなコンテンツに触れているので、
「永遠の愛」とか「不滅の絆」なんて
ドラマチックなものを信じてしまいがちです。
しかし、実はそれは作られたもので、
人間の真実の姿とは
かけ離れたものではないかと思うのです。
すっかり子供みたいになってしまった
義母の相手をしていると、つくづくそう感じます。
結局、寒くもなく暑くもない、
適度に衛生的で快適な環境に身を置いて、
毎日うまいものを食べて、
面倒を見てくれる誰かがそばにいれば、万事OK。
幸福に、満ち足りて眠りに落ちる。
それが人間の本質なのだと、
義母には教えてもらっているようです。
けれどもみんながそんな本質的な部分だけで生きていたら、
人間の社会生活はままなりません。
というか、そもそも人間社会というもの
が成り立たなくなります。
僕たちには、愛とか夢とか自由とか理想とか、
そういう美しい幻想が必要です。
それは個人的なものでなく、
むしろ社会的な要求です。
生きるとは、ひとりひとりが
死ぬまでそうした幻想を抱き続けること。
僕も願わくば、最期までそうありたいので、
そのために毎日、
こうしていろいろな
文章をこねくりまわしているような気がします。

電子書籍無料キャンペーン
1月30日(木)17:00~2月3日(月)16:59
昨夜よりもっといい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」2022年9月から23年末のなかから抜粋。
「まちがった万能感」は捨てられない

10時間超のフジテレビの会見。
全部見ていたわけではありませんが、
僕にとっては遠藤副会長の
「間違った万能感を植え付けられた」
という言葉がとても印象に残りました。
昨日、壇上に上がって記者会見を行った役員は、
フジテレビ黄金時代をつくり上げた
ディレクター、プロデューサーの皆さんです。
35年ほど前、僕はADやリサーチャーをやっていて、
テレビ番組の制作現場にも少し携わっていましたが、
当時は「フジテレビの仕事に携わっている」というだけで
誇らしいこと、優越感を持てることでした。
彼らはいわば業界人のリスペクトを集める敏腕クリエイター、
まさに万能神だったのです。
それがあんなさらし者にされるとは・・・。
昨日の記者会見は、
輝いていたテレビ界の落日を見るかのようでした。
そして同時に、ひどい矛盾も感じました。
これだけみんながカネ、カネ、カネと言っている
世の中でありながら、
「カネもうけより人権が大事」??
どんな業界の会社にもそれが求められているというのです。
でも、本当にそれが実現されている日本の会社は、
フジテレビに限らず、まだほとんどないでしょう。
昭和末期から平成前期、
「カネもうけより人権が大事」なんて言おうものなら
笑いものにされました。
「大事にしてほしけりゃ、面白いもの、
ウケるものを作ってみろ」
そういうなかで勝ちあがってきたのが、あの役員さんたちです。
変わろうにも変われるはずがありません。
新刊の「昨夜よりもっといい夢を見る方法」には
「なぜ30年前のトレンディードラマには
お彼岸が出てこなかったのか?」
という一編があります。
まだあの時代を懐かしがっています。
残念ながら、僕もフジテレビの役員さんたち同様、
あの時代の残像に支配され、
まだ頭がちゃんとアップデートされていないようです。
過去を清算し、頭をクリーンアップするためにも、
この際、しばらくの間、
彼らが作ったフジテレビ黄金時代の番組を
地上波で一挙に放送してみてはどうでしょう?
出演者の権利問題もあるので、可能な分だけですが。
人が変わるのは、とても難しい。
人が集まって作る組織が変わるのは、さらに難しい。
フジテレビだけじゃありません。
どこの会社も明日は我が身です。

電子書籍無料キャンペーン
1月30日(木)17:00~2月3日(月)16:59
昨夜よりもっといい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」2022年9月から23年末のなかから抜粋。
映画「怪物」と脚本家の来歴、フジテレビのドラマについて

是枝裕和監督の映画「怪物」を見た。
息子を愛するシングルマザー、
生徒思いのまじめな小学校教師、
そして無邪気な子どもたちが送る平穏な日常。
それがある小さな事件がきっかけでガラガラと崩れる。
その背後にいるのは、正体不明の怪物。
ひとことで言えば、
タイトルの「怪物」とは誰か?何か?を追究する物語だ。
それは親なのか? 教師なのか?
学校という組織なのか?
それとも子供たちなのか?
いったい何なのか?
前半は学校と家、地域を舞台とした、
リアルでドキドキするサスペンス。
そして後半からクライマックスは、
それが一種のファンタジーにまで昇華する。
還暦を超えても全く衰えを感じさせない
是枝監督のクリエイティビティに舌を巻く。
音楽は最晩年の坂本龍一。
坂本龍一と言われなければ、
わからないくらい主張は少ないが、
随所でとてもいい味を出している。
そして脚本は坂元裕二。
いまや日本を代表する脚本家だが、
彼は1987年に初めて行われた
「フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者。
つまり、フジテレビが発掘した才能だ。
1991年の、あのフジ・トレンディドラマの代表作
「東京ラブストーリー」の脚本を手掛けた人でもある。
坂元氏はその後、テレビ業界が嫌になり、
一時的にテレビドラマの脚本を書かなかったこともあり、
最近はもうプロフィールにも
「東京ラブストーリー」については触れられていない。
そんな大昔のことなど持ち出す必要もなく、
クオリティの高い作品をコンスタントに手がけ、
充実した活動を展開しているからだろう。
この作品は、第76回カンヌ国際映画祭の
コンペティション部門で脚本賞も受賞している。
そんな坂元氏を輩出した1990年代のフジテレビは、
恋愛を中心としたトレンディから
先鋭的なサイコサスペンスまで、
ドラマの制作能力がとても高く、
TBSと競い合うように傑作・問題作を次々と放送していた。
それはもうすっかり過去の話だが、
そうしたコンテンツ制作の資産は残っているはずだ。
サザエさんや、ちびまる子ちゃんや、
ガチャピン&ムックもいる。
このままダメになるのは、あまりに惜しい。
けれども再出発のためには今いる、
過去の栄光に浴した経営陣営陣ではダメなことは明らか。
なんとか改革して、また優れたコンテンツ、
動画配信をしてほしいと願う。
フジテレビの話に傾いてしまったが、
是枝映画「怪物」はほんとに傑作。
カンヌで認められた、なんて話はどうでもいいので、
ぜひ、このドラマの奥に潜む怪物を
自分の目で発見してほしい。
中居・フジテレビ問題と「心の解放区」

中居問題・フジテレビ問題がこんなことになって、
なんだか嫌な気持ちになっています。
芸能界とかテレビって、もともと一般社会とは隔絶した、
理不尽だったり、いい加減だったりする世界だったはず。
そして、そうした世界で成功し、活躍できる、
エンターテインメントの才に長けた人たちは、
常人離れしたエネルギーを持っている人たちです。
普通の人たちは、毎日お祭りやっているような
「ハレ」の日ばかりだと疲れちゃって、
とても持たないけど、
あの世界の人たちは、それができちゃうわけです。
で、一般ピープルもそういう「ハレ」の部分を楽しんだり、息抜きとして利用していたと思うのですが・・。
ということをいうと、
中居君がやったことやフジテレビの疑惑を
肯定しているかのように思われるかもしれません。
そうではないのですが、
かつての「面白くなければテレビじゃない」
「きっかけはフジテレビ」みたいなノリは、
一般社会とは異なる、理不尽だったり、
いい加減だったりすることころから
出てきたのだと思います。
あの時代のフジのドラマやバラエティも、
つくる側のそうしたエネルギーと、
視聴者側の「ハレ」を楽しみたい気分が合致して
質の高いものになっていたのではないでしょうか。
あれから30年~40年あまり。
社会が成熟し、そんな面白ノリよりもっと大事な
人権やモラルが優先される世のなかになった
ということでしょう。
それはきっといいことなのだと思います。
ただ、僕は正直言って、
そういう空気に何とも言えない息苦しさも
感じてしまうのです。
少なくとも、詳しい事実関係もわからずに
「中居は、フジは」と、声高に糾弾する気にはなれません。
話はちょっと飛ぶけど、
今年初めのNHKスペシャル「ネオ・ジャポニズム」で
マンガの特集をやっていました。
今、日本のマンガは欧米の先進国だけでなく、
アジアやアフリカなどの新興国、
また、戦場になっているウクライナなどでも
読まれているといいます。
番組ではその理由について、
日本のマンガの世界の中に「心の解放区」が
あるからでないか、と表現していました。
かつてのフジのドラマやバラエティ番組に代表される
「テレビ的なるもの」は、
まさにその「心の解放区」だったのでしょう。
今、その役を担うのは、テレビではなく、
マンガやアニメ、ネットの世界なのかもしれません。
中居君と被害女性の間で、本
当は何があったのかは、本人同士でないと分からないし
、互いの心情を客観的に判断するのは難しいと思います。
ただ言えるのは、芸能がらみの世界でずっと続いてきた、
そして、当たり前と思われてきた、
(実力・才能がある)男がおいしい思いをできるという
習慣というか、文化は、
今後、わりと速い速度で廃れていくのは確かでしょう。
その先にやってくる新しい常識の世界がどんなもなのか、
まだちょっとクリアには想像できませんが。
65歳の誕生日が来ると・・・

1月21日は誕生日なので、
何人かの方からメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ただ、これからの方のために言っておくと、
65歳の誕生日は、
本人にとってそんなにおめでたいものではありません。
単純に1つ齢を取った、ではなく、
「さあ、あんたも高齢者の仲間入りだよ」ということを
嫌でも思い知らされるからです。
具体的に言うと、役所から介護保険証が送られてきます。
年金のナンタラ通知も到着します。
その他、体力測定を受けたり、
健康診断の通知も次から次へときそうです。
会社員の場合は、当然、定年退職の手続きもあるでしょう。
ありがたいやら、鬱陶しいやらですが、
これら一つ一つの事象が、
ボディーブローのように効いてくる感じがします。
ちょっと気にし過ぎなのかもしれません。
「へっ、そんなもの気にしちゃいねえぜ。
おれは今まで通り、おれだぜ」
と、ロックンロールなセリフが吐ければいいのですが、
そんなに強くもカッコよくもないので、
ちょっとため息を漏らしています。
これをお読みのあなたは、
もっとしっかりしていると思いますが、
自分の時のために
「あいつ、65の誕生日の時に
こんなこと言ってビビってたな」
と、心に留めておいてください。
ちょっとは心構えが違ってくると思うので。
というわけで、あまりおめでたくもない誕生日ですが、
数日前、カミさんに新しいコートを買ってもらったので、
ごきげんで生きてます。
あなたにとっても、
これを読んだ日が、良い日になりますように。

おりべまこと電子書籍新刊
昨夜よりもっと
いい夢を見る方法
「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。
そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
AmazonKindleから発売中。¥360
「昨夜よりいい夢を見る方法」発行

受験シーズン。
かつては受験について「四当五落」
という言葉がありました。
これは「4時間睡眠なら合格・5時間だと落ちる」
つまり、合格したけりゃ寝る時間を削って勉強しろ!
根性出してぶっ倒れるまでガンバレ! という意味です。
さすがに今どき、こんなことを言ったら、
ひんしゅくを買ったり、笑われたりしますが、
昭和世代の人たちは、受験でも仕事でも、
「ねたら負け」神話に洗脳されていました。
僕も21世紀のはじめ頃までは、夜中、
いつもふらふらになりながら仕事をやっていました。
「俺は徹夜でやっている!」
「みんな、徹夜でがんばろう!」
テレビ・イベント・映像制作などの職場だったので、
そんな空気が社内に充満し、
おかしな自己満足と、一種のイベント感がありました。
若かったので、それなりに楽しかったのですが、
もちろん、今はもう無理です。
マインドセットが「ねないでガンバレ」から
「ねなきゃダメダメ」に変わったのは、割と最近。
ここ10年ほどか、
せいぜい平成後半からではないでしょうか?
睡眠の重要さは、さかんに唱えられるようになりましたが、それに付随して、
夢の重要さが語られることはあまりありません。
夜でも明るくなった現代、とくに都市部では、
世界の半分、人生の半分が夜であること、
さらにその大半である睡眠時間は、
自分の意識を離れた夢の世界であることは
忘れられがちです。
夢から文学や芸術を生み出す人がいます。
夢から仕事のヒントを得るひとがいます。
夢から自分の運命を考え、人生を変える人もいます。
昔の人はかなり「夢のお告げ」
みたいなものを重要視しました。
そう考えると、
昼間の仕事や生活に閉塞感を感じている人は、
もっと夢みることを大切にしていいのではないかと
思います。
それにいい夢を見ると、
単純に幸福で元気な気持ちになれますよ。
そんな思いから書いた「いい夢を見る方法」をはじめ、
何をすれば人生楽しくなるか、
世の中がちょっとは面白くなるかについて、
自身のブログで綴った36のエッセイを電子書籍にしました。「生きる」をテーマにしたシリーズの第6弾です。
読めば、人生がちょっと元気に、楽
しくなるかもしれません。
本日1月20日から発売。
おりべ まこと 電子書籍新刊
「昨夜よりもっといい夢を見る方法」
AmazonKindleから発売中。¥360
「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。
そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」
2022年9月から23年末のなかから抜粋。

●もくじ
・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?
・「芝浜」と女落語家
・名古屋の母と母校の話
・入学祝いはやっぱり桜
・百年生きるホモサピの世界はこれから
・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶
・これからどうやって旅に出るか?
・自分の未来、世界の未来、子どもの未来
・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない
・ときにはダンゴより花
・4630万円の振り込み
・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?
・井上ひさしと笑いについて
・人生は長くて短い
・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる
・潮騒の音楽を楽しむための海
・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用
・いい夢を見る方法
・なぜ30年前のトレンディードラマには
お彼岸が出てこなかったのか?
・親より先に死んではいけません
・余命7年で行こう
・女じゃなくなる恐怖
・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。
・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」
・こっそりカメ走
・人生は地中に埋もれた化石のようなもの
・アーカイブ世代のクロニクル研究
・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?
・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話
・9月15日はロージンの日?
・お祭リベンジ
・同窓会の話
・地球の重力に逆らうべからず
・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論
・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方
・美しきニューヨークのカレンダー 全36篇
昨夜よりもっといい夢を見る方法
おりべ まこと 電子書籍新刊
「昨夜よりもっといい夢を見る方法」
1月20日、AmazonKindleから発売予定。¥360
「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。
人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。
そう思ったら読んでみてほしい。
生きるのが楽しくなる36のエッセイ。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」
2022年9月から23年末のなかから抜粋。
●もくじ
・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?
・「芝浜」と女落語家
・名古屋の母と母校の話
・入学祝いはやっぱり桜
・百年生きるホモサピの世界はこれから
・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶
・これからどうやって旅に出るか?
・自分の未来、世界の未来、子どもの未来
・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない
・ときにはダンゴより花
・4630万円の振り込み
・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?
・井上ひさしと笑いについて
・人生は長くて短い
・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる
・潮騒の音楽を楽しむための海
・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用
・いい夢を見る方法
・なぜ30年前のトレンディードラマには
お彼岸が出てこなかったのか?
・親より先に死んではいけません
・余命7年で行こう
・女じゃなくなる恐怖
・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。
・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」
・こっそりカメ走
・人生は地中に埋もれた化石のようなもの
・アーカイブ世代のクロニクル研究
・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?
・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話
・9月15日はロージンの日?
・お祭リベンジ
・同窓会の話
・地球の重力に逆らうべからず
・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論
・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方
・美しきニューヨークのカレンダー
良い夢を見る方法2025

今朝はとても美しい夢を見てめざめた。
最近、何かいいことあったっけ?
と振り返ってみたが、特に思いつないので、
未来方面に目を向け、近々いいことがあるのかな?
と期待してしまう。
たかが夢でこんなに良い気分になるなんて、
ほとんど記憶がない。
もしかしたら人生を変える夢になるかもしれないと、
ちょっと大げさなことまで考えた。
そして「良い夢を見る方法」
なんてものがあるのだろうかと思って、
学者・研究者のサイトを検索してみたが、
とくにそういうものはないようだ。
強いていれば悩みごとを抱え込まないとか、
良い睡眠をとるとか、
その程度のごくごく当たり前のことしか書かれていない。
「良い睡眠をとる方法」と
[良い夢を見る方法」とは別だと思う。
記憶がどうこう、潜在意識がどうこうなど、
いろいろ説明はできるようだが、
結局、科学的に解明できないし、
メソッドなんて誰も編み出せない。
だから夢は面白い。
そこで今朝の夢を参考に、
自分で「良い夢を見る方法」を考えてみた。
・自分にウソをつかないこと。
・ある程度、人を慮って丁寧に接すること。
・好きなものは好き、面白いものは面白いと、
声に出したり、紙に書き出したりすること。
・自分を見失わないよう、
いつも、できるだけ心の中を整理整頓しておくこと。
要は本来の自分を大切にして、自分らしく生きるという、
ごくありきたりのことばっかりだけど、
夢が人生を映し出すとすれば、こうなるのだと思う。
夢は潜在意識からの贈り物だ。
潜在意識は、無意識の領域の一部であり、
無意識は個人的なもののほかに「集合的無意識」がある。
個人の経験による無意識よりも深く、
太古の時代からの無数の人々の
体験や記憶などが含まれており、
夢や神話の起源とも考えられている。
そして、過去ばかりでなく、
未来の誰かが体験する記憶であるとも考えられる。
僕たちは、人類、さらには地球の、
何百年か何千年か何万年か続く、
ストーリーの一部になっているのかもしれない。
眠りの中でそうしたストーリーの断片を時々、
見ているとしたら、
夢の世界にはもっと可能性が見いだせるだろう。
もうすこし経って、また科学が進歩し、AIが進化したら、
そうした夢の研究が進み、解析が行われるかもしれない。
そして、国家とか、企業とか、財閥とかの支配層が、
最後に残されたフロンティアを開拓するために、
「ためになる夢、役に立つ夢、利用しがいのある夢」
を見るメソッドを開発し、
ドリームマシンみたいなものを作り出して、
夢を征服しよう・管理しよう・搾取しようと
するかもしれない。
——という夢の話、というかSF的妄想もふくらんでくる。
でも願わくば夢は夢として、
「ああ、良い夢みたな」と楽しくなって、
後は忘れてしまいたい。
いずれにしても良い夢、
美しい夢を見られることは幸福なこと。
あなたも初夢だけでなく、
年中たくさん良い夢を見られますように。
おりべまこと電子書籍新刊
エッセイ集「生きる」シリーズ6
「良い夢を見る方法」
1月20日(月)AmazonKindleより発売予定。¥300
90歳は人生卒業の齢?

今日は義母の90歳の誕生日でした。
90歳の長寿祝いは「卒寿(そつじゅ)」です。
由来を調べてみると、
卒の字の略字「卆」が九十と読めるからと、
ダジャレみたいなことをもっともらしく書いてありますが、
いやいや、やっぱり「そろそろ人生卒業ですよ」
という意味だとしか思えません。
だって、そもそも「卒」という字を使っているんですから。
「卒」とは終わるっていう意味ですよ。
60歳の還暦で赤いちゃんちゃんこを着るのは、
もう一度、赤ちゃんに返って
人生やり直すというという意味が
含まれているとのこと。
そこから30年経って再び成人し、
卒業して今度はどこに行くのでしょうか?
ちなみにこの後の長寿祝いは、
99歳の「白寿(はくじゅ)」。
百から一を引くと「白」になることに由来。
なんて、これまた、ほとんどダジャレ。
白紙に戻るということでしょうか?
僕は「あしたのジョー」の
「まっ白な灰になっちまったよ」
というセリフを連想しました。
正式には白と紫の帽子とちゃんちゃんこを着るようです。
天台宗の坊さんは、いちばん下っ端は赤い袈裟で、
位が上がるにつれて、色が変わっていくのですが、
白とか紫の袈裟は、たしか、かなりの高僧です。
あの衣装の習わしはそこから来ているのでしょうか。
本人は認知症で何もわかっていないので、
さすがにそんな儀式などやらず、
お昼に助六寿司をごちそうしてお祝いしました。
生の魚が嫌いなので、お寿司は安上がりな
いなり・巻きずし・玉子しか食べません。
お誕生ケーキは成城石井のチーズケーキ。
これはどっちかというと、僕とカミさんが好物なので。
食べたらいつものように公園を散歩。
認知症でもまだまだ食べるし、歩けるし、
道行く人・犬・子どもに笑顔をふりまくことができる。
今日も「パーフェクト・デイ」。
人生卒業はもうちょっと先だと思います。
「パーフェクトデイズ」 どうせ死ぬのに、なぜ一生懸命生きるのか? を考える映画

青く晴れわたった空を見ていると、
なぜか胸が切なくなり、涙が出てくる。
歌だったか、小説だったか、忘れてしまったが、
誰かがそんなことを書いていた。
ヴィム・ヴェンダーズ監督、役所広司主演の映画
「パーフェクトデイズ」の感想を一口で言うなら、
そんな映画だ。
たんにエンタメとして楽しませてくれるよりも、
いろいろなことを考えさせてくれるのがいい映画、
あるいは、きょうはそういう気分になっている
人にとっては、これほどいい映画はない。
役所広司演じる主人公は、トイレの清掃員・平山。
朝、夜明け前に起き出し、支度して仕事に出かけ、
終わると安い飲み屋で一杯ひっかけ、
夜はふとんで本を読んで寝る。
その単調な生活、同じような毎日の繰り返しを淡々と描く。
周囲の人たちとの、小さなエピソードはいくつかある。
そして、彼が毎朝、若木に水をやったり、
公園の木々の写真をフィルムカメラで撮ったりする描写も、
そうした命を愛する人だということを伝える。
しかし、それだけだ。
平山の生き方を変えてしまうような劇的な展開、
物語らしい物語はいっさいない。
テーマらしいテーマもないように見える。
でも、僕はこの映画の秘密めいたテーマを見つけた。
まだ序盤のあたり、同じ清掃員仲間の若い男が
平山の丁寧な仕事ぶりをちょっとくさすように、
「どうせ汚れるんですから」という。
トイレだから当然だ。
どうせ汚れるのに、汚されてしまうのに、
どうしてそんなに一生懸命になって掃除するんだ。
僕もそう思う。
きっと誰もが、若い男のセリフを借りれば、
「10人のうち9人は」、いや、もしかしたら10人が
そう思うと思う。
誰もが豊かで便利で平和に生活できる、この社会では。
「どうせ汚れるのに、どうして一生懸命掃除するのか」
これは言い換えれば、
「どうせ死ぬのに、どうして一生懸命生きるのか」
につながる。
平山はきっとそうしたことを考えながら、
毎日のトイレ清掃に励んでいる。
それがどんな仕事でも、
ていねいに仕事をすることは、
ていねいに生きることにながる。
ていねいに生きれば、一日一日がきれいに輝く。
そんなメッセージが流れている。
平山は現代社会に取り残されてしまったような人だ。
孤独だし、もう若くないし、カネも持っていなさそうだ。
スマホもパソコンも使わなければ、
ボロアパートの部屋にはテレビさえ置いていない。
車は持っているので、ラジオは聴くかもしれないが、
彼がラジオを聴くシーンは出てこない。
車内で聴くのはもっぱら古いカセットテープ。
1960年代から70年代の音楽だ。
彼の年齢は60歳前後と察せられる。
要は、学生だった40年ほど前の時代と
ほとんど変わらない生活を送っているのだ。
そんな取り残され、落ちこぼれた、
高齢者に近い孤独な男だが、
なぜか周囲の人たちを励まし、
元気づける存在になっている。
先述の若い男もそうだし、
その男が好きになった女も平山にキスをする。
極めつけは、中盤で彼のアパートにやってくる姪だ。
高校生らしき彼女は、伯父である平山を慕って、
仕事についてきたり、いっしょに銭湯に行ったりする。
この姪との会話のなかで、平山は、
「みんな一緒の世界に住んでいるようで、
じつは別々の世界に住んでいるんだ」
といった意味のことをいう。
彼のバックストーリーは一切語られないが、
この姪を連れ戻しに来た母親=彼の妹との短い会話は、
平山の人生を想像させる。
妹は高級そうな車に乗っており、
彼とは段違いの裕福風な暮らしを送っていることが
見て取れる。
また、彼の父親は高齢で認知症らしく、
施設に入っているようだ。
実家はかなりの資産家で、
長男である平山は、父の生き方に反発し、
家を出たまま、齢を重ねてしまったのかもしれない。
妹とは同じ家庭で育ちながら、
互いにまったく違う価値観を持った人間になってしまった。
けれども、きょうだい仲は悪くない。
姪の家出もそんなに深刻なものではなく、
母親に素直に従って帰っていく。
けれども彼女にとって、伯父の持っている世界は、
一種の憧れに満ちた世界として映っている。
この姪や、仕事仲間の男、そのガールフレンドらは、
みんな若く、軽やかに、
面白おかしく生きているように見える。
けれどもその裏側に漂う切なさは何だろう?
彼女らは、平山の存在に何を感じていたのだろう?
それはきっとこういう予見だ。
わたしも、おれも、いずれ齢を取り、死ぬ。
それまでどう生きればいいのか?
そうした思いにあまり齢は関係ないのかもしれない。
映画の終盤、彼が最後に励ますのは、
行きつけの飲み屋のママのもとを訪れた男である。
平山と同年代らしいこの男は、ママの元夫で、
ガンでもう寿命があまりない。
それで別れた妻に最後に会いに来たという経緯だ。
「結局、何もわからないまま終わっていく」
という男のセリフは胸に刺さる。
そんな男をやさしく励ます平山のふるまいは、
ひどく感動的だ。
平山の人生はこの先、劇的に展開する気配はなく、
きっと彼はこのアパートの一室の片隅で、
野良猫のように一生を閉じるのだろう。
社会に置き去りにされた、底辺のエッセンシャルワーカー。
高齢者に近い孤独で無口な男。
そんな彼の存在にも価値がある。
1本1万円で売れる、
聴きつぶした中古のカセットテープのように。
彼の人生は輝いている。
一日一日がパーフェクト・デイ=完璧な日だ。
このタイトルは、ルー・リードが、
1972年に発表した同名曲から取ったものだろう。
晴れわたった青空を想起させるような、
美しいが、ひどく物悲しい旋律に乗せて、
意味深な歌詞が繰り返される。
Just a perfect day
ただただ完璧な一日
You just keep me hanging on
君は僕をかろうじて生かしてくれている
You're going to reap just what you sow
自分の蒔いた種は、すべて刈り取らなくてはいけない
2023年のカンヌ映画祭など、
世界的に評価された作品であることは
あまり意識せず、
素直にありのままの気持ちで見た方がいい。
そうでないと、この映画の真価は見えてこない。
ヴェンダースの作品はむかし何本か見たが、
若い頃の自分にとっては退屈だった。
たぶんヴェンダース映画を見るのがイケてる、
カッコいいといった意識が入っていたからだろう。
これはシニアの自分には面白く見られたが、
若い人には退屈かもしれない。
でも、自分の目で見てほしいと思う。
「ベルリン天使の詩」「パリ、テキサス」など、
かつてはつまらないと思ったヴェンダース作品も
齢を取った目でもう一度、見てみたいと思う。
新しい何かを発見できるかもしれない。
「世界に一つだけの花」がテレビの懐メロ特集から消えた話
年明け間もなく話題を提供してくれた中居正広君の
9千万円示談金問題。
事実関係がよくわからず、
例によって憶測ばかりが飛び交って、
たぶん2月になる頃には、
みんな忘れてしまうだろうから一切触れませんが、
それよりちょっと気になったのが、
彼が所属してたSMAPの歌のこと。
年末のテレビにおいて恒例のように、
あちこちのチャンネルで懐メロ特集をやっていましたが、
ゼロ年代、国民的流行歌と言われた、
SMAPの「夜空ノムコウ」や
「世界に一つだけの花」がまったく出てこない。
なんだかあのグループ、あのヒット曲の数々が
エアポケットに落っこちて、
この世から消え去ってしまった感じでした。
いや、いろいろ権利の問題があるのは知っています。
そして、天下御免だったジャニーズ事務所が
あんなことになってしまった今となっては、
とてもテレビでは放送できないのでしょう、きっと。
けれども僕たちのようないい齢をしたおとなはともかく、
当時、SMAPの歌(或いは嵐など、
他のジャニーズグループの歌)を
聴きながら育った世代の子どもたち・若者たちの心情は
どうなるのでしょうか?
とくに「世界に一つだけの花」などは、
学校をはじめ、全国さまざまな地域イベントなどで使われ、語られ、彼らの子ども時代・青春時代の記憶とも
強く結びついているはず。
それが一切なかったことにされてしまうのは、
なんとも寂しいこと・悲しいことだと言わざるを得ません。
テレビや芸能界のルールとやらは、
そうした人びとの思い出や、
あの時、音楽がもたらした感動をチャラにしてしまうほど、ご大層なものなのか?
これでは若者はテレビにそっぽを向くわけだ、
と思わざるを得ず、考えれば考えるほど、
腹立たしくなりました。
「おとなの事情」なんてくそくらえ!
もっと懐メロを大事にしろ!
そんなわけで、AmazonKidleから
電子書籍「週末の懐メロ」全6巻を出版しています。
これは、2000年10月からブログ「DAIHON屋のネタ帳」で
3年半にわたって連載した文章をまとめたエッセイ集。
20世紀の、自分の好きなミュージシャン・楽曲について、
個人的な思いや体験、
あるいはその曲を聴いていた時代の状況、
当時のロック・ポップミュージック、
日本の歌謡曲やニューミュージックを取り巻く状況などを好きなように書き綴ったもので、1960~90年代の音楽を体験した人にとっては面白く読めるのではないかと思います。2000年リリースの「夜空ノムコウ」についてもスガシカオの楽曲として、第5巻に載録しています。
また、旧世代にだけでなく、
20世紀当時を知らない若い世代にとっても
きっと面白いに違いないと自負しています。
いまや 年代関係なく、インターネットを通して、
20世紀のポップ・ロック・歌謡曲などを
みんなが楽しめる時代になりました。
僕の20代の息子もキング・クリムゾンや
ブラック・サバスを聴いています。
僕よりよほど精通した、ロック博士みたいな若者もいます。若い人たちもネットでいろいろ調べて、
聴いて、懐メロを楽しむ時代。
その参考書、ガイドブックとしても、
役に立ててほしいと思っています。
ペットロスから人生観・死生観が変わる

ペットロスによって人生観が変わった
という人の話を聞いた。
飼っていた柴犬が目の前で車に跳ねられたという。
話によると、散歩中、首輪がすっぽ抜けてしまい、
その犬が走り出した。
彼は追いかけたが、犬は面白がってグングン走り、
大量の車が行き交う大通りの交差点に飛び出した。
信号は赤。車が停まれるはずがない。
衝突した瞬間、犬は空中に高くはね上げられた。
歩道にいた彼の視界からは、交差点の風景は消え、
空の青をバックに、スローモーションで踊るように3回、
からだが回転する犬の姿だけが見えていたという。
「僕、赤信号渡ってましたね。
よく自分も跳ねられなかったと思います。
道路に落ちた犬を抱き上げました。
病院に連れて行こうと思って、
まず家に帰ったんですけど、
ちょうど玄関までたどり着いた時に、かくって死んだ。
よくドラマなんかで「かくっ」って死ぬでしょ。
あれだったよ。かくっとなってね。
口からすんごい色の血が出てきて」
この飼い主というのは、坊さんだ。
お寺の坊さんなので、それまで葬式や法事でお経を唱え、
何百回とご供養のお勤めをしている。
しかしというか、だからというか、
死は坊さんにとっては日常的なことであり、
他人事でもある。
ビジネスライクになっていたところは否めない。
けれども、犬の死はこの坊さんに大きな衝撃を与えた。
彼は精神的におかしくなって仕事が出来なくなり、
本山に行って一週間、
引きこもり状態で法話を聴き続けたという。
「あんなに真剣に、
仏様についての話を聞くことはなかったです。
そのきっかけを犬がくれましたね。
だから僕は仏様が犬の姿となって現れて
僕をまとも坊主に導いてくれたんだと今でも思ってます」
彼は今、自分の寺を持ち、
そこにはペットロスの人たちが自然と集まってくる。
ペットが死んだからと言って、
誰もが彼のような経験をすることはないと思うが、
それでもペットロスがきっかけとなって、
人生観・死生観が変わるといった話は時々聞く。
いっしょに暮らす、命ある生き物は、
僕たちが通常送っている
人間の社会生活とは違った角度から、
生きること・死ぬことについて、
考えさせてくれるのは確かなようだ。
死について考えることは、
よりよい生について考えること。
Deathフェス|2025.4.12-17 渋谷ヒカリエで開催
「死」をタブー視せずに人生と地続きのものとして捉え、
そこから「今」をどう生きるかを考える 。
新たに死と出会い直し、
生と死のウェルビーイングを考える「Deathフェス」を、
毎年4月14日(よい死の日)を中心に開催。
著名人の死2024とDeathフェス2025

1月4日:篠山紀信(83)写真家
1月16日:庄司歌江(94)漫才師
2月6日:小澤征爾(88)指揮者
2月20日:山本陽子(81)俳優
3月1日:鳥山明(68)漫画家
3月4日:TARAKO(63)声優
3月14日:寺田農(81)俳優
4月8日:宗田理(95)作家
4月10日:曙太郎(54)力士
4月21日:フジ子・ヘミング(92)ピアニスト
4月26日:桂由美(94)デザイナー
5月2日:小山内美江子(94)脚本家
5月4日:唐十郎(84)劇作家
5月16日:中尾彬(81)俳優
5月27日:今くるよ(76)漫才師
6月9日:久我美子(93)俳優
7月4日:赤塚真人(73)俳優
7月26日:園まり(80)歌手
8月1日:桂米丸(99)落語家
8月28日:宇能鴻一郎(90)作家
9月3日:ピーコ(79)タレント
9月29日:大山のぶ代(90)声優
9月30日:山藤章二(87)イラストレーター
10月4日:服部幸應(78)料理評論家
10月17日:西田敏行(76)俳優
10月23日:せなけいこ(91)絵本作家
10月25日:楳図かずお(88)漫画家
11月12日:北の富士勝昭(82)力士
11月13日:谷川俊太郎(92)詩人
11月14日:火野正平(75)俳優
11月15日:崇仁親王百合子(101)皇族
12月6日:中山美穂(54)俳優
12月9日:小倉智昭(77)フリーアナウンサー
12月19日:渡辺恒雄(98)実業家
昨年(2024年)亡くなった著名人を書き出してみた。
上記は僕が知っている人たちだが、
どの世代の人も、このうち半分くらいは
ご存知なのではないだろうか。
彼ら・彼女らの活動・作品・発言・パフォーマンスの数々は、
僕たちの心の形成に何かかしらの影響を及ぼしてきた。
少なくとも何十年も会っていない親戚よりは、
かなり身近に感じるはずだ。
テレビなどで、このように
身近に感じて来た人たちが亡くなるたびに、
僕たちは、日本が超高齢化社会であるとともに、
超多死社会であることを思い知る。
死について考えることは、
よりよい生について考えること。
Deathフェス|2025.4.12-17 渋谷ヒカリエで開催
「死」をタブー視せずに人生と地続きのものとして捉え、
そこから「今」をどう生きるかを考える 。
新たに死と出会い直し、
生と死のウェルビーイングを考える「Deathフェス」を、
毎年4月14日(よい死の日)を中心に開催。
息子の安上がり正月リゾート

暮れから正月にかけて、足掛け1週間、
息子が泊まっていった。
別々に暮らすようになって以来、
こんなに長くいたのは初めてだ。
元旦が映画の日だから、ということで、
一人で池袋に「マッドマックス怒りのデスロード」と
「地獄の黙示録」を観に行ったのと、
昨日(4日)にいっしょに初詣に行った以外は、
家でゴロゴロしていた。
うちをリゾート施設扱いしているのかもしれない。
ずいぶん安上がりなリゾートだ。
その代金というわけではないが、
自分ではなかなかアプローチしない
マンガのこと、小説のこと、映画のことなど、
若い世代のトレンド的なものについて、
いろいろ教えてもらった。
会うたびにそういう話をして、
彼のおすすめをあれこれ見たり読んだりするのだが、
いつもなかなか消化しきれない。
今年こそはと思い、
本はいくつか手配したが、
どこまで読めるか。
今日の昼飯を食って帰ったが、
しばらくいっしょにいたので、
なんだかちょっと寂しくなった。
かといって、すっかり大人になった息子に
帰ってきてほしいとは思わない。
子供に戻ってもらっても困るし。
ただ、齢を重ねた親というのは、
こういう微妙な気分も味わうのだぁなと、
しみじみした。
というところで今年の正月はお終い。
年賀状卒業生の皆さん、また会おう

「勝手ながら今年で年賀状を卒業させていただきます」
今年も何枚か、年賀状でこうした文面を見かけた。
ふだん、オンライン上でやりとりはしていないが、
連絡を取ろうと思えば、いつでも取れる人なので
いいと言えばいい。
べつに腹を立てるとか、いやな気持になるとか、
そういうことではないのだが、
それでも正直、ちょっと胸の中がモヤっとする。
どんな心境の変化だろう?
何か彼・彼女の身に何かあったのだろうか?
たしかにハガキ代は値上がったが、
そこまで節約しなくてはならないほど、
経済が困窮しているのか、
いやいや、まさか・・と、
あれこれ、どうでもいいことを考えてしまう。
「虚礼廃止」ということか。
僕は最初から義理立てするために
年賀状なんか出していないので、
「虚礼」をしているつもりはない。
仕事上の交流がなくなった人とは、
自然にやりとりもやめたし、
いまだ出しているのは、
やっぱり年一度は挨拶しておきたいなと
思う人ばかりである。
なので、ノリとしては中学生や高校生の時と変わらない。
あの頃の年賀状はすごく楽しくて、ワクワクした。
いかにもガキっぽい、面白い絵柄と文面は
50年以上経った今でもはっきり覚えている。
好きな女の子から来た年賀状はずっと大事に取っていた。
「お正月は○○神社で巫女さんのバイトやってます」と、
可愛いイラストを付けて書いてあった。
(家が遠かったのでその神社には行かなかったが)
そう考えていくと、
卒業宣言した人たちは、
僕とのやりとりも「虚礼」と捉えていたのかなと思う。
たぶん、それが「モヤっと」の正体だろう。
確かに、10年どころか、20年、30年、
一度も会っていない人もいた。
別に彼らを責める気はない。
僕の方が勝手にモヤっとしているだけだ。
それによくよく考えると、20代の頃は
ほとんど自分から出していなかった。
ちゃんと毎年出すようになったのは30代からだ。
いや、もしかしたら結婚してから、
子供が出来てからかもしれない。
よく憶えていない。
一時期は可愛い子供の写真、
幸せそうな家族の写真の年賀状がいっぱい来ていたし、
僕も息子が中学のころまでは
カミさんと息子と3人で撮った写真を
年賀状にして出していた。
あれっていま思えば、同じ立場の人たちはともかく、
そうでない人たちにとっては
かなり鬱陶しかったのかもしれない。
それに最近は個人情報開示のリスクが大きいので、
ああいうファミリー年賀状はヤバイのではないかと思うが、
小さい、可愛いお子さんをお持ちの方は
どうしているのだろう?
そして、もうこの世にいない人の年賀状も、
彼らの顔つきで何枚か思い出した。
去年が最後になってしまった友だちもいる。
長く生きていると、年賀状ひとつをめぐって、
あれこれ考えることがたくさんある。
年賀状文化の終わりということなのだろうか?
だからと言って寂しがっているわけではないが、
時代の移り変わりの一つの表れであることは確か。
LINEやメールなどで送られて来る
デジタルなご挨拶でも、
何十年か後、こんなふうに、
あれこれ思い出すことがあるだろうか?
と、ふと考え込んでしまった。
義母のお正月スペシャル
義母を初詣に連れていく。
出かける前、靴下がはけないと言って騒いでいるので、
見に行ったら、なんと、手袋を履こうとしている。
そりゃ履けるわけないよ!
新年初笑い劇場か。
と、お正月スペシャルボケをかましてくれた。
都内有数、皇室御用達でもある大宮八幡宮が近いので、
義母もいっしょに行っていたのだが、
この数年、とくに昨年夏、肺炎ぽくなって
1週間入院してからは、さすがに以前ほど歩けなくない。
近いと言っても、年寄の足だと30分近くかかるので、
代わりに半分程度の距離の尾崎熊野神社に詣でる。
こちらは大賑わいの大宮八幡宮と比べると、
規模も人出も1割、2割程度。
僕ったちが行った10時過ぎは
ほかにほとんど人がおらず、
お参りの後、二人でベンチに座って日向ぼっこをしていた。
今日は日中はぽかぽか陽気で、
帰りもあちこちで坐って日向ぼっこしていたので、
結局2時間も散歩していた。
これもまたお正月スペシャルということで。
2025年、高齢者1年生は18歳

あけましておめでとうございます
年初の目標は「18歳になって生きる」。
どれだけジタバタしたところで、
今年から「高齢者」と呼ばれる齢になってしまう。
なのでこの際、自分を洗脳することにした。
ただし、体力も感受性も半減どころか、8割減。
そして、カネもうけ主義と
魑魅魍魎渦巻くネット情報に
すっかり脳をやられてポンコツになっている。
そんなありさまなので、
言い換えれば、きょう「18歳でいよう」
と決めたことを
どこまで維持できるかが今年の目標になる。
具体的には、小説4作を含め、
月1で電子書籍を出して行く。
さらに小説については、
声優さんと組んでオーディオブックを出したい。
あとは昨年、100冊本を読んだ息子を先生にして、
19世紀文学の探究と、
最近のマンガの探究をしていきたい。
いつまでも昭和や懐メロで心を癒していられない。
新しい世界の探究も今年のテーマだ。
そして昨年の政治情勢、国際情勢、
名のある文化人・芸能人・芸術家らの多くが
他界したことを考えると、
今年はまた、時代の大きな変化があるだろう。
さすがに「老害」が退潮の兆しを見せている。
なんとなく18歳の時のわくわくした気持ちが
お腹の奥でうずくのを感じる。
いろいろ面白くなりそうだ。
ということで、とりあえずは
来週までに年末に取材した会社の
ホームページのテキストを仕上げる予定。
18歳でも生活は着実に。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
おりべまこと電子書籍2024
今年は長編・中編、1作ずつの小説を出版。
2025年は書きかけの長編、
プロットを用意してある長編のなかから2作、
新しいアイディアの中短編を2作リリース予定。
エッセイ集は「週末の懐メロ」全6巻完結。
昭和99年は「昭和99年の思い出ピクニック」刊行。
その他、「食べる」「生きる」「動物」シリーズも。
2025年は「AI」「認知症」「エンディング」など
リリース予定。
そして締めくくりは「昭和100年の思い出ピクニック」。
新設ノンフィクションシリーズ
「市井の賢者(仮題)」を1月か2月にリリース予定。
2025年も書いていきます。
また読んでくださいね。
●今はまだ地球がふるさと
https://amazon.co.jp/dp/B0CW1FWZ59
●花屋のネコの大いなる任務
https://amazon.co.jp/dp/B0DPCN144Z
●週末の懐メロ第6巻
https://www.amazon.com/dp/B0CW1KKHXL
●昭和99年の思い出ピクニック
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWG58MCQ
年末の認知症ミステリー

クリスマス前から年内UPの仕事に追われ、
なんとか完了。
年賀状も書き終え、大掃除も本日昼過ぎに終えた。
豆を煮て、花を飾ったところへ、
夕方、息子がお年賀を持ってやってきた。
やれやれ、やっと落ち着いて正月を迎えられる・・・
と思って義母の帰りを待っていた矢先、
デイサービスのスタッフがひとりで来て、
「すみません。車から降りないんです」。
驚いて見に行くと、
がんとして後部座席に座ったままの義母。
「さあ、いっしょに晩ごはん食べよう」
と言っても、心を開かない。
仕方なく、スタッフがひと回りして戻ってくると、
やっと応じて車を降りた。
その後はいつもと変わることなく、
いっしょにご飯を食べて床に就く。
食欲に支配されているので、
ふだんは家にいない息子(彼女には孫)が
来ていることにも頓着しない。
というか、そもそも気付いていない。
じつは2日前、別のデイサービスの帰りでも
同じことがあった。
これまでいっしょに暮らして5年半、
こんな振る舞いは一度もなかったのだが。
どういう心の動きがあるのだろうか?
1年が終わることをどこかで察知して、
無意識のうちに不安になっているのだろうか?
認知症の不思議な現象は、どこからともなく降ってくる。
クリスマスカードと年賀状2024

今年も天才クラフトワーカーから
クリスマスカードが届いた。
今回のは一段と手が込んでいて、
かわいい靴下は本物の手編み。
いつも数十通、こんなのを送っているという。
彼女にはお返事として、毎年必ず年賀状を送る。
今年は郵便料金が値上がったこともあって、
「年賀状じまい」が加速しているらしい。
まさか、まさかの事態。
年賀状文化の崩壊が始まっている。
でも、SNSやLINEを使った年賀の挨拶と
年賀状とは、ずいぶんニュアンスが違う。
しばらく会ってない人、
ふだんは頭の中に存在していない人から
いきなりスマホに届く「おめでとう」には
戸惑いや怪訝な感じ(勧誘・商売の伏線?とか・・・)
を覚える。
仕事でデジタルはいいが、
正月の挨拶はやっぱりアナログであってほしい。
その点、年賀状だと違和感がない。
ああ、まだ生きてるな、
まだ彼(彼女)と繋がっているんだな、
という安堵感・安心感を覚える。
たしかに形式だけのやりとりならいらないと思うが、
SNSで連絡を取り合うほど
密な交流はしたくないけど、
なんとなく自分の人生のどこかにいて欲しい人とは
正月だけでも「おめでとう」と紙面で挨拶したい。
というわけで、クリスマスが済んだら、
あっという間にお正月。
これから年賀状書きます。

おりべまことの電子書籍
現代を生きる大人に贈る童話
花屋のネコの大いなる任務
無料キャペーンは、本日16:59をもって終了しました。ご購入いただいた方、ありがとうございます。よろしければレビューをお寄せください。同書は引き続き、AmazonKindleにて¥500で販売中。年末年始のあなたの心にプレゼント。
自分へのクリスマスプレゼント

おりべまことの電子書籍
現代を生きる大人に贈る童話
花屋のネコの大いなる任務
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
無料キャンペーン間もなく終了。
12月23日(月)16:59まで。
さあ、急がニャいと。
自分へのクリスマスプレゼントにどうぞ。
旅のお供はネコですか?

夢をかなえたあとも、
成功を果たしたあとも、
欲しい物をすべて手に入れたあとも、
まだまだ人生は続く。
夢に届かない人も、
失敗して転んだ人も、
何も手に入れられない人も、
まだまだ人生は続く。
あなたがどっちか知らないけど、
いっしょに旅をするおともがいれば、
まだまだ人生続けられる。
現代を生きる大人のための童話
花屋のネコの大いなる任務
12月23日(月)16:59まで
無料キャンペーン開催中。
あなたの“ねこ”は、どこにいますか?
夢をかなえても、
成功を果たしても、
欲しい物をすべて手に入れても、
むなしかったり、涙が出たりする。
そんなあなたの心を満たす“ねこ”は、
どこにいますか?
現代を生きる大人のための童話
花屋のネコの大いなる任務
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPCN144Z
12月23日(月)16:59まで
無料キャンペーン開催中。
「花屋のネコの大いなる任務」無料キャンペーン

おりべまこと電子書籍最新刊
おとなも楽しい少年少女小説
「花屋のネコの大いなる任務」
本日より6日間無料キャンペーン開催中。
12月23日(月)16:59まで。
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
クリスマスの賢者の贈り物として、
あなたの胸の本棚に1部いかがかニャ?
●あらすじ
彼女は「お花屋さんになりたい」という
少女時代の夢をかなえた。
今はとある町の小さな花屋の女主人として、
ひとりで店を切り盛りしている。
花に関する豊富な知識、アレンジメントのセンスと技術。
加えて人柄もよく、お店の評判は上々で、
商売はうまいこといっている。
彼女自身も毎日、大好きな花に囲まれて
仕事ができて幸せだ。
ところが、明日は母の日という土曜日の朝、
店の外に出て、びっくりした。
そこに置いてあったカーネーションの花が
ネズミに食い荒らされていたのだ。
ショックを受けた彼女は、
今後、二度と店にネズミを寄せつけないよう、
ネコを飼う決心をする。
保護猫サイトを探すと、
かわいらしい子猫たちにまじって大人のネコがいた。
人間に保護されるまで1年間、
野良猫として生き延びてきた頼もしそうな奴だ。
しかも彼は、オスの三毛猫というレアものである。
女主人は彼を引き取り、
「ダビ」と名付け、自分に言い聞かせた。
「寂しいからじゃない。癒されたいからじゃない。
ネズミよけのためにこのネコを飼うんだ」と。
そして、自分とネコとの関係を明確にするために、
雇用契約を結ぶ。
彼女は仕事の依頼主。
その報酬として彼に食事と寝床を与える。
こうして、花屋の女主人と
三毛猫ダビの暮らしが始まった。
花屋のネコの大いなる任務 無量キャンペーン予告2
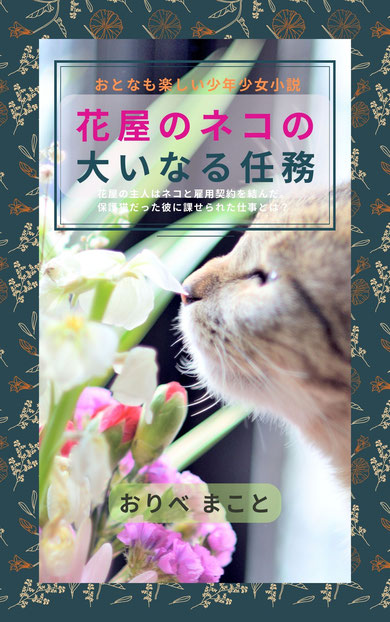
お待ちかね。6日間無料キャンペーン開催します。
12月18日(水)17:00~23日(月)16:59まで。
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
ふと気が付くと、最近、
女性や女の子が主人個の話ばかり書いている。
この齢になると、男でも女でも、
子供でも大人でもジジババでも、
イヌでもネコでもネズミでも、
なんでも自由自在に変身できる。
「花屋のネコの大いなる任務」無料キャンペーン

お待ちかね。6日間無料キャンペーン開催します。
12月18日(水)17:00~23日(月)16:59まで。
一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、
彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。
花好き、ネコ好きに贈るクリスマスプレゼント。ぜひ。
●あらまし
彼女は「お花屋さんになりたい」という
少女時代の夢をかなえた。
今はとある町の小さな花屋の女主人として、
ひとりで店を切り盛りしている。
花に関する豊富な知識、
アレンジメントのセンスと技術。
加えて人柄もよく、お店の評判は上々で
、商売はうまいこといっている。
彼女自身も毎日、
大好きな花に囲まれて仕事ができて幸せだ。
ところが、明日は母の日という土曜日の朝、
店の外に出て、びっくりした。
そこに置いてあったカーネーションの花が
ネズミに食い荒らされていたのだ。
ショックを受けた彼女は、
今後、二度と店にネズミを寄せつけないよう、
ネコを飼う決心をする。
保護猫サイトを探すと、
かわいらしい子猫たちにまじって大人のネコがいた。
人間に保護されるまで1年間、
野良猫として生き延びてきた頼もしそうな奴だ。
しかもオスの三毛猫というレアものである。
女主人は彼を引き取り、
「ダビ」と名付け、自分に言い聞かせた。
「寂しいからじゃない。癒されたいからじゃない。
ネズミよけのためにこのネコを飼うんだ」と。
そして、自分とネコとの関係を明確にするために、
雇用契約を結ぶ。
彼女は仕事の依頼主。
その報酬として彼に食事と寝床を与える。
こうして、
花屋の女主人と三毛猫ダビの暮らしが始まった。
AIはマンガのロボットみたいな相棒

今年はAIが大きく進化した年だった。
僕も去年まではお遊びで触る程度だったが、
今年は夏場、ちょっとヒマだった時期に
セミナーを受けて、
AIを仕事で積極的に使い始めた。
新しいテクノロジーを肯定するか比例するかは
その人の自由だが、
これだけ世間でAIについて言及され、
いずれ多くのマンパワーがAIに取って代わられる
といった話を聞いていると、
やはりある程度は知っておかないと駄目だ。
ろくに知りもしないで「AIなんか要らない」
と、ただ否定していると、
内心、どんどん不安とストレスが溜まっていく。
これはあまり良くない状態だ。
AIを知り、使い方を身に着けるには、
ただ遊んでいるだけでは不十分で、
やはり実際に仕事で使ってみる必要がある。
というわけで,いろいろ試して、
AIライティングの概要を
つかんでからは、できるだけ、
どんどん使うようにしている。
僕の場合、取材の文字起こし、記事の構成、
リード文の作成、タイトル案の作成などが主な用途だ。
一度完成した原稿をもっとカジュアルに、
若い読者向けに、みたいな指示を与えて
アレンジする場合もある。
小説を書く際に、
対話しながらプロットを書くこともある。
自分がどの程度、
使いこなせているのはよくわからないが、
僕はあまりAIの普及を心配していない。
やっぱり機械は機械なので、使っていると、
いかにもみたいなビジネス文章の文型、
「成長「発展」「拡大「希望」といった、
やたらポジティブなワードを多発し、
きれいにまとめようとする傾向が強いからだ。
いわば「模範解答」みたいな文章ばかりで面白くない。
もちろん、プロンプトで「もっと柔らかい表現で」とか、
「もっと砕けて」とか指示すれば、
代案を出してくるのだが、
何度もやり直しさせるのがめんどくさいので、
結局、自分で書き直すことになる。
でも、AIのNG案を見て、
新しいアイデアがひらめくこともあるので、
AIの作業が無駄とか、使う意味ないとは思わない。
ようは付き合い方しだいだ。
AIは人間より神様に近いかもしれないが、
日本は多神教の国。
神様はヒューマンタッチで愛嬌があって、
ときどき悩んだり、ズッコケたりしている。
だからアトムやドラえもんみたいなマンガも生まれた。
来年以降、AIがどれだけ進化するかはわからないが、
当分の間は、できるだけ、マンガのロボットに見立て、
優秀だけど可愛くて楽しい
仕事の相棒にしていきたいと思っている。
週末の懐メロ180編
今年はブログで3年半連載した
「週末の懐メロ」を終えて、6冊の本にまとめた。
第1回「5年間/デビッド・ボウイ」から
最終回「オールウェイズ・リターニング/
ブアイアン・イーノ」まで、
国内外を問わず、自分が好きだった
楽曲・ミュージシャンについて
トータル180のエッセイを書いた。
最初は手抜きコンテンツとして始めたのだが、
やっていくうちにどんどん面白くなって、
自分の記憶・当時の時代状況や
音楽雑誌で読んだこと、個人的エピソード、
そして、YouTubeをはじめ、
各種ネット情報などをかけ合わせ、
ネタにした楽曲・ミュージシャンによっては
2千字、3千字におよぶこともしばしばあった。
20世紀の頃には知り得かなった
歌詞の詳しい内容、ミュージシャンの来歴、
その楽曲が生まれたエピソードなども
発見・深掘りできて、毎週とても楽しかった。
あの頃、心を満たしてくれ、
神秘の世界・感情の世界に誘ってくれ、
普通に生きているだけでは感じられないものを
体験をさせてくれた20世紀の
ロック・ポップカルチャーに感謝の念が尽きない。
人間が生きている限り、
音楽がこの世からなくなることはないが、
栄華を極めた音楽産業は、
この先、衰退の一途を辿るだろう。
今後はAIが進化して、誰でも簡単に、
いくらでも良い曲がつくれると言われている。
しかし結局、
それらはこの20世紀ロック・ポップカルチャーの
膨大なデータがあるからこそ生まれるものだ。
1950年代~90年代の天才たち、
そうでなくても、この時代、
幸運にも音楽の神とコンタクトできた者たちの
感性・知性から生まれた音楽の価値は、
これからも、いささかも下がることはないだろう。
アーカイブ文化が発達して、
僕の息子のような若い人たちでも、
僕などよりははるかに
20世紀ロック・ポップカルチャーに
詳しい人たちがいっぱいいる。
そうした人たちの勉強になるようなものではないが、
当時のリスナーの私的な感想・意見を交えた
雑文として読んでもらえたらいいなぁと思っている。
人生の半分はオンラインにある

先日、テレビのニュースで
闇バイトに関わってしまった
大学生の母親のインタビューを見た。
印象に残ったのは、同じ家で暮らす家族でも、
一人一人、何をしているのか・考えているのか、
どんな人間と付き合っているか、
まったくわからないという点である。
そんなこと今に始まったことではなく、
昔からそうではないかという声が
聞こえてきそうだが、
昔と違うのは、今はスマートフォン、
インターネットがあることだ。
僕が子どもの頃は、
テレビが「1億総白痴化装置」とディスられていたが、
それでもテレビは、家庭の暖炉の役割を果たしていた。
冬は特にそういった印象が強く、
みんなで居間で炬燵に入り、みかんなどを食べながら
テレビを見る時間は、
かけがえのない一家だんらんのひと時だった。
令和の時代において、そうした風景は、
ほとんど失われてしまったように思える。
たびたび書いているが、
「サザエさん」も「ちびまる子ちゃん」も、
もはや現実とかけ離れた
昭和ファンタジーの世界になっている。
子も親もオンラインの中に潜り込んで、
自分で様々な情報を収集して知識を蓄え、
SNSなど通じて、自分だけのコミュニティを持ち、
個々で楽しめる娯楽や心の拠り所を育てている。
同じ家に住んでいても、もはや、
昔の意味での家族ではなく、
個人個人がなりゆきで同棲し、
家をシェアして暮らしているという感じだ。
それぞれの人生の半分は、オンラインにあるのだ。
それでも大人はまだいいが、
子どもはどうだろう?
件の母親は、いっしょに暮らしている息子が
オンラインのギャンブルにはまり、
依存症になって多額の借金をつくり、
焦って闇バイトに引っ掛かってしまったという経緯に、
まったく気づけなかったという。
父親も同様だ。
大学生だから、へたに干渉すべきでない。
ある程度は自己責任で・・・
という親の気持ちはわかる。
ただ、今の子供はかなり高い割合で、
オンラインの世界に脳を乗っ取られていると
思ったほうがいい。
「デジタル・ネイティブ」という言葉は、
どちらかというとポジティブな意味合いで
使われることが多かった。
これからの世の中は、ITが発達するので、
そうした仕組みをよく理解し、
使いこなせる人間が活躍する。
僕たちは漠然とそう思っていた
(思わされていたのかもしれない)。
実際、街中でスマホに子守をさせ、
自分もスマホを見ている親にしばしば出くわす。
でも、子どもは大人と同じではない。
親(大人)は、リアル体験を重ね、
アナログ時代の情報取得のプロセスを経て、
オンラインと向き合っているので、まだいい。
でも、子どもは大人と同じではない。
リアル体験も、アナログ時代のプロセスも乏しい。
大人と違って、小さな子どもの脳には、
魑魅魍魎が混じり合っている情報のカオスに対し、
自分を守るシールドがまだ出来ていないのだ。
文字でも映像でも、情報の弾丸や刃が、
柔らかい肌をブスブスと簡単に突き破って、
むき出しの脳に、心臓に突き刺さってくる。
それらは人間性を著しく歪め、
破壊するほどの威力を持っている。
そうしたオンラインの脅威を感じ取ったのか、
先月、オーストラリアでは
未成年のSNS使用を禁止にする法案が通り、
施行されることになった。
いま一度、僕たちの人生の、少なくとも半分が
オンラインに移行している現状を考え、
子どもにどうこの装置を使わせればいいのか、
検討することも必要になるだろう。
ITが普及しようが、AIが発達しようが、
人間は人間のまま、変わるはずがない。
そう考えていると僕たちは安心できる。
けれども、その安心感が、じつは危険を孕んでいる。
テクノロジーの急激な進化によって、
いま、人間は変わり始めている。
あとの時代になって、
あの21世紀の最初の四半世紀の頃が
その変わり目だったのだ・・・
という歴史が生まれるかもしれない。
「クリスマスエクスプレス」におじさんたちは涙ぐむ
かつてJR東海に勤めていた、
もと鉄道マンの本を書いている。
彼はまだ民営分割化前の国鉄時代に入社。
39年間勤務して定年退職直前に辞めて
シニア起業家になった。
JR時代のアイテムや写真・記事などを
たくさん保存していて、
そのなかにあった牧瀬里穂との2ショット写真を
ちょっと自慢気に見せてくれた。
それは2017年、新幹線のぞみデビュー25周年記念の
イベントで撮ったものだそうだ。
彼は、1992年3月14日の、
のぞみデビュー車の運転士だったのだ。
でも、あれ?
あの牧瀬里穂のCM
「クリスマスエクスプレス」は1989年。
東海道新幹線は、
まだ「ひかり」と「こだま」しかなか
った時代だが‥‥。
ま、いいか。みんな喜べば。
たった1分のCMなのに、
いまや牧瀬里穂さんは、新幹線、
JR東海のイメージと分かちがたく結びついている。
これはすごいことだ。
そして山下達郎は、けっしてこのCMのために
「クリスマス・イブ」を書いたわけではないのだが、
このCMのおかげで、かの曲は
クリスマスソングの永遠の定番となった。
(初出は1983年。
実は竹内まりやのために書いたらしいが、
彼女が歌わなかったんで、
もったとないと自分で歌ったらしい)
その「クリスマスエクスプレス」が
4Kの美しい映像でよみがえり、
YouTubeに上がっている。
1989年の牧瀬里穂バージョンと、
1988年の深津絵里バージョン(実はこっちが初代)。
牧瀬と深津があまりにかわいくて
感動的なドラマであると同時に、
ついているコメントが面白い。
ループさせてえんえんと見ている人もいる。
夜中に家族に隠れて
こっそり泣いている人もいる。
僕も含め、最近、クリスマスて言ったってなーと、
全然盛り上がらない人は、
これを見て、テンション上げてください。
メディアの声より自分の声を聴け

僕たちはメディア、エンタメが
成長してきた時代とともに生きてきた。
だから、一度も会ったことがなくても
親しみを感じたり、寄り添ったり、
自分を重ね合わせる対象が大勢いる。
芸情人、アーティスト、文化人、スポーツ選手。
そのほか、本・舞台・ラジオ・映画・テレビ・ネットの
世界のあの人たち。
彼ら・彼女らの存在や活動、発言を
心のよりどころにしている部分もたくさんある。
多くの人、特に40代~60代の人たちにとって、
中山美穂さんはその代表的な一人だろう。
まだ54歳。
人生100年時代ではまだ十分に若い。
あまりに当然の死にショックを受けている人は
少なくない。
思えば今年も20世紀カルチャーをつくった、
たくさんの有名人が亡くなった。
トシだから仕方ないかと思える人もいれば、
まさか、あの人が…という人もいる。
20世紀カルチャーは終焉し、
僕らはこれから膨大なアーカイブのなかで
心を癒しながら生きることになるのかもしれない。
と思うことがしばしばある。
あなたはどうだろうか?
終わりは急にやってくる。
人生100年という言葉・イメージは、
希望の糧であるとともに、
大きな負担・不安のタネでもある。
100年、100年と言われている間に
「ライフプラン」という体のいい言葉を考えすぎ、
老後の不安ばかり膨らませ、
老後に備えることできゅうきゅうしながら
漫然と生きることになる。
自分は本当はいくつまで生きるのか?
60か70か? 90か100か?
もちろん、それを知るすべはない。
でも、「今」に集中して、
自分を活かして毎日を生きていれば、
どこかで事前にそれを知らせる声が
脳の奥から訪れるのではないかとも思う。
おまえは十分にやったと。
物語のような妄想だけど、
心の支え・励みにはなる。
生と死は表裏一体。
どう生きるのか?
どう死ぬのか?
メディアの声より自分の声を聴け。
秋の最後の日の散歩
明日から寒くなるそうなので、
今日は今年の秋の最後の日かも、
と思って、午後から義母を連れて
近所の公園を散歩する。
遠くに行かなくても紅葉をたっぷり楽しめる。
なかなか色づかなかったイチョウが
12月になってどんどん黄色くなり、
見事なゴールデンイエローに。
ほんの少しの風で落葉が雪のように舞って、
切なくも美しい。
「ほらほら、空からまたくるくる降ってくるよ」
と、高い木の枝から回転しながら降りて来る落葉を見て、
義母に促すのだが、どうも反応が鈍い。
認知症にも関わらずというか、だからこそなのか、
この人はときどき、路傍の小さな花を見つけたりして、
小さな子どものような感性の鋭さを見せることがあるが、
紅葉・落葉に関しては全然気をそそられないようで、
僕がどれだけ「ほら見て見て」言っても、
ほとんどゴミ扱いである。
そのくせ、そのへんに落ちている
お菓子の空き袋、ポケットティッシュ、
子どもが落としていったおもちゃやアクセサリーなどは
目ざとく見つけてガメようとする。
せっかく秋を楽しみに来たのに・・・。
と文句を言っても始まらない。
しかし、今日は暖かく、お天気も良く、
気分も体調もよかったようで、
なかなか帰りたがらず、2時間近くも歩いた。
こんなによく歩いたのは久しぶりだ。
ちなみにネコのいる花屋さんでは、
秋の花が終わったらクリスマスや正月を挟んで、
もう春の花。
暖かい部屋で春を楽しんでほしいのだそうだニャ。

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ
「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。
カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、
僕も土曜日に見たが、確かに面白い。
それにしても僕の中では、
綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、
そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。
役柄はもっと年上の設定らしいが、
もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。
そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの
スタッフも多くは40代
(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。
来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。
今や60・70代よりも40・50代のほうが
しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?
それどころか、20・30代も
「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。
どうやらがんばって終活するためには、
若いエネルギーが必要なのだ。
60・70代からじゃ遅すぎる?
いったいどうなっちょるんじゃ?
あっという間に1億総終活時代に突入だ。
「ひとりでしにたい」本当に面白いので、
観てない人は、NHKプラスで観てみてください。
電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」
無料キャンペーンは本日終了。
ご購入ありがとうございます。
よろしければレビューをお願いしますね。
AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
AIライフ、不老不死サイボーグ人生に興味のある方は必読。
6月30日(月)15:59まで 2025年半分終了記念
4日間限定無料キャンペーン開催中!
あとわずか。この機会にぜひどうぞ。
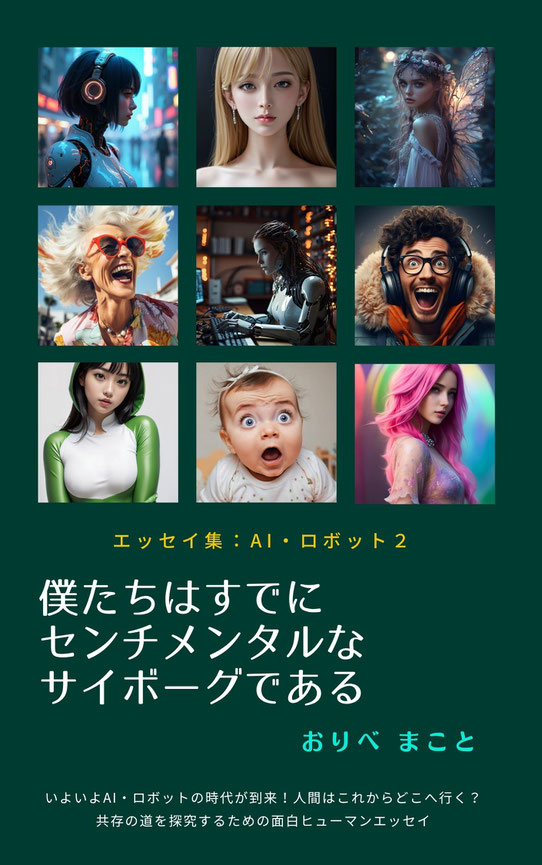
私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。
住環境から身体機能まで、あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、人間とは何かを問い直す時が来ました。
本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、
おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。
その内容の振り幅には驚かされます。
アンドロイド観音への戸惑いから始まり、
生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と
罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、
パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、
さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——
26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を
容赦なく描き出しています。
特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、
まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。
終活・終末期医療における
「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、
SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。
この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から
人間ドラマへと昇華させています。
「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、
これからどこへ向かうのでしょうか。
AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、
示唆に富んだエッセイ集です。
もくじ
アンドロイド観音とどう向き合うか?
100万回生きたロボット
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値
ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る
自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界
終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目
人生の半分はオンラインにある
AIはマンガのロボットみたいな相棒
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく
ほか全26編採録
「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から 「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ

子供は、強くて賢くて、何でもできちゃうロボットっていいな、
カッコいいな、僕もロボットだったらよかったのにな、
と憧れるのに、
大人になると「わたしはロボットじゃないんだ!」と言いだす。
なんで?
でも、齢を取ってくると、ふたたび、
ロボットだったらよかったのに、と思うかもしれない。
だってロボットはアンチエイジングだし、死ぬこともない。
最近思う。
人間として生まれた以上、
僕たちは一生ロボットにはなれないが、
技術の力で限りなくロボットっぽく生きることはできる。
私はそんなのごめんだ、
という人もこの時代に生きているかぎり、
じつは刻一刻とすでにサイボーグ化しているのだ。
そんな思いを込めて、AI・ロボット・エッセイ集第1弾
「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から
第2弾「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ。
AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ。
6月30日(月)15:59まで
2025年半分終了記念 無料キャンペーン開催中!
https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S
「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」無料キャンペーン開催
おりべまこと電子書籍 エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでに
センチメンタルなサイボーグである
本日6月27日(金)16:00~30日(月)15:59
2025年半分終了記念 4日間無料キャンペーン開催
私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。
住環境から身体機能まで、
あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、
人間とは何かを問い直す時が来ました。
本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、
おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。
その内容の振り幅には驚かされます。
アンドロイド観音への戸惑いから始まり、
生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と
罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、
パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、
さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——
26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を
容赦なく描き出しています。
特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、
まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。
終活・終末期医療における
「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、
SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。
この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から
人間ドラマへと昇華させています。
「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、
これからどこへ向かうのでしょうか。
AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、
示唆に富んだエッセイ集です。
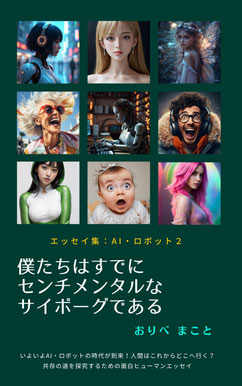
もくじ
アンドロイド観音とどう向き合うか?
100万回生きたロボット
ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します
生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値
ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る
自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界
終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目
人生の半分はオンラインにある
AIはマンガのロボットみたいな相棒
AIエロコンテンツが現実世界を変えていく ほか全26編採録
AIにご興味のある方、この機会にぜひご購入下さい。
山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識
なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」
小説(原作)と映画は別物。
それはそれでいいのだが、
そのギャップが大きければ大きいほど。
ツッコミがいがあって面白い。
「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は
その最たる例と言えるかもしれない。
川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、
映画にするなら、
全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。
それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、
その見せ場もいろいろ作る必要がある。
というわけで、この作品の場合は、
そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、
社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、
謎めいた演出が随所に散見される。
日本人の差別問題が裏テーマ
社会問題とは差別問題だ。
1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は
ちょっと遅れて日本にも及んだ。
70年代前半は、学生運動の挫折があり、
昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、
ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。
当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、
当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、
日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。
川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、
大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、
そうした日本人の差別意識が、
いかんともしがたい悪しき現実として、
随所にちりばめられている。
映画はそれらの材料をかき集め、
大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。
「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文
三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、
彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。
旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、
下賤な職業の人間として蔑視されている。
物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った
休憩所(だんご屋)の婆さんは、
旅芸人たちと親しげに話していたが、
学生に対しては
「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、
親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。
実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では
「あの人たちは今日の宿も決まっていない
(放浪者みたいなものだ)」と言っている。
映画ではこの婆さんの差別意識を、
いっそうあからさまに表現しているのだ。
セクシー少女・百恵の魅力の開花
なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、
「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と
一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。
彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。
これらは原作にはなく、この映画における演出である。
山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、
彼女の人気に火が付いたきっかけは、
シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、
当時ローティーンながら、
セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が
大ヒットしたからだ。
男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。
他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、
子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、
多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、
アイドル百恵の誕生につながった。
この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を
踏まえたものであり、
観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、
山口百恵の独特の、青い性的魅力を
うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。
ラスト1分 衝撃の不協和音
そして見せ場は最後の最後にやってくる。
学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。
見送りに来たのは、
かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、
船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、
大喜ぶで叫び、手を振り返す。
離れ離れになってはじめて
「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。
その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、
きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、
というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。
叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が
唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。
え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。
かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。
ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。
しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。
ひきつりながらも笑顔を保ち、
懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。
最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、
ストップモーションになってエンドマークが出るのである。
なんとも奇妙で、
まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。
なぜラストショットが、
若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、
汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?
夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。
ととでもメッセージしたいのか?
せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、
このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、
怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、
50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。
あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を
ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。
船が出る前、学生は地元の土方風の男に、
3人の幼子を連れた婆さんを
上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。
現代ならとんでもない無茶ぶりだが、
大正時代、エリートたるもの、
こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、
みたいな空気があったようで、
彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。
そして踊子との別れを終えた後、
伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、
東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて
彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。
当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、
庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、
立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、
そんな前向きな感想を持っただろう。
ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、
少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、
古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。
本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、
まだ読んだことがない人はぜひ。
そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、
豊かになった昭和日本で、
この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、
令和の世からタイムトラベルして、
若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。
母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから
「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」
と言われて、割とショックを覚えた。
でも、なかなか彼女は鋭かった。
確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に
いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。
女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、
同時にめんどくさかったり、怖かったり、
時々いやになったりもする。
それが態度や行動に出ていたかも。
その感情の遠因には、子供の頃、
母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と
一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。
その頃は母のことがあまり好きではなかった。
よく怒られたからである。
叔母と祖母はそれを見ていたせいか、
僕にやさしく、猫かわいがりした。
それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。
だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。
一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。
母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように
むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、
よけいにイライラを募らせたのだろう。
なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。
父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。
べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、
女運はよかったのかもなと思う。
思い出の中の女は、みんな可愛い。
この齢になると出会いも限られてくるので、
あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが
できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。
みんな齢を食ってしまったが、
女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。
こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。
今日は母の命日だった。
天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。
映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子
伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした
(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、
ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。
アマプラで1974(昭和49)年公開の
山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。
僕が中学生の時に公開された映画で、
当時大きな話題になっていた。
しかし当時、中二病にかかっていた僕は
「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」
と言って無視していた。
しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」
なんて映画は観に行った覚えがある。
山口百恵のファンだった試しはない。
「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、
少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、
僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。
中高生がアイドルに求める
可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが
大きな要因だったのではないだろうか。
同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、
むしろ女子の方に人気があった。
しかし今、この齢になって観ると、
唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。
この映画は女優として初出演作でもあるので、
演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、
明るさと陰とのバランスが素晴らしく、
この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。
●「え、はだか?」ではありませんでした
物語中、温泉に入っていたかおるが
学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって
裸で手を振るシーンがあるが、
そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。
最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、
いきなりグイっとカメラが寄る。
そして「え!?」と思う間もなく、
1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。
「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、
やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。
そりゃ当然だよね。
●「旅情」「異文化体験」を描いた原作
そんなわけで原作と並行して観たので、
小説との違いに目が行った。
俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い
「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を
リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。
もちろん、主人公の学生が旅先で出会った
芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が
メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。
少女を描くことに固執し、
ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、
この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、
恋愛的感情の表現はごく薄味だ。
そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ
「伊豆の踊子」が、
老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。
人物描写や風景描写などがイマイチで、
文学作品として未熟な部分も、
却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、
つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。
そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。
今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、
旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、
この物語の舞台である100年前は、
東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。
作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには
うってつけの場所だったのだと思われる。
そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う
旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。
「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが
圧倒的多数を占めていた、大正日本における
エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。
●河原乞食という現実
先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。
明治維新以降の近代日本では、
こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、
それはあくまで建前上、表面上のもので、
庶民がしっかり理解していたとは言い難い。
人々の心情に根付いた差別意識は、
まだ江戸時代のままだったのだ。
芸能人はどんな大スターだろうが、
すべからく「河原乞食」である。
原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)
という立札が出てくる。
この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、
旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。
川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、
ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。
踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、
こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。
とはいえ、川端は差別を告発しようと、
この作品を書いたわけではない。
あくまで旅で出会った現実の一つとして、
さらっと流している感じである。
クリエイティビティを刺激した山口百恵
この立札は原作では後半、終わりに近いところで
「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、
この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、
立札も物語が始まって間もないところで現れ、
かなり強い印象を残す。
まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。
かなり意図的なものと思われるが、
その背景として、おそらく当時、
社会改革の余波で部落問題などに焦点が
当たっていたことがあるのだろう。
また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、
日本の映画人も多かれ少なかれ、
社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。
それで監督や製作陣が、
単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、
と考えたのかもしれない。
山口百恵という稀有な素材は、
そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。
吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、
百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、
昭和の高度経済成長期以降の
「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、
現代にまで残る傑作にしたのだ。
映画の話、さらに次回に続く。
「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台
伊豆の河津に行ったのは先週だが、
駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。
それで初めて河津が、かの日本文学の名作
「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。
主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、
今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。
ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も
河津町だ。
いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、
そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、
生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。
おどろきの踊子
いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が
なんとなくどこかから耳に入ってきて、
知ってるつもり・読んだつもりになっている。
僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、
スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。
そして正直、びっくりした。
え、これだけ?って感じ。
文庫本でわずか40ページ。
字数にして2万字あまりの短編で、
30分ちょっとあれば読めてしまう。
旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで
けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、
ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。
どうしてこんなすぐ読める物語なのに、
俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、
自分の人生を後悔してしまった。
でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。
100年前の変態ロリコンじいさん
ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。
なんといっても「世界のカワバタ」。
ノーベル文学賞を受賞した、
敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、
その幻想もガラガラと崩れ去った。
今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。
「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、
最近の川端康成の定番像のようだ。
踊子へのエロい思慕
そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、
この「伊豆の踊子」の物語も、
なんとなくエロっぽく読めてしまう。
主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。
いわば川端の分身みたいな人物だが、
それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。
大学生が中学生に――ということなので、
今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、
ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)
全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が
メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、
いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、
頭がくらくらしてくる。
わずか40ページの短編のなかに、
こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、
日本文学の名作、それどころか世界名作としても
親しまれているゆえんなのかもしれない。
そう考えると、100年前の日本の文学界、および、
世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、
みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった
のではないか?という疑念にとらわれる。
いい加減だから名作になった?
正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、
そんなに中身のある話ではない。
話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。
物語としてはかなり薄味である。
川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、
もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、
旅芸人の一座との交流の部分を、
何年後かに抜き書きしたものらしい。
いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの
ノベライズなのである。
また、川端は、この作品では
「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。
でも、この作品の場合、その「さらっと感」
「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。
発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。
まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、
日本人のハートをわしづかみにした。
川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、
6度にわたって映画化された。
映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、
その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。
「女が箸を入れて汚いけど」
なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、
かなり深く心に刺さった部分もある。
それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。
100年前、旧制一高の学生と言えば、
日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。
対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。
さらにその中でも女は一段身分が低く、
一座のリーダー役の「おふくろ」は、
(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、
(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、
二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。
(川端が言わせている)
現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界
江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は
どんなに人気があろうとも被差別民であり、
身分制度の埒外の存在、
つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。
それは徳川幕府が、町人や農民に
「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、
できるだけ不満を抱かせないようにするための、
狡猾な支配構造をつくったからだ。
その意識は明治になって近代化された以降も、
えんえんと人々の意識に残った。
そういう意味では100年前、
大正から昭和になったころの日本はまだ、
現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。
モモエ踊子は差別問題を強調?
小説を読んだ後は、映画も見た。
1974年、昭和49年に公開された、
三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。
これも今に至るまで気が付かなかったが、
このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で
「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。
今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。
その話はまた次回に。
夫の精神的支配を受けた女性の話

うちのカミさんは鍼灸治療をやっているが、
話を聴いていると、患者さんの半分くらいは
精神疾患のせいで体もおかしくなっているようだ。
今日も不登校の高校生が
いきなり予約の合間を縫って昼食の時間に来たり、
「30年以上、一人で外出できなかった」という
60代の女性が診療を受けに来たと言う。
後者は、旦那の精神的支配を受けていて、
結婚して30年余りの間、
友だちとの付き合いはおろか、
買物も外食も、ひとりでは出してもらえなかったそうだ。
本当か? と耳を疑ったが、
いまだに一人で店に入れないという症状があるところを見ると、
どうも9割がたは本当のことらしい。
村上春樹の小説の中で、
金持ちではあるけれど、そういう恐ろしい価値観の男と
結婚してしまった女性の悲劇が
書かれてあったことを思い出した。
これは立派な精神的虐待だと思うが、
ひと昔前までは、
そんなに表立った問題にはならなかったのだろう。
もしかしたら今の50代以上--
昭和に生まれ育った女性では
そんなにレアなケースでもないのかもしれない。
その女性の場合は、子供がいないのも悲劇だった。
子供がいれば若い世代に救い出されたかもしれないし、
旦那の意識も変わっていた可能性もある。
結局、その旦那は3年前に借金を残して突然死んでしまった。
経済的には親戚のお金かなんかで助かったようだが、
彼女の病気はそのまま残った。
もう支配者がいないので自由なはずなのだが、
長年しみついた習性で一人で外出するのが難しい。
おそらく夫婦間で共依存の関係が出来上がっていたので、
自分で考え、行動することができなくなってしまったのだろう。
その女性がどういうきっかけで
来院することになったのか聴いてないが、
カミさんのところに来られるようになっただけ
治癒に向かっているのではないかと思う。
どうも買い物や食事に出かけるのは
「娯楽」として植えつけたらしく、
それを30年以上も禁じられていたので、
自分でも「娯楽=贅沢、無駄、悪」
みたいな意識が貼りついているらしい。
カミさんは、ひとりで喫茶店やレストランに入ることを
一つの目標にしなさいと言っているらしいが、
まだ実現できず、なかなか難しいようだ。
こういう話を聴くと、結婚とか、夫婦とか、
家族といったもののネガティブな面について考えてしまう。
よけいなことかもしれないが、
結婚ハッピー、夫婦なかよし、家族バンザイといった
画一的な価値観は怖い。
もちろん、明るく考えたほうがいいが、
そうしたダークな面があることも
常に心の片隅に置いておいたほうがいい。
そして、自分の間違いに気づいたら、
たとえ年寄りになっていても、
人生やり直す勇気を持つべきだと思う。
雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面
前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、
河童伝説の顛末を紹介したが、
いよいよ後編では本丸である。
住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、
快く承諾してくれた。
住職が大切そうに持参したのは、
見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。
よく見ると表面がややぼこぼこしており、
いかにも古い時代の手作り感が漂っている。
蓋は何度か作り変えられているそうだが、
壺本体は実に700年以上前のものだという。
「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」
住職がひっくり返すと、
底には「祖母懐」という文字が刻まれている。
●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産
「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。
これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、
温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。
愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、
そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。
さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。
「加藤四郎左衛門景正」
これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。
加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、
一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、
帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。
現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、
景正を祀った「陶彦社」が存在する。
「本物なら国宝級の品物です。
ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、
鑑定などしてもらったことはありません」
住職は笑いながら説明してくれた。
「河童からもらいました」と言えば、
鑑定士はどんな顔をするだろう?
そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら
どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。
さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、
粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。
そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、
焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが
四郎左衛門の作風だったそうだ。
確かに、目の前の壺も実に味わい深い、
野趣に富んだ風合いを見せている。
●いよいよ河童のせせらぎ体験
「河童はこれを置いていくときに、
『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。
これを聴いて私を思い出してください。
この川の音が聴こえる限りは、
私はどこかで元気に暮らしていますから、
和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」
住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。
果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?
「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、
ぼーっという音は聞こえるものなんです。
それは容器の中で風が流れる音で、
貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、
お分かりかと思います。
しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、
下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、
小さな水が流れる音がします」
住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。
最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。
しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!
確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが
聞こえてくるではないか。
まさに小川のせせらぎのような、
優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。
思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。
やはり聞こえる。確実に水の音である。
正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。
●プロの最新機材で録れなかった音が、
子供のラジカセで録音成功
住職によると、この不思議な音を録音しようと、
NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。
しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。
「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、
ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」
なんとも不思議な話である。
最新の録音機材では録音できないのに、
子どものラジカセでは録音できる。
まるで河童が、純真な心を持つ者だけに
水音を聴かせてくれるかのようだ。
試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。
すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。
後で家に帰って聞き返してみると、
確実にせせらぎの音が記録されている。
超うれしい!
これは一体どういう現象なのだろうか。
科学的に説明のつく現象なのか、
それとも本当に河童の仕業なのか。
真相は定かではないが、確実に言えるのは、
この壺から不思議な音が聞こえるというのは、
真実であるということだ。
●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告
住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。
豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、
壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、
洪水を予告してくれるのだそうだ。
「今でも川の音が聞こえるのですが、
河津川の水位が上がりそうな時など、
壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」
これは確かめようがなかったが、
もし本当だとすれば、
河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、
災害から人々を守り続けてくれているということになる。
●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー
ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。
「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。
ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、
と思いを巡らせることができます」
その上で住職は、禅宗の根本的な教えである
「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。
「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。
これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、
それに惑わされてしまうという教えです。
実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、
例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、
肌で感じたりすることで、
現実には目に見えないものに思いを馳せたり、
いろいろな想像・連想ができたりする。
そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」
なるほど、これは深い話である。
現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、
さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、
僕たちはそれらに振り回されがちだ。
しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。
むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、
真実が隠されているというのだ。
「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、
自分で感じなさいという教えです。
現代社会では、テレビやインターネットを通じて
文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、
皆さん惑わされますから。
こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と
想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、
という教えが、
この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」
●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心
住職はさらに続けた。
「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、
もともと仏の心を持っています。
ところが、現実の社会で生きるうちに、
心にたくさんの垢がこびりついてしまう。
真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」
これも禅宗の重要な教えの一つである。
すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。
しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、
先入観といった「垢」が心に付着してしまう。
その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。
河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。
現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、
僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。
「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、
実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。
昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。
ですから、そんな中で、こうした体験をすると、
より心に響くのかなと思います」
確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。
現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、
素朴で自然な美しさがそこにはある。
そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、
日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ
河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、
僕は深く心を動かされた。
これは単なる音響現象以上の何かがある。
人はみな心に仏性を持っており、
それによって、せせらぎの音を聴くことができる。
虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、
こてはとても大切な体験であるように思える。
SNSで飛び交う断片的な情報、
ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、
AI生成による真偽不明の映像や音声、
誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--
僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。
そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、
本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。
そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、
僕たちに大切なことを思い出させてくれる。
文字や人工的な情報で表現できない真実が、
この世界にはあるということ。
そして、その真実は五感を通じて、
心で感じ取るしかないということを。
●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心
この河童の壺の音について、
科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。
壺の形状による音響効果なのか、
それとも何らかの物理的現象なのか。
しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、
実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。
大切なのは理屈ではなく、
その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。
最新の科学技術よりも、
純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。
河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、
この音を聴く時、
僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。
河童が実在するのかどうかは問題ではない。
大切なのは、その存在を通じて、
自然との調和や他者への慈悲といった
大切な価値を思い出すことなのだ。
●あなたの心の中の河童に出会うために
700年という長い年月を経ても、
河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。
伊豆に来たら、河津に来たら、
ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。
ただし、河童の壺を体験したい場合は、
この壺が寺宝中の寺宝であるため、
必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。
そこで、あなたも河童の封じ込めた
せせらぎの音を聴いてみてほしい。
音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。
日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。
もし音が聞こえたなら、
それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。
そして、河童という架空の存在を通じて、
自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を
思い出すことができるだろう。
あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。
そして河童が、
人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。
文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、
河童の壺が奏でるせせらぎの音は、
きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。
(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺
今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある
「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を
訪ねることになった。
JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。
駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が
目の前に広がる。
あいにくの小雨模様だったが、
河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、
これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。
ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。
むしろこの雨模様のほうが、
なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、
まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。
●椅子まで河童という油断のならない境内
境内に入ってまず驚かされるのは、
とにかくあちこちが河童だらけということだ。
持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、
よく見ると河童の形をしていた。
思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。
寺院としては日本的な古さを感じさせる、
いかにも由緒正しそうなお寺だ。
と同時に、どこか懐かしい感じもする。
よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に
境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。
これは後で知ったことだが、
ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが
なせる業なのだ。
●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年
「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、
実に700年の歴史を持つ古刹である。
その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。
開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である
徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、
なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。
徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、
二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の
大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。
その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、
帰国後は各地の名刹を歴任した。
そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。
興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という
真言宗の寺があったということだ。
それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。
「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)
という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、
深い意味を込めた名前である。
●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割
現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。
「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、
河津桜で有名になる前--
昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」
今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、
桜まつりが始まったのは今から34年前の
1991年(平成3年)のこと。
桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える
大イベントに成長したが、
それ以前は河童が町の看板だったのである。
「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、
商工会に飾られていたりしたんです。
でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、
そういったものを寺で預かったんです」
なんとも皮肉な話である。
河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、
河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。
そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を
果たすことになったというわけである。
●「つくったが、作られていないように」のアート美学
現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。
「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」
ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。
人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、
まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、
「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、
心憎いばかりだ。
書家の師範のスタッフもいるということで、
寺院としての格式を保ちながらも、
現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。
●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー
以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、
町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、
昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、
一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。
「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、
住職は苦笑いを浮かべながら、
「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。
●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人
さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。
それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。
昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。
お寺の裏に位置するその場所は、
川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。
この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、
いろいろないたずらをして村人を困らせていた。
そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか
「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、
村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。
なんとも人間らしい話である。
最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。
●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童
そして運命の日がやってきた。
ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。
そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。
そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。
よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。
「河童だ、河童がいるぞ!」
誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。
河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、
裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。
ここでの河童の行動が実に人間臭い。
馬のしっぽにしがみつくという、
なんともマヌケな状況で発見され、
慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。
●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑
しかし村人たちは容赦しなかった。
井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。
河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、
井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。
村人たちは河童を取り囲み、
「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、
棒切れで叩き始めた。
ちょっとやりすぎな気もするが、
当時の人々にとって河童は子どもを攫う
恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。
●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命
ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。
村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、
河童が息も絶え絶えに倒れている。
それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。
和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。
「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。
寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」
さすがは禅僧である。
暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、
慈悲の心で河童を救おうとした。
村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、
和尚さんの言葉に従って河童を預けた。
●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し
和尚さんは村人たちがいなくなると、
「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」
と言って、河童を逃がしてやった。
この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。
その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で
目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。
すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。
●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺
河童は言った。
「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」
そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。
「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。
口に耳を当てると、水の流れる音がします。
水の音が聞こえたら、
わたしがどこかで生きていると思ってください。
和尚さまもどうぞお元気で」
そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。
●令和の今も、壺に耳を当てれば
和尚さんは夢心地で聞いていたが、
我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、
河童が本当に来たのだと確信した。
それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、
村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。
けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、
底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、
河童の無事を思った。
また、河津川に出水があった際、
このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、
人々が助かったこともあり、
それから寺の宝として大切に奉られてきたという。
今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、
河童が元気で生きていることを伺える。
そして人々は水の流れが心を洗うと言い、
ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~
さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、
実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。
果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが
聞こえるのだろうか。
後編では、この神秘的な河童の壺による
不思議体験をレポートする。
僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、
数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を
体験することになるのだが、
その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。
後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、
そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。
(後編に続く)

鉄道マン発 洗たく女 サイボーグ
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
無料キャンペーンは終了しました。
たくさんの方にご購入いただき、ありがとうございます。
気に入っていただけたら、紹介・購入サイトの下のほうに
「カスタマーレビュー」があるので、星をつけてもらったり、
レビューコメントを書いていただき、
他の読者におすすめいただければありがたいです。
(できれば高評価、でも厳しいご意見も歓迎です)
同書は引き続き、800円で販売しています。
また、おりべまことにご興味を持たれたら、
他にもいろいろ出していますので、ぜひ覗いてみてください。
格差社会ではたらく女の労働ファンタジー小説
洗たく女の空とぶサンダル ¥500
最新刊!AI・ロボットエッセイ集
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
¥500
脱サラ・起業・転職のリアル
今、60歳が人生の新たなスタート地点になった。
シニアも若者も必読!
生き方に悩む人のためのリアルな参考書がここにある。
鉄道マン発 映像調理師®
ー高塩博幸の人生甘辛レシピー
無料キャンペーン、いよいよ明日、
6月9日(月)15:59まで
すでに120部を突破。
脱サラ・起業・転職を考える人たちの間で大きな話題に。
無料で購入できる最後のチャンスです。
専用端末は不要。アプリを入れてスマホで読もう。
鉄道マン発映像調理師® 無料キャンペーン実施中
大好評!
鉄道マン発 映像調理師®
ー高塩博幸の人生甘辛レシピー」
6月9日(月)15:59まで
6日間無料キャンペーン開催中。
このチャンスをお見逃しなく!
今、60歳が人生の新たなスタート地点。
シニアも若者も必読。
生き方に悩む人のためのリアルな参考書。
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!
かつて新幹線を走らせた男が、今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。本書「鉄道マン発 映像調理師」は、シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追ったルポルタージュです。
高校生だった高塩少年は祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に国鉄に入社。その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。
しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?
映像クリエイターとしての第二の人生では、自らを「映像調理師®」と名乗り、終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。
「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。
運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、学ぶべきものがたくさんあります。
人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。
足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、
第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。
「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?
「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、
あなたも勇気をもらえるはずです。
本書は単なる成功物語ではありません。
昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、
失敗や挫折を乗り越え、常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。
起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、
そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。
人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵がここにあります!
ヘビとの遭遇

今年の干支は?
って聞かれて「えーと」なんてダジャレてる人、
けっこう多いのでは?
1年半分の6月ともなると、お正月の熱狂もどこへやら。
今年は何年だったか、みんな忘れてしまっている。
改めて、今年-2015年、令和7年はヘビ年。
そのせいか、この春からは初夏にかけて、
川沿いを散歩していると、やたらとヘビに出会う。
護岸の下のコンクリの岸の上に
何やら太いロープが落ちているなと思ったら、ヘビ。
散歩道の植え込みの中で何かにょーっと
動いているなと思ったら、ヘビ。
手すりに何か紐みたいなものが
ぶら下がってるなと思ったら、ヘビ。
そして昨日は、くねくねしながら悠々と川を泳いでいる
ヘビを目撃。
どれも長さ1メートルほどの青黒いアオダイショウだ。
周囲にはカルガモやコサギ、アオサギ、
カワウなどの水鳥が何羽もいるが、
さすがにこれらは体が大きいので襲ったりはしない。
うまいこと共存しているようだ。
そろそろカルガモの赤ちゃんが生まれる時期なのだが、
今からそれを狙っているのだろうか?
毎年1回か2回、
梅雨から梅雨明けの時期にお見掛けするヘビだが、
今年はすでに目撃4回。
ヘビ年大売り出しだ。
遭遇するとちょっとギョッとはするが、
ヘビに遭うとラッキーなのだそうな。
そういえば数年前だが、
住宅街の道路を白ヘビが
超高速で横切るのを見たことがある。
神の使いともいわれるヘビ。
今度会ったら手を合わせて願いを唱えよう。
人の気配が薄れる夜の時間は、
ネズミでも襲って腹を満たしているのだろうか。
杉並区も人間が知らないところで
ワイルドな世界が繰り広げられている。
岸辺露伴×水の都ヴェネチア
「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、
「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。
「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。
人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、
オールヴェネチアロケ。
映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。
テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、
ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。
主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、
そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。
それによって事件を解決していくストーリーだ。
原作のマンガも全く知らないが、
高橋一生は超ハマり役だと思った。
舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。
ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、
幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。
年中、観光客が押し寄せていると思うが、
いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、
人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、
歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。
僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、
ヴェネチアにも訪れたが、
見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。
それは当たり前で、
この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。
世界遺産になった宿命みたいなものである。
車はもちろん、自転車も街の中に入れない。
観光客がわんさか来るのだから、
スタバやマックなどの店もありそうだが、
少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。
そうした規制も多いはずだ。
オーバーツーリズムを避けるため、
街に入るための入場料徴収も検討されているという。
世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、
僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。
一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、
僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に
奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、
どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。
ヴェネチアはその最たる街だ。
さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような
スケールの都市ではなく、
せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。
そこに独自の文化が集約されている。
観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、
実際の観光収入はそんなにないのではないか。
ヴェネチアを舞台とした映画で、
ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)
という作品があった。
そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、
たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、
ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、
普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、
ゴンドラやボートに乗ったり、
写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。
僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、
多分そうしたのだと思う。
それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが
あるのだろうか?
観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、
この街の住人たちがどうやって暮らしているか、
庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、
ひどく気にかかる。
この岸辺露伴の映画も、
けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、
人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。
それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、
とても心に残った。
地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。
この風景はいったいいつまで見られるのだろう?
本日より無料キャンペーン「鉄道マン発映像調理師®」
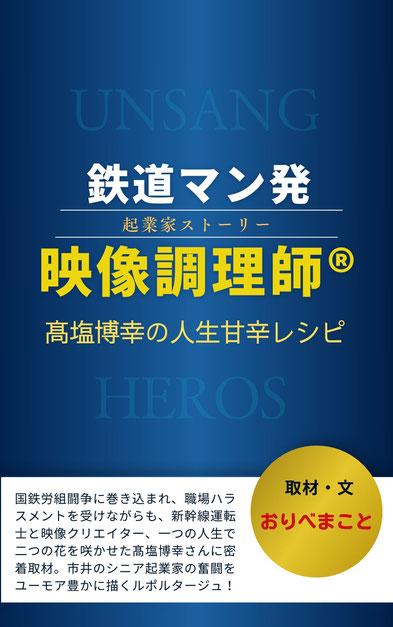
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
本日6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで
発売記念 6日間無料キャンペーン実施
このチャンスをお見逃しなく!
もくじ
第1章 高塩さんと映像の仕事
映像調理師®高塩博幸
エンディング産業展2022
倫理法人会での人脈から映像制作を受注
おいしい料理は“下ごしらえ”から
その人のストーリーを見つける作業
運転士の教官として培ったインタビュー術
AIなど最新ツールの駆使
ユニークなサービスメニュー
★ 自分史・遺言ムービー「nokosu」
★ nokosu 周年映像制作
★ 家系史継承箱《メモリアルボックス》
★ 死後の自分史
★ 子ども史・子育て自分史
●講座開設
★ 講座「スマホで自分史動画を作ろう!」
★ 講座「AIを使ってコマーシャル動画をつくる」
なぜ人は自分史を作ろうとするのか?
第2章 高塩さんの起業家スピリット
誰もがアーティストになれる
人生百年時代のチャレンジャー
ケンタッキーおじさんでもよかった
芸術と起業の街・足立区北千住からの再出発
映像調理師®誕生の舞台裏
映画より映写室が好きな子ども
きみは「ポピュラーチューズデイ」を聴いたか?
コンサートで音響アルバイトを経験
あんた、学校行ってどうするの?
高塩家のファミリーヒストリー
日本電子工学院と国鉄のW受験
第3章 高塩さんのJR東海道中膝栗毛
クリスマスエクスプレスに涙ぐむおじさん
花形鉄道マン
昭和の「青春18きっぷ」
国鉄百年の盛衰
組合闘争に巻き込まれて
「会社のイヌ」と呼ばれて
出世の秘密
JR東海出世街道
人生の憂鬱な昼下がり
鉄道マン最後の日
第4章 高塩さんと終活映像市場
高齢化社会における終活市場の拡大
映像が紡ぐ、新たな人生のしまい方
終活映像市場に輝く、ブルーオーシャンスターズの価値
映像調理師®の理念
欲しいけど欲しくない:終活映像営業の難しさ
終活映像市場に咲く、高塩博幸の営業哲学
新しいアプローチ
第5章 ブルーオーシャンスターズの未来
AIの進化を追いかけて
高塩式AIディレクター構想
10年後・20年後の世界を見据えて
「停止位置不良」の夢を見た人、来たれ!
鉄道マン発 映像調理師® 無料キャンペーン開催
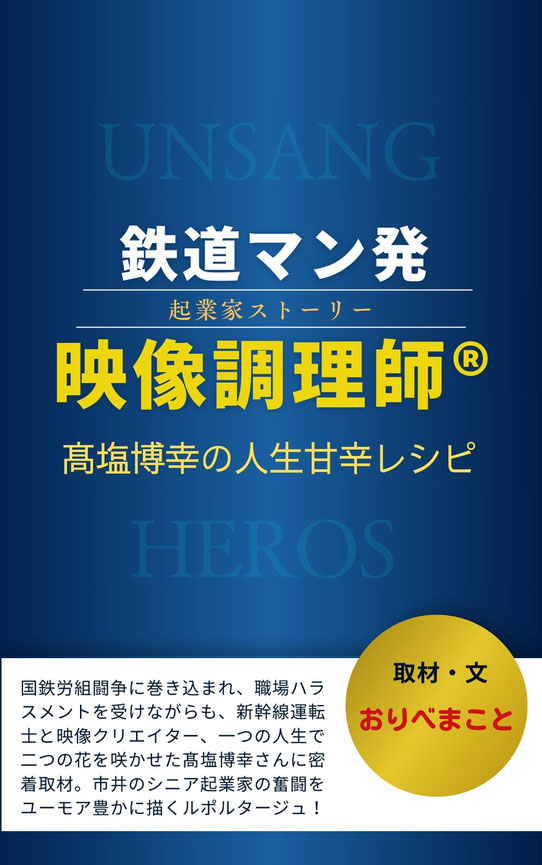
今、60歳が人生の新たなスタート地点
シニアも若者も必読!生き方に悩む人のためのリアルな参考書
鉄道マン発 映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで
発売記念 6日間無料キャンペーン実施
このチャンスをお見逃しなく!
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
おりべまこと電子書籍最新情報:AIエッセイ+起業家ストーリー
★本日6月2日(月)発売!
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである
https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S ¥500
スマホを握りしめ、メガネをかけ、工場製の服を着て生きている僕たち。実はもう「純粋な人間」なんてどこにもいません。世界的ロボット工学者が断言するように、現代人はすでに「動物と技術を合わせたもの」なのです。AIにパワハラプロンプトを仕掛け、アンドロイド観音に手を合わせ、エロコンテンツで技術革新を推し進める——抗えないテクノロジーの波に翻弄されながらも、どこか愛おしいAI・ロボットたちとの共存を模索する現代人の心境を、ユーモアと哲学的洞察で描いたエッセイ集です。
★6月4日(水)16:00~9日(月)15:59 無料キャンペーン!
ノンフィクション
鉄道マン発映像調理師®-高塩博幸の人生甘辛レシピー
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!
映画「エイリアン」とアンドロイドたち

ここのところ、急にまたSF映画が見たくなって、
ほとんど連日何かしら見ている。
今週はエイリアンシリーズを鑑賞。
シガニー・ウィーバーが主役のリプリー中尉を演じた1~4は、
SFホラーとして、単純に恐怖し、楽しめる部分と、
それだけで終わらない哲学的考察がミクスチャーされていて、
今、通して見ると当時とは違った印象・味わいがある。
●20世紀末20年の科学の進歩の集大成
この1~4は、1970年代の終わりから90年後半まで、
約20年の間に作られており、
この間の現実の人間社会の変化--
女性の権利の拡大と深化、ロボット・AI技術の発展、
クローン技術など、生命工学の進化などを積極的に取り入れ、
それらのエッセンスが絶妙な塩梅で織り込まれている。
また、初代監督リドリー・スコットの功績を引き継ぎ、
2でジェームズ・キャメロン、
3でデビッド・フィンチャー、
4でジャン・ポール・ジュネという
強烈な個性を持つ巨匠たちが、
それぞれ独自の美学と演出術を持って、
1本1本色合いの違う、独立した作品でありながら、
しっかりつながった物語を構成していることが、
このシリーズの成功要因になった。
●各物語のキーパーソンとなるアンドロイド
第1作における、ハンス・リューディ・ギーガーのデザインによる
最凶の宇宙生物エイリアンの登場は、
斬新でオリジナリティ豊か、
そして、怖さ・気持ち悪さの点で、衝撃度満点だった。
しかし、回数を重ね、見慣れてくると、
やはりその怖さ・気持ち悪さのインパクトは薄れてくる。
エイリアンシリーズの名作たる所以は、そこを補うために、
どんどんストーリーを拡大・深化させていったところにある。
そのキーとなるのが、ロボット(アンドロイド)の存在だ。
どの作品にも必ず人間そっくり(実際に俳優が演じている)の
アンドロイドが登場し、
その策略と行動が大きくドラマを動かしていく。
第1作のオリジナル脚本で、
どこまで設定が作られていたのか定かでないが、
宇宙開発事業を行う民間企業のシステムの一つとして、
彼らの頭脳(AI)は重要な役割を担い、
表向きの事業とは異なる、
隠された裏ミッションの担い手として暗躍するのである。
そして、これらのアンドロイドが、エイリアンに匹敵するほど、
怖くてグロテスクで気持ち悪い。
第1作の「アッシュ」も、第2・3作の「ビショップ」も
最後に人間やエイリアンに破壊されるのだが、
引き裂かれた体の内部は人間の内臓っぽかったり、
体液みたいなものが出てきたり、
半壊してボロボロの姿になっても機能できたりするシーンは、
なまじ人間そっくりなので、思わず目を背けたくなるぐらいだ。
第4作の「コール」は、
当時の人気若手女優ウィノナ・ライダー演じる女性型だったので、
さすがに他の二人みたいな凄惨な目に合わせるのは
スタッフも気がとがめたのか、
銃で撃たれるだけで済み、ラストまで原形をとどめて生き残る。
●仕事優先の機械人からヒューマンタッチな仲間への変遷
注目したいのは、シリーズにおける
これら「エイリアン・ロボット」の変遷だ。
第1作の「アッシュ」は宇宙船の科学担当者として、
割と単純に人間と敵対する(サンプル採取のため、
エイリアンの元を船内に招き入れる)、
割と単純な、お仕事最優先の機械的なロボットだ。
第2作の「ビショップ」はこれよりちょっと複雑化し、
最終的にリプリーたちをエイリアンから救う
「人間の味方」になる。
そして第3作では彼と同じ俳優が演じる、
「人間のビショップ」が、
企業のアンドロイド開発者=リプリーの敵対者として現れる。
同じ顔かたちでありながら、
ロボットよりも人間のほうが冷徹なのである。
第4作の「コール」は、前2体とは対照的に、
人間的な感情を持ち、
(エイリアンを宿した)リプリーを殺す使命を持って現れるが、
人間的な感情を持つ、いわゆる不良品のロボットで、
最後にリプリーと仲間になる。
日本では「アトム」や「エイトマン」のような
漫画で描かれたように、いくら強くて優秀でも、
自分が人間でないことに悩み苦しむロボット、
あるいは、「ドラえもん」のように、
もともと人間の仲間・友だちみたいなロボットが主流だが、
欧米では、70~90年代の20年あまりで
従来のロボット観がかなり変わってきたようである。
それは「ターミネーターシリーズ」や「ロボコップシリーズ」、
「ブレードランナー」「AI」など、
この頃、立て続けに作られた、
他のロボット映画の影響も大きいだろう。
●人間観・ジェンダー観の変化がロボットを魅力的にした
しかし、それよりも大きいのは人間観の変化、
特にジェンダー観の変化かもしれない。
昔、何かの本で「男がロボット好きなのは、
子供を産まない(産めない)からだ」
というフレーズを目にしたことがある。
つまり、子供を産める女性に対抗して、
命の創造に関わりたいという潜在的欲求が男の中にあり、
ロボットへの興味・研究に向かわせる、というのだ。
こうした出産機能を基点に考えるジェンダー観は面白い。
ハリウッド映画には、おそらく1970年代初め頃まで、
「女・子供を映画のなかで殺さない」という不文律があった。
アメリカ社会(及び、日本も含む、西洋型社会全般)には
女性や子供は「善なるもの」「聖なるもの」の象徴であり、
侵してはならないもの、男が命を賭けて守るべきもの
と考えられていたのだ。
もちろん、病気や事故、あるいは戦争に巻き込まれて
恋人や家族が死ぬなどのエピソードはあるが、
それらは情報として処理されるか、あくまで美しく描かれ、
けっして血まみれになるようなシーンはなかった。
そして女性や子供の死は、
男が奮い立って行動するためのモチベーションになっていた。
それらは言い換えれば、女性や子供を弱き者、
男の支配下に置かれる者、でなければ、
女神や女王のように崇め奉る者といった意味があった。
それが60年代の変革を経て、劇的に価値観が変わり、
女性も男性と対等の自立した人間として
描かれるようになっていく。
1979年に初登場した、シガニー・ウィーバー演じるリプリーは、
女神でも聖女でもなく、リアルな自立した人間として活躍する、
新しいタイプの女性ヒーローだったと思う。
彼女は自分のゆるぎない価値観と使命を持ち、
エイリアンと闘うヒーローとして描かれるが、
それゆえ、かつての映画の女性像からは想像もつかない、
相当ひどい目に遭わされる。
死んで生き返り、エイリアンとの「あいのこ」になり、
おぞましい姿をさらすことにもなる。
そうした惨劇のなかから
女性主人公ならではのテーマ「命の創造」をビビッドに提示する。
さすがにウィーバーの出演は4で終わるが、
最後の作品では、フランス人監督ジャン・ポール・ジュネが
グロテスク極まりない、リプリー最後の戦いを描きつつ、
「アメリ」「ロストチルドレン」のような寓話的な余韻を残し、
いったん、エイリアンシリーズの幕を下ろす。
そして、ジュネの残した余韻を受けて、
初代監督リドリー・スコットが再登板し、
「プロメテウス」「エイリアン・コヴェナント」
といった前日譚--21世紀の「エイリアン」を製作する。
エイリアンとジェンダー観の変化については、
また別の機会に詳しく書いてみたい。
●未来の記憶から生まれるコンテンツ
現実の科学技術の進歩を踏まえて作られた
20世紀末のSF映画だが、
昨今の技術の進捗状況は、これらエイリアン映画などの世界を、
そう遠くない未来に実現させてしまいそうな勢いがある。
もしかすると人類は未来の記憶を持っていて、
そのヴィジョンに向かって突き進んでいるのかもしれない。
SF映画はそれらの記憶を表現するコンテンツの一つなのだ。

おりべまこと電子書籍最新刊
エッセイ集:AI・ロボット2
僕たちはすでに
センチメンタルな
サイボーグである
近日発売!
AmazonKindleにて
世界のエンディングの潮流は、エコ葬と安楽死

最近、墓じまいや相続問題など、
日本でも終活の話題が増えているが、
海外に目を向けると、世界の葬儀・終活の焦点は、
安楽死とエコ葬に傾いているようだ。
●英国で安楽死法案が成立目前
いま、英国では安楽死法案が下院での審議を通り、
6月には上院での審議に移るが、
この法案が成立するのは、ほぼ確実と言われている。
すでにスターマー首相も支持を表明しており、
BBCニュースなどで昨年末から
頻繁に審議の様子が報道されている。
日本では超高齢化社会・多死社会が
進展しているのにも関わらず、
長らく安楽死・尊厳死・自殺ほう助といった課題は、
ほとんど、まともに議論されてこなかった。
しかし、この英国の法案が成立したら、
何か大きな影響がおよぶかもしれない。
●この10年で安楽死が認められた国が・・・
少し前まで安楽死と言えば、
オランダとスイスしか思い浮かばなかったが、
現在はどうなのだろうと調べてみた。
2025年1月末時点でのデータだ。
・完全に合法化されている国・地域:
オランダ(2002年)
ベルギー(2002年)
ルクセンブルク(2009年)
カナダ(2016年)
コロンビア(2015年)
スペイン(2021年)
ポルトガル(2023年)
・部分的に合法化:
スイス(1942年から自殺幇助のみ合法)
ドイツ(2020年に憲法裁判所が自殺の権利を認定)
アメリカ(オレゴン州、ワシントン州など複数州で
医師幇助自殺が合法)
オーストラリア(複数州で合法化、
2019年ビクトリア州から開始)
・2023年(コロナ明け)以降の動き:
ポルトガルが2023年に完全施行。
英国は現在審議中(下院可決済み)
他に現在審議中・検討中の国を挙げると、
フランス(マクロン大統領が法案検討を表明)
イタリア(国民投票の動きあり)
アイルランド(市民議会で議論)
かなり衝撃的だった。
あくまで欧米に限っての話だが、
安楽死・尊厳死・自殺ほう助を認めた国は
この10年ほどで激増している。
●エコ葬も激増
一方、エコ葬も増加しているようで、
今世紀に入ってから、遺体をフリーズドライにしたり、
アルカリ溶液に浸して分解する水火葬、
土中の微生物を使って堆肥にする有機還元葬など、
さまざまな環境負荷の少ない葬法が考案されてきた。
どれも当初はキワモノ扱いだったが、
アメリカではすでに12州で有機還元葬も認められ、
水火葬も広がっている。
特にコロナ禍以降、この2,3年の変化は大きい。
安楽死とエコ葬は、まさに現代の葬儀・終活業界の
大きな潮流になっているのだ。
●何が人の心を、社会の常識を変えたのか
安楽死については、人権問題と深くかかわっているようだ。
「どう死ぬか」という個人の選択権の拡大、
医療技術の進歩で延命が可能になった一方での
「死の質」への関心、
超高齢化社会での終末期医療費の問題、
家族への負担軽減
といった視点が増加の要因になっていると思われる。
また、エコ葬については、
環境意識の高まりと持続可能性への関心
土地不足問題(特に都市部)
従来の墓地・埋葬への価値観の変化
樹木葬、海洋散骨、自然葬などの多様化
といった精神・ライフスタイルの変化が大きい。
両方とも、従来の「伝統的な死生観」から
「個人の価値観を重視する死生観」への転換を表している。
特にコロナ禍を経て、人々の死に対する考え方が
より現実的で個人的なものになったという面もあるだろう。
葬儀・終活業界としては、
これらの多様化するニーズにどう対応していくか、
また法制度の変化にどう準備するかが重要な課題になってくる。
あまり考えたくないという人が多いと思うが、
そう遠くない未来、日本でも今後、嫌でも
これらの議論をしなくてはならない時が来そうだ。
時空を超えた家康AI 好みの女性は天海祐希と石田ゆり子

「千住宿」は日光街道の最初の宿場町。
現在の北千住界隈がそうだ。
宿場が開かれたのは3代将軍・家光の時代、
1625年だから、今年でちょうど400年。
それでお祭りをやっているというので、
18日の日曜日、北千住まで行ってきた。
北千住は、拙著「鉄道マン発 映像調理師®」で
取材させていただいた髙塩博幸さんの
「ブルーオーシャンスターズ」が会社を構える街。
生まれも育ちも起業も足立区の髙塩さんは、
ビジネスとともに地域貢献にも熱心で、
今回は、この千住宿400年に際して、
オリジナルソングとビジュアル(プロモV)を提供。
さらにこの日は、AI企業研修を行う会社
「TSUYOMIHO」の宮田剛志さんとタッグを組んで
街頭に「家康AI」のブースを出店した。
「家康AI」は、家康に向かって質問すると、
「拙者が家康じゃ」などと徳川家康が
ユーモラスに答えてくれる体験。
歴史を「教わる」のではなく「対話する」スタイルで、
子どもから大人まで楽しめるのがウリだ。
テレビ局の取材も来ていて、
面白がって問いかける子供たちにインタビューをしていた。
僕もあれこれ質問してみたが、
没後409年を経て、AIの力で現代によみがえったこの家康、時々、「拙者がこの千住宿を開いた」なんて
トンチンカンなことを言う。
いやいや、五街道を整備しようと努めたのはあなただけど、
宿を開いたのは孫の家光でしょ。
そもそも400年前の1625年って、あなた、もう死んでるし。
それで「あなたの後の14人の徳川将軍のうち、
最も評価できるのは誰ですか?」
と聞くと家光の名を挙げたりする。ほうほう。
トンチンカンな部分は差し引いて、答がいかにもAI的な、
優等生の模範解答みたいなのが気に入らない。
それでいろいろ変化球を投げてみる。
「来年の大河は『豊臣兄弟』なので、今度はあんた悪役だね?
誰にやってほしい?」とか、
「『どうする家康』では、あんた、北川景子の
お市に惚れてたみたいだけど、ホントに好きだったの?」とか。
このへんの質問はうまくかわされたけど、
「好みの女性のタイプは?」と聴くと、
「しっかりしてて優しい人」なんて、まともに答えてきた。
「じゃあ、たとえば現代の女優さんだったら誰?」
と聴いてみたら、「天海祐希と石田ゆり子」と、
照れもせずにペロッという。
どういうラーニングをしたのか、
髙塩さんと宮田さんに突っ込もうと思ったが、
ま、お祭りだし、やめておいた。
てなわけで、今年は北千住で
随時、400年のお祭りをやっているので、
機会があれば遊びに行ってみてください。
髙塩さんと僕の本もよろしくね。
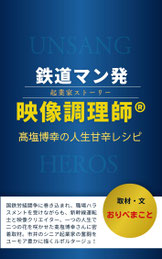
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
Amazon Kindleより好評発売中。¥800
国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!
世界の果ての海風さやか 吉祥寺で地中海料理

週末、息子の誕生日だったので、お祝いで
吉祥寺にある地中海料理の店「The MED」に行く。
店名は英語の「Mediterranean」の
頭の文字から取っているらしい。
これは「大地の真ん中」を意味する
ラテン語の「mediterraneus メディテッラーネウス」
medius 「真ん中」 + terra 「土、大地」に由来する語だ。
何だかカッコいい。
日本語の「地中海」もエキゾチズムの香りがする、
イメージ豊かな言葉。
明治時代に作られた可能性が強いが、当時の翻訳者は、
遠いヨーロッパのさらにそのまた向こう、
まるで世界の果てに広がる
天国のような優しい海を想像したのではないか。
さて、The MED。
外見はおしゃれだが、中は小さな居酒屋のような、
気さくな店で、キャパはせいぜい15人程度というところか。
店主らしき、料理を作るおっさんと、
注文をきく店員の若い女性でやっている。
(店員は日替わりかもしれない)
仕込む材料によって日替わりになるのか、
はたまた店主が毎日同じ料理ををつくると飽きちゃうからか、
決まったメニューブックがなく、
キッチンの前にその日出せる料理を紙に書いて貼りだしている。
さらにそれぞれの料理名の紙は
小さな国旗のマグネットで留められており、
どこの国の料理か、わかる仕組みになっている。
なにせ地中海はヨーロッパの南部、アジアの西部、
そしてアフリカの北部に囲まれた海で、
「地中海地域」に属する国は20以上もある。
よく知られているのは、ギリシャ、イタリア、スペインだが、
ヨーロッパではクロアチアやスロベニア、フランスも入る。
アジア~中近東方面は、
トルコ、レバノン、シリア、イスラエルなど。
アフリカだとエジプト、リビア、チュニジア、モロッコなど。
イタリア料理店やスペイン料理店は、
日本でもそれぞれ単独でたくさんできたので、
一般的にはギリシャ料理を中心に語られることが多く、
この日もムサカやグリークサラダを食べたが、
はじめて食べたモロッコの
「羊肉とプルーンの煮込み」がめちゃウメェ~。
甘いプルーンソースでトロトロに煮込まれた羊肉は、
まるで豚の角煮のごとしで、
これまで食べた羊料理の中でいちばん美味だった。
地中海料理は、健康長寿の食事法として、
日本でもよく知られるようになり、
「地中海ダイエット」なる言葉も生みだした。
その特徴は、野菜や果物、豆、ナッツ類、オリーブオイル、
全粒穀物、魚介類、乳製品がふんだんに使われていること。
さらにそれらを調理する際に使うスパイスの豊富さ。
スパイスと言っても、アジアンと違って、
辛い料理がほとんどないことも特徴かもしれない。
もう40年近く前だが、
当時のユーゴスラビアの首都ベオグラードから
殺人的な18時間すし詰め夜行列車に乗って、
ギリシャまで旅行したことがある。
おもにアテネとエーゲ海のロドス島を回ったが、
島で泊まった民宿の夫婦は、
なぜか「ギリシャのめしはうまくないだろ」と
僕に言ってた。
ギリシャ人は何でもかんでもオリーブオイルをかけるから
みんなオリーブ臭くなっちゃんだよ。
チーズだってヤギのミルクからつくるからおいしくないし、
パンもぱさぱさしているし。
と、妙に自虐的だったのを覚えている。
僕が日本人(当時は世界に冠たる経済大国)で、
イギリス(当時、ロンドンに住んでいた)から来たと
言ったので、そんな態度になったのだろうか。
今につながる西洋文明発祥の国の末裔なんだから、
もっと胸を張ってほしいなぁと内心思ったが。
しかし、彼らが「うまくない」と思っていた
オリーブ、ヤギのチーズ、全粒粉のパンなどが、
今や健康長寿食として重宝され、
ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。
「The MED」ではギリシャワインも飲んだが、
それより感動的だったのは「地中海ビール」である。
普段、ワイン党でビールなどあまり飲まないのだが、
このビールは違っていた、
日本のキレ、ニガ一辺倒のビールとはまったく別物で、
ほのかにフルーティーで、まろやかな感じ。
それでいながら甘く、べったりした感じはない。
長く記憶に残る香りと風味がある。
これを少ししょっぱい「おつまみオリーブ」と
いっしょに味わうと、
世界の果てから海風がさやかに吹いてくるようで、
体は吉祥寺のまま、気分はもう地中海。
ちょっとクセになるかもしれない地中海料理。
各国の多国籍な料理を試したければ、
「The MED」は超おススメ。
ほかに麻布十番と新宿歌舞伎町には
ギリシャ料理専門の店があるので、
機会をつくって行ってみたい。

生き方に悩む人のためのリアルな参考書 「鉄道マン発 映像調理師®」
鉄道マン発映像調理師®
高塩博幸の人生甘辛レシピ
https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX
AmazonKindleより好評発売中 ¥800
国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!
(あとがきより)
彼の祖父の時代は、日本を欧米諸国に負けない、
近代的な文化国家にすることが、国民共通の目標でした。
また、父の時代は、敗戦によって物も心も貧しくなってしまった
日本を復興させ、豊かな社会を築くことが共通目標となりました。
しかし、高塩さんや僕の世代になると、
祖父や父の世代のような、誰もが共有できる目標は、
もはやありません。
それに代わって、僕たちひとりひとりが、
生きる目標や生きがいを設定しなければならない
状況が訪れているのです。
これは日本のみならず、経済的な成功を成し得た、
世界の先進国すべてに共通する課題でしょう。
「人生百年」と謳われる未知の世界は、
豊かでありながらも、未来に希望を見出しにくく、
不安があふれる世界です。
ここでは、60歳の還暦は、
かつてのように人生の終わりを意識し始めるのではなく、
新しく生き始める年代といえるかもしれません。
インターネットの普及、AIの進化によって、
僕たちの子供世代、孫世代も平等に知識や情報を共有しています。
子供や孫たちと、さらにそこに加わるであろう
AIやロボットたちと、
どんな人生を送り、どんな社会を築き、
どんな未来をめざせばいいのでしょうか。
そのために、あなたの生きた証、活動の足跡は、どう生かされ、
のちの時代にどんな響きを残すのでしょうか。
もし、あなたが、高塩さんに終活映像や人生ストーリーの
制作を依頼する機会があれば、
ぜひ、過去の記憶とともに未来へ向けても想像力を広げて、
想いを盛り込んでください。
Deathフェスと有機還元葬のnanowaプロジェクト
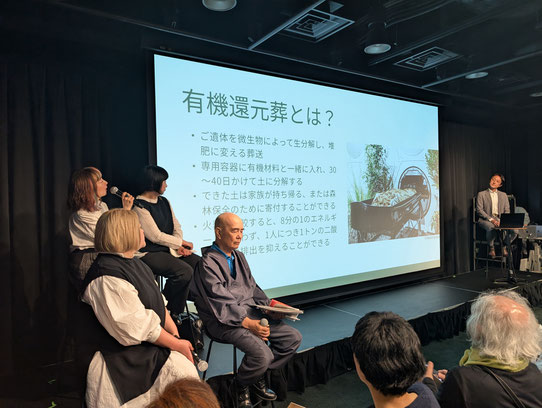
●私が死んだら、お花たちよ
そのむかし、1970年代のこと。
イルカが「いつか冷たい雨が」という歌を歌っていた。
イルカとは「なごり雪」を歌う、
あのフォーク歌手のイルカのことだ。
「いつか冷たい雨が」の歌詞のなかには
「いつか私が死んだら、お花たちよ、そこから咲いてください」
といった一節があったことを覚えている。
自分が死んだら花になる・木になるという
夢想を抱く人は少なくない。
最近の樹木葬の流行は、そんな人々の願いを反映したものだろう。
この樹木葬、見た目は確かに美しく、
「自然に還った」感があるが、
粉砕した遺骨を樹木のあるエリアに撒く・埋めるだけなので、
実際に亡くなった人の遺体を栄養分にして
植物が育つわけではない。
ところが、これを実践する葬法が欧米で普及し始めている。
それが「有機還元葬」、別名「堆肥葬」である。
遺体を土の中に埋め、微生物を使って分解し堆肥に変える。
イルカの歌のとおり、あなたが死んだら、栄養のある土になり、
そこから花が咲き、木が育ち、森にもなりますよ、というわけだ。
●神仏の道理に悖る新葬法の開発者たち
環境問題の影響から、欧米では2000年代頃から
地球環境に負荷をかけない葬法=遺体の処理方法、
つまり従来の土葬や火葬以外の方法が
いろいろ考えられてきた。
考える人たちは真剣だが、
それを伝えるメディアの報道の多くはキワモノ扱いで、
「ほら、こんな面白い、でもちょっと怖い人や会社がありますよ」
といったニュアンスが強かったように思う。
はっきりと決めつけるわけではないが、
当時、葬儀に関してはまだ伝統的な宗教を尊ぶ傾向が強く、
新しい葬法の開発者たちは、神仏の道理に悖る者ども、
人間の尊厳をないがしろにする罰当たりな輩と見られていたのだ。
それがこの数年、潮流が変わってきた。
インターネットが浸透し、AIが広まり、
時代が変わり、世代も変わり、
「土に還る」「地球に還る」という思いを、
たんなる夢物語でなく、リアルなものとして、
肯定的に捉える人が世界各地で、
特に若い世代の間で増えているのではないかと思う。
●世界で普及の兆しを見せる有機還元葬
「有機還元葬」はそうした新葬法の代表格で、
呼び方や細かいシステムは違えど、
アメリカとドイツで幾つものスタートアップ企業が、
すでにビジネスとして営業を始めている。
営業しているということは、イコール、
法的に認められているということ。
実際、この先駆者たちは自治体に対して、
何度も粘り強くプレゼンを続け、ついに認可を勝ち取った。
ワシントンで、ニューヨークで、カリフォルニアで、
アメリカに限って言えば、2025年4月時点で
およそ4分の1の州、計12州で合法化されている。
メディアも、もはやキワモノ扱いできない状況だ。
ワシントン州 (2019年)
コロラド州 (2021年)
オレゴン州 (2021年)
バーモント州 (2022年)
カリフォルニア州 (2022年、施行は2027年)
ニューヨーク州 (2022年、施行は2024年8月7日)
ネバダ州 (2023年)
アリゾナ州 (2024年)
メリーランド州 (2024年10月1日施行)
デラウェア州 (2024年)
ミネソタ州 (2025年7月1日施行予定)
メイン州 (2024年)
僕はコロナ前から仕事で新葬法に関する記事を書いており、
冒頭のイルカの歌を思い出し、
有機還元葬はなかなかいいんでねーの、
土より生まれて土に還る。
僕も終わりが来たら、地球の一部になりたいと思っていた。
しかし同時に、これらは海の向こうの話で、
日本では到底無理だろうとも考えていた。
自分や家族をまんま土に埋めて、微生物に食わせるなんて、
考えただけでおぞましく、ほとんどの日本人は
拒否反応を示すに違いないと思いこんでいたのだ。
ところが、この有機還元葬を実現しようと
動いている人たちがいるのを知って仰天した。
それも「できればいいね」といったレベルでなく、
本気中の本気なのだ。
●nanowaプロジェクトの活動
このプロジェクト「nanowaプロジェクト」は、
年内にまず動物で、実際に国内で有機還元葬を行う予定で、
学者・研究者や、ある有名企業も支援に動いているという。
ちょうど1か月前、「4月14日は“よい死の日”」と謳って、
渋谷ヒカリエで6日間、Deathフェスという、
死をポジティブに考えようというイベントが開かれたが、
そこでもトークセッションの一つとして、
「有機還元葬」のコンセプト、
そして実現に向けた活動について語られた。
反響は大きく、
日本でも有機還元葬(堆肥葬)への潜在的なニーズは
決して低くないようだ。
実現にはもちろん法整備が必要で、
かなり厳しいのではないと推測するが、
この国は前例さえあれば、特にそれが欧米のものなら、
意外とあっさりクリアできてしまう可能性もある。
少なくとも安楽死・尊厳死よりもハードルは低そうだ。
まさか、自分が生きている間に、
この葬法がこの国で実現するとは(まだしてないが)
思いもしなかった。
「nanowaプロジェクト」のスリリングな展開は、
これから注目に値する。
認知症になると、それまでの愛はどこへ行くのか?
母の日。
スーパーマーケットがいつも売っているデザートに
ポチっと赤いシールを貼り付けて、
「花より団子」の「母の日スペシャル」を
用意していたので、買ってきた。
「2個入りだけど、母の日だから、おかあさんは1個。
僕らは子供だから半分ずつね」と言っても、
何のことやらさっぱり認知しない様子。
だが、何か、普段あまりお目にかからないものが出てきた、
しかも自分の好物のカテゴリーに入るものだ、
ということは何となくわかるらしい。
けれどもやっぱり1個まるまる食べてしまっては悪いと思うのか、
半分残したので、僕とカミさんで半分ずつ食べる。
これは母の愛なのか?
そう言うと、カミさんは、
「わたしたちに恩を売っておいたほうが、
後から何かと有利だと算段しているんでしょ」
と、クールな分析をする。
親子ではあるが、この二人の相性はイマイチなようだ。
義母は時々、僕に対して「だーい好き!」と言って、
ベタベタ抱きついてくる。
たぶん、毎日、お菓子をあげて面倒を見るので
そうなるのかと思うが、相性はいいのかもしれない。
好きでいてもらったほうが、
ある程度、言うことを聞いてくれるので、
こっちとしては助かる。
デイサービスのスタッフに対しても、相性のいい・悪いはある。
以前、毎週土曜日の送迎に来ていた
Sさんという30前後の若い男性が、大のお気に入りだった。
その人はもう2年以上前に辞めてしまったのだが、
いまだにその記憶が残存しているのか、
土曜日の朝は概してご機嫌が良く、
なんとなくウキウキ感があるようだ。
待てど暮らせど、もうその人は来ないのだが・・・。
相性のいい人(波長が合う人)とは居心地の良さを感じる――
これも一種の愛情・愛着と呼べるものだろう。
時々、認知症になると人間が生きてきた中で
培った愛情なるものはどこへ行くのか?と考える。
親でも夫でも子供でも、
若い頃の恋愛の相手や友だちでもいいが、
人間、成長過程で誰かを愛し、愛されることで、
あるいは仕事や趣味などに愛を注ぐことで、
いろいろな関係を紡ぎ、人生を築いていく。
認知症になると、そうした愛の記憶は、ほぼすべて初期化され、
食欲などの本能的な部分と、
自分が安全に、有利に生活できるための打算が、
非言語されて内側に残る。
打算というと印象が悪いが、
これもまた生きていくための本能の一つなのだろう。
その一方で、幼い子供や動物を見て「かわいい」と感じたり、
花をきれいと感じたりする原始的な愛情は
ずっと消えるに持ち続けるようだ。
豊かな時代に生まれ育った僕たちは、
周囲にあふれかえる「愛」という言葉に洗脳され、
この得体のしれない概念に、過剰に期待する傾向がある。
人間には愛があって然るべき、
愛がなければだめ、人を愛せ、みたいな。
女と男の愛、家族の愛、至上の愛。
時はあまりにも早く過ぎ、喜びも悲しみもつかの間だが、
ただ一つ、愛の世界だけは変わらない――
昭和歌謡にそんな歌詞の歌があった。
でも、そんなことはないのだ。諸行無常だ。
愛の世界も変わっていくし、失われていく。
だがしかし、それはそう悪いことでも、
悲しいことでもないのかもしれない。
純粋でありながら、どこか邪で、ご都合主義的。
義母からは、人間のニュートラルな状態とは
「こんなもんよ」と教えてもらっているような気持ちになる。
ありがとう、おかあさん。
新刊「鉄道マン発 映像調理師® 高塩博幸の人生甘辛レシピ」
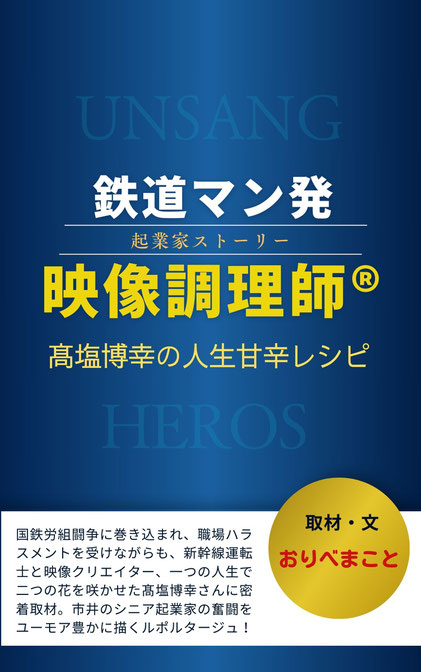
国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、
そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。
一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。
「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、
還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、
彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。
人生の味わい深いエピソードを素材に、
心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、
笑いあり涙ありの起業ストーリー!
かつて新幹線を走らせた男が、
今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。
本書「鉄道マン発 映像調理師」は、
シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追った
ルポルタージュです。
高校生だった高塩少年は
祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に
国鉄に入社。
その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、
JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。
しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。
それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、
還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?
映像クリエイターとしての第二の人生では、
自らを「映像調理師®」と名乗り、
終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。
「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。
運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、
クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、
学ぶべきものがたくさんあります。
人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。
足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、
第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。
「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?
「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、あなたも勇気をもらえるはずです。
本書は単なる成功物語ではありません。
昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、
失敗や挫折を乗り越え、
常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、
そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。
人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵が
ここにあります!
スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」
一昨年、としまえんの跡地にオープンした
「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。
正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京
‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。
約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る
ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。
●見どころ満載6時間ツアー
映画ハリー・ポッターシリーズや、
ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の
舞台裏を体験できる。
映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、
実際に撮影で使われた小道具などが展示され、
視覚効果を使った体験型展示もある。
初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、
音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。
かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも
満足のいくツアー。
6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。
施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。
映画ハリー・ポッターシリーズは、
ほぼ2000年代に制作されており、
CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。
その分、アナログ的というか、
昔ながらの手作りの部分も残っていて、
セットや小道具などの作りこみがすごい。
魔法学校の教科書など、映らないページまで
しっかり書き込まれており、
映画スタッフの間で受け継がれてきた
「魂は細部に宿る」の精神が生きており、
職人的な意気込みが伝わってくる。
でも、こういう部分は果たして、
今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?
コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?
「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。
映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。
そんな言い方もできるのかもしれない。
●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも
というわけで、このツアー後、
アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで
全8作を一気見した。
(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)
主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、
映画各話のトーンが変わっていく。
第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、
ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる
中盤から後半にかけて、
ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。
そして、やっぱり最終作における謎解き――
ハリーの運命をめぐる、
ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。
何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、
演者の子供たちが青年に成長していく過程は、
さすがに機械では実現できない。
それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、
やはり空前絶後の作品だろう。
こんな作品は二度と作れない――
と思っていたら、
何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。
キャストはもちろん全とっかえ。
(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)
映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、
出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。
製作はすでにけっこう進行していて、
今年の夏には撮影開始予定とのこと。
製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。
1作につき1シーズンで、最低7シーズン。
後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。
いずれにしても10年スパンで、
映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。
この時代にすごい構想だ。
「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。
このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。
どうしても映画版と比較してしまうだろうが、
かなり楽しみにしている。
小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。
ジャイアント太鼓in府中
昨日、府中駅から東京競馬場に向かう途中、
出くわした、直径2メートルはあろうかという大太鼓。
バットみたいなバチで打つと、
すごい音が街中に響きわたる。
毎年4月30日〜5月6日の1週間、
大國魂神社を中心に府中市内で開催される
「くらやみ祭り」の一つ、「大太鼓送り込み」だ。
東京都の無形民俗文化財に指定しているらしい。
初めて見たが、間近で見るとすごい迫力。
偶然出会えてラッキーだ。
それにしても、この太鼓の皮は何だろう?
大きさからして牛以外に考えられないが、
どうやって作っているのか気になった。
ぜひ職人さんの仕事を取材してみたい。

おりべまこと電子書籍
認知症の
おかあさんといっしょ2(に)
https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99
無料キャンペーン終了しました。
ご購入いただいた方、ありがとうございました。
よろしければ、レビューをお寄せください。
引き続き、AmazonKindleにおいて、
¥500で販売中です。
東京競馬場ローズガーデンで漫遊
どこに行っても混雑しているゴールデンウイーク。
穴場はないかと、大穴狙って府中にある東京競馬場へ行く。
大あたり!ガラガラだ。
土日は競馬はやっていない。
お目当てはバラである。
東京競馬場にはバラ園――ローズガーデンがあって、
無料開放しているのだ。
6月1日の日本ダービーに合わせて調整しているので、
見頃としてはまだ少し早いが、十分に美しく、見ごたえがある。
全体が7つのエリアで構成されており、
300品種を超えるバラと脇役の小さな花・葉・草も充実している。
歩いているとロンドンの公園にいるようだ。
歴代のダービー馬の記念碑と、騎手の人形がかわいい
ダービーホースアベニューもいい感じだ。
そして何より有名な庭園と違って、
あまり知られていないので来園者が少なく、すいていて、
ストレスフリー。ついでに入園料もフリー。
人の映り込みなども気にせず、写真も好きなだけとれる。
テーブルやベンチもたくさんあるので飲食も自由だ。
だだし、自販機も含めて飲食関係の販売施設はないので、
府中駅周辺でドリンクとかサンドイッチとか
お弁当とか持っていくといい。
連休はもう終わりだが、5月・6月の平日はおすすめ。
正門前に電車の駅があるが、
競馬が開催される土日しか運行していないので、
アクセスは府中駅から。ぷらぷら歩いても15分程度です。

おりべまこと電子書籍
認知症の
おかあさんといっしょ2(に)
https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99
5月6日(火)15:59まで無料キャンペーン開催中。
「認知症のおかあさんといっしょ2(に)無料キャンペーン開催中」

「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。
「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。
幻の家族と会話する義母。
笑いあり、涙あり、驚きありの認知症介護エッセイ。
認知症になっても人生は続く。
むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。
この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、
ユーモアとリアリティで描き出しています。
忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。
もくじ
- 幸せの歌と認知症の女
- 春だけど自分にいいこと何かやってる?
- サスペンスフルな認知症映画「ファーザー」
- 蛭子能収さんと「with弱者」の社会の実現について
- 認知症 花のアートワーク
- 二度と洋食屋には連れていくべからず
- 認知症患者に安心とハピネスを
- 食卓のマナーと認知症
- また今日もざしきわらしがやってきた
- 赤ちゃんはおとなになって働いています
- 要介護認定更新の日
- 認知症と回想療法士
- リス系認知症患者の冬じたく
- 京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族
- 認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉
- 認知症患者のごあいさつを受け止められますか?
- みかんせんべいに秘められた物語
- 魔女っ子カーチャン
- 親の介護は5年で卒業(というマイルール)
- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる
- 認知症患者の純粋な「かわいい」の価値
- 鏡の国のお義母さん
- 「痴呆症」は老害ワード?
- 義母の入院
- 食べ物の恨みは死ぬまで残る
- 入院していたことなんて記憶にありません
- お母さんといっしょの夏休み
- 義母の回復と阿佐ヶ谷の七夕まつり
- 笑える遺影
- 秋の最後の日の散歩
- 年末の認知症ミステリー
- 義母のお正月スペシャル
- 90歳は人生卒業の齢?
- 生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること
- 認知症になっても人生は続くか?
- AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する
(全36編採録)

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。
お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。