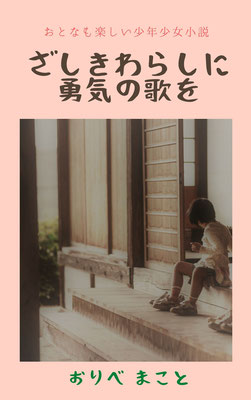- ホーム
- 電子書籍:おりべまこと劇場
- NEWS
- わたしの「わたしストーリー」
- 台本ライターとは?
- 実績:わたしの「しごとストーリー」
- サービスメニュー・料金プラン
- ブログ「台本屋のネタ帳」
- 仕事
- 生きる
- 食べる
- ロボット・AI
- 物語
- 歴史
- 世界
- 動物
- 音楽
- ビートルズ
- ドラマ・映画・演劇
- インターネット
- 本
- 台本
- エッセイ
- 子ども
- 2011年5月
- 家族
- エンディング
- 農業
- 旅
- 社会問題
- 昭和
- 認知症介護
- 広告
- 電子書籍
- 週末の懐メロ
- 2011年6月
- 2011年7月
- 2011年8月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年10月
- 2011年12月
- 2012年1月
- 2012年2月
- 2012年3月
- 2016年5月
- 2016年6月
- 2016年7月
- 2016年8月
- 2016年9月
- 2016年10月
- 2016年11月
- 2016年12月
- 2017年1月
- 2017年2月
- 2017年3月
- 2017年4月
- 2017年5月
- 2017年6月
- 2017年7月
- 2017年8月
- 2017年9月
- 2017年10月
- 2017年11月
- 2017年12月
- 2018年1月
- 2018年2月
- 2018年3月
- 2018年4月
- 2018年5月
- 2018年6月
- 2018年7月
- 2018年8月
- 2018年9月
- 2018年10月
- 2018年11月
- 2018年12月
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 新規ページ
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年4月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2020年11月
- 2020年12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- お問い合わせ
小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。
やつらはカレンダーがわかっているらしい。
というわけで、いよいよ夏本番。
といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。
関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。
そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、
近年、カタツムリをあまり見かけない。
息子がチビだったころには、
いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。
前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を
よくノロノロ歩いていた。
今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、
草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、
カタツムリをまったく目にしない。
まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、
ちょっと心配になる。
夏になると、生き物たちの活動は活発になる。
昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。
ガラスにへばりついていると、
ひんやりして気持ちいのかもしれない。
ちょっと窓をズラしてやると、
驚いてペタペタ動きまわる。
ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。
トカゲもちょろちょろしていて可愛い。
このあたりの輩は高速移動できるからいいが、
悲惨だなと思うのはミミズである。
ここのところ毎日、
道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。
それも一匹や二匹ではない。
赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が
数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。
まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。
それにしても、なぜだ?
果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、
無数のミミズたちに僕は問いかける。
おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、
なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて
熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?
なぜ故郷をあとにしたのか?
なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?
この道路の向こう、この地獄を超えた先に、
おまえたちの目指す楽園があったというのか?
それはあの植え込みか、草むらか?
もちろん、誰も答えてはくれない。
ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。
セミやハチやチョウのように空を飛べれば。
せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。
しかし、ミミズはミミズ。
地を這い、土に潜る。
それが宿命づけられた生き方だ。
その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、
それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?
というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、
ちょっと悲惨過ぎて載せられない。
ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも
いやだという人が多いだろうが。
なので本日は、クールビズしている
元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。
ヘビとの遭遇

今年の干支は?
って聞かれて「えーと」なんてダジャレてる人、
けっこう多いのでは?
1年半分の6月ともなると、お正月の熱狂もどこへやら。
今年は何年だったか、みんな忘れてしまっている。
改めて、今年-2015年、令和7年はヘビ年。
そのせいか、この春からは初夏にかけて、
川沿いを散歩していると、やたらとヘビに出会う。
護岸の下のコンクリの岸の上に
何やら太いロープが落ちているなと思ったら、ヘビ。
散歩道の植え込みの中で何かにょーっと
動いているなと思ったら、ヘビ。
手すりに何か紐みたいなものが
ぶら下がってるなと思ったら、ヘビ。
そして昨日は、くねくねしながら悠々と川を泳いでいる
ヘビを目撃。
どれも長さ1メートルほどの青黒いアオダイショウだ。
周囲にはカルガモやコサギ、アオサギ、
カワウなどの水鳥が何羽もいるが、
さすがにこれらは体が大きいので襲ったりはしない。
うまいこと共存しているようだ。
そろそろカルガモの赤ちゃんが生まれる時期なのだが、
今からそれを狙っているのだろうか?
毎年1回か2回、
梅雨から梅雨明けの時期にお見掛けするヘビだが、
今年はすでに目撃4回。
ヘビ年大売り出しだ。
遭遇するとちょっとギョッとはするが、
ヘビに遭うとラッキーなのだそうな。
そういえば数年前だが、
住宅街の道路を白ヘビが
超高速で横切るのを見たことがある。
神の使いともいわれるヘビ。
今度会ったら手を合わせて願いを唱えよう。
人の気配が薄れる夜の時間は、
ネズミでも襲って腹を満たしているのだろうか。
杉並区も人間が知らないところで
ワイルドな世界が繰り広げられている。
ペットロスから人生観・死生観が変わる

ペットロスによって人生観が変わった
という人の話を聞いた。
飼っていた柴犬が目の前で車に跳ねられたという。
話によると、散歩中、首輪がすっぽ抜けてしまい、
その犬が走り出した。
彼は追いかけたが、犬は面白がってグングン走り、
大量の車が行き交う大通りの交差点に飛び出した。
信号は赤。車が停まれるはずがない。
衝突した瞬間、犬は空中に高くはね上げられた。
歩道にいた彼の視界からは、交差点の風景は消え、
空の青をバックに、スローモーションで踊るように3回、
からだが回転する犬の姿だけが見えていたという。
「僕、赤信号渡ってましたね。
よく自分も跳ねられなかったと思います。
道路に落ちた犬を抱き上げました。
病院に連れて行こうと思って、
まず家に帰ったんですけど、
ちょうど玄関までたどり着いた時に、かくって死んだ。
よくドラマなんかで「かくっ」って死ぬでしょ。
あれだったよ。かくっとなってね。
口からすんごい色の血が出てきて」
この飼い主というのは、坊さんだ。
お寺の坊さんなので、それまで葬式や法事でお経を唱え、
何百回とご供養のお勤めをしている。
しかしというか、だからというか、
死は坊さんにとっては日常的なことであり、
他人事でもある。
ビジネスライクになっていたところは否めない。
けれども、犬の死はこの坊さんに大きな衝撃を与えた。
彼は精神的におかしくなって仕事が出来なくなり、
本山に行って一週間、
引きこもり状態で法話を聴き続けたという。
「あんなに真剣に、
仏様についての話を聞くことはなかったです。
そのきっかけを犬がくれましたね。
だから僕は仏様が犬の姿となって現れて
僕をまとも坊主に導いてくれたんだと今でも思ってます」
彼は今、自分の寺を持ち、
そこにはペットロスの人たちが自然と集まってくる。
ペットが死んだからと言って、
誰もが彼のような経験をすることはないと思うが、
それでもペットロスがきっかけとなって、
人生観・死生観が変わるといった話は時々聞く。
いっしょに暮らす、命ある生き物は、
僕たちが通常送っている
人間の社会生活とは違った角度から、
生きること・死ぬことについて、
考えさせてくれるのは確かなようだ。
死について考えることは、
よりよい生について考えること。
Deathフェス|2025.4.12-17 渋谷ヒカリエで開催
「死」をタブー視せずに人生と地続きのものとして捉え、
そこから「今」をどう生きるかを考える 。
新たに死と出会い直し、
生と死のウェルビーイングを考える「Deathフェス」を、
毎年4月14日(よい死の日)を中心に開催。
「むじな地蔵」と善光寺
「わたしゃ殺生しないと生きられない。
だから、ご供養のために灯篭を寄進したいのです」
そう言って人間に化け、
長野の山中から善光寺参りをしに来たのはムジナ。
ところが泊まった宿坊「白蓮坊(びゃくれんぼう)」で
お風呂に入ってうっかり正体を現したところを、
宿坊の坊さに見られ、あわてて飛び出して山へ逃げ帰ってしまった。
そんなムジナを不憫に思った住職は、
ムジナの代わりに境内に灯篭を建ててあげた。
そんな昔ばなしが残る白蓮坊には、
今、入口にかわいい「むじな地蔵」が立っていて、
人目を集める「招き地蔵」「招きムジナ」になっている。
時に妖怪扱いされるムジナには、
タヌキ説とアナグマ説がある。
どちらも雑食性なので、
他の生き物を殺生するのは同じだが、
人に化けるというパフォーマンスから考えると、
ここではタヌキ説が有力だろう。
像もやはりアナグマではなく、タヌキに見える。
いずれにせよ、
こうしたユーモラスな昔ばなしが残るほど、
善光寺は動物に対しておおらかな場所である。
さすがに本堂のなかや建物の中には入れてもらえないが、
境内にはタヌキの親戚であるイヌが大勢散歩している。
仲見世通りのお店には「招き犬(豆柴)」もいた。
ネコも何匹か住み着いていて、
夜になると出て来るらしい。
そういえば「牛に引かれて善光寺参り」という
有名なことわざも残っている。
仏さまの聖域は、どんな人間も、どんな動物も、
ウェルカム状態なのだ。
訪れたのがちょうど七五三の季節だったので、
かわいい着物を着た子どももあふれていて、
昼間は宗教施設というよりも、
子どもや犬が遊ぶポップアートゾーンみたいな
イメージのところだった。
おおらかな気持ちになることが
ごりやくにつながるのだろう、きっと。
べつにガチで信心しなくても、
近所の神社やお寺の前を通った時、
神さまなり、仏さまなりに
日常的に手を合わせていると、
いいこと、いろいろあるかもよ。
ベッソン映画「DOGMAN」は「GODMAN」
犬を自由に操る女装のダークヒーロー。
壮絶なアクション。
監督は「ニキータ」「レオン」のリュック・ベッソン。
ということで、ベッソン特有の
妙に重量感のあるアクションシーン、
そして、目を覆いたくなるような暴力・殺人シーンが
先行して頭に浮かんで、
しばらくためらっていたが、やっと見た。
良い意味で裏切られた。
「ドッグマン」(2023年)は、人間の美しさ、
そして、犬の美しさを描いた、すごくいい映画だ。
これはAmazonPrimeでなく、
映画館で観るべきだったかもしれない。
何と言っても、主役ダグラスを演じる
ケイレブ・ランドリー・ジョーンズが魅力的。
少年時代、彼は父と兄に虐待されて
犬小屋に放り込まれて生活することになり、
障害を負いながらやっと脱出する。
その後、養護施設で、のちにシェイクスピア女優になる
養護員の女性に芝居を通して生きる喜びを学び、
彼女に恋をして成長する。
しかし、そんな彼に世間は決してやさしくない。
やがてドラッグクイーンとなって歌って
アイデンティを保つ一方で、
犬たちと生活するために犯罪に手を染める。
そうした変化の在り様・人間形成の在り様を
じつにビビッドに演じ描く。
また、紹介文や予告編などから、
犬たちは恐ろしく凶暴で、獰猛で
野獣的な犬を想起させるのだが、
意外にもけっこう可愛いのが多い。
随所に人を襲うシーンがあり、
クライマックスのギャングとのバトルでは
それこそ壮絶な闘いを繰り広げるが、
けっしてリアルには描かれず、
ここで出てくる犬たちは、
ファンタジーの領域にいる生き物のように見える。
動物愛護団体の視線もあるので
襲撃・戦闘シーンは、
あまりリアルには描けないという
事情もあるのかもしれない。
ベッソンの映画はアクションやバイオレンスばかりが
取りざたされる感があるが、
彼のドラマづくりは、
いつも人間の美しさ・崇高さを追求している。
そういう意味では、
アクションで売り出す前の出世作「グランブルー」で
前面に出ていたファンタジー性こそ、
ベッソン映画の真髄・醍醐味なのだと思う。
この映画では最後にそれが表出される。
ラスト5分は本当に美しく、
ダグラスは人間を卒業して神になるかのようだ。
そして犬たちがダグラスを導く
天使のように見えて涙が出た。
「DOGMAN」は「GODMAN」。
アナグラムになっているのだ。
一つ気になるのは、全体の雰囲気が
「ジョーカー」(2019年)によく似ていること。
こちらも主役ジョーカー(アーサー)を演じた
ホアキン・フェニックスの怪演が見ものだが、
「児童虐待」「障がい者差別」「貧困との戦い」
これらを物語の根底のテーマに
置いているところも同じだ。
別にパクリだとは思わない。
こうした個人的問題と社会的問題が
ダイレクトにつながって感じられる点が現代的で、
映像系であれ、文学系であれ、
エンタメコンテンツに求められている
現代的役割の一つなのだろうと思った。
ちなみに「ジョーカー」の続編、
『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が
来月、10月11日(金)劇場公開。
なんとレディー・ガガが共演する。
同窓会とベンジャミン・バトン

同窓会のコピーライティングの仕事を頼まれた。
同窓会のために
わざわざコピーライティングやロゴデザインを
依頼するくらいだから、
とても大規模なものだ。
もちろん、クライアントの名前は言えない。
フリーランスになってしばらくの間、
2000年頃までは割とこうした系統の仕事があったのだが、
今回は久しぶり。
何かちょっと若がえった感じがする。
最近、コロナ禍明けの世界の変わりように
ちょっとまごつき、
なんだか64歳でこの世に新しく生まれた
錯覚にとらわれることもある。
まるで映画の「ベンジャミン・バトン」みたいに。
生まれた時は年寄り。
成長するにつれて若くなり、
最期は子どもになって人生の幕を閉じる。
この間、歌手のテイラー・スウィフトが
ハリス大統領候補支持を表明したが、
その時にのニュースで、
彼女の飼い猫の名前も
「ベンジャミン・バトン」だと知った。
(3匹飼っているうちの1匹らしい)
たぶん、あの映画からとったのだろう。
ネコとファンタジーはお似合いだ。
僕もネコのように生きたいと思って、
その希望に忠実に生きてきたが、
その思いは齢と共にますます強まっている。
脳みそを10代・20代に戻すために
同窓会は特効薬。
さりげなく、明日1日ニャンばって考えてみる。
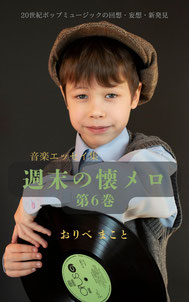
20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!
音楽エッセイ集
週末の懐メロ 第6巻
9月23日(月・祝)まで
無料キャンペーン実施中!
ちょっと一息つきたくなったら動物ばなし
人間はひとりでは生きられないし、
この星で人間同士だけでは生きられない。
だから僕たちは動物を見たり、
いっしょに遊んだりしたくなる。
動物エッセイ集 無料キャンペーン実施中!
8月18日(日)15:59まで。
●ねこがきます
・明治35年の少女とうさぎ
・ネズミは夕焼け空に叙情を感じるか?
・アニマルガモの愛のいとなみ
・ヒョウモンリクガメとの遭遇
・ヒトとブタは神目線ではブラザーなのか?
・あなたのワンちゃんが今、ウンコしましたよ!
・ねこがきます ほか全34編
●神ってるナマケモノ
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・金魚の集中力は人間以上
・カラス対ガマガエル 真昼の決闘
・なぜプードルもチワワもダックスフンドも“いぬ”なのか?
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ ほか全36編
戦争でワニを喰った話

「ねえ、お父さんもワニを喰ったんだよね?
喰ってくれたんだよね?」
つかこうへいの芝居
「戦争で死ねなかったお父さんのために」
に出てくる主人公のセリフが、
今でも耳に残っている。
同作は、1970~80年代にかけて活躍した
劇作家つかこうへいの代表作の一つだ。
僕が子どもだった昭和40年代は、
周囲の大人から戦争にまつわる
さまざまな逸話を聞くことができた。
いまと同様、
「戦争=悪・地獄・二度と繰り返してはならない」
という主張はもちろん主流だったが、
その一方で、戦争体験者、
なかでも前線で戦った元・兵士の
戦地におけるリアルな体験談は、
誰かに強制されることがなくても、
自然とピンと背筋を伸ばして聴いた。
僕たち子どもは、
彼らを尊敬のまなざしで見ていたのだ。
しかし、その体験談のなかには、
耳を疑うようなトンデモ話も混じっていた。
飢えをしのぐために「ワニを喰った」
という話もその一つだ。
直接ではないが、
友だちの○○くんの親戚の△△さんが、
「南方戦線に行ってジャングルでワニを喰った」
という話を聞いた憶えがある。
それだけでなく、
人づてにワニとかオオトカゲとかを喰ったという噂を
いくつも聞いた。
心底すごいなと思った。
そんな地獄から生還したような人を引き合いに出されて、
「今どきの子供は恵まれてていいねぇ」
などと言われると、
「すみません。のうのうと生きてて」
と、悪いことをしたわけでもないのに
頭を下げたくなった。
戦争で、南方で、敵と戦い、
食べ物がなくなり飢えた。
ジャングルの沼にはワニがいる。
体長5メートルを超えるほどの
巨大で凶暴な人食いワニだ。
その人食いワニを
逆に捕まえて殺してさばいて喰った。
そうして飢えをしのぎ、
ぎりぎりのところで生き延びて日本に帰ってきた。
そんな人は、今どきのマンガや映画のヒーローが
束になってぶっ飛ぶような、
超英雄、激ヤバ、最強の日本人だ。
アメリカに負けて失意のどん底から立ち上がった
70~80年前の日本人は、ホントかウソかなんて、
どうでもいいから、
そうした英雄伝・武勇伝を欲していたのだろう。
「こんなにすごい、ヤバい、強い仲間がいるのだ」
という思いは、
戦後のハングリーな日々を生き抜く強壮剤として、
ぜひとも必要だったのに違いない。
つかこうへいは、僕より一回り上の団塊の世代である。
戦後の復興・経済成長とともに生れ育った世代にとって、
戦中世代・親世代に対するコンプレックスは、
僕などよりはるかに強烈だったのだろう。
「戦争で死ねなかったおとうさんのために」の主人公も
兵士だった父にそういうものを求めていた。
しかし、同じ兵士でも彼の父には
前線で敵と渡り合った体験もなく、
修羅場をくぐり抜けた体験もなく、
息子の期待するものを与えられない。
それで息子は、自分の父は他のさえない、
薄汚れた大人とはちがう、尊敬すべき存在なんだ、
という思いを持って、悲痛な思いで問い詰めるのだ。
「ねえ、お父さんもワニを喰ったんだよね?
喰ってくれたんだよね?」
親世代に対する劣等感と憧れ、
そして自分のアイデンティをどう作るかが
ないまぜになった屈折した感情の世界に、
観客の僕らは、笑いと涙を抑えられなかった。
昭和の頃、「戦争」という圧倒的なリアル体験は、
貴重で尊敬すべきものだった。
けれども70年・80年という時間は、
「ワニを喰った」といった、
リアルだけど下賤な物語を風化させ、
「平和を大事に」「戦争を繰り返さない」
という美しい理念だけを残した。
終戦記念日も、
もう大半の日本人にとって特別な日ではない。
それでもやはり、毎年この日には
僕のからだの中に昭和の空気が帰ってきて、
父やその仕事仲間のおじさんたちの顔が
よみがえってくる。
だから忘れてはいけない。
戦争を体験した人たちへの畏怖と敬意を。
僕たちは、恵まれた世界で生かしてもらっているのだ、
という思いを。
おりべまこと電子書籍
夏休み無料キャンペーン
本日8月13日(火)16:00~8月18日(日)15:59
ねこがきます
神ってるナマケモノ
動物エッセイで笑って、癒され、考えてみてください。
オリンピックと老害的トド発言

和田アキ子さんが、パリ五輪のやり投げで
金メダルを獲った北口選手を
「トドみたい」と表現して、ネットで大炎上している。
司会をやっているバラエティ番組での発言らしい。
実際に聞いてないが、
けっして侮蔑的な意味で言ったわけではなさそうだ。
むしろ親しみを込めて、
ユーモラスに表現しようとしたのだろうと思う。
ちょっと昔だったら、
しかも大御所・和田アキ子さんが言ったことであれば、
みんなで軽く笑って終わってたことだろう。
しかし、最近はコンプライアンスがめちゃ厳しく、
そうは取ってもらえない。
また、文字になって情報が流通してしまうと、
言葉に込めた感情やニュアンスがはぎとられて
違う意味合いを帯びてしまう。
いずれにしても人を動物にたとえることは、
かなり気をつけないといけない。
野蛮な(?)時代を生きてきた昭和人のなかには
人を傷つけたり、ネタにしたりして
人気を獲得してきた人たちが大勢いる。
毒舌家やイジメ役は、痛快な印象を与え、
むしろ大衆から歓迎される傾向にあった。
しかし、特にコロナ後、風潮が大きく変わり、
そうした昭和人の感覚がまったく通用しなくなってきた。
政治家しかり。
芸能人しかり。
文化人しかり。
一般ピープルがつくるネットのパワーは威力を増し、
「これ以上、“老害”は許さない」とばかりに、
世のなかが大きく動いているようだ。
昭和世代に対する、
平成世代の悪感情も作用しているかもしれない。
SNSの影響力もますます大きくなっている。
今回のオリンピックでも、
選手や審判への誹謗中傷も問題になったようだ。
人類の超絶すごさ・とんでもないダメさ、
両方ごたまぜの「ヒューマン大博覧会」、
「サピエンスギャラリー」であるオリンピックは、
情報化社会のさまざまな負の面、
そして時代の大きな変化とも
この先、ずっと向き合っていかなくてはならない。
おりべまこと電子書籍
夏休み無料キャンペーン:動物エッセイ2タイトル
明日8月13日(火)16:00~
8月18日(日)15:59まで。
発売早々大人気「ねこがきます」

おりべまこと 電子書籍新刊
動物エッセイ集「ねこがきます」
本日発売! 発売早々大人気
人間社会で日常生活を送るあなた、
ちょっと疲れていませんか?
ふっとひと息つきたくなったら、
動物を見たり、いっしょに遊んだりしたくなりませんか?
人は疲れた心を癒すために
イヌやネコなどのペットを飼います。
公演に行って野鳥を見ます。
動物園や水族館へ動物に逢いに行きます。
あるいはテレビやネットで動物の姿や行動を見て
笑ったり、ほっこりした気持ちになったり。
どうしてあなたもわたしも動物を求めるのでしょうか?
なぜなら人間はひとりでは生きられないし、
人間同士だけでは生きられないから。
わたしたちにはこの世界、
この地球でいっしょに暮らす仲間が必要です。
たとえそれが違う種類の生き物でも。
その仲間の存在を確認することが、生きていく上で欠かせないのです。
この本は、そんなことを考えながら、
身近に目にする動物たち、物語の中の動物たち、
そして人間と動物との関係について
綴ったエッセイ集です。
頭の中にネコやイヌやウサギやカメの姿を
思い浮かべながら
お気軽に覗いてみてください。
もくじ
- 子どもはネズミ好きなのに、おとなはどうしてネズミが怖いのか?
- 今宵、夢の中で耳木兎は羽ばたき、不苦労な明日を連れてくる
- うさぎと少女ヒロイン
- 脂ののったカルガモを狙う野生のクロネコ
- 飼い主にはペットを看取る使命がある
- ペットの遺骨を真珠に育てる真珠葬 「虹の守珠(もりだま)」
- ネズミは夕焼け空に叙情を感じるか?
- 善福寺川のチビガモ成長中
- アニマルガモの愛のいとなみ
- 杉並・善福寺川どうぶつキッズサマー
- ワイルドボーイ・オオタカきょうだい大成長
- 目覚めればオオサンショウウオ
- ねこがきます
- そのワンちゃん・ネコちゃんの動画投稿は虐待ではないですか?
- ニャンとかもっと稼がニャいと
- インターペットで真珠葬大人気
- 「世界カメの日」に考える なぜ浦島太郎はカメを助けたのか?
- 烏山寺町のネコ寺
- さらばノラネコきょうだい
- ヒョウモンリクガメとの遭遇
- ヒトとブタは神目線ではブラザーなのか?
- 愛しきブタと「ねほりんぱほりん」のFIRE
- ウルフとチワワと犬の本能の発散について
- ペットも参列できるお葬式
- あなたのワンちゃんが今、ウンコしましたよ!
- チビガモ8きょうだいの冒険
- チビガモ8きょうだい続編
- カッパの正体を解明(?)した本
- 日本人にモテる“グロかわいい”ハンザキ
- 杉並ラプトル・オオタカ物語
- 雨の中、子どもたちはカエルを放つ
- 高価情報商材制作の裏話
- 犬と息子(娘)との上下関係について
- ネコのタマはタマなし?
全34編載録
(DAIHON屋ブログ https://www.daihonya.com/より)
電子書籍「ねこがきます」発売予告

おりべまこと新刊
エッセイ集:動物2「ねこがきます」
7月27日(土)発売予定!
人間社会で日常生活を送るあなた、
ちょっと疲れていませんか?
ふっとひと息つきたくなったら、
動物を見たり、いっしょに遊んだりしたくなりませんか?
人は疲れた心を癒すために
イヌやネコなどのペットを飼います。
公演に行って野鳥を見ます。
動物園や水族館へ動物に逢いに行きます。
あるいはテレビやネットで動物の姿や行動を見て
笑ったり、ほっこりした気持ちになったり。
どうしてあなたは動物を求めるのでしょうか?
なぜなら人間はひとりでは生きられないし、
人間同士だけでは生きられない。
いっしょにこの世界、この地球で暮らす仲間が必要です。
その仲間の存在を確認することが、
生きていく上で欠かせないからです。
そんなことを考えながら、
身近に目にする動物たち、物語の中の動物たち、
そして人間と動物との関係について綴ったエッセイ集。
頭の中にネコやイヌやウサギやカメの姿を思い浮かべながら
気軽にどうぞ。
もくじ
明治35年の少女とうさぎ
脂ののったカルガモを狙う野生のクロネコ
飼い主にはペットを看取る使命がある
ネズミは夕焼け空に叙情を感じるか?
アニマルガモの愛のいとなみ
ワイルドボーイ・オオタカきょうだい大成長
目覚めればオオサンショウウオ
ねこがきます
ほか 全34編載録
AIが書く「初めての猫とのくらし」

AIライティング講座では「初めて猫を飼う」
というキーワードを使って
記事を作っている。
「AIがあれば人間要らない」
というイメージが先行しているが、
型にはまった形式的な文書ならともかく、
人の読書に耐えうる文章を生成するという点では、
いろいろ問題がある。
先週、プロンプトの見本を使って
AIに原稿を生成させたが、
今週の課題は、その原稿=初稿を人の手で直す作業。
いわば、編集・校正作業だ。
AIは自信満々で嘘八百の情報を交えて
文章を作ってくることがある。
一見ちゃんとしていて、
それなりにまとまったものになっているので、
うっかり騙されることが多い。
僕もChatGPTにさんざん混乱させられた。
なのでまずハルレーション、
つまりAIが勝手に作るウソ情報を見つけて訂正した上で、
読みやすく修正する、
という手作業が必要になってくるのだ。
だから、AIライティングと言っても
全然ラクではなく、なかなか手間がかかる。
ところが、Claudeが出してきた
「初めて猫を飼う」の初稿は素晴らしい出来ばえ。
猫の寿命、購入金額、飼育費用など数字の部分も、
猫の病名とか、僕が知らなかった専門用語にも
ハルレーションはなく、ほぼ完ぺきと言っていい。
文字数は1万7千字近く(原稿用紙40枚以上)あるが、
けっして冗長ではなく、しっかり情報を詰め込んでいる。
プロンプトの入れ方がよかったのか、
十分、人間らしい温かみがあり、
楽しんで読める記事になっている。
ChatGPTが出してきた同じキーワードの原稿と比べると、
そのレベルの差は一目瞭然だ。
毎回同じことを言っているが、
Claudeすごい!
講師の先生からは、
さらにすごいClaudeの機能の話を聞いたが、
それはまた別の機会に。
余裕ができたので、明日・明後日は、
もう1つやったキーワード「花屋開業」の編集にも
トライしてみようと思っている。
ネコのタマはタマなし?

たまたまタマなしネコの話を調べることになり、
タマなしのオスの生きる道について考えてみた。
今回ここでいう「タマなし」とは
動物の去勢のことで、ジェンダー問題とは関係ない。
今どき都会で飼われるイヌやネコは、
ほぼほぼ愛玩用で、自然の状態から切り離し、
人間社会に組み入れるわけだから、
その辺に出て行ってヤリまくって
子供がうじゃうじゃできると困る。
そういうわけで避妊・去勢もやむなし、と考えられている。
ちょっと古いが、2017年の調査によると、
避妊・去勢手術をしたイヌは全体の約5割、
ネコは8割だという。
これは多分、飼い方の違いだろう。
イヌは外出の際、必ず飼い主といっしょだが、
ネコは勝手に出歩くことが多い。
それで雄雌がくっついてやっちゃうからだ。
「去勢」という言葉には心がざわつく。
男子なら誰でもそうだろう。
実際、雄イヌ・雄ネコの男性飼い主は
「そんな可哀そうなことできるか」と
反対する人が多いらしい。
それに対してメスの避妊にはあまり反対しない。
可愛い娘がその辺の男とやっちゃってできちゃったら
大変だという、父性愛(?)の由縁だろうか?
人間同様、イヌもネコもお年頃になると、
脳内にホルモンがドバドバ出て、
やりたくてたまらなくなる。
オスの立場に立つと、
強烈なフェロモンを発散しているメスに遇ったのに
ガマンを強いられると、頭狂いそうになるかもしれない。
これは人間も同じで、男の人生の半分は、
そうした己の性欲との戦いとも言えるのだ。
実際、イヌ・ネコも未去勢だとストレスが溜まって
暴力的になったり、
夜鳴きやマーキングなどの問題行動が増えるらしい。
だから男の子のイヌやネコと
なかよく平和に暮らしたければ、
できるだけ性欲に悩まされないよう、
去勢しておっとりした子にしたほうがいい――
という意見が優勢に見える。
でも、タマなしネコだと
ネズミを捕らなくなっちゃうのでは?
と思ったら、そんなことはなく、
狩猟本能そのものには大きな影響を与えないようだ。
今どき、ネコをネズミ駆除用に飼う家は少ないと思うが、
せっかくいるのなら役立ってくれれば、
それに越したことはない。
これ見よがしに血まみれの獲物を持て来られると
嫌かもしれないけど。
動物病院のネコの去勢手術の動画を見たら、
麻酔をかけて結構簡単に済ませていた。
ただ手術後、そのネコが股の間を舐めていて
「あれ、タマないぞ」と気付くシーンには、
やっぱちょっと胸が切なくなったな。
ちなみに家畜のブタやウシのオスも
少し成長すると、オス独特の体臭がついて
肉の味を落としてしまうため、去勢する。
しかし、こちらの場合、
日本ではまだ麻酔をかけずにやっているので、
アニマルフェアウェルの観点から問題視されている。
肉の味をよくするために男の子のブタ・ウシが
タマを切られて痛い思いをしているのを想像すると、
けっこう複雑な気持ちになる。
業者の人たちは、一生懸命おいしい肉を作ろうと
努力してやっているのだが……。
犬と息子(娘)との上下関係について

先日、川沿いの公園で体長1メートル強、
体重は20キロ弱ありそうな秋田犬を散歩させている
高校生か大学生と思しき男の子に遇った。
ところがその犬、疲れたのか、
その場所が気に入ったのか、
あるいはご機嫌を損ねたのか、
途中で道の真ん中に座り込んで動かなくなった。
「おい、どうした?行くぞ、行こうよ」と、
彼が何度もなだめすかそうとも、
ハーネスのリードを引っ張ろうとも、
泰然自若としていて、
とうとうその場で寝そべり始めた。
「某は動きたくないでござる」という感じ。
歩き方や全体の雰囲気からして、
シニアっぽい犬だったので、
ゆうに10歳は超えていると推察する。
ということは彼が子犬だったころ、
今連れて歩いている若僧はまだ小学校の低学年。
親からはもちろん子ども扱いだ。
犬は上下関係に厳しい。
家のなかで息子は最低の地位。
彼がまだチビの間に犬はおとなになり、
自分はこいつより地位が上だと思っている。
息子が大きくなって、だんだん両親と対等になっても、
犬の意識は「おれは上、あいつは下」のままだろう。
だから坐りこんで
「なんで某が下っぱの貴君の言うことを
聞かねばならぬのか」となる。
困った彼はしたかたなくその犬を抱きかかえて
歩き出した。
とはいえ、20キロ近くあろう大型犬なので
そのまま家に帰るのは大変だっただろう。
それにしても、もし何らかの事情で、
それまでの主人である父や母が家からいなくなり、
息子(あるいは娘)と犬だけの暮らしになったら、
二者の関係はどうなるのだろうか?
犬の意識は「これからはおれは下、あいつが上」
に変わったりするのだろうか?
あるいは若殿(姫君)と
年長の家来みたいになったりするのだろうか?
飼い主さんで、もし知っている人がいたら
教えてください。
高価情報商材制作の裏話

今日はかさこさんの
「良いセミナー、悪いセミナーの見分け方講座」
に参加した。
自身もセミナーを主催する、ネット発信のプロだけあって
いろんな事例を知っている。
話自体はブログやSNSでいつも書いていることだったが、
改めて聴くと本当に面白かった。
てか、受講料100万円とか、すごいセミナーがあるものだ。
大学の年間の学費じゃん!
僕のところにもよく7ケタ稼げる、8ケタ稼げるとかいう
お誘いのメッセージが来る。
なぜか女が多い。
顔を見て、こいつは女に弱そうだから
女からのお誘いだよんということにしとけってことか?
20代・30代の時だったら引っかかってたかもね。
今日の講座で思い出したが、
僕も「情報商材」のビジネスに加担したことがある。
情報商材というのは、
今で言えば電子書籍みたいなもので、
原稿をPDFファイルにパックしたもの。
まだこれだけSNSが普及する前だから
もう15年近く前だと思う。
その情報商材ビジネスで儲けているという会社が
プロデューサーを募って作らせるのである。
僕はそのプロデューサーのMくんという青年に頼まれ、
犬のしつけコーチの先生に取材して原稿を
本一冊分書いた。
そこそこのボリュームで、
たぶん4~5万字程度あったのではないかと思う。
内容としてはいたってまともで良い商品だったが、
それを確か2万円だか、3万円だかで
ネット販売するというのだ。
取材した先生はテレビ出演や本の出版の経験もある、
そこそこ有名な人だったが、
それにしても本ならせいぜい2千円程度の代物を
2万、3万で買う人がいるのだろうか?
なんかインチキっぽい。
実際に製作に関わった
僕と先生とイラストレーターは大いに疑問を抱いたが、
その会社はいくつもその情報商材を売って
実績を上げているし、
Mくんもちゃんとギャラは支払うというので協力した。
ところが、原因は忘れてしまったが、
そのMくんと先生との間でトラブルが起こり、
会社の上役たちがゾロゾロ出てきて説得していたが、
結局、計画は頓挫してしまった。
優秀なスタッフを揃え、
成功まちがいなし・大儲けを信じていたMくんは
結局、僕らのギャラを払っただけで大赤字だった。
あまりに気の毒なので僕のギャラは
当初よりかなり安くして請求した。
それでも何回かの分割払いだった。
SNSや電子書籍全盛の時代になったが、
まだこのPDF式情報商材はネット上で
けっこう流通しているようで、
あちこちでトラブルを起こしているのを見かける。
ジャンルとしてはどうやら
投資やギャンブルに関するものが多いようだ。
そう言えば、ライターのエージェンシーのサイトでも
時々、「情報商材ライター募集」という求人を見かける。
情報商材も、怪しいセミナーも、投資サロンも、
それぞれはっきり実態がわかってるわけではないが、
同じ穴のムジナと思われる。
それにしても3万円出して情報商材を買う人、
数十万円・100万円出してセミナーを受ける人って、
どういう人なんだろう?
カネの使いどころに困っている金持ちさんなのだろうか?
ビジネスが成り立ち、成功者がたくさん出るほど、
そういう人が大勢いるのだろうか?
そういや、特殊詐欺でも
信じられないほどの金額を振り込む人がいる。
とてもまともな金銭感覚ではない。
みんな、金のことを考えすぎて
頭も価値観もおかしくなっているのではないか?
たんに僕がビンボー人だからそう思うだけなのか?
日本はますます不思議な国になってきた。
雨の中、子どもたちはカエルを放つ

小雨の降る中、義母をつれて川沿いを散歩していたら、
小3くらいの子どもたちが4、5人、
自転車やキックスケーターで爆走していく。
雨ふりなんてへのカッパって感じ。
最後に走って来た、
ピカピカ光るキックスケーターの女の子に
「雨なのに平気なの?」と声をかけたら、
振り返って
「あのね、これからカエルを放しにいくんだ」と、
目をキラキラさせながら言う。
彼女らの行先には池がある。
捕まえたのか、それとも
飼ってたオタマジャクシが成長したのか、
わからないが、どうやらその池に
カエルを解き放ってあげるらしい。
いろいろ訊きたいことはあったが、
彼女はひとことだけ言い残すと、
ワクワクした気持ちが抑えらえないらしく、
またキックスケーターをかっ飛ばして
風のように去って行った。
なんだか春の雨が心地よく感じられる。
いいぞいいぞ、
カエルもきみたちも解き放たれて
自由に飛び跳ねてケロ。
あなたもお忘れの4月29日「昭和の日」にちなんで、明日から昭和エッセイ本2冊同時6日間無料キャンペーンやります! この機会にぜひ。
4月25日(木)16時~30日(月)15時59分迄。
昭和99年の思い出ピクニック
昭和96年の思い出ピクニック
杉並ラプトル・オオタカ物語
お正月も終わったが、
今年は元旦に川沿いを散歩していたら、
杉の木のてっぺんでオオタカが雄姿を晒していて、
こいつは縁起がいいと思わず拝んでしまった。
オオタカのお正月スペシャルサービス?
おかげで初夢も見た。
仕事仲間とタクシーに乗って
銀座や原宿に行くという
わけのわからない夢だったが、
まぁ悪い夢ではない。
もしかして今年は仕事が忙しくなって
がっぽり儲かる夢--と解釈できなくもない。
どうせ意味などわからないので、
いいようにとっておこうと思う。
それにしても縁起の良い初夢が、
どうして1富士、2鷹、3茄子なのか?
諸説あるようだが、有力なのは徳川家康がらみの説。
家康は三河(愛知県)の生まれだが、
江戸に幕府を開くまで長い間、
拠点にしたのは駿河の国(静岡県)。
静岡の名物と言えば富士山。
一番高いのは富士山だが、
次に高いのは空飛ぶ鷹、三番目は初茄子の値段。
というシャレの世界。
また、富士山の国で暮らしていた家康が
鷹狩りが好き、茄子も好物という説もあり、
鷹は獲物をつかみ取る。
家康のように天下をつかみ取ろう、
学芸でも商売でもその世界のトップになろうと
願をかける意味合いがあったらしい。
うちの近所のこの川沿いの杉の木に
オオタカが住み着くようになって
もう5、6年の年月が経つ。
昨年はクマやイノシシなど、
元来、山に住む動物たちが街に出てきて
人間に危害を加える事例が頻発し大問題になったが、
いま動物たちは長年の経験で
人間に慣れて恐れを抱かなくなり、
人間の生活圏に侵入することに
抵抗を感じなくなってきたようだ。
「人間はこわくない」
「人間が住んでいる場所にはうまいものがある」
「だいじょうぶ、いける、いける」
個体ごとに経験則を学ぶのか、
それとも世代間で情報が受け継がれるのか
わからないが、だんだんそういうことが
山の動物の間で常識として
広がってきているのかもしれない。
だとすれば人間が暮らし方を変えるか、
動物との付き合い方を変えなくてはいけない。
どうやらそういう時代になってきたようだ。
さて、わが杉並区のオオタカもまたしかりで、
住み着き始めた当初は、人目を警戒して
常に高い木のてっぺんあたりからめったに下りず、
天空の生活圏から出てこようとしなかった。
近所のカメラマンの人たちはそれこそ
野生動物専門のプロカメラマンのように
一瞬でもその姿を捕らえようと、
毎日木の下をウロウロしながら
朝から日暮れまで何時間も張っていたが、
幾たびも子育てを重ねるうちに、
だんだんオオタカたちは大胆に姿をさらすようになった。
人間は遠目で見ているだけで、近づいてこないし、
ましてや捕まることなんてありえない。
そうしたことをしっかり学習したようで、
低木に、時には地面に降りて餌を食うようになった。
もちろん、バシャバシャ写真撮りまくりである。
また、割と低空飛行でゆうゆうと飛ぶところ、
「ほーら、見てごらん」とでも言いたげに、
川を横断して人目に付く木の枝に止まり、
モデルのごとくポーズを取るといった行為も
見せるようになった。
翼を広げたオオタカはやっぱりカッコいい。
びっくりしたのは昨年秋。
11月ごろのことだったので、
まだ2カ月ほど前である。
夕方近く、義母と散歩中に
カルガモがひどくざわつく声が聞こえるので
なんだろうと川を見たとたん、
オオタカがシャーっと舞い降りてきて
一羽のカルガモを足でムンズとつかみ、
あっという間に連れ去った。
わずか3秒くらいの出来事だった。
身体は小柄だったが、
ヒナではなくおとなのカモである。
このあたりのオオタカは
ハトやムクドリを常食としているが、
何が起こったのか?
あの時は常駐のカメラマンたちも大騒ぎで、
聞いてみたらカモを襲ったのなんて
初めて見たとのこと。
まさにラプトル(猛禽)!
もともと飼いならされて鷹狩りに
使われていたぐらいだから、
人間と相性がいいのだと思うが、
人慣れしてきたオオタカは今年は
どんな暮らしを見せてくれるのか、楽しみである。
まあ、クマ、イノシシ、サルなどと違って
安心して見ていられるから
こんなのんきなことが言えるのだけど。
神ってるアオダイショウ

川沿いの道で長さ1メートルのヘビに遭遇。
青みを帯びた銀色に輝くボディのアオダイショウ。
カメラ目線をキメてくれた。
なかなかいい面構えでしょ?
神々しくて思わず手を合わせてしまった。
今年も残すところあと3カ月。
大将、よろしくたのんます。
ナマケモノもよろしくたのんます。
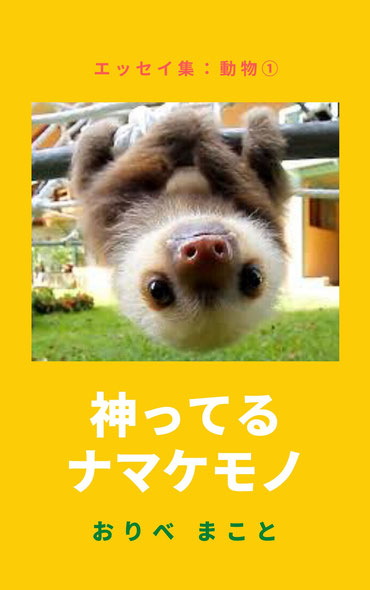
日本人にモテる“グロかわいい”ハンザキ
岡山県真庭市・湯原温泉郷の「はんざき祭り」は、
本日が本祭。
「ハンザキを喰った話」なんて本を書いていたのに、
こんなお祭りが60回も行なわれてるなんて、
ついこの間までちーとも知らなかった。
ちなみに本来は8月7日が前夜祭、8日が本祭。
今年は台風接近のリスクを避けて日程を変更した。
今年は無理だったが、いつか行きたい。
ハンザキ愛にあふれた湯原温泉郷の人たちのお話を
ぜひ聞いてみたいと思う。
じつは「ハンザキを喰った話」は、
岡山でなく他県のハンザキ生息地の人のお話を
モチーフに書いた。
どう見てもグロいとしか思えない地球最大の両棲類だが、
日本各地において、その“グロかわいさ”は
時代を超えた人気を獲得し、
歌に、キャラクターに、お土産物に、お祭りに
大活躍している。
まさに日本の誇り、日本の宝。
そしてどこかSDG'sのシンボルのようにさえ見え、
世界中から愛される勢いさえ感じられる。
これからの時代、ますます
ハンザキ、ハンザケ、オオサンショウウオに注目だ。

はんざき祭り開催につき、さらに延長
親子で読もう!
夏休み無料キャンペーン最終弾
ハンザキを喰った話
8月24日(木)15:59まで
オオサンショウウオに変態した100歳の発明家をめぐる怪異幻想譚。
カッパの正体を解明(?)した本

頭にお皿、背中に甲羅、口はくちばし状、手足に水かき、
からだは人間の子ども(幼児~小学校低学年)
くらいの大きさで、
皮膚がヌメヌメしていて体色は緑系。
いたずら好きで、キュウリが大好物。
過去100年くらいで、
日本人の間にそんなカッパのイメージが定着した。
地域によってまちまちだった呼び名も、
かの芥川龍之介が、死の間際、
そのものズバリ「河童」という小説を書いてから
統一された感じがする。
そのカッパは実在するのか否か?
その他、柳田国男の「遠野物語」をとっかかりに
東北の民話の世界を探検し、
登場する怪異・妖怪の類の秘密を解き明かそう
というのがこの本「荒俣宏妖怪探偵団 ニッポン見聞録」
の趣旨である。
おなじみ、この手の妖怪学・博物学の大家・
荒俣宏先生を中心に、
小説家・理学博士がチームを組んで、
東北各地の大学教授・学者、博物館などの研究員、
郷土研究家、お寺の住職などを訪ねて回る。
面白いのは、たとえばカッパに話を絞れば、
みんな、カッパの実在を肯定していること。
ただ、そのカッパとされる妖怪は、
“現代人の視点で見ると”、
どれも別の様々な生き物であるという点だ。
あるところではそれはウミガメだったり、
あるところではイモリ、あるところではカワウソ、
あるところではネコだったりする。
それら爬虫類・両棲類・鳥類・哺乳類にまでまたがる
多種多様な生き物が、
「カッパ」という妖怪・生き物に
ひとくくりにカテゴライズされていたのだ。
どういうことかというと、
人間は自分(あるいは自分を取り巻く社会)が持っている
知識・情報の埒外にあるものと遭遇したとき、
「わけのわからないもの」としておくことができず、
それを分類するために
特定のファイルみたいなものを必要とする。
その一つに「カッパ(地域によって呼び名は異なる)」と
題されたファイルがあり、
「これは何だ?わからん」と思ったものをみんな、
とりあえずそのカッパファイルの中に突っ込んでいたのだ。
だからそれぞれの動物の特徴・生態・イメージが、
そのファイルのなかで混ざり合い、繋がり合い、
時には化学変化を起こして、
カッパという妖怪の形になって
多くの人々の頭のなかに生息するようになり、
民間伝承として伝えられるようになった。
そしてまたその伝承・民話をもとにして
時代ごとに絵師などがカッパの姿を絵として描き上げた、
ということらしい。
僕たち現代社会で生きる人間は、
科学的に解明された知識・情報を
すでに頭のなかに仕入れてあるので、
これは犬とか、カエルとか、ウサギであると知っている。
だから、なんでカメやイモリやカワウソやネコを
カッパだなんて思ったんだろう、と不思議がるが、
それは逆で、カッパというファイルの中から
Aタイプが実はカメで、Bタイプがカワウソで、
Cタイプがネコだった・・と、
後で(だいたい明治以降~昭和初期の間に)
分類・整理されたのである。
言い換えれば、江戸時代以前の日本人にとって、
奇妙な野生動物は皆、UMA(未確認動物)であり、
ほんの150年ほど前まで日本の海も山も里もUMAで
溢れかえっていたのである。
この本ではカッパ以外にも
いろいろな妖怪・民俗学的伝承が紹介されているが、
そうした昔と今の人間の心の地図の違いについて
気付かせてくれることに重要な価値があると思う。
荒俣宏妖怪探偵団 ニッポン見聞録 東北編
著者:荒俣宏/荻野慎諧・峰守ひろかず
発行:学研プラス 2017年
カエルの幸福サラダ

先週だったと思うが、
スーパーや飲食チェーン店の野菜サラダに
カエルが混入していたニュースがあり、
そのせいかやたらとブログのアクセスが増えた。
そう言えば、カエル食とか、カエルのから揚げとか、
カエル女とか、カエル男とか、
カエル石とか、カエル君とか、
よくカエルのことを書いている。
カエルに魅入られる人は少なくない。
やはり地球に生きる生物としては、
人間よりはるかに大先輩であり、
学ぶべき点がいっぱいある。
そもそも子ども時代の生き方と
大人になってからの生き方が
まるっきり違っているのが面白い。
むかしのSF小説で
「両棲人間」というのを読んだことがあるが、
人間は心のどこかで両棲類に憧れているフシがある。
そう言えば、ウーパルーパやオオサンショウウオのことも
書いたことがある。
オオサンショウウオは小説まで書いてしまった。
このへんはみんな、むかしは食糧になっていたようだ。
カエルは最も身近な両棲類で、
日本人にとって大事なお米を育てる田んぼの
妖精みたいな存在である。
梅雨の季節、カエルに会えた人はラッキーかも。
野菜サラダのカエルに当たっちゃった人も、
あまり怒らずに「幸福ガエル」に当たったと思って
ケロッとやりすごそう。
カエルサラダのおかげでこの夏はいいことあるかもよ。
チビガモ続編
善福寺川の川べりでアジサイが色づいた。
早や季節は夏。
写真に撮れなかったが、夕方、ジョギングに出たら
川には先日、歩道から3メートル下の川岸へ
仰天ダイブを見せたチビガモたちが元気に泳いでいた。
カラスも飛び回っているし、
この間の雨で増水もしていたし、
食われるか、流されるかして
何羽か減っているだろうと思って数えてみたら・・・
あれっ?9羽もいる。
たしか前見た時は8羽だったような。
いつの間に1羽増えたのか???
いずれにしてもみんな元気で生きていて
すごいスピードで泳ぎまくって遊んでいる。
生きているのが面白くてしかたない。
そんなチビガモたちにお散歩の人たち、
みんな感激。
写真は13日前の生まれたてのチビたち。
(やっぱりこの時は8きょうだい)
今はちょっと大きくなって、
顔も体もヒヨコ色の部分が減って、
全体にカモ色(茶色)っぽくなってきた。
小学生レベルかな。
もうちょと大きくなれば、
カラスも簡単に手が出せないぞ。
がんばれチビ。
チビガモ8きょうだいの冒険
善福寺川添いの散歩道でカルガモ親子に遭遇。
いままで3メートル下の川の中や中州、
岸でしか見たことがなかった。
こんな間近で見たのは初めて。
どうやらこのお母さん、
このあたりの草むらで卵を産んで孵したらしい。
散歩の犬などがよく草むらをかき分けて
クンクンやったりしているのに
よくぞ無事に生まれたものだ。
ひなは8ぴき。
でも、こんなところでのんびりしていたら、
たちどころにカラスや蛇のごはんになってしまう。
お母さんは一生懸命川に降りられる場所を探す。
子ガモたちはピイピイ言いながら、
押し合いへし合い、必死になってついていく。
やっと橋のたもとで降りられそうな場所を見つけた。
母はダイブ。
母はいい。何と言っても大人だし、飛べるし。
「早くみんな来なさい!」
グワグワグワと下からがなり立てる。
「ひえー、お母ちゃん、そんなこと言ったって、
こわいよこわいよ」ピーピーピー。
「はよ来い、ボケカス!」グワグワグワ―!
いやいや、人間だって飛び降りるのはこわい3メートル。
子ガモの体に換算したら、こりゃドバイの超高層ビルから
地上まで飛び降りるのに匹敵するんじゃないのか?
それでも行かなくては、この先、生きることはできない。
あっという間にカラスのごはんだ。
えいっ!
勇気ある一匹がダイブ!
もちろん飛べないので、そのまま落っこちる。
斜面をひたすら転げ落ちる。
でも大丈夫だ、生きている。
おれたちは死なないぜ、きょうだい!
ピーピー言いながら、
みんな「ナムアミダブツ」と唱えつつ、
つぎつぎとダイブ。
護岸工事がされたコンクリの岸に
たたきつけられてもなんのその。
それ行けとばかりに川に飛び込みむと
ぷかぷか浮かんでいる。
さすがカモ!
みんなよくがんばった。
きみらの勇気と冒険に大感動だ。
(この間、つれてきた義母はほったらかし)
しかし油断大敵。
ごちそうを前によだれをたらしながら
カラスが近づいてくる。
必至に交戦し、追い払うお母さん。
しかし、シングルマザー1羽で
チビガモ8兄弟を守るのは至難の業だ。
一昨年はオスかメスかわからないけど、
複数のおとなが協力してヒナを守ったおかげで、
抜群に生存率が高かったという。
みんなで子育てに協力してチビたちを守ってくれ!
あなたのワンちゃんが今、ウンコしましたよ!

「あなたのワンちゃんが今、ウンコしましたよ!」
とは言えなかった。
川沿いの遊歩道にワンちゃんをお散歩に連れて来た
おしゃれなヤングマダムは、
旦那か子どもかお友だちかわからないけど、
掛かってきた電話に夢中。
その足元でワンちゃん(小型犬)が
自分に注意が払われていないのを
これ幸いと思ったのかどうか、
よっしゃと言う感じで地面にお尻を落とした。
ときは春うらら。
舗装された遊歩道のわきの道には
みどりの草が萌え始めている。
その萌えた草の上にお尻を落として、
うーんとふんばってるのだ。
あの格好は、もしや!
川の向こうからその瞬間を目撃した僕は
思わず足をとめて見た。
遠目からも二本の後ろ足の筋肉に力が入り、
お尻の真ん中あたりが
小刻みにピクピク震えているがわかる。
出る。
僕がそう思ったとたん、
ワンちゃんのお尻から
むにゅっと茶色の物体が出てきたのが目に飛び込んだ。
しかし、飼い主さんは電話で喋っていて、
そんなことはつゆとも知らない。
ワンちゃんは「あー、すっきりした」と満足気。
からだが軽くなったのか、
気持ちよさそうにピョンピョン跳ね始める。
飼い主さんはちらりと
そんな彼(彼女かもしれない)に目をやったが、
その下にある落とし物には
まったく気が付かない。
電話はまだ終わらず、
何やら笑って喋りながら、
そのままハーネスのリードを引っ張って歩き出した。
僕の口からは思わず、タイトルのセリフが喉まで出かかった。
「あなたのワンちゃんが今・・・」
が、なにせ川を挟んだ向こう側で5,6mは離れている。
周りに聴こえるような大声で叫ばなくてはならない。
それを聞いた彼女の心に巻き起こる嵐のことをを想像すると、
とてもそんな勇気は出なかった。
そよ風が吹くおだやかな春の午後。
あの草の上の犬のウンコが、
お散歩やジョギング中の誰かに踏まれることなく、
無事、土に還ってくれるのを願うばかりである。
おりべまこと動物小説+エッセイ

いたちのいのち
小学4年生の女の子カナコとペットのフェレット「イタチ」とのおかしてくちょっと切ない友情物語。フェレットの飼い主さんはもちろん、ワンちゃん・ネコちゃんの飼い主さんにも読んでほしい動物ファンタジー。

神ってるナマケモノ
イヌ、ネコ、カエル、ウーパールーパー、ナマケモノなど、楽しい動物、怖い動物、いろいろな動物と人間との関係について語る面白動物エッセイ集。
ペットも参列できるお葬式
千歳烏山にあるJA東京中央セレモニーセンターでは、
今年から「ペットに見送られる、私の葬儀」
というプランを始めた。
その名の通り、お葬式にペットも参列し、
亡くなった飼い主さんをお見送りする、というものだ。
このプランは、世田谷区、杉並区、大田区にある
同社の3つの専用ホールでできる。
今までもこっそりお通夜などに
キャリーケースに入れた小型犬を連れてきて、
故人とお別れをさせていた家族はいるようだが、
公にこうしたお葬式ができます、と打ち出したのは、
おそらく日本で初めてではないだろうか?
というわけで月刊終活の取材で千歳烏山まで行ってきた。
こうしたサービスを始めた下地として、
この会社ではガチでペット葬に力を入れており、
敷地内に専用のお別れ室や専用の火葬車、
霊柩車も揃えてる。
そして、安心のキーポイントとして、
ペットシッターというスペシャリストも控えている。
供養グッズもおしゃれでかわいい。
ペットのお葬式では、
立場や人間関係などに気を遣うことなく、
純粋に悲しみの感情を表出できるので、
なりふり構わず号泣する人も多いという。
取材でプラン開発の経緯を聴くと、
そうした人たちの心情を日頃から肌で感じており、
インフラも整っているので、
始めるのに大きな葛藤はなかったという。
ペットは永遠の子供。
自分が可愛がった子に最期を看取ってもらいたい
という人は多く、ニーズは高いだろう。
ペットー主にイヌだが―は、人の死がわかるのか?
という疑問もある。
でも、散歩のときに逢う犬たちを見ていると、
たぶんわかるのではないかという気がする。
人と一緒に暮らしている犬は、
もしかしたら幼い人間の子供より
死とか別れの意味はよく理解できる。
取材してみて思ったのは、
これ以降、死という事象の前では
人もペットも同等になるのではないかということ。
同じ命の重み――というと、反感を買うかもしれないが、
おそらくペットに心を寄せて暮らしている人にとっては、
心情的にそうなるのは自然なことだと思う。
もちろん、社会的な意味合いと重みはまったく違うけど、
いろいろ人間関係に倦んで、
ペットのほうに心を傾けたり、思い出を育む人が
これからどんどん増えていくのかもしれない。
ウルフとチワワと犬の本能の発散について
川沿いを散歩していると、いろいろな犬に逢う。
あくまで印象だが、うちの近所では柴犬、
チワワ、トイプードル、ポメラニアンが
人気トップ4だ。
それぞれの犬の名前はわからないので、
シバくん、チワちゃん、プーちゃん、ポメちゃんというと、
みんなどうも自分のことだと分かるらしく、
しっぽを振って寄ってくる子が多い。
かつて飼犬人気ナンバーワンだった
ミニチュアダックスフントは、
めっきり数が減ったように思う。
短足胴長の体型が災いして、
体を壊しやすいと聞いたことがあるが、
そのせいなのだろうか?
代わって目立つのがジャックラッセルテリアなどの
テリア種。
これら犬種の名前がジャック以外、よくわからない。
でも、ジャックは好きなので、
「おっ、ジャックラッセルテリアくんだ」と
フルネームで呟くと、なぜか本人(本犬?)より
飼い主さんが喜んでくれる。
大型犬も結構いて、やっぱりゴールデンレトリバーと
ラブラドールレトリバーが気があるようだ。
僕もゴールデンくんとラブちゃんは大好きだ。
小熊くらいありそうなバーニーズマウンテンとか、
シェパードやサモエドもいる。
サモエドくんはポメラニアンのご先祖らしく、
たまにポメちゃんだと思って飼っていたら、
みるみる大きくなってサモエドになることがあるらしい。
サモエドくんは図体はデカいが、めちゃくちゃ可愛い。
さて、そんな中で最近、オオカミみたいな犬に出逢った。
その名も「ウルフドッグ」というらしい。
シベリアンハスキーの親戚かなと思ったら、
そういうわけでもないらしく、
ハスキーよりもオオカミの血が濃いらしい。
「おっ、カッコいい」というと、
「え、おれのこと?」と聞き耳を立てて止まり、
「ねえねえ、もっとほめて」と寄ってくる。
精悍な顔をしている割になかなかかわいいやつなのだ。
それにしても、こんな怖そうなデカいイヌと
チワワみたいなおチビが同じ犬とは・・・。
犬の遺伝子というのは、いったいどうなっているのか?
そういえば広場で「ピー」とか「キュー」という
音の出るボールやオモチャで遊んでいる犬をよく見かける。
あの音の出るおもちゃは好奇心を刺激されて犬が喜ぶ――
という説明がされていることが多い。
好奇心というのは、
そう言えば納得するだろうと言われているみたいで、
なんだか腑に落ちない。
なぜ好奇心を刺激されるのか?
そう思い巡らせて森の道を歩いていたら
思い至ったところがある。
あの音は、オオカミが狩りをしたときに
獲物が出す断末魔の声なのではないか?
それで本能が刺激されて犬が喜ぶのではないだろうか?
残酷な話だが、今はかわいい犬たちも、
もとは野生の肉食獣である。
ああいうオモチャで適度に本能のはけ口を作ってやると、
万一、人間に噛みつく事故をが起るのを
防ぐ効果があるのではないだろうか?
――と勝手に想像を巡らせてみたが、どうなのだろう?
誰かワンちゃんの飼い主で、
知っている人がいたら教えてください。
こんど「チワワ、オオカミと旅に出る」という
動物物語を書こうと思っている。
地球の歩き方 関東版ねこの御朱印&お守りめぐり 週末開運にゃんさんぽ
今年、2022年は寅年。
来年、2023年はうさぎ年。
というわけで、トラの親戚で、
ウサギのようにかわいいネコはいかが?
というこじつけで、ネコ寺めぐりはいかが?
「地球の歩き方」が、御朱印シリーズとして
『関東版ねこの御朱印&お守りめぐり
週末開運にゃんさんぽ』を発売している。
関東1都6県の「ねこにゆかりのある神社とお寺」を
集めたガイドブックで、
有名な「猫寺」下野厄除大師や長福寺をはじめ、
「招き猫発祥」の豪徳寺や今戸神社など、72寺社を紹介。
御利益がすごいとうネコの御朱印や
かわいいネコのお守りなどの授与品を多数掲載し、
話題の寺社やねこの聖地をめぐる週末プランは、
東京、栃木、群馬の3コースを案内している。
参拝マナーや仏像の鑑賞ポイントなどの
基本情報や解説も充実。
と、お寺紹介の一環として、
「月刊終活12月号」でご紹介させていただいた
「地球の歩き方」。
おなじみ、海外旅行のガイドブックとして、
国内最大の売り上げを誇っていた。
僕もその昔、世界をほっつき歩いていた時に
ずいぶんお世話になったものが、
こんな大変貌を遂げていて、びっくり。
そうなのだ。
旅行業界とともに、コロナ禍で大打撃を受け、
存亡の危機に立たされていたのだ。
しかし、その大ピンチをチャンスに変えた。
2020年東京五輪に合わせて国内ガイドにシフトした後は、
都心や近場を「旅する」ガイドブックに変身。
その一方で、40年以上の取材の成果を
グルメや動物など、多彩なテーマで再編集した
「図鑑」シリーズを発刊し、大ヒット。
さらにオカルト・ミステリー雑誌「ムー」とのコラボで、
『地球の歩き方ムー』も刊行。
ネス湖、ストーンヘンジ、モアイ像、雪男出現地など、
“世界の不思議”を「旅行ガイド」の視点で特集して
ヒットを放っているという。
あっぱれ!
やっと旅行需要が戻って来たので、
これからはまた、
もとの形に戻るのかどうかはわからないが、
ユニーク企画は引き続き、どんどんやってほしい。
それにしても需要が戻ってきたとはいえ、
円安のせいもあって海外はべらぼうに高い。
年末年始は海外へ昨年の7倍の客が出かける予定だ、
と、今日のニュースで言っていたが、
結構なお金持ちしかいけないのでがないか。
このガイドブック片手に
年末年始はかわいく神社めぐりやお寺めぐりで
ネコちゃんと遊んでみてはどうかニャー。
愛しきブタと「ねほりんぱほりん」のFIRE

NHK・Eテレの「ねほりんぱほりん」のファンなので、
先週末から新シリーズが始まってうれしい。
見たことある人はご存じだが、
これはモグラの人形に扮した山里亮太とYouが
インタビュアーになって、
ブタの人形に扮したゲストに根掘り葉掘り
事情を聴いていく、という番組である。
ゲストは皆、一般人で、
いろいろ話題になる社会現象の当事者。
普段は聞けないその裏事情を容赦なく暴いていく。
てか、本人もぶっちゃけたいから出てくるわけだが。
顔出しはNG。
音声ももちろん変えてある。
そこで人形に扮するわけだが、そのへんの手間暇かけた
丁寧な作り方が、
雑なのが多い今どきのテレビ番組の中でひときわ光る。
ところでゲストの人形はなぜブタなのか?
番組側の説明によると「タブー」をひっくり返した
言葉遊びの発想から生まれたものらしい。
しかし見ていると、
これはやっぱりイヌでもネコでもサルでもダメ。
絶対ブタが大正解と思えてくる。
欲の深くて、業が深くて、ずるくて、煩悩まみれ。
なのに、愛らしく、切なく、泣けて笑えて
ヒューマンタッチ。
その人間らしさを表現できる動物は
ブタ以外にあり得ない気がする。
先日、ムスリム(イスラム教徒)にとって、
なぜブタはタブーなのか、という理由として
「豚は余りに人間に似すぎていて人肉食に通じるから」
という珍説を唱えてみた。
皮膚や臓器の移植事例など、科学的にもそうだが、
イメージとしても、ブタはサルよりも人間に近い。
実際、ブタはその豚生(?)の中で
かなり人間に近い喜怒哀楽の感情を体験するようだ。
新シーズン初回の「ねほりんぱほりん」は
Lean FIRE(リーン・ファイア)の20代・30代がゲスト。
FIREは早期退職してリッチに遊んで暮らす人たちという
イメージだったが、
リーン・ファイアは、
働かず資産のみで暮らすのは同じだが、
最低限の暮らしで資産を作り、
これまたその最低限で暮らす。
「ミニマリスト」と言えば聞こえはいいが、
一言で言えば、胸が切なくなるほどの貧乏暮らし。
そこまでしてやめたかったというのは、
よほどひどいブラック企業に勤めてしまい、
会社勤めそのものに絶望感を
抱いてしまったのだなと思った。
そこもまた家畜(社畜)であるブタの哀愁を感じさせる。
社畜を脱するためにFIREしたお二人。
でも、人生は長い。
会社も辛かったようだが、
そのFIRE、けっこう辛いのではないか。
よけいなお世話かも知れないが、
まだ若いんだし、起業するなり、
バイトでもボランティアでもするなりして、
どこかで働く喜び、仕事する楽しさを見出してほしい。
そう思ったぞブヒ。
ヒトとブタは神目線ではブラザーなのか?

マイナビ農業の仕事で、
ハラールに関する8千字の記事を書いた。
「ハラール」とは、ムスリム(イスラム教徒)にとって
「許されたもの」。
これに対して禁じられているものは「ハラム」という。
これらは彼らの聖典であるコーランに記されている。
このハラムで有名なのが、豚肉とアルコールだ。
ロンドンのレストランで働いていたとき、
職場の仲間にエジプト人のムスリムがいて、
彼は酒が好きだった。
さすがにそんなにガバガバとは飲まなかったが、
チビっと飲んでは酔っぱらっていた。
地元の国ではどうだか知らないが、
外国に在住しているムスリムの間では、
アルコールの禁忌については割と甘いようである。
けれども豚はダメだ。
彼もけっして豚肉は食べず、
賄いでトンカツやハムカツが出てくると、
オー!と、天を仰いで嘆いていた。
それにしても疑問はやはり、
なぜイスラム教は豚を禁忌としたかである。
「豚は不浄の動物だから」というのは
どうも説得力がない。
豚は本来、きれい好きな動物で、
豚小屋が汚いというイメージは、
むしろ飼う人間の側の問題・責任である。
それよりも有力な説は、イスラム教の創始者とされる
預言者ムハンマドが生きていた時代(7世紀はじめ)、
中東地域(現在のサウジアラビアあたり)で
豚肉が原因となって疫病が流行したということ。
豚は雑食性なので、ヒツジや牛などの草食動物より
肉が腐りやすい。
衛生管理がなっていなかった当時としては、
十分あり得る話である。
もちろんヒツジだって牛だって鶏だって
冷蔵しとかなきゃ腐るのだが、
たまたまムハンマドが豚肉由来の疫病に
出逢ってしまったのだろう。
歴史は僕たちが思っている以上に、
必然よりも偶然の力が大きい。
なんとなく納得してしまう説だが、それでも釈然としない。
仏教やキリスト教の地域だって同様のことはあったはず。
これだけ世界に広がった宗教の創始者だから、
ムハンマドの信念はもっと複雑で深いはずだ。
彼は直観で知っていたからではないかという気がする。
「豚は人間に酷似してる」
つまり豚を食べることは、人肉食に通じる。
そうイメージして恐怖し、ブタにフタをしたのである。
実際、豚の皮膚や臓器は、類人猿よりも人間に近く、
代替が可能だという。
皮膚や臓器の移植手術は
190年代から試行検討されており、
つい最近、ついに実際に行われた。
今年2月には
「世界初、ブタからヒトへの心臓移植の注目点は」
という医学記事も発表されている。
(以下抜粋)
2021年1月7日、米メリーランド大学の医療チームにより、
世界で初めてヒトへの遺伝子改変ブタの心臓を用いた
異種移植が実施された。同大学の公式サイトによると、
2月9日現在、レシピエントの57歳男性に移植されたブタの心臓は
問題なく機能しており、
24時間体制のケアを受けている様子が伝えられている。
https://www.m3.com/clinical/open/news/1018905
預言者ムハンマドは、イエス・キリストと違って
神の子として生まれてきたわけではない。
彼は商人として暮らしていた40歳のときに突然、
天使ガブリエルによる啓示を受け、
預言者として神からのメッセージを
人々へ伝えていくことを決意したという。
彼はその中で人間と豚の近親関係を感知し、
それを人々に「豚肉食禁止」と言う形で説いた。
それが人々の心の奥底にあった、
豚に対する近親相関的感情に響いたのではないだろうか?
上記のような移植の話は、
到底、ムスリムの人々は受け入れられないだろうが、
医学的・科学的に興味を抱く人は少なくないはずだ。
あなたは自分が、あるいは家族が、
命を救うためにこの臓器移植の提案をされたら、
どうしますか?
今回の仕事は、ハラールについて、イスラム教について、
豚についての神秘を感じた面白い仕事だった。
この件についてはまたおいおい。
カメとの遭遇

いつもの散歩で今日はカメに遭遇。
川沿いのから家に戻る道は、ちょっとした坂になっている。
上り出すと、向こうから変な歩き方をするイヌが
坂を下りて来るのが見える。
どこか体が悪いんだろうかと思ったが、
よく見たらカメだった。
甲羅の長さが40センチくらいあるやつなので、
遠目では体の丸っこい小型犬に見えたのである。
こんなところをノシノシ歩いているカメは、
もちろんノラガメではない。
どうやらその後についてきた親子(母と娘)が
飼い主らしい。
聞いてみたら、親戚のペットのヒョウモンリクガメを
1週間預かってるのだという。
僕に話しかけられ、足を止められた臨時飼い主を尻目に、
カメは自分のペースでノシノシ、
ひたすらまっすぐ川に向かって歩いていく。
カメをトロいとかノロマだとか、バカにしてはいけない。
4本の逞しい足を交互に繰り出して、
ぐんぐん前に進んでいく歩みは実に力強く、
年寄りで足腰の弱ったイヌなどよりもよほど速い。
顔つきも精悍そのもの。
これならのんびり昼寝していたウサギも負かせる。
あっという間に10メートル以上進んでしまったので、
娘(小4くらい)がささっと捕まえにいった。
少女とカメのコンビは、
なんとなくミヒャエル・エンデのファンタジー小説
「モモ」に出てくるモモとカシオペアを思い出させる。
ひたすら進んでいくカメは、川まで辿り着いたら
娘を連れてタイムトラベルするかもしれない。
臨時飼い主のお母さんの話によると、
なかなか骨があるというか、肝の坐ったカメで、
イヌなどと逢っても泰然としているという。
逆にイヌの方がビビッて尻尾を巻いてしまうらしい。
その行く先に何が待っているのか面白そうなので、
ぜひ一緒にフォローしたかったのだが、
義母がいっしょだったし、
パラパラ雨が降り始めていたので帰らなくてならず断念。
また、あのカメに遇えるだろうか?
おりべまこと電子書籍 夏休み企画2022
真夏の世の夢 16日間連続無料キャンペーン予告
●第1世:短編小説特集
8月5日(金)16:00~8日(月)15:59
・魚のいない水族館 http://www.amazon.co.jp/dp/B08473JL9F
・茶トラのネコマタと金の林檎 http://www.amazon.com/dp/B084HJW6PG
・ざしきわらしに勇気の歌を http://www.amazon.com/dp/B08K9BRPY6
●第2世:長編小説特集
8月9日(火)16:00~12日(金)15:59
・オナラよ永遠に http://www.amazon.co.jp/dp/B085BZF8VZ
・いたちのいのち http://www.amazon.co.jp/dp/B08P8WSRVB
・ちち、ちぢむ http://www.amazon.com/dp/B09WNC76JP
●第3世:エッセイ集:昭和/子ども/動物
8月13日(土)16:00~16日(火)15:59
・昭和96年の思い出ピクニック http://www.amazon.co.jp/dp/B08WR79ZCR
・子ども時間の深呼吸 https://www.amazon.com/dp/B0881V8QW2
・神ってるナマケモノ http://www.amazon.co.jp/dp/B08BJRT873
●第4世:エッセイ集:生きる
8月17日(水)16:00~20日(土)15:59
・酒タバコやめて100まで生きたバカ http://www.amazon.com/dp/B09MDX2J45
・いつもちょっとクレイジーでいるためのスキル https://amazon.co.jp/dp/B09QQ823C9
・銀河連邦と交信中なう http://www.amazon.co.jp/dp/B09Z6YH6GH
さらばノラネコきょうだい
「あの子たち、保護猫ということになって
先週、埼玉の川越の里親さんのところに行っちゃったのよ」
暑さがやっとやわらいだ夕方、
義母を連れて、いつもの川沿いの道を散歩していたら、
ネコ使いのおばさんがそう言って声をかけてきた。
あの子たちというのは、このあたりのネコ林や
ベンチのあるネコ庭にゴロゴロしていた
クロネコと白黒ブチのことである。
ぼくたちはクロとか、ブチとか呼んでいたが、
ネコ使いのおばさんは「松ちゃん」「竹ちゃん」と
名まえをつけていた。
二匹はきょうだいである。
とてもフレンドリーで、
この近くに引っ越してみてから
僕もずいぶん写真を撮らせてもらった。
野良猫として川のほとりに
骨をうずめるのかと思っていたら、
詳しい経緯はわからないが、意外な展開が待っていた。
そう言えば最近見かけていなかったが、
暑いのでどっかに引っ込んでいて
夜、行動しているのかと思っていた。
二匹ともノラとは思えないくらい、人懐っこく、
散歩の人たちに可愛がられていたので、
そうしたキャラが幸いしたのか、
すっかりおとなになっていても
引き取ってくれる里親が現れ、
めだたしめでたしというところか。
よくごはんをやっていた
ネコ使いのおばさんは仲介役だったのか、
川越からいろいろ情報が入ってくるようで、
わざわざスマホを開いて僕と義母に、
二匹の現在の暮らしぶりの写真や動画などを見せてくれた。
ちょっと寂しがっているのかもしれない。
それにしてもクロ(松ちゃん)のほうは
よくネコ林のあたりで小鳥を狙ったり、
川岸に降りて行ってカルガモの親子を狙ったりしていたが
そんなワイルドなご趣味も卒業ということなのだろうか。
新しい暮らしになって、野生の血は疼かないのだろうかと
少々気にはなるが、住めば都という言葉もある。
かなり環境に対する順応性が高いようなので、
川越で幸福にくらしてほしいと思う。

エッセイ集:音楽
神ってるナマケモノ
AmazonKindleより好評発売中
¥300
烏山寺町のネコ寺
世田谷区の千歳烏山に近い烏山寺町でお寺の取材。
この地域には大正末期の関東大震災のとき、
浅草や築地あたりで被災した26ヵ寺が
こぞって引っ越してきて集まっている。
東京西部でこれだけのお寺が集まっているところは、
ここだけ。
寺町ができる前はもちろん一面の農地で、
このあたりから1キロほど先の千歳烏山駅まで
ズドーンと見渡せたそうだ。
訪れたのはその中の一つ、
首都高速からすぐのところにある乗満寺。
このお寺の境内には20歳になるネコがいて、
めっちゃ人なつっこい。
スマホを向けたら嬉しがってニャーニャー寄ってくる。
近すぎてちゃんと撮れないだけどにゃあ。
奥さん(坊守さん)がネコ好きらしく、
この長老ネコの「みいちゃん♂」を筆頭に
5匹のネコが暮らしており、
時々、というか、けっこう頻繁に
ノラネコも何匹か遊びに来て、
勝手にめしを分捕っていくらしい。
月に1回「ねこ茶房」をやっていて、
住職の話とセットでお寺のネコと遊べる日を設けている。
普段の日でも、運が良ければ
境内でウロウロしているみいちゃんに出逢えるかもニャー。

動物をめぐる面白エッセイ集
神ってるナマケモノ
http://www.amazon.co.jp/dp/B08BJRT873
「世界カメの日」に考える なぜ浦島太郎はリスクを負ってカメを助けたのか?

「浦島太郎」のお話の始まりは、
太郎が浜辺でカメが子どもたちに
いじめられているのを助けるところから始まる。
勝手に解釈すると、イジメてたわけではなくて
捕まえて殺して食おうとしていたのだと思う。
昔はウミガメを捕まえて食うことなんて
海辺の村では日常茶飯事で、
この子どもたちも親たちから
「今夜のめしはカメ鍋にするから捕まえてこい」と
指図されたのだろう。
ひと家庭では食べきれないので、
村でパーティでもやる予定だったのかも知れない。
このカメは産卵するため浜辺に上がってきたところを
狙われたのだ。
これでは逃げようがない。
海辺の村人にとっては年に数少ない、
栄養満点のごちそうにありつく
絶好のチャンスだったのに違いない。
それを邪魔した浦島太郎は、子どもらのみならず、
ほとんど村全体を敵に回したと言っていいだろう。
そもそも彼はこの村の人間ではないのではないかと思える。
カメを助けるから動物愛護の精神に富んだ
いい人に思えるが、それは現代人の感覚で、
こんなことをしたら、子どもたちが親に言いつけて、
あとから村じゅうの人間から
袋叩きに逢うことは目に見えている。
結果的に彼はカメに竜宮城に連れて行ってもらい、
乙姫様と結婚して夢のような暮らしを送るので、
これだけの危険を冒したかいがあったということになる。
まさしくハイリスク・ハイリターン。
投資は大成功だ。
助けられるカメは、
現在では竜宮の使者ということになっているが、
一説では乙姫様が化けていたというものもある。
産卵しに上がってきたわけだからメス。
辻褄があっている。
ちなみにオスのウミガメが陸上に上がってくることは
ほとんどないようだ。
よく考えると、浦島太郎と乙姫様は
かなりミステリアスなキャラクターである。
夫婦だったのか?
愛人関係だったのか?
どうしてあっさり別れたのか?
玉手箱を持たせたのは乙姫の復讐だったのか?
太郎はじいさんになってどこへ行ったのか?
海が舞台ということもあり、
この物語には想像力を刺激される。
もしかしたら浦島太郎は
ちょっと過剰な動物愛護の精神を持った
現代のアメリカ人がタイムスリップしてきた
お話なのかもしれない。
今日、5月23日は「世界カメの日」。
カメに対する知識と敬意を高め、
カメの生存と繁栄のための
人類の行動を促すことを目的として、
2000年に米国カメ保護会によって制定された
記念日とのこと。
人新世(アントロポセン)という新たな地質学的時代、
カレンダーにはいつの間にか、
いろいろな動物の記念日が増えている。
「ナマケモノの日」とか
「ヤマアラシの日」なんてのもある。
急激に地球環境を変化さえてきた人類が、
単に保護するだけでなく、動物の声を聞き、
そこから新たな生き方を学ぼうとしているようにも思える。

インターペットで真珠葬大人気
少し先の話だが、月刊仏事で
ペット葬特集をやるというので、
東京ビッグサイトで開かれている
「インターペット~人とペットの豊かな暮らしフェア~」
を見に行った。
以前もご紹介した「真珠葬」が出展している。
亡くなったペットの遺骨を、
長崎の海のアコヤ貝に入れて
1年かけて真珠に変えて記念品にするという
ユニークなプロジェクト。
ペットの飼い主さんは当然、
「うちの子」の看取りまでする義務がある。
飼う以上はこうした葬儀・供養のことも
ちゃんと考えておいたほうがいい。
ブースには撮影コーナーを設けており、
写真を撮ってもらって啓蒙活動にするという。
これはなかなかいいアイデアだ。
海のデザインが素敵で長蛇の列ができていた。
全体の傾向として、ペットも高齢化しているせいか、
健康とか介護とかに関連した
商品・サービスが目立って見えた。
それにしてもこの展示会は
ペットを連れた人がぞろぞろいっぱいいて壮観。
ほとんどイヌばかりで、
普段、近所では見なれないデカいやつ、
高級犬(なのだろう、きっと)も大勢いて大さわぎ。
食べ物系のブースのあたりが一番混んでいたが、
興奮してケンカが起きないのだろうか、
とちょっと心配になった。
ネコはこういう所は苦手らしく、
いてもケージの中に入っておとなしくしているので
あまり目にしなかった。
真珠葬のスタッフに話だと、
昨日はタカやフクロウを連れてきている人もいたとか。
初めてきたが、
こんなアニマルな展示会を毎年やっているんだ、
そしてこんないっぱいいろんな人が
いろんなペットを飼っているんだ、とオドロキ。
ちょっとしたカルチャーショックである。

おとなも楽しい少年少女小説
ちち、ちぢむ
お父さんが「ちっちゃいおじさん」に!
役立たずの男たちが縮んでしまう怪現象は地球の意志なのか?アベコベ親子の奇々怪々でユーモラスな物語。
新発売&新年度無料キャンペーン
4月3日(日)16:59まで続行中!
ニャンとかもっと稼がニャいと
来月早々、青色申告に行くので
今日は収支の計算に専念。
「めんどくせー」とブー垂れている人も多いが、
僕は年に1回、こういう作業をするのは嫌いではない。
めっちゃ儲けてる人、毎日のように出し入れがある人、
時間の無駄だと思う人は、税理士に任せればいいと思うが、
僕はスモールビジネスなので、
自分で心を込めて?計算に取り組む。
するとだんだん脳からアドレナリンが出てきて、
数字の「ゾーン」に入っていく。
領収書の1枚1枚、
数字の一つ一つにストーリーを感じられる。
ああ、取材のためにこんなものを買ったなぁとか、
あそこにいって取材したなぁとか、
時間がなくてタクシーに乗ったなぁとか、
けっこう雨が降ってたとか、クソ暑かったとか、
帰りは夕焼けがきれいだったなとか、
いろいろなシーンを思い浮かべられる。
スマホやパソコン、手帳や領収書をにらみながら、
昨年1年を振り返って、笑ったり嘆いたり
舌打ちしたりできる醍醐味がある。そして、
よし、今年はもっとがんばろうと改めて思えるのだ。
大きく変わったのは、
一昨年から取材も打ち合わせもリモートが増えたので
交通費が激減したこと。
収入はむしろ増えたので、ぶっちゃけ稼いでいる。
一昨年の申告時(つまり2019年の収支)が
一番ひどかったので、
まぁまぁのところに戻ってきたのかなという感じ。
たぶん世の中の雰囲気からすると、オミクロンの後、
よほど殺人的な変異株が出てこない限り、
コロナは終息——というか、
経済優先のために強制終了ということになるだろう。
だから今年の後半からは社会全体がリハビリ状態になり、
景気は上向くと思う。
でも、なんか思ってもいない
社会的後遺症も出てきそうで、ちょっと怖い。
てなわけで2月22日、
222(ニャンニャンニャン)の日だそうなので、
商売繁盛・先客万来を願って豪徳寺の招き猫をアップ。
このお寺には生きた招き猫もニャンニャンしてます。
あなたのところにも、僕のところにも、
キャット良いお仕事がたくさん
にゃんころりんと転がり込みますように。
高円寺・猫の額で麻乃真純さんの作品を見る
電子書籍の表紙絵を描いてもらっている
漫画家・イラストレーターの麻乃真純さんが出展している
グループ展「春待祭」を覗きに行く。
高円寺北口にあるギャラリー「猫の額」は、
その名の通り、猫の額ほどの小さなスペースに
猫雑貨・猫アートがぎゅうぎゅうに詰め込まれている。
麻乃さんの絵はなんだか年を追うごとに
だんだんファンタジックになっている。
可愛がっていた犬や猫を看取るごとに
動物が妖精化していく。
僕も仕事でペットの葬儀や供養グッズのことを
書くことがあるが、
どうも動物の死は、人の死と違って
何かそうした異化作用を脳に及ぼすのかもしれない。
会期は終わりに近く、麻乃さんの絵は
ほとんど買い手がついていた。
猫好きの人は、高円寺方面に用事があったら
「猫の額」に行ってみてください。
「アトリエあさの」もよろしく。
猫の額 http://www6.speednet.ne.jp/nekojarasi/
アトリエあさの http://nazuna.jp/purofiru.html
そのワンちゃん・ネコちゃんの動画投稿は虐待ではないですか?

動物(ペット)虐待のニュースをしばしば耳にするが、
知らないうちに虐待しているということはないだろうか?
テレビで毎日、ネットにUPされている
ペットの動画をよく見る。
たしかに可愛いし、面白いし、こころ癒される。
ただし、時々、おかしな歩き方・おかしな動作をしている
イヌやネコを目にすることがある。
投稿主(おそらくイコール飼い主)は、
「うちの子、面白いでしょ」というつもりで
投稿しているのだと思うが、
どこか体が悪いために
変な歩き方・変な動作になっているのでは?
と感じることがあるのだ。
人間だって腰が痛かったり、脚が悪かったり、
背中がおかしかったりすると、
歩き方や恰好が変になってしまう。
イヌやネコは言葉が話せないので、
そんなことは訴えられない。
おかしな歩き方や変な動作をしている場合は、
飼い主さんがおかしいなと気づいて、
まず獣医さんにどこか病気やけががないか
診てもらうべきではないだろうか。
ネットやテレビで観ている人は「わはは」と
笑っているしかないが、
飼い主さんは言葉の話せない
ワンちゃん・ネコちゃんを気遣う義務がある。
それをしないで「みてみて、うちの子、おもしろいよ」と、
ウケを狙って投稿するのは動物虐待になるのでは、と思う。
認知症の義母と散歩中のワンちゃんと演じるシュールな野外劇についての断章
人間というのはとても複雑で面白い。
義母といると良い勉強になる。
基本的にこの人はあんまり生き物が好きではない。
ところが、なぜかそれを認めたがらない傾向があり、
時々、自分が飼っていたというイヌやネコの話をしたがる。
動物をかわいがる自己像を大事にしているのかもしれない。
そのせいか、散歩中の犬とすれ違うと、
たいてい「わぁ、かわいいワンちゃん」と大きな声を上げる。
100%本心ではなく、
連れている飼い主さんに気を遣っている部分が大きい。
しかし、多くの犬は「かわいい」という言葉がわかるので、
尻尾をふって寄ってくる。
そうすると、ビビッて引いてしまう。
しょうがないので代わりに僕がその犬を撫でてあげると、
義母と犬と飼い主さんの間で平和で安定した場が成り立ち、
なんとなく一つのエピソードが完結する。
それでたぶん、その飼い主さんから見ると、
義母は「イヌ好きな良い人」というイメージとして残る。
義母のほうはその場を離れたとたん、
犬のことも飼い主のことも忘れている。
それで橋を渡って折り返してくると、
同じ犬と飼い主さんに出くわすことがある。
すると、先ほどと同じシーンが繰り返される。
飼い主さんは顔で笑いながらも内心、
「さっきも同じことしたんだけど・・・」
と思っている。たぶん。
僕も敢えて「認知症なんで・・・」と説明することなく、
同じことを繰り返す。
なんだかシュールな野外劇のようだ。
ネコに対しては、飼い主さんがいないので、
「かわいいわね」と言いつつも、
僕が対話しに行くのを、ちょっと距離を置いて見ているだけ。
ソーシャルディスタンスを守っている。
そのくせ、離れるとまたもや
「私の家も子どもの頃はネコを飼っててね」と
言い出したりする。
この人、じつは幼い頃、女中さん・使用人がいる
目白のお屋敷で育ったお嬢様である。
とは言っても、それは4,5歳までのことで、
認知症になる前も、そんな記憶はほとんどなかったらしい。
けれども時おり、本当に、あ、そうだったのかなと思う時もある。
時々発症する「カエル病」も
そのお屋敷のイメージがどこかに残っていて、
魂がそこに帰ろうとするらしい。
そうすると、僕はさながら
おつきのじいやといったところかもしれない。
なんとなく「ちびまる子ちゃん」に出てくる
花輪君のおつきの「ひでじい」を思い浮かべる。
黒塗りのリムジンは運転できないが
そういう設定で面倒を見ると、
また面白くなる気がする。
ねこがくる

昔から児童公園の砂場でよく見かける看板。
いつから出してるのか知らないけど、
ゆうに30年は変わってないと思う。
「ねこがきます」と言ったら
「えー、ネコが来るの、うれしい。
どんなかわいいニャンコがくるんだろう?」と
目をキラキラさせる子どもはいないのだろうか。
「ねこが来るまで待ってる」とか
「ねこと遊びたい」と
がんばる子どもはいないのだろうか?
ちゃんと「ねこがうんちをしちゃいます」とか、
はっきり書けばいいのに。
ねこがくるからニャンなんだ?
とツッコミ入れる人はいないのだろうか?

楽しい動物エッセイ集
神ってるナマケモノ
もくじ
・ネコのふりかけ
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上 ほか 全36編
目覚めればオオサンショウウオ

ステイホームで山椒魚化?
ずっと岩屋の中で暮らしていて
体が大きくなっちゃって
外に出られなくなった山椒魚の話は、
井伏鱒二の「山椒魚」である。
この間、たまたまオオサンショウウオについて
調べる機会があったので、気になって読んでみた。
確か中学の国語の教科書に載って居たと思うので、
約50年ぶり?
最近ずんずん目が悪くなって
本を読むのも結構疲れるのだが、
これはずいぶん短い話なので楽に読めた。
面白いかというと微妙で、
なぜこの人はこんな話を書いたんだろう?
と疑問がわく。
ウィキを見ると、結構いろんなことが書いてある。
やっぱ教科書に載っているだけあって
知名度が高く、日本文学の中では
夏目漱石の「坊ちゃん」や「吾輩は猫である」、
あるいは芥川龍之介の「蜘蛛の糸」や「杜子春」、
宮澤賢治の「銀河鉄道の夜」や「やまなし」
くらいの人気があるのかもしれない。
ストーリー自体は別に面白くないが、
この山椒魚のキャラや、
描き出される岩屋のイメージは興味深い。
ちなみにオオサンショウウオは大きいのだと
体長1・5メートルになる、現在、地球上で最大の両棲類。
英名は「ジャイアントサラマンダー」。
半分に裂いても生きている、というすごい生命力で、
「ハンザキ」「ハンザケ」という異名を持つ。
すごい悪食で何でも食べるとも、
1年くらい何も食べなくても生きている、とも言われる。
戦後、昭和26年に得bつ天然記念物になったが、
その前は生息している地域ではよく食べられていたらしい。
あの食通のおじさん・北大路魯山人も、
まるでフグのような味と絶賛していた。
京都のある料亭では、
中国から輸入したオオサンショウウオを料理して
こっそり出しているという噂も。
いまや仕事も食事も遊びも
何でも岩屋(家)の中で済ませてしまえるご時世。
今夜はカフカの「変身」みたいに
朝起きたら山椒魚になっていた、
という夢でも見そうな気がする。

Amazon Kindle 電子書籍
おりべまことエッセイ集:動物
神ってるナマケモノ
ワイルドボーイ・オオタカきょうだい大成長
2021年も早や半分が過ぎようとしている。
人間はいまだコロナ禍に苦しめられているが、
野鳥天国・善福寺川では、
鳥たちの子育てがうまくいっている。
今年はオオタカも3羽のヒナが無事成長。
この3きょうだいがもう中高生レベルに達し、
超音波怪獣クラスの鳴き声を上げながら、
川沿いのヒマラヤ杉近辺を飛び回っている。
と思ったら、今日はすごいシーンに出くわした。
杉の下にある低い梅の木の枝に止まって
ごはんを食っているのだ。
ごはんになられたのは、どうやらムクドリさんらしい。
これまでオオタカがいることは知っていたが、
ほとんど姿を見たことはなかった。
杉の木のてっぺんあたりの木陰から
小さくかすかに見えたのが2~3度きり。
肉眼では無理だなと思っていたが、
きょうは10メートルもない距離でばっちり、
それも食事シーンが見られるとは。
ちなみにこの林の周辺は、
オオタカにストレスを与えないように、
という配慮でロープが張られ、
それ以上近くには寄れないようになっている。
カメラマンの人たちもそのへんはわきまえ、
きちんとそれを守っている。
おらがアイドルを見守るファンのようだ。
撮影したが、さすがにスマホのズームではこれが限界なので、
望遠レンズで撮影している人のモニターを
覗かせてもらった。
子どもとは言え、迫力満点。
目は鋭く美しく、猛禽の凛々しさを備えている。
ただ、まだガキンチョなので食べ方が下手。
くちばしできれいに羽根をむしるのはいいが、
いざつつき出すと
ときどき肉を地面に落っことす。
落っことしたのは地面に降りて
また熱心に、丁寧にくちばしと足を使って食べる。
他のきょうだいに盗られまいとしているそうだ。
このごはんは自分で取ったものでなく、
親から与えられたものを食べているらしい。
まだ狩りはできない
すねかじりの王子さまだ。
狩りはできないけど、
攻撃力は日に日に増しているらしい。
1ヵ月ちょっと前、杉の木のてっぺん近くにある巣に
数羽のカラスが波状攻撃をかけているところを見た。
どうやら生まれた頃の彼らを狙っていたらしく、
大丈夫だろうか? と心配していた。
しかし、カルガモ8きょうだいと同じく、
ここも夫婦で子育てをしていて、
しっかり守り抜いたようだ。
あれから1ヵ月あまり、
この中高生レベルの王子様たち
(王女様もいるかもしれない)は
今や大胆にも十数羽の群れに向かって
猛スピードで突っ込み、
カラスたちを蹴散らしているという目撃談まである。
たんに遊んでいるのか、
チビの時に襲われたことのお礼参りか、
「おれはタカだ」というアイデンティティの確認か、
いずれにしても体格的にそう違わないカラス軍団に
果敢にケンカを仕掛けるとは、
驚くべきワイルドボーイぶり、成長ぶりだ。
オオタカがここで暮らし始めて、
もう5年くらい経つと思うが、
さすがに人に慣れてきて、
人間は危害を加えないということを知ったようだ。
ごはんにされてしまうムクドリさんなどには気の毒だが、
動物園でもこんなシーンにはめったにお目に掛かれない。
ワイルドボーイ・オオタカのアイドル度は
ぐんぐんUPしている。

Amazon Kindle 電子書籍
おとなも楽しい少年少女小説
いたちのいのち
猛禽はちょっと怖いイタチ(フェレット)もお話。
杉並・善福寺川どうぶつキッズサマー
5月の半ばに生まれた子ガモは、
お父さん(かな?)も子育てに協力してくれたことで
8きょうだいが無事に中高生レベルまで育ち、
うるさいほど元気に泳ぎまくっている。
やっぱり2羽で守っていると、
かなり敵から襲われるリスクを回避できるようだ。
大きくなったので、親父はどっかに行っちゃったみたいだが。
まぁここまで育てばもう親父いなくて大丈夫だろう。
と思ってたら、水上でバタバタ大騒ぎ。
何やっているんだろう? と思って観察すると、
なんと飛び立つ練習をしているのだ。
飛行機と同じで水上を羽ばたきながら滑走し、
飛び上がろうとするが、まだうまくいかない。
思わず、がんばれ! と応援したくなる。
この間、目撃した愛の営みが結晶したのか、
いつの間にか新しい赤ちゃんも5匹登場。
こっちはシングルマザーのようだから
敵から守り切れるのか、ちょっと心配だ。
頭上にはカラスがカーカー飛び回っているし。
その川の向こう岸のスギ林では、
すごい甲高い鳴き声が響き渡る。
これはオオタカの子どもだ。
姿は見えないが、すごいすごい。
オオタカは善福寺川沿いのアイドルなんで、
きょうはカメラマンが押しかけ、
かなりエキサイト気味。
だけど、赤ちゃんガモは
このオオタカの子たちのごはんになるのだろうか?
けれども気をを付けるべきはやっぱりカラスだ。
カラスもいつの間にか子育て完了したのか、
やたらと増えている。
さらに子ガモの天敵・ヘビーなアオダイショウも
低木の上にニョロリ。
おとなのアオダイショウはその名の通り、
青緑色だが、こいつはほぼグレー。
体もまだ小さくてシマヘビ並なので、
アオダイ少年だと思われる。
きょうはアオサギ君までご訪問。
魚を取る瞬間は撮れなかった。
ワイルドに夏本番。

Amazon Kindle 電子書籍
おりべまことエッセイ集:動物
神ってるナマケモノ
子ガモとアニマルガモ
先週は取材で日中、出ずっぱりだったので、
ほぼ1週間ぶりに泡沿いを散歩する。
チビガモ8羽、いつものホームエリアで確認。
少し見ぬ間にまたもや大きくなった。
はじめて目撃してから1ヵ月経つ。
そろそろチビとは呼べなくなりそうだ。
ところで1週間前の夕方の散歩中、
ガーガーギャーギャー
すごいわめき声が聞こえるので
どうしたんだろう?と慌てて駆け寄ってみると
カルガモカップルが子作りに励んでいた。
またもう少しして今の子どもたちが
おとなになる頃。新しいチビガモが生まれるかもしれない。
それにしても、いくらカルガモとはいえ、
プライベートライフを盗撮するのは
失礼かなと思って
写真も動画も撮らなかったが、
かなりワイルドな世界。
(野生の鳥だから当たり前だけど)
オスはメスにのっかってバシバシたたくわ、
くちばしをくわえて引っ張るわで、
平和そうな顔つきに似ず、
なかなかエキサイティングな愛の営みを繰り広げていた。
もちろんカモだって個体差があるので、
そいつが特別暴力的だったとか、
メスもそういうのが大好きだったという可能性もあるが。
生まれた子どもはかわいいけど、
子孫繁栄のための行為は、
やっぱりけっこう
スケベでアニマルだよなと再認識。

Amazon Kindle 電子書籍
エッセイ集:動物
神ってるナマケモノ
なぜ日本にカエル食が定着しなかったのか?

かわいいから食べられなかった?
そんなに殊勝な民族なのだろうか、日本人は。
というわけで昨日の続き。
どうして中華やフランスには
カエル料理があるのに、
世界に冠たる日本料理にはそれがないのか?
なぜ日本ではカエル食が定着しなかったのか?
そう考えて検索してたら、
素晴らしいものを見つけてしまった。
その秘密は横浜にあった、
横浜の、あまり実用的とは言えない
さまざまな面白情報を載っけている
「はまれぽ.com」というウェブマガジン。
「横浜には食用ガエルの養殖場があったって本当?」
という記事だ。
この記事によると、
日本の食用ガエルの歴史は、
1918(大正7)年4月に東京帝国大学(現:東京大学)
名誉教授・渡瀬庄三郎(わたせ・しょうざぶろう)
博士によって、
アメリカのルイジアナ州ニューオリンズより雄10匹、
雌4匹を輸入したことが始まりだ。とされている。
食用ガエルは当初、帝国大学伝染病研究所内(東京都文京区)の小規模な養蛙池で養殖され、食用蛙養殖が国内でも可能なことが立証された。(以上引用)
となっている。
当時、カエルは栄養素も高く貴重なタンパク源として、
食糧問題解決の一策として注目された事業だったらしい。
このアメリカからやって来た食用ガエルの正式名は
「ブル・フロッグ」。
まんまウシガエルだ。
そして昭和になってから、そのエサとすべく
今や親しみ深いアメリカザリガニも輸入された。
今や指定外来種として、
石もて追われるような存在になってしまった
ウシガエルとアメリカザリガニだが、
100年前は鳴り物入りで、
日本の新たな食の救世主として招かれたんだね。
で、どうやら今の新横浜駅の近くにある
スケートセンターのあたりに
1938(昭和13)年ごろまで
大規模な養蛙場があったらしい。
はっきりとはわからないが、
日本にあった養蛙場は1940年代、
つまり終戦の前後ですべてなくなり、
そこで日本におけるカエル食の歴史は
途絶えてしまったようだ。
横浜で養殖されたカエルたちは
中華料理店などに出荷されていたらしいが、
その頃は中華街でカエルを食べさせる店が
あっただろうか?
このはまれぽの記事は、
女性ライターが、実に丹念に現地取材と文献調査を行い、
写真も豊富に載せていて、
日本の食用ガエルの歴史がわかる仕組みに
なっているので、
興味のある人はぜひ読んでみてください。
(カエルが苦手は人はやめたほうがいいです)
https://hamarepo.com/story.php?page_no=1&story_id=4457
カエルのから揚げを食べた経験上、
カエルの肉は結構おいしい。
味や食感としては、
鶏のささみと魚の中間みたいな感じだ。
いいお値段がするけど、ネットで買うこともできる。
話のネタに一度食べてみてケロ。
しかし、はまれぽの記事にも
「なぜカエル食が日本に根付かなかったのか?」
の考察はなかった。
やっぱり見た目の問題なのか?
と、今日もYouTubeのカエルの合唱をBGMにして
夜な夜なかんガエル。
6月にカエルを愛でる日本人と 「みんなが作ってる カエルのから揚げレシピ」の衝撃

6月と言えばジューンブライド。
というのはヨーロッパの話で、
日本は6月と言えばカエルである。
お米の国・日本では田んぼの妖精みたいなカエルは
人気者だ。
ケロケロ鳴いて
恵の雨を降らせてくれると信じられていた。
人気者どころか豊作の神様みたいなものである。
食糧が豊富になった現代はそんなありがたみも薄れ、
雨もカエルが呼んでくるような情緒あるものでなく、
災害の恐怖を伴う集中豪雨。
しかし、時代は変わってもカエルはかわいがられる。
幼稚園とか学校とか、子どもびいるところは
かわいいイラストとか折り紙のカエルだらけ。
昨日、スーパーに行ったら季節感を出すために
ここにも蓮の葉の傘を差したカエルがいっぱいいた。
そこでつい売り場のお姉さんに
「こちらのお店ではカエルの肉は売ってないですか?」
と聞こうとしたが、抑えた。
嫌がらせに来たのかと思われても嫌なので。
なんでそんなことを聞こうと思ったのかと言うと、
だいぶ昔のことだが、
名古屋にある浜木綿(はまゆう)という
中華料理のチェーン店のメニューに
カエルのから揚げがあって、
それがけっこうおいしかったことを
思い出したからだ。
帰省するたびに家族で食べに行っていた。
まだ父が生きていた頃だから
もう12年以上前のことである。
今はもうメニューにないが、
中華料理では普通にカエルを食べる。
タイとかベトナムなどの東南アジアでもあるし、
ヨーロッパではフランス料理の
重要な素材になっている。
今の日本ではどうなのだろうと
ネット検索してみたら、
「みんなが作ってる カエルのから揚げレシピ」
というタイトルを見つけた。
なんとクックパッドに載っている。
レシピの生い立ちには
「田んぼ道でふと見かけて、
捕まえられたので作りました」とあり、
ちゃんと写真付きで作り方が書いてある。
脚だけかと思ったら、
なんと丸ごと姿揚げなので、
ちょっとびっくりした。
ただ、当然というか、
他に作って食べてみましたという
「たべレポ」は見当たらなかった。
そこでまた考えた。
どうして中華やフランスには
カエル料理があるのに、
日本料理にはないのだろう?
どうしてゲテモノ扱いなのだろう? と。
実は明治期から昭和の戦時期にかけて
日本でもカエルを食べようという施策が
国家プロジェクト波のスケールで進んでいた。
東京都文京区の実験田をはじめ、
鎌倉や横浜に大規模な養蛙(ようあ)場も
儲けられていたのである。
というわけでこの話の続きはまた明日。
善福寺川のチビガモ成長中

善福寺川のカルガモの子がすくすく育っている。
先々週初めて見た時から比べると、
3~4倍くらいの大きさに成長。
確認できたのは9羽。
最初に見た時はたしか1ダースいたので、
ちょっと減ってしまった。
しかし、生存率はかなり高い方だと思う。
もうちょっと大きくなれば、
そう簡単には他の生き物に食われなくなる。
一緒に見ていたバードウォッチャーのおじさんによると、
川の上流のほう(阿佐ヶ谷・荻窪方面)の岸辺には
アオダイショウがいるが、
このあたりは生息していない。
この家族は良い場所にホームを取った。
向かって左がお母さんで、右がおやじだ。
夫婦で協力して子育てしているから、
これだけたくさん生き残っているんだ。
と話していた。
美しい物語だが、ほんとかどうかはよくわからない。
おじさんの願いが混じっているような気もする。
でもまぁ、そういうことにしておいていいだろう。
チビガモたちにがんばて生きて大きくなれと、
ガァガァ声援を飛ばした。

Amazon Kindle 電子書籍
神ってるナマケモノ
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちといっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた、おりべまことの面白エッセイ集。
人生百年時代の浦島伝説

のろまなカメがマッハのスピードで空を飛ぶ、
という大きなギャップは、かつての少年たちの夢を育んだ。
ゴジラと人気を二分した大映映画の怪獣ガメラは、
ひっこめた手足の穴からジェット噴射を出して
クルクル回転しながら空を飛ぶという離れ技、
さらにそのまま敵の怪獣に体当たりするという
神風特攻隊みたいな荒技で子どもたちを驚愕させた。
一方、昨日ご紹介したウルトラQ「育てよカメ」の
大亀ガメロンはそんな技など使わず、
ウルトラマンみたいに、というかオバQみたいに
背中に少年をひょいっと乗せて空を飛ぶ。
この「育てよカメ」は早い話、浦島太郎のパクリなのだが、
なぜか竜宮城は雲の上にあり、そこには乙姫らしき女の子が
ごく普通のワンピースを着てブランコに乗っている。
いったいどういう発想であんなシーンが出てきたのだろう?
お前が夢みる竜宮城なんて、じつはこんなもんだよ
――というアイロニーなのか?
人生百年という超高齢社会において、
浦島太郎の物語は、日本人、いや、世界中の人たちにとって
さまざまな示唆に富み、考察をするに値する重要な物語だ。
物語のラストは浦島太郎が玉手箱をあけたら
もくもくと煙が出てじいさんになって終わるが、
それをどうとらえるのかで、意味は変わってくる。
そもそもこの物語が今の形になったのはまだ明治時代のことだ。
これは僕の憶測だが、何と言っても富国強兵の時代。
いじめられているカメを助けるという人徳ある若者が、
一度、遊び惚けて飲んだくれて、
女に腑抜けにされてしまったら、
一生を棒に振ることになる。
そんな“ありがたーい人生訓”を盛り込んで、
日本男児たる者、そんな堕落の道に落ちぬよう自己を戒めよ――
という訓示に繋げようとしたのかも知れない。
しかし自己を戒めてどんないいことがあるのか?
それで幸福になるのか?
今の時代感覚から見ると、
カメを救うというちょっとした福祉をして感謝され、
飲んで食って楽しんで美人に愛されて一生過ごすなんて
こんなハッピーでサクセスフルな人生はない。
最後にじいさんになるのは人間、当たりまえの定めなのだから、
まさしく浦島太郎は人生の成功者と言えるではないか。
それにしても竜宮城にずっといればいいものを、
なんでまた浦島は故郷に帰りたいなんて思いに駆られたのか?
家族のことや村のことなど
放っておいて楽しみ続けることはできなかったのか?
玉手箱で太郎をじいさんにしてしまうのは、
裏切られた乙姫の復讐だったのか?
何もかも変わってしまった世界に絶望した
太郎に対する救済だったのか?
ところで浦島太郎がその後、どうなったのかは描かれていない。
明治から昭和にかけてはそれでおしまいだったかもしれないが、
人生百年時代のこれからは、じいさんになっても
ポジティブに生きていく浦島太郎の後日談が加わってもいい。
「昔はよかった」とか
「昔はこんなじゃなかった」なんてぼやくことなく、
浦島は荒野を目指して旅に出る。
まったく変わってしまった世界を
この目で見てやろうと世界の果てまで放浪する。
もしかしたらどこかの街で
人々に竜宮城の話をして喜ばれるかもしれない。
仙人や高僧だと持ち上げられて敬われるかもしれない。
また恋をして、
若い娘に惚れられてねんごろになることだってあり得る。
令和の世はそんなふうに浦島太郎の話を
つくり替えたってOKなのではがないだろうか。
それでは明日はこの続編で、
カメはなぜ浦島に助けられたのかと、
乙姫様が仕組んだ、女の陰謀のお話を一席。
おりべまこと電子書籍 AmaonKindleで発売中!
★子ども時間の深呼吸:子どもエッセイ集
★昭和96年の思い出ピクニック:昭和エッセイ集
★神ってるナマケモノ:動物エッセイ集
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
カネゴンは鳥を見た

現在、毎週月湯深夜にNHK-BSプレミアムで
「ウルトラQ」を放送している。
「ウルトラQ」は1966(昭和40)年にTBS系で放送された
円谷プロ制作の特撮ドラマで、
ウルトラシリーズの元祖となる作品だ。
日曜夜7時からの番組で、当時のファミリーが視聴対象。
怪獣が出てくるのでもちろん子供も大喜びだが、
中身は完全におとな向けのSF、ミステリー、ファンタジー。
僕は当時6歳で、
ものすごく怖くてとても一人では見られなかった。
同じように昭和の子供たちは、
毎週「ウルトラQ」によって
恐怖のどん底に落とされていただろう。
いま振り返ると、そこには子どもが
家族といっしょに怖いものを楽しめる
安心感・幸福感があった。
そういう意味でファミリー向けだったのだ。
ほとんどが大人っぽい内容だが、
3本だけ子どもが主人公のファンタジー物語があった。
それが「育てよカメ」「鳥を見た」「カネゴンの繭」である。
この3本のオープニング(エンディング)は、
あのこわーいテーマ曲でなく、
わんぱくマーチみたいな曲が使われていた。
「育てよカメ」は少年が飼っていた亀が突然巨大化して、
そいつに雲の上にある竜宮城みたいなところに
連れて行ってもらうというおとぎ話。
確かゆめ落ちだったのではないかと思う。
雲上の竜宮城にはブランコしかなくて、
乙姫様らしき女の子がやたらおきゃんで、小悪魔っぽかった。
「鳥を見た」も、少年が飼っていた小鳥が巨大化する物語。
こちらはコミカルではなく、芸術的な短編映画のようで、
「鳥を見た」というセリフがキーワードとして使われていた。
古代の怪鳥に変貌した友だちの鳥が
夕空の彼方へ去って行くのを見送る少年。
その後姿をバックにエンドロールが流れる。
話の内容は憶えてないが、
そんな詩情あふれる美しいラストシーンを見たのは
生まれて初めてだった。
「カネゴンの繭」はおなじみ人気怪獣カネゴンが
出てくる回である。
カネゴンはおカネ大好きなカネオ君という少年がある日、
不思議な繭に取り込まれ、
出てきたらカネゴンになっていたという話で、
言ってみればカフカの「変身」のパクリである。
そのカネゴンを人間に戻すために
友だちがあの手この手で知恵を絞ってがんばる。
表現はシュールでコミカルで現代批評だが、
基本構造は友情物語なのだ。

わが散歩道・善福寺川周辺にはカメも鳥もカネゴンもいる。
カメは基本的にこの先にある和田堀公園の池にお住まいだが、
ときどき川を上って出張してくる。
鳥はいっぱいいる。
春から夏にかけてはカワウやアオサギまでやってくる。
こいつらはなかなかの迫力で、
面構えはまさしく怪鳥だ。
そして今やこのあたりの名物となったオオタカも子育て中だ。
本当に時々だが、木の陰に白い体がちらっと見える。
そしてカネゴンがぞろぞろ歩いている。
僕を含めて「オオタカを見た」「カワウを見た」
「アオサギを見た」と騒いでいる。
人間の皮を被っているけど実はカネゴン。
カネゴンはいつもおカネを食べてないと生きていけない。
胸につけてるカウンターがゼロになったら死ぬ。
僕らも預金残高がゼロになったら・・・
いや、死なないで笑って生きよう。
カネはないけど心配するな、と。
庵野監督、ウルトラマンと仮面ライダーが終わったら、
今度は「シン・ウルトラQ]をお願いします。
おりべまこと電子書籍 AmaonKindleで発売中!
★子ども時間の深呼吸:子どもエッセイ集
★昭和96年の思い出ピクニック:昭和エッセイ集
★神ってるナマケモノ:動物エッセイ集
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
オバマのタカハシさんちの娘は人魚の肉を喰った

人魚はメルヘンであり、ファンタジーであり、
ホラーであり、モンスターである。
ついでにかなりセクシーでもある。
アンデルセンの「人魚姫」の下半身が魚から
人間の脚に変わるのは、
女性の性的成長を表すメタファーである、という解説を
ある本で読んだときは、
まさしく目から魚のウロコが落ちた。
というわけで古今東西、人魚に恋する者は後を絶たず、
世界各地に人魚伝説が残されることになった。
ヨーロッパには、人魚姫のイメージを覆す
人魚が船乗りの男どもをおびき寄せて
食っちゃうという話がある。
(というか、逆にアンデルセンがこの怖いイメージを覆して、
可愛く、美しいイメージを創り上げたんだけど)
対して日本では人魚を食べちゃった、という話がある。
オバマ大統領の時、大いに盛り上がった福井県小浜市。
そのオバマの地に伝えられている「八百比丘尼」の話は
日本の民話の中でも異常に人気が高い。
昔、若狭国小浜(わかさのくにおばま)に
高橋権太夫という長者が住んでいた。
ある日、舟を出して遊んでいると嵐が起こり、
見知らぬ島に流されてしまった。
そこで彼は思わぬもてなしを受けることになる・・・
という感じで始まるこの話、このタカハシさんはこの土地の
お偉いさん、お金持ちで、彼が贅沢な会食をするのは
いろんなバージョンがある。
しかし、その後はどのバージョンも共通している。
その贅沢な会食の食卓に上るのは人魚の肉なのである。
(タカハシさんが厨房で人魚がさばかれるのを
目撃してしまうというバージョンもある)
タカハシさんは金持ちのくせにセコいのか、
少年のように好奇心旺盛なのか、
この人形の肉をこっそりテイクアウトして、
家の戸棚に隠しておく。
お刺身だったのか、塩焼きだったのか、ムニエルだったのか
わからないが、いずれにしても
冷蔵庫のない時代、そんなところに入れておいて
腐らないのかと心配になるが、
腐る前に家族の者が見つけて食べてしまった。
そのつまみ食いの犯人が、
みめ麗しい年ごろのタカハシさんちの娘だったのである。
肌の白い美しいその娘は、
それ以後、まったく齢を取らなくなった。
人形の肉を食べたせいで不老不死の体になったのである。
夫も家族も友人も死に絶え、時代が変わっていっても、
彼女は若いまま生き続ける。
やがて彼女はその長い生に倦み、村を出て、
尼さんとなって全国を遍路する。
そして人々を助け神仏への信仰を説き、
行く先々で白い椿を植えたという。
(杉の木を植えたなど、違うバージョンもある)
ちなみに八百比丘尼は正確には不死だったわけでなく、
800歳でこの世を去ったということだ。
だけど十分過ぎるほど生きた。
魚食文化を持つ日本人にとって、
そう遠くない過去--昭和の貧しい時代まで、
魚は不老長寿の薬、とまではいかないにせよ、
病気を治し、健康を保つ薬だった。
そういえば僕も子どもの頃に、
産後の肥立ちが悪い母親とか、病気の大人に、
タイやコイを食わせろーーという話を聞いたことがある。
この間、取材した島根県の坊さんは、
このあたりでは戦前まではオオサンショウウオ
(現在、特別天然記念物の地球最大の両棲類)を
捕まえて食っていた。
オオサンショウウオは半分に裂いても死なないほど
生命力が強いことから「ハンザキ」の異名がある。
おそらく滋養強壮剤として食べられていたのだと想像する。
これも実際は両棲類だが「山椒魚」というくらいだから、
昔の人は魚の一種だと考えていたのだろう。
オオサンショウウオを食べて不老長寿を獲得する―ー
そういう人がただの一人もいなかった、とは言い切れない。
それにしても、八百比丘尼の話は、
人魚を殺して肉にする。
それを若い娘が喰う。
不老不死になる。
旅に出て、花や木を植える。
モンスター、ホラー、ファンタジー、メルヘン、
そして考えようによってはセクシーも。
すべての要素を一つの物語に凝縮したかのようだ。
そのおかかげで現代のマンガや映画、小説、アートなど、
いろいろなカルチャーのモチーフになっている。
そういえばコロナ退散祈願のアマビエも人魚っぽい。
僕は800歳になった八百比丘尼は死んだのではなく、
人魚になって海に帰っていったのではないかと思うのだが、
いかがだろうか?
「恐怖!かえる女」はプリンセス

どうやら弱みを握られたようだ。
「椎名町の家にカエル」
「家族が迎えに来てるからカエル」
「すごそこに兄貴がいるからカエル」
そうやってケロッピーなセリフを放つと、
僕やカミさんが慌てて対応してくれることを
義母は学習してしまったようである。
認知症患者、侮るなかれ。
こうした「かえるコール」が出るのは、
たいてい「飯まだか」「おやつが食べたい」
「散歩に行きたい(退屈だから外出したい)」
のいずれかである。
要するに自分の要求を訴えたいとき、
「かえるコール」を発射することが
最も有効な手段なのだ。
仕事でテンパっているときに
これをやられると、プシューっと脳みそが沸騰するが、
やむを得ずニコニコ仮面を被って要求に応じる。
これ以上エスカレートしないことを念じるばかりだ。
さらに最近、ときどき朝起き出してくると、
「あれ、男の子たちは今日いないの?」
といった、ボケゼリフが飛び出す。
最初は幼い頃のきょうだいとか、息子のことを言ってるのかな、
だけど兄しかいないし、娘しかいないし、
「男の子」には縁がないはず。
幼なじみがいたのかな・・・と、カミさんと話していたが、
どうもそれはデイサービスのスタッフのことを
言っているらしい、ということに思い至った。
最近はデイサービスで若い男のスタッフが
けっこうチヤホヤしてくれていて、
お姫さま気分を味わっているようだ。
少なくとも本人にとって、
認知症になったのが悲劇であるとは限らない。
もしかしたら、今こそがお姫でいられる
わが世の春なのかもしれない。
逆に幼い頃、お城みたいなところに住んでていて
召使に傅かれていたけど
わたしは不幸だった、と語る人もいた。
諸行無常。万物流転。
今がいいから、またはダメだからと言って
人生の幸不幸をそう単純に決めてはいけない。
おりべまことの エッセイ集
amazonKindleより発売中
●昭和69年の思い出ピクニック ¥318
アイドル、家族、戦争・・・あの時代を面白まじめに考察する昭和エッセイ集。
●神ってるナマケモノ ¥321
動物の神秘と面白さ、人間との関係性を探究する動物エッセイ種。
●子ども時間の深呼吸 ¥324
誰の心の中にもいる「子ども」に焦点を当てた子どもエッセイ種。
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ から
「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
ネズミやネコやイヌは夕焼け空に叙情を感じるか?

♪夕日が沈むよ ポコ・ア・ポコ
と、トッポジージョがギターを持って歌っていた。
トッポジージョは僕が子どもの頃、
テレビで人形劇として放送されており、
終わるときに必ずこの歌が流れるのだ。
当時の子ども番組、それも動物が主人公の番組には
似つかわしくないメランコリックなメロデイで
トッポジージョは
ミッキーマウスとかジェリー(トムとジェリー)とは
ひと味ちがう、ちょっと大人っぽいイメージのネズミだった。
振り返ってみると、スパゲティ以外では
はじめてのイタリア体験だったかもしれない。
人形劇の内容はさっぱり憶えてないが、
僕の中では勝手に海に沈む夕日に向かって
ギターを弾いているトッポジージョの姿が形成されていた。
ナポリタンスパゲティのイメージも絡まって、
すっかりナポリのネズミだと思っていた。
昭和40年代はスパゲティと言えば一般的には、
赤いウインナーの乗っかったケチャップ和えのナポリタンか、
ミートソース(今でいうならボネーゼ)しかなかったので。
でも、つい最近知ったことだが、
トッポジージョはナポリでなく、ミラノのネズミらしい。
ちなみに「ポコ・ア・ポコ」というのは
イタリア語で「少しずつ」という意味で、
イタリア料理店、パン屋さん、お菓子屋さんなどの
店名としてよく使われているようだ。
かわいくて憶えやすい語感だからね。
トッポジージョは僕の中で、いたずら野郎でなく、
そういうメランコリックなネズミなのだが、
当たり前のことながら、夕空を見て叙情的になるネズミはいない。
基本的に夜行性なので、
夕方になれば活動開始!と思うだけである。
いつも散歩する公園では夕刻になると、
僕が「ネコ林」と呼んでいる場所に野良猫たちが集まってくる。
日が暮れる頃になると、ネコ使いのおばさんがやってきて
ごはんをくれるのを知っているからだ。
ネズミもネコもイヌも、人間のように夕日を見て
何か物思うことなんてしない。
そもそも彼らは四つ足で地面に近いところで生きているので
空なんて見上げない。
見るとしたら、上空から猛禽類が襲ってくるかも知れない、
という危険を感じた時だけだ。
でも人間も都市に暮らし、引きこもって生活していると
空を見上げなくなる。
朝でも夜でもいいから1日に何回か空を見上げないと、
だんだん人間から四つ足動物の感性になっていく、
ような気がする。
さて、と書いてきたことは僕の勝手な思い込みで、
空を見上げるのは実は人間の特権ではないのかもしれない。
もしかかして、あなたが一緒に暮らしている
イヌやネコやネズミは
遠い空の彼方に思いを馳せたり、
夕焼け空に叙情を感じたり、
「見上げてごらん夜の星を」を心の中で歌い、
UFOを発見し、ETとコンタクトできるのかもしれない。
もしそんなイヌやネコやネズミがいたら教えてほしい。
ポコ・ア・ポコ。
◆Enjoy!緊急事態宣言期間キャンペーン◆
Amazon Kindle電子書籍
おりべまことエッセイ集5タイトルを
10日間連続無料でお届けします。

★11日(木)17:00~13日(土)16:59
神ってるナマケモノ (動物エッセイ)
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちといっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた、おりべまことの面白エッセイ集。
自身のブログから36編を厳選・リライト。
目次
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・ヌード犬・ファッション犬
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上 ほか
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
ttps://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
中国製ネコ型ロボットが食事をお届け
日本でネコ型ロボットといえばドラえもん。
便利な機械を出してくれるわけではないが、
韓国や中国ではコロナ禍の中で、
ネコ型配膳ロボットが大活躍している。
人への感染が特徴であるコロナウイルスの特性から、
非接触配送の需要が世界中の病院で高まり、
現在、韓国のソウルや中国の北京、武漢など数百の病院で
中国のロボットメーカー、Pudu Roboticsの製品
「BellaBot」が利用されている。
このネコ型ロボット、配膳にかかる工程を
すべて自動で行うため、
感染の拡大を効果的に防止することができる。
また大容量のトレイを搭載しているので
食事、医薬品、その他の物資を一度に患者に
届けることができる。
病院だけでなく、昨年からレストランや
オフィスなどでも利用され、
現在では2000社以上の国際企業で
非接触配膳サービスとして
採用されているとのこと。
コロナ禍の間隙を縫って中国では
AI・ロボットが大発展しているようだニャー。
◆Enjoy!緊急事態宣言期間キャンペーン◆
明日よりAmazon Kindle電子書籍
おりべまことエッセイ集5タイトルを
10日間連続無料でお届けします。

★11日(木)17:00~13日(土)16:59
神ってるナマケモノ (動物エッセイ)
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちといっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた、おりべまことの面白エッセイ集。
自身のブログから36編を厳選・リライト。
目次
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・ヌード犬・ファッション犬
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上 ほか
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
冬の散歩道
「テレワークをやるようになったので」
「介護していた主人が亡くなったので」
理由はいろいろだけど、それまでの暮らしが変わって
最近、川沿いを散歩するようになったという人に何人か逢った。
聞くと、僕たちよりもずっと昔からこのあたりに
住んでいる人たちだ。
すぐ近くにあっても、タイミングが合わなければ
ともに生きることはない。
人生は長いようで短い。
何と巡り合うかは運しだい。
それをどう大事にするかは自分の意思しだい。

Amazon Kindle 電子書籍新刊
「ポップミュージックをこよなく愛した僕らの時代の妄想力」
ビートルズをきっかけにロックが劇的に進化し、ポップミュージックが世界を覆った時代.僕たちのイマジネーションは 音楽からどれだけの影響を受け、どんな変態を遂げたのか。心の財産となったあの時代の夢と歌を考察する、おりべまことの音楽エッセイ集。ブログ「DAIHON屋のネタ帳」より33編を厳選・リライト。
ASIN: B08SKGH8BV ¥311
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ から上記コードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
もくじ
●八王子・冨士森公園のスローバラード駐車場で、ポップミュージックをこよなく愛した僕らの時代の妄想力について考える
●アーティストたちの前に扉が開いていた
●21世紀のビートルズ伝説
●藤圭子と宇多田ヒカルの歌う力の遺伝子について
●ヘイ・ジュード:ジョンとポールの別れの歌 ほか
ペットの遺骨を真珠に育てる真珠葬 「虹の守珠(もりだま)」
11月に開かれたエンディング産業展2020の出展ブースの中で、で印象に残ったのものが「真珠葬」だった。
ペットの遺骨を真珠にする真珠葬「虹の守珠(もりだま)」は、2018年11月に事業として開始された。
真珠になるまで1年~1年半かかるため、2019年末、初めての遺骨の真珠が依頼主(犬や猫の飼い主)の手もとに返された。
8㎜以下の遺骨を8個預かり、個体識別用のICチップとともに樹脂でコーティングした後、アコヤガイに入れ、10㎜前後の真珠に育てる。
場所は長崎県の奈留島(五島市)にある「多賀真珠」という養殖場で、その養殖業者、長崎大大学院水産・環境科学の教授、そして、化粧品・健康食品など、女性のための企画商品を開発しているウービィー株式会社のの社長の3者が共同開発した。
このサ-ビスの素晴らしいところは、単に遺骨を1年間預かって真珠にします、というだけでなく、その「過程」を大事にすることだ。
コーティングした遺骨を核入れした後、真珠の生育状況を写真や動画で撮影してコメントをつけたレポートを随時、依頼者ひとりひとりにネット配信している。こうしたやりとりを通して丁寧に気持ちをつなぐことが、高質な付加価値になっている。
つまり、ストーリーがあるのだ。
結果だけポンと渡されても感動は生まれない。
誰もが結果ばかりを重視し、早く結果を知りたがる世の中だから、逆に時間と手間暇をかけた、こうしたサービスが貴重に思えるのかも知れない。
やさしく丁寧なイメージを大事にしているので、積極的な広告は打たず、人から人へ口コミなどで自然に伝わり、心に留まるのが相応しいと考えている。
とは言え、事業である以上、世の中に存在をアピールしたい、ペットの葬儀や仏具を扱う人にも知ってほしいという思いがあって出展したという。
少し意地悪く「それじゃ、こうやってアピールして、いっぱい引き合いが来たらどうするんですか?」と質問してみたら「予約待ちしていただきます」という返事だった。実際、生前から亡くなったら真珠葬をしたいという予約問い合わせが少なくない。
今、ペットの遺骨はお墓に埋葬するか、庭に埋めるか、自宅で保管するか、という3択だという。する・しないは別にして、そこに虹の守珠が加わればそれだけでいい。
飼い主の人たちの心の中に真珠葬というもう一つの選択肢があることが大事なのだ、というお話だった。
預けた人が「子どもを留学に出しているような気持ちになる」という真珠葬。
亡くなったのに成長を見守ることができ、「行ってらっしゃい」「おかえり」と言葉を掛けられる。
ペットの飼い主は、いずれは看取りをしなくてはならず、ペットロス症候群を覚悟する必要もあるが、そうした人たちにとってのグリーフケアの一つになると思う。

「いたちのいのち」ASIN: B08P8WSRVB
12月4日(金)17:00~12月7日(月)16:59
3日間限定無料キャンペーン実施!
少女とペットのフェレットとのくらいを描いた、おりべまことの新刊・長編小説「いたちのいのち」(Amazon Kindle 電子書籍)を3日間限定キャンペーンを行います。この機会にぜひ!
★アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
★スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
★Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
●あらすじ
カナコは10歳。小学4年生。
一人娘の子育てに悩まされながら、生活を支えるのに忙しい母親のマヨと二人暮らしをしている。
しかしもう一人、というか一匹、いっしょに暮らす同居者がいる。その名は「イタチ」。ペットのフェレットだ。学校でも家でも口をきかないカナコにとって、イタチは唯一、心を開いて話ができる親友であり家族だ。
国語の授業で、その大好きなイタチのことを作文に書いたら、
担任のあかり先生が目にとめ、
「すごくいいので、コンクールに出しましょう」と言ってきた。
そんなつもりじゃなかったのにと、内気なカナコは困惑し、
先生に激しく抵抗する。
しかし、母と先生と関わる中で、カナコはだんだん変わり始める。それをイタチは察知していた。彼女が3歳の時からずっと一緒に暮らしてきたイタチは、地球に生まれて間もないころから、自分がカナコに必要な存在だとわかっていた。
彼は天国にいた時の記憶を持っている。
天使だったイタチは、もともと人間として地球に生まれることを望んでいたのだが、生き物としての命を与え、地球に送る〈地球いきもの派遣センター〉の手続き上のミスによって
人間になるのを諦めた。
その代わりにフェレットとして
ワンサイクルの命をまっとうすることになったのだ。
子どもからちょっとおとなに変わっていくカナコと、
そのそばで天使の目を持ったまま生きるフェレットのイタチ。
それぞれの視点から代わる代わる、日常生活とその中で起こる事件の数々、そして、ふたりの別れまでのストーリーを描く。
なお、表紙イラストは
漫画家・イラストレーターの麻乃真純さんが制作。
「パートナー 進め!ソラ」「ほっと・ペットクリニック」「あしたはハッピードッグ」「母のバッカス」「いぬの先生」など、動物ものの作品を多数発表している。
おりべまこと電子書籍第10作:長編小説「いたちのいのち」発売

カナコは10歳。小学4年生。
一人娘の子育てに悩まされながら、生活を支えるのに忙しい母親のマヨと二人暮らしをしている。
しかしもう一人、というか一匹、いっしょに暮らす同居者がいる。その名は「イタチ」。ペットのフェレットだ。学校でも家でも口をきかないカナコにとって、イタチは唯一、心を開いて話ができる親友であり家族だ。
国語の授業で、その大好きなイタチのことを作文に書いたら、
担任のあかり先生が目にとめ、
「すごくいいので、コンクールに出しましょう」と言ってきた。
そんなつもりじゃなかったのにと、内気なカナコは困惑し、
先生に激しく抵抗する。
しかし、母と先生と関わる中で、カナコはだんだん変わり始める。それをイタチは察知していた。彼女が3歳の時からずっと一緒に暮らしてきたイタチは、地球に生まれて間もないころから、自分がカナコに必要な存在だとわかっていた。
彼は天国にいた時の記憶を持っている。
天使だったイタチは、もともと人間として地球に生まれることを望んでいたのだが、生き物としての命を与え、地球に送る〈地球いきもの派遣センター〉の手続き上のミスによって
人間になるのを諦めた。
その代わりにフェレットとして
ワンサイクルの命をまっとうすることになったのだ。
子どもからちょっとおとなに変わっていくカナコと、
そのそばで天使の目を持ったまま生きるフェレットのイタチ。
それぞれの視点から代わる代わる、日常生活とその中で起こる事件の数々、そして、ふたりの別れまでのストーリーを描く。
なお、表紙イラストは
漫画家・イラストレーターの麻乃真純さんが制作。
「パートナー 進め!ソラ」「ほっと・ペットクリニック」「あしたはハッピードッグ」「母のバッカス」「いぬの先生」など、動物ものの作品を多数発表している。
目次
1.カナコ、イタチに起こされる
2.イタチ、マヨさんは起こさない
3.カナコ、朝からあかり先生に呼び出される
4.イタチ、カナコと出会ったときの話をする
5.カナコ、あかり先生に作文を読まれる
6.イタチ、自分がほんとうはどこから来たかを話す
7.カナコ、虹を超えてイタチの秘密を知る
8.イタチ、フェレットの習性について研究する
9.カナコ、あかり先生に長い宿題を出される
10.イタチ、全自動洗濯機の中でグルグル回る
11.カナコ、自分のことを作文に書く
12.イタチ、動物病院で天日干しの夢を見る
13.カナコ、雨ふりのことについて考える
14.イタチ、公園でカラスとネコに出会う
15.カナコ、イタチとはぐれたことをマヨに電話する
16.イタチ、あかり先生に拾われる
17.カナコ、帰ってきたイタチを抱きしめる
18.イタチ、どうして自分が帰ってこられたのか振り返る
21.カナコ、これから先のことで心配になる
22.イタチ、おフロ場の冒険に出かける
23.カナコ、イタチ救出作戦を実行する
24.イタチ、カナコといっしょに生きることをちかう
25.カナコ、あかり先生にラブレターを書く
26.イタチ、悪い病気にかかる
27.カナコ、イタチとお別れする
28.イタチ、空へ帰る
29.カナコ、イタチのいない暮らしをする
30.イタチ、〈いたちのいのち〉を抱きしめる
●いたちのいのち ASIN: B08P8WSRVB ¥520
★アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
★スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
★Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
飼い主にはペットを看取る使命がある
人間の場合は
「(子どもが)親より先に死んではいけません」と教えられるが、
動物の場合は
「親(飼い主)が子ども(ペット)より先に死んではいけません」となる。
動物を飼う以上、
飼い主は彼ら・彼女らの看取りをする使命がある。
そういう意識が浸透してきたのか、
ペットの葬儀供養関係事業は
この数年でかなり質が上がってきていると聞く。
エンディング産業展も毎年、
いろいろペット葬儀関連の業者がブースを出している。
こういうものは業界人だけでなく、
一般の人にもちゃんと見てもらっておいたほうがいいと思う。
今年の月刊仏事の取材では、ブース紹介も数を絞って、
わりときっちりコメントするという編集方針。
なので受け持ったな中で3つをペット関係にして、
グッドワークの「段ボール棺」、
フランスベッドの「ペット仏壇」、
ウーヴィーの「真珠葬」を取材した。
グッドワークは段ボールケースを作っている会社で、
昨年からこのペット用の段ボール棺を
Amazonで販売しているという。
簡易な棺だが、お花などを入れてあげて
そのまま火葬できるのはいいなと思った。
(ただし、自治体によってはできないとこるもあるようなので、
お問い合わせください)
フランスベッドは最初、リストだけ見た時は
最近、CMなどで見かける介護用ベッドを
展示しているのかなと思ったら、
なんとペット仏壇がメイン展示だった。
担当に人に聞いたら「フランスペット」というシリーズを作って
ペット用のソファやベッドも開発・販売しているという。
高級なベッドメーカーのイメージがあるが、
なかなかダ洒落が効いている。
「仏壇」というのは便宜上の呼称で、
要は亡くなったペットをちゃんと供養するための
インテリア用品を、ということで開発したのだそうだ。
さすがに一流メーカーらしい、
シックで上品な趣のある家具になっている。
ウーヴィーの「真珠葬」については詳しい説明を要するので、
また後日。
★おりべまこと 電子書籍新刊★
動物ストーリー「いたちのいのち」
11月30日(月)、Amazon Kindleより発売予定
子どもからちょっとおとなに変わっていく小学4年生のカナコ。そして、天使の目を持ったまま生きるフェレット「イタチ」。
飼い主とペット、それぞれの視点から代わる代わる、日常生活とその中で起こる事件の数々、そして別れを描く長編小説。
「ほっとペット・クリニック」「いぬの先生」などの作品でおなじみ、日本の動物マンガの第一人者、麻乃真純さんが表紙イラストを制作。お楽しみに。
脂ののったカルガモを狙う野生のブラックプリンセス
善福寺川で暮らしているカルガモさんたちは皆、
秋が深まるとともに脂がのってきた。
まさしく天高く、カモ肥ゆる秋である。
ガァガァ。
ジビエグルメの方によると、
マガモよりは味が落ちるものの、
なかなかの美味だそうである。
やはりネギと煮て鴨鍋だろうか。
寒い冬はごちそうである。
けど、このあたりでは取って食うわけにはいかない。
しかし、そのカモたちを毎日、
虎視眈々と狙っている肉食系女子がいる。
わが友クロネコちゃんである。
どこへ行ったのか探すと、最近は
たいてい川べりに降りて茂みの中に隠れたり、
ウロウロ歩き回ったりしている。
なんだか狩りの練習をしている
トラやライオンの子どもみたいである。
彼女はふだん、美しい尻尾をくねらせて
フェロモン発散しながら、
人間にゴロゴロすり寄って
おなかを見せてなで回してもらっている、
けっこうお色気満点のお姫様だ。
それなのに野性味に富んでいて、
この辺の人の情報によると、
小鳥やネズミなど捕まえて食べているという。
かと思うと狩りがうまくいかなかったのか、
ネコ使いのおばさんが他のネコたちに
餌をあげていたりすると、自分もちゃっかりもらいにくる。
人間は自分を愛してくれていることをちゃんと知っていて、
このあたりの野良猫のなかではいちばん堂々としている。
でもボスという感じではなく、あくまで気ままに生きているのだ。
なかなかしたたかで自由なブラックプリンセスななのである。
しかし、ヒナならともかく、自分と同じくらいの体格の
おとなのカモなんて狩れるのだろうか?
かなりリスキーではないかと思うが、
野生の声に突き上げられて、
いつか脂ののったカモを食う夢を見ている。
それこそが彼女のニャン生の目標なのだろう。
カルガモもクロネコもどちらも愛でる僕としては、
なかなか複雑な心境である。
★おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中★
おとなも楽しい少年少女小説
・ざしきわらしに勇気の歌を ¥317 ASIN: B08K9BRPY6
・ピノキオボーイのダンス ¥500 ASIN: B08F1ZFLQ6
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
面白まじめなエッセイ集
・どうして僕はロボットじゃないんだろう? ¥318 ASIN: B08GPBNXSF
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
ネコのお遍路さんと笑劇の人生

ミニミニ四国八十八ヶ所巡りをする白装束のネコを見ていたら、
なぜか喜劇王チャップリンの名言を思い出した。
「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから眺めると喜劇である」
ほとんどの人生は、終わってみれば、
きっと笑い話にすぎないのだろう。
でも、笑い話にしてやろうと思って生きている人はいない。
みんななんとかいいものにしようと一生懸命やっている。
でもでも、ときどき、自分を分離させて、
悩んだり、しゃかりきになっている今の姿を
「ニャハハハ」と笑ってみるのもいいかもね。
おりべまこと電子書籍「ざしきわらしに勇気の歌を」
Amazon Kindleにて 無料キャンペーン実施中
実施期間:10/16(金)16:00~19日(月)15:59
世界を分断する壁から人々を救うために
75歳の寅平は新しい人生の扉を開いた。
老いた少年と妖怪とロボット介護士の、
笑いと恐怖と不思議が交錯する物語。

ロボット介護士に支えられて余生を送っている寅平じいさんが、ある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。その子を追って木の穴に潜り込むと、奥には妖怪の国が広がっていた。
子どもの正体はざしきわらし。
ざしきわらしは最強の妖怪“むりかべ”の脅威から人間を守るために闘うので、応援してほしいと寅平に頼む。寅平はこれぞ自分のミッションと思い、闘うざしきわらしのために勇気の出る歌を歌う。
おとなも楽しい少年少女小説最新作。
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー「ASIN: B08K9BRPY6」、または「おりべまこと」、
または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
幸せの青い鳥はすぐそこにいた

美しき青きカワセミのラブラブカップル。
並んでじっと魚を待つ。
おりべまこと電子書籍「ざしきわらしに勇気の歌を」
Amazon Kindleにて 無料キャンペーン実施中
実施期間:10/16(金)16:00~19日(月)15:59
世界を分断する壁から人々を救うために
75歳の寅平は新しい人生の扉を開いた。
老いた少年と妖怪とロボット介護士の、
笑いと恐怖と不思議が交錯する物語。
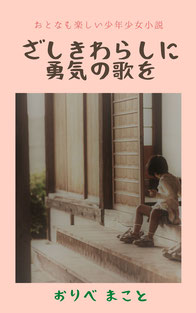
●あらすじ
ロボット介護士に支えられて余生を送っている寅平じいさんが、ある日、林の中を散歩していると不思議な子どもに出逢う。その子を追って木の穴に潜り込むと、奥には妖怪の国が広がっていた。子どもの正体はざしきわらし。
ざしきわらしは最強の妖怪“むりかべ”の脅威から人間を守るために闘うので、応援してほしいと寅平に頼む。
寅平はこれぞ自分のミッションと思い、闘うざしきわらしのために勇気の出る歌を歌う。
おとなも楽しい少年少女小説最新作。
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー「ASIN: B08K9BRPY6」、または「おりべまこと」、
または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
女のダークサイド

しばらくの間、雨続きだったので、久しぶりに義母と川沿いを散歩する。
金木犀も彼岸花も終わり、秋が深まっていくのが感じられる。
依然として蚊が多いのには閉口するが、夕方になっても結構人通りがあり、
子どもや犬の散歩の人たちが大勢歩いていた。
認知症の人は子どもとおなじように無邪気に見える。
なので散歩に行くと、
「あら、こんにちは」
「(子どもと親やイヌと飼い主に向かって)かわいいですねぇ」
「また会いましょうね」
などとにこやかに声をかけるので、
たいていの人は胸を開いて笑顔で応じてくれる。
そしてよく顔を合わせる人でも、たぶん、
彼女が認知症だとは夢にも思っていない。
多くのイヌは「かわいい」という人間の言葉に
敏感に反応するので、
義母の後をクンクンついてきたする子もいる。
とてもとてもいい人に見えるのだろう。
でも本当は100%いい人というわけではない。
そうやって一見、社交性があるものの。
じつはそんなに開放的なキャラではないのだ。
にこやかにあいさつして通り過ぎた後に、
「あの人、おっかしいわよねぇ」とディスって、
ブラックに笑ったりもする。
でも、僕といるときは割と控えめらしいだ。
異性の前ではあまりそういう面は見せないのだ。
同性であるカミさんと二人の時はその傾向がかなり顕著だという。
なかなか女はいやらしくて狡猾だ。
いくつになろうが、認知症になろうが、
そうした女のダークサイドを失わない義母は
なかなか強かで面白い、魅力的な存在である。
しかし、彼女の「かわいい」にイヌはイチコロだが、
ネコには通用しない。
ネコは僕のものである。
ねこなきじじい・ねこなでじじいの僕とネコとの戯れを
義母はソーシャルディスタンスを取って、
じっと嫉妬深げな目で眺めるのみである。
おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
おとなも楽しい少年少女小説
・ざしきわらしに勇気の歌を ¥317 ASIN: B08K9BRPY6
・ピノキオボーイのダンス ¥500 ASIN: B08F1ZFLQ6
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
面白まじめなエッセイ集
・どうして僕はロボットじゃないんだろう? ¥318 ASIN: B08GPBNXSF
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
キャットライダーBLACK

お友だちのクロネコは本日はバイク乗り。
ねこなきじじいの僕は啼くのも忘れて
「おお!」と感動して思わず足を止めてしまった。
パチパチスマホで撮ってたら、
「キャー、かわいい!」と黄色い声がして、
ねこなでばばあたちがやってきて、
やっぱりスマホでパチパチ。
そんな状況にも慌てず騒がず、逃げもせず、
ふふんと何食わぬ顔で
彼女はスーパーカブをわがものにしている。
ちなみに高齢者が飼うには世話が大変なイヌよりも
ネコがお薦めすると、とあるペットの専門家が言っていた。
そんなわけで、令和時代はネコに癒されたい
「ねこなきじじい」や「ねこなでばばあ」が大増殖しそうな気配。
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・どうして僕はロボットじゃないんだろう? ¥318 ASIN: B08GPBNXSF
・ピノキオボーイのダンス ¥500 ASIN: B08F1ZFLQ6
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
こなきじじい と ねこなきじじい

●こなきじじいの出世
こなきじじじいはかなり知名度の高い妖怪である。
カッパ、天狗、のっぺらぼう、ざしきわらしなどには及ばずとも、
知名度ランキングではベスト10に入るかどうかというところまで行くのではないだろうか?
こなきじじじいの名を世に知らしめたのは、
なんといっても妖怪マンガの巨匠・水木しげる先生の
「ゲゲゲの鬼太郎」のおかげである。
こなきじじいという妖怪がいることなんて、
ぼくたちの親の世代以上の日本人はほとんど知らなかった。
鬼太郎の友だち、ファミリーの一員となったことで
こなきじじいは日本でも指折りの妖怪に昇格・出世したのだ。
●柳田國男が発見した「こなきじじい伝説」
なぜ、それまでほとんど知られていなかったというと、
あまりにローカルな妖怪だったからである。
こなきじじいは阿波の国(徳島県)の山奥の出身だ。
この妖怪を“発見”したのは、民俗学者の柳田國男である。
阿波の山分の村々で、山奥にいるといふ妖怪。
形は爺だといふが赤児の啼声をする。
或は赤児の形に化けて山中で啼いてゐるともいふのは
こしらへ話らしい。
人が哀れに思って抱き上げると俄かに重く放そうとしてもしがみついて離れず、しまひにはその人の命を取るなどゝ、ウ
ブメやウバリオンと近い話になって居る。
木屋平の村でゴキヤ啼きが来るといつて子供を嚇すのも、
この児啼爺のことをいふらしい。(後略)
柳田國男『妖怪談義』1956
この記述から、水木しげるがあの金太郎の腹掛けをした
こなきじじいの姿を描き出した。
僕たちはこうした妖怪の話は大昔から地域の伝説として伝わっていると思い込んでいるが、じつはそうでもなくて、
このこなきじじいの話などは割と最近のことらしい。
●こなきじじいの正体は実在の徘徊じいさん
以下は妖怪小説の大家・京極夏彦氏の「妖怪の理 妖怪の檻」
(角川書店/平成19年)の記載事項(を僕なりにアレンジ)。
上記の柳田國男の記事を読んで、
本当にこんな妖怪がいるのだろうか?
と疑問を抱いた地元・徳島の郷土研究家が
詳細な現地調査を行ったそうだ。
柳田國男もまたある文献をもとに記事を書いたので、
そのネタ元をもとにあちこち調べまくったというから、
すごい情熱・執念である。
その結果、本当にこなきじじいがいた、
❝実在していた❞〝ということが判明した。
大昔の伝説でもファンタジーでもなく、リアルな事実。
その正体は、赤ん坊の泣き真似が得意で、
泣き真似をしながら山の中を徘徊していた、
実在の爺さんだったのだ。
ある家で子どもが悪さをしたり、言うことを聞かなかったりすると
「山からじじいが来るよ」と、嚇しのネタに使っていたという。
それが妖怪こなきじじいの出生の秘密だったのだ。
まさしく驚愕の事実。
●年寄りなんてそんなもの
柳田國男が収集したそのネタ元が、
いったいいつの時代のものかわからないが、
話の成り行きから察するにそう大昔のものとは思えない。
昭和初期くらいの話なのではないかと思える。
こなきじじいの歴史は100年に満たないのでないか。
それにしても赤ちゃんお鳴きまねをして
山中を徘徊している爺さんって・・・
いまの時代ならとても放っておいてもらえないだろう。
変質者として通報され、警察に保護されるか、
認知症患者として病院に連れていかれるに違いない。
昔はよく言えばおおらか、悪く言えばいい加減だったので、
こうしたこなきじじいも自由にしていられた。
そもそも年寄りはそんなもの、
齢を取れば大半の人間は、生産的な現実世界とは異なる、
妖怪的な世界の住人になっていく。
そんな暗黙の了解というか、
こころやさしい認識があったのかも知れない。
●ねこなきじじいは令和の妖怪?
そう考えて、ふと自分のことに思い至った。
そういえば昨日も義母と散歩の途中でネコに逢い、
にゃーにゃ―ネコの鳴きまねをしていた。
これは僕の得意技で、
いつもこれでネコを手なづけようとしている。
(が、ほとんど効果がない)
これはもう「ねこなきじじい」ではないか。
将来、認知症になって、ねこなきじじいとして妖怪伝説となる———
そういう未来が待っているのかも知れないニャー。
そうしたら、ネコ娘はなかよくしてくれるだろうか?

●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・どうして僕はロボットじゃないんだろう? ¥318
ASIN: B08GPBNXSF
・ピノキオボーイのダンス ¥500 ASIN: B08F1ZFLQ6
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
義母とざしきわらし
義母がいつも散歩で楽しみにしているのは、
カモ、イヌ、子どもである。
ネコはどっちかというと僕の楽しみだ。
善福寺川で涼しそうに泳いでいるカルガモは25羽にもおよぶ。
日によってはコサギ(白い鷺)、カワウ(黒い鵜)、
アオサギ(大型のグレーの鷺)なども混じっている。
こいつらが水に頭を突っ込んだり、バシャバシャやっている風景が
平和で楽しげみたいなのだ。
イヌと子どもはリアクションがあるので面白いみたいだ。
彼女は臆病なので、じつはイヌはけっこう怖がる。
ソーシャルディスタンスを取って遠目で見るならいいが、
特にラブラドールなどの大型犬が近くに来るのは怖いらしい。
だけど、つい「かわいいねえ」などと言ってしまう。
散歩しているイヌの7割くらいは、
この「かわいい」という言葉がわかるので、
それを聞きつけて「はいはい、かわいがって」と
義母のもとに寄って来るのだ。
その時の彼女のちょっと緊張した顔がけっこう面白い。
その点、人間の子どもは安心だ。
特に1~3歳くらいのおチビさんはにっこり反応して
手を振ってくれたりする子が多い。
そうした義母と子どもとのやりとりを傍で見ていると、
僕は内心「今日はざしきわらしに逢えた」と思う。
子どもの姿をしたざしきわらしという妖怪に逢うと、
幸運になると言われる。
昔はせっかくこの世にオギャーと生まれてきても、
大きく育つ前に死んでしまう子どもが多かった。
特に東北地方の貧しい農村などでは
病気や事故はもとより、
家族が食っていくために間引きされることも
少なくなかった。
なので小さい子どものイメージは
現代とはずいぶん違っていたのだろう。
「7歳までは神のうち」などとも言われるが、
“将来、人間として生きるかもしれない”
精霊に近い存在だったのではないかと思う。
たぶん、ざしきわらしの伝説は、
そうした幼くして逝ってしまった
子どもたちのことを偲んで生まれたものなのだろう。
いずれにしても、散歩でざしきわらしに逢えると
義母の中に幸福のタネが一つ植わる。
家に帰るころにはもう忘れているんだけど、それでもいいのだ。
夏の魔法のネコ時間

猛暑日でもわりと涼しい。
たぶん都心のコンクリ・アスファルトだらけのエリアより
2~3度は低いのではないだろうか。
なので朝や夕方は義母を連れて散歩する。
夕方は夕涼み中のネコと出くわす。
特にこのクロネコは頭の上を飛来するカラスにも、
散歩中のイヌにも、
わいわい寄ってくる人間にも、
まったく動じることなく、
いつも道の真ん中でゴロゴロして
自由気ままに真夏の夕べを満喫している。
僕はいつも彼(彼女かもしれない)を
ソーシャルディスタンスを保ってフォローし、
写真を撮らせてもらう。
おかげでスマホの中はクロネコだらけだ。
僕の友だちはクロネコだが、
義母の友だちは、この周辺の野良猫たちを
手なづけているネコ使いのばあさんだ。
ここんとこ毎日のように会うので、
すっかり顔なじみになって井戸端会議を始める。
はたで見ていても何の違和感もない。
ネコ使いのばあさんは、うちの義母が認知症だとは
夢にも思わないだろう。
午後6時の♪夕焼け小焼けの歌が流れると、
家路に向かう(といってもここから5分くらいだ)
家に帰って夕食時、「きょうもクロネコちゃんと
ネコ使いのばあさんに会えて楽しかったね」と話すと、
「え、ネコ? 何のこと?」と、と、なんにも憶えていない。
夢でも見たんじゃないの?って顔をされてしまう。
けれども翌日、あの道を通れば
「ああ、昨日はどうも。また今日も会いましたね」と
記憶がつながるのだろう。
けっこう奇妙な日々を送っているような気がするが、
まぁ、今日も無事に楽しく生きられました、ということで合掌。
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・ピノキオボーイのダンス ¥500 ASIN: B08F1ZFLQ6
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
「人新世(アントロポセン)」を生きる

イギリスの作家が書いた動物に関する本を読んでいて
「人新世(じんしんせい/ひとしんせい)」
という言葉に出逢った。
英語でAnthropocene(アントロポセン)。
現在私たちは「人新世」と呼ばれる、
生命の歴史において、かつてなかったほどの
大規模な絶滅と転換の時代に生きている
と、その作家(およびサイエンスジャーナリスト)は言う。
地質時代の区分では、最終氷河期の終わる
およそ1万年前から現在までを「完新世」と呼ぶ。
この完新世において、地球のシステムに唯一最大の
影響を与えているのが人類。
そうした認識に基づき、この「人新世」という新しい年代が
発案されたという。
2008年には、これが地質学者らの賛同を得た。
この年代が始まった時期については諸説あるようだが、
やはり化石燃料を消費し始めた産業革命以降、
この200年のことと考えて間違いないだろう。
特に20世紀後半以降、ここ半世紀余りの繁栄による
大量消費はすごかった。
それが今年、コロナによって世界中の経済活動が減退。
それによって世界各都市の大気が浄化されたとか、
ベネツィアの運河にイルカがやってきたとか、
地球環境には良い影響が出ているとかいう話もあったが、
そう単純なものとは思えない。
コロナで人の行き来に支障が出たら
国際協調もままならないだろう。
今年の夏も九州で大規模な豪雨被害が出た。
被災する場所は、地盤の緩い、かつて(明治時代以前)は
人が住まなかった土地だという話も聞こえてくる。
そうしたところを宅地にしたり、工場を建てたり、街を作るなど、
人間の生活圏として開拓してきたわけだが、
その考え方自体が無理なんじゃないかという気がする。
もう「100年に一度」だとか「数十年に一度」だとかいう
言葉ではごまかせない。
温暖化が原因となって毎年豪雨被害、台風被害は起こると
思っていたほうがいい。
もう昔には戻れない。
かといって、目先の経済を無視しては
明日からの生活も立ちいかなくなる。
結局、防災にしてもコロナ対策にしても、
国に頼らず、マスコミなどの情報も鵜呑みにせず、
自己責任でやっていくしかないようだ。
そして「人新世」に生きているという、
地球視点、野生動物視点も持っていると、
これから先、何かの役に立つかも知れない。
少なくとも動物や植物に愛しみの心をもったほうが
幸福になれるのではないだろうか。
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873 ¥321
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
あなたが求めているもの・怖がっているものと神ってるナマケモノ

おりべまこと電子書籍 週末限定3冊連続無料キャンペーン続行中。
本日、7月12日、日曜日16;00から24時間は
「神ってるナマケモノ」です。
「動物にまったく興味がない」という人間は
この地球上に存在しない。
意識していようといまいと、僕たち人間は、
はるか昔の祖先の時代から、ずっと自らに問いかけ続けている。
自分という存在、あるいは
自分が求めているものや怖がっているものと、
こいつらはいったいどんな関係があるのだろう?
動物学者でもなく、飼育係でもなく、
金魚とミドリガメ以外、一度もペットを飼ったことのない僕も、
生まれてこれまでことあるごとに、
この問題について考え続けてきた。
すると、木にぶら下がっているだけの、あのナマケモノさえも
じつは人間にとって大切なことを教えに来た
神の化身ではないかと思えてくる。
このブログでも大人気の
「なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?」
「ウーパールーパーな女子・男子」
「金魚の集中力は人間以上」
「結婚記念日の花束と、ネコのいる花屋と、花を食べるネズミの話」
「四国化け猫➡猫神さま伝説」
「犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業」
など36編を収録。
ぜひあなたもペットや動物たちとあなたの人生、
あなたの生きる社会、あなたの生きる世界を
リンクさせてみてください。

Amazon Kindle 電子書籍
7月12日(日)16;00 ~
13日(月)15:59
無料キャンペーン
おりべまこと
「神ってるナマケモノ」
可愛いくて、楽しくて、笑える彼ら。奇妙で、不気味で、不思議な彼女ら。美しくて、おぞましくて、くさくて、汚くて、怖くて危険なやつらも。
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちといっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた面白エッセイ集。
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
※上記3冊について7月10日(金)~13日(月)まで
週末限定無料キャンペーン実施中
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
おりべまこと電子書籍 週末限定3冊連続無料キャンペーン
7月10日(金)から13日(月)まで
おりべまことエッセイシリーズ3作品の
無料キャンペーン実施。
この機会にAmzon Kindle電子書籍で ぜひどうぞ。
スマホがあれば無料アプリを入れてすぐ読めます!
・7月10日(金)16:00~11日(土)15:59
ロンドンのハムカツ
・7月11日(土)16:00~12日(日)15:59
子ども時間の深呼吸
・7月12日(日)16:00~13日(月)15:59
神ってるナマケモノ

7月10日(金)16:00~11日(土)15:59
ロンドンのハムカツ
「食」こそ、すべての文化のみなもと。
その大鍋には経済も産業も、科学も宗教も、
日々の生活も深遠な思想・哲学も、すべてがスープのように溶け込んでいる。
「食べる」を学び、遊び、モグモグ語るおりべまことの面白エッセイ集。ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から33編を厳選・リライト。
もくじ
・お米と田んぼとお母ちゃんのニッポン!
・お米を研ぐ理由と人間の味と匂いの話
・フツーのおにぎりでも日本のコメなら800円!?
・ロンドンのハムカツ
・スーパーマーケット・イン・マイライフ
・植物のいのちは人間・動物より高次元にある ほか

7月11日(土)16:00~12日(日)15:59
子ども時間の深呼吸
だれの心のなかにも「子ども」がいる。
自分のなかの子どもにアクセスしてみれば、何が本当に大切なのか、何が必要なのか、幸せになるために何をすればいいのか、どう生きるのか。自分にとっての正解がわかる。〈少年時代の思い出〉×〈子育て体験〉×〈内なる子どもの物語〉でモチモチこねた面白エッセイ集。ブログから40編を厳選・リライト。
もくじ
・大人のなかの子ども、子どもの中のおとな
・ちびちびリンゴとでかでかスイカ
・天才クラゲ切り:海を駆けるクラゲ
・子ども時間の深呼吸
・卒業式の詩と死
・働くシングルマザーと生活保護のシングルマザーの価値観
ほか

7月12日(日)16:00~13日(月)15:59
神ってるナマケモノ
可愛いくて楽しくて笑える彼ら。奇妙で不気味で不思議な彼女ら。美しくておぞましくて、くさくて汚くて怖くて危険なやつらも。僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちと暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた面白エッセイ集。ブログから36編を厳選・リライト。
もくじ
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ ほか
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・神ってるナマケモノ ¥321 ASIN: B08BJRT873
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
★上記キャンペーン編期間中は無料です。
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
神ってるナマケモノ 週末限定無料キャンペーン 今日午後4時59分まで

おりべまこと電子書籍「神ってるナマケモノ」の第1回無料キャンペーン実施中。
本日、6月28日(日)午後4時59分までです。
この機会に、ぜひどうぞ。
可愛いくて、楽しくて、笑える彼ら。
奇妙で、不気味で、不思議な彼女ら。
美しくて、おぞましくて、くさくて、汚くて、
とてつもなく怖くて危険なやつらも。
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちと
いっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、
人間の世界観の大きな領域をつくってきた
仲間たちについてのエピソードや、
あれこれ考えたことを編み上げた面白エッセイ集。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から36編を厳選・リライト。
内容
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・ヌード犬・ファッション犬
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上
・アザラシの入江でヤギの乳を搾ってチーズを作る娘
・ロンドンのリスとイヌとネコ
・ピーターラビットの農的世界への回帰現象
・京龍伝説
・失われたPTAコラムとライオンの面倒を見るコアラの話
・カエル男のスキンケロ情報
・迷子の猫とネコ探し名人ナカタさんのこと
・住宅街のヘビーなアナザーワールド
・おいらセイウチ
・カラス対ガマガエル 真昼の決闘
・ネコミュニケーションをスキルアップして、ネコから情報を取得する野望
・アポトーシスによって消失するオタマジャクシの尻尾と、
これからの人間の進化のパラドックス
・結婚記念日の花束と、ネコのいる花屋と、花を食べるネズミの話
・なぜプードルもチワワもダックスフンドも“いぬ”なのか?
・見タカ、聞いタカ、朝タカ情報
・野生の本能の逆流に葛藤する都会暮らしのネコ
・いつも心にカメを
・カエルの歌が聞こえてくるよ
・四国化け猫➡猫神さま伝説
・ヘビ女・ワニ男のパワーアイテム
・バニーガールと会ったお話、そして、女子はなぜウサギが好きなのか?
・クローン犬ビジネス
・『鳥のように自由に」と80歳になって語れるか?
・ヤモリは家守。かわいく、さりげなく守り神
・田町駅のペディストリアンデッキの鳩
・ぼくらはにおいでできている(チワワのハナちゃんに教えてもらったこと)
・地球に生きる人間の数と、人間の適正な大きさについての疑問
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ
★本日のちょっと立ち読みは、
「おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖」

近所の道端で御用を足して、
飼い主さんにお尻をふきふきしてもらっているイヌに
ときどき出会う。
このときのイヌたちは皆、
一様に「テヘヘヘヘ・・・」という顔をしている。
今日会ったのはポメラニアンの女の子(服装から判断)だったけど、これはラブラドールだろうが、ダックスだろうが、
トイプーだろうが、シバだろうが、
ほんとにおんなじような顔をしているので面白い。
「ちょこっと恥ずかしいけど、ハッピー♡」
といった感じだろうか。
こういうイヌたちは姿かたちはイヌのままなれど、
顔つきだけは人間そっくりだ。
どうも自分は今、四足で歩いているけど、
大人になったら飼い主みたいに二本足で歩く人間になる――
そう思い込んでいるやつが多いのではないだろうか。
僕は、ちゃんとけじめをつけなきゃならんと思い、
「きみはイヌ。いつまでたっても四足。ずっと子ども。
死ぬまで人間にはなれないの」
と心の中で叫ぶ。
しかしもちろん、そんなことは口に出して言わない。
せっかく幸せな思いをしているイヌの夢を
壊すのもなんだなぁと思うし、
そんなことをいきなり言おうものなら、
イヌより先に飼い主に噛みつかれそうだからだ。
ただ「テヘヘヘヘ・・・」という顔をしている彼ら・彼女らを
5秒間じっと見つめ、最後にウィンクし、
黙って去っていくだけである。
そんな僕を、彼ら・彼女らは
「テヘヘヘヘ・・・」の顔のまま見送っている。
いつか大きくなったら人間に・・・という希望を抱きながら、
だんだん年老い、疲れ、やがて体も頭も動かなくなって
人間の家族らと死に別れることを知っているんだろうか・・・
と不憫に思いつつ。
それにしても「きみはイヌ、わたしは人間。
人間には逆らっちゃダメ」ってちゃんと教えている飼い主は
どれくらいいるのだろうか?
もう一つ、イヌのお尻を拭いている飼い主は決まって女の人で、
男の人にはまだお目にかかったことがない。
これはたまたまなのだろうか?
男はお尻の世話までしないのかなぁ?
●電子書籍 AmazonKindle より販売中
・神ってるナマケモノ ASIN: B08BJRT873 ¥321
※6月28日(日)午後4時59分まで無料キャンペーン中
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー
「ASIN: B08BJRT873」、または「おりべまこと」、
または書籍名「神ってるナマケモノ」を入れてアクセス。
●Kindle無料アプリを入れればスマホやタブレットで読める!:
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980でKindle本が読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
神ってるナマケモノ 週末限定無料キャンペーン実施中

おりべまこと電子書籍第6弾「神ってるナマケモノ」の無料キャンペーンを、6月26日(金)午後5時から、28日(日)午後4時59分まで実施中。この機会に、ぜひどうぞ。
可愛いくて、楽しくて、笑える彼ら。
奇妙で、不気味で、不思議な彼女ら。
美しくて、おぞましくて、くさくて、汚くて、
とてつもなく怖くて危険なやつらも。
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちと
いっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、
人間の世界観の大きな領域をつくってきた
仲間たちについてのエピソードや、
あれこれ考えたことを編み上げた、面白エッセイ集。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から36編を厳選・リライト。
内容
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・ヌード犬・ファッション犬
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上
・アザラシの入江でヤギの乳を搾ってチーズを作る娘
・ロンドンのリスとイヌとネコ
・ピーターラビットの農的世界への回帰現象
・京龍伝説
・失われたPTAコラムとライオンの面倒を見るコアラの話
・カエル男のスキンケロ情報
・迷子の猫とネコ探し名人ナカタさんのこと
・住宅街のヘビーなアナザーワールド
・おいらセイウチ
・カラス対ガマガエル 真昼の決闘
・ネコミュニケーションをスキルアップして、ネコから情報を取得する野望
・アポトーシスによって消失するオタマジャクシの尻尾と、
これからの人間の進化のパラドックス
・結婚記念日の花束と、ネコのいる花屋と、花を食べるネズミの話
・なぜプードルもチワワもダックスフンドも“いぬ”なのか?
・見タカ、聞いタカ、朝タカ情報
・野生の本能の逆流に葛藤する都会暮らしのネコ
・いつも心にカメを
・カエルの歌が聞こえてくるよ
・四国化け猫➡猫神さま伝説
・ヘビ女・ワニ男のパワーアイテム
・バニーガールと会ったお話、そして、女子はなぜウサギが好きなのか?
・クローン犬ビジネス
・『鳥のように自由に」と80歳になって語れるか?
・ヤモリは家守。かわいく、さりげなく守り神
・田町駅のペディストリアンデッキの鳩
・ぼくらはにおいでできている(チワワのハナちゃんに教えてもらったこと)
・地球に生きる人間の数と、人間の適正な大きさについての疑問
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ
それでは本日のちょっと立ち読み。
「なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?」

「かえるくん、東京を救う」というのは、
村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品だ。
主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、
というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説に近い。
しかし、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまう。
この話は1995年に起こった阪神大震災とオウム真理教事件をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのだが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザっぽかったりして独特の作品世界が出来上がっている。
しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思った。
このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないだろうか。しかもその振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気がする。
欧米ではカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の助手とか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い。
ところが日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、文学・サブカルチャーの中で、かわいい系・愛すべき系の系譜がしっかりと存在している。
僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないだろうか。
お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。
そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのだろう。
カエル君に対する良いイメージはそういうところからきている気がする。
ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」と呼ばれている。
茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。
やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろう。
雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってない。ケロケロ。
●電子書籍 AmazonKindle より販売中
・神ってるナマケモノ ASIN: B08BJRT873 ¥321
※6月28日(日)午後4時59分まで無料キャンペーン中
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー
「ASIN: B08BJRT873」、または「おりべまこと」、
または書籍名「神ってるナマケモノ」を入れてアクセス。
●Kindle無料アプリを入れればスマホやタブレットで読める!:
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980でKindle本が読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
神ってるナマケモノ 週末限定無料キャンペーン
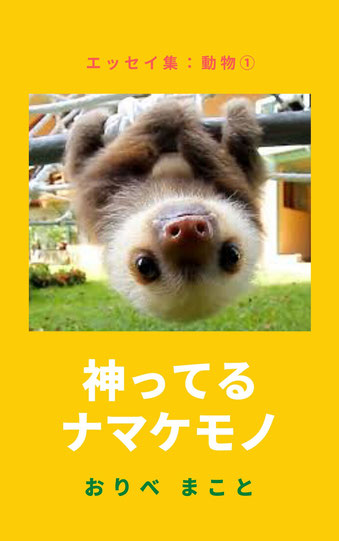
おりべまこと電子書籍第6弾「神ってるナマケモノ」の
無料キャンペーンを、本日、6月26日(金)午後5時から、
28日(日)午後4時59分まで行います。
この機会に、ぜひ読んでみてください。
可愛いくて、楽しくて、笑える彼ら。
奇妙で、不気味で、不思議な彼女ら。
美しくて、おぞましくて、くさくて、汚くて、
とてつもなく怖くて危険なやつらも。
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちと
いっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた、おりべまことの面白エッセイ集。
ブログ「DAIHON屋のネタ帳」から36編を厳選・リライト。
内容
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・ヌード犬・ファッション犬
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上
・アザラシの入江でヤギの乳を搾ってチーズを作る娘
・ロンドンのリスとイヌとネコ
・ピーターラビットの農的世界への回帰現象
・京龍伝説
・失われたPTAコラムとライオンの面倒を見るコアラの話
・カエル男のスキンケロ情報
・迷子の猫とネコ探し名人ナカタさんのこと
・住宅街のヘビーなアナザーワールド
・おいらセイウチ
・カラス対ガマガエル 真昼の決闘
・ネコミュニケーションをスキルアップして、ネコから情報を取得する野望
・アポトーシスによって消失するオタマジャクシの尻尾と、
これからの人間の進化のパラドックス
・結婚記念日の花束と、ネコのいる花屋と、花を食べるネズミの話
・なぜプードルもチワワもダックスフンドも“いぬ”なのか?
・見タカ、聞いタカ、朝タカ情報
・野生の本能の逆流に葛藤する都会暮らしのネコ
・いつも心にカメを
・カエルの歌が聞こえてくるよ
・四国化け猫➡猫神さま伝説
・ヘビ女・ワニ男のパワーアイテム
・バニーガールと会ったお話、そして、
女子はなぜウサギが好きなのか?
・クローン犬ビジネス
・『鳥のように自由に」と80歳になって語れるか?
・ヤモリは家守。かわいく、さりげなく守り神
・田町駅のペディストリアンデッキの鳩
・ぼくらはにおいでできている
(チワワのハナちゃんに教えてもらったこと)
・地球に生きる人間の数と、人間の適正な大きさについての疑問
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ
ちょっと立ち読み。
「ネコのふりかけ」

もう前世の記憶に近いが、そのむかし
「劇団ねこ」という小劇団をやっていた。
なんでそんな名前を付けたのかというと、
管理社会を自由にすり抜け、何者にも縛られず、
ネコのように柔軟に生きながら、
可愛がってくれる人がいれば調子よくニャオンとすり寄り、
ごはんと寝床をせしめたい。
そんなメッセージを、演劇を通して発信しようとしていたからだ。
というのは今しがた考え付いた、まったくのこじつけだけど、
潜在的にはそんな気持ちがあったのだと思う。
劇団ねこは三〇年以上も前に消滅してしまい、座長と演出をやっていた男も十年前に死んでしまった。
けれども最近のネコのモテモテぶりに触れると、
現代を生きる人たちの心の奥底には、
冒頭に書いたような、ネコのように生きたいという思いが、
ずっとくすぶり続けているのでないかと推測する。
そして、その思いは三〇年前より
ますます強くなっているのではないかと感じる。
こんなことを言っては申しわけないけど、受験生とか、
就活している若者たちとか、その親とかの顔を見ると、
何に縛られているのかさえ分からなくなってしまって、
もう闇雲にネコ的なものを求めたくなっているように思える。
だから、絵本も写真集もテレビ番組も、ネ
コを使えばみんなが観てくれるし、
ファッションもグッズも
「ネコのふりかけ」をかければ魔法のように美味しくなる。
こんなにも身近にいながら野性を感じさせてくれ、
しかも基本的に安全。
人間に甘えてくれるけど、
そうかといって媚びているわけではなく、
独立性を保っている(少なくともそう見える)。
もはやネコは人間にとっての夢の存在であり、
希望の星と言っても過言ではない。
この先、テクノロジーが進むとともに、
人間のネコ依存症はますます深まっていくのではないだろうか。
すると何が起こるか?
そうだ、AIを搭載したネコを作ろう――という発想が生まれる。
というわけで、ネコ型ロボット・ドラえもんの誕生だ。
そうなると逆転現象が起こって、
僕たちはのび太くんのように
ネコのドラえもんに甘えるようになるだろう。
そして、ドラえもんにいろんな夢をもらうようになる。
ネコのふりかけは未来まで果てしなく効能を発揮する。
そうか「劇団ねこ」の演劇は、ドラえもんに繋がっていたのかと、前世の記憶が新たな発見を伴ってよみがえった今宵。
いずれ、ネコとロボットをテーマにしたお話を書いてみたい。
●電子書籍 AmazonKindle より販売中
・神ってるナマケモノ ASIN: B08BJRT873 ¥321
※6月26日(金)午後5時から、28日(日)午後4時59分まで無料
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー
「ASIN: B08BJRT873」、または「おりべまこと」、
または書籍名「神ってるナマケモノ」を入れてアクセス。
●Kindle無料アプリを入れればスマホやタブレットで読める!:
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980でKindle本が読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
サギとカワウとカルガモのザ・リバー
近所の善福寺川には、いろいろな水鳥が雑居している。
今朝は雨の中、カルガモをはじめ、
コサギやカワウまで飛んでいてにぎやかだった。
きょうはいなかったかが、アオサギも時々見かける。
サギと言えば魚を食べる水鳥だが、
昨日の「ダーウィンが来た!」(NHK)を観ていたら
イタリアではサギがネズミを食べていると聞いてびっくり。
イタリア北部に乳牛を育てるための牧草地があるのだが、
ここはロクに手入れもしないでほったらかし。
ほったらかしには理由があって、
その中に自然に生えてくる、ある雑草を牛のエサにすると、
バクテリアの影響で牛乳をチーズにしたとき、
独特の風味がつくのだそうだ。
こうして出来上がるチーズが
「パルジャミーノ・レッジャーノ」。
イタリア産のチーズの王様だ。
ところがこの牧草地、手入れもせず、
もちろん農薬も使わないので、
畑にいろんな虫が湧いたり、ネズミ天国になる。
その虫やネズミを食べに猛禽類をはじめとする、
いろんな鳥が集まってくる。
生態系はホントよくできている。
それにしても水鳥のサギが魚をとらず畑に来て
タカやフクロウに混じってネズミを食ってるとは・・・。
善福寺川のサギはさすがにそれはなさそうだ。
しかし黒いカワウは、いったい何を食っているのか、
春先はしょっちゅう川にサーモンピンクのウンコを垂れていた。
まさかサケを食っているわけではないだろうけど。
いつも散歩コースにしている
成園橋から白山前橋の間の約100メートルは
カルガモの居留区になっている。
義母がカモ好きなので、
通ると一生懸命見ているのでちょうどいい。
カモに年寄りのお守をしてもらっているみたいだ。
これもアニマルセラピーの一種?
もちろん、その上流・下流にも行くが、
この辺がいちばん落ち着くようで、
他の区域にいない時でも、必ずここにいっくと何羽かいる。
多い時は1ダースくらいいてガアガアやっている。
その中で1羽、ヒナと思しきカモを発見。
もうだいぶ大きくなっているが、明らかに他の連中よりチビだし、
観察していると、懸命に親の後をついて泳いでいる。
ここで生まれ育ったのか、
他のところから引っ越していたのか定かでないが、
カラスやネコにやられずに無事、大人になってくれぃ。

電子書籍第6弾 神ってるナマケモノ発売!
ASIN: B08BJRT873 ¥321
可愛いくて、楽しくて、笑える彼ら。
奇妙で、不気味で、不思議な彼女ら。
美しくて、おぞましくて、くさくて、汚くて、とてつもなく怖くて危険なやつらも。
僕たちはこの星の上で137万種類を超す動物たちといっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域をつくってきた仲間たちについてのエピソードや、あれこれ考えたことを編み上げた、おりべまことの面白エッセイ集。
「DAIHON屋のネタ帳」から36編を厳選・リライト。
内容
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ ほか
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー
「ASIN: B08BJRT873」、または「おりべまこと」、
または書籍名「神ってるナマケモノ」を入れてアクセス。
●Kindle無料アプリを入れればスマホやタブレットで読める!:
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980でKindle本が読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
電子書籍第6弾「神ってるナマケモノ」発売!

お待ちかね、おりべまこと電子書籍第6弾。
仕事が忙しくて発売が遅れましたが、
なんとか6月に発売できました。
今回は動物エッセイ集。
動物好きなあなた、ぜひ読んでみてください。
可愛いくて、楽しくて、笑える彼ら。
奇妙で、不気味で、不思議な彼女ら。
美しくて、おぞましくて、くさくて、汚くて、
とてつもなく怖くて危険なやつらも。
僕たちはこの星の上で
137万種類を超す動物たちといっしょに暮らしている。
イマジネーションを掻き立て、人間の世界観の大きな領域を
つくってきた仲間たちについてのエピソードや、
あれこれ考えたことを編み上げた、
おりべまことの面白エッセイ集。
自身のブログ「DAIHON屋のネタ帳」から36編を
厳選・リライト。
内容
・ネコのふりかけ
・おしりを拭いてもらうイヌの幸せと人面犬の増殖について
・なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?
・ウーパールーパーな女子・男子
・ヌード犬・ファッション犬
・いやしの肉球
・金魚の集中力は人間以上
・アザラシの入江でヤギの乳を搾ってチーズを作る娘
・ロンドンのリスとイヌとネコ
・ピーターラビットの農的世界への回帰現象
・京龍伝説
・失われたPTAコラムとライオンの面倒を見るコアラの話
・カエル男のスキンケロ情報
・迷子の猫とネコ探し名人ナカタさんのこと
・住宅街のヘビーなアナザーワールド
・おいらセイウチ
・カラス対ガマガエル 真昼の決闘
・ネコミュニケーションをスキルアップして、ネコから情報を取得する野望
・アポトーシスによって消失するオタマジャクシの尻尾と、
これからの人間の進化のパラドックス
・結婚記念日の花束と、ネコのいる花屋と、花を食べるネズミの話
・なぜプードルもチワワもダックスフンドも“いぬ”なのか?
・見タカ、聞いタカ、朝タカ情報
・野生の本能の逆流に葛藤する都会暮らしのネコ
・いつも心にカメを
・カエルの歌が聞こえてくるよ
・四国化け猫➡猫神さま伝説
・ヘビ女・ワニ男のパワーアイテム
・バニーガールと会ったお話、
そして、女子はなぜウサギが好きなのか?
・クローン犬ビジネス
・『鳥のように自由に」と80歳になって語れるか?
・ヤモリは家守。かわいく、さりげなく守り神
・田町駅のペディストリアンデッキの鳩
・ぼくらはにおいでできている
(チワワのハナちゃんに教えてもらったこと)
・地球に生きる人間の数と、人間の適正な大きさについての疑問
・犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業
・神ってるナマケモノ
●電子書籍 AmazonKindle より販売中
・神ってるナマケモノ ASIN: B08BJRT873 ¥321
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー
「ASIN: B08BJRT873」、または「おりべまこと」、
または書籍名「神ってるナマケモノ」を入れてアクセス。
●Kindle無料アプリを入れればスマホやタブレットで読める!:
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●Kindle unlimited 1ヶ月¥980でKindle本が読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
明治35年の少女とうさぎ

ブログや電子書籍に挿入する用に、
無料で使える画像をよく探している。
すると時々、思いがけないものに出会う。
これもその一つで「うさぎ 画像 無料」で
検索していったら出てきた。
山本芳翠(やまもと・ほうすい)という
明治時代の洋画家の作品だ。
岐阜の農家の出身だが、少年時代、
葛飾北斎の「北斎漫画」に出会い、
画家を志したという。
日本の西洋画の基礎を作った人のひとりと言える。
パブリックドメインのこの作品には
「おまちかね」という洒落たタイトルがついている。
ハイカラさん風の少女にウサギが
ニンジンをおねだりしているのが可愛い。
昔も今も、子どもでも年寄りでも、女性はウサギ好きである。
加えて日本の文化のなかでは
女の子とウサギはシンクロ率が高いというか、親和性がある。
「いなばの白兎」とか「かちかち山」などの
頭の切れるウサギには、
なんとなくボーイッシュな女の子のイメージがダブる。
「かちかち山」のウサギなど、
風の谷のナウシカをはじめとする
戦闘少女の原型のようなイメージすらある。

おりべまこと
AmazonKindle電子書籍
ロンドンのハムカツ
「食」こそ、すべての文化のみなもと。
その大鍋には経済も産業も、科学も宗教も、
日々の生活も深遠な思想・哲学も、
すべてがスープのように溶け込んでいる。
「食べる」を学び、遊び、モグモグ語るおりべまことの面白エッセイ集。
自身のブログ「DAIHON屋のネタ帳」から33編を厳選・リライト。
内容
・お米と田んぼとお母ちゃんのニッポン!
・お米を研ぐ理由と人間の味と匂いの話
・永遠の現物支給 : 2018年3月15日
・フツーのおにぎりでも日本のコメなら800円!?
・ロンドンのハムカツ
・インヴァネスのベーコンエッグ ほか
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
近日発売 神ってるナマケモノ 動物エッセイ
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
1Q84の「ネズミを取り出すミケランジェロ」

ミケランジェロは大理石の塊の中にダビデを見出し、解放した。
そう伝えられている。
若い時分、なにか美術関係の本で読んだのだが、
そのときは「ふーん」と思っただけだった。
ま、おれ、彫刻やるわけじゃないし、といったところ。
しかし最近、この言葉こそ創作の真実を表現し、
人生でやるべき最も重要な事ではないかと思うようになった。
彫刻とか芸術作品に限らない。
人はそれぞれ人生をかけてやるべきことを持っている。
それが見つけられるかどうか。
そして見つけたものをわが手で形にして取り出せるかどうか。
それがすべて、と思う。
村上春樹の小説「1Q84」の中で
このミケランジェロの逸話と共通する
印象深いエピソードがある。
女主人公の青豆に対し、
麻布のお屋敷のマダムの用心棒を務めるタマルが電話で、
自分の子ども時代の仲間について語るシーンだ。
タマルは在日コリアンの男で
戦後、樺太から引き上げてきた両親と離れ、
北海道の山奥の孤児院で少年時代を過ごした。
そこでひとりの頭の弱い混血児と友だちになり、
彼の面倒を見ることになる。
というか、いじめる連中から彼を守る用心棒になる。
その混血児が「ネズミを取り出すミケランジェロ」だった。
以下、BOOK2・第17章「ネズミを取り出す」から引用。
木の塊を手に取ってじっと長いあいだ見ていると、
そこにどんなネズミがどんなかっこうで潜んでいるのか、
そいつには見えてくるんだよ。
それが見えてくるまでにはけっこう時間がかかった。
しかしいったんそれが見えたら、あとは彫刻刀をふるって
そのネズミを木の塊の中から取り出すだけだ。
そいつはつまり、木の塊に閉じ込められていた架空のネズミを
解放し続けていたんだ。
タマルは村上作品中、最もハードボイルドな登場人物だ。
彼はゲイなので、青豆(彼女もハードボイルドキャラ)とは
友情関係のようなものを感じているらしい。
彼は14歳のとき、ひとりで生きる決心をし、孤児院を脱走する。
ミケランジェロのその後は知らないと言いつつも、
記憶は離れないと語る。
そいつが脇目もふらずネズミを木の塊から
『取り出している』光景は、
俺の頭の中にまだとても鮮やかに残っていて、
それは俺にとって大事な風景のひとつになっている。
それは俺に何かを教えてくれる。あるいは、何かを教えようとしてくれる。
人が生きていくためにはそういうものが必要なんだ。
言葉ではうまく説明はつかないが意味を持つ風景。
俺たちはその何かにうまく説明をつけるために生きていると思われる節がある。
俺はそう考える。
タマルが語った話の意味を青豆は
「私たちの生きるための根拠」と言い表す。
本筋とは関係ない逸話だが、ひどく胸にしみる場面だ。
人はそれぞれ無意識の領域では自分がやるべきことを知っている。
タマルの友だちのように他にやるべきことを持たず、
(彼は普通の仕事や社会生活に必要なことがまともにできない、
世間的には「とろいやつ」だ)
最初からただそれしかできないという人間は、
ある意味幸福。ある意味天才なのだろう。
僕たち凡人は望むなら
何らかの努力をし、何らかのタイミングで
ダビデなりネズミなりを見つけ出し、取り出さなくてはならない。
もし、それができれば人生の成功と言えるのはずだ。
ただし、世間的成功とイコールではないかも知れないが。

おりべまこと
Amazon Kindle 電子書籍
茶トラのネコマタと金の林檎
20代半ばで独立起業し、6畳一間のアパートの自分の部屋で探偵事務所を開いた私立探偵・飛田健太(とびた・けんた)。
その健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れ、“なんちゃってホームズ”のいでたちで現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。
健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、黒服・黒メガネの4人組の男たちがこの山にやってきて、どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし、明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、山中の雑木林に入ってスコップを振るい、肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、コミカルでファンタジックな探偵小説。
●おりべまこと電子書籍
Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
近日発売 神ってるナマケモノ 動物エッセイ
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
ウンコしてオシッコして、切れば血の出る連中とのくらし
新しいエッセイ集「神ってるナマケモノ」の編集を始めました。
今回のは動物エッセイです。
動物を観たり、動物について考えたりすると、
人間とは何者か見えてくる。
一緒に住んでいるこの地球がどういう星なのか見えてくる。
動物は可愛くて、面白くて、楽しくて、不思議で、不気味で、
気持ち悪くて、怖い。
でもこの形容詞はすべて人間にも当てはまります。
そうではありませんか?
生きててウンコやオシッコして、
切れば血の出る連中は汚らしいので、
みんな機械にしてしまえば、
クリーンで明るい世界になるでしょう。
でも、そういう世界になったら、人間は生きていけないでしょう。
きっとどこかの牢獄に入れられたような気持ちになって
発狂してしまうでしょう。
そんなことを感じてもらえる本になればいいと思います。

おりべまこと電子書籍
茶トラのネコマタと
金の林檎
20代半ばで独立起業し、6畳一間のアパートの自分の部屋で探偵事務所を開いた私立探偵・飛田健太(とびた・けんた)。
その健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れ、“なんちゃってホームズ”のいでたちで現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。
健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、黒服・黒メガネの4人組の男たちがこの山にやってきて、どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし、明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、山中の雑木林に入ってスコップを振るい、肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、コミカルでファンタジックな探偵小説。
●おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
善福寺カモの赤ちゃんはいずこへ?
神田川のカルガモの赤ちゃん目撃情報を聴いてから、
どうしてわが散歩コースの善福寺川のカルガモには
赤ちゃんができないのかと、ずっと疑問を抱えて
5月を生きてきた。
最近、カルガモさんたちは
夕日がきれいな白山前橋付近で
いつも気持ちよさそうにスイスイ泳いだり、
岸に上がってくつろいだり、
なぜだか時折、「ガーガー」と
大声を上げたかと思うと、
バサバサと羽を広げて舞い上がり、
初夏の空に見事に飛翔したりする。
どこへ飛んでいくのか分からないが、
また翌々日になるとちゃんと川に戻っていて、
水の中に首を突っ込み、藻かなんかを食べている。
その様子を見ながら5月も終わりの本日、
僕ははたと気が付いた。
あの「ガーガー」という大声は
「カーカー」というカラスに抗議するかのような声だ。
カラスはカルガモの天敵だ。
そういえば以前、神田川でカルガモが
生まれたばかりの赤ちゃんを1ダースほど
連れて泳いでいたのを発見したことがある。
保育園の子どもたちが「かわいい」と言って
大はしゃぎしていたが、
1日立つごとにだんだん数が減っていき、
1週間もすると2~3羽しか残っていなかったような記憶がある。
この善福寺川周辺はカラスの天国だ。
たぶん赤ちゃんはみんなカラスに食べられてしまったのだろう。
それとも卵のうちにやられてしまったのか・・・。
あの「ガーガー」という鳴き声には
カルガモの怒りと悲しみが篭っている。
この都会の真ん中を流れる川にも
日夜さまざまなドラマがあるのだ。
「そうだよニャ」
と声がするので、ふと振り向くと、
このあたりをねぐらにするワイルドキャット。
ふだんは近所のネコおばさんにねこかわいがりされ、
ニャーニャー甘えてキャットフードをもらっているが。
「赤ちゃんを食べちゃったのは黒いやつだニャ、きっと」
と、ニヤリと笑った。
え? も、もしやおまえ・・。。

おりべまこと電子書籍
茶トラのネコマタと金の林檎
20代半ばで独立起業し、6畳一間のアパートの自分の部屋で探偵事務所を開いた私立探偵・飛田健太(とびた・けんた)。
その健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れ、“なんちゃってホームズ”のいでたちで現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。
健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、黒服・黒メガネの4人組の男たちがこの山にやってきて、どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし、明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、山中の雑木林に入ってスコップを振るい、肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、コミカルでファンタジックな探偵小説。
おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
在宅ワークにカエルの合唱
そろそろカエルの季節です。
うちのそばには川がありますが、さすがにカエルは鳴いてない。
田んぼがないとだめなのです。
そこでYouTubeを探したら、
いっぱいアップされていました。
懐かし・癒しのサウンドスケープ。
やっぱり日本人の故郷は田んぼだね、
ごはんはお米だよね、という感じ。
というわけで最近、仕事のBGMはカエルの合唱。
中でもこれはいろんな種類のカエルが混じっていて楽しい。
カエルのダイバーシティというところでしょうか。
ほどよくうるさくて、なかなか脳にいいのでおすすめです。
あなたも在宅ワークに使ってケロ。


おりべまこと電子書籍
ロンドンのハムカツ
¥326 ASIN: B086T349V1
「食」こそ、すべての文化のみなもと。その大鍋には経済も産業も、科学も宗教も、日々の生活も深遠な思想・哲学も、すべてがスープのように溶け込んでいる。
「食べる」を学び、遊び、モグモグ語るおりべまことの面白エッセイ集。自身のブログ「DAIHON屋のネタ帳」から33編を厳選・リライト。
Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
人間1年生
自分の家系のことは知らないが、
少なくとも貴族やら武家やら商家やら、
由緒正しき家柄ではないことはわかる。
そうした現実的・歴史的なルーツとはべつに、
「前世が〇〇だった」という話を若い頃、よくした。
というか聞かされた。
この手の「なんちゃってスピリチュアル」は、
特に女の子が好きである。
実際、自分は篤姫の生まれ変わりとか、
ハプスブルグ家の皇女だったとか、
まじめに話す子と何人も会った。
正直もう顔も思い出せないが、
彼女らは今頃、おばさんになってどうしているんだろう?
よほどのセレブにでもなってない限り、
齢を取るとなおさら貴族の血が騒いで
現実とのギャップに苛まれるのではないかと心配だ。
それはさておき、前世がお姫様か召使いか、の前に、
そもそも人間だったのか? と考えてみる。
というのも、世の中にはすごい人たちがいっぱいいて、
こういう賢い人たち、器用に生きられる人たちは
もう何回も人間に生まれ変わっていて
経験を積んでいるんじゃないか、
この世の中を泳ぐ要領が最初からわかっているんじゃないかと
思えてしまう。
そもそもあらかじめ持っているスペックというか、
エンジンというか、CPUが違うのだ。
生来の不器用ぶり、知恵の回らなさを考えると、
僕はおそらく今回初めて人間になった1年生である。
では前世は何だったかと言えば、
運動神経も鈍いし、動物占いではコアラなので、
きっとコアラとか、ナマケモノとか、
その手のあまり精力的でも活動的でもない、
森の中でのんびり葉っぱを食べている動物だったのでは?
という気がする。
いずれにしても今回初めて人間になった1年生が
5年生や6年生にかなうわけがない。
還暦になると、いろいろ諦めもつき、
そんなにがんばらなくてもいいやと諦観する。
それでも幸運なことに、
ここまで楽しく面白く、好きなことをやって生きてこられた。
なので1年生の終わりへ向けて
「人間1年生をやってみて」というレポートを
書かなくていけない。
どうもそれが宿題になっているようだ。
というわけで
毎日引きこもって、何千字、何万字と書いている。
宿題出しても2年生になれるのかどうかわからないけど。
落第したら、またコアラやナマケモノに戻るのだろうか?
ま、それでもいいか。

おりべまこと電子書籍
茶トラのネコマタと金の林檎
20代半ばで独立起業し、6畳一間のアパートの自分の部屋で探偵事務所を開いた私立探偵・飛田健太(とびた・けんた)。
その健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。
山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索。
健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れ、“なんちゃってホームズ”のいでたちで現場に飛ぶ。
そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。
健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。
ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、黒服・黒メガネの4人組の男たちがこの山にやってきて、どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。
しかし、明らかに彼女の話はおかしい。
これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?
健太と六郎は、その話を信じたふりをして、山中の雑木林に入ってスコップを振るい、肉体労働に精を出すことになった。
はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?
それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、コミカルでファンタジックな探偵小説。
●Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
手洗い習慣と手抜き人生への道

新型コロナウィルスの感染者・死亡者は、
世界中を見渡して、なぜか男のほうが多いらしい。
その理由は衛生観念の性差のようだ。
要するに一般的にだが、女子の方がきれい好き。
だから手洗いもしっかりする。
一方、男はといえば、駅のトイレに入ればわかるが、
「おれは忙しいんだ」と言わんばかりに、
用を足した後もろくに手を洗わずに出ていく人が大半。
かくいう僕もせいぜいちょろっと
10秒に満たない時間で済ませていた。
だが、コロナの蔓延以来、
これでもかとよく手を洗うようになり、しっかり習慣にした。
アルコール消毒液がいまだに薬局で
品切れなのかどうかは知らないが、
流水だけでも指の1本1本、
手の甲も手首もしっかり洗えば大丈夫である。
むしろアルコールをシュッシュしてそのまま放っておくほうが
付着したウィルスが残存する率が高い。
ちなみに人間が使うエネルギーの2割以上は脳が使う。
なんでも習慣づけて脳を省エネモードで働くようにすれば、
ラクに、手抜きして生きられる。
ただし、習慣として定着させるには平均2カ月かかります。
手抜き人生もラクじゃない?
2カ月間努力して、あなたが習慣づけたいことは何ですか?


だれの心のなかにも「子ども」がいる。
自分のなかにいる子どもにアクセスしてみれば、
何が本当に大切なのか、何が必要なのか、
幸せになるために何をすればいいのか、どう生きるのか。
自分にとっての正解がきっとわかる。
〈少年時代の思い出〉×〈子育て体験〉×〈内なる子どもの物語〉で
モチモチこね上げた おりべまことの面白エッセイ集。
自身のブログ「DAIHON屋のネタ帳」から40編を厳選・リライト。
おりべまこと電子書籍 Amazon kidleより販売中
・子ども時間の深呼吸 ¥324 ASIN: B0881V8QW2
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 1ヶ月¥980で読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
疫病の災禍からケロっとよみガエル

新型コロナウィルスの災禍が早く収まりますように、
と神頼みをしに、杉並大宮八幡宮にお参りしました。
なるべく人出が少ないうちにと思って
午前中に行ったのですが、参拝するのに
こんな長い行列が! と一瞬びっくり。
でもよく見るとソーシャルディスタンスということで、
間隔をあけて並んでいたので長く見えたのでした。
これだけ現金・物質主義の世の中になっても、
日本人は神仏の前では素直に、行儀よくなります。
お参りの後は例によって「しあわせ撫でがえる」
を撫でて、帰ってよく手を洗いました。
「しあわせ撫でがえる」というのはカエルに見立てた
大きな石ですが、その足元にはかわいいチビガエルも。
昔からカエルは薬にも使われ、
健康の縁起物。
アマビコなる妖怪も活躍しているようだし、
科学・医学と日本得意の
森羅万象八百万神的スピリチュアルの合わせ技で
疫病拡散を防ぎましょう。
でもコロナ流行にかこつけた
ヘンなカルト宗教や高額請求のスピビズ詐欺などには
気を付けてケロ。

●おりべまこと電子書籍Amazon kidleより販売中
・ロンドンのハムカツ ¥326 ASIN: B086T349V1
・オナラよ永遠に ¥593 ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ¥329 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ¥328 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/ からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
●kindle unlimited 読み放題
https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true
「みみずくは黄昏に飛び立つ」は、書き手・聞き手のバイブル

ちょうど100年前に書かれた芥川龍之介の「地獄変」と同じく、
みみずくが作品世界の象徴のように登場する現代の傑作が、
村上春樹の「騎士団長殺し」です。
村上氏が「地獄変」を意識したわけではないでしょうが、
この物語も主人公は絵師(画家)で、
何やら現代版の地獄めぐりをイメージさせる物語になっています。
この本は芥川賞作家の川上未映子氏が
2015年から2017年にかけて行った
村上氏へのインタビューをまとめたものです。
時期が「騎士団長殺し」の執筆時期と前後していたので、
川上氏がかの作品に登場する「みみずく」と、
「ミネルヴァのふくろう」
(ローマ神話の女神が従える知恵の象徴)を
かけ合わせて考案したようです。
昨年末に文庫版が出ましたが、
これも文章書きやインタビュアーなら、
バイブルにしたくなるような傑作です。
べつに小説を書いたり、創作活動などやってなくても、
仕事やら、ネットでの活動やら、何らかの理由で、
人に読ませる/読んでもらう文章を書く人なら、
あるいはインタビューをしたり、
質の高いヒアリングをしたい人なら、
参考にできるところがいっぱい見つかると思います。
この本に限らず、村上氏はエッセイやインタビューで
しばしば自らの執筆作法について語っていますが、
これは彼個人にだけでなく、普遍的に通じる法則だなと思います。
ただし、あくまで時間をかけて、コツコツ書く――
ということを前提とした話なので、
「速く、手っ取り早く、効率的にうまい文章が書きたい」
という人はそれ用のマニュアルを使ってください。
誤解を恐れずに言えば、
村上春樹という作家が世の中にもたらした最大の功績は、
多くの人たちに
「誰でも、普通の人でも、物語を作り出すことはできる」
と思わせたことです。
かつて作家とか芸術家の多くは「狂気の天才」でした。
芥川の「地獄変」の主人公の絵師のように、
作品を生み出すためなら
家族や大切な人たちを犠牲にして構わない。
そんな邪悪で醜悪で狂気に侵された人間でなければいけない。
少なくとも世間の常識から逸脱した生き方をしなければだめだ。
長い間、人々そんなイメージを持っていました。
もちろん古今東西そんな作家や芸術家ばかりでなく、
まともな職業につき、社会活動を行い、
良き家庭人として生きる傍ら、
後世に残る名作を生みだした
作家や芸術家は大勢いました。
しかし、そうではない人たちのクレイジーな面、
強烈に個性的な面がクローズアップされ、
誇大広告的に流通していました。
人々がそうした非日常的なものを作家や芸術家に求めていた
という側面もあると思います。
そうしたイメージを覆し、
普通に生活しながら、
机に向かって手を動かじ続ければ誰でも書ける――
ということを村上氏は広く伝えたのです。
もちろん、そう伝えることができたのは、
同氏がこの40年間、リリースしてきた作品が、
ことごとく僕たちの心をつかむ優れたものだったからです。
川上氏は村上氏の全作品はもちろん、
これまでの様々なエッセイや書簡、
インタビュー、雑文などの類も読み込んで、
計4回、最後は村上氏の自宅にまで乗り込んで
インタビューに臨み、話を引き出しています。
ちょっと固い文学論的な対話から、
思わず声に出して笑えるジョークや軽口、
そして、すぽっと懐に入るような質問の投げかけなど、
よくぞここまで胸を開かせた・・・と感心することしきり。
時折見せる、川上氏の小学生の女の子のようなテンションや、
関西弁によるコミュニケーションも
うまく作用しています。
創作活動にしても、インタビューにしても、
本番の、その場でしか発生しないスパークを
いかに瞬間冷凍するかが勝負、
ということを改めて思い知らされました。
そのためにはアスリート同様、
日常のたゆまぬトレーニングが不可欠だということも。
まさしく奇跡のような対話の記録であり、
生き方のバイブルにもなり得ます。
●おりべまこと電子書籍
Amazon kidleより販売中
・オナラよ永遠に ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
から上記コードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
今宵、夢の中で耳木兎は羽ばたき、不苦労な明日を連れてくる

個人的に芥川龍之介の最高傑作だと思っているのが「地獄変」。
これは平安時代の狂気の絵師を描いた、
かなりすさまじい物語です。
この中に登場する「猫によく似た鳥」が耳木兎(みみずく)で、
これが地獄の“怪鳥”として凄惨なシーンを繰り広げます。
ミミズク・フクロウの仲間たちは、
かねてからそのネコ似の風貌と、夜行性の生態で
ミステリアスな、そしてまたちょっと哲学的・文学的な
イメージを醸し出してきました、
明治大学ではフクロウの「めいじろう」が
すでに10年以上、マスコットキャラクターとして活躍するなど、
「学びの守り神」とか「ものしり博士」みたいに扱われ、
そのうえ、かわいいのでモテモテです。
「不苦労」「福来郎」なんて縁起のいい字も当てられて
イメージ的にはカラスやトンビがうらやむほどポジティブ。
うちにもお守りの「不苦労」がいて、、
これは息子が子どもの頃の修学旅行のお土産。
さらにJKローリングの「ハリーポッター」に登場してからは、
その人気にますます拍車がかかり、
近年は「フクロウカフェ」もあちこちにできています。
それでは飽き足らず、かわいくて
自分でペットにしたいという人も激増中。
しかし、冒頭でご紹介した
芥川の「地獄変」ではありませんが、
こいつはやっぱり“怪鳥”の一種。
とまでは言わないものの、猛禽、つまり肉食鳥なので、
エサをやるのは大変です。
スーパーで買ってきた
牛・豚・鶏などパックされた肉なんて食べません。
“生餌”が必要なんですね。
ネズミとかウズラなどの小鳥とか。
内臓なども丸ごと食べられる“全体食”じゃないと
必要な栄養が取れないのです。
ペットショップでは肉食動物用の
冷凍ネズミとか冷凍ウズラとかを売っているので、
それらを与えるようです。
これを残酷だとか、かわいそうとか、
気持ち悪くてダメという人は飼えないし、
フクロウカフェのスタッフも勤まらないでしょう。
夜、脳は知識の工房と化します。
人間の脳は夜、眠って休んでいる間に成長する。
むかしの人はそんな脳科学的なことなど
理屈としては知りませんでしたが、
直感的にそのメカニズムに気づいていたのでしょう。
闇の中を自由に飛翔し、
夜の森の王として君臨するミミズク・フクロウは
世界のどの国・地域でも
そのシンボルとして扱われ、さまざまな物語が生まれ、
彼らのイメージが作り上げられてきたのだと思います。
今宵、あなたも夢の中でミミズク・フクロウを
夜空に羽ばたかせてください。
●おりべまこと電子書籍
Amazon kidleより販売中
・オナラよ永遠に ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
ネコのヒューマニャズム

春は恋の季節。
野生動物の世界では弱肉強食。
ケンカに勝った強いオスがメスを分捕るということが
当たり前とされてきました。
ところが、どこだったかの猫島
(ノラネコがいっぱい住み着いている島)では、
あるメスは、ボスの座についたオスをフッて、
以前に子育てに協力してくれた
イクメンのオスを選ぶこともあるといいます。
前に見た動物ドキュメンタリー番組でやっていた話ですが、
ネコの世界も、人間の世界とどこかでリンクして、
ヒューマニャズムが文化になってきているのだろうか?
と、わりとよく公園でお会いする
この方にお尋ねしてみようと思いましたが、
そもそも♂か♀か存じ上げなかった。
でも、お写真は撮らせていただきました。
うちの近くの公園では、ここ数日、
子どもや、野鳥観察の人たちや、イヌの散歩の人たちや、
たんなる散歩やジョギングの人たちでにぎやかになっています。
そうそう。
引きこもってテレビやネットと首っ引きになっていると
頭の中がウィルス情報に汚染されてしまいますからね。
天気のいい日は外の空気を吸いましょう。
春だからにゃー。
●おりべまこと電子書籍
Amazon kidleより販売中
・オナラよ永遠に ASIN: B085BZF8VZ
・茶トラのネコマタと金の林檎 ASIN: B084HJW6PG
・魚のいない水族館 ASIN: B08473JL9F
●アクセス
https://www.amazon.co.jp/
からコードナンバー、
または「おりべまこと」、または書籍名を入れてアクセス。
●スマホやタブレットで読める:Kindle無料アプリ
https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page
人類を進歩させたのは「やばい食べ物」

今度はエッセイを電子書籍で出そうと思って
自分のブログを漁っていたら、
2年前のバレンタインデーに
「チョコレートは“やばい食べ物”と言われていた時代もある」
といったことを書いていました。
考えてみると、人類発展の歴史とは
「やばい食べ物」を探し求める旅だったと言っても
過言ではありません。
そもそも塩が「人類最初の麻薬」とも例えられるくらい。
だから、縄文人なんかを基準に置いたら、
アルコールはもとより、
砂糖、胡椒、数々のハーブ、スパイス、コーヒー、タバコ、
そしてチョコレート(カカオ)も、
今、世の中にある嗜好品や調味料の類は、
みんな最初は「麻薬」みたいなものだった。
その麻薬を発見し、「こいつはやばい!もっとくれ」と
人々が求め、それに応じて大量生産し、
世界中に行きわたらせることによって、
経済も産業も文化も、この200~300年の間に大躍進。
現代の社会が出現し、今日の姿になったのは、
めっちゃ大雑把に言うと、そういうことではないでしょうか。
僕もチョコレートのない人生よりも、
ある人生のほうが好きなので、
現代に生まれてよかったと思っています。
ところで「やばい食べ物」というのは動物にもあるようで、
ネコを飼ってる人ならみんな知ってると思うけど、
「チャオちゅ~る」というのは相当やばいらしい。
街角のその辺で番張ってる獰猛なノラでも、
これさえあればイチコロで手なずけられると聞きました。
ほんと?
べつにマタタビが入っているわけでもないようで、
メーカーの長年の研究・努力の成果なのでしょう。
最近「ワンちゅ~る」というイヌ用のが出たそうだけど、
こっちもあのCMに出ているワンちゃんたちみたいに
食いつきがハンパないのだろうか?
今年のバレンタインデーは
社内の義理チョコはスルーして
かわいいネコちゃん・ワンちゃんに
ちゅーるをプレゼントする女性が増えてるとかいないとか。
電子書籍第1号「魚のいない水族館」完成

おりべまこと というのは、
芝居をやっていたころのペンネームです。
今回、AmazonKindleで本を出すにあたり、
おりべを復活させることにしました。
戯曲や小説やドラマの脚本は、
どうも本名ではやりにくいので。
昔は漢字表記でしたが、
これ以降はかな表記です。
というわけで去年の夏に書いた
「魚のいない水族館」を電子書籍にしました。
現在レビュー(審査)中なので、
2~3日したら出ると思います。
出たらまたお知らせします。
ずっと紙の本じゃないと納得できない、
みたいな思いがあったのですが、
そうした思い込みというか、
こだわりもなくなりました。
還暦になったせいか?(笑)
いいか悪いか、面白いか面白くないかは
市場が判断してくれるでしょう。
本作は短編で30頁程度のボリュームだし、
すでに推敲済みで原稿をいじる必要はなかったので、
試しに作るにはやりやすかったです。
・・・というと軽く作れたようだけど、
以前のワード原稿は印刷用にレイアウトしていたので、
いろいろ不都合が出て、
結局、いったんメモ帳(シンプルテキスト)に落として、
それをまたコピペして白紙のワードに戻す、といった
ややこしいことをやったので、
結構時間がかかりました。
概念が紙の本と電子書籍ではだいぶ違うので
その混乱から抜け出すのに戸惑った感じ。
プレビューと原稿を見比べながら、
10回くらいアップロードしなおしを繰り返しました。
一応ちゃんと前付きと後付き、コピーライトも入れて
それらしく仕上がったので満足です。
表紙もアプリで、そこそこのものなら
簡単に自分でデザインできます。
今回のは短編小説なので、目次も画像も入れませんでしたが、
今後いろいろ創っていきたいと思っています。
次回は今月終わりから来月初め、
ブログに書いたエッセイを集めたものを出す予定です。
子どもはネズミ好きなのに、 おとなはどうしてネズミが怖いのか?

大みそかに今年の干支に会いました。
真昼間、道路わきの排水溝に
チョロチョロ入って行ったドブネズミ。
危うく自転車でひきそうになってドッキリ。
「縁起がいいからぜひお目にかかりたい」
そう思う人はあんまり多くないと思います。
僕もそうだし、たぶん、あなたも。
しかし、やつらは間違いなく僕たちのそばにいます。
嫌でも付き合わなきゃならない友達みたいなもの。
クマネズミやドブネズミが、
ミッキーやジェリーやピカチュウみたいに
かわいいといいんだけどねぇ。
そういうキャラがいっぱいいるせいか、
イヌやネコを怖がっても、、
ネズミを怖がる子どもは少ないようです。
しかし、なぜかおとなになると
ネズミを怖がるようになる。
家の中にでも出てきた日にゃ大騒ぎだ。
なんでだろう?
悪い病気をまき散らす悪党かと思えば、
日本昔話では金銀財宝をくれたりする
善玉妖精みたいになったりする。
人間とネズミの関係って、
けっこう複雑怪奇で面白い。
ネズミ年(じつは僕の干支でもある)ので、
少しは愛の混じった目で見てあげたいと思いますが・・・。
うーん、難しいな。
2020喪中はがきと終活年賀状

4月に義父が亡くなったので、
毎年、年賀状を戴いている人たちには
今月初めに喪中はがきを出した。
というわけで今年(じゃなくて来年:2020年)は
年賀状1回休み。
もうここ10年ほど、
かつてのように年賀状に一生懸命にもなってなかったので、
特に感慨はないが、
1枚も来ないと思うと、やっぱりちょっと寂しい気もする。
そんな折、「終活年賀状」のニューズを聞いた。
「来年から年賀状を辞退させていただきます」
といった一文を添えて、それっきりにするらしい。
昨年、鎌倉新書がマーケティング会社に登録する
65歳以上のモニター約200人を対象に調査を行った。
その調査によると
「終活年賀状を受け取ったことがある」
という人は57%いるという。
受け取った時、受け取ることを想像した時の気持ちについて、7割近くが「さびしい」と回答した。
「出したことがある」は6%だが、
「送ろうと思っている」と答えた人は半数近くに上った。
理由は「付き合いを身近な範囲にとどめたい」「年賀状作成の負担が大きい」「体力に自信がなくなった」など。
終活年賀状には、挨拶文内に
「これまでのお付き合いへの感謝」
「年賀状をとりやめる理由」
「今後も年賀状以外のお付き合いをお願いする」
という3つの要素を入れるのが基本だという。
今年はウェブサイトで印刷屋さんが
終活年賀状の文例を紹介している。
自分も受け取ることをちょっと想像してみたが、
たぶん上記の7割の回答者と同じく「さびしい」と思うだろう。
僕も年賀状のやりとりは年々減ってきて、
今年、喪中はがきを出したのは40人弱。
学校の1クラス分だ。
その8割以上は、
リアルでもネットでもほとんど会う機会がない。
連絡を取ろうと思えばすぐ取れるけど、
会っても話すことないし、昔話ばっかしてもなぁ・・・・
と思ってて、会わずにずるずる。
中にはもう30年以上会っていない人もいる。
それでも年賀状が来るとほっとする。
最近は虚礼のカテゴリーに入って、
不必要と言う人が多いみたいだけど、
年賀状というのは良い日本の文化だと思う。
というわけで僕は死ぬまで終活年賀状は出しません。
たぶん。
インタビュー術「あなたの健康の秘訣は?」

インタビューをする人は、
相手にこの質問を投げてみるといいと思います。
仕事柄、インタビュー取材が多いのですが、
ビジネス関係だと、通常は仕事の話、商品の話、
サービスの話ばかりになります。
当たり前だけど。
それだけで面白く、興味を持てる記事になる場合も、
もちろんありますが、
それだけだとどうも味が薄いなと思うことの方が多いのです。
“会社を代表して”応じる社員の方は、
選ばれて出てくるだけあって優等生がメイン。
なので、受け答えも無難な模範解答になりがちです。
今時のインタビュー記事に求められるのは、
実はその話している人の人柄です。
どんな人がその仕事について、商品について、サービスについて
語っているのかが結構重要。
読者はその人となりを読み取ろうとします。
もちろん仕事の話のインタビューで、
それがメインになることはあり得ませんが、
この「人間味」という隠し味が効いているのと、いないのとでは
かなり出来上がりの文章のクオリティが違ってきます。
ただし通常のクライアントさんは、
あんまりそんなの気にしません。
それどころか、余計なこと訊いてくれるなという場合が多く、
間に入っているメディアや広告代理店の担当者は、
かなりドキドキハラハラするようです。
でも僕は時間とチャンスがあればやってしまいます。
ただし、プライベートなことに関わってくるので、
「あなたの趣味は?」みたいな質問は良くありません。
親しい友人同士の間がらならともかく、
初対面のインタビュアー、ライターに
こういうことを訊かれたら、
ほとんどの人は反射的に身構えます。
べつにやましいこと、恥ずかしいことをやっているわけじゃなくても、
趣味について語ることは、イコール、人間味をさらけ出すこと。
脳の防御本能が働いてしまう人が大半で、
適当な、当たり障りのない答で逃げられてしまいます。
そこで便利なのがこの「健康の秘訣」というキラークエッション。
一通り要件を訊き終わった後で、
「お元気そうですが、○○さんの健康の秘訣は何ですか?」
と訊いてみる。
これだけストレスという概念が普及した世の中で
仕事をしていて何のストレスも感じてないと言う人は
ほぼ皆無と言っていいでしょう。
なので質問自体は自然だし、
相手も安心して答えてくれる人、
割とノッて答えてくれる人が多い。
そして、その答はたいていスポーツとか、
音楽がやる・聴くとか、趣味の分野と繋がってきます。
すると抵抗なく、趣味や生活習慣、家族などの話に広がっていく。
大病や手術をしたなんて、
ちょっとシリアスな話になる場合もありますが、
そういう告白をする人に対しては、
ちゃんと聞いてあげると、むしろたいへん満足します。
中には「仕事が楽しくてストレスなんてたまらない」とか、
「健康のケの字も考えてない」とか、
「俺の健康の秘訣はタバコをバカバカ吸うことだよ」
なんて返してくる豪傑もいますが、
それはそれで「じゃ、仕事の時以外では
どんなところで活躍しているんですか?」とか、
「じゃ、タバコとかお酒とか詳しいんじゃないですか」とか、
いろいろ展開でき、相手もたいがいそうした話題には
気分を良くしてくれます。
もちろん、このへんの話を全部記事にできるわけではないけど、
相手の人柄がにじみ出してきて、とても面白いです。
機会があればぜひ試してみてください。
ネコとロンリーハートと正義のロンリー

最近、うちの近所はネコ通りが少ない。
イヌ通りはワンさかあるのだが、
ネコはいったいどこにいるんニャ?
と思ってたら、今日は雨上がりの
公園の散歩道で遭遇。
木の上の獲物か何かをにらんで
野性味たっぷり。
と思いきや、おニャカがポヨヨン、
タポタポ状態。
赤ちゃんをはらんでいるのか、
それともメタボなのか。
いずれにしてもお腹が重そうで、
ついに木の上には跳び上がれずじまいだった。
頻繁にエサを上げに来る人がいるらしく、
むかしこの辺にいたネコは糖尿病になって
死んでしまったらしい。
もちろん、エサをあげるのはよくないこと、
人の迷惑にもなるし、
結果的にネコを不幸にするのかも知れない。
けど、ネコに癒しを求める
ひとり暮らしのお年寄りとかに、
そういう正義の味方の論理が通じるのか、と思う。
ひとり暮らしの年寄りでなくても、
寂しい心を抱えた人は増えている。
そんな現代人を救うのに
ネコほど適した動物はいない。
人とネコとの関係は、割とDEEPに考えるべき問題だ。
オス犬は令和の時代も片足を上げてオシッコをするのか?

今日、久しぶりに片足を上げて
電柱におしっこしている犬を見た。
何か心を打たれるものがあった。
なぜ心打たれたのか?
おお、ここにまだオスがいる。
ああ、ここにまだ昭和が残っている。
そう思ったからだ。
片足を上げておしっこするのは、
オス犬の所業である。
彼らはオシッコの匂いによって
「われ、ここにあり」と、
自分の存在の証を立てる。
それを近所の仲間らに知らしめるわけだ。
「ああ、今日ここを山田さんちの
ごっつい秋田犬のケンさんが訪れたのだ。
ケンさんは強くてかっこいいからな」と、
近所の仲間らは認識し、
ケンさんのところからなるべく離れたところで
「ここなら怒られないかな」と、
シャーっとするわけだ。
・・・というのはもはや昭和時代の話なのではないか?
いま、果たしてオス犬たちの間で
街中でこうした仁義を切る習慣は残っているのだろうか?
以前は飼犬の多くは番犬、もしくは猟犬の役割を担っていた。
なので野性の本能が残っており、
ゆえにおしっこマーキングの習慣も
当たり前のように続けられていたわけだ。
しかし時代は流れ、少なくとも街中にいる犬は、
ほとんどが愛玩犬になり、家の中で人間と一緒に
暮らすようになった。
よその犬と争うこともなく、
飼い主さんの言うことを聞いていれば
平和に穏やかに腹を減らせることもないオス犬が
片足を上げておしっこするのだろうか?
街中でそんなことをしたら、、
下品な犬、しつけがなってない犬と見られて、、
飼い主が恥ずかしい思いをするので、
子犬の頃からきちんとしつけられ、
おしっこも管理されるのではないだろうか?
そう言えば昔ロンドンで暮らしていた頃、
公園などを犬が散歩しているのをよく見たが、
片足上げておしっこしている犬は見たことなかった。
そもそも今の生活環境で、
わざわざマーキングして自分の存在を他の奴らに
誇示しなくてはいけない必然性などないように思える。
また、老犬になり、自分の体力の衰えを感じても
オスは頑張って片足おしっこするのだろうか?
さらにまた、イヌの仲間であるキツネやタヌキ、
先祖と言われるオオカミなども、
オスは片足上げておしっこして存在を誇示するのだろうか?
いろいろ疑問が広がるオス犬のおしっこ。
現在の新常識はどうなっているのk?
イヌの飼い主さんがいたら教えて下さい。
サンマの未来はどうなるのか?

●今秋の初サンマ
今年のサンマ、高っ!
スーパーに行くと、いつもチラ見していたが、
たまに「おお安っ!」と思ったのは、例外なく冷凍モノ。
生サンマは一尾300円前後のお値段で推移している。
しかもなんだかダイエットしてきたような
スマートな奴、ヒョロヒョロの奴ばっかりだ。
以前はこの季節、週に一度はサンマを食べてたが、
年々その頻度は減り、
今年は何度か不漁のニュースを聞き、
半ば諦めかけていた。
しかし、昨日はついに一尾100円を切り、96円!
もちろん生、しかもプリプリと太り、脂肪たっぷりだ。
ジュージュー焼いた。
七輪はないので、ガスレンジだが、
それでも十分ジュージュー言って、
きれいに焼けた。
今年の初サンマは美味かった。
遅ればせながら、わが家の食卓にも
日本の秋がやってきた。
●遠ざかるサンマ
サンマの不漁は2つの要因があるらしい。
地球温暖化による海洋環境の変化。
温暖化によって海水温がどんどん上がり、
魚が生息する場所が変わってきた。
ちょっと前までは、「ふーん、そうなんだ」
と聞いていた情報が、
だんだんボディーブローのように効いてきた。
そしてもう一つは社会環境の変化。
中国や台湾など、ひと昔前までは
サンマが商売になるなんて思ってもいなかった国々が、
日本文化に触れて「サンマって美味しい」
ということを学んだがために起こった
グロ―バリズム問題の一つともいえる。
地球は変わる。
世界は変わる。
いずれにしてもこのままでは、
サンマを安く気楽に食べられた時代は
だんだん遠ざかっていく気がする。
●サンマの養殖?
で、あなたや僕が考えるのは、
養殖はできないのか? ということ。
これまでの常識として、
うじゃうじゃ獲れるサンマの養殖なんて
誰も考えなかったし、
そもそもそんなの無理と言われてきた。
しかし今や、マグロやサーモンの養殖だって可能な時代。
サンマだってけっして不可能とは思えない。
ただ、寿司ネタとしても重宝される
マグロやサーモンと違って、
サンマは一尾100円――という安さが魅力の大衆魚。
いちばんのネックは、そこまで研究開発コストをかけても
そうそう高く売ることはできないってこと。
回収できるのか? 採算が合うのか?
秋深まり、サンマの未来、食の未来、
日本の、世界の、地球の、お天気の未来が
どんどん気になってくる。
スマホ充電と健康ダイエット

「つねに腹八分目は健康の秘訣なり」
というのは、人間だけでなくスマホにも通じる法則だ。
いつもほとんど空っぽになるまで使い切り、
そのたびにフル充電する――
こうした充電方法は、極限まで腹ペコになったところで、
「うおおおおおおおおおお!」と、
ドカ食いするのと同じ。
こうした生活習慣(使用習慣)をつけてしまうと、
バッテリーに大きな負担がかかり、
寿命が短くなってしまうのだそうだ。
長持ちさせる秘訣は30%くらいになったら充電。
できればフルにせず、80~90㌫に止めておくことが
長持ちさせる秘訣とか。
電気の過食・虚飾は厳禁です。
ロクに使わないアプリをどっさり搭載するのも
皮下脂肪を貯め込むのに似てる。
年一度くらいは、
生活習慣(使用習慣)をチェックして
メタボなスマホのダイエットを実践しよう。
パソコンもね。
フリーマーケットは個性を楽しみ、ビジネスの基本を学ぶ場

●中野四季の森公園とお犬さま
カミさんがフリーマーケットに行きたいと言うので、
義母を連れて3人で「中野四季の森公園」に出かけた。
中野駅・サンプラザから徒歩5分とちょっと。
中野区役所の裏手にある。
フリーマーケットは久しぶりに来たが、
年齢も国籍も関係なく、みんなでワイワイやってて、
やっぱり賑やかで楽しいものだ。
特に子ども連れやイヌ連れの人たちにとっては
パラダイスのようなところ。
ちなみにサンプラのあたりは、
江戸の昔、「生類憐みの令」でおなじみの
5代将軍・徳和川綱吉の「お犬さま屋敷」があったらしい。
●フリーマーケットのお店は、みんな個性的
さて、フリーマーケットというのは
僕も出店したことがあるが、
ふつう、中古品を中心に、家で余っているもの、
どこかで余っていたのを安く買い取ったか、
もらってっきたものを寄せ集め、並べて売る。
だからリアルな商売目的の出店と違って、
店のコンセプトがナンチャラとか、
面倒なことを考えたり、
今日の、この場所のお客は、
こうした生活をしている人が多いとか、
そんなマーケティング分析・戦略的な
小賢しいことは考えず、ただ楽しくやる。
それで売上が上がれば儲けもの――
なのだが、
不思議とその店の個性が滲み出る。
売ってる人のキャラクター、品揃え、プライスカード、
敷物、接客態度などを
見ていると「ふむふむ、ここはこういう店なのね」と
何となくイメージが出来上がる。
こういうのを見ていると、
べつだん声を大にして「個性が、個性が」と
叫んだりするのが、バカらしく思えてくる。
そんな力まなくても、ちゃんと個性出てるじゃん。
●ブランド屋の玉石混交メニュー
その中で、「ブランド屋」とでも呼ぶべき店があった。
並べてあるのは服も雑貨も香水などもブランドものばっか!
すげー!
・・・と思いきや、その大半はニセモノである。
しかし、どれもきれいで、ほとんど新品に近いものが多い。
そして面白いことに、その中で1割くらい本物が混じっている。
本物の方はボロボロになってたり、
クタクタにくたびれたりしているのがほとんどだ。
お値段はボロボロクタクタの本物が1万円、
ピカピカに近いニセモノが2000円程度。、
どちらに価値を見出すか?
そのブランドに心を奪われている人は、たとえ高くても、
ボロでも、もう現在では手に入らないようなブランド品なら
間違いなく大金をはたく。
そんなものに無頓着で、
ただ生活で使えればいいと思っている、
僕のような輩はちょっとでも安く買いたたく。
●価値観が合うかどうか
それにしても6月の引っ越し以来、
いくら安くても無駄なもの、飾りにしかならないものは
絶対買わない、家に置かないという意識が
強まってしまった。
今日、自分のものとして買ったのは、
普段着用のネルのピンクのシャツ1枚なり。
100円だった。
いずれにしても、売り手と買い手の
価値観が合うかどうかが、商売成立の条件だ。
価値はその時の状況でもころころ変わる。
砂漠の真ん中で、水を売られたら、
たとえペットボトル1万円と言われても、
喜んで買うに違いない。ですよね?
これはビジネスの基本だけど、
フリーマーケットは改めてそのことを教えてくれる
絶好の場だなぁと思った。
ホームページに心のこもったお手入れを

こういうテーマで取材するところを探しているけど、
どこか適格な会社はないか?
今度、話を聞く会社はどんなところか?
・・・てな感じで、仕事柄、割と頻繁に
ちこちの会社や団体、お店などのホームページを見る。
ざっとした全体の印象として、5年ほど前よりだいぶ変った。
この5年くらいの間にリメイクしたところも多いのではないか?
無料作成ツールもたくさんリリースされ、利用し放題。
無料とは言っても、載せる内容がしっかりしていれば、
ちゃんと作り込め、訪問者にPRできる。
こういうところは、本当に便利でいい時代になった。
その分、年季の入ったホームページが気になる。
いや、べつに古いことが悪いわけではない。
もう随分更新されてないな、
お手入れもしてないな、
ほったらかしだな、とわかってしまうのが結構多いのだ。
付随されているブログを見て、
最後の記事がもう数年前の日付だったりすると、
この会社・団体・お店はまだ存在しているのか、
まともに稼働しているのか、疑ってしまう。
最近は情報発信はSNSで、というところも多いので、
ホームページの扱いはぞんざいになっているのだろうか?
だけど個人ならともかく、
会社や公共団体がSNSオンリーでいいのか?
ホームページはやっぱり社会に見せる顔であるはずだ。
マーケティングに有効かどうか以前の問題である。
時折、ふと気になって、以前、懇意にしていた幾つかの会社の
ホームページを覗いてみると、
10年ほど前と同じ状態なのを発見する。
時が止まっている。
心にピューと木枯らしが吹き荒れる。
立派だったり、見た目すごくカッコいい必要はありません。
でも、ちゃんと社会的な活動をしているのなら、
今の時代、中身のしっかりした、面白くて、
人柄(会社柄?)の伝わるホームページを出してほしい。
やっているところは、製作者がたった一人でも
素晴らしいのを作っています。
必要ならお手伝いしますよ。
善福寺川緑地アンバランス生物との記念撮影

善福寺緑地アンバランスゾーンに生息する
謎の生物を遂に捕獲。
「こわいよ、こわいよ」と言って逃げ惑う義母を
説き伏せて、
無理やりシャッターを切らせる。
「わかんない、できない」と言ってた割には
なかなかグッドな撮影。
どや!
しかし、を地球の平和と宇宙のバランスを保つため、
写真撮影だけにとどめ、
引き続き観察活動をすることにする。
見れば見るほど不気味な風貌だが、
この雨の夜、やつはどうやって過ごすのだろう?
異次元をトリップして、
僕の夢に入り込んできたらどうしよう?
おお、こわ。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。
お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。